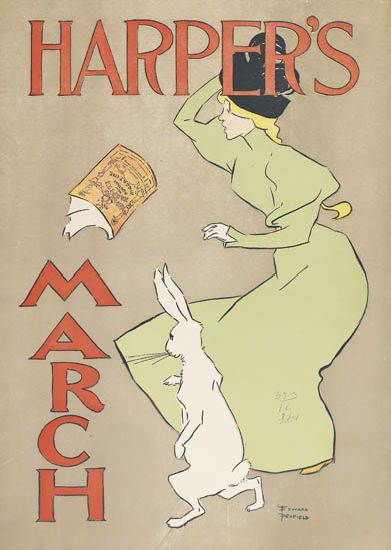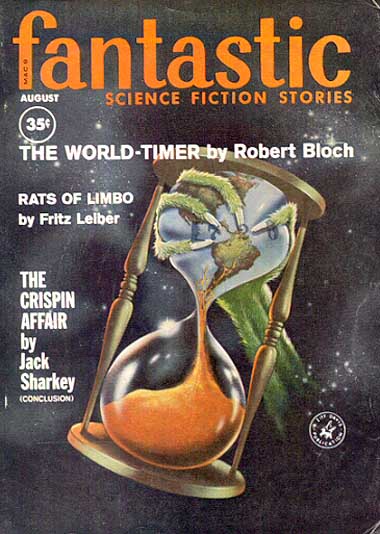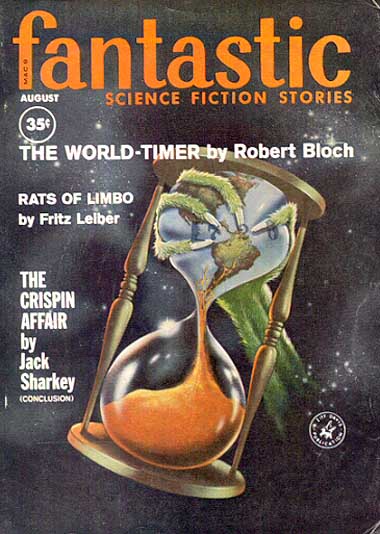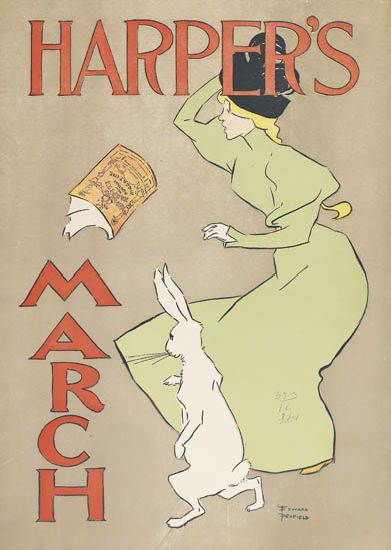ザ・ハウス
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
プロローグ
彼は、家のポーチまで来ると、中に入るのを、すこしためらった。背
後の道や、
道端にはえた緑の木々や、黄の平原、遠い丘、それに、明る
い陽射しも、これが、最後の、見おさめだった。それから、ドアをあけ、
中へ入った。背後で、ドアが閉まった。
うしろを振り返ると、あるのは、ただの壁で、ドアノブも鍵穴も、ド
アのへりさえなかった。へりがあったとしても、うまくまわりの壁に溶
け込んで、輪郭さえ見つけられなかった。
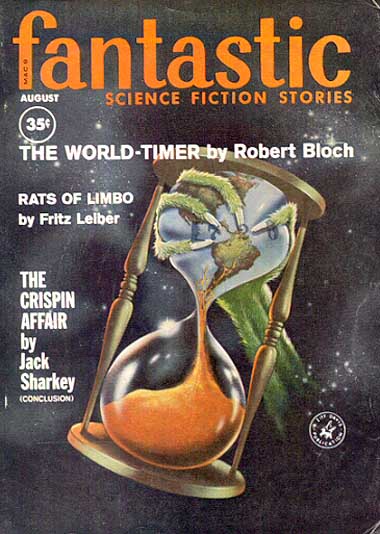
1
目の前にあるのは、くもの巣のように広がる広間だった。床には、ほ
こりが厚くつもり、その先には、細く曲がりくねった通路が、2匹の小
さな、へびか、あるいは、2匹の大きな、いも虫のように、続いていた。
暗く見えにくい通路で、右の方の最初のドアに近づくまで、気がつかな
かった。そのドアには、旧英国書体で、「常に忠実」と刻まれていた。
ドアを抜けると、そこは、大きなクローゼットほど広さの、小さな赤
い室であった。1脚のイスが、室の壁沿いにおいてあり、イスの足は、
1本折れてぶら下がっていた。近くの壁には、1つだけ、額に入れられ
た、ベンジャミンフランクリンの肖像画があった。額は、ななめに傾い
て、ガラスには、ひびがはいっていた。床にほこりはなく、最近、そう
じしたようにきれいだった。床の中央には、きれいに磨かれた、アラビ
アの片刃刀がおいてあった。つかは、赤く染められ、刃先は、緑の軟泥
で、厚くコーティングされていた。室には、ほかに、なにもなかった。
彼は、ながいあいだ、この室に立っていたが、そのあと、広間を横切
って、反対側の室に入った。そこは、小規模な講堂くらいありそうな、
広い室で、壁がすべて黒なので、最初に入ったときは、それほど広くは
感じなかった。紫のビロードの劇場用のイスが、何列もならべてあった
が、ステージや壇はなく、黒の壁から数インチのところから、イスの列
が始まっていた。室には、ほかに、なにもなかったが、一番近いイスの
上に、コンサート曲目プログラムの束が積み上げてあった。1枚をとっ
てみると、裏表紙には、広告が2つあって、ひとつは虫歯予防ハブラシ、
もうひとつは、サブロサ分譲地の区画販売の広告であった。前の方のペ
ージには、誰かが、鉛筆で、ガーフィンクルという名前を書きこんでい
た。
彼は、プログラムをポケットに押し込むと、広間に戻り、階段をめざ
して、壁に沿って歩いた。
2
ある室を通りすぎるとき、誰かが、ハワイアンギターを調弦している
ような、あまりうまくはない曲が聞こえた。ドアをノックすると、走り
さる足音が聞こえたが、返答はなかった。ドアをあけると、ちらりと見
えたのは、シャンデリアから吊るされた腐りかけた死体で、あまりにひ
どいにおいに、いそいでドアを閉めるしかなかった。階段のほうへ歩い
た。
階段は、せまく、曲がりくねっていた。手すりもなかったので、壁に
しがみつくようにしてのぼった。下から7段目までは、きれいにそうじ
されていたが、その先は、ほこりがたまり、ふたたび、曲がりくねった
通路が見えた。上から3段目のあとの階段は、つぶれて消えていた。
階段を引き返し、広間に戻って、階段の脇の右手の最初のドアを開け
てはいると、そこは、ぜいたくな家具がおかれた、広いベッドルームだ
った。すぐに、室を横切って、彫刻のある、うしろのベッドのところま
で行って、カーテンをひいた。ベッドは、きれいに整えられていた。な
めらかそうな枕の上に、ピンでとめたメモ用紙があって、そこには、女
性の手書きで、「デンバー、1909」と走り書きされていた。裏には、
別の手書きで、こんどは、きちんとしたインク文字で、代数方程式が書
かれていた。
静かに、この室を出ると、ドアの外でしばらく立ち止まって、広間の
暗い通路のむこうから聞こえてくる音に耳をすませた。
それは、男の低い声で、奇妙な発声法で単調に歌っていた。リズムも
単調で、まるで、仏教の経典を詠唱しているかのように、上がったり、
下がったりしたが、北欧神話で世界の終末をあらわすワード、ラグナロ
クが繰り返し唱えられていた。そのワードは、かすかに、どこかなじみ
があって、いろいろ加工された、彼自身の声のようにも聞こえた。
その声が、青く震える沈黙に消えてゆき、どろぼうが隠れているかの
ような広間に、夕暮れが忍び寄ってくるまで、彼は、頭をさげたまま、
立っていた。
3
急に目が覚めたように、今は静かになった広間を壁に沿って歩き、3
番目の最後のドアまでくると、上部のパネルに、金の小さな文字で、彼
の名前が印刷されているのが見えた。ラジウムが混ぜてあるのか、広間
の薄暗がりのなかで、金の文字が輝いていた。
彼は、ドアノブに手をおいたまま、しばらくじっと立っていたが、つ
いに中へ入り、後ろ手に、ドアを閉めた。鍵のかかるカチッという音が
聞こえ、2度と開かないことがわかったが、恐怖感はなかった。
暗闇は、マッチをすった時に背後にできる影と同じに、暗いがいくら
でもあやつれるものだった。その室は、彼が生まれた、ウィルミントン
近郊の父の家の東側の寝室を再現してあった。それで、彼には、ろうそ
くはどこをさがせばあるのかがわかった。引き出しに2本と、使い残し
が1本あった。1度に1本づつともせば、全部で、10時間はもつとい
うことが、わかっていた。最初のろうそくに、火をともし、壁から突き
出たしんちゅう製のろうそく立てに立てた。ろうそくの火が揺れると、
イスの影や、ベッドの影や、ベッドぎわにある小さなゆりかごの影も、
おどっているように見えた。
テーブルの上には、彼の母の裁縫バスケットがあり、その脇に、ハー
パースマガジンの1887年3月号がおいてあった。雑誌を手にとり、
ページをざっとめくった。
しばらくして、雑誌を床に落とすと、もう、ずいぶん前に亡くなった
妻のことを、思い出し、ほのぼのとした気分になった。くちびるにかす
かな笑みが浮かび、いっしょにすごした何年ものあいだの、ちょっとし
たできごとを、いくつも思い出した。

エピローグ
ろうそくの残りが、あと1センチになるまで、9時間もかからなかっ
た。暗闇が、室の片隅から集まりはじめ、近くまではいよってきた。彼
は、悲鳴をあげて、ヴィンテージものの古雑誌であることも忘れて、ド
アをたたき、両手が原料のままの血のにじんだパルプになるまで、つめ
でひっかいた。
(終わり)