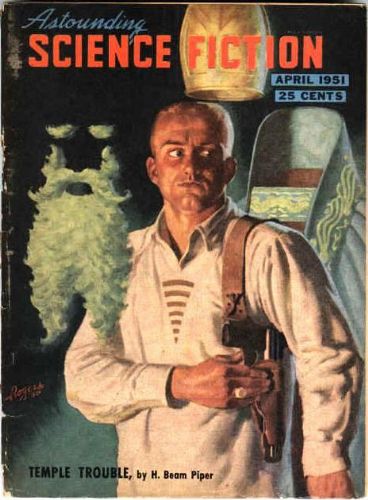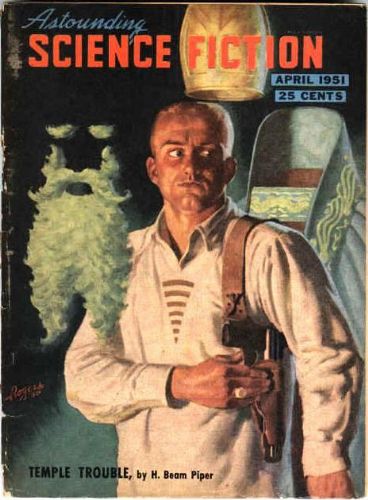武器
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
プロローグ
室は、夕暮れのなかで、静まりかえっていた。ジェームズグラハム博
士は、主要プロジェクトの中心メンバーの科学者であったが、お気に入
りのイスにすわり、考えごとをしていた。隣の室で、彼の息子が、絵本
をめくる音さえ聞こえてきそうなほど、静かだった。
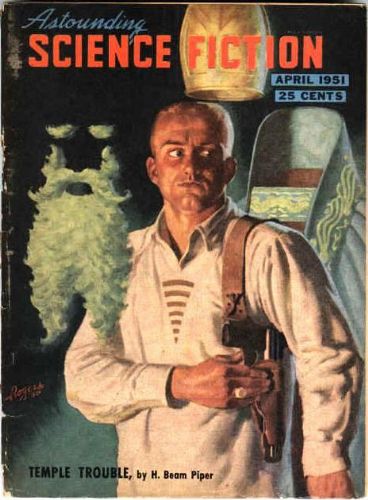
1
グラハムは、このようなときに、もっとも創造的で、すばらしい仕事
をした。昼間の雑用から解放されて、自宅の薄暗い室に、ひとりすわり
ながら。しかし、今夜は、彼の心は乱れて、建設的な方向に進まなかっ
た。考えていたのは、隣の室にいる、精神的に未発達の息子のことだっ
た。おもに感じていたのは、愛情であって、数年前に、息子のことを初
めて聞かされた時に感じたような、怒りでは、なかった。少年は、幸せ
だった。それで、じゅうぶんではないか?子どもが、いつまでも子ども
で、親元を去ることのない子どもを、どれだけ多くの人が持てるという
のだろうか?たしかに、そう考えるのは、理にかなったことだ。間違っ
た理屈かもしれないが。そのとき、玄関のベルが鳴った。
グラハムは、立ち上がり、玄関へ行く前に、ほとんど暗くなった室の
電気をつけた。思考を中断された、イラつきはなかった。今夜ばかりは、
中断されたことを、むしろ歓迎した。
玄関のドアをあけた。
「グラハム博士ですか?」と、見知らぬ男性。「私は、ニーマンドです。
少し、お邪魔してもいいですか?」
男は、背が低くく、特徴的なところもなく、見たところ、まったく無
害そうだった。たぶん、どこかの記者か、保険の勧誘かなにかだろう。
しかし、彼がなにものかは、どうでもよかった。
「ええ、どうぞ、ニーマンドさん」と、グラハム。思考の転換を、むし
ろ喜んだ。そして、居間で。「お座りください。なにか、お飲み物は?」
「いえ、けっこうです」ニーマンドは、イスに座った。グラハムは、ソ
ファに。
「グラハム博士」と、ニーマンド。両手の指を組んで、前に。「あなた
の科学的業績は、すばらしいです。人類を絶滅させることに関しては、
他の科学者の追随を許しません」
ただの変人だった。グラハムは、中へ招き入れる前に、男の身分を訊
いておくべきだったと、後悔した。困ったインタビューで、無礼にもほ
どがあるが、男は、無礼を加速させた。
「グラハム博士、今、開発なさってる武器ですが」
男は、急に、口をつぐんだ。そして、頭を、寝室に通じるドアに、向
けた。ドアがあいて、15才の少年がはいってきた。少年は、ニーマン
ドを無視して、グラハムに駆け寄った。
「ダディ、絵本を読んで!」と、少年。笑顔は、4才の子どもの笑顔だ
った。
グラハムは、少年のからだに腕をまわして、訪問者を見た。少年のこ
とを、知っているのかどうか。ニーマンドは、驚く表情を見せなかった
ので、おそらく、知っていたのだろう。
「ハリー」と、グラハム。愛情に満ちた、暖かい声で。「ダディは、今、
忙しいから、自分の室で、すこし、待っていなさい。すぐ、行くから」
「ちっちゃなニワトリさんを?すぐ、読んでくれる?」
「いいよ。さぁ、行って!あ、ハリー、こちら、ニーマンドさん」
少年は、恥ずかしがりながら、訪問者に笑いかけた。
「ハイ、ハリー」と、ニーマンド。少年の手をとって、笑顔を。グラハ
ムは、それを見て、ニーマンドは知っていた、と確信した。笑顔も仕草
も、少年の精神的年齢に合わせたもので、実際の年齢に対するものでは、
なかった。
少年は、ニーマンドの手をとった。そのうち、ニーマンドのひざに上
がってしまいそうだった。グラハムは、少年をやさしくひっぱった。
「室へ行ってなさい、ハリー!」
少年は、スキップで自分の室へ戻った。ドアは、あけたままだった。
「彼が好きですね」と、ニーマンド。グラハムの目を見て、あきらかに、
親しみを込めて。「彼の言うことを聞いてくれたら、それがいつも正し
いのだと思いますよ」
グラハムは、相手が、なにを言いたいのか、分からなかった。
「ちっちゃなニワトリさんのことですよ。すばらしい物語です。しかし、
お空が落ちてくることが、いつも間違いだったかもしれません」
2
グラハムは、ニーマンドが少年を好きな態度を示したことで、ニーマ
ンドに好感をもった。インタビューを、すぐ終わらせるべきことを、思
い出した。毅然として、立ち上がった。「ニーマンドさん、あなたは、
時間をムダにしてますよ。私は、すべての議論を承知してますし、あな
た方が言ってることは、何千回も聞かされました。たぶん、あなた方が
言うことに、真実があるのでしょう。しかし、私には、まったく関心の
ないことです。私は、科学者です。私は、武器、究極の武器に関する、
研究をしてます。しかし、個人的には、それは、科学の進歩の副産物に
すぎません。研究を推し進めることが、唯一、関心のある事なのです」
「しかし、グラハム博士、人類は、究極の武器をもつ、準備ができてる
んですか?」
グラハムは、眉をひそめた。
「ニーマンドさん、私は、私の観点を、お話ししたのです」
ニーマンドは、イスから、ゆっくり立ち上がった。
「いいでしょう。議論したくないのなら、これ以上、お話しすることは
ありません」
彼は、組んだ手を、ほどいた。
「もうすぐ、おいとましますが、グラハム博士、もしよければ、先ほど
の、飲み物のお申し出を、お受けしたいのですが」
グラハムのイラつきは、消えた。
「いいですよ。ウィスキーに、水は?」
「いいですね」
グラハムは、キッチンへ行った。ウィスキーボトルと、水、氷にグラ
スを持って、戻ると、ニーマンドが、少年の寝室から、戻ろうとすると
ころだった。
「おやすみ、ハリー」と、ニーマンド。
「おやすみ、ニーマンドさん」と、ハリー。うれしそうに。
グラハムが、1杯目を作り、ニーマンドが、2杯目を作り、玄関に向
かった。
「あなたの息子さんに、ちょっとした贈り物をしました、博士。さっき、
台所へいらしてるあいだに。そのことを、お許しください」
「もちろん、いいですとも。おやすみ」
エピローグ
グラハムは、玄関をしめ、居間を通って、ハリーの室へ行った。
「ハリー、それじゃ、絵本を、読んであげようね」
そのとき、グラハムの額に、汗が吹き出た。つとめて、平静をよそお
って、ハリーのベッドまで行った。
「ハリー、それを、見せてもらっていいかな?」
安全に、それを、ハリーから受け取って、中を調べて、ショックで、
手が震えた。
「精神的に未発達の子どもに」と、グラハム。心のなかで。「フル装填
の拳銃を与えるなんて、とんでもないことだ!」
(終わり)