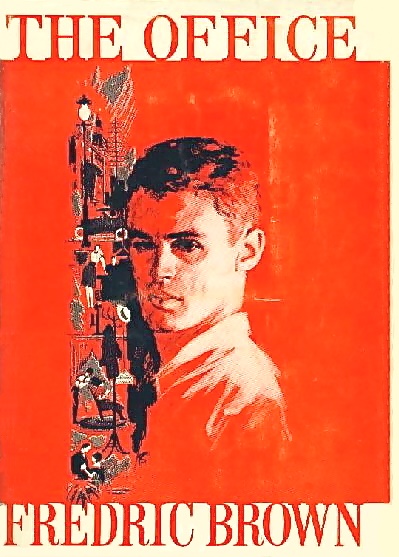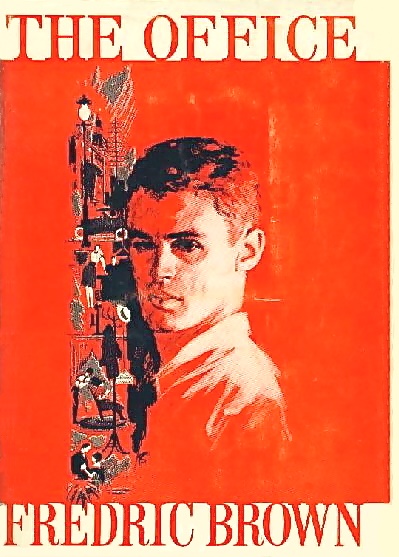ザ・オフィス
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
パート1=始まり
∨
パート2=始まりの終わり
∨
パート3=終わりの始まり ∨
パート4=終わり ∨
登場人物
コンガ氏:コンガ&ウェイ社の経営者、機械類を工場に売っている。
ウィロービィ氏:オフィスマネージャー、鋭い目線で監視している。
マーティレインズ:簿記係、21、ステラをデートに誘いたい。
ステラクロスターマン:ファイル係、19、背が高い。
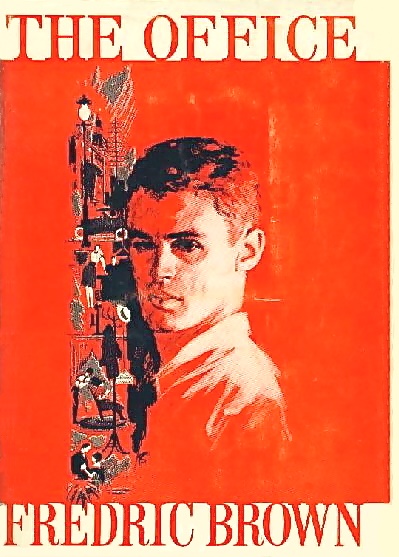
フレッド:オレ、語り手、高卒で雑務係に応募。読書好き、作家志望。
メアリーホートン:速記タイピスト、22、たまに指をすべらす。
ブライアンダナー:営業マン、25、独身。営業成績が良い。
ジョージスパーリング:営業マン、27、活気がない。成績が悪い。
パート1=始まり
1
コンガ&ウェイ社のオフィスは、かつてはシンシナティのコマースス
トリートに建っていたビルの2階にあった。そこは当時有名だった吊り
橋からそれほど離れてはなかった。吊り橋は、ケンタッキー州コビント
ンへと流れる広い泥だらけのオハイオ川に架かっていた。
フォンテインスクエアやコマースストリートといった町の中心部から
数ブロックのところだったが、そのあたり3ブロック一帯は、すべて家
賃が安かった。それは建物が古い、それもすごく古いせいもあるが、わ
ずかフロントストリートとウォーターストリートを隔てただけで、川か
ら非常に近かったからだ。大きな川が増水で溢れると、しばしば洪水に
なった。しかしこれは、オレが書いているこの物語の短いあいだは、一
度も起こらなかった。
そのビルは今はもうない。20世紀初頭の当時においても、そのビル
は非常に古かった。ビルのあった場所は、橋に出る新しい通りの一部に
なった。そのビルは今はもうないというだけでなく、そもそも建ってい
た場所がない。もしもその場所が土やコンクリートで埋められていたら、
ビルはなくなったと言えるかもしれない。そこは名前も知らないビルに
なった。
コンガ&ウェイ社は、一方で、本来のもの以外に多くの社名があった。
特殊なビジネス用語で、20世紀初頭固有の、スクリューマシンプロダ
クツやミッドウェスト旋盤サプライ会社、仕上げ研磨会社といった名前
だった。すり減ってはいるがくっきりとした、黒で縁取られた金色の文
字で書かれた社名は、コンガ&ウェイ社の看板の下、オフィスの出入り
口のドアに書かれていた。
こんなふうに名前が4つもあるのは、詐欺ではないかとあんたは言う
かもしれない。ビジネスは、もっぱら、エドワードB・コンガという名
前の一人の男によって行われていた。ウェイ氏は10年近く前に亡くな
っていた。しかし共同経営規約に従って、ウェイ氏の未亡人は利益の2
5%を受け取った。彼女が生きてるあいだはずっと。しかしそれ以外の
ことに関しては、彼女は一切口出しせず、すべてをコンガ氏にゆだねる
代わりに、社名に亡き夫の名前を残すことを主張して譲らなかった。コ
ンガ氏は、みんなの利益のために、彼女に関しては例外を認めたが、自
分に関しても同様に感じた。ウェイ夫人をとても嫌っていた一方で、共
同経営者のハリーウェイはずっと最良の友人であったので、会社の看板
に彼の名前を残すことでハリーの思い出を大切にしたいと感じた。会社
の別の名前に関しては━━━仕上げ研磨会社は、メアリーホートンの一
番上の引き出しにある爪やすりのようなものを含めなければ、研磨機は
扱ってなかった。ミッドウェスト旋盤サプライ会社は、コンガ氏にとっ
ては紙の重さくらいの重要性しかない、モーステーパシャンクに設置す
る4分の3インチの第2中心軸しか扱ってなかった。スクリューマシン
プロダクツが扱うスクリューマシンに最も近いものは、エンピツ削りや
パウダー状の黒鉛だった。扱う量はとても少なく、ほとんど利益につな
がってなかった。
このような小さな不備は、かといって別段、大きな不備につながって
もいなかった。コンガ氏は全面的に信頼できるという男ではなく、ただ
の仕事人だった。シンシナティやその近くの店から機械を仕入れ、ピッ
ツバーグやアクロン、シカゴにある工場に売っていた。
コンガ氏のもとで、7人が働いていた。
2
人間は、生まれて、そして死ぬ。つまり、始まりと終わりがあって、
どちらも時間的にはっきりとした地点がある。情熱的な興味深いできご
とが、生まれる前に起こったり、葬儀屋やうじ虫たちのできごとが、死
んだ後も続くことはあるが、その人間自身に関する限り、はっきりとし
た始まりとはっきりとした終わりがある。
場所については、時間で定義するのは、より難しい。場所はいつもそ
こにあるし、これからもいつもあるだろう。その光景は変わるかもしれ
ないが、そこには時間的な境界がない。
コンガ&ウェイ社があった場所は、かつては別の会社やさまざまな会
社があった。あるときは、平屋の小屋だったり空き地だったりした。そ
れより以前は、ロサントビルという町の初期移民のひとりが耕した広大
な土地が広がっていた。のちにそこはシンシナティとなった。その前は、
そこには1本のオークの木が枝を広げていて、インディアンの少年が木
登りをしていた。インディアンたちが来るはるか昔、オークの木のずっ
と以前は、どんぐりのなるトゲのある木が立っていた。過酷な季節のあ
いだ、モズは獲物をトゲに突き刺して保管し、そこに巣を作り、その場
所がのちに正確に、簿記係のマーティレインズの机の上のインクつぼを
置いた場所となった。
3
1922年6月29日木曜の午後、そこから始めよう。この年は好況
が始まる年だった。また、不況が始まる7年前でもあった。2年に及ぶ
不況の終わりを見た年で、20世紀がうなりを上げ始めた年だった。
マーティレインズを登場させる。年令は21、身長5フィート7イン
チ、体重130ポンド、普通のブロンド髪で、簿記係。モズの巣にペン
を刺したり、借り方に項目を記入したり、自分の勇気を知るためだけに
ファイル係のステラクロスターマンをデートに誘ったりするようなやつ。
研磨剤10パウンドと半ガロンの接着剤を借り方に記入してから、台帳
から顔を上げて、オフィスの奥で、ステラがファイルキャビネットの下
から2番目の引き出しに腰を曲げているところへ目をやった。
ステラは、ほどよく肉付きのよい、すばらしい体をしていた。顔は別
の方を向いていたが、マーティは、彼女が温かい茶の目をして、ときど
き涙でかすむことを知っていた。髪は肩までのショートヘアでやはり温
かい茶だった。彼女は背が高く、ふつうのハイヒールでは、目の高さが
ほとんどマーティの背の高さだった。ときどき彼が少し不快に思い悩む
のは、夜に高いヒールをはいてきたら、彼より背が高くないように見せ
られるかどうかだった。また、ステラはまだ背が伸びるのではないかと
悩んでいた。いや、そんなことはないと彼は考えた。彼女は19だし、
19になったらふつうはもう背は伸びない。少なくとも、彼、マーティ
は、17で背が伸びるのが止まった。17から20才のあいだ、もう1
インチか2インチ、背が伸びないかと虚しい望みをかけながら、注意深
く背を測ってきたが、1年前に彼はあきらめた。
さらに2つの項目を記入すると、ふたたび目を上げた。ステラは今は
一番下の引き出しに体を曲げていて、スカートが数インチめくれて、巻
き上げたシルクのストッキングの上1インチか2インチ、滑らかなオリ
ーブ色の肌が見えた。
それは、マーティには興味があるところだったが、気にしていいのか
悩むところだった。それは不謹慎だった。娘はヒザの下までストッキン
グを巻き上げるべきでないし、そんなふうに腰を曲げるべきでない。彼
がまた思い悩むのは、ほかの男たちはオフィスでこのようなものを見る
のかどうか。営業マンのふたりは不健全な心があったが、ふたりとも外
出していた。年寄りのコンガ氏は、自分のオフィスにいた。雑務係のマ
ックスならどうするかと捜したが、思い出した。マックスは2日前に辞
めていた。しかし、オフィスマネージャーのウィロービィ氏は自分のデ
スクにいたので、マーティは彼を見た。そしてすぐに、数字を記入して
いた台帳に目を落とした。ウィロービィ氏の目は、ステラクロスターマ
ンの足を見ていなかった。マーティを見ていた。目からレーザービーム
が出て、こちらに向かってきていた。ウィロービィ氏の、なんという嫌
味っぽい目!すべてを見ていて、すべてお見通しであるかのような。マ
ックスが前にこう言っていた。ウィロービィは、頭の後ろにも目がある。
それほど間違ってはなかった。
マーティレインズは今度は目を上げずに、さらに6項目記入した。グ
レイソン会計を終え、項目にしるしをつけて、ページをめくった。彼の
顔はまだ、先ほどの気まずさから少し紅潮していた。
なぜ、と彼は思い悩んだ。ほかのやつらのような図太い神経がないの
だろう?ひどく恥ずかしがり屋なことを、なぜ悩んだりするのだろう?
彼は恋人がなく、白人で、21だった。ハンサムではなかったが、醜く
もなかった。背は平均より少し低かった。それはそれほど重大なことで
もないし、それによってなにかができなくなるわけでもなかった。週2
0ドル稼ぎ━━━一部を貯金した。
ステラクロスターマンは、まだ19で、ただのファイル係だった。
(いや、と彼の内部のなにかが言った。彼女は女神だ!彼女は特別な存
在だ!彼女はなぞに満ちている!)
しかしなぜ、つぎのチャンスで、自然に「ステラ、今夜の予定は?」
と訊けないのだろう?彼は、彼女には好かれていると考えていた。たぶ
ん、彼女はすぐいい返事をくれるだろう。あるいは、悪くても、なにか
予定があって、こう言うだろう。「なぜって、今夜は忙しいの、マーテ
ィ。でも━━━」そして、つぎの予定のない夜になにを約束するかは、
彼に託される。
「ステラ、今夜の予定は?」たったの4ワードを言うだけだ。しかし
自然に4ワードを言おうとしても、自分の声がなにか変なのが分かって
いた。正しく言い始めても、最後には自然な質問にしてはピッチが高く
なりすぎて、自分がアホに思えて、たぶん恥ずかしくなって、後悔する
ことになる。なにか欠けていることでもあるのだろうか?
彼は、また、ステラを見た。今は立ったまま、一番上の引き出しで作
業していた。キャビネットの上に書類の入ったカゴが置いてあった。一
番上の紙を取り上げて、名前を見て、それぞれのファイルに入れていた。
単調な仕事に違いない、とマーティは考えた。
すばらしいアイデアを思いついて、彼の目が輝いた。彼女が取り上げ
た手紙のひとつが、ヒーラー&リー社やシンシナティ旋盤会社といった
宛名でなく、ミス・ステラクロスターマン宛てになっていたら?なぜだ
めなんだ?彼女をデートに誘ううまい方法だ。コンガ氏が手紙を口述筆
記させるときの形式ばったビジネスレターのように書ければ、なにかの
目的のためにうまくしゃべれるようになる第一歩になるだろうし、今ま
で恥ずかしがり屋だと思われていたのは、ただの気まぐれだったと見な
されるようになるだろう。
「ミス・ステラクロスターマン
コンガ&ウェイ社様方
シンシナティ、オハイオ州
親愛なるミス・ステラクロスターマン:」
よく考える時間がなく、少し怖かった。つまり、少し考えて、心に決
めてしまったので、彼女がどう考えるだろうかとかどういう返事をくれ
るか心配し出した。ウィロービィ氏が見てないことをさっと確認して、
デスクの引き出しから1枚紙を出して、開いたままの台帳の上に広げて、
書き始めた。自分の大きな誇りになっている、きれいなスペンサリアン
書体で、デートという目的のために書いた。簿記係として、マーティは
単に適任というだけだった。コンガ&ウェイ社の簿記システムは、同様
に、シンプルというだけだった。
マーティレインズは鈍感な少年だった。彼の前に何人かの登場人物を
登場させたが、彼は物語の要になっている。
彼が鈍感な少年だというのは、なにも彼のせいではないし、仕事がそ
うさせていたのでもなかった。実存主義者は、もちろん、すべて彼の責
任だと言うだろうが、実存主義の思想は、1922年には、まだ台頭し
てなかった。フロイトもアメリカでは知識人にしか知られてなかった。
語り手であるオレは、それは彼の母親のせいだと言いたい。陽気な1
990年代の終わりにかけて、彼女はバルチモアの売春宿の娼婦をして
いた。そこで敬虔な長老派教会のビジネスマンと知り合い、愛し合い結
婚した。しかし3年もしないうちに、彼は心臓発作で亡くなった。彼女
には、幼い息子と質素な生活なら暮らしてゆけるだけの財産を残した。
彼女は、そのように暮らすことにためらいはなく、過去の仕事に戻るこ
とはなかった。夫の宗教については、やめたわけではなかったが、それ
ほど熱心でもなかった。彼女のよくない過去への心からの償いの気持ち
から、過度に自分を責めていた。
マーティに対しては、多くの者が無条件に信じる神を強く信じるだけ
でなく、女性の神聖さを強く信じるように教えた。彼女の教えによれば、
純粋さは神にもっとも近い場所で生まれると言う。このことは、なんど
も強調された。考えることの純粋さは、行ないの純粋さと同じように、
とても重要だった。
この信念を過剰投与されれば、どんな男でも曲げられてしまう。マー
ティは過剰よりもっと多く吹き込まれた。彼の父は、ふつうに良心的な
男で、生き、そしてまったく違う形の物を残した。最悪でもマーティは、
比較的健全なエディプスコンプレックスを発展させた。しかし、ほとん
ど覚えてない父を憎む理由がなかった。物については、全く違っていて、
長老派よりもカソリックを支持した。この場合には、処女マリアの崇拝
から、彼は、純粋な女性像を崇めることになった。それにより、彼の母
親も含めて、他の女性たちは、肉体および神聖さからは程遠いなにかで
作られていることを、見抜くことができた。物に支えられて、21にな
って彼は完全に、行ないと同様、考えることにおいて純粋だった。彼が
セックスの仕組みが分かっていなかったと言ってるのではなく、なにか
そこには嫌悪すべきものがあって、純粋に、少なくとも彼の意識下の心
では、そう考えるようにしつけられていたのだ。もちろん、彼はそれが
出産のために必要な行為で、種の保存につながるということを知ってい
た。もちろん、彼はそのことが分からない程おろかではなく、彼が今い
るのは、過去にそのようなことが行われたからということを知っていた。
彼の母親の結婚生活において、あとで彼の父親となる、見知らぬ男と。
しかし、彼の心がシャイでその事実から離れたがって、それについて考
えるのを拒んだ。つまり、互いに愛し合っている結婚生活の場合は、事
情はまったく異なっていた。その行為が単独で行われようと、あるいは
基本的に出産のために行われようと。
友好的でない精神分析医は、当時でさえ数少ないが、たぶんこう言う
だろう。マーティレインズは予想もされなかった、ただの事故で生まれ
てきただけで、装填した銃の引き金に髪が引っ掛かっただけだったと。
しかし彼の母親は、彼はパーフェクトだと考えた。彼女の基準に照ら
して、そうだった。
4
1922年6月29日木曜日。いい天気だった。
オフィスマネージャー、ジェフリーウィロービィは、そのことに感謝
した。太陽は出ていて、暖かかった。ウィロービィ氏は、暖かい日を愛
し、寒い日を憎んだ。彼に寒い日々が訪れたのは、自分の残りの人生す
べてを賭けて戦った、1917年から1918年の冬の4ヶ月だった。
4年半前は、塹壕の中にいた。神に誓って彼が決心したことは、もう2
度と塹壕には入らないということだった。たとえ殺されようとも。彼の
遺書は、それがなければ重要でもないが、埋葬ではなく火葬にしてくれ
ということだった。
彼は少し身震いした。死だとか埋葬やら、軍隊や塹壕のことを考えさ
せたのは、なんだったのだろう?死は、避けることができるなら、考え
ないでも済むものだ。塹壕での数ヶ月間を除けば、彼は軍隊でイヤな日
々を過ごしたわけではなかった。1917年の志願兵の中では、彼は年
齢が少し上の方で、少し優秀だった。事務の経験があったので、補給部
の仕事に回され、すぐに軍曹になって、フランスの港へ送り込まれた。
そこでは今とさほど変わらない仕事、それほどやっかいでもない仕事が
与えられた。その後、悪い時期に、彼は愛国主義の影響を受けて、世界
を救うために自分の生涯を捧げるべきだという大胆な考えを抱き、前線
に配置替えしてもらった。彼が犯した哀れな間違いによって、成し得た
ことのなんと少なかったことか!
◇
彼のデスクから、オフィスの開いたドアを通して、いろいろ見ること
ができた。外廻りから戻った営業部のふたりが、デスクについていた。
窓から明るい日射しが差し込んでいるのが見えた。
彼の視線は、窓から、ファイルキャビネットで忙しい、ステラに移っ
た。日射しを見ていたので、彼の目には日射しが残った。ステラは、明
るく、暖かい日射しのようだった。もしも彼がもう少し若ければ━━━。
本当のところ、それほど年寄りではなかったが、彼女は彼をたぶん中
年と見るだろうし、彼女は自分をどちらかというと少女と考えているだ
ろう。あまりにきれい過ぎて、彼女の年令の2倍にわずかに届かない男
や、結婚する気などまったくない独身者からも、からわれることはなか
った。
その上、数年前、彼がオフィスマネージャーになってすぐ、彼の下で
働く女性を口説いたり、デートに誘ったりは決してしないと固く決心し
た。そのことを今思うと、「彼の下で働く」というところが、苦しいシ
ャレに思えて、ニヤリとした。ウィロービィ氏は、シャレや2重の意味
を楽しめる心を持っていて、無理やりのこじつけでさえ楽しんだ。ぎり
ぎりのきわどさを楽しむために、多くの人から心が汚いと言われながら
も、彼は言葉遊びを楽しんだ。きれいなものであっても。同様に、色気
さえ、きわどさを増してくれるものだった。
色気があろうがなかろうが、彼は言葉を愛していた。精神的にそれら
と遊ぶことを愛していた。輪でそれらを遠くに跳ばしたり、さかさまに
したり、あるいは、道に迷わしたり。今朝のように、速記タイピストの
メアリーホートンが、デスクサイズもある計算機を両腕にかかえてオフ
ィスを横切って、ウィロービィ氏の方へ運んでいた。メアリーは計算機
を胸に押し付けていた。そう考えると、明るい1日がさらに明るくなっ
たように彼には思えた。
ウィロービィ氏は、言葉の連想や乖離を愛していた。彼はかつては優
秀な語源学者であった。それに真剣に取り組んでいたという意味で。語
源学について言うと、彼はかつて、とても若いころ、虫を研究する、昆
虫学の言葉と混乱する傾向があった。結論として彼は、〜する人を表す
エントが、昆虫学の蟻のエントと同じことに突然気づいて、幸せな気分
になった。
誤植による間違いは、2重の意味を持てば、彼を幸せにさせるチャン
スだった。速記タイピストが指を滑らすか気分が乗っていない時に、ど
んな奇妙なことが起こるかを見て陶酔するには、あまりに短い間で、一
瞬のスリルとなる。たとえば、先週の月曜日は赤文字の日とされた。メ
アリーホートンがコンガ氏の手紙をタイプしているときに、あるワード
の1文字をとばしてしまった。電話を修飾するpublicのlをとば
してしまった。pubic電話(陰の電話)というフレーズは、魔法で
呼び出されたかのようなすばらしいフレーズだ!慎重に作り出されたよ
うな、おもしろさがあった。偶然できたにしても、真珠やルビー以上の
ものだ。
もちろん、彼はそのことを誰かに見せるわけではない。みんなと共有
するような種類のものではなかった。少なくとも、コンガ&ウェイ社で
働いている者たちとは。彼は、ただ修正を行うだけだった。コンガ氏の
手紙を読んだり修正するのは、彼の仕事の一部であったので、修正しな
ければならなかった。ときどき、美しいものを破壊しているかのように
感じた。
今、彼はため息をつくと、これから出される手紙の最新の束をチェッ
クする仕事に戻った。5通あり、どれも間違いはなかった。それぞれに
コンガ氏自身のサインを完璧にまねた筆跡で、エドワードB・コンガと
サインした。他人の筆跡をまねることは、ウィロービィ氏の多くの才能
のひとつで、これがあまりに長けていたために、にせ物作りの公衆の敵
として、犯罪的な活動に手を染めていた時期があった。
彼はまた、ため息をついて顔を上げた。ステラクロスターマンは一番
下の引き出しに、手紙をファイルしようと、体を曲げていた。ウィロー
ビィ氏には、マーティレインズにあるような、そのようなことについて
考える上での、いかなる禁止事項もなかった。例えば、ステラのスカー
トのふちと、巻き上げたストッキングの間の露出した温かそうな肌は、
なんとすべすべして、なんていい感じで触れるんだろう、というような
ことを考えても。彼の心は、それがなんであれ、さらに白昼夢を見て、
彼の下で働く部下たちを楽しく淫らな想像をすることに、なんのルール
もなかった。
そのとき、彼は簿記係のデスクを見て、愉快なことを思いついた。マ
ーティレインズは、ステラのことを、まるで月に取り憑かれた子牛のよ
うに見ていた。マーティの目はオフィスを見まわして、彼の目と合った。
マーティの顔は赤面して、すぐにまた台帳を見るように頭を下げた。
ウィロービィ氏はマーティをしばらく見続けて、彼の愉快なことは、
ゆっくり哀れみへと変わっていった。それは地獄に違いない、と彼は考
えた。その子が縛られているように結び目に縛り付けられているのは。
女のことはもちろん、影にもおびえて。それに彼は20だ。いや、21
だ。ちょうど1年前に仕事を始めたときは、20だった。21は、感情
的にも、少なくとも女に関しては、彼は、まだ幼稚園レベルだ。たぶん、
まだ彼の生涯で、女に触ったことはなく、夢に見たことさえないだろう。
ステラを見つめる彼の目を見れば分かる。子犬の恋で、降り積もる雪の
ように純粋だ。
なにがマーティをそうさせるのだろう?過度に溺愛されたから?過度
に純粋な母親に?それはありうる。彼はマーティの応募書類の履歴書か
ら、彼が母親と住んでいて、父はマーティがまだ幼い頃に亡くなったこ
とを知っていた。ほかの少年たちの多くは、母親に育てられた子どもた
ちで、それが普通だった。
ウィロービィ氏は、手紙を、送信バスケットに入れた。それから彼は、
マックスレイスマンは辞めて、手紙を出す雑務係がいないことを思い出
した。手紙を折って封筒に入れて、封をして、切手を貼って━━━封書
の切手は2セント?
マックスはかわいそうに、と彼は考えた。なぜ職業紹介会社は、雑務
係の仕事にもっと敬意を払わないのだろう?今朝早くに、そのことで電
話した。
彼はまた顔を上げた。マーティレインズは、台帳ではなく、1枚の紙
になにかを書いていた。それはうしろ暗いかんじがした。たぶん、と彼
は考えた。開いた台帳の上に置いて、見えないがなにかしている。勤務
時間中に、私的な手紙を書いているのだろうか?そうに違いない。しか
し、ウィロービィ氏は、そのことを怒る気にはなれなかった。社員たち
がそのようなことをしないように、見張るのが彼の仕事だった。しかし、
彼は奴隷の監督官ではなかった。マーティが内職しているのを見つけた
のは、初めてだった。マーティがしょっちゅうそんなことをしない限り、
注意する気にはなれなかった。
マーティは書き物を終えて、注意深く見回した。ウィロービィ氏は、
そのときは目を下げていた。頭を下げながら、見てないふりをしながら、
こっそり監視していた。マーティが前かがみになったのが見えた。そし
て今書いたものを、送られてきた送り状書類の手紙を入れる、受信バス
ケットに入れた。それは、ステラがつぎに調べるものだった。しかも、
マーティは注意深く、送り状書類の一番上ではなく、束の中央あたりに
入れたのが見えた。あは、ウィロービィ氏は考えた。マーティは、がん
ばってる。ステラに伝言か手紙か、弱々しい1歩を打とうとしている。
最初の1歩には違いない。
しかし、なんと弱々しい!
突然、ウィロービィ氏は、悪魔のアイデアを思いついた。なんとか抑
えようとして、いったん押し戻したが、打ち負かされた。
彼は顔を上げて、呼んだ。「マーティ、少しいいかな?」
「ええ、もちろん、ミスターウィロービィ」マーティは、高いスツール
から降りて、彼のデスクを回って、オフィスを横切って、ウィロービィ
氏のデスクに来た。
ウィロービィ氏は言った。「マーティ、今日出す手紙の切手が足りな
くなりそうだ。あいにく今日は、雑務係がいないから、代わりに、郵便
局まで行って、いくつか買ってきてくれないか?」
「ええ、もちろん、ミスターウィロービィ、喜んで!どのくらい?」
「10ドル分あれば十分。2セント切手を9ドル分、1セント切手を1
ドル分。おカネは現金ボックスから取って、マックスがしていたように
伝票に残せばいい。5時までに戻れる?」
マックスは壁の時計を見た。「片道15分はかからない。4時半には
戻れる。お安いご用。ほかになにか?」
「ないが、出るついでに、郵便局で、ここの手紙は出してきて!」彼は
送信ボックスにある、封済みの切手が貼られた手紙の方にうなづいた。
マーティはそれらを持って行った。
◇
マーティが出て行ってから、ウィロービィ氏は、小声でなにか言いな
がら、マーティのデスクまで行き、受信バスケットを取った。それを自
分のデスクに持ち帰り、その手紙が出てくるまで、送り状書類を1枚1
枚辿った。
読んでから、悲しそうに頭を振った。それは、ステラに今夜空いてい
ればデートに誘う手紙で、形式は、堅苦しいビジネスレターのように書
かれていた。大げさな書体で。
ウィロービィ氏は、顔をしかめた。引き出しから1枚の紙を出し、ペ
ンを手に取って構えた。マーティのスペンサリアン書体をまねる練習は
いらなかった。ウィロービィ氏は、そのような書体にはかなり熟練して
いて、眠りながらでもまねできた。
なにを書くかも考える必要なかった。それは、他ならず、ソロモンの
愛の詩だった。マーティの純粋な惚れ込みは、聖書の中の純朴さ以外に
なにがある?彼がすぐ思い出すのは、第7章の詩で、内容はそれで十分
だった。
あるいは、少しためらい、
「ステラ、きみの美しさは、古代船のように━━━」
いや、ソロモンは、よくない。別なふうに書いた。
「ステラへ
なんじの靴をはいた足は、なんて美しい
王子の娘のように、ため息は宝石のよう、
手は熟練した大工のように動き、
胸は2匹の双子のノロジカのよう、
偉大な美しいアートのよう、愛と喜びの
なんじのくちびるは、最愛のワインのように、
甘くしたたり、なんじのへそは、酒杯の下で
いざ、参らん、いとしの」
書き終え、すぐに、無造作にM・R・とサインした。(元のビジネス
レターは、マーティレインズとあった)満足気に読み直した。よくでき
たラブレターだ。
書き忘れたことを思い出して、また、顔をしかめた。結局、マーティ
の手紙は、平凡だが、1つのことを訊いていて、ステラが今夜会ってく
れるかどうか、その返事が欲しいのだ。
ソロモンなら、娘をどうデートに誘うのだろう?彼ならそんなことは
しない。娘の両親に娘を買う交渉をするだけだ。ソロモンは置いておい
て、彼は役目を果たすため、もっと現代的に、要点を抑えて、一行付け
加えた。
「PS ステラ、今晩、空いている?」
これはソロモンとは相容れないが、付け加える必要があった。
ウィロービィ氏は、元の手紙を丸めて自分のゴミ箱に捨て、書き直し
たものを、受信バスケットの元あった場所に入れた。彼はバスケットを
マーティのデスクに運ぶと、自分の席に戻った。時計を見て、また、バ
スケットを見ると、ステラがちょうどそこからファイルしているところ
だった。タイミングは完璧だった。彼女は数分の間に送り状バスケット
から、1通取り出すだろう。マーティは、あと10分くらいで戻る。気
が変って、バスケットを捜して自分の手紙を取り返すチャンスはないが、
彼女がその手紙を取り上げるまでには、自分のデスクに戻っているだろ
う。そう、タイミングは完璧だ、と彼は考えた。
誰か少年が、エントランスとオフィス本体を仕切るレールのところに
立っているのに気づいた。ウィロービィ氏のデスクは、レールの脇にあ
ったので、彼は、セールスマンやご用聞きの応対をしたり、断ったりす
る受付の役目を果たしていた。
彼は振り返り、尋ねるようにオレを見た。
オレは息を飲んだ。「あ」と、オレ。「クイーンシティ職業紹介から、
ここへ来るようにと言われて。雑務係の募集で」
5
オフィスの概観を説明させてくれ!実際と違うかもしれない。それは、
当時の記憶はあいまいだからだ。だが、ここで説明しておいた方がいい。
パーティッションがあっても、基本的に、そこは1つの室だ。25フ
ィートから30フィートと広い室で、天井は12フィートと高い。1つ
しかないドアから入ると、そこは南側の中央で、入り口は1つの、木の
レールで区切られた狭いエリアになっている。左には、南側の壁に向か
って置かれたタイプラーターのデスクがあって、速記タイピストのメア
リーホートンの席になっている。右には、壁に背を向けてなにが起こっ
ているか見ることのできる、オフィスマネージャーのウィロービィ氏の
デスクがある。西の壁近くに、壁に背を向けてマーティレインズの簿記
のデスクがある。それは(当時でさえ)旧式の高いスツールに座るデス
クだ。
メアリーホートンの席と簿記デスクの間のかどに、金庫が置かれてい
る。重厚な旧式の金庫で、少し腕に自信のある泥棒なら、タンブラーを
回せばはっきりと解除の音が聞こえるので、1・2分ですぐに開けられ
そうな単純な組み合わせ鍵だった。オレでさえ、昼休みにひとりでいる
時に、おもしろがって、(ちょうど「盗賊ラッフルズ」を読んだところ
だったので)、ロックしたあと、その方法で解錠できた。5分しか掛か
らなかった。金庫の目的は、わずかな現金を泥棒から守ることではない。
ビジネス取引は、切手代のような小額の購入を除いて、すべて小切手で
行われるので、現金ボックスにある平均の金額は、ごくわずかなものだ。
金庫の本来の目的は、コンガ氏が望むように、会社の最も大切な書類を
火災から守ることだった。当時の周辺の土地では、もっとも身近な災害
が火災だった。すべての重要な取引等の書類は金庫で守られ、マーティ
のすべての台帳も夜は中に入れられ、朝に取り出された。
東の壁には、ステラクロスターマンが担当する4段のファイルキャビ
ネットが並んでいて、古いタイプライターが置かれたテーブルもあった。
ステラはファイル係で、勤務時間の半分は実際にファイルを整理してい
たが、他の仕事もした。彼女は速記はできないが、送り状書類の手助け
で、タイプが上手だった。
ほかに2つの保存用キャビネットがあった。そこには手紙や封筒や営
業マンの書類や、備品などが入れられていた。もうひとつのテーブルや
イスは、雑務係の作業用で、ものを詰めたり、シールを貼ったり、封筒
に切手を貼ったりした。
下半分3フィートが木製で、上半分4フィートが曇りガラスのパーテ
ィッションが、オフィスの北側を2つの小さい室に分けていて、1つは
コンガ氏が私室として使っていた。もうひとつは、2つのデスクが向か
い合って置かれ、ふたりの営業マンがオフィスにいるとき、つまり通常
は営業日の最初と最後の1時間に使用した。
窓は、北側の端にのみあって、パーティッションに遮られていたが、
窓は4つで、大きく、ほとんど天井に達するくらい長い窓だった。光は、
パーティッションの上を越えて十分に届き、明るい日には、曇りガラス
を通して、メインオフィスに十分な光をもたらした。各デスクの上には、
円錐形の緑のシェード付きの照明もあって、曇りや雨の日にはそれらを
使った。
すべての家具を説明しただろうか?2脚の予備のイスがあった。帽子
掛けに傘用スタンド。オレの記憶では、それですべてだ。家具はどれも
新しくはなく、いくつかは、特に、簿記デスクとファイルキャビネット
のいくつかは、かなり使い古していた。しかし頑丈に作られていて、こ
の先もまだまだ同じ年数くらい使えそうだった。
オレが一番よく覚えているのは、タイプ用テーブルと同じくらい小さ
なテーブルだ。外の用事がなくて、オフィスで仕事するときは、オレは
いつもそのテーブルで作業していた。時々、すばらしい日に、外の用事
もオフィスでの仕事もないときは、そこに座って、読書が許された。そ
のような時に読む本や雑誌を用意していて、ウィロービィ氏は、オレに
することがない場合に限り、読書していても文句は言わなかった。オレ
は読書依存症だった。アル中が酒に依存するように、読書に依存してい
た。当時は、昼食時にも本を脇に置いて、食事中も本を読んでいた。も
ちろん、図書館で借りた本だった。多くの本をかなりなスピードで読ん
でいた。もしも借りた本でなければ、稼ぎのすべてを使っても、読んだ
本のほんの一部にもならなかっただろう。
それが、オレの知ってるオフィスだった。
しかし、第一印象は、最初の日のレールの外に立って見た印象だった。
こざっぱりして、整理されてはいるが、すすけたかんじだった。ビルは
かなり古く、設備はすべて老朽化していた。だが、当時は、ちゃんと動
いていた。コンガ氏の目的にもかなっていて、新しいスマートなオフィ
スと同じように機能していた。彼は受付を置かなかった。顧客は、営業
マンを呼ばなかったし、コンガ氏も顧客を呼ばなかった。つまり、おも
な顧客は、注文を手紙か電話でした。
そう、そのオフィスは、特別な印象を与えたわけではなかった。しか
しオレには仕事が必要だった。高校を卒業して2週間、オレは仕事を捜
していた。
4時20分だった。ウィロービィ氏は、オレがレールの上から手渡し
た、職業紹介会社の応募書類を見ていた。
彼は言った。「入りたまえ、中へ━━━」応募書類を一瞥して、オレ
の名前を呼んだ。「━━━フレッド」
オレはレールのゲートを越えた。数千回のうちの最初に。
6
メアリーホートンは、口述のため、コンガ氏のオフィスにいた。
ドアは開いていた。コンガ氏のオフィスに女がいるときは、ドアはい
つも開いていた。彼はそのことをはっきり口で言ったわけではなかった
が、もしも、ある状況下で不適切にも部分的にでも、ドアが閉まってい
たら、コンガ氏は言い訳をして外側のオフィスに出て行って、おそらく
はウィロービィ氏となにか話して、戻ってきたときには、ドアを広く開
けたままにしておいた。
コンガ氏の年令では、これはバカげた警戒だったが、ずっとそのよう
な習慣でやってきたし、バカげていると感じたことはなかった。
メアリーホートンは、もちろんこのことは知っていた。彼女が本能的
に常識的に分かっていたことは、コンガ氏は年取ったカナリアのように
性的に危険だということだった。ドアについての彼のルーチンは、時々
は彼女を驚かして、たまたまドアをほとんど閉めて室に入ってしまった
ら、コンガ氏がルーチンを始めるまで何秒かかるか計ったりした。コン
ガ氏はすぐに言い訳をして室を出て、戻ったら、ドアを大きく開けた。
今のように。
しかしこの時は、午後の遅い時間でコンガ氏の口述をしていたが、メ
アリーホートンは驚かなかった。
なぜなら、開いたトアを通して、チックタック言う音が聞こえて、時
計の針も見えたから━━━
(おっと、オフィスの家具を説明した際、オレは重要なものを忘れて
いた━━━時計だ。時計はオレたちの生活を律するものだ。12時に向
かってゆっくり針が上っていけば、その時刻で、1時間自由になるし、
5時に向かってゆっくり針が下ってゆけば、その時刻で、翌朝の8時ま
で自由になる。時計の名前は、ハモンドだった。その名前は、数字と同
じくらいの大きさの文字で、刻まれていた。大きく、前面が矩形ガラス
の角ばった時計だった。真鍮の振り子でチックタックと大きな音で、ウ
ィロービィ氏のデスクの背後の壁の上に掛かっていた。正確に時を刻み、
1週間で1分以上ずれることは決してなかった)
メアリーホートンは、コンガ氏のデスクと同じ側に座っていたので、
そこから、ハモンドの針をはっきり見ることができた。彼女は絶望しな
がら、文章を読んだ。コンガ氏は、午後の遅くに手紙を口述することは
めったになかった。しかし今日は、4時を過ぎていたが、彼はまだ続け
そうだった。午後早くに口述して、すでにタイプに変換した5通は、ウ
ィロービィ氏に回してあったが、今ちょうど口述した8通は、そのうち
の3通は、ゆうに1ページを越えるものだった。そして今、彼はつぎの
口述を始めようとしていた。もしも彼が今日中にすべて済ませたければ、
いつもは手紙はすべて片付けたいと思うので━━━
彼は今、ハス&カンパニーのコールマンの手紙を読んでいて、(すぐ
に彼女にその名前を告げるだろう)、返事を考えていた。太った下唇を
前に突き出し、それがよく考えてる時のくせだった。
時計はチックタック言って、時は過ぎた。もしも彼が手紙の半分だけ
でも、今夜中に済ましたいと言えば、彼女は少なくても6時まで縛り付
けられる。そして、エディは彼女をもうしばらく待つことになる。しか
しそれほど長くないかもしれない。彼も考えるだろうから━━━
「ウー」と、コンガ氏。メアリーホートンは、鉛筆を止めた。
ああ、神様!と彼女は祈った。
「紳士殿」と、コンガ氏。「ターレット盤のロスタイムに関する18番
目の事例の返事は、我々のお勧めの方法━━━として━━━」
困った、とメアリーは考えた。また、長くなりそう、ああ、困った、
困った━━━
メアリーは、不謹慎な娘ではなく、野生的でもなかった。若さが燃え
上がる時期で、そう、プラスチック世代だった。もう少し若い世代は、
パラダイスの側にいた。彼女は単に、恋に深く落ちる少女だった。あま
りに深く恋するあまり、それが彼女の唯一悪い点で、恋に捧げ過ぎて、
しかし完全に悪いわけではなく、教会がなんと言おうが、たぶん、悪で
はありえなかった。特に、彼女が彼と決して結婚できないのは、教会の
せいである場合には。
エディ、エディ、エディ。彼は、彼女にとって唯一重要なものだった。
ハンサムで、頭が良くて(彼女よりずっと)、とてもやさしかった(彼
女が電話してくるのは嫌うけど)しかし、真の熱心なカソリック少女に
とって、恋に落ちたことは、なんと望みのない選択だったのだろう!彼
は、完全な無神論者でないとしても、不可知論者で、完全な共産主義者
でないとしても、急進派であった。しかも失業中で、無一文で、雇用者
ブラックリストにのっていた。
彼についてのそうしたことは、徐々に分かってきて、彼女が気づいた
ときには、問題とするにはあまりに遅過ぎた。それ以来、望みのない恋
に真っ逆さまに落ちていって、恋以外に重要なものなどなくなってしま
った。イエスへの愛や天国への憧れさえも。
「であるから」と、コンガ氏。「2トン容量のハイスピードチェーン起
重機が貴方の問題を解決すると思われる。昇降は9フィート、価格は、
税抜きで160ドル、回転ベアリングと下部スイベル付き━━━」
エディ、と彼女は考えた。
聞いて、そんなことってある?盲目の激しい恋、他のことを考えない
恋、結果を考えない恋、永遠の恋だとしても。
メアリーの鉛筆は、速記ノートの枠をはみ出し、ページから下へ。開
いたドアの向こうの、彼女を見てみよう!
デリケートに着飾った、小さな少女。背は5フィート1インチ(ステ
ラより4インチ低い)、漆黒の髪(ステラはブラウン)、青白く、透き
通ったような肌(ステラはオリーブ色)、恋するハート(ステラのは、
相手に応じる愛、愛に応じての愛)、ステラより3つ年上の22。
メアリーホートンは、いわゆる世紀跨ぎ世代だった。1900年の世
紀が変わる年に生まれ、1922年に22才だった。
彼女は、オハイオ州アセンズ郊外の農場で生まれ、両親によって敬虔
なカソリックとして育てられた。18で高校を卒業すると、ベールを被
った尼僧になると本気で考えていた。なにかが、彼女にも分からないな
いかが、彼女を止めた。代わりに、当時開校されたばかりのアセンズ速
記タイピストスクールに通い、ローカルな農機具販売会社の仕事を見つ
けた。しかし1年後、社長が亡くなって、息子が会社を引き継いだ。そ
の1週間後に、メアリーは仕事を辞めた。辞めた理由は言わなかった。
彼女が決心したことは、都会に行くということ。明確な理由はなかっ
た。両親には、彼女のオフィスでの経験から、速記タイピストの仕事は
都会に行けばたくさんあると説明した。両親が期待して送り出してくれ
るほど、うまく説得できた。そうならなくても、明確な意志があったの
で同じことをしただろう。納得のゆく折り合いをつけて、両親の黙認を
取り付けた━━━シンシナティへ。シンシナティは、結局、まだオハイ
オ州だった。家とそれほど離れてなかった。もともとは、ニューヨーク
へ行くことが最初の希望だったが。シンシナティの最初の仕事は、6ヶ
月後に終わった。会社は、1919年の戦後不況に巻き込まれた。
当時、仕事はまれで、彼女はつぎを捜すのに苦労した。1ヶ月以上か
かった。彼女はわずかな貯金を使い果たし、両親の元に帰るか、両親に
カネの無心の手紙を書くかの楽しくない選択に迫られた。そのとき、1
つの仕事が、ついに、彼女にやって来た。それが、コンガ&ウェイ社だ
った。
1年後に、エディレーノルズに出会い、彼女の世界、彼女の宇宙が引
っくり返った。彼女は最初のデートで頭脳と心臓を失い、2回目のデー
トで、処女性と━━━そして、心のほとんどを失った。それは、逆らう
ことのできない出来事のひとつだった。彼女は抵抗するチャンスさえな
かった(彼のやさしさにもかかわらず、彼女は強制されもせず、なすす
べなく説得された)、まるで太陽の中心で解ける氷のように。
「それに鉄製で安全保証付き」と、コンガ氏。「ここで終わり。メアリ
ー、終わらすのを忘れないように!この起重機のフルスペックのパンフ
レットを入れて!かならずご期待に沿えるものと━━━」
彼女の人生は、今までは、法悦と苦悶だった。それは普通でなく、彼
女自身も普通でないことが分かっていた。彼女の宗教や両親と交わした
厳かな約束、宗教からはずれた結婚はしないという約束は、克服できな
い障碍だった。そういったものがすべて存在しなかったとしても、エデ
ィ自身が存在した━━━言うならば、財政的無責任。結婚は、子どもを
持たないなら、ほとんど意味がなかった━━━メアリーは少なくとも6
人は欲しかった━━━しかし働き続けなければならないなら、子どもは
持てない。そして、エディが仕事につけない、あるいは、つかないなら、
彼女はどうやったら自分の仕事をやめられるというのだろうか?それは、
エディが頭が悪いからではなかった。エディは頭が良かった。彼は輝か
しかった。彼は、あまりに独立心が強すぎて、口答えをした。特に、彼
が考えていることが、仲間の労働者たちの権利侵害や搾取についてのこ
とである場合はいつも。彼は1・2週間以上仕事につこうとすることは、
まれで、すぐに別の仕事を捜し始める。そして、ふつうは、仕事の面接
中も、将来の労働者の権利さえも遠ざけるようにふるまっていた。彼が
規則的に食事ができたのは、唯一、ビリヤードの腕前がプロ並み、いや、
プロ以上だったからだ。ビリヤード場を巡り歩き、小さく賭けて、負け
るより勝つ方がしばしば多かった。たまに、大きく賭けて、5ドルや1
0ドル、20ドル稼ぐと、いつも彼女をお祝いに連れ出した。彼女がカ
ネを貯金するように言ったり、明日のことを考えるように言う意味が、
彼はまったく理解できなかった。
コンガ氏は繰り返した。「かならずご期待に沿えるものと━━━」
静かだった。ハモンドのチックタック言う音と、コンガ氏のイスのス
イベルがキーキー言う音以外はなんの音もしなかった。彼は後ろにのけ
ぞって、「満足」よりもっと満足のいく言葉を捜して天井を見た。
外の通りで、トラックの警笛が単調に鳴った。
神よ!メアリーは祈った。どうか彼に、そこの手紙を全部、今夜じゅ
うに片付けようとさせないで!エディは30分は待つけれど、それ以上
は待たせないで!彼に、わたしが約束を破ったのだから言い訳も聞かな
いと、決めつけさせないで!
「━━━満足」と、コンガ氏。「速やかに納品可能。過去のご愛顧に感
謝。等々。あとひとつで今夜は終わりだ、メアリー。ひとつは、バファ
ム製作所。残りは明日の朝にしよう!」
「分かりました、ミスターコンガ」
そして、神に感謝。
彼女は手紙を予定通り出せるだろう。オフィスを横切ってタイプライ
ターのデスクに向かうとき、彼女のヒールがクリック音を立てた。
彼女が知らないだれか、少年が、オフィスのレールの外に立っていた。
しかし、ウィロービィ氏がすでに彼と話していた。たぶん、雑務係に応
募してきた誰かだろう。
それで、彼女は、まったく注意を払わなかった。デスクに座って、レ
ターヘッドを上げて、カーボンとセカンドシートをタイプライターにセ
ットして、2通の手紙の最初に取り掛かった。彼女は、日付をタイプし
た。
「1922年6月29日」
7
「入りたまえ!」ウィロービィ氏は、オレに言った。
それでオレは、レールの入り口をまたいで、ウィロービィ氏のデスク
の前に立った。彼は、壁に立て掛けてあった予備のイスの方を向いて、
言った。「それを引っ張ってきて、座って!」彼は、今チェックしてい
る送り状書類の山を横にどかした。オレは彼のデスクの端にイスを引い
て、そこに座った。
オレは、金銭的猶予の喜びから、自分自身を見た。高校を卒業して2
週間で、8回目の面接だった。オレはだんだん、面接がイヤになり始め
ていた。雑務係の仕事は、見つけるのが困難になりつつあった。ほとん
どの雇い主たちは、雑務係のような地位の低いポストであっても、1つ
の仕事に10人以上の応募者と面接してから1人を選んだ。しかもそれ
は、多くの応募書類の中から、職業紹介会社が最初にマッチングした会
社の面接がほとんどなのだ。
開いたドアから、速記タイピストが━━━それは手に、速記ノートを
持っていたから分かったのだが、ちょうど出て来るところだった。ひと
りの男が見えた。年寄りで、プライベートオフィスがあることから、ボ
スだと思われた。会社名がコンガ&ウェイ社だったことを思い出して、
ふたりのボスのうちのひとりだろうと訂正した。デスクに向かって後ろ
にもたれ、天井を見ていた。ボスは、上が少し丸いボタンをしていて、
それが似合っているように見えないのだが、後ろに頭を傾けているせい
で、ピンクの禿げの中心にある茶のほくろを見ることができなかった。
けれど、彼は背が低く、太っていて、年寄りであることは分かった。オ
レが座っているアングルからは、2つあるプライベートオフィスのもう
ひとつは、見えなかった。オフィスの一方の端に、簿記係のデスクがあ
った。たまたま不在だったが、台帳や紙が広げたままになっていたので、
誰かがいたことが分かった。向かいの壁が見えるように、オレは頭の向
きを変えた。ほとんどがファイルキャビネットで、そのひとつに、その
時、作業中らしき少女の背中が見えた。しかしオレの目は、彼女を素通
りして無視した。彼女は背の高い女で、その頃のオレは、自分より背の
高い女に、強いコンプレックスを持っていた。
もうひとりの少女は、オレがレールの外側に立っていたときに、オレ
の方に歩いてきた女で、今、レールのないエントランスの向こうのデス
クで、忙しそうにタイプを打っていた。もう一度見返す必要はなかった。
ひと目で、彼女は背が低く、少し年寄りなことは分かった。年寄りとい
っても、オレから見てという意味で、彼女は20代だった。いずれにせ
よ、デートの見込みはなかった。デートするために来ているのではなく、
仕事をもらいに来たのだ。いずれにせよ、前者の前に、後者が先行しな
くてはならない。
オレは、そのときは名前を知らなかったが、ウィロービィ氏の方を向
いた。彼は書類から目を上げて、オレを見た。彼は、笑っても微笑んで
もなかったが、なにか顔は愉快そうに見えた。たぶん、目尻が上がって
いたせいだ。彼は、表面だけでなく、オレの内側も見ているかのように、
オレを見た。オレが考えていることが、正確に読み取られている感じが
した。その感覚は、オレを落ち着かなくさせ、その後、2年間に亙って
しばしばやって来た感覚だった。
それを別にすると、彼は、不快そうに見えた。中年で━━━まだ10
代の者から見れば、30代は中年に見える━━━中肉中背、少し薄くな
りかけた灰色の髪。遠近両用めがねのようなものを数に入れなければ、
取り立てて、特徴的なものもなかった。こざっぱりと、こせこせと着飾
っていた。しかし、一方で、ごてごてと、こってりして、想像力に欠け
るところもあった。ただし、彼の目と、彼の見かけは別だった。特に、
彼の目はオレを驚かした。
◇
「フレッド、年は?」と、彼は訊いた。
「18」と言ってから、気づいた。1つ若く言えばよかった。16か1
7なら、雑務係によりふさわしかった。ほかのもっといい職を見つける
まえに、1年多く勤められるからだ。18だと、数ヶ月で辞めてしまい
そうだった。しかしオレ自身は、手助けができるなら、ほかを捜す気は
まったくなかった。実際のオフィス業務に十分長く勤められれば、つぎ
に簿記係や事務員、あるいは少なくともタイピストの仕事を捜し始めら
れる。オレは、多かれ少なかれ、それらのどの仕事にも訓練は受けてい
た。高校は商業科だった。実際、それらのカテゴリーのいずれかで、ほ
とんど2週間、職を捜したが、それらの仕事に空きがあるのはまれで、
空きがあったとしても何十人も応募者が殺到するので、オレはすでに2
箇所から面接で落とされていた。オレは年より若く見えて、オフィスワ
ークの経験がどれもまったくなかった。
「う〜む」と、ウィロービィ氏。「経験は?」
「夏休み中のアルバイトで」オレは彼に言った。「ヒューズ高校を2週
間前に卒業したので、定職にはまだ就いてない。しかし去年の夏、ワー
リッツァーで働き、その前の夏は、ポッターショアで働いた」
どちらも有名な会社で、名前を挙げても、経歴を傷つけることはない
と思った。また、そのような仕事の経験から、オレが卒業した高校が商
業科で、あらゆるオフィス業務の訓練は受けていることを言わなくても、
分かってもらえると思った。望むのは、雑務係の仕事も短く終わらせて
もらうことだった。すぐに就けると思っていた良い仕事に、なんども落
とされる前の2週間前は、もっとずっとあざ笑うかのように楽観的だっ
た。
「そう」と、ウィロービィ氏。「今は親といっしょに?」
「両親は亡くなった」オレは彼に言った。「母は5年前、父は1年前」
「それはすまない、フレッド。それじゃ、高校で最後の1年は?」
オレは言った。「父は死亡保険に入っていて、死後、少しだけカネが
残った。オハイオ州オックスフォードにいる叔父が、遺産の管財人にな
ってくれて、ヒューズ高校を卒業することに賛成してくれた。毎週少し
づつ仕送りしてくれて、最後の1年を過ごせた。室は、友人の家に下宿
させてもらった」
「今でもそこに?」
「いいえ、ノースサイドに引越した。卒業したときダウンタウンに自分
の室を借りて、そこで仕事を捜し始めた。レースストリートにある」
「高校の成績は?」
「かなり上位」と、オレ。「4年間の平均は、91点」
「大学に行く予定は?」
それは、オレが夏休みに、アルバイト先を捜したことに通じる。9月
に辞めてる。幸いなことに(ほかでもなく)オレは正直に答えた。オレ
は言った。「その可能性はない。カネが底をついた。あと1年も、もた
ない。シンシナティ大学の夜間スクールなら、来年の秋に通うかもしれ
ない」
「よく分かった。聞いていいかな?フレッド、将来の夢は?どのような
職業を、究極的に目指したいんだね?」
「そう」と、オレ。少しためらった。そのとき、オレは決心した。結局、
本当のことを話すしかないと。そうすれば、傷つくより、良いことの方
が多いだろう。オレは作家になりたいと、彼に話したら、生活のために
書くことは、かなり時間がかかると思うだろう。それは確かだ。ストー
リーを売って生活するまで、すでに、2年掛かっている(オレは15で
作家を目指した)一方、彼は思うだろう、雑務係としてどんな仕事を任
されるかは、オレにとってはたいしたことではないと。つまり、ビジネ
スマンを目指したいと言うより、扱いやすいと思うはずだ。それで、オ
レは言った。「オレはストーリーを書きたい」
彼は驚いて、興味を持ったように見えた。「どのような種類のストー
リー?」
「そう、確かには決めてないが、たぶん、さまざまなものを書いてみた
い。もっとも書きたいものが見つかるまでは」
「なるほど。あんたがもっとも読みたいストーリーが、たぶん、あんた
がもっとも書きたいストーリーだよ。好きな作家は?」
オレは言った。「HGウェルズ、ジュールベルヌ」ほかに、声には出
さなかったが、サックスローマー、エドガーライスブローズ。ウェルズ
とベルヌをより尊敬する。「あと、イプセン」オレは付け加えた。
そう付け加えたことで、ウィロービィ氏の目尻が少し上がったが、そ
のことで彼を責める気はない。オレの言ったことは本当で、少なくとも
イプセンを読んだことまでは。公立図書館で借りられた、イプセン戯曲
の全巻を1巻づつ頑固に読み続けた。そしてついに、それが自分にとっ
てどう良かったのか分からないが、全巻を読み終えた。今、その戯曲の
どれもあいまいな印象しか残ってない。最近読み返した数冊と、上演さ
れたものを見た以外は。しかし、頑固に読み続けたことは誇りに思って
いるし、ウィロービィ氏の目尻には、断固として、ひるんだりはしない。
「ふ〜む」と、ウィロービィ氏。「そう、フレッド、あんたがこの仕事
ができることは疑いもない、イプセンを1冊も読んでなくても。唯一の
問題は、もっと若い者を雇ったことがないことだ。数週間や数ヶ月で辞
めてしまう者を、雇いたくはない。少年を雇って、すぐ辞めて、裏切ら
れるのは辛い」
「分かる」と、オレ。「別の職は捜してない。夜は書いてるので」
ウィロービィ氏は、それほど疑ってなかったので、オレは希望を持ち
始めた。しかし、彼は言った。「もうひとつ。職業紹介会社から、ここ
で支払う給与の額を知らされていると思うが、それがすべてで、少なく
とも最初は。その額は自宅から通う者には十分だが、ひとり暮らしの者
にはどうか━━━それでやって行ける?」
「はい」と、オレ。「自分にとっては、十分。すぐにストーリーを売り
始めて、それを足しにするつもりなので」
「それじゃ━━━」一瞬、疑ってるように見えたが、彼は言った。「よ
し、あんたに仕事のチャンスをあげる。明日の朝8時から、どうかね?」
オレはできると言った。彼は手を差し伸べた。「オーケー!ついでに、
オレの名前は、ウィロービィ、ジェフリーウィロービィ。ほかのみんな
は、明日の朝、紹介する」
オレは彼の手を取り、握手した。オレは仕事を得た。
立ち上がって、向きを変えると、面接中にオフィスの人数が増えてい
た。オレより少し年上で、少し背の高い若者が、オレが入って来た時は
誰もいなかった、簿記係のデスクに座っていた。
ふたりの営業マンが、ほとんど同時だが、まったく別々に入ってきて、
もうひとつのプライベートオフィスに、入れ替わりながら向かった。
オレは彼らの名前を、ウィロービィ氏以外は知らなかった。彼らのす
べてを、オレが見ていた、あるいは、見ているということを、そのとき
は気づかなかった。しかし、彼らはみんな、そこにいたのだ。ジェフリ
ーウィロービィ、ブライアンダナー、ジョージスパーリング、マーティ
レインズ、メアリーホートン、ステラクロスターマン、それに、エドワ
ードB・コンガ。人生の半分、35年の霧を通して、その時や続くその
あとも、彼らを見ているように、今、オレは彼らを見ている。
あんたは、彼らすべてをふたたび、1つのオフィスに集めることはで
きないだろう。何人かは死に、ほかの3人だけ、まだ、シンシナティに
住んでいる。ほかのみんなはバラバラになった。オレ自身も、25年間、
シンシナティには帰っていない。そして、2000マイル離れた場所で、
これを書いている。そう、彼らすべてをふたたび、集めることはできな
いだろう。今、ここで、オレの心の中で、集めるのでない限り、そして、
望むべきは、これらのページで、集めるのでない限り。
8
コンガ氏は、少年が出て行くのを見ていた。彼は、「ジェフ」と呼ん
だ。ウィロービィ氏は、ちょうど電話の受話器を持ち上げていたところ
で、それをふたたび下に置いて、コンガ氏の私室のドアのところへ行っ
た。「はい、ミスターコンガ?」
「雑務係の応募者かね?雇った?」
「はい、彼の方もいいようで」
「いいね、マックスの給与と同じ?」
ウィロービィ氏は、頭を振った。「1ドル半、低く。彼の仕事ぶりが
良ければ、すぐに昇給させる。その方が、最初から高いより、彼の喜び
は長く続く」
「いいね、スタートは、明日の朝から?」
「はい、職業紹介会社に電話して、ほかの応募者をまわさないように伝
えたところ」
「オーケー、ジェフ。知りたかったのは、それだけ」
ウィロービィ氏は、自分のデスクに戻り、コンガ氏は、座った。
マンガのフォクシーじいさんのように顔をしかめている、コンガ氏。
背が低く、太っていて、頭はツルッパゲで、周りを薄い白髪のふさがお
おい、中心に茶のほくろがあった。てっぺんに、丸くて小さなボタン。
コンガ氏には、心配事が多かった。
心配なのは、売り上げが下がり気味で、あるべき活況を呈してないこ
とだった。十代の娘が最近ピアノを始め、奥さんから、グランドピアノ
を買うよう迫られていることも心配だった。家族は、頭に穴が必要であ
るかのように、グランドピアノを必要としていた。会社の売り上げが落
ちているにもかかわらず、一般のビジネスは好調続きで、バブル崩壊が
心配だった。大学生の息子は、ジャズに熱中していて、社会に出て生活
費を稼ぐ準備をするよりも、酒を飲んでばかりいることが心配だった。
そういったことより、なにより心配だったのは、彼の健康のことだった。
胸に痛みがあって、医師から、喫煙は1日2本までと、きつく言われて
いた。1日2本であろうが1日12本であろうが、30年以上たって、
大きな違いがあるというのだろうか?
明日が彼の60才の誕生日なのが、心配だった。59なら年寄ではな
いと言えるが、60でもそう言えるだろうか?あと数年しか生きられな
ければ、どうする?医師の言うことが正しくて、禁煙できなければ、も
っとわずかしか生きられないかもしれない。
顔をしかめながら、私室の外のメインオフィスを見ていた。営業マン
のブライアンダナーとジョージスパーリングのふたりが、帰って来たと
ころだった。ひとりはメインオフィスのウィロービィ氏のデスクの前で、
なにかを尋ね、私室へ戻った。たぶん、価格か割引率を訊いたのだろう。
ウィロービィ氏は、カタログを見ることなく、すぐに、どちらの質問に
も答えていた。頼りがいのあるやつ、ウィロービィ。
戻りながら、ブライアンダナーは、ふたりの営業マンのうち若い方で、
はるかに営業成績のいい方だが、コンガ氏の私室のドアを覗き込んだ。
彼は言った。「ハイ、ミスターコンガ!いい天気で!」
コンガ氏も「いいね」と認め、ダナーが営業マンオフィスに戻って、
笑顔が届かないにもかかわらず、笑顔を作った。
ダナーのやつめと、コンガ氏は考えた。若くて、妻も子どももいない
から、出費がなく、心配事もない。彼よりずっと金銭的に余裕がある。
先週、ダナーのために60ドルを越える小切手にサインしなければなら
なかったことが、悔しかった。若い独身ものは、ずっとリッチなんだか
ら、手首の厚さを越える貯金をしてなければ、するべきだ。
ところで、ジョージスパーリングは、今日はなにを?たぶん、よくな
かったのだろう。入ってくるときに、顔を見せなかった。営業マンがボ
スを避けるのは、成績が良くなかったからだ。
コンガ氏は、「ジョージ」と呼んだ。スパーリングが室に入って来た。
コートは、すでに、脱いでいた。ベストは、ボタンをはずして、だらし
なく見えた。彼は、なぜ、キチンとできない?ダナーは、暑い日でもコ
ートを脱がない。しかし、スパーリングは、疲れているようで、営業マ
ンにあるべき、活気がない。
「どうだね、ジョージ」と、コンガ氏。
「それほど、良くは、ミスターコンガ。2・3、小口の注文だけ。季節
的に、時期が悪い。いくつかの工場は、人減らしをしている」
ボスである彼が、そういったことを知らないかのように。しかし、ダ
ナーは注文を取ってきている。それに引きかえ、スパーリングは、とコ
ンガ氏は考えた。ビジネスはどこも行き詰まってなんかないし、減退も
してない。彼は、まだ、30代だ。ダナーと比べたら若くはないが、6
0と比べれば、ずっと若い。コンガ氏は、40代でも、ファイヤボール
のように、1日12時間働いて、それを楽しんでいた。
今、彼は小言を言った。「ダナーは、どうやって注文を?」
驚くことに、スパーリングは、ニヤリとした。彼は言った。「たぶん、
オレより、有能な営業マンだから?」
これには、どう答えたらいい?コンガ氏は、答えることなく、無視し
た。自分が、有能な営業マンでないことを認めた男に、どう対処したら
いい?
いつか彼は、スパーリングを配置変えするだろう。それが、彼にでき
るすべてだ。あるいは、他に手は?スパーリングが取ってくる注文は、
ダナーの半分だとしても、少しは売り上げになっていて、彼のお得意さ
んもいるので、コンガ&ウェイ社としては、彼なしにはできなかった。
たぶん、3人目の営業マンが、答えかもしれない。しかし、3人目は、
ダナーやスパーリングのテリトリーを奪わねばならず、あるいは、顧客
リストの一部を、彼用に用意しなければならない。
あるいは、彼の顧客の一部をあきらめろと、商売してるのに?彼が担
当している売り上げには、手数料を支払っているので、これも1つの重
要な決定だった。しかし、彼も年を取ってくれば、かつての元気はなく
なって、しばしば達成していた売り上げを見れるのは、まれになった。
もしも、ダナーのように若くて、やり手なら、彼が6・7年前に達成し
ていたような、売り上げを達成できるだろう。あるいは、彼でもできる?
6・7年前は、戦時中で、条件が今とは違っていた。戦時中は、機械類
産業全体が好景気だった。売り手市場で、売ればなんでも売れる時代で、
唯一の問題は、どう仕入れるかで、お客を見つける苦労はなかった。
しかし、彼の担当医師は、完全に引退するよう言っていて、引退が無
理なら、勤務時間を半分にして、給与も半分にするとか、オフィスにず
っといたとしても、第3の営業マンを雇うとか。それは、彼を家庭でも
地獄に追いやる。給与が下がるという点で。妻は、彼が与えられる以上
のものを、すでに要求していて、息子や娘も同じだった。
それで、彼は、もう考えるのはやめにした。
ため息をついて、立ち上がり、オフィスを横切って、ウィロービィ氏
のデスクへ。「ジェフ、オレの引退を考えてくれ!オレでなければなら
ないものは、もうないだろう?」
「ええ。メアリーに打ってもらった手紙は、今夜じゅうに出す?」
「そうしてくれ!2通は、特に。それで━━━」
コンガ氏は、立ちくらみがして、デスクに手をついて、回復するまで
休んだ。ウィロービィ氏は、それに気づかなかった。あるいは、気づか
ないふりをした。
9
スパーリングとダナー。ダナーとスパーリング。
ふたりは、あとで、よく知ることになるが、今、その日の売り上げ伝
票を書いている、ふたりの服装や外観を見てみよう。オフィスの外側の
ドアが、コンガ氏のうしろで閉まったとき、ジョージスパーリングは、
すでに伝票を書き終えていた。当然、彼が記入する伝票は、数が少なか
った。
彼は、実際、5分前に書き終えていた。コンガ氏は、普段なら、5時
より20分ぐらい前に退社するのだが、(それは、5時の帰宅ラッシュ
で混んだ路面電車を避けるため)、そして、スパーリングは、自分の伝
票を書き終えたら、帰宅してもよいことになっていた。しかし、彼は、
コンガ氏より先に帰ることは、避けるようにしていた。数分が大きな違
いとなる場合はいつも。
彼は顔を上げて、ダナーを見た。ダナーは、忙しそうに伝票を書いて
いる最中で、顔は上げていたが、並んだデスクにいる彼の方を見ること
はなかった。彼は、「コンガ氏は、もう帰った?」と、訊いた。ダナー
は、ドアの近くに座っていて、メインオフィスの方を見れた。
ダナーは、うなづいて、言った。「海辺には、誰も」辛抱強い不満を
もって。それは、彼がスパーリングに対して感じていたことだった。辛
抱強い不満。軟弱な男。無茶はしない。
スパーリングがダナーに感じていたことは、もっと定義するのが難し
い。ねたみでは、なかった。彼には、ダナーと張り合えるところは、な
にもなかった。彼は、ダナーと同じくらい良い営業マンになりたかった。
少なくとも、ダナーと同じくらい稼ぎたかった。しかし、彼は、いかな
る点でも、ダナーになれなかった。なぜなのかを、言うことはできなか
ったが。(多くの人間が、他の人間になりたがっている。しかし、そう
なれない理由を言える人間は、なん人いるだろうか?)よく彼は、ダナ
ーは、なぜそんなに稼げるのだろうと不思議に思ったが、しかし、答え
は1つではなかった。1つには、もちろん、ダナーが信じるところでは、
誰でも情熱と気力のすべてを捧げれば、12回訪問したら、12回の注
文を取ってこれるということだった。年令の違いではない。ふたりの年
令に、それほど大きな差を生む違いはなかった。それに、彼は、ダナー
と同じくらい機械類ビジネスについて、よく知っていた。すでに、1・
2年、そのビジネスに携わっていた。さらに、カネを稼がなければなら
ない理由もあった。ダナーは独身だが、彼は結婚していた。結婚後6年
で期待されるほどに、妻を愛していた。
目立った違いを生んでいるのは、ダナーが貯蓄を株式投資にも回して
いて、売り上げ手数料より、手首の厚さを越えるカネを稼いでいること
だった。
スパーリングは、ベストのボタンを掛けながら、ゆっくり立ち上がっ
た。後ろに手を伸ばして、コートを取ると、イスの背に掛けてから着る
と、ボタンを掛けた。イスを回って、壁のフックから、ハットを取った。
2・3秒立ったまま、頭の後ろにずらしてかぶり、窓から外を眺めた。
そこは、いつものように、乱雑な工場と倉庫が立ち並ぶ一画だった。
それから、自分の売上伝票をつかむと、ウィロービィ氏に渡し、グッ
ナイと言ってから、マーティにもソロングと手を振り、(あのかわいそ
うなノイローゼ気味の少年、と彼は考えた)、出て行った。ドアの外で
立ち止まって、タバコに火をつけた。マッチの明かりで、ガラスに、か
すかに、彼の姿が映った。ふつうの背丈、中年、体格もふつう、顔もふ
つうの男の姿。ハンサムでもなく、醜くもない。他になにもない、失望
してなければ。なぜ、失望しなけりゃならないんだ?彼は考えた。どこ
かへ行くわけじゃなし!ガラスの影に背を向けると、彼に取り憑く前に、
足早に遠去かった。そうさ、きのうも同じだった。今日も、明日も、そ
の先も、永遠に。
◇
ブライアンダナーは、最後の注文欄に最後の数字を書き込むと、金の
シャープペンをベストの左上のポケットに戻した。金のペンの隣りに。
このペンとシャープペンのペアには、強い誇りを持っていて、営業の強
い味方でもあった。値段は、週の稼ぎを上回った。もちろんこれは、彼
の稼ぎが今ほど高くなかった頃の話だが、今でも、この金のペアを大切
にしていた。ゴールドメダルを獲れ!当時の決意のシンボルであった。
意味するのは、いつか金持ちになるということだった。このペンとシャ
ープペンのペアは、彼の唯一の贅沢だった。あんたたちが、贅沢として、
いい服を買うのと同じだった。彼は営業マンなので、それができなかっ
た。正確には、それほど迷信を信じていたわけではなかった。それに近
いというだけだ。ただ、新しいものやもっと高いものに変えるという気
はなかった。
伝票書きを終えて、わざと、この瞬間を味わうために待っていた。デ
スクの電話に手を伸ばし、(電話はスパーリングと共用だが、スパーリ
ングはめったに使わない)、番号を告げた。だれかが出たので、彼は言
った。「ユナイテッド石油の終値は?」答えを聞いてから、「フリーポ
ート石油は?」
「サンクス」と言って、電話を切り、急いで、頭で計算した。ユナイ
テッド石油の終値は、きのうと同じだった。しかし、フリーポート石油
は、0・5ポイント高かった。60株持っていたので、彼は、きのうよ
り、30ドル金持ちになったということだ。カネが増えることは、毎日、
コンガ氏のために働くよりも、満足にも不満にもつながる、と彼は考え
た。しかし、今の彼には、すぐ会社を辞めて、株式投資で生活するには、
資金が足りなかった。将来的には、少なくとも数年のあいだには、りっ
ぱな仕事に就いて、安定した所得を得たいと考えていた。特に、資金に
は手を付けないで、それが増えるままに、自然に増やしたかった。生活
費を稼ぐために、どっぷり仕事に漬かっていたら、いつ増やすんだ?
伝票をそろえて手にして、立ち上がると、しゃれた山高帽を、いきな
アングルでかぶり、(オフィスの中でのみのかぶり方で、通りでは、そ
んなふうにはかぶらない)、外側のオフィスのウィロービィ氏のデスク
に行った。「急いで、できる?」と、訊いた。
ウィロービィ氏は、シートをパラパラめくった。「いい仕事ぶりだ、
ブライアン!1つ言うとすると、グロービー社の0・5インチのカッテ
ィングバーだが、あんたの指定したC&Wでは、来月までに納品できな
い。そんなに待たせたくないなら、別のブランドでもだめなら、キャン
セルするしかない」
「そう?」と、ダナー。顔を上げて、ドアの上の時計を見た。「グロー
ビー社は、ふつうは5時までやっている。担当者がいるかもしれないか
ら、今、電話して訊いてみる」
彼は自分のオフィスに戻り、電話して、戻って来た。「オーケー、ジ
ェフ。在庫の注文だったので、1か月待てるそうだ。注文伝票は、その
ままで。じゃ、また、トゥードゥルー!」
彼はドアに歩き始めて、メアリーホートンのデスクの前で立ち止まっ
た。彼女は、封筒に住所を打っていたが、顔を上げた。
「ハイ、キッティ!今夜、忙しい?」
それが、彼のルーチンで、毎晩欠かすことがなかった。うんざりされ
るだろうが、週2.3回は彼女に訊いて、これは、少なくとも、100
回目にはなる。彼は、最初は、まったく本気だった。彼女のことが好き
で、チャンスがあれば、好き以上の関係になれると思っていた。しかし、
12回以上、ストレートにふられると、プライドはずたずたになり、そ
のうちバカらしくなって、それは、ただのギャグだったことにして、面
目を保つため、ずっとルーチンとして続けていた。
彼は、どういう返答が来るか、分かっていた。「そうね、ミスターダ
ナー。今夜は、忙しいの」彼女の返答は、彼の質問と同じく、ルーチン
化されていた。
彼は、ニヤリとした。「そう、なら、楽しんできて!そして、オレを
夢に見てくれ!」
「悪夢を見たら、そうする、ミスターダナー」
これは、新しい会話だった。彼女は、これを予想していたに違いない。
メアリーは、アドリブでうまく答えられるタイプでなかった。
ダナーは、嘲りのため息をついた。「傷ついたよ、キッティ!」
そして、傷つきながら、山高帽をまっすぐにして、ドアを出て行った。
外へ出てすぐ、スパーリングがしたように、立ち止まり、タバコに火を
つけた。そして、メアリーは、なぜデートしてくれないのだろう、と考
えた。たぶん、別の誰かと、恋をしているのだろう。そうに違いない。
ダナーは正直であったが、ほかの論理的理由を考えられないほど、想像
力がなかった。彼は、個性的で、魅力的で、貯金があって、将来有望だ
った。それ以上、彼女は、なにを望むというのだろう?彼女が、別の誰
かと恋に落ちているのでない限り、そのうち、彼と結婚することになる。
彼は、ため息をついた。いずれにせよ、彼はルーチンを続ける、真剣
な気持ちで。たとえ、なんども誘うのは、ただのジョークであるかのよ
うに見せていたとしても。そして、いつか、愛が伝わって、彼女がイエ
スと言う日が来るだろう。
10
ファイルキャビネットは、閉じていた。ステラクロスターマンは、軽
い目まいを感じながら、引くと、それは開いた。金属製のキャビネット
の上に置いてある、ファイルバスケットが、がたがたと音を立てた。
彼女は、額の後ろに茶の髪を丸くまとめ上げていて、バスケットから
次の手紙を取り出した。それは、一番下の引き出し行きで、すべての手
紙が一度、その一番下の引き出しのファイルの束に加えられた。彼女は、
その手紙を手に取った。
手書きで、ペンとインクで書かれ、奇妙だった。今まで、見たことが
なかった。たまに、ウィロービィ氏は、手書きで書いた手紙を、メアリ
ーにタイプしてもらうために渡すが、その場合は、オリジナルのものは
メアリーが見るだけで、タイプ済みの束に加えられる。ときどき、ごく
まれだが、営業マンのふたりのいずれかが、メアリーに、同じようにタ
イプしてもらうことがあった。しかし、この手書きの筆跡は、馴染みの
あるように見えるが、ウィロービィ氏のものでも、営業マンたちのもの
でもなかった。
それから、ファイルするために、宛名の会社名を捜したが、ステラが
見たのは、『ステラ』という文字だった。
なぜ、わたしなのか、彼女は考えた。バカらしいように思えた。彼女
の目は、すぐに、手紙の一番下を見た。そこには、M・R・とサインが
あった。一瞬、M・R・は、ミスターのことかと思ったが、MRなら、
最初の文字のあとにピリオドはない。しかし━━━
それから━━━背中に視線を感じて━━━だれなのか分かった。マー
ティレインズ。台帳に記入された、手書きの文字を見たことを思い出し
た。しかし━━━
なんじの靴をはいた足は、なんて美しい
王子の娘のように、ため息は宝石のよう、
手は熟練した大工のように動き、
胸は2匹の双子のノロジカのよう、
なぜ『ソロモンの詩』?
あんたなら、3度見、4度見するかもしれない。悪い冗談に思えた。
だれも、彼女の顔を見ている者はいなかった。(ウィロービィ氏は、彼
女を何度も見ていることがあった。背中さえも。しかし、今日はまった
く見てなかった。自分の仕事に没頭していた。今はちょうど、スパーリ
ングとダナーが提出した、売り上げ伝票の数字を集計していた)彼女は
仕事を中断したまま、急いで読んだ。美しい言葉は、聖書からの引用で
はあるが、彼女に宛てて書かれたものだった。彼女に、ステラクロスタ
ーマンに。
その瞬間、顔が熱くなった。頬に、突然、赤味が差すのを感じた。
おかしさがやって来た。欲しかったもの。次の瞬間、くすくす笑い出
しそうで、耐えられなかった。しかし、耐えた。彼女は、くすくす笑う
タイプでなかった。「なんじのへそは、酒杯の下で━━━」
そのとき、突然、静かに立ったまま、マーティレインズが後ろの席に
いる気がした。彼女が読んでいることにも気づいているに違いない。彼
女は、もう一度読み、態度を決めた。最初のショックのあとは、もう、
ショックでなくなった。彼女は、しとやかぶるタイプでなかった。くす
くす笑いしそうな瞬間が過ぎると、まったくおかしくなくなった。しか
し、それは奇妙だった。もっとも奇妙だったのは、ほかでもないマーテ
ィが、それを書く勇気を持ったということだった。彼はいい人で、楽し
そうだったが、同時に、おとなしく、シャイで、顔をじっと見たりすれ
ば、赤くなった━━━そう、彼女は、彼がこれを書いたことが、ほとん
ど信じられなかった。彼女の手の中にある、この手紙を。
しかし、5度目に考えたことは、いや、10度目?(数秒しかたって
なかったけれど)ステラは、自分の反応に、恐れを抱いた。だれかが、
欲していて、あえて、彼女に宛てて、これらの情熱的で美しい言葉を、
あえて書いたことに、恐れを抱いた。彼女に、ステラクロスターマンに。
王子の娘ではない、雑貨店の店主の。(とても小さな近所の雑貨店(そ
こに建って営業してるだけで、店主に十分な稼ぎをもたらす)の娘。彼
女に、ステラクロスターマンに。今までのボーイフレンドとの付き合い
は、このような、黒ずんだ、詩的な、五行戯詩のステージに来たことは
なかった。
彼女は振り返って、マーティを見た。まるで初めて彼を見るような新
鮮な目で。しかし、今すぐには、あえて行動しなかった。代わりに、手
紙を小さく折りたたんで、ドレスの前から下へすべり込ませた。双子の
ノロジカのような胸の間に。
次の10分間は、ゆっくり仕事し、5時より少し前に仕事を終えた。
空のバスケットを、簿記係の隣のテーブルに運んだ。ドキドキしながら、
目線を下に落として、奇妙な気がしながら。
彼女は、マーティレインズが咳払いするのを聞いた。彼は言った。
「う、ステラ、オレのメモを見た?」
彼女は彼を見て、また赤くなったが、声は冷静だった。「なぜ、そう
ね、マーティ。ないわ、今夜は、特にすることは。(彼女は女友達と映
画に行く約束をしていたが、すぐにキャンセルできた)迎えに来てくれ
る?そうね、7時半に。早過ぎる?」
「うぅ、いいよ、ステラ、大丈夫。そう、家は?」
「ホルツマン、6の18番地。ブライトンの先。父の雑貨店の2階。名
前は、クロスターマン雑貨店」
「いいよ、7時半なら大丈夫。住んでるところから、歩ける距離。いい
ね、ステラ」
彼は、ハンサムではないし、と彼女は考えた。自分は、もう少し背が
高い男が好き。しかし、ローヒールをはけばいいだけだし、彼は顔立ち
は、素敵。ブロンドの髪は、いい具合にウェーブがかかっていた。それ
に、今まで気づかなかった。
11
5時になった。退社の時間。
オフィスの時間は単純だった。8時から12時と、1時から5時。週
44時間労働の決まりを守るため、土曜は午前のみ。(なんと、土曜の
午後と、日曜は自由!)
朝、ウィロービィ氏が、いつも最初に来た。コンガ氏を除けば、彼だ
けがオフィスのカギを持っていた。ふつうは、8時10分前を過ぎない
ように来た。彼は、デスクに座って、その日の準備をする。その間に、
オレたちは、ばらばらに入って来る。ふつうは、時間通りか、1・2分
早く。しかし、数分遅れたとしても、何度も遅れたのでない限りは、な
にも言われなかった。(もちろん、時々は、定時を越えての仕事もあっ
た━━━ごく、ごくまれには、とても遅くまで━━━定時を越えての仕
事に支払いはなかったので、それはフェアなことだった)
オレたちというのは、メアリー、マーティ、ステラ、そしてオレ。営
業マンのダナーとスパーリングは、少し違う時間帯だった。彼らは、8
時半にオフィスにいることはなかった。彼らが、そこですることは、あ
まりなく、顧客を回る1日の計画を建てたり、時々は電話で約束を取り
付けたりするが、9時前にすることはほとんどなかった。顧客の多くも、
オレたちと同じに、8時から仕事が始まるが、営業日の最初の1時間は、
営業マンたちに邪魔されたくなかった。同様に、最後の1時間も。営業
のもっともいい時間帯は、9時から4時までだった。それで、営業マン
は、どこにいたとしても、だいたい4時には会社に戻り始める。戻れる
ときはいつでも。顧客は、ほとんどがダウンタウンの近くであったから、
戻るのが4時半になることは、めったになかった。1日の注文伝票を書
き終えれば、帰るのは自由だった。これは、彼らは、オレたちより、仕
事の時間が短いことを意味するが、仕事は、給料ではなく、手数料制だ
ったから、オフィスにいようが、外で時間つぶしをしていようが、問題
とならなかった。その上、たまに、顧客と会ったり、食事をいっしょに
したりすることもあった。これは義務ではないが、仕事の一部と認めら
れていた。コンガ氏は、それらの支払いは、経費と認めなかった。しか
し、あるタイプの顧客に対しては、注文を取るために、手数料とともに、
経費として認められた。
コンガ氏は、みんなより働く時間が、短い。すごく短くはないが。年
令や健康を考えて、また、彼は会社の創設者であり、ボスであり、パン
ヤンドラムだったので。彼は、ふつうは、9時に来て、もっと前に来た
のでなければ、ランチの時間までオフィスにいた。その日の手紙に、ウ
ィロービィ氏に任せるルーチン書簡以外は、返事を書いた。ふつうは、
ランチのあと、すぐ戻らずに、彼の顧客に電話して会っていた。オフィ
スに戻るのは、3時と4時のあいだで、いつもの路面電車に乗るために、
ふつうは5時20分前には帰った。(コンガ氏は、自動車が嫌いで、今
まで運転したことがなく、将来もしない)
ウィロービィ氏がいる時間が、もっとも長かった。朝、最初に来るだ
けでなく、夜も、いつも最後までいた。メアリーが残って、手紙の束を
済ませなければならないときも、彼は、チェックしサインするために、
彼女が終わるまで、オフィスにいた。マーティが簿記で残業するときも、
これは、月の初めにはよくあって、小切手が支払期日になったり、簿記
の計算を合わせるために、ウィロービィ氏も残って、手助けした。彼は、
自分用のサンドイッチを持って来ていて、ランチのときもオフィスにい
た。彼は、ずっと仕事してるわけではないが、誰かが入って来たり、電
話が鳴ったときには、そこにいた。ときどき、オレたちの誰かが、早目
にオフィスに戻って、ランチの残り時間もいる場合は、外の空気を吸う
ために、あるいは個人的な用事を済ませるために、外に出た。(オレが
ひとりでオフィスに残されたのは、そうした日で、「盗賊ラッフルズ」
のマネをした)いいやつ、ジェフリーウィロービィ。給与がいくらであ
っても、それだけのことはしてる。オレが思うに、もしも彼がいなけれ
ば、オフィスは空中分解してしまう。そして、コンガ氏も、それが分か
っていると思う。
パート2=始まりの終わり
1
そう、彼らがふたたび、いっしょになることは決してない。しかし、
その時期、彼らは同じマシンで、協力してギアや歯車を切り替えて、働
いていた。オフィスというマシンで。
ニブいやつら、とオレは考えていた、特に、そこで働き始めた、最初
の数か月は。その頃、オレは本の世界に鼻先まで浸かっていて、つぎか
らつぎへと本を読んでいた。仕事の行き帰りの路面電車でも、ランチを
食べながらでも。本の登場人物たちは、オレの仲間で、いっしょに働く
ことになったニブい連中とは、かけ離れて、魅力的な存在だった。彼ら
は、本の登場人物ではない方は、非現実のまぼろしだった。彼らのひと
りかふたりが、オレに雑用をさせたりすると、やっかいで、インクつぼ
をいっぱいにしろとか、封筒に切手を貼れとか、キャビネットからファ
イルを持ってこいとか、窓を開けろ、閉めろとか。オレは、そんなこと
は、少しも気に掛けなかった。彼らを、オレの心から排除していた。な
るべく、考えないようにしていた。それに、もしも、オレに言いつけら
れる用事がなくなったら、オレにはする仕事がないということになって、
それはつまり、つぎの仕事を捜さなければならないことを意味した。こ
れは、もっと、うれしくなかった。
そんなふうに、時は過ぎて、秋が来た。なにも起こらなかった。重要
なことは、まだ、起こりそうになかった。
しかし、オレとあんたで、彼らを、振り返って見てみよう。オレがい
っしょに働いていたやつらを、もう一度、今度は、オフィスから離れて、
遠くから、どんなふうに彼らが、生きていたか見てみよう、。だれから?
ウィロービィ氏がいい。オレが一番好きなやつから。
2
10月の夕暮れが濃くなり、空を雲が横切った。陽の光は消え、星も
月も見えなかった。大きな雲が、空をおおった。もちろん、あんたには、
夜、雲を見ることができない。月が横切って、照らしてくれるのでない
限り。夜の立体の雲は、空の見える部分が一部、欠落しているに過ぎな
い。視覚的にネガティブで、干渉によってしかその存在を知ることがで
きない。しかし、雲は、そこにある。大気は、だんだん湿気を帯びて、
小さなそよ風が吹いていても、完全な静寂に飲み込まれる。
雲は、水滴を落とし始めた。最初はゆっくり、霧雨になり、だんだん
速度を増して、雨は、冷たい強風を伴った。大粒の雨粒が、斜めに落ち
て、セメントの舗道やアスファルトの道路に、水しぶきを上げた。
1時間後、8時少し過ぎに、雨は、突然、止んだ。まるで、だれかが
蛇口を閉めたみたいに。数分で、側溝は雨水の残りを下水道へ運び、下
水道は川へと運んだ。水たまりと濡れた舗道の輝きを除いて、雨はなか
ったかのようだった。
ウィロービィ氏は、食料品店から帰る途中で、雨が止んだとき、立ち
止まった。だれが雨を突然止めたのか確かめるように、上を見上げた。
電線からの大きな雨粒が、驚くほどの正確さで、彼の右目めがけて落ち
てきた。彼は、まばたきして、頭をすくめた。
よけいな世話をやくと、と彼は考えた、ひどいめにあわすぞ。買い物
袋を、別の手に持ち替えた。そして、ハンカチを出すために、レインコ
ートのえりのボタンをはずした。
冷たいそよ風が、雨を心地よく甦らせ、10月にしては、蒸し暑かっ
た。レインコートのえり元はあけたまま、頭の上のハットをうしろにず
らした。空気は、新鮮できれいになって、よく眠れそうな夜だった。
また、歩き出した。今度は、もっとゆっくりと。
黒いなにかが、通りを渡って、彼の前を横切った。それは、とても大
きな、濡れて泥だらけのネコだった。ネコは、彼が歩く方向に横切るこ
とで、ウィロービィ氏に追いつこうとしていた。舗道まで来た。
ネコは走るのを止めて、彼が歩く前で、こちらを見た。ウィロービィ
氏の背後の街灯が、そいつの目を、黄緑のペアミラーのように輝かした。
そいつは、とても大きく、とても黒くて、とても濡れていた。やせて
いるように見えた。雨で、毛皮が体から、はがれ落ちたように、腹をす
かせていた。耳は裂け、尻尾は6インチしかなく、先の方で鋭角に曲が
っていた。明らかに、そいつは、そこら辺で生きている、野良ネコだっ
た。
そいつは、おどおどしたネコではなかった。ウィロービィ氏を、恐れ
ることなく見つめた。それから、見るのをやめて、動かなかった。彼の
方で、よける必要があった。
ウィロービィ氏は、代わりに、立ち止まった。彼は、そいつに言った。
「少し待って!」そいつがしようとすることが、正確には分からなかっ
たが。買い物袋に手を入れて、形と大きさから手探りでひとつを取り出
して、もう一方の手で包みを割いて、スライスハムを出した。
彼は腰をかがめて、それを下に置いた。「空腹かい?」と、そいつに
訊いた。「キャットフードはないが、ボイルしたハム。空腹なら━━━」
ネコは、周りに気を付けながら、近づいた。ハムを注意深く、慎重に
くわえると、まるで手品のように一瞬でハムが消えた。
「いいね!」と、ウィロービィ氏。また、パッケージを手探りして、ス
ライスハムを取り出した。なんの警戒もデリカシーもなく、ネコはそれ
らも食べた。明らかに、そいつは、すごく腹をすかせていた。
ウィロービィ氏は、ため息をついた。前かがみになる代わりに、かか
との上にしゃがんだ。パッケージをはがして、のこりを取り出した。少
しだけ残しておいてもしようがない━━━ハムをたくさん挟んだ、厚い
サンドイッチが好きで、そうでなければいらない。もうそれほど残って
なかった。1分もしないうちに、ハムは全部なくなった。
買い物袋には、もう、ネコにあげられるものはなかった。らい麦パン、
ロックフォールチーズ、ジュース、それにレタス。
彼は言った。「それで終わり、キャット!」そして、立ち上がった。
そいつは、彼が予想した通り、ついてきた。アパートのドアで、彼は
言った。「悪いが、ここまでだ。中には入れない!」
すべり込まれないように、慎重にドアをあけたが、まわり込んだのは
ネコの方だった。ウィロービィ氏より、年令的に賢いのか、彼より先に
廊下に入っていた。次の動きを読んで、準備していた。ネコは、そう軽
々しく扱えなかった。
ウィロービィ氏は、ニヤリとして、言った。「分かった。デザートは
出そう、けれど、それで帰ってくれ、お分かり?」
階段をひとっ跳びで越えて、2DKの室へ入った。冷蔵庫を開けて、
買い物袋から非ネコ用食料を中に入れて、中にネコ用のものがあるか見
た。コーヒー用の生クリームが残っていた。そう、彼は、朝、コーヒー
を飲んだり、仕事に行く途中で飲んだりしていた。明日は、後者にする
ことにして、クリームを皿に注いで、床に置いた。それから、また、冷
蔵庫の中を見た。
ベーコンが少しあったが、生のまま食べることはしない。夜のこの時
間に、ネコのためにベーコンを焼く気がしなかった。その上、朝、ハム
サンドの代わりに、ベーコンサンドを作って持って行くつもりだった。
買ってきたロックフォールチーズに加えて、チーズがかなりあったが、
チーズサンドを作って持って行くつもりはなかった。ネコはチーズを食
べる?食べないことはない━━━ネコはネズミを食べて、ネズミはチー
ズを食べる。だから━━━
しかし、棚にサーモンの缶詰があることを思い出した。ネコはクリー
ムを舐め終えていたので、サーモンの缶詰をあけた。
大きな缶だったが、見たときは、底が見えるくらい食べていた。食べ
終えたときは、少しを残して、ほとんど食べ尽くしていた。そいつは、
モリスチェアの前のジュータンに寝そべって、濡れた体を舐めて前足で
乾かすという、望みのない作業に取り掛かった。
ウィロービィ氏は、窓の外を見た。となりの1階の屋根は、窓のすぐ
数フィート下で、彼が外へ出なくても、屋根にネコを降ろせそうだった。
向かい側の1階の建物まで、階段状に続いていて、ネコは容易に屋根を
伝って降りれそうだった。それに、雨は止んでいた。
彼はネコを見てから、ひとりごとを言いながら、バスルームに行って、
使ってはいるが乾いているタオルを持って来た。ネコは、物憂いそうに、
完全に乾いてない、毛皮をできるだけ乾かそうと、前足でこすり合わせ
ていた。
「なにか問題でも?」と、ウィロービィ氏。「びしょ濡れのネコは、ど
うする?」
タオルでふいても、乾かなかったので、彼は、そいつをしばらく居さ
せることにした。冷蔵庫へ行って、自分のためにビールを出した。その
とき、ネコは、さっきクリームを飲んだが、ハムとサーモンを食べて、
のどが渇いているかもしれないと考えた。クリームを出した皿を洗って、
新しく水を入れて、ネコの前に出した。そいつは、尊大な態度で、くん
くんと水を嗅ぐと、それ以上、注意を払わなかった。
「興味がない?」と、ウィロービィ氏。「なにに興味が?これは?」皿
の水を空けて、ビールを少し入れた。ネコは、あっという間に飲んだ。
ウィロービィ氏は、ため息をつき、皿にビールを満たした。立ったま
ま見ていると、ネコは、ほとんどの、全部ではないが、ビールを飲み終
えてから、寝そべって、この時は、目も閉じ、酒びたりで気分よく、ネ
コがよくやる背伸びをした。
ウィロービィ氏は、ネコに顔をしかめると、本棚に行って、本を1冊
取って、ビールをすすりながら座って読み始めた。11時までにビール
はなくなって、まぶたが重くなった。本を戻し、前かがみでネコをなで
ると、毛は乾いて、すべすべしていた。
彼は、「悪いが、ここまでだ!」と言って、ネコを窓まで運んで、屋
根の上に放した。服をぬいで、ベッドに入った。ビールと読書が眠気を
誘い、すぐに、眠りについた。
目覚ましの鳴る、ずっと前に目がさめた。室は、明け方のグレーで、
足元が重かった。見ると、それは、黒くて、大きなネコだった。彼は考
えた。チェッ、寝室の窓を閉めるのを忘れていた!
足を動かして、ネコを起こすと、ネコは黄の目で咎めるように、彼を
見た。
ウィロービィ氏は、ため息をつくと、体を起こした。前かがみになっ
て、ネコの毛をなでると、ネコはゴロゴロ言って、ずっとゴロゴロ言い
続け、ウィロービィ氏がふたたび横になって、また、眠ろうとしている
ときも、ゴロゴロ言っていた。
ウィロービィ氏は、自分に言った。あんたが間違えた!その結果が、
これだ!そいつに触れるべきでなかった。そんなふうに、なでるべきで
なかった。あんたは、ネコといっしょになった。妻を持つことにつぐ、
最悪のことだ。運命に人質を差し出したのだ。なぜなら、やがて、あん
たは、そいつを愛するようになるからだ。
彼は、そいつに、ペットになるようなネコかどうか、訊いてさえいな
かった。仕事に行ってるときに、ベッドにペットがいるなんて、ステキ
な状況だ。しかし、彼は、そいつがどんな種類のネコなのか、考えてな
かった。(そいつは、考えていたようなネコでなかった)そいつは、い
くらか、遊び人ふうの捕食性のオスだった。ウィロービィ氏が望む、自
分にもある雰囲気だ。もっとも、オフィスでそれをまとうことはできな
かったが。
そう、と彼は考えた。前々から、ネコを飼いたいと思っていた。しか
し、シャムネコとか、ペルシャネコのような美しいネコであって、尻尾
が折れ曲がった、路地に住む野良ネコではなかった。もうそれも、今と
なっては、遅過ぎる。彼がネコを飼う。あるいは、ネコが彼を飼う。違
いは?
頭を回して、時計を見た。アラームが鳴る30分前だった。また、眠
ると思ってなかったが、眠った。そして、夢を見た。その夢は、明け方
の夢がそうであるように、鮮やかな部分があった。ステラクロスターマ
ンの夢だった。これが最初ではなかった。このときのものも過去のもの
も、きちんと記憶の棚にしまっておいた。プライバシーの侵害になる部
分があったが。
目覚ましが鳴って、彼が目覚めたとき、ネコはいなかった。
バカげたことだが、ベッドの端に座っていたとき、孤独感が襲って来
た。彼は、ナイトスタンドを手さぐりして、タバコを捜した。
しかし、別の室へ行くと、ネコは、ちゃんといた。静かに冷蔵庫の前
に座って、黒の前足で顔をきれいにしていた。
「じゃあ」ウィロービィ氏は、がさつに言った。「なにがほしい?」
ネコは、答えなかった。
ウィロービィ氏は、ため息をついた。ネコのために、ベーコンを焼き、
自分のために、仕事に持って行く2つのチーズサンドイッチを作った。
これからは、キャットフードを切らさないようにしないと、自分のラン
チは、ミートなしになってしまう。
3
10月下旬のある日の夜半早々に、ジョージスパーリングは、仕事帰
りに、スピークイージーという店にいた。
店のオーナーでもあるバーテンダーを別にすれば、自分のための店だ
った。飲んでもよい、時間外のオフタイムだった。しかし、ジョージは、
普通の日より悪いことが1つあった。飲むべきでない、理由があるはず
だった。特に、禁酒法の価格では。だが、そのことは考えないようにし
ていた。
バーのスツールに腰かけ、ハットは隣のスツールに置いていた。店内
は、それほど暑くなく、トップコートを着たままで、前だけ開けていた。
スツールは古く、ぐらぐらした。バーカウンターを除いて、店内のすべ
てがそうだった。バーカウンターは、美しいマホガニー製で、明らかに、
禁酒法以前には、上流階級向けのサロンで使われていた。ここでは、場
違いで、ふさわしくなかった。バーテンダーは、やって来ると、手をふ
いた。
「ビール、ひとつ」と、ジョージスパーリング。「それと、それを賭け
て、ダイスで勝負!」
バーテンダーは、アイスボックスを見てから、戻って来た。「最初に
言っておいた方がいいが、50セントになる。オーケー?」
ジョージは、うなづいた。「先週、飲まされた、馬のしょんべんみた
いな味のするビールと同じじゃないだろうな?」
「あれは、もう、扱ってない。こっちは、もっと悪い。むしろ、あと2
0セント出して、ジンバックを飲んだ方がいい!これが、言っておきた
かったこと!」
「ジンバック一杯は、60セントじゃなかった?」
「それとは、ものが違う。ジンは入れるが、ジガーは使わない」
「オーケー!」と、ジョージ。「ジンバックにしてくれ!」
バーテンダーは、ノーラベルのボトルから、やさしい一杯を注ぎ、氷
にジンジャエールを加え、半分のライムを絞った。「これは、いいジン
だ。ケンターキーから船で届いたばかり」
「ビールの値段も上がるわけだ━━━それは、川を渡って届いた?」
「そう」
「ニューポートのギャング同士の、撃ち合いのやつに違いない。新聞で
見た。バグリオとか言う名前のボスが撃たれて、強奪された。ビールは
そいつから仕入れた?」
バーテンダーは、顔をしかめた。「ミスター、仕入先を明かすのは、
オレの生命に関わる。言えることは、それは最悪で、もっと悪くなって
いるということ。禁酒法が続く限り、状況は、さらに悪くなって、それ
が、永遠に続くように見える」
「やつらは、それで、ジンの値段も上げている?」
「少しは。だが、ここの値段を、上げなければならないほどじゃない。
ここは、いつも60セント。確かに、ほかでは、50セントのところも
ある。しかしそれは、指ぬきで計ってるから。さて、まだ、60セント
賭けて、ダイスを振る気は?いざ、倍かゼロの勝負!」
「ああ」と、ジョージ。
バーテンダーは、ダイスとシェーカーを出してきて、前に置いた。
「どうぞ、最初は、あんた。こっちは、やさしい気持ちでいる」
ジョージは、ジンバックに引き寄せると、ダイスボックスをピックア
ップして、中に入れた。よく振ってから、投げたのは、エースが1つ、
ジュースが2つ、トレイが1つに、フォーが1つ。彼は、ダイスを見つ
めた。「3つのジュースを1つに。奇数はオレ好み。しかし、オレは頭
が良くない」彼は、エース以外みんなピックアップして、さらに、2回
投げて、3回のシェークで、結局、ファイブが4つとなった。バーテン
ダーは、1回のロールで、すぐに、シックスが4つで、勝ちを奪った。
「カモにされた!」と、ジョージ。「あんたが、やさしい気持ちなのも
分かる」彼は、バーテンダーが1回のロールでフォーを3つ出して残し
ていったのを、見つめていた。ジョージは、また、ダイスをピックアッ
プして、言った。「オレが頭が良ければ、これに打ち勝とうとはしない。
清算して、労働を節約する。しかし、オレは頭が良くないんだ!」ダイ
スを投げて、すべてを失った。
彼は、バーカウンターに1ドル紙幣を置いて、その上に、50セント
硬貨を乗せて、ため息をついた。それで得たのは、2杯のドリンク。つ
ぎが欲しくなる予感がした。つぎは、たぶん、また、1ドル50セント
の出費になるだろう。しかし、彼は、今、シェークをやめることができ
ないので、家に2杯のドリンクを持ち帰るための出費としては、あまり
に大きな金額だった。シェーカーにドロップしたとき、ビール1ビンに
40セント、あるいは、2ビンに80セント使うという考えでいた。
彼は、自分のドリンクをひとすすりした。頭をうしろに傾けて、バー
カウンターのうしろにある壁に吊るされている、1922年のカレンダ
ーを見た。渓谷を蒸気を上げて走る、鉄道の写真が載っていた。それを
見たとき、前に見た気がした。そうだ、少し前に、列車の夢を見たのだ。
列車に乗るのではなく、列車に乗り損ねる夢だった。それから、なにか
が起こる━━━なんだったか、思い出せない━━━恐ろしい夢だった、
悪夢に近かった。
「たとえば」と、彼。「オレは、もう、6回もスッているが、カネヅル
のジョージと呼ばないように!」
バーテンダーは、ニヤリとして、左手をバーカウンターについた。
「オレのことも。ところで、ジョージと言っても、いろんなジョージが
いる。有名なやつも。イングランドの歴代の王にも。それに、ジョージ
カーペンター」
「そうそう。それに、ふたりのジョージ。ジョージバーナードショーに
ジョージサンド」
「聞いたことない。そのふたりのジョージは、なにをした?」
ジョージスパーリングは、頭をかしげた。深いどこかで、冗談でない
部分もあったが、ふざけたギャグだった。「なにも」と、彼。
なにか言いたそうなバーテンダーを見ながら、続けた。「オレは、営
業マンのジョージだと言われている。しかし、なにも売ることができな
い。営業マンになる方法さえ、知らないんだ。からかってるんじゃない。
オレは知らないんだ。本を何冊か読んでみたが、なにも伝わって来なか
った。オレには、営業マンに必要な、なにかが足りないんだ。たぶん、
それは、強い気持ちだと思う」
「しかし、あんたは、それで食ってるんだろ?」
「ああ。オレは客と会って、研磨剤による修理が必要か訊くことはでき
る。そして、研磨剤が必要なら、あるいは、磨いた歯車が必要なら、注
文をもらう。しかし、客がノーと言ったら、なにもいらないと言ったら、
そのあと、なにを言ったらいいのか分からない」
彼は、下のグラスを見た。カラだった。
「お代わりは?」と、バーテンダー。
「電話を借りても?」
バーテンダーは、うなづいて、バーカウンターの別の端を見た。「あ
っち!」
「オーケー。電話してる間に、もう一杯作ってくれ!」
彼は、妻に電話した。「ハニー、オレは今、一杯やってる。少し遅く
なる。電話しておいた方がいいと思ってね。夕食までには帰る」
「いいわ、ジョージ。分厚いステーキを買ったわ。あんたが帰るまでは、
フライパンには入れないつもりだった。なにを飲んでるの?」
「ジンバック。1杯飲んで、2杯目はこれから。それも飲んだら、帰る
よ」
「ジョージ、今夜は、わたしも1杯やりたい。ジンを1ビン買って帰る
カネはある?」
「あるとも」と、ジョージ。そのアイデアは良かったが、あまりハッピ
ーじゃなかった。今日は給料日で、1週間分のカネはあったが、それが
意味することは、来週は、週末まで持たせるために、ランチを何回か抜
くか、借りるしかないということだった。
「カネが足りないのは、分かってるわ、ジョージ。今、カネがあるかど
うか訊いただけで、あとで、返せるわ、先週残った生活費があるの」
「いいね、ハニー!30分もしないで、帰るよ、バイ!」
彼は、スツールに戻った。新しいドリンクが、そこで彼を待っていた。
彼は言った。「ひとつ言えることは、オレには、すばらしいワイフがい
るということ!」
「そりゃ、いい!」と、バーテンダー。「この一杯のために、ダイスを
振りたい?リベンジできるかも!」
「だれも、リベンジしない、絶対!」と、ジョージスパーリング。
「しかし、いいだろう。それを賭けて、ダイスで勝負!」
彼は、また、負けた。
しかし、今の気分は、最高だった。
4
同じ夜遅く、ステラクロスターマンは、2階の家のドアの内側に寄り
かかって、マーティレインズが階段を降りてゆく足音を聞いていた。彼
女の顔のかすかな微笑みは、モナリザを連想させた。
かわいそうなグーフィ、と彼女は考えた。
少なくとも、12回目の彼とのデートだった。彼が彼女に、おやすみ
のキスをしたとき、(4回目か5回目のデートから彼女に、おやすみの
キスをするようになった)あっさりとしていて、情熱がなかった。彼は、
ささやいた。「おやすみ、ステラ。また、月曜日」彼女の背中から肩へ
置いていた手は━━━決して、真剣に、彼女に腕を回すことはしなかっ
た━━━やさしく力をゆるめた。一歩下がって、くるっと回って、階段
を降りて行った。彼女を、ふたたび、ひとり寂しく残して。再度、期待
を裏切って。もう、この時までに、形だけのキス以上のものは、期待で
きないことを知っていたが。
マーティの悪いところは?
彼は、彼女を、遠くから、ほとんど、あがめているように見えた。愛
情の温もりはなく、必要以上の、体の接触もなかった。移動するときも、
彼女の手を取らなかった。実際に、彼女は、最初、おやすみのキスをす
るよう頼み、彼は、そうした。それ以来、彼女と別れる際は、かならず、
そうしたけれど、それ以外で、そうしようとはしなかった。最後のおや
すみのキスも、1分前のことだったが、最初のものとまったく同じであ
った。
初めは、それは、彼がとても信心深いせいだと思った。彼女は、宗教
のことは、ほとんど知らなかった。彼女は、ルター派の日曜学校に通っ
て、一度、教会バザーにも参加したことがあったが、それは、おもに、
両親を喜ばせるためだった。それは物事を説明するものと考えていた。
しかし、マーティとともに、宗教を歪めて考えて、分かったことは、彼
は、神やジーザスを信じてはいるが、熱狂することもなく、そのほかの
ことについてもそうだった。映画館での、できごとのように。ドアマン
が、マーティから2枚のチケットを取り忘れたが、彼は、あまりに正直
過ぎて、同じ映画館にまた行ったときに、同じチケットを使うことがで
きなかった。
彼は、自分の母親に対しても、女性一般についても、奇妙だった。母
親については、どんなに彼女がすばらしいか、よく話した。ステラが見
たところでは、彼の母親には、強い考えがあった。特に、セックスと純
粋については。マーティは、母を崇拝していて、彼の考えが誰から教え
られたかは、分かっていたはずだった。
しかし、彼の考えがどこから来るにせよ、なぜなのか疑問が残った。
なぜ、彼は彼女をデートに誘ったのか?なぜ、彼女とのデートを週1回
づつ続けるのか?彼女に触れるのが恐ろしいなら、あるいは、触りたく
ないなら、デートから、なにが得られるというのか?あるいは、彼が意
味するかのように、彼女にキスさえもしたくないなら。
彼は、親密な接触は、わずかだとしても、すべて、結婚のあとまで取
っておかなければならない、と信じているのだろうか?これは、もちろ
ん、ありうるが、彼は、近い将来に、結婚する気は、まったくなかった。
それは、2回目のデートで、彼女には分かった。彼は、母を養っていて、
それが喜びであり、そうする権利があると考えていた。近い将来に、彼
が母も妻も養えるだけの稼ぎが得られる可能性は、ほとんどなかった。
もちろん、結婚しても彼女が働き続ければ、生活して行けたが、それを
言い出す勇気はなかった。そもそも彼女は彼と結婚したいのかさえ、ま
すます疑わしく思えてきた。たぶん、彼はふつうではなくて、結婚後も
たぶん、そうなのだろう。
室の暗がりに目が慣れてきて、バスルームから廊下へ流れて来る、淡
い光が見えた。バスルームの光は、バスルームのドアが開いているから
だが、クロスターマン家の夜遅くまで起きている者の目印となる、灯台
だった。
それと、母の声。母は、少し眠っていたが、だれかが帰って来ると、
どんなに静かに入って来ても、かならず目を覚ました。
「アンジー?」と、母の鋭い声。
「いいえ、ステラよ」
「なん時?」
「11時少し過ぎ」
「ひとり?」
「ええ、マーティは、すぐ帰ったわ」
「外でなにを?」
「なにも、マム」その言葉は、まだ、説得力に欠けていたので、付け加
えた。「すぐに、ベッドに入るわ」
バスルームに通じる廊下を降りて、ドアを閉めた。バスルームの冷た
く硬い光で、鏡に、自分の顔が映った。よく見るために、立ち止まった。
称賛するでもなく、疑うでもなく、ただの、好奇心から。
それは、ただの、かわいい顔よりは、なにかあった。美しい顔とも、
また、違った。頬骨は少し高く、口は少し広かった。しかし、簡単に笑
える口だった。肌は、きれいで、なめらかで、やわらかだった。あたた
かい茶色かかった肌だった。ヨークタウンによくいるドイツ北東部系と
いうよりは、地中海系だった。
鏡の裏のキャビネットをあけると、顔は鏡の端からすべり落ちた。ほ
とんど残っていない明るい色の口紅を、こすり落ちすために、洗顔用の
ティッシュを1枚出した。歯をみがき、濡れたタオルで顔を拭き、タオ
ル掛けに掛けた。それから、廊下に戻った。
バスルームのドアは、明るくするために、もっと広くあけた。歩くと
き、床を見た。夜には、かならず、廊下にゴキブリがいた。下の雑貨店
から上がってくる、巨大なやつらが。毎日、ゴキブリ用殺虫剤をまいて
いたが、いつも同じように、やつらがいた。彼女は、やつらが嫌いだっ
た。踏みつぶしたい憎しみではなく、理由もなく、見ただけで叫び出し
そうな嫌悪感だった。間違って踏んでしまったら、靴かスリッパの下で
クシャッという音がして、まさに、ホラーだった。もちろん、彼女は家
では裸足ではなく、子どもの頃でさえ、そうだった。子どもの頃から思
い出しても、ずっと、彼女の人生には、ゴキブリがいた。しかし、慣れ
るどころか、ますます、やつらに対する嫌悪感は増していた。
今も、廊下には、1匹、黒の巨大ゴキブリがいた。彼女の前を這いず
り回った。そいつは、彼女がそいつに持つのと同じように、彼女を怖れ
ていた。それは、たぶん、嫌悪感で、死の恐怖もあっただろう。しかし、
そいつは、ありがたいことに、アンジーとの共同室のドアを過ぎて、キ
ッチンの方へ行ってくれた。
「ステラ!来て!」また、母の声。
彼女は、別の階段を上がって、両親の室のドアへ行って、中をのぞい
た。暗闇にうっすらとベッドが見え、ベッドの遠いサイドで寝ている、
父の山のような盛り上がりも見えた。父の規則正しい、重い息遣いも聞
こえた。彼女や母が、いかに大声で呼んだりしゃべったりしても、父が
目を覚ますことはなかった。朝の5時に、1分もかからずに、枕元のア
ラームクロックは消され、彼が目覚め、挨拶する。それまでは、どんな
音でも、ゆすぶられてさえ、いささかも、父の眠りを妨げられない。あ
る夜、雑貨店でボヤがあって、煙が床下から上がって来た。煙のにおい
で、クロスターマン夫人は目を覚まし、消防署へ電話した。しかし、父
を起こすには、顔に水を掛けるしかなかった。
「イエス、マム」と、ステラ。ドア口から。
「入って、ステラ。しばらく、座って!」
ステラは室に入り、ベッドの脇のイスに、緊張しながら座った。目が
暗闇に慣れて、母の、やせた角ばった顔が見えた。母の目線が、鋭く感
じられた。「マーティのことだけど、いくらもらってるの、ステラ?」
「さぁ」と、ステラ。話の内容が分かると、あきあきしたように。「給
与明細を見てないけど、週12ドルだと思う」
「簿記係なら、もっともらうわ」
「小さなオフィスでは、違う。簿記帳の数も少ないし。もっと年をかさ
ねるとか。大きな会社でないと。会計士になれば、給与も上がると思う」
「マーティは、会計士を目指してるの?」
「そう思う。一度、そういう話をしていた」
母の声は、鋭さを増した。「彼と外出するようになって、もう何か月
もたつのに、彼のプランも知らないの?なにも知らなくて、彼の残りの
人生もどうなるか分からないまま、わたしが自分の娘を、そのような誰
かのところへ、行かせたいと思うの?彼女の時間をムダにさせて」
ステラは、答えなかった。長年の経験から、母に反対してもムダだと
知っていた。
沈黙が続き、母が言った。
「あんたも分かる。分からなければ、今度、彼が来たとき、わたしが訊
いてみる」
ステラは、ため息をついた。「わたしが訊く。おやすみ、マム!」
「あんたも分かる」と、母。
ステラは、2つ上の姉との共用室の方へ、廊下を歩いて行った。アン
ジーは21だった。小柄のブロンドで、活発、かわいらしい顔と空っぽ
の心を持っていた。彼女は、ジャズと男、ダンス、そしてダンスの後の
停めた車の中のこと以外、なにも考えてなかった。
同じ両親から生まれたふたりが、ほんのわずかでも似たところがない
のは、不思議と言えば不思議だった。一方で、弟は、今、12だが、父
親の完全なコピーになりつつあった。ロバートは、太っていて、落ち着
いていて、少しマヌケだった。友人には、ダッチと呼ばれていた。ロバ
ートは、屋根裏部屋で寝ていた。ステラとアンジーは、2階のメインフ
ロアの両親の室の隣の唯一のベッドルームを、ふたりで共用していた。、
ベッドルームに入ると、ステラは、すぐに服を脱いで、コットンパジ
ャマに着替えた。
ベッドの中で、グレイの天井を見つめながら、目は、はっきり覚めて
いた。それは、自分の体が分からなかったからだ。たぶん、マーティは、
それに完全に気づかぬように見えたからだった。彼女は、彼に気付かな
いで欲しかったのではなく、正確には、彼に気付かないふりをして欲し
かったのだ。彼女は、愛のあたたかさが欲しかった。愛し合ったり、キ
スしたり、少しのペッティングとか。結婚するまでは、結婚してない限
り、本当のセックスは、たぶん、イヤだった。彼女は、2年前、17だ
った時に、ハーマンロイターとのことで、それについての好奇心を満た
していた。それ以来、彼とのデートは断って、今では彼もあきらめてい
た。彼女は、それを楽しみにしていたが、それが実現するまでは、今は、
待っていられた。そうなって欲しかったのではなかった。アンジーのよ
うに。
自分の体に気づいて、横になりながら、さらなる驚きにも気づいた。
眠くはなく、眠ろうともしなかった。アンジーが帰ってきたら━━━ふ
たりは、だいたい、11時に眠るのだが、アンジーは遅くなることもあ
った━━━起こされるだろうし、彼女は、眠って1時間以内に起こされ
るのが嫌いだった。しかし、アンジーは静かに入って来るどころか、い
つも彼女を起こして、話しかけて、もちろん、ささやき声だったが、デ
ートのことを話したがるのだ。それが、今までのデートと完全に同じだ
ったとしても、気づかぬふりをして、少し、ねたましかった。アンジー
のやつめ!アンジーは姉だったが、アンジーは━━━チープだった。
ステラは、アンジーのことはやめにして、また、マーティのことに戻
った。彼のことを、ほんとうに、愛してる?あるいは、チャンスを与え
られたら、愛せる?しかし、愛がなにか、知ってるのだろうか?そんな
ことを考えるのは、おかしい!それは、自分が生きているかどうかとか、
見ることができるのか、どうかとか、と同じだ。一度、虫歯の痛みを経
験したからと言って、虫歯についてなにが分かる?しかし、彼女は、マ
ーティが好きだった。それについては、疑いがない。
アンジーが、ひとりで、階段を上がって来る足音がした。アンジーは、
いつも車の中でボーイフレンドにおやすみを言った、車がある場合は。
なければ、階段の下の暗がりで。というのは、母がアンジーの階段を上
がる足音を聞きつけて、目を覚まし、階段の足音のあと、長くドアがあ
かなければ、ドアまで来ることを知っていたからだ。(しかし、そのこ
とは別にして、母がアンジーを、良い娘だと信じて、疑わなかったこと
は不思議だった)
アンジーが、帰って来た音がして、ベッドルームのドアで母と話し、
それから、バスルームへ行く音が聞こえた。
ステラは、アンジーが、すぐに、なにか小声で話し掛けてきて、マー
ティとの領域まで入り込んで来て欲しくなかったので、オフィスでいっ
しょに働く別の男たちのことを考えることにした。
それは、ウィロービィ氏だった。ほかの者は論外だった。コンガ氏は、
年寄りで既婚者、ジョージスパーリングも、ヤボでやはり既婚者。ブラ
イアンダナーも好きでなかった。彼には、なにも特別なものを感じなか
った。しかし、ウィロービィ氏は、好きだった。いっしょに働き始めた
ときから、夢中だった。彼女は、長い間、自分のことを女として見て欲
しかった。少女ではなく。そして、デートに誘って欲しかった。しかし
彼女は、マーティがデートに誘う前から、もう、それをあきらめていた。
彼は、彼女にとっては、年寄りでなかった。実際━━━彼女は、19な
ら、もう、りっぱな女?━━━しかし、彼は、たぶん、自分を年寄りと
考えていた。男は、そんふうに、奇妙だ。たったの数年、そう、10や
15の年の差を、重要だと考える。女が好きになれば、そんなことは重
要でなくなる。そして、ウィロービィ氏は、彼女にとって、明らかに、
魅力的だった。彼には、親しみやすさや温かさがあった。それに、ユー
モアのセンスも。(マーティは、彼女が知る限り、ユーモアのセンスは
ゼロだった)そして、彼女が気づいたのは、彼には、感じたり、望んだ
り、愛する心があった。━━━彼が、女について語るさまを、彼女は思
い描くことができた。「あんたは、なんて楽しい、すばらしい芸術なん
だ、いとおしく、喜びに溢れて!」
しかし、語ってくれることはなかった。彼女は、もうほとんど、その
ことを忘れていた。
トイレを流す音がして、アンジーのハイヒールの音が廊下を歩いて来
て、室へ入った。ステラは、明かりがつくのに備えて、すぐに手で目を
おおった。
明かりがついた。「ステラ、起こした?」
「もともと起きていたわ、アンジー」
5
彼らが、どう走っていたか、あるいは、走るのに失敗したか?つぎに、
マーティレインズを見てみよう!
ステラとのデートから、数日たった、ある夜。その日は、急に温かく
なった日だった。いわゆる、インディアンサマー。夜でも、まだ、温か
く、開いた窓の脇に座って、背後のフロアランプの光で、ヒザに本を置
いていた。
読もうとしたが、代わりに、眠くなった。ステラという王女の夢を見
た。しかし、本から目を離さなかった。彼を見よ!弱い頭脳にムチ打っ
て、ページにかじりついている。この夢見る者を、見よ!
「項目178、在庫費用。在庫費用は、購入時の費用と未処理の費用か
らなる。在庫費用は、原材料費を含む。原材料費は、購入時は費用勘定
に算入するが、未処理の部分は━━━」
言葉や文字が、かすんできた。読んでも、意味が分からなかった。夜
遅くなると、よく、そういうことがあった。完全に理解できるように集
中しても、1週間後に別の項目に進むと、記憶から消えてしまった。費
用勘定、非営利組織、剰余、決算後在庫仕訳。1度に1つづつ覚えても、
そのうち、忘れてしまう。つぎを覚えると、前のものは忘れてしまうか、
曖昧になってしまう。
単に、頭が悪い?頭が悪過ぎて、会計処理を覚えられない?一生かけ
ても、会計士にはなれず、今の稼ぎ以上には、なれない?今の簿記係を
卒業して、会計士になるためには、もっと努力が必要で、それが唯一の
方法だった。簿記係をやめて、別の道に進むには、今からでは遅すぎた。
最悪の場合、今の簿記係より、もっと給与の悪い職に就いてしまうかも
しれなかった。彼は、集中力が足りず、多くの計算違いをした。ウィロ
ービィ氏は、笑いながらだが、きつく彼に言った。仕事にもっと集中し
て、簡単な足し算、引き算の間違いを無くし、決算後の繰り越し金額を
正しく出すこと。
先月の初め、彼とウィロービィ氏は、借方と貸方が一致しなかったた
めに、3時間の残業をした。間違いは1つではなく、4つあって、すべ
てマーティの間違いだった。ひとりで残業して、ひとりで直したとして
も、良くなかったが、自分の時間をロスしたばかりか、オフィスマネー
ジャーの時間も長くロスさせたので、もっと悪かった。
ウィロービィ氏は、彼を、奇妙な驚きをもって見ていたが、4つ目の
間違いが見つかって、修正され、会計が一致しても、叱ったりはしなか
った。頭を振って、こう言っただけだった。「マーティボーイ、あんた
に必要なもの、間違いが分かった!」
「それは、なに、ウィロービィ氏?」
「もしもオレがあんたに言ったら、オレを信じられなくなって、混乱し
てしまう、マーティ。たぶん、あんたは大声を出す!」
ウィロービィ氏が言っているのは、間違いなく、ステラにずっと夢中
だったことだ。それは本当のことだったが、実際には、ウィロービィ氏
は、そのことを言わなかった。彼にとっては、それは良かった。大声を
出さずに済んだが、のちに彼を悩ますこととなった。
彼は、ステラを見ることをやめず、愛することをやめなかった。彼の
首を絞めるような悩み事なしに。
しかし、彼は彼女と結婚できずにいた。彼の給与が今の2倍になるま
では、あるいは、ならない限り。それには、数年かかった。今の会計の
勉強のペースでいったら、一生、なれそうになかった。今のままだった
ら、自分の給与を上げたり、あるいは、もっと良い職に就くどころか、
今の職さえ失いかねなかった。
もの事を、今までのように、だらだら引き延ばして、数年後に結婚し
ようとか、あるいは、もうできないとか言い出せないのは、ステラにと
ってもフェアでなかった。彼の母が、元気な限り。
母の死を考えるだけで、彼の心は引き裂かれ、ショックを受けた。
母は、年寄りとは言えず、長く、長く生きるだろう。彼は、それを毎
日祈っていた。母は、一番元気だった。
しかし、彼は、ステラに対しても、フェアだった?確かに、彼は、彼
女に、もの事を正直に話した。彼女は、彼の母を知っていたし、彼の責
任も、チャンスも知っていた。そして、彼は十分注意していたが、ふた
りは、恋人同士のようになりつつあった。彼女のことを、日曜の夜は、
みんなに紹介したし、別の日の夜も、そして━━━
彼は、目を本に戻した。
「この項目を記入する原理も同じであることに、注意すること!項目の
記入は、貸方のさまざまな勘定でも行われ、前と同様、購入収益や給与
にも。これらの記入に加えて━━━」
しかし、彼は、ステラのために、彼女と別れることはできるのだろう
か?同じオフィスに働き続け、毎日、彼女と顔を合わせながら。
そのため、オフィスをクビになって、職を失うのが、一番いい方法か
もしれない。しかし、もちろん、彼がクビになったら、なんのつてもな
く、つぎの職を見つけるのは、とても困難で、長い間、職に就けないか
もしれない。しかし━━━
「マーティボーイ」母が、ドアのところに立っていた。「今夜の勉強は、
もう、やめにしたら?進み具合は?」
「とても、のろい、マザー!すごく複雑なんだ。しかし、まだ、やめら
れない」
「でも、マーティ、もう、10時を過ぎてる。あんたは疲れている。も
っと勉強したいなら、今は眠って、明朝、30分早く起きれば?その方
が、頭が冴えている」
それができないのは、寝起きの1時間は、頭がボケて働かなかったか
らだ。しかし、彼は、母が、すぐやめて寝てほしいことが分かったので、
言った。「分かった、マザー!」立ち上がって、本を本棚にしまった。
「レモネードを作ったわ。寝る準備をして、パジャマに着替えたら、ロ
ーブをはおって、キッチンに来なさい!いっしょに、一杯ずつ飲むのは
どう?」
「ジー!いいね、マザー!」
「マーティ、そういう言葉を使わないように、お願いしたはずよ!『い
いね』のことではない。これはただの、スラッグ。もうひとつの方よ!
牧師が言っていたわ、救世主の名前の短縮形で、一部を取ったものだっ
て!」
「けど、みんな使ってるよ、マザー。みんな、意味なんか知らない!」
彼女は、やさしく笑った。「しかし、あんたは知ってる、マーティボ
ーイ。2度と使わないと、約束してくれる?とにかく、それは、良くな
い言葉よ!」
「分かった、マザー」彼は、使わないつもりだった。そう努力するだろ
う。
彼女は、キッチンへ行き、彼は着替える前に、注意しながらドアを閉
めた。彼と母は、非常に慎み深く、少しでも着衣が乱れていたら、互い
に、見ないようにしていた。寝るときの着衣(マーティならパジャマ、
母ならフランネルのナイトガウン)の上にバスローブを着ていなければ、
互いに見ることはなかった。そして、スリッパが必要で、裸足は、一応、
不謹慎だった。彼の記憶では、それ以下の服装の母を見たことはなかっ
た。彼女もそうで、最初に入浴と服の着替えを教えて以来、彼の裸を見
なかった。普通の子どもたちより、ずっと早く、それらを教えた。
彼は、今、窓を閉めただけでなく、ネクタイを取る前に、すべてのシ
ェードを降ろした。慎み深さは、マーティの第2の特徴だった。彼は、
泳ぎを習ったことがなかった。それは、同性であっても、水泳パンツ姿
を見られることが、とても嫌だったからだ。彼は、ときどき、ちゃんと
した服装以下の姿を、みんなに見られている、悪夢に近い夢を見た。
マーティのことを、理解し始めた?それなら、つぎに、キッチンでレ
モネードを作っている、彼の母を見てみよう!服はちゃんと着ていた。
それは、彼女はマーティより早く、ベッドへ入ることはなかったからだ。
朝は、寝たいだけ寝ていたかった。やがて、彼女は起きて、朝食をとる。
しばしば、言っていたことは、彼女には、そうする必要があった。そう
しなければ、マーティが抗議した。彼には、彼女への思いやりを教えて
いて、そのことから、彼が信じていた。彼女は遅くまで睡眠を取る必要
があると。特に、早朝、家の中が寒い日は。彼は、彼女に風邪を引いて
欲しくなかった。
◇
彼女を見てみよう。40代後半で、ひとりの女性の堂々とした姿をし
ていた。ほとんど、気高くさえあった。力強く、髪には、かすかに、グ
レイが混じっていた。マーティと同じ背丈で、数パウンド重く、よく知
られているように、体力は強かった。しかし、よく知られていないこと
に、彼女は、しばしば、体のふしぶしの痛みや、疲れやすさに不満をも
らしていた。これは、彼女自身への不満だった。女性は、つまり、婦人
は、強いとはされていない。強いことは、弱点でもあり、彼女は、自分
にさえ、偽っていたことだった。実際にウソをつくのではなく、それと
なく知ることによって。心に宿り始めた、ほんの少しの痛みが、虫垂炎
の怖れになったり、少しの筋肉痛が、関節炎や、リューマチを疑われる
怖れになったり、一時的に、心に浮かんだ疲れの感覚が、それは働き過
ぎで、その日疲れすぎたせいだと気づく。睡眠のあとで、横になったま
ま、10分か15分、眠り、不眠症になった。このことをあとで考えて、
つぎの日、ほとんど眠れなかったと、言った。
このことの背景にある、なにが悪かったのだろう?たぶん、それは、
彼女が長い間、23年前まで遡る、自分の人生の全記憶を、心の奥底に
隠してきたことだった。そのとき、アーサーP(フィネスのP)レイン
ズは、彼女と出会い、恋に落ち、ボルチモアの売春宿から彼女を連れ出
し、妻にし、そして、母に、尊敬される、敬虔な女性となった。彼女が、
どんなに尊敬される女性になったかは、彼は、推しはかることはできな
かった。そうでなければ、彼は躊躇していたかもしれない。アーサーレ
インズは、善良な男で、善良なまま過ごし、親密なクリスチャンだった
が、熱狂的からは遠く離れていた。彼は、神を信じていたが、それは、
合理的で、寛容な神で、男の度重なる、肉体的欲望の耽溺を、(そもそ
もそれは、神が最初から彼に与えたものだった)、結婚生活の中であれ、
外であれ、見逃してくれる神だった。結婚生活は、もちろん、良い状態
で、30のとき、彼は、考えられるあらゆる方法で彼を喜ばせてくれる
女性との、どこで出会ったかは別として、結婚生活の聖なる状態に入っ
てゆくことに、ためらいはなかった。
しかし、聖なる状態は、彼が考えていたより、ずっと聖なる状態だっ
た。彼は、もちろん、エルサを教会へ連れて行った。彼女が洗礼を受け
たいと言ったとき、喜んだし、彼女は、長老派になり、教会へ通う女性
となった。しかし、結婚から6か月後に、彼女が、信仰に、特に、性的
な純粋性の教義に、真っ逆さまにどっぷり浸かったときは、あまり喜べ
なかった。性的行為は、結婚して、法的に許されていても、彼女にとっ
ては、嫌悪すべきものだった。彼女はそのときまでに、妊娠していたの
は、幸運だった。そうでなければ、マーティは、決して、生まれて来な
かっただろう。
アーサーレインズは、普通に、男盛りの男だったので、悩んだ。少し
のあいだ、彼は、十字架を身につけていた。しかし、マーティが生まれ
て1年たったとき、彼自身と彼の妻との関係は変化したことを知り、慎
重に、どこか別の場所での満足を求め始め、そして、見つけた。
つまり、ある値段で。病気を移されることはなかったが、1年後の、
ある夜、病気の噂のある売春宿から帰る途中、強盗に襲われて、殴られ
た。強盗は、たぶん意図していた以上に強打したため、アーサーレイン
ズは、つぎの日、死んだ。妻と2才の息子に、普通に暮らして行けるだ
けのカネを残して。
エルサレインズは、事件の起こった場所と状況もあって、彼の死を、
それほどは、悲しまなかった。ボルチモアを去り、シンシナティへ行っ
た。シンシナティを選んだ理由は、姉が住んでいたからだったが、これ
は、本当の理由ではなかった。姉とは、宗教上の意見の相違で、絶交し
ていた。しかし、彼女は、シンシナティに住み、マーティを育て、すべ
ての━━━もちろん、教会での活動以外の━━━愛情を、彼に注いだ。
彼女の全生活は、彼を中心に形作られた。
彼女の財産は、つつましく暮らしていたが、彼が高校を卒業する頃に
は、ほとんど無くなっていたので、彼を、仕事に就かせなければならな
かった。彼女は、彼に牧師の勉強をして欲しかった━━━彼は、善良な
少年ではあったが━━━勉強について、なんらかの素質があるサインも
見られなかったので、彼を大学へ行かせられないと、自分に説得するし
かなかった。高等教育は、神学校を除いて、彼女には、まったく信用で
きないものだった。なぜ、新聞は、アライグマのコートを着ているよう
な大学生たちの奔放な振る舞いを、書き立てたりするのだろう?また、
彼女は、教授のなん人かは、実際のところ、不可知論者だと聞いていた。
りっぱなオフィスで働いて、そのような影響を受けないところにいるの
が、彼にとってずっとベターだった。
少なくとも、彼女は、神に、彼をキリスト教の牧師になりたがるよう、
説得することはできなかったけれど、彼女と神のあいだで、彼を善良な
少年にさせることはできた。彼は、心が純粋で、体もそうだった。そう、
彼女は信じていた。彼からの悪いことは、すべて受け止めていたことは、
言うまでもなかった。彼女は、アーサーレインズとの結婚以前は、模範
的な生活をしていたと、彼に信じさせていた。それは、ウソではなかっ
た。そう言ったわけではなく、ただ、そう信じるように仕向けただけだ
った。1つだけウソだったのは、彼の父が良い夫で、ボルチモアで働い
ているときに、心臓発作で死んだということだった。そのことを、神に
許してほしいと祈った。そして、許してもらった。
そう、彼女は、マーティとともにしたこと、彼のためにしたことに満
足していた。
しかし、彼が結婚したら?もしも、悪い女が、彼を操って、彼の父が
陥ったような悪の場所に導いたら?
◇
彼女は、レモンを2つのグラスに絞り終えて、氷のかけらを入れ、水
と砂糖を足すためにシンクへ行った。彼女は、自分のグラスには、1イ
ンチだけ入れ、上半分はあけていた。
一瞬、耳をすませ━━━大丈夫、彼はまだ来てない━━━素早く、シ
ンクの上の戸棚をあけて、酢と書かれたラベルのボトルから、自分のグ
ラスに1インチ注いだ。ボトルを元に戻すと、2つのグラスをかき混ぜ
て、どっちがどっちなのか忘れないよう、慎重に、テーブルに運んだ。
酢のボトルは、ジンで、ジンのグラスは彼女の席に、ジンのないものは
彼の席に、クッキーの皿も用意して、あいだに置いた。
彼女は、ため息をついて、自分のグラスから、ほんの少しだけすすっ
た。彼をまったく待ってなかったように見せるには、まだ、十分でなか
った。また、ため息をついた。それは、おいしく、よく眠らせてくれた。
彼女には、眠りが必要だった。
それは、本当のところ、罪深い秘密ではなかった。そのジンは、神も
知っていたからだ。マーティには知られたくない、というだけだった。
マーティのために。彼は、酒を飲むには、まだ、若過ぎた。それに、今
は、禁酒法が敷かれていた。彼は、一度もそれを味わうことなく、大人
になるかもしれない。どんな強い酒も、ビールやワインでさえ。飲酒は、
悪いことではなかった。法律違反だとしても。彼女は、健康や睡眠のた
めにそれを必要とした。彼女は、アーサーに出会う、ずっと以前から、
それを味わい、それを愛していた。彼女にとって、あきらめられない1
つでもあった。そう、あきらめられないことが、心配事だったが、ある
日、彼女に洗礼を施した牧師と個人的に話したときに、訊いてみた。、
彼は、いいえ、たまに飲むことは罪でなく、過度に飲んだり、乱用する
ことが悪だ、と言った。
そして、ジンは、少しのジンは、胃にとっても良いことは、よく知ら
れていた。胃にとっても良く、少しづつ飲むことが習慣になっても、毎
晩飲んだとしても、(ほかの時間でも多く飲むことはめったになかった)
確かに、飲むことは眠る助けになった。よく眠ることは、健康にも大切
だった。
マーティは、パジャマの上にバスローブで、入って来た。少し疲れて
いるように見えたが、笑って言った。「ハイ、マザー!このクッキーは、
ほんとにうまそう!ちょっと腹ペコ!」座って、手を伸ばした。
「マーティ!」
「ゴメン、忘れてた!」
彼は頭を下げ、彼女も頭を下げた。食事の前に言う、たとえクッキー
だけだったとしても、感謝の祈りを、数語、言った。
彼は、レモネードを飲みながら、クッキーを4枚食べた。彼女も自分
のグラスから飲んだ。「おいしかった、マザー!サンクス!」と、彼は
言って、彼女を見た。彼女は、目に涙を浮かべていた。「マザー、なに
か悪いことでも?」
彼女は、涙を浮かべながら笑った。「考えていた、マーティボーイ。
あんたは、大きくなって、いつか、離れて行ってしまう。わたしを、ひ
とり残して。あんたは、わたしのすべてなの。わたしのリトルボーイも、
大人になってしまう」
「マザー!」彼の声は、ショックを受けていた。「そんなことは、決し
て」
彼女は、少し、すすり泣きになった。突然、彼女を慰める唯一の方法
に気づいた。彼は、ヒザを彼女のイスに近づけて、腕を彼女に回して、
固く、強く抱きしめた。「マザー、なによりも、だれよりも、愛してる。
決して、去ったりはしない!」
彼女は、ほとんど発作的に、彼をつかんで引き寄せた。「マーティ、
あの少女は、どうなの?週1回会ってる、もう数か月にもなる、ステラ?
彼女について、ほとんど、話さない!良い少女?」
「前に、たくさん話した、マザー!もちろん、彼女は良い。もしそうで
なければ、デートなんか」
「洗礼は、マーティ?彼女は、クリスチャン?」
「もちろん!前にもそう話したけど、忘れてしまったんだ。彼女の宗派
は、つまり、彼女はルター派の教会に行って、オレたちのとは違う、し
かし、クリスチャン」
彼女は、ため息をついた。「マーチンルターは、気が変だったと、牧
師が言っていたのを聞いた。しかし、それは、ずっと昔のことだった。
たぶん、今でも、ルター派は━━━彼女とは、真剣なの、マーティボー
イ?」
「もちろん、違うよ、マザー!彼女は、遊び!いっしょに映画を見るの
が好きで、いろいろ話したり、ほとんどは、オフィスでのできごと、そ
れだけ!」
彼女は、小声で、感謝の祈りを捧げた。彼は、前に一度、しばらく家
をあけたことがあった。彼の年頃によくある、若い仲間との付き合いで。
しかし、神に感謝!それだけのことだった!少なくとも、今は!彼が結
婚まで考えてなかったことを、神に感謝!彼が、わたしのすべて!
そして、彼女は、マーティが本当のことを話したことを知っていた。
すべて本当で、ウソはつかないと。
数分後、マーティはベッドへ行き、彼女は、レモネードを、もう1杯
作った。今度は、少し強めに。
6
残りは、3人、しかし、3人と会った夜の話をする前に、ある午後の
話をしよう!まだ、秋で、時間は、午後だった。
オレは、前任者のマックスに会った。
ウィロービィ氏は、かなり悪いカゼを引いて、家にいた。3日間、会
社を休んでいた。その3日で分かったことは、オフィスは、それまで経
験したことのない、混乱状態に陥って、彼がオフィスでいかに多くのこ
とをしてきたか、それらが、いかに重要だったかを、みんなに知らしめ
る結果となった。オフィスのルーチンは、修羅場と化した。メアリーは、
口述筆記に入っていた。ステラは、ファイルしていた。マーティは、そ
う、マーティの簿記帳は、オレに任せて、混乱状態にあった。彼は、エ
ラーがどこで発生したか、追跡中だった。バランスシートの、たった数
百ドルのエラーが、どこで発生したか追ってるうちに、不一致がますま
す広がって、良くなるより、もっと悪くなった。オレ自身は、ひとりと
言うより、なん人かの雑用を処理中だった。コンガ氏は、前足を痛めた
灰色クマのように、苛立って、最初にだれかに用を言いつけて、つぎに
別の人に、そのうち大混乱になった。正確には、マッドハウスではない
が、平穏な場所とは言い難かった。オレは、ウィロービィ氏が仕事に戻
ってくれたら、どんなにすばらしいか、思い知らされた。
それは、ランチのすぐ後の、午後のことだった。コンガ氏は、「フレ
ッド!」と呼んだ。オレは、していることを中断して、彼のオフィスへ
行って、言った。「はい、ミスターコンガ?」
「ウィロービィ氏がどこに住んでるか、知ってる?」
オレは、頭を振った。
「メアリーに住所を聞いて、そこへ行って来てくれ!これを持って」デ
スクから、書類の束を持ち上げた。「そして、彼が、これらを片付ける
まで待って、また、持ち帰ってくれ!交通費は、メアリーからもらって、
あとで、領収書を出して!」
それが、彼が、どれだけオフィスのルーチンを知ってるかを、示して
いた。メアリーは、現金ボックスの現金には、さわれなかった。それは、
マーティだった。オレが言われたような、ちょっとした出張の現金を出
したり、領収書を発行するのは、マーティだった。
しかし、オレは言った。「イエス、サー」そして、「彼は、オレを待
っている?」
「そうだ!」彼は、吠えた。それから、声のトーンはふつうに戻って、
人間になった。たぶん、病気のところへ人を向かわせる行為を、オレに
対してでないとしても、自分に言い訳する必要があったからだ。「電話
で、今、彼と話した。彼の提案だ。彼は大丈夫だが、ドクターの命令で、
今週いっぱいは、会社を休むそうだ。しかし、2時間くらい、家で仕事
する分には、悪くならないだろうと言っていた。そこで、あんたが待っ
ているあいだにできる、雑用があるか、訊いてみて!」
オレは、うなづいて、室を出ようとすると、彼が言った。「書類は、
バラバラにならないように、なにかに入れて━━━待って!」彼は、デ
スクの一番下の引き出しをあけて、平らなブリーフケースを出して、中
がカラなのを確かめた。「これに入れて!下に置かないで、路面電車で
は、ヒザの上に乗せて!」
オレは、そうすると約束した。
オレは、マーティから交通費、メアリーから住所をもらって、外へ出
られるのがうれしくて、喜んで、出発した。住所から、片道30分で、
もしも、ウィロービィ氏が2時間で書類の仕事を終えれば、退社時間の
1時間前までに戻れる。修羅場を出て、平和な午後になるだろう。
コレライン路面電車は、オレを、近くの通りまで連れて行ってくれて、
目的地は、すぐ見つかった。そこは、ブラウンストーンフロントと呼ば
れる古いビルだった。しかし、ブラウンストーンは、使われてなかった。
ウィロービィ氏の名前は、フロントホールの8つのメールボックスの1
つにあった。2階に、その室番号の室を見つけ、ノックした。
ウィロービィ氏は、中へ入れてくれた。彼は、服を着こんで、ウール
のスカーフを首に巻いていた。目は、少し充血していたが、明るく、楽
しそうだった。風邪は、見たところ、ほとんどは彼の頭の方に行ってい
た。それは、鼻をよくすすったり、しばしば鼻をかんだりしているが、
声は、ふつうだったからだ。
「ハイ、フレッド!」と、彼。「入って、座って!オールドボーイが、
なにを?」彼は、ブリーフケースを受け取った。彼は、家では、いくら
か違っていた。彼は、オフィスでは、決して、コンガ氏を『オールドボ
ーイ』とは呼ばなかった。
コンガ氏がなにを?という質問は、ただのレトリックだった。という
のは、すぐに、ブリーフケースをあけて書類を調べていたからだ。オレ
は、周りを見た。本がぎっしり詰まった、大きな本棚があって、タイト
ルを見るために、自然と引き付けられて行った。それは、本棚のある奇
妙な室に入って、オレが最初にしたことだった。
背後で、ウィロービィ氏が、少しうなった。「これで、すべて?電話
では、1・2時間と言っていたが、しかし、あんたを5時まで帰せるま
でに終われば、ラッキーだな。わざわざやっかいごとを招いた」
オレは言った。「終わるまで待つようにと、言われた」オレは、ウィ
ロービィ氏が、オレはオフィスに一旦戻って、誰かの仕事をして、また、
書類を取りに来るよう提案されるのが、イヤだったので、すぐに、付け
加えた。「待ってるあいだ、なにか雑用があればするようにと、言われ
た」
彼は、オレの心を読んでいたに違いない。それは、その時までにオレ
が気づいていたことだったが、彼には親切なところがあった。静かに笑
ってから、言った。「心配すんな!待っていていい。雑用はない。食料
品店も雑貨屋も、電話1本で、必要なものを届けてくれる。今すぐ必要
なものは、なにもない。あんたには、退屈しないよう、読める本が、た
くさんある?」
それは、疑いがなかった。本棚は、ゴミで一杯だったわけでなかった。
その当時好きだった作家、H・G・ウェルズの本がたくさんあった。オ
レがまだ読んでないタイトルの本も、何冊かあった。ジャックロンドン
やオーヘンリーの完全セットも。それ以外の本も、おもしろそうだった。
そう、ここに数日いても、オレは退屈しなかっただろう。何時間でも、
ひとりでいられた。
「いい?」と言って、オレは、本棚のガラス扉に手を伸ばした。
「いや」と、彼。「まだだ。座って、少し話しをしよう。それから、飲
み物を作ってくれ!こいつと奮闘する前に、1杯やりたい。あんたも飲
みたいだろ?」
「ええ」と、オレ。彼が、上司だということを思い出した。「少しのあ
いだ、1杯だけ」
彼は、キッチンへ行って、ボトルとグラス2つを持って、戻って来た。
彼は、ボトルを持ち上げた。「本物のウィスキー、処方薬!風邪にはウ
ィスキーが一番いいと信じている、古いタイプの良いドクターがいて、
オレが今のように鼻をぐずつかせている限り、好きなだけ、処方箋を書
いてもらえる!」
オレは言った。「両親も、そうだった。オレも、熱い、ウィスキー入
りのトッディで育てられた。つまり、風邪を引いているとき、たぶん、
10才くらいから、ウィスキーに熱いお湯にシュガー」
グラスは、4オンス入りで、彼は、グラスに、ボトルから1・5オン
スすつ入れて、ボトルはキッチンに戻した。「失礼して、ボトルは片づ
けた。勤務中に、あんたを酔わせるつもりはない。こいつに取り掛かる
前に、自分を酔わせるつもりもない!」
彼は、オレとテーブルのあいだのイスに座って、グラスの1つを持ち
上げた。オレも、もう1つを持ち上げた。「ゴクッと飲み込まないで」
と、彼。「すするだけ!それが、オレがチェイサーを使わない理由!禁
酒法という現代の、ビッグミステイク!」
「いつか廃止される!」と、オレ。
「たぶん、いつかは。しかし、それほど先ではない。オフィスは、どう
なった?」
「かなりの、混乱状態!」と、オレ。みんなが、3つのことを同時にや
ろうとしている!」
彼は、それを待っていたかのように、うなづいた。彼は、話題を変え
た。「フレッド、書く方はどう?」
オレは、考える時間を作るために、少しすすった。オレは、今でも書
きたいと思い、書くことを目指していた。しかし、話せるようなものは、
なにもできずにいた。2つのストーリーを書き始めたが、プロットの問
題にぶつかって、それらを捨てた。オレは、高校で校内誌に発表したも
の以降は、なにも書き上げてなかった。発表させられたものも、憎んで
いた。
しかし、ウィロービィ氏は、オレが答える前に、自分で答えた。「あ
まりできてないんだろ?それを、あまり心配するな!書くことを目指し
ている限り、いつかは達成できる!こう言うのを許してくれるなら、も
う少し大きくなってからでも、遅くはない!まだ、18だろ?」
「先月で19.書くことについては、あんたが正しい!しかし、とにか
く、今はたくさん読みたい!たぶん、すごくたくさん!」
彼は、頭を振った。「あんたは、それを必要としている。しかし、あ
まり多く読み過ぎない、もっと重要ななにかから、あんたの目をそらさ
せてしまわない程度にする。たとえば、オレが思うに、人々を観察し、
人々を理解することなんかを」
オレは言った。「オレも、そうだと思う」オレは、ほんとうは彼の言
うことを、まったく、真に受けてなかったが、そのことについて議論し
たくなかった。
「フレッド、ここにある本の1冊に鼻を向ける代わりに、あんたが会い
たそうな誰か、興味が湧きそうな誰かと、今から会って、話しをすると
いうのは、どう?」
「う〜ん」と、オレ。「分からない。オレはむしろ」
「同時に、善きサマリア人であれ?結論を出す前に、説明させてくれ!
マックスレイスマンは、あんたの前任者の雑務係の少年、あんたと同じ
年令、数か月若いだけだと思う。彼は、ここの近く、数ブロックのとこ
ろに住んでる。彼が病気でやめたことは知ってると思う。彼は、まだ、
病気で、胃にトラブルを抱えている。2回手術したが、直ってない。彼
は、陽気で明るいが、まだ、ベッドにいる。おしゃべりのできる人は少
ない。特に、同じ年令の者たちとは。寂しがっているに違いない。彼は、
あんたを好きになると思う。そして、あんたも彼のことが好きになる。
彼のところへ行って、話しをしてみないか?少しだけでも!」
「しかし、どう説明する?」
「なにも説明は、いらない!母親に、オレから電話する。彼女は、すば
らしい女性で、あんたも好きになる。あんたが、そこへ向かっているあ
いだに、電話で説明する。この仕事が終わりそうになったら、また、電
話するから、あんたは帰ってくればいい。もちろん、退屈だったら、す
ぐ帰ってきてもいい」
「分かった」と、オレ。行きたくなかったが、言い出せなかった。彼の
最後のひと言が、ホッとさせてくれた。つまり、30分くらいで、帰っ
てきてもよかった。
彼は、ドリンクを飲み終えると、すぐに、電話を掛けに行った。それ
は、室の外の廊下にあったので、会話をよく聞き取れなかった。オレも、
ウィスキーを飲み干した。プレーンの味は、好きではなかったが、胃に
ホットスポットができた。それから、本のタイトルをもっと見た。電話
が失敗に終わることを、望みながら。
しかし、彼は、笑顔で戻って来て、オレの望みを打ち砕いた。
「オーケー、フレッド、その線で行こう!同じ通りの1214番地、1
ブロック西。3階の10号室。彼らが、あんたを待ってる!」
オレはトップコートを着た。「彼ら?」と、オレ。
「マックスと母親だけ。父もいるが、営業マンで、今週は、街を離れて
いる。マックスが疲れたら、あんたに言うから、それまでは、いたいだ
け、あるいは、オレが電話するまで、滞在していい!」
「オーケー、ミスターウィロービィ!」
オレは、階段を降りて、また、外へ出て、1ブロック歩き、階段を2
つ上った。オレの階段の足音が聞こえたらしく、ドアが開いて、太目の、
太ってるというほどでない、笑顔の女性が、廊下に出て来た。ユダヤ人
だと思った。「ミスターブラウン?」と、彼女。
「イエス、マム!」と、オレ。「ただの、フレッドと、呼んで!」年上
に、ミスターで呼ばれるのは、きまりが悪かった。
彼女の笑顔は、チャーミングだった。「入って、フレッド!」オレの
コートとハットを受け取ると、ラックに掛けた。「マックスは、だれか
と話せるので、喜ぶわ!」
そこは、中流家庭の家で、感じのいい家具の室だったが、統一感がな
かった。レイスマン夫人は、しゃべり続けた。「マックスには、親しい
友人がいない。おかしな子で、友人は多くなく、ごく、わずか。その友
人も、たまに会うくらいで、ほとんど会うことはない。5か月に一度く
らい」
オレは、5か月に一度しか会わない友人なんているのだろうか?と、
疑問に思ったが、言った。「そう、レイスマン夫人。どのくらいいて、
いい?」
「なぜ?好きなだけ、マックスが疲れていなければ。それは、わたしが
見てる。しばらくしたら、また来る。そんなふうにして」
オレは、彼女のあとから、明るいベッドルームに入って、ベッドの少
年に、楽しそうに、初めまして、と言った。彼の枕は、高い位置に吊る
され、ベッドも水平でなかった。水平のベッドにいる者と、しゃべるの
は難しい。彼は、オレと同じくらいの背丈と体重だった。1インチくら
い高いかもしれない。髪は黒髪で、カールしていて、オレより、ずっと
ハンサムだった。若いギリシャ神の、顔立ちだった。
彼は、オレに歯を見せて笑い、握手した。「ハイ、フレッド!フレッ
ドと呼んでも?」
「いいとも、マックス」と、オレ。
「どこでも、座って!チェスは、する?」
「少しなら」と、オレ。「少ししかできない。8か10才くらいに覚え
たが、勉強してないから、うまくなるには、長い道のり」
「いいね。オレたちは、だいたい、同じレベル。1ゲームか2ゲーム、
あとでやろう。すぐではなく、最初は、しばらく、話そう。オフィスは、
どう?」
「いいよ、ただし、今週を除いて!今週は、ウィロービィ氏が風邪で休
んでいて、マッドハウスと化した。しばらく、外にいられて、助かった」
彼は、ニヤリとした。「分かる。ウィロービィ氏は、めったに、ミス
はしなかった。オレがいたときでも、ミスは、2回だけ。彼がミスをす
ると、確かに、すべてだめになった。みんなは、どう?」
「元気だよ」と、オレ。誰かのことを、詳しく言おうとしたが、誰も思
い出せなかった。みんな、ふつうの人々だった。一番よく知ってるのは、
数分前まで話していた、ウィロービィ氏だった。その話の内容も、考え
てみると、自分のことでなく、オレのことばかりだった。オレは、みん
なのことを、なにひとつ知らなかった。
「仕事は、どう?」と、彼。
オレは、肩をすくめた。「ほかの雑務係より、悪くはないけど、すぐ
に、もっといい仕事を捜し始めると思う。高校は、商業科だったので、
簿記もできるし、タイプも、営業職も、みんなできる。しかし、まだ若
く見られて、営業をやらせてもらえない。すごくふさわしいとは思わな
いが、タイプも、事務もできる。雑務係より、少しはまし。給与もいい」
「幸運を祈ってる!一生、雑務係じゃない」
「だとしても、コンガ&ウェイ社では、チャンスはない」と、オレ。
「マーティがやめるか、クビにならない限り、チャンスは全くない。そ
うなれば、やらしてくれるかも。あるいは、ステラ。オレでも、ファイ
ルくらいできる。ステラの方が、すこしはましだろうけど、すごくでき
るわけでない」
マックスは、頭を振った。「ステラがやめたら、別の女の子を雇うさ。
コンガ氏は、女性と男性の仕事を、はっきり分けている。速記タイピス
トやファイル係に、男性は雇わないし、雑務係やオフィスマネージャー
に、女性は雇わない」
オレは言った。「その通り!とにかく、あんたが雑務係に戻りたけれ
ば、あいてるから、いつでも戻れる。戻って来れる、見込みは?」
「たぶん、数か月。しかし、雑務係があいていても、戻らないと思う。
同じ理由で、あんたは、たぶん、やめる」
「ほかのプランでも?」
「そう、メディアを勉強して、メディアの職に就きたい。今後、大きく
発展するよ、フレッド。父の仕事も、それ関連が、多くなって、病気が
よくなれば、メディアの学校に行かせてくれるそうだ。実際、もう勉強
を始めている」ベッドの脇のテーブルに置かれた本を、指差した。「メ
ディアに興味は?」
「それほどは」と、オレ。「数年前、放送が始まったときに、水晶ラジ
オを作った。しかし、そんなに興味なく、真空管ラジオに進む気もない」
「なにに興味が?」
オレは、書くことを目指している話しをした。そのとき、レイスマン
夫人が、グラスを乗せたトレイを持って、入って来た。「マックスのミ
ルクを飲む時間、あんたもどう、ミスターブラウン、つまり、フレッド?
オレンジジュースの方がよければ、持って来れる」
オレは、ミルクがいいと言って、マックスは、彼女にチェス盤を頼ん
だ。
オレたちは、チェスをやって、同じくらいだと分かった。オレの戦術
は、少しはよかったと思うが、早指し過ぎて、ときどき、ミスをした。
一方、マックスは、ゆっくりだが、注意深かった。のろすぎて、あきて
しまうほどではなかった。2ゲームやって、1勝1敗だった。少しのあ
いだ話しをして、それから2ゲームやって、同じ結果だった。プレイオ
フのために駒を並べ終えたときに、居間の電話が鳴った。腕時計を見た
ら、4時過ぎだったので驚いた。その午後は、実際、早く過ぎた。オレ
は、言った。「たぶん、ウィロービィ氏だ。仕事が終わったようだ」
その通りだった。
彼らは、オレが行くのが悲しいと言い、また来て欲しがった。「チェ
スの決着をつけよう、フレッド!」と、マックス。オレは、彼らに、ま
た来ると約束した。それも、すぐに。そのつもりだった。
ウィロービィ氏は、すでにオレのために、ブリーフケースを用意して
いて、コートを脱がなかった。それに、オレが前に座っていたイスには、
しっぽの曲がった大きい黒ネコがいた。ウィロービィ氏は、それに気づ
いて、「キャット」と、言った。そして、オレの顔を見て笑った。「つ
まり、名前がキャット。マックスは、どうだった?」
「楽しかった」と、オレ。「チェスをなん回かやった」
「病気がどのくらい続くと、言っていた?」
「数か月だと言った」そして、ウィロービィ氏は、レイスマン一家と知
り合いだから、知ってるはずだと気づいた。それで、オレは訊いた。
「なぜ?」
「彼がどう話したか、知りたかっただけ。それは、本当のこと、ある意
味で。つまり、どのくらい生きられるか、フレッド」
「なんて?」と、オレ。「彼は、死ぬ?」
「そう、病気は、癌。彼は、それを知っている。彼は、オレが、あんた
に話して、午後の訪問をだいなしにして欲しくなかった気がした。たぶ
ん、その代わりに、将来の夢をしゃべったんじゃないか?」
オレは、うなづいた。
オレは、雑誌を手にしていたが、オフィスに戻る路面電車の中で、読
む気がしなかった。オレは、集中できなかった。マックスレイスマンの
ことを考えるのを、やめられなかった。
死の概念は、オレにとって新しいものじゃない。両親は、この6年で、
ふたりとも死んだ。しかし、今度のことは、違っていた。オレは、深い
悲しみを感じたが、ホラーではなかった。人々は、大きくなって、中年
になって、そして、みんな死んでゆく。それは、知っていた。しかし、
マックスは、数か月、オレより若いだけなのに、今のオレより、年を取
るまで、生きられない。
彼は、そのことを知っている。たぶん、彼は頭が良くて、みんなが隠
そうとしたことを、見抜いてしまった気がする。そのことが、オレにと
っても恐ろしく思える。彼は、オレとしゃべりながら、あと少ししか生
きられないことを知っていることが、信じられなかった。それに、体の
どこか痛みを、少なくとも、癌で死が近い痛みを抱えていたに違いない。
それに、彼は、笑って、陽気で、彼に迫る死の影で、訪問がだいなしに
ならないように、オレにウソをついていた。
くそっ、ミスターウィロービィ!と、オレは考えた。オレに話さない
で、そこへ行かせたことに対して。しかも、あとで、そのことを話した。
くそっ、やつめ!そうすることが、目的だった!本と同様、人間も見る
ように言ったあとで!いいだろう、オレは、なにかを学んだ。しかし、
とにかく、くそっ、ミスターウィロービィ!
オレは、レイスマン一家との約束を守って、すぐ戻るべきだった。
しかし、そうしなかった。それは、分かっていたからだ。オレには、
自然にふるまうなんてことは、まったくできないし、チェスに集中する
ことさえできない。オレには、マックスレイスマンや彼の母と同じくら
いの、勇気さえ持てなかった。ただ、それだけだった。
7
4時20分前。メアリーホートンは、忙しそうに、タイプしていた。
しかし、幸せそうだった。それは、10分か15分でタイプは済み、2
0分後には仕事を終え、あとは自由だからだ。コンガ氏は、すでに帰っ
ていて、つまり、これ以上の手紙はない。ジョージスパーリングが出て
来て、彼女の前を通りながら、言った。「グッナイ、ダッチェス」彼女
は、タイプライターから目を上げずに、言った。「グッナイ、ジョージ」
スパーリングは、彼女を、ダッチェスと呼び、ブライアンダナーは、
キッティと呼ぶ。2つのニックネームは、矛盾していると、あんたは考
えるかもしれない。しかし、ほんとうは、矛盾してない。どちらも、あ
る意味、ふさわしい。それは、あんたが、どの位置から、彼女を見てい
るかに依るのだ。
「ハイ、キッティ」と、ダナー。「今夜、忙しい?」いつものように、
帰りぎわに、彼女のデスクの前に立ち止まって、訊いた。
「ええ、ミスターダナー、今夜は、忙しい」と、メアリー。
そして、「じゃ、楽しんで来て!」と、彼が言うのを待った。しかし、
この時は、変化球で来た。「メアリーは、いつまでも子ども?つまり、
いつも忙しいなんて、ありえない!たまには、羽目を外したら?楽しい
場所を知ってる、いっしょに、どうだい?紳士的にふるまうことを誓う、
それが、心配だったんだろ?オレは、悪い野郎じゃない」
彼女は見上げた。真顔だった。「ソリー、ブライアン!残念ながら、
分かるでしょ?」
彼は、助け舟を出した。「誰か、ほかに?婚約してる?」
「そう、だれか」
「婚約を?」
彼女は、そのことに不正直になって、イエスと答えたかった。しかし、
彼女には、不正直なところはなかった。「いいえ、婚約はまだ。しかし、
彼を愛している」
ウソはなかった。
ダナーは、うなづいた。「オーケー、キッティ。しかし、トライし続
けるオレを咎めないで!ある日、心変わりするかも。ある時、彼とケン
カするかも」
そして、彼女の返事を待たずに、出て行った。つまり、彼は、また、
ルーチンに戻ることを意味していた。毎晩、そう訊かれるのは、悪くな
かった。それが、あくまで、冗談ベースである限り。ブライアンダナー
と、ほんとうに、いっしょに出掛けたいわけではなかった。たとえ、エ
ディがいなくなったとしても。ダナーは、とても、うぬぼれが強く、生
意気だった。
それは、エディも、もちろん、そうだった。しかし、エディは、少し
違って、それは表面だけで、深いところでは、自分を見失って、彼女を
必要としていた。
ステラとフレッドは、帰るところだった。彼女は、ふたりにグッナイ
を言った。ウィロービィ氏は、まだ、デスクにいた。マーティも、自分
のデスクに。かわいそうな、キッド。たぶん、また、簿記帳にトラブル
を抱えてる。時計を見上げた。5時2分だった。最後の手紙の時間を、
見誤っていたことに気づいた。あと、ダナーとの会話も、少し時間をロ
スした。残りのパラグラフは1つだけで、数分で終わりそうだった。エ
ディは、数分待っても、気にしないだろう。
彼に、数分、待ってもらう、と彼女は考えた。彼のために。彼は、し
ばしば遅れてきて、いつも、彼女が待っていた。彼女だけが、遅れるこ
とを気にしていた。すぐ行くわ、エディ、と彼女は考えた。急いで、タ
イプミスをした。修正に、30秒かかった。手紙を終え、封筒にタイプ
して、ウィロービィ氏のデスクに持って行った。
「最後のもの」と、彼女。「読むまで、待つ?」
彼は、頭を振った。「帰っていい、メアリー。なにかあれば、自分で
直せる。少し残って、マーティのサポートをしてあげなくては」
彼女は言った。「サンクス、ミスターウィロービィ、グッナイ!」
コートラックまで歩いてゆくと、脇の鏡を見た。鼻は、光ってなかっ
た。しかし、少し、パウダー掛かっていた。それから、昼休みに買った
ハットを、注意深く、かぶった。もう、彼女は自由で、時間を好きに使
えた。エディには、彼女のために、5分か10分待ってもらう、気分転
換に。ハットは、バカげていて、かわいらしかった。彼に向けた、愛。
しかし、エディは、気づきもしないだろう。彼に会ったら、彼が気にも
しないことに、気づきもせず、あとで、自分の室でそれを取るまで、ハ
ットのことなんて覚えてもいない。そして、エディはそれに気づきもし
なかったと、彼女は考えるだろう。
ドアに向かって、「グッナイ!」と言った。ウィロービィ氏、マーテ
ィ、残ってる者へ。彼女のヒールは、木製の廊下で、音を立て、すり減
った木製の階段を下った。
通りは、午後遅くの陽射しで、まだ、明るかった。東に西に、陽射し
は走った。黄の太陽は、通りの一方の端のビルの真上にあって、3ブロ
ック先から、通りのもう一方の端へと、傾きかけた陽光が、きれいに掃
き清めていた。きれいな黄金色が、玉石の舗道をピカピカに新しくさせ、
まるで朝のようだった。そう、それは彼女にとって、まさしく、朝だっ
た。仕事が済んで、1日が始まる。
彼女は、いつもの場所へ向かって、急いだ。それは、角を曲がったと
ころだった。もちろん、彼は、オフィスのあるビルの、すぐ外で待つこ
ともできた。しかし、彼女は、そこで待っていて欲しくはなかった。そ
れは、彼女の仕事であって、ほかの誰のものでもない。彼女といっしょ
に出て来た、オフィスの誰かを、エディに紹介したくはなかった。2つ
のもの、彼女のオフィスの生活と彼女のほんとうの生活は、まったく別
のものだった。オフィスを出た瞬間、そこで働いていた者たちのことは、
すべて忘れた。そんなふうに、突然、それは、少なくとも突然、目覚め
た瞬間、夢が終わるのと似ている。夢の一部を、1・2分、ぼんやり覚
えているが、やがて、それは無の淵へと、消えてゆく。
そう、あんたは、夢から現れた人間を、ほんとうの人間に紹介するこ
とはできない。
メアリーホートンが、2つを区別する鋭さは、たぶん、異常だった。
彼女の生活の2つの側面を、わずかな程度だとしても、ミックスさせる
ことは、間違いだった。道徳的な間違いではなく、2プラス2が5であ
るような意味での間違い、頭に靴をはいたり、足にペアハットをかぶっ
たり、逆さに本を読んだり、砂糖とクリームをビールに入れたりするよ
うな、間違い。
角まで来て、彼女の心とハートと体は、ブロックの舗道に、彼がいな
いのに気付いて、無になった。いつも彼が待っている、隣のビルの壁に
寄りかかる姿もなかった。
彼は来る、と彼女のハートが言った。少し、遅れただけ。まだ、5時
10分にもなってない。遅くとも、15分までに来る。彼女は、ゆっく
り歩き出した。彼が来るまで、そのブロックを行ったり来たりしなくて
はならなかった。女は、立ち止まれなかった。男がするように、ビルの
壁に寄りかかれなかった。エディが最初にそうして、ずっとそうしてた
ように。
◇
彼女は、ゆっくり歩いて、隣のビルを過ぎた。エディの声が聞こえた。
「メアリー!」
振り返ると、彼がいた。角に停めた車の運転席に座って、彼女に歯を
見せて笑った。彼女は考えた。彼は、そんなことすべきじゃない。その
うち、トラブルに巻き込まれる。誰かが停めた車に乗ってるなんて!
しかし、彼は車から降りてきて、ドアを閉めなかった。彼女のために、
開いたままにしていた。
彼女は、彼に向って1歩踏み出した。ためらいながら。「エディ、誰
の車?借りたの?」
彼は、笑った。「ビクビクしなくていい、ハニー!オレの車、そのう
ちに、買ったところさ」
エディが車を買った?仕事もないのに?今日、仕事が見つかったとし
ても、そんなにすぐ、車が買えるはずがない。彼は、数週間、働いてな
かった。最後の仕事も、長く続いたとは言い難かった。彼女は、車を見
た。ブランドものの新車ではなかった。しかし、古いオンボロ車でもな
かった。おそらく、数百ドルはしただろう。
彼女が車を見ているさまを見て、また、笑った。「そんなに疑わない
で、メアリー!正直、盗んではいない!」
「エディ、とても、こんな」
彼女は、彼の視線をとらえた。彼は、まだ、彼女に向って笑っていて、
彼女も笑い返した。緊張の糸が、少し笑いながらも、彼が説明してくれ
るまで、ピンと張り詰めたまま続いた。彼女は、車に乗り込んだ。彼は、
ドアを閉め、ぐるりとまわって、運転席についた。ボタンを押すと、せ
き込むような音が一瞬して、エンジン音が鳴り響いた。そして、1度、
バックファイアの音。彼は言った。「セルフスターターで、あとは全部
やってくれる。マックスウェル1919モデル、しかしまだ2万キロし
か走ってない、新車同然、どう、気に入った?」
「気に入るもなにも、まだ、エディは」
「今、今はどうだい?そのときが来れば、みんな説明する。食べながら
でも。お祝いに、乾杯は?」
「飲んだりしない方がいいと思う、エディ、運転中は」
「ちゃんと、注意してる、スウィートハニー!ご心配なく!飲みたくな
るまで、飲まない。聞いて!イタリアンスパゲッティは?」
「ステキ!」
「決まり!いいスパゲッティ屋を知っている。そこで、食べたり飲んだ
りできる。ニューポートで川を渡ってすぐ」
「あまり、遠いところは」
「マックスウェルなら、すぐさ!気づく間もなく、着いてる!」
「でも」
彼は、車のギアを入れ、カーブを曲がった。彼女は、話し掛けるのを
やめた。運転から彼の気をそらすことが、事故のもとになるかもしれな
かったからだ。もちろん、彼女は、前にも車に乗ったことはあったが、
そう、しばしばではなかった。1度、少し怖い目にあった。そして、車
は、橋を渡る、交通量の多い場所へと入って行った。
彼女は、だんだん、彼の運転がうまいことに気づいた。楽々と、車を
運転していた。そして、彼が、前に数か月、仕事がまったくなかった頃、
タクシーキャブを運転していたと話したことを思い出した。そのあと、
料金のことで客とケンカになって、そのことで裁判所で罰金を言いわた
されて、その仕事も失った。ほんとうは、エディの過失ではなかった。
男が、いっしょの少女をいじめて、あまりに意地悪かったので、エディ
はキャブを停めた。少女は、エディに守ってほしいと言ったので、彼は
そうしたが、あとで、警察が来ると、そのあとの裁判所でも、態度を変
えて、男に、ぜんぜん、いじめられてなかった、と証言したので、すべ
てエディの過失になって、彼が自分からケンカをしかけたことになった。
そのようなことは、よく、エディには起こった。
彼女は、少し向きを変えて、運転している彼を見た。彼は、なんてい
い、クリーンカットな横顔をしているんだろう。
(このとき、彼女は、「クリーンカット」って、どういう意味なんだ
ろうと思った。それは、本を読んでるときに出て来たが、正確な意味は
知らなかった。しかし、エディの横顔に合っているように思えた。その
ような言葉やフレーズは、たくさんある。あんたが、意味を分かってた
り、分からず使ってたりするような。気をもんで、なんかも、今がまさ
にそうで、エディになにがあって、車を手に入れたのか知るまでは、す
べて大丈夫だとしても、なにに気をもんでる?)
彼は、運転に集中していた。特に、橋にさしかかってからは。そして、
彼女を見たり、しゃべったりしなかった。それで、彼の顔を、ゆっくり
観察できた。それに、ふさわしい言葉を捜した。彼女がベストと思うの
は、「意図的」だった。エディに、ふさわしい言葉は、意図的だった。
彼の顔は、意図的な顔だった。今、運転に意図的、いつもなにかに意図
的。それは、ハンサムな顔ではなかったが、注意を引く顔だった。なぜ
なら、なにかを意味する顔だから。背後に、だれかが取り憑いている顔。
それは、予言者の顔のようでもあり、あるいは盗賊、あるいは殉教者、
王の座にいるシーザーを無視して見つめる、あるいは、シーザーの背後
を見つめる、アリーナの砂にまみれた犠牲者の顔。その顔は、(神を冒
涜する考えをいだいて、彼女の手は、自然に十字架を切るように動いた)
神の顔、あるいは、悪魔の顔。
そのとき、車は停まろうとしていた。信じられないことに、すでに、
ニューポートにいた。
エディは、カーブ近くに、うまく車を停めて、エンジンを切り、顔を
向けて、彼女に歯を見せて笑った。それは、少年の笑顔で、神も悪魔も、
どちらも消え去った。彼女も、笑い返した。
「ここが、ビッグトニーの店」と、彼。「スパゲッティやラビオリ、ど
ちらも、うまい!」車から降りると、回って、彼女の側のドアを開けに
行った。
「どちらも、おいしそう」と、彼女。「あなたのおすすめなら、どちら
でも」
彼女は、ドアへ向かおうとしたが、彼は、彼女の腕をとって、ビルの
あいだへ入って行った。「そっちは、食事だけ。エントランスは、こっ
ち。回って行けば、バックルームへ行ける」
ビルのあいだに、サイドエントランスがあった。エディはノックした。
ドアが開いて、日焼けしたイタリア人が顔を出し、まぶしい白い歯を見
せた。「入って!ミスターエディ、どうぞ!」
そこは、表のメインルームのような、ダイニングルームになっていた。
しかし、小さ目だった。赤と白のチェックの、テーブルクロスが掛かっ
たテーブルだった。スパゲッティソースの匂いが強くした。うまそうな
匂いだった。
「トニー、オレの彼女のメアリー!」
トニーは、頭を下げた。「どうぞ、ミス・メアリー」テーブルへ案内
した。「ワイン、それとも、ジンバック?」
エディはメアリーを見たので、彼女は言った。「ワインがよさそう」
彼女は、ほんとうは、どちらの味も好きではなかった。ワインの方が、
エディの支払いが少なくて済みそうに思えた。彼女は、ほんとうは、今
まで飲みたいと思ったことはなかった。1度だけ、エディを喜ばせるた
めに、1口か2口飲んだことがあった。幸運にも、彼はあまり多くは酒
を飲まなかった。
彼は言った。「トニー、オレもワイン」トニーは言った。「いいね、
イタリア料理には合う。食事のオーダーは、今、ミスターエディ?」
エディは頭を振った。「まだ!先に、ワインを味わいたい」トニーは、
それもいいというように、うなづいて、出て行った。
メアリーは、エディがニュースや車について話すのを、心待ちにして
いたが、(どうやって車を手に入れられた?)一方で、エディは、質問
されるのが好きでないことも知っていた。彼は、急かされるのがキライ
だった。準備ができれば、彼女に話すだろう。彼女は、しばらくの間し
ゃべる話題を捜した。
「なぜ、みんなは、ビッグトニーと呼ぶ?」と、彼女。「ただのトニー
ではダメ?それほど大きくないし」
エディは、ニヤリとした。「モンマース通りには、こんな感じのトニ
ーの店が、もう一軒ある。彼は、とても小柄。それぞれの店の名前は、
もちろん、実名。ここは、カプルッチ家だし、向こうは、ブルーグロッ
ト家。いつしか、みんなは、ビッグトニーの店、リトルトニーの店と呼
んだ。リトルトニーの店には、行ったことないが、そう聞いている」
「ビッグトニーとは、ずいぶんよい知り合い?」
エディは、頭を振った。「あんたと会うようになったから、ここへは、
2年間来てなかった。ニューポートで、しばらく働いていた頃は、よく
来た。ずいぶん前のことだ。しかし、今日の午後、あんたと会う直前に、
トニーがまだ店をやってるか確認するために電話すると、オレのことを
覚えていてくれて、それで、ここへ来ることにしたんだ。つまり、バッ
クルームに」
トニーは、ワインを持って来て、話しが聞こえたのか、言った。「そ
う、ミスターエディのことは、よく覚えてる、また、来てくれて、うれ
しい、ミスメアリー!なにかお祝いごと?もしかして、婚約では?」
エディは言った。「そうではないが、お祝いをするところ。これから、
よく来る」
「いいね、それなら、オレもお祝いに、今夜のワインのお代は、なし!」
出て行く彼に、エディの「サンクス、トニー」が追いかけた。
エディは、メアリーを見て、笑い、グラスを持ち上げた。「オレたち
に、メアリー!そして、オレたちの、大きな変化に!」
メアリーもグラスを持ち上げ、グラスとグラスが触れ合ったとき、彼
女の手が少し震えた。彼がついに、カソリック信者になって、ふたりは
結婚することが、ありうるだろうか?いや、ありえない。あまりにあり
えないから、望むこともできない。彼女は、それを祈ったが、ほんとう
は望んでもいなかった。エディは、そんなに大きく変われない。
◇
彼は言った。「ニュースなんかではないんだ、メアリー。お祝いする
ためのカネをどう得たかだが、本を売ったんだ」
「本を売った?」
「そう、どんなものでも扱ってくれる、新世界書店で、20ドルになっ
た」くちびるを少しゆがめた。「心配しないで、あんたがくれた、トー
マスアクィナスは、売ってない。彼の世界を、信じてるわけではないが」
エディが本を売ったことは、彼女には驚きだったが、すごい驚きとい
うほどでもなかった。彼の本棚には、マルクス主義、社会主義、弁証法
的唯物論、その他いろいろな本が揃っていて、なんどか説明してくれた
が、彼女には全く理解できないものばかりだった。しかし、彼女には、
何か月過ぎるうちに、だんだんと彼がそうしたものに、ロシアで革命が
起きたときに、彼が夢中になったものに、幻滅を感じ始めたことが分か
った。
しかし、彼女はうれしかった。彼が本を売ったということは、ついに、
踏ん切りがついたということを意味していた。まだ、神を信じていない
としても、実際、そうなのだが、トーマスアクィナスの言葉を信じてな
い、と言ったばかりだとしても、彼には、今、真実を見て信じるところ
まで来る、チャンスが開けたということだった。彼が神を信じるところ
まで来ているとしたら、それは、最初の大きなステップとなるだろう。
少なくとも、今、彼は、間違った宗教からは自由だった。社会主義に
は、いつも彼女を驚かすなにかがあった。時々、エディは彼女に説明し
ようとした。彼女は、だいだいは、理解した。それが意味するところは、
誰も、物を所有せず、人々は、みんな平等に物を共有する。その部分は、
キリスト教とだいたい似ていた。しかし、ロシア人は、キリスト教信者
ではなかった。教会を攻撃し、宗教は、大衆のアヘンと呼んだ。その上、
アメリカでは、血の革命で、コンガ氏のような人々を殺さないかぎり、
社会主義は生まれて来ないだろう。エディは、それを認めていて、それ
が起こって欲しいとさえ言った。彼は、暴力を怖れなかった。しかし、
彼女には怖かった。コンガ氏が殺されるべきだとは思わなかった。
彼女は言った。「しかし、エディ、あの車。20ドルでは買えない」
「もちろんさ、ハニー。20ドルは、今夜のふたりのためだけ。それと、
最初の支払いまでの生活費。
ここで、ビッグニュース!オレは、ついに仕事を得た。かなり給与が
いい。仕事のために車が必要。車を持つことは、オレたちの楽しみにし
てはいけないことはない。雇い主の男性から、車を預かっている。支払
いはまだだが、彼はオレの毎週の稼ぎから、少しづつ支払いに回してく
れる」
「エディ、それはすばらしい。いい仕事に違いない、つまり、彼がそん
なふうに車を売ってくれるなら」
「支払いは、今までの仕事よりずっといい!この仕事を失ったり、辞め
たりしたくない。今、お祝いすべきでは?」彼は、自分のグラスを見た。
すでに空だった。「飲み干して!あんたも、それに賛成なら!」彼は、
大声で呼んだ「トニー、ワインを追加!」
義務であるかのように、彼女は自分のワインの残りを飲んだ。トニー
は、ボトルを持って来て、ふたりのグラスに注いだ。
「料理の注文もするけど、トニー、持ってくるのは、ゆっくりでいい!
どっちがいい、メアリー?ラビオリ、それとも、スパゲッティ?」
「あるいは、ラザニア」と、トニー。「今夜は、ラザニアもある」
メアリーは、ラザニアを知らなかったが、エディが特別なものだと言
ったので、それにすると言った。彼は、ふたりに同じものを注文した。
今回は、トニーはワインのボトルを置いて行った。
今、質問しても大丈夫だった。「仕事はなんなの、エディ?」
「軽い配達。それで、車がいるんだ。ひとつ都合の悪いことがあって、
メアリー、ふたりにとって、それは、ほとんどが夜なんだ。しかし、毎
晩働くわけじゃない。それに、日曜はある」
「夜?いったいぜんたい、夜に、あなたはなにを配達する?」
彼は、ニヤリとした。「ディープで、ダークなシークレット。しかし、
あんたのライトな頭で、心配しないで!知らなければ、知らないほどい
い」
「エディ!あなたは、酒の密売人のために働くって言うの?」
彼は、トニーに聞こえるんじゃないかと、あたりを見回した。「シー
ッ!そんな大声を出すな!取引先のだれかに、聞かれたらどうする?静
かに!なにも、心配することはないことを説明するから!それは、大き
な取引じゃない。ハイジャックされそうな酒樽を積んだトラックの列で
もないし、警官に見張られてそうなものでもない。聞いて!メアリー、
それは100パーセント安全なんだ。オレが配達するのは、小さなやつ。
客が緊急で必要になったときとかオペレータが言うには、小売りで買え
なかったとか、予想外に品薄になったとか。オレは、いつでも電話が取
れるよう待っていて、急いで必要になった電話が入ったら、1ケースや、
あるいは、半ケースを届ける。その夜や、つぎの定期配達まで持たせら
れるように。在庫はトラックにあって、オレは、集金などのカネを扱う
ことは一切しなくていい。相手は、得意客のみ。ジェイクが、つぎの定
期配達で、その分を追加で集金してくれる」
「しかし、エディ、もしも警察に」
「逮捕されるって?」彼は肩をすくめた。「千に1つもありえない!事
情を知ってるのはひとりだけ、ジェイクが━━━」
彼は、顔をしかめた。「名前を出すべきじゃなかった。しかし、彼の
ラストネームは言わない。彼は、ちゃんと、秘密を守るための策を講じ
ている、メアリー。川の両岸で。それに、聞いて!それは、違法かもし
れない。しかし、なにも悪いことじゃない。あんたが今、イタリア人が
持って来た赤を飲んでいる、それ以上に違法なことではない」
メアリーは少し赤くなって、自分のグラスを見下ろした。彼は、うま
く彼女をワナに掛けたのだ。しかし、違法な酒を飲むのと売るのとでは、
違いがあった。どちらも違法だが、一方は、危険だった。
エディは言った。「禁酒法のジョークを知ってるだろう、メアリー?
やつらは、それを千年続けられない。そして、いつの日か、やつらは賢
くなって、それを廃止する。しかし、それまでは、酒にはカネが掛かる。
なぜ、そのカネを楽に稼いではいけない?長いこと、オレは、まともな
仕事を捜して、とんでもない苦労をしてきたんだ」
それに対する答えは、多くはなかった。彼は、ずっと努力してきた。
禁酒法がうまく機能してないというのは、彼が正しかった。あんたも新
聞で読んで、よく知ってるだろう。飲酒それ自体は、道徳的に悪くはな
い、飲み過ぎない限り、しかし━━━
それが悪かろうが、危険だろうが、あるいは、その両方であろうと、
彼女に分かっていたのは、彼と議論するのは、彼女にとって良くないと
いうことだった。彼は仕事を得て、決心もしたので、彼の心を変えさせ
ることはできないだろう。彼女は、大きくて重要なところで、彼の心を
変えることはできなかったが、彼は、映画を見に行って、見る映画を変
えるような、小さなことでは、彼女のやりたいようにさせてくれた。
突然、彼女は、怖ろしい考えが浮かんだ。「エディ、あなた、拳銃を
持ち歩いてる?」
彼は笑った。「ハニー、オレはなにも、ギャングになるわけじゃない。
ただの走り使い!しかし、走り使いの少年がいい稼ぎができるビジネス
が、ここだけにある。あんたのワインを忘れないで!そのために働く。
もう一杯づつ飲もう!トニーに、ラザニアを運んで来させる」
彼は、彼女に笑い掛け、彼女はひと口飲んだ。「それに、ハニー、少
しは気が安まるなら言うけど、これは、オレが見つけた仕事ではなく、
向こうがオレを見つけた」
「どんなふうに?」
彼は、話す雰囲気になった。彼女に話すのが、楽しかった。ある日の
午後早く、彼は、かつて出荷係をやっていたときの元上司の男に会いに
行った。彼は、その仕事をクビにされたのではなく、不景気のために解
雇された。それで、彼は、出荷係が、また募集されてないかと、男に会
いに行ったのだ。募集はなかった、しかし、元上司の男は、やさしくし
てくれて、そこらをゆっくり話しながら歩こうと誘ってくれた。そして、
一杯飲みに入った。そこには、別の話し仲間がいて、そのひとりが、ジ
ェイクだった。
ジェイクは、かつては、ある集会のメンバーで、彼とエディは、親し
く、いっしょに多くの集会の仕事をした。1年前、ジェイクは集会を辞
めた。彼は、今、酒の密売人で、かなり手広くやっていて、稼ぎも多か
った。話しの中心は、酒の密売人で、みんなは、彼がもうすぐ家を買う
だろうと言った。彼は、すぐに、エディと元上司のために酒を注文した。
それから、エディを脇に呼んだ。
「まだ、集会に、キッド?」彼は、知りたがった。エディがノーと答え
ると、つぎに知りたがった。エディは仕事がある?、つぎは見つかった?
ノー。そして、「前はタクシーを?」と、彼は訊いて、イエスを得ると、
提案をした。彼は、運転ができて、コビントンの地理に詳しくて、信頼
できるやつを捜していた。エディは、どの条件も満たしていた。緊急デ
リバリーサービスは、新しい職種だが、そのビジネスは成長を続けてい
て、需要も多かった、お客の要求に応えられてる限り。警察の形式的な
手入れが入る可能性があるので、(それは、深刻なトラブルというわけ
でなく、エージェントは、少しのあいだ、取り調べに応じなければなら
ない、といったものだった)もぐり酒場の店主たちは、多くの在庫を抱
えたくなかった。それで、結果的に、急に忙しい夜とか、大きなパーテ
ィが入ったりすると、少量を、緊急にデリバリーしてくれるサービスが
ないと、ビジネスチャンスを失って、お客も逃してしまう。
エディは、イエスと答え、ふたりは、すぐに、中古車販売店へ行って、
マックスウェルに目を付けた。ジェイクが、エディの名前でそれを購入
し、キャッシュで払った。車の代金に達するまで、彼は、エディの毎週
の給与から5ドル受け取る。それでも、エディの手元には、毎週30ド
ル残る。ジェイクへの支払いは、35ドルだった、プラス経費、それは、
ガソリン代と車の維持費以外はあまりなかった。そんなふうに、彼は給
与から貯金もできた。車は、1年半後に支払いが済むまでは、所有して
いるとは言えなかった。
「すばらしいだろ、どう?」と、エディ。
「すばらしい!」と、彼女。その通りだった、カネに関しては。週35
ドルは、彼女の給与より、週10ドル多かった。しかし、彼女の胃の片
隅に、小さな、冷たい恐怖の塊があった。エディが危険は無いと言った
としても、それはあるに違いなかった。
「そう、というわけで」と、エディ。ボトルを取って、ふたりのグラス
に注いだ。
ふたりは、グラスを持ち上げ、触れ合わせた。
「成功に!」と、エディ。「そして、ふたたび、オレたちに!」
グラスを置くと、トニーがラザニアを運んで来た。
8
ブライアンダナーを見てみよう。それは、彼を見るには、いい時間と
場所で、彼のすべてを見れる。時間は、夕方の5時半で、場所は、YM
CA寄宿舎の彼のロッカーフロアにあるシャワールームだった。彼は、
冷たいシャワーが好きだった。(いつもは、浴びるのは朝だったが、今
朝は、少し寝過ごして、浴びる時間がなかった)そして、彼は、あんた
が見ている、自分の体が好きで、自慢だった。それは、特別大きくも筋
肉質でもないが、背は5フィート10インチでウェルター級、きれいで
コンパクト、健全な体。メーンス サーナ イン コルポレ サーノー。
これは、ラテン語のフレーズで、(あるいはギリシア語?)なん年か前
に見掛けて、とても気に入ったので暗記し、それ以来ずっと、自分のモ
ットーにして来た。健全な肉体には健全な精神を、という意味。
自分は、輝かしくもないし、そう認めるのは自由だろうが、彼の心は、
体と同じように健全だった。直線的に物を考えるのは、心で、どこへ行
きたいか分かるし、そこへ行くためのベストで確かな方法を示してくれ
た。
トラブルから守るのも、心だった。心は、慎み深くもなかった。それ
は、軽い悪や重い悪さえ許した。彼がそれらを注意深くコントロールで
きて、ベストを得るのに必要な場合には。
彼を成功に導く、最終ゴールを知っているのは、心だった。たまたま、
そうなれればラッキーだが、彼は、かならずしも、金持ちになりたいと
は思わなかった。しかし、成功したビジネスマンにはなりたかった。雇
われる方ではなく、雇う方に、尊敬された名誉ある男、みんなが、彼を
見たら、尊敬を込めて、「あそこを行くのは、ブライアンダナーだ!」
と言われる男になりたかった。
もしも、あんたが、この時代、尊敬されたければ、適度に、悪いこと
もしなければならない。例えば、あんたは、禁酒主義者にも清教徒的な
人物にもなれない。あんたは、取引相手の話題に合わせなければならな
い。もしも一杯差し出されたら、一杯やれる準備をしてなくてはならな
い、一杯お返しする準備も。禁酒法の高貴な実験について、悪い冗談で
あるかのようにしゃべれなくてはならない。よく話題にのぼるニュース
について、よく知ってるかのように話せなくてはならない。もしも大物
の密売業者を知っていたら、あるいは、そのうちのふたりのファースト
ネームを知っていたら、帽子には羽毛の飾りがいる。
もしも、男の中の男になりたければ、喫煙もできなければならない。
少なくとも、うまい食事のあとの葉巻の1服、特に、顧客との食事では、
別のセールスマンがいたり、あるいは、ビジネス上の知り合いがいれば、
なおさら。ブライアンダナーは、タバコを吸っていたが、それは、第1
次大戦の休戦後の1年間まで。彼には、悪い体験はなかった。ずっと供
給サービス業に関わっていて、塹壕も銃撃も見たことはなかった。しか
し、この3年間は、ロストイヤーだった。彼のキャリアに関する限り。
だが、完全に失われていたわけではなかった。兵士たちとは違って、
給与のほとんどを貯蓄し、賭け金に戻した。ずっとその増額を続けて、
今では十分な額、ゲームの最初の6千ドルまで戻した。この期間で見れ
ば、なん人かのセールスマンが達成した額に匹敵する。
すべて貯蓄したわけでは、もちろん、なかった。この期間にできる最
大限の貯蓄以上を稼ぐことはしなかった。軍隊から戻った最初の年(こ
れは、コンガ&ウェイ社に入った最初の年でもあった)に見つけたのは、
株式市場で、株を買うことで利ザヤが稼げることだった。それは、牛肉
市場で、1銘柄あるいは同じタイプの銘柄に、極端な投資をするのでな
い限り、住宅市場と同じくらい安全だった。購入する株式は、多様に分
散させて、一極集中を避けた。たまに、少額の損失が出たが、それ以外
は、安定的にかなりなゲインがあった。
続く数年は、彼の資金は、そのまま増え続け、全体を見渡して、どの
業種を買うか、もっとも稼げそうなものを調べ始めた。1万ドルは、そ
の目的のために投入するに、いい額だった。
それに伴って、彼は、妻を捜し始めた。妻も子どもも欲しかった。か
わいくて、よく気がつく妻、メアリーのような娘が欲しかった。可能な
ら、メアリーが欲しかった。彼女に恋人がいたとしても、実際に結婚す
るか、結婚の約束をしているのでない限り、いつもチャンスはあった。
ケンカして、彼女が彼と、あるいは彼が彼女と別れるかもしれない。そ
れで、彼はいつも彼女にデートの誘いをしていた。そうでなければ、別
れたかどうか知りようがなかった。彼は、それを、軽く続けていた。そ
れで、彼女も怒ることなく、暗黙の了解が成立していた。しかし、それ
が冗談ではないこと、ほんとうに彼女が欲しいことは、すでに知らせて
あった。
もしも、メアリーが、ある日、イエスと言って、彼とのことを考え始
めたら、例外として、彼の原則に反して、自分のビジネスを成功させる
前に、彼女と結婚しただろう。彼女は頭がよく、ビジネスのこともよく
知ってるから、障害よりも、むしろ、大きな助けになるだろう。彼女は、
たぶん、自分の貯金もあるので(カネ目当てではないが)、それを彼の
貯金に加えて、彼との生活やふたりの独立に役立ててくれと言うだろう。
そう、神に賭けて、彼はメアリーと結婚する!それを合理化し、彼の健
全な心と折り合いをつけたとしても、健全な心が宣言できるものにも、
限界があった。恋愛は、ふさわしくなく、どこかでひび割れが生じた。
なぜ、彼は、ニューポートへ10数回デートするよりも、メアリーと映
画館へ行こうとするのだろう?
◇
彼は、シャワーを出て、タオルで元気よく体をふき始めた。冷たいシ
ャワーのあとのタオルが気持ちよく、そこは彼専用のシャワールームだ
ったので、お気に入りの歌、「グリーンの装い」を歌った。
オー パディ そのニュースを聞いた?
広まって
シロツメクサは アイルランドでは 法により 禁ずる
地面に
ブライアンダナーは、アイルランド名もあって、アイルランド人であ
ることをうれしく思っていた。しかし、実際には、それは1/4だけだ
った。ダナー家は、カソリックで、ブライアンも、もちろん、そうだっ
たが、彼は、積極的というよりは、受動的なカソリックだった。彼は、
ただ、それについてまともに考えたことがなく、その仕事もしたことは
なかった。しかし、カラーとして、彼の考えには染みついていた。例え
ば、カソリックは、プロテスタントの娘との結婚を拒むが、彼は、どう
しても彼女が必要なら、結婚してもいいと思っていた。しかし、メアリ
ーホートンがカソリックだと伝え聞いたときは、うれしかった。
彼は、タオルでふき終えて、歌いながら、タオルを腰にまいて、自分
の室へ廊下を歩いて行った。そうすることは、YMCA寄宿舎では、早
朝と夜は許されていた。女性は、寄宿舎フロアへの立ち入りは許されて
なかったからだ。掃除婦を除いて。掃除婦も9時前と、4時以降は働い
てなかった。
自分の室で服を着た。ただ下へ降りて、地下1階のカフェテリアで食
べるのではなく、夜の街へ出て食べるかのように、細かい神経で、注意
深く。ふつうは、彼は、夕食を地下で取っていた。ふつうは、室へ上が
る前に、しかし、今夜は、あまりお腹がすいてなかった。朝のシャワー
を逃したこともあって、食欲を増すように、食べる前にシャワーを浴び
た。それを終えたので、今は、かなり腹が減った。
夕食のあとは、たいていは、室に戻って、眠る時間までは、本を読ん
だ。新聞や軽い雑誌以外は、あまり読まなかった。しかし、今は、とて
もおもしろい本の途中だった。夜を楽しく過ごせるような。誰かに薦め
られて、図書館で借りた本を出した。(ジェフウィロービィ?そうだ、
ジェフが読むように薦めてくれた)本は、バビットと呼ばれていて、ビ
ジネスマンのことが書かれていた。とてもよく書かれていた。ただ、著
者が時代の一部をどう変えてゆきたいのかは、よく分からなかった。彼
には、ジョージバビットは、物事を間違って捉えて、負けを喫している
ように見えた。バビットは、間違いを犯したが、良きセールスマンであ
り、良き扇動者であり、成功した男だった。ダナーは、著者は、本に出
て来る若者と同じくらい成功し、幸せだったが、著者自身ではなかった
方に賭けただろう。
エレベータで下へ降り、カフェテリアへ行って食事をした。食べ終わ
ったとき、急いで室に戻って本を読む必要はないことに気づいた。むし
ろ、誰かと、しばらく話しがしたかった。
階段を上がって、メインフロアのロビーへ行った。寄宿舎のメンバー
は、ひとりのとき、しばしば、そこへ座って、話し相手を捜した。ダナ
ーは、今までに、ほとんどの者と知り合いになっていて、だれがおもし
ろくて、だれがつまらないか知っていた。
エマーソンがいた。ジョンエマーソンは、ラルフウォルドの子孫か親
戚だと言っていた。ラルフウォルドエマーソンについては、ほとんど知
らなかったので、どっちだか覚えてない。ジョンエマーソンは、ダナー
が中学生の頃、15年間、ウォルナットヒルズハイスクールで歴史公民
の教師をしていた。
寄宿舎の住人のなん人かは、エマーソンは退屈だと言っていたが、ダ
ナーは、ビジネスや経済や株式市場に興味があったので、彼を輝かしい
男だと思っていた。彼は経済学は教えたことはなかったが、大学でのそ
のテーマに詳しく、自分はまだエクスパートだと自慢していた。エマー
ソンがもっとも興味ある趣味は、切手収集だったが、ダナーは、ほとん
どの時間を、景気循環や株式、コールマネー、ビジネスに関連した政治
についての質問をして、切手収集の話題から遠ざけた。結果として、彼
がもっとも興味があるテーマに関して、大学のフリーコースと同じ内容
を、苦労なしに得ることができた。
また、彼は、株式市場についての価値ある助言や知識を得た。エマー
ソン自身は、株をやることはなく、貯金は切手収集につぎ込んで、いつ
か、それが飛んでもない額になると考えていた。しかし、生活がかかっ
ているかのように、株式市場を詳しく調べていた。それで、アドバイス
も適切で、ほとんどいつも、有益だった。ダナーは、この2年間の株の
利益のうち、エマーソンの助言により、ひとりでやるよりも得られた利
益は、合計で、少なくとも500ドル、もしかしたら千ドルを越えたに
違いないと考えている。そのため、切手収集の話を聞いたり、エマーソ
ンが新しく買った切手を称賛したりすることは、支払う価値があった。
今、エマーソンは、彼が来るのを見つけて、手を振り、ラウンジの隣
りにスペースのある場所に少し移動した。そして、彼が読んでいる「タ
イムズスター」を置いた。
ダナーは座った。「なにか新しい切手を買った、ジョン?」もしも、
新しい切手を見なければならないなら、最初に見ておいた方がいい。
しかし、エマーソンは、首を振った。「前に見せた、コロンビア州の
景観以来、まだだ。あれは良かった、真の美しさ。あんたの方はどう、
ブライアン?」
「そう、そう」ダナーは、エマーソンが置いた新聞をチラッと見た。株
式市場レポートのところが開いていた。「今日、新聞は読んだ?AT&
Tの動きは?」
「同じ値。0・5上がったが、また戻して同じ」
「それを、どう見る?」
エマーソンは、それについて考えた。「長期設備投資は好調。しかし、
言うほどの変動はなく、しばらくは、上がったり下がったりが続く。先
月の上昇のあと、鈍化している。週で3ポイント上がった?」
「3・5」と、ダナー。ちゃんと知っていた。彼は、その20株を持っ
ていて、3・5ポイント上昇で、75ドルの利益を持たらした。その週
の給料より多かった。しかし持ち続ける意味がないので、決心した、ブ
ローカーのカルバー氏に電話して、それらを売るよう頼もう。
「営業マンの仕事は?」
「なんとか水面から、顔を出している。あんたの仕事は?」
「やんちゃ坊主たちに、てんてこ舞い、いつも通り」エマーソンは、た
め息をついた。「なんて人生だ!あんたは5千ドル持ったことは?」
ダナーは、はっと驚いた。6千ドル以上あったが、エマーソンには知
られないようにしていた。いつも、エマーソンの前では、株をやってる
が、2ドルくらいの少ない掛け金で、ゲームのように遊んでるだけ、と
いう振りをしていた。そして、確かに、エマーソンとは、なにかに集中
して稼ぎにゆくような調子に合わせたくはなかった。
「5千ドルなんて、どこに?」と、彼。実際、ウソはついてない。彼は、
小切手帳の残高は、200ドルを越えないようにしていた。残りは株に
投資していた。「なぜ?」と、彼は言い足した。
「ただの夢さ。教えるのに疲れた。もしも、援助してくれる人がいたら、
切手とコインの小さな店を持ちたい。経営は自分でやれるから、援助し
てくれる人は、ただの影のパートナー。運は、いらないが、自分の生活
ができて、投資してくれた人に、いい収益を支払えれば、と思っている」
一瞬、ダナーは気が引かれた。しかし、すぐに、良識が勝った。貯金
しているのは、自分のビジネスのためであって、他の誰のためでもない。
自分がよく知っていて、運営できるビジネスであって、切手とコインな
んて、もっての他だった。
「いいアイデアに聞こえる」と、彼。「助けてくれる人が見つかるとい
い。銀行が助けてくれるとは思えないが」
「オレが用意できる担保が、もっと多くなければ、ダメだ。10フィー
トのポールを飛び越えるようなもんさ。忘れてくれ!言ったように、夢
を見てただけ。しかし、オレは本気でそれがやりたい。オレにカネがあ
れば、あるいは、カネを増やせれば。ブライアン、もぐり相場屋とは、
まだ、付き合いがある?いつも、正規のブローカーを通しているだけ?」
ダナーは言った。「まだ、カルバーに頼んでいる。しかし、彼は、町
のどの正規のブローカーにも劣らないくらいまともだ。しかし、あんた
は、前にオレに言った、もぐり相場屋は、少額の投資でのみ有利になる
と。利益率は低く、手数料も安いが、株が下がりそうなら、それから得
られる利益がどうであれ、その限界に来るまでに、すべて売ってしまう
ことで、自分たちを守っていると。そう、あんたは、100とか100
0株単位で買うような、大きな投資をするなら、直接、株式市場から買
った方がいいと思う。だが━━━」彼は、肩をすくめた。
「あんたが正しいと思う。今夜の予定は、ブライアン?気分が落ち込ん
でるので、外出したい。一杯やりたいが、ひとりでは気が進まない。い
っしょに、どうだい?」
ブライアンは、ためらった。ほんとうは飲みたくなかったが、すぐ買
うべき新しい銘柄は?といった会話もしたくなかった。AT&Tを売っ
たら、カルバー氏と話すのは、彼の残高で資金を遊ばしておくより、す
ぐになにか新しい銘柄を買った方がいい、ということになりそうだった。
「行きたい店は、遠く?」
「たった2ブロック先。新しい店で、オープンしたばかり。静かで、ジ
ャズはなし、レコードさえなし」
ダナーは賛成して、上の自分の室でオープンコートとハットを着て来
た。エマーソンのは、ロビーの彼の脇のイスに最初から置いてあった。
◇
話していた店は、プラムストリートのペンキ屋の2階にあった。黒人
地区のヘリにあったが、その中ではなかった。ドアに、のぞき穴はなか
ったが、エマーソンが、あるリズムでドアをノックしすると━━━それ
をダナーは覚えた━━━ドアが開いた。若い男━━━ダナーには、ポー
ランド系に見えた━━━がドアを広く開け、エマーソンを見て、笑顔に
なった。「入って、ミスターエマーソン」と、彼。「会えてうれしい!」
ダナーは、エマーソンが本名を教えていたことに少し驚いた。ふつう
は、このような場合、本名は教えないで、ファーストネームだけで呼び
合う。しかし、その理由が、店に通されて、すぐに分かった。エマーソ
ンは言った。「友人を紹介する、ハリー。同じ宿舎なので、いつでもこ
こへ来れる。オレが保証する」ダナーは手を差し出して言った。「名前
は、ブライアン」ハリーは、温かく握手した。「会えてうれしい、ミス
ターブライアン。オレは、あんたより、おそらく、ずっと前からミスタ
ーエマーソンと知り合いなんだ。6年前、彼から歴史公民を習った」
エマーソンは笑って、ハリーの肩を叩いた。「頭が良かったが、修正
第18条が成立する前にクラスを飛び出したので、結局、習えなかった」
ブライアンとハリーも笑った。
店は、確かに、静かだった。1つのテーブルにカップル、別のに3人
の男。しかし、大声でしゃべる者はなく、音楽もなかった。
「今夜のオレの個人的客」と、ハリー。「来て、キッチンテーブルへ」
彼はテーブルへ案内した。
「それで、今」と、彼。「悪いニュースがあって、ウィスキーとジンを
切らしている。あるのは、ワイン━━━イタリアの赤━━━とビールだ
け。しかし━━━」彼は窓に行って、シェードを上げて、外を見渡した。
「しかし、ジンとウィスキーは、まもなく、ここへ来る。やつに電話し
て、それぞれ半ケースづつ、すぐに持ってくるよう注文したところ。少
し待ってくれれば━━━」
「ワインでいい」と、ダナー。エマーソンも、ビールが冷えてれば、そ
れでいいと言った。少なくとも、酒が来るまでの時間潰しになる。
しかし、まだ窓を見ていた、ハリーが言った。「待って!ちょうど車
が停まった。たぶん━━━エディだ!失礼、ドアまで行かないと」
「賢いやつだ」と、エマーソン。ハリーが室を出て行くと言った。「彼
は、この店で、彼の前の教師より、たぶん、10倍も20倍も、稼ぐこ
とになるだろう」
「あるいは、刑務所行きか」と、ブライアンダナー。「そう、彼が金持
ちなら、切手とコインの店の資金を頼めるかもしれない!」
彼は、冗談として言ったのだが、エマーソンは笑わなかった。彼は言
った。「それは不可能だと言った。彼は、ほかの誰よりも興味を持つと
思う。彼も自分で、切手を収集している。高校時代に始めた。オレが彼
に手ほどきしたのさ。収集の核として、オレの持ってる切手で二重のも
のをあげた」
「彼が金持ちであることを祈ろう」と、ダナー。理由もなく立ち上がり、
ブラブラ窓の方へ行って、ハリーがしたように、外を見るためにシェー
ドを少し動かした。
角に、オープンカーが停めてあった。マックスウェルのように見えた、
それほど古くない、マックスウェル。そして、助手席に座って待ってい
る娘がいた。
その角度からは、娘は、メアリーホートンによく似ていた。しかし、
もちろん、それはあり得なかった。メアリーホートンは、100万年経
ったって、酒の密売人の運び屋の車に乗ったりはしない。バカバカしい
考えだ。偶然の空似。
彼は窓から戻り、キッチンテーブルに座った。
「コンチネンタルオイルはどう?」彼は、エマーソンに訊いた。
9
1か月後のクリスマスイブ。サンタクロースに会ってみよう。とても
陰気で不幸な、エドガーB・コンガという名のサンタクロースだった。
自分の室で服を着ていた。彼の妻は、今夜のパーティのために、きれい
なカラーと最高のスーツを着るよう、きつく言っていた。ウェイ夫人と
彼女の姉は、今夜のディナーのために集まっていた。今は6時で、もう
しばらくは、ここにいるだろう。
気の進まない、サンタクロース。この特別なクリスマスが、家とオフ
ィスで、少なくともいくらの出費になるか、大雑把に計算した。そう、
1日の有給休暇から始まって、オフィスを5時でなく3時に早く締めた
ので、合計1日と2時間。営業マンとオフィスマネージャーに、それぞ
れ、20ドルのボーナス、他のみんなには10ドル。顧客とその他のビ
ジネス上の付き合いで出したクリスマスカードが、切手代も含めて50
ドル。全部合わせて、少なくとも300ドルになる。たぶん、もう少し
多いだろう。
家では、少なくとも、その2倍だ。見て行こう、ビビアンのピアノに
200ドル。(これは、もっと悪くなり得た。彼の妻は、娘のために家
庭用グランドピアノを買うよう言っていた。しかし、それではリビング
ルームがあまりに混み合ってしまうので、古いアップライトを新しくて
良いピアノに買い替えることで満足するよう誘導した)ジミーは、大学
のクリスマス休暇で家に帰って来ていた。彼が家にいるあいだ、いろい
ろ言われていたが、また、200ドルの小切手。これも、もっと悪くな
り得た。ジミーは、車が欲しかった。彼の母が、1台買うよう、彼の肩
を持った。大学の友達はみんな車を持っていると、彼は言われた。この
議論では、彼は一貫して、ジミーに車は買えない、という不動の姿勢を
貫いた。可能だとしても中古車、新車はダメ。クリスマスプレゼントに
中古の物は、ふつうはあげない。妥協点は、200ドルの小切手だった。
古いピアノで取引した、ビビアンのピアノと同じ額だった。もしもジミ
ーがその額で中古車が欲しければ、簡単に買えた。それは、彼の守備範
囲だった。コンガ氏は、1つのことを主張した。車を買う前に、オハイ
オ州のウースター大学に戻ること。シンシナティからウースターまでの
長いドライブは、100マイル以上あって、冬のこの時期、とても危険
だった。(彼は知らなかったのは、ジミーはすでにシンシナティで車を、
少しの手付金で買っていて、あとは、残金を支払うために、小切手待ち
だったことだ。それで、もちろん父には内緒にして、休暇のあいだ車を
使うことができた。大学に帰るのも、その車が使えた。コンガ氏は、な
にも知らなかったので、傷付くことはなかった。彼の息子は、クリスマ
スの翌日には、車を買って、シンシナティでの休暇や、ウースターに帰
るのにも使ったが、事故は起こさなかったので、コンガ氏が知ることは
なかった)彼の妻は、子供たちに比べると、リゾナブルだったが、それ
でも、クリスマスプレゼントに100ドル掛かった。彼女の欲しいもの、
それはコートで、毛皮のコートでなかった、を彼に言ったとき、もっと
安くても変えると思った。毛皮でないコートが100ドルを越えるとは、
想像もできなかった。しかし、買った。105ドル、正確には。あとは、
友人や親戚、彼の妻の親戚に、小さなプレゼント。彼の妻や子どもたち
を除いて、彼自身を救うものはなかった。クリスマスカード、クリスマ
スツリー、クリスマスの食べ物や、飾り、キャンディ。キャッシュでの
プレゼントを、家庭内のお手伝いさんや、郵便配達、新聞配達に、全部
合わせて、少なくとも700ドルが家に、少なくとも300ドルがオフ
ィスに、合わせて、少なくとも1000ドル。子どもの頃から、なにも
楽しくなかった、自分から与える側でなく、いつも受ける側だった、あ
のイヤな休暇を祝うために。
そう、確かに、プレゼントのお返しはもらった。しかし、それらは、
靴下、ネクタイ、ハンカチ、それに、マフラーだった。オフィスの面々
が、彼に買ってくれたのは、今年は、吸取紙にハサミ、封筒開けが入っ
た小物セットだった。彼は、それを欲しくなかった。吸取紙は嫌いだし、
邪魔だった。デスクでは、めったにハサミを使わなかった。封筒開けに
ついては、完全に使い道がなかった。ウィロービィ氏は、いつも、持っ
てくる前に開封してから手紙を持ってきた。
◇
「ハーク、ヘラルド エンジェルス シング」ビビアンが階下でピアノ
を弾いていた。彼女が、ここ数か月で、かなり上達したことは認めるが、
新しいピアノと古いピアノの音色の違いは、聞き取れなかった。たぶん、
まったく違いがなかった。
かわいそうなコンガ氏。カラーのボタンは、ずんぐりした指から飛び
出て、衣装ダンスの下にころがって行った。それを拾うために、ゆっく
りと痛々しく、ヒザでかがんだ。かわいそうなコンガ氏。かわいそうな
コンガ氏、かわいそうなサンタクロース、疲れて、年をとって、病気を
抱えている。それでも、多くの人が生活のために彼を頼っている。
オフィスの7人。家でフルタイムで家事や料理をする、マークハム夫
人で8人。これを、つぎの者も含めて、8・5と数えよう、平均して週
2日の庭師に、週1日洗濯やアイロン掛けをする黒人婦人。
それから、彼が外からサポートする3人、妻に息子に娘、みんな基本
的に、彼にとっては、見知らぬ者たちだった。妻のセルマは、かつては
知っていた、あるいは、そう思っていたが、今は、彼には見知らぬ者だ
った。息子や娘は、もともと不可解だったが、大きくなるにつれ、ます
ます不可解になった。
ウェイ夫人は、亡くなった共同経営者の未亡人だが、ずっと昔にハリ
ーウェイと交わした共同経営規約によって、今も、純利益の4分の1を
もらっていた。(もちろん、彼がハリーウェイより先に死んでいたら、
セルマが同じ収入を得ていただろう)
全部合わせて、12・5人が、彼に依存していた。
「来たれ、友よ」ピアノが奏でていた。「喜んで、来たれ、来たれ、ベ
ツレヘムへ」彼は、少年の頃、聖歌隊で歌っていた。プロテスタントの
聖歌隊だったが、特別なキャロルは、ラテン語で歌っていた。ほとんど
60年たっても、歌詞をまだ覚えていた。「来たれ、拝め」来たれ、彼
を拝め!
彼は、ネクタイをしめ始めた。突然、硬いカラーのきつさで、わなに
掛かった気がした。硬いカラーのきつさが、さらに増した。すべてのも
のに、わなに掛けられた。
どこかで、間違った方向転換をしたのだ。間違えを犯した。しかし、
いつ?どこで?
◇
エドワードB(ベンジャミンのB)・コンガは、60・5年前に、マ
ウンド通りの小さな家で生まれた。(それは、ブラックベルトにあって、
近所に黒人一家がいた、今では、60代の尊敬すべき白人一家もいた)
父は、尊敬すべき小さな機械店のオーナーだった。彼は、6人兄弟の末
っ子だった。6人のうちの唯一の生き残りだった。ほかのだれも、世紀
の変わり目までさえ、生き残れなかった。
学校はまったく興味がなかったので、16でやめて、父の店で働き始
めた。彼は、一生懸命働き、よい仕事をしたが、なにもいいことがなか
った。1882年に、彼が20のとき、父が死んだ。店は、破産のため
閉店した。判明したことは、売るような資産はほとんどなく、母に残さ
れたものも、ほとんどなかった。新しいオーナーには、息子たちがいて、
エドワードコンガを事務員として雇うこともしなかった。
しかし、彼の経験から、大きな町の機械店の事務員の仕事を得た。彼
は、多くを学んだ。機会は、とても限られていた。12年後、32にな
ったが、まだ、事務員だった。もちろん、昇給もわずかだった。独身で
質素に暮らしていたので、貯金の額は、数千ドルあった。唯一の昇給の
チャンスは、部門長である直属の上司が、死ぬか、引退することしかな
かった。しかし、部門長は、まだ、40代で、ピンピンしていた。
ハリーウェイと出会い、友人となったのは、このときだった。ハリー
ウェイは、機械の卸売業者の巡回販売員だった。彼とハリーは、最初、
営業中に、店で会った、しかし友情が生まれて、仕事以外でも会うよう
になった。友情は熟した。ハリーは、エドワードコンガより2つ若いだ
けだった、もっとも親しい友人になった。ふたりは、おたがいに、もっ
とも親しい友人であり続けた、ハリーが1913年に死ぬまで。突然の
予想できない死だった。ハリーは病気したことがなかった。生涯で1日
も病気にならなかった。医者の診断では、血のかたまりが脳に達して、
そこでとどまったことが原因だそうだ。たった48才だった。
1896年、知り合ってから2年より少し短く、ハリーが32、エド
ワードが34で、ふたりの共同経営が形成された。ハリーの提案だった。
彼は言った。「エド、オレたちには、機械は、まったくない。あんた
が小売店を見つけても、売るべき機械がない。卸売店は、そこで働いた
ことがある者しか見つけられない、オレのように。そう、オレたちは、
わずかな貯金しかない。それをプールして、オレたちだけの小さな小売
店を始めよう。それは、小さくて、近所の店というかんじ。そこから、
もっと大きくすることは、たぶん、できない。それを維持できるかどう
かも分からない。あんたは話してくれた、父の店がどうなったか、それ
が、オレたちにも起こるかもしれない、しかし━━━」
ハリーは、印象的に、ひと息入れた。
「シンシナティで、飛躍的に成長している分野がある。機械用具産業だ。
オレたちの古き良きクィーンシティは、その中心になろうとしている。
オレたちがギャンブルするなら、オレたちの絶好の機会になる」
「ギャンブルって、どう?」エドワードは、知りたがった。「小さな機
械店から出発したとしても、売り上げを10倍にすることができる」
「とにかく、オレたちは、店をどう経営してゆくか、分かってない、エ
ド。いや、オレが考えているのは、こういうことだ。そういう機械店に
すべて売ること。仕事をすること。必要なことや問題点を、まったく知
らない。しかし、ふたりとも、機械のことはよく知っている。それは、
大きな力になる。卸売業者や機械製造業者をリストアップして、販売店
を持たない業者や、オレたちに注文してくれる業者をピックアップしよ
う。オレたちは、注文をもらい、商品を直接、出荷する。在庫は持つ必
要はない。彼らは、オレたちに請求し、オレたちは顧客に請求する」
「オレたちは、オフィスとスタッフが必要だな?」
「オフィスは必要だ、手紙を受け取る場所としてのみなら。しかし、そ
れは小さなものでいいし、ダウンタウンとか良い場所になければならな
い。初めは簿記は必要最小限に抑えて、オレたちだけなんとかなる。ビ
ジネスが大きくなってくれば、誰か女性で、簿記もタイプもできる事務
員が必要になる。当分のあいだは、その従業員ひとりでやってゆける」
エドコンガは、言った。「経費が増えるのは、良くない?」
「そうだな、ビジネスが十分大きくなって、もっと多くの従業員が必要
になるまでは。大きな出費は、最初は、オレたちの口座から引き出され
る。毎週引き出していいのは、生活費だけだ。たぶん、しばらくのあい
だは、利益は出ない。まったくのゼロかもしれない。ずっと利益が出な
くても、どこまでやれるか、可能性に挑戦しよう!」
エドコンガは、勇気のある決断をした。「オレはゲームだと思ってる、
ハリー。もしも、あんたもそうなら、今まで取って来た仕事は、また、
取って来れるとして、さらにその上を目指すなら、オレたちはそのまま
で、どこへも行かない。どちらも30代で、ずっと仕事をして来たなら
ば、ここらで打ちまくる時だ。あんたもゲーム?」
ハリーもそうだったが、もう少し、注意深かった。ふたりは、いきな
りすぐに、ビジネスを始めたわけではなかった。初めに、可能性を調べ
た。ハリーウェイは、彼の仕事が、エドワードが店にいるのが仕事だっ
たのに対して、外まわりだったので、その地域や人脈を調査した。夜は、
エドコンガは、手紙を書いた、オリバータイプライターで2本指で、郊
外の卸売業者や製造業者に、彼らの気持ちになって。反応は、全般的に、
勇気づけられるものだった。機械工具店で扱われる消耗品の卸売業者や
製造業者のいくつかは、シンシナティを周期的に巡回する営業マンを持
っていたが、もっと密接に、より頻繁に、顧客に接してくれる専門店と
の取引に、快く応じてくれた。それ以外は、シンシナティに手紙で販売
していたので、地域の専門店に扱ってもらえることを喜んだ
その話題の最初の会話から5週間もたたないうちに、ハリーウェイと
エドコンガは、それぞれの仕事に2週間の猶予を与えただけで、背後の
退路の橋に火を放った。2週間の猶予が終わるときまでに、ふたりは準
備を整えた。ハリーは、会社の住所となるフロントストリートに小さな
壁の穴のようなオフィスを見つけてきて、借りた。最初は、電話さえな
かった。一日の大半は、誰も電話に出られる者はいなかったし、189
6年の電話は、商業的にどこにでもあるものでなく、小さなビジネスは、
ほとんど電話なしに行われていたからだった。
ふたりは、2つの中古のデスクと2つの中古のイスを買った。ふたり
は、ビジネスをミッドウェスト旋盤サプライ会社で始めると決めて、社
名の看板を印刷した。けれど、数週間もしないうちに、研磨剤が、ほか
のどの製品よりずっとよく売れると気づいて、仕上げ研磨会社という会
社名でやって行こうと決めた。その後ほどなくして、スクリューマシン
プロダクツができた。
結局、その他のすべてを、単一のスタイルでやって行くと決めて、社
名を、コンガ&ウェイかウェイ&コンガにするかを、コインを投げて決
めた。しかし、ほかの社名もすべて引き継いだ。理由を訊かないで欲し
い。その時代の、ビジネスのやり方だったのだ。商品の特徴をより狭く
絞り込めば込むほど、それにマッチした社名もいろいろ必要になって来
る。
ふたりは、昼も夜も働いてはなかった。昼と夕方には、働いていた、
しばしば深夜まで、たまにそれより遅く。ハリーは、初歩の簿記ができ
た。エドは手紙をやった。夕方には、つまり、明るいうちに、ふたりと
も、販売を終了した。ハリーは、もちろん、良き営業マンで、営業の経
験が長かった。しかし、エドも、かなりすぐ、良きライバルになった。
全体の初期投資は、最初に考えていたものより、かなり少なくて済ん
だ。ふたりの全体の経費は、オフィス代、印刷、すべて含めて、数千ド
ル必要と思っていたが、それぞれ、数百ドルで済んだ。その時代の価値
で、月たったの60ドルだった。少額を投資に回せたし、ビジネスが利
益を生み出すまでは、生活費は、それぞれの貯金から賄った。可能性に
ついて議論して、決めたことは、より良いビジネスチャンスに使えるよ
うに、ふたりの資金の全額をプールしておいて、各人は、自分の生活費
だけを毎週引き出して、自分の稼ぎにするということだった。エドワー
ドは、機械会社の事務員として、週22ドルもらって、そのまま貯金し
ていたが、週20ドルあれば、十分だと考えた。しかしハリーは、営業
マンとして、そして企業家として、顧客や将来の顧客に対して、いい服
を着て、繁盛しているように見せなければならないので、それぞれ週3
0ドルは引き出すべきだと主張した。
それで、ふたりは、楽に生活して、いい服を身につけていた。しかし、
ふたりは、イヌのように働いた。(コンガ氏が、あの頃が生涯でもっと
も幸せだったと思い起こすのは、そのせいなのだろうか?)そして、あ
る週に、ほん少しの利益を生み出したのは、1年と少したった頃だった。
経常経費を上回る金額が、数ドル、会計に記された。ふたりは、週末だ
ったので、夜までお祝いした。そして、コンガ氏は、今でも、そのお祝
いを思い出す、おだやかで、安上がりだった。ふたりで、バインストリ
ートへ繰り出して、運河の北は、当時そう呼ばれていた、ふたりで、数
杯飲んで、バイエルンのドイツ音楽を聞いた。
コンガ氏は、今でも、25年もたつのに、ネクタイを締めるように、
あの夜のことを思いだす。
ほとんどは、彼は、ハリーウェイのことを考えている。ハリーは、た
だひとりの親しい友人、今まで持ったことのない、ただひとりのほんと
うの友人だった。死んでからもう10年たつ、しかし、今、生きてる者
たちよりも、いっしょに働いている者たちよりも、鮮明に覚えている。
ハリーウェイ、良き古きハリー。ハリーが死んだとき、コンガ氏のなに
か小さなものも死んでしまった。
◇
ふたたび、彼の心は、過去へと戻って行った。ある週にわずかな利益
が出ても、支払い能力を得るには遠く及ばず、イージーストリートへ繰
り出すこともできなかった。ふたりは、ただがむしゃらに働かなければ
ならなかった。ふたりがビジネスを始めてから、2年半たって、やっと、
明らかな黒字になった。最初の従業員を雇う準備ができた。それは、簿
記も速記タイプもできる若い女性で、ふたりを夕方の仕事から解放して
くれた。そして、オフィスには昼間でも誰かいるので、電話を入れた。
これで、やっとビジネスらしくなった。
ふたりが懸命に働くのを、やめたわけではなかった。それを続けた。
しかし、ふたりは働くことを楽しんだ。今、ただただ、その頃に戻れる
なら戻りたい、戦いだったが良い戦いだった、彼とハリーが30代だっ
た時代、ふたり、いつもいっしょだった。
つぎの大きな飛躍があったのは、1903年だった。もうひとり、正
規の従業員が必要だった。そして、すぐに、ほかになん人か必要になり
そうだった。今までの小さなオフィスは、もはや、広さが足りなかった。
ふたりは歩き回って、コマースストリートに現在のオフィスを見つけ
た。室代は、最初、びっくりするほど高かったが、ギャンブルをするこ
とにして、そこを借りた。ふたりは、まだ、そこにいる。(ふたり?コ
ンガ氏は、まだ、そこにいるが、ハリーウェイは?ハンサムで陽気、留
まることを知らない楽観主義、ウルトラ健康体、どんなことがあっても
笑いとばせる才能)
ハリーウェイが結婚したのも、1903年だった。かわいい娘で、当
時から少しふくよかではあった。今、20年たって、彼女は、太った腑
抜けの雌牛だった。今夜は、彼女の姉といっしょだった。
ハリーの結婚は、エドワードコンガにとって、突然で、まったく予想
外だった、疑いもなく、その年のエドワード自身の結婚へとつながった。
つまり、それが、突然、彼に、もう40で、支払い能力もあり、尊敬さ
れるビジネスマンだという事実に気づかせた。そして、今までずっと、
結婚して家庭を築くことを望んでいて、今、それについて真剣に考え始
めるときだと気づかせた。彼がそれについて考え始めたころ、セルマエ
ンダーズに出会った。彼女は、26で、同じ教会地区に属していて、同
じ教会に、ふたりは出席した。セルマは、魅力的で、かなり知的で、そ
して、いつも楽しそうにしていた。彼は、ほかを捜す理由が見つからな
かった。それは、強引な求愛でも、特別にロマンチックなものでもなか
ったが、ふたりは、いっしょにやって行けそうに見えた。出会ってから
3か月もしないうちに、彼はプロポーズして、受け入れられた。遅らせ
たり、長い婚約にする理由はなにもなく、それから1か月で結婚した。
(セルマは、遅らせたくなかった。彼女は、学校の教師で、教えるのが
嫌いで、早く夫を見つけたかった。一方、エドワードは、40で、見た
目も美男子ではなかったが、人前に出せるし誰からも尊敬され、大量の
取引がないとしても、収益を上げている企業の共同経営者でもあった。
彼は、堅かった。つまり、彼女が26で捜そうとしていた、夢以上の夫
だった。なぜ、彼の気が変わる前に、彼を取り逃がさなかったのか?)
ふたりの結婚は、完全に満足の行くものではなかった。簡単なハネム
ーンでさえ、鉄道でナイヤガラの滝へ行って、ホテルで5泊したが、エ
クスタシーよりももっと困ったことがあった。エドワードコンガは、決
して、セックスが強い方ではなかった。彼は、20才のときに、女性へ
の好奇心を満足させた。彼が決心したのは、明らかに過度だということ
だった。それ以来、ハリーウェイが突然結婚するまで、女性への肉体的
な考えは持たなかった。ハリーの結婚で、いつか自分の王国を築くのな
ら、今がその時だと考えた。もしも彼が結婚しなかったら、また、彼は、
家族や子どもといった固い土台が欲しかったことを除いて、結婚する気
はなかったが、疑いもなく、残りの人生を、結婚のことを考えることな
く、独身で過ごしただろう。
それについては、彼は、理想的な伴侶を選んだ。たしかに、情熱的な
女は、彼を不幸にしただろう。セルマに情熱的な部分があったとして、
ふたりとも、それには気づいてなかった。たいていは酒の力を借りて、
(それ以外は、ほとんど、彼は酔うことはなかった)たまに彼女に要求
することがあっても、彼女はそれを黙認したが、正確には冷たくはなく、
しかし情熱的でもなかった。(美容院に行って来たばかりだから、セッ
トを崩さないように注意して!)
それにもかかわらず、結婚して1年で息子が生まれた。そして2年後
に、娘が生まれた。2回目の出産は難産で、医者は、セルマはもう子ど
もを作らない方がいいとアドバイスした。エドワードとセルマは、もう
ひとりについて相談したわけではなかったが、そのアドバイスにホッと
した。エドワードは3人目が欲しかったが、2人で始めることに、完全
に同意した。特に、ひとりは息子だったので。
エドワードがウォルナットヒルズに家を買ったのは、その頃、190
7年の初めで、今、クリスマスイブのために服を着ているのも、その家
だった。その前は、もっと狭い貸家に住んでいた。しかし、ウォルナッ
トヒルズの家は、広かった。多くの寝室があった。それは、ふたりに、
ただ認められ、話し合いもなかった。それ以来、エドワードとセルマは、
別々の寝室で、互いのプライバシーを守った。
そのことを、不和が生じたと言うことはできない。実際、ふたりは、
離れてから、前よりもっと親しくなった、少なくとも、しばらくの間は。
出産のために必要な困った行動をする困った必要から自由になって、
ふたりは、お互いに相手のことを、もっと好きになった。より良い方向
へ向かった。それ以来、(実際には、それよりもっと前以来、妻が2番
目の子どもを妊娠したとき以来)彼は、妻を肉体的に知らなかった、あ
るいは、別の女も。彼は、そうしたことは、まったく考えなかった。
それ以来、そして今も、セックスは、心配でもない些細なことだった。
彼が心配だったのは、すぐにタバコが吸えないことだった。(彼は、
セルマに、1日3本以上は吸わないと約束した、そしてそれを守ってい
る、たとえ脅迫されても。今日は、2本吸ったので、3本目は、ディナ
ーのあとに取っておいた。この1本のタバコの慰めのために、今夜は、
事態は悪くなりつつあった。その慰めもなければ、がまんできないだろ
う)
◇
ネクタイは、まっすぐ付けたが、少し、きつ過ぎた。息が詰まったの
で、鏡に映る赤くなりつつある顔を見ながら、ネクタイをゆるめた。赤
くなったのは直ったが、まだ、鏡に映る顔を見ていた。年取った顔。な
ぜ、否定する?それは、60・5才の年取った顔だった。父は、50才
くらいにどこかで死んだ。母も同じ年の頃に、数年あとだったが、死ん
だ。兄や姉たちは、だれも、その年まで生きてなかった。ハリーウェイ
は、48で死んだ。
そのくらい長く?つまり、生きることに、重要ななにかを見いだせな
いときに、それに、なにか意味がある?死は、驚くべきことだが、神を
信じるなら、なぜ、それがある?エドワードコンガは、神を信じていた。
ほとんどの日曜は、教会へ行った。生涯を通じて、そうだった。
そして、彼は死を怖れていた。医者は、聴診器を持って、おしゃべり
で、心臓肥大症や狭心症の初期症状の話をした。1日3本、ほんとうに?
なんの話か気づいてない。(あるいは、気づいている?彼が自分に許し
ている1本を、すべてやめれば、その分、長く生きれる?つぎのクリス
マスが見れる?)
「リーベシュタウム」今、階下からピアノが聞こえて来た。
「愛の夢」が意味の、ドイツ語だった。好きな曲のひとつ。しかし、な
ぜ?なぜ、いつも、その曲を聞くと、ハリーウェイを思い出す?
ドアのベルが鳴った。コンガ氏は、ベストを身に着けた。客たちは早
い。「神さえ、おったまげ!」と、彼。彼は、すぐに神に謝罪したり宣
誓したりする男ではなかった。
10
春が来た。1923年の春、なにも起こらなかった。まだ、なにも。
オレたちは、みんな、1つ年を取った、これを始めた日から。それがす
べてだった。病気もなし、死もなし、昇給もなし、クビもなし。ビジネ
スは、ある時は、少し上向きで、別の時は、少し下向きだった。給与の
ために働いている者にとっては、どうでもいいことだった。営業マンた
ちは、マージンの違いを見て、コンガ氏は、利益の違いを見た。ウィロ
ービィ氏は、すべてをチェックした。給与のために働いているみんなの
ことも、ビジネス上の利益のことも、すべてに興味があった。
4月初めに、最後の重い雪が降った。同じ月の下旬に、最後の軽い雪
が降った。5月に入って、春がやって来た。5月末に、本格的な春にな
って、あたたかく、陽射しに溢れ、陽気になった。
ステラクロスターマンの20才の誕生日は、5月末の土曜だった。
誕生日に、特別なことはなにもなかった。ほとんどの者は、1年に1
度、誕生日があった。オフィスでは、唯一の例外は、ウィロービィ氏だ
った。2月29日に生まれたので、4年に1度しか誕生日が来なかった。
占星術を信じるなら、彼はどこか違っていると考えるかもしれない。た
ぶん、ウィロービィ氏に関しては、占星術的になにかあるだろう。オレ
は、このオフィスで、すでに11か月、働いていた。仲間の社員たちを
少し知るようになって、(上司については、それよりは少なく)、ウィ
ロービィ氏については、まったく違うなにかがあると、気づいていた。
彼を称賛してしまうような、違うなにかだった。これを、オリンピック
選手の冷静さと呼ぼう。彼は、オレたちのように、怒ったり、興奮した
りしないし、急ぐこともなかった。心配もしないし、怒りも見せないし、
苛つきさえ見せなかった。(怒られはしないが、黒ヘビのむちを使われ
るよりもっとイヤな、叱責を飛ばされることはあった)
ステラの20才の誕生日に戻ろう。それは、音楽の最初の裂け目とな
った、と言える。初めて、マーティとのデートをすっぽかした。それに
ついて、彼女はウソもついた。
その日が、彼女の誕生日であることを、オフィスのだれも知らなかっ
た。彼女は、わざと、マーティのこともあって、そのことを言わなかっ
た。ふたりは、その夜もデートした。もしも彼女の誕生日と知っていた
ら、たぶん、特別なお祝いをして、プレゼントを用意しただろう。彼女
は、彼に、そのようなことに彼のカネを使って欲しくなかった。彼女は、
彼が母を支えていて、自分のためにはわずかしかカネが使えないことを
知っていた。彼女は、そのことをいつも考えて、デートの費用が少しで
も高くならないように注意していた。ふたりは、たいていは映画へ行っ
たが、できるだけ近所の映画館へ行った。それは、値段が安いだけでな
く、電車賃も安くなるからだった。たまに、ダウンタウンにショーを見
に行くときは、いつも彼女は、バルコニーの席がいいと言い張った。
そう、マーティは、今日が彼女の誕生日だと知らなかったに違いない。
知っていたら、プレゼントや夜に、あるいは両方に、特別な用意をした
だろう。そのために、1・2週間は、ランチを節約しただろう。彼女は、
そのような健康を害するようなことは、して欲しくなかった。
彼が好きだから、あるいは愛しているから?彼女には分からなかった。
彼女に分かったのは、物事は、ふたりの間で、この数か月のあいだ、改
善されたということだった。6か月前、彼女は、もうデートするのをや
めようとしていた。しかし、彼女はためらった。彼は、性格がよくて、
やさしくて、よく考えていた。彼が好きだった。彼を愛するようになる
かも知れない感情が、芽生えていた。
それから、彼のおかしなところ。オレたちは、みんな、おかしなとこ
ろが1つや2つはあるんじゃないか?あんたを尊敬している少年といる
方が、ひとつのことしか考えないで、いつも、あんたにちょっかい出し
てくるやつより、いいんじゃないか?
そして、彼は、彼女を愛していた。ついには、そう、口に出して言っ
た。今からだいだい、5か月前、ふたりが最初のデートをしてから6か
月後のことだった。クリスマスだった。イブではない。彼は、母親と過
ごしていた。そして、彼女も自分の家族といっしょのように過ごしてい
ると、考えた。(彼女の方は、とても居心地が悪く、退屈なクリスマス
イブだった。しかし、そのことは決して彼に言わなかった。彼は、自分
の母親をとても深く愛していたので、彼女は、彼は決して、自分の両親
や弟や妹に対する、彼女の態度を理解できないだろうと思っていた)し
かし、ふたりは、クリスマスの日の夜も、デートをした。そして、デー
トの終わりに、階段の一番上で、ドアのすぐ外で、彼は彼女におやすみ
のキスをした。彼女は、進行に気づいた。なぜそれをしたのか、まだ、
確信がなかった。クリスマス精神?急に思ったのは、これは最後のデー
トで、彼とは別れる、オフィスで顔を合わせるのを除いて、これが、ふ
たりのお別れだということだった。しかし、理由はなににせよ、彼女は
キスを受け入れた。腕を投げ出して、ほんとうのものにした。彼は一瞬
とまどったが、腕を彼女に回して、彼からのもののように、キスをし返
した。いや、激情ではなく、愛情をもって、愛情プラスなにかをもって。
そして、彼は、かすれ声で、言った。「ステラ!」
しかしそのとき、彼はステップバックして、彼女から急いで離れて、
言った。「ごめん、ステラ」
「なぜ?」と、彼女。「わたしがしたこと、とにかく、わたしが始めた。
キスになにか悪いことがあれば、それは、わたしのせい」
彼は、うなるような、かすかな声を出して、言った。「愛してるよ、
ステラ。しかし、できない、すべきじゃなかった、頼めないのなら、正
しくなかった」彼は、そこで、行き詰まった。彼は言った。「おやすみ」
急いで、階段を降りて行った。
明らかに、彼女は、彼を困らせていた。彼女は、自分のしたことを喜
んでいた。なにかを学んだ、それは、彼といっしょにいることで、時間
をムダにしているだけじゃないという希望だった。
◇
つぎの日、オフィスで、彼は、困っているように見えた。しかし、彼
はそこから抜け出るだろう。終業時間が来て、彼は彼女に、つぎの土曜
の夜にデートに誘った。そして、物事は、少しづつだが、改善に向かっ
た。キスは、まだ、おやすみのキスを除いて、してなかった。しかし、
彼女に腕を回すようになった━━━軽くだったが、決して、強く彼女を
引き寄せることはしなかった━━━キスは、少し良くなった。少なくと
も、ふたりには愛情があった、劇情ではなかったが、温かさがあった。
彼女は、まだ、彼を愛しているのか、いないのか、分からなかったが、
少しづつ、愛せそうに感じ始めた、もしも。
このもしもは、不可能なことではなかった。それは、もちろん、起こ
り得た。もしも、彼の給与がかなり上昇したら、あるいは、もしも彼の
母が死んで、その責任から解放されたら、あるいは、その両方が起こっ
たら。彼の母は、彼が言ったことから考えると、体が弱く、病弱で働く
ことができなかった。健康で若さの溢れたステラから見れば、それは、
彼の母は、あと1年か2年しか生きられないかもしれないということだ
った。彼の母が死んで欲しかったのでは、もちろんない。しかし、そう
なったら、すべてが変わる。それが2年後より長かったとしても、ふた
りは若かった。彼女は、今日で20、マーティは、今までは、22だっ
た(彼女は、彼の誕生日を知らなかった)多くの者は、中年になるか、
20代後半になるまで結婚しない。それは、彼女がそう考えたいもので
はなく(マーティのために、彼の母に会ったことがないので、個人的感
情もなかった)ただの可能性だった。別の可能性は、会計の仕事に就い
て、給料が上がることだった。彼は会計の勉強はしていた。彼女には、
自分は頭が悪く、進歩がのろいと言ったが、たぶん、ふつうの頭だった。
心は素直だから、いつか、いい会計士になれないことはなかった。
とにかく、彼女が別のだれかと恋に落ちない限り━━━
◇
彼女は、不注意に、壁の時計を見上げた。さっき見たとき、11時だ
った。そのとき、少なくとも30分は、2度と見ないと決心していた。
しかし、そのことを忘れていた、それで、見てしまった。まだ、11時
15分だった。土曜の午後の自由まで、あと45分あった。ドレスをゆ
るめて、ワクワクする体を感じたが、その気配は少しも見せなかった。
ファイルバスケットに戻った。
電話が鳴った。自分と関係ないので、気にしなかったが、ウィロービ
ィ氏の声がした。「ステラ、きみにだ」
彼女に?それは、家でなにか悪いことでも起こらない限り、あり得な
かった。個人的電話は、正式には禁止されてなかったが、あまり推奨さ
れなかった。彼女の母には、ものすごく重要なことでもない限り、仕事
場に電話しないように言ってあった。
ウィロービィ氏のデスクに行くと、彼は言った。「コンガ氏のオフィ
スを使うといい、ステラ」コンガ氏は、その日はもういなかった。20
分前に帰っていた。
「サンクス、ミスターウィロービィ」と、彼女。コンガ氏のオフィスに
入って、後ろ手にドアを、キッチリとではなく、閉めた。
受話器を持ち上げて、言った。「ハイ、こちら、ステラクロスターマ
ン」クリック音がして、ウィロービィ氏が受話器を戻したのが聞こえた。
「誕生日おめでとう、ステラ!」
一瞬、彼女は混乱した。声に聞き覚えがあったが、誰なのか分からな
かった。彼女は言った。「サンクス、だれ?」
「ハーマンだよ、ハニー、ハーマンロイター。忘れたとは言わないでく
れ!」
「ハーマン、もちろん、覚えてる。けど、聞いて!仕事場の個人的な電
話はしてはダメ、だれに番号を?」
「だれにも、ステラ。自分で電話帳から見つけた、あんたの母親に勤め
先を聞いたので。前に人伝に聞いていたが、忘れた」
「そう、でも、電話はダメ」
「仕事場の個人的な電話は」と、彼。言葉をつなげた。「すまんが、電
話しないでくれ、というのは、もう遅い、それで、最後まで話しでも?」
「そう、仕方ない」結局、ほかの人も少なくとも1度は電話していて、
彼女は、長電話になるのは、これが最初だった。そしてなにより、コン
ガ氏は、すでに帰っていた。彼女は、ハーマンに、なぜ誕生日を知って
たのか訊こうとして口を開いた━━━1年半前から、会ってなかった、
しかし、なぜか思い出した。誕生日が同じだったのだ。年令は1つ離れ
ていたが、カレンダーの同じ日に生まれた。それで彼は覚えていて、電
話して来た。
「誕生日おめでとう、ハーマン!」と、彼女。「21になった感想は?」
「20より1つ年取った気分だよ、ステラ。聞いて、ハニー!もっと前
に電話すべきだったが、今朝、決まったことなんだ。今夜、パーティが
ある。ハンクとグラディ、バッチとドナ、フリッツと━━━フリッツは
知らないだろう、それに彼の彼女。オレ以外に3組のカップルと、オレ
の連れのだれか。それは、ある意味、オレの誕生日パーティで、それで、
あんたの誕生日パーティでもあるから、なぜ、ふたりのダブルパーティ
にして、仲直りしてはダメなんだ?と思ったんだ。まだ、オレのことを
怒ってる?」
自分が怒ってるのか、いなのか、分からなかった。ハーマンロイター
は、彼女が処女でないという事実に責任のある少年だった。しかしそれ
は、彼と同じくらい彼女にも責任があった。彼は口説いたが、彼女も口
説かれるままにした。なんの強制もなかった。しかし、最後のデートで、
今から1年半前、マーティとの最初のデートの7か月前、彼女はノーと
言った。ハーマンは、もう少しで強制的になりそうになった、それで、
彼女とケンカになった。
「いいえ、ハーマン」と、彼女。「もう、そんなには怒ってない、また、
同じことをされなければ、言ってる意味、分かるわね」
「オレは心を改めたんだぜ、ハニー。いろいろ経験を積んで。今夜のパ
ーティ、どう?」
「ソリー、デートがある、ほんとうに」
「甘えん坊の少年と?断ってしまいな、こっちは、ほんとうのパーティ
だぜ」
マーティについて、彼は、どのくらい知ってる?確かに、2・3度、
マーティといっしょのところを、友人に出くわして、彼を紹介して、し
ばらく話したことはあった。そして、その噂が広まった。しかし、そん
なに早く、マーティにレッテルを貼ったのだろうか?そのレッテルは好
きじゃなかった。彼のことを、甘えん坊とは思いたくなかった。
彼女は言った。「ソリー、ハーマン。わたしは、一度デートの約束を
したら、キャンセルしない」
「ああ、覚えてる、ステラ、そうだった。しかし、約束は破らなくてい
い、1日か数日、遅らせればいい。彼とのデートでなにをするにしても、
いつものこと。しかし、こっちのパーティは、今夜だけのもの。あんた
とオレの、誕生日パーティ。楽しくなりそう」
彼女には、彼の言う「楽しく」の意味が分かった。ダンスにドリンク、
ペッティングにメイクラブ、順番はどうあれ。
あるいは、マーティとの静かな映画。
なぜ、彼女の息が少し荒くなった?うう、と彼女は考えた。今日は彼
女の誕生日だし、なぜ、実際に、リアルパーティがダメ?酒を飲んだり、
メイクラブやハメをはずしてはダメ?
「うう」彼女は、弱くなって、ほとんど、もう少しで約束しそうになっ
た。もしも、ハーマンがもうひと押しすれば、彼女は、決心する、あと
少しの時間を持てたかもしれない。「聞いて、ハーマン!今は、勤務時
間で、これ以上話せない。決めるまで少し時間がもらえる?あとで、掛
け直す」
「もちろん、いつ?」
「仕事が終わったら、すぐ。1時間以内。とにかく、電話ブースで話し
た方がいい」
「確かに、ハニー。水道工事の店にいる、1時までは。しかし、電話す
るときは、イエスと決めてくれ、うん?くだくだしたくない。ただ、イ
エスと言って欲しいだけ、バイ!」
彼女は、受話器を置いた。そして、少しのあいだ、決心するふりをし
て、そこに立っていた。しかし彼女は知っていた、すでに心は決まって
いることを。それを、うまくごまかしていただけだった。
彼女は、自分がハーマンに電話して、イエスと言うと知っていた、そ
れが、どういう結果をもたらそうと。12時過ぎたら、もちろん。待た
されて、長く、どっちだか迷わされるのは、すぐにイエスと言われるよ
りは、彼にとってもうれしいだろう。
彼女は、プライベートオフィスを出て、真っ直ぐ、マーティの簿記デ
スクへ行った。早く話せば、彼も助かるだろう。もちろん、ほんとうの
ことではないが。ほんとうのことを言うのは、冷酷過ぎる。白いウソの
方がいい。白いウソは、事実の近くにある。彼も、彼女が電話していた
ことには気づいていたに違いない。
「マーティ」と、彼女。「さっきの電話は、女友達から、別の女友達の
ことで。彼女が、来週、結婚する、つまり、2番目の女友達が、なので、
今夜パーティをするの、バチェラーパーティのようなもの、こちら側の
女だけで。今夜のデート、来週に回したら、イヤかしら?」
「もちろん、イヤじゃない。月曜か、火曜の方がいいかも?」
「どちらでも」
たぶんそれは、と彼女は考えた、マーティにとっては、土曜のデート
よりは良くないだろう。もしかしたら、彼を失ったことに気づくかもし
れない、彼を、どんなに長く待たなければならないとしても、待ち続け
られるほど、彼を愛していると。
あるいは、たぶん━━━
彼女がファイルキャビネットに戻る姿を、マーティは、崇拝するよう
に、目で追った。ウィロービィ氏も、シニカルな喜びをもって、目で追
った。いいえ、ウィロービィ氏は、電話の会話を聞いていたわけではな
い。しかし、彼女がマーティのデスクで、マーティに言ったことは部分
的に聞こえて来た。言うときの彼女の声の調子から、ウィロービィ氏に
は、彼女が言ったことが、黒いウソだろうが、白いウソだろうが、明ら
かにウソだと分かった。
「マーティ、マイボーイ」と、ウィロービィ氏。「心を決めた方がいい。
あんたは、あの娘を失おうとしている、もしも、まだ、失ってなかった
のなら」もちろん、自分に言ったのであって、声には出してなかった。
11
つぎの月曜は、オフィスにとって、悪い日だった。ふつうではなく、
悪い日で、ものさびしい日だった。
オフィスのドアをあけて、つまり、どのオフィスだろうが、頭を入れ
て、「みんな、ハッピー?」と叫ぼう!
そこにいる者は振り向いて、あんたの気が触れたかのように、こちら
を見るだろう。そうだろう、訊いたからには。
オフィスはどこも、ハッピーなところはなかった。そこは、毎日、8
時間過ごす場所であり、そこで食事することもできれば、眠ることもで
きる場所で、自由時間に青い鳥を追うチャンスもあった、夜とか週末に。
通常のオフィスの仕事では、熟練した職人が、少なくとも、なんらかの
店の仕事で感じるような誇り高い達成感はなかった。
オフィスでは、カネを稼ぐのに苦労するくらいだ。おおかみが入らな
いようにドアで守ったり、鈍くどんよりしている。みんな幸せか?ノー。
しかし、ほんとうに、ものさびしい日もある。この日は、そのような
日だった。
その日は、オレたちのうち、ウィロービィ氏とコンガ氏を除いた、6
人がオフィスの外で、ドアがあかないために、待たされているところか
ら始まる。前触れもなく、ウィロービィ氏は遅れていた。コンガ氏が別
の鍵を持っていて、8時半には、まず出て来ることはなかった。ふつう
は、9時近くだった。
ウィロービィ氏になにかあったのなら、オレたちは、少なくとも30
分は待たされることになる。
しかし、彼は、遅れたのは10分だけだった。「すまん」と、彼は言
って、ドアの鍵をあけた。「マックスレイスマンが、今朝、7時くらい
に死んだ。レイスマン夫人が電話して来て、なにかできることがないか、
会いに行っていた」
オレたちは、彼のあとに続いて中へはいったが、すぐに、彼のところ
には行かずに、その辺に立っていた。
ジョージスパーリングが訊いた。「葬儀は、いつ?」
ウィロービィ氏は、コートとハットを掛けていた。「時間はまだ、決
まってない、たぶん、水曜か木曜。しかし、家族と親しい友人だけのプ
ライベート葬になる。あんたたちは、彼を知ってたし好きだったが、い
っしょに働いただけだ。出席する理由はない」
マーティレインズが言った。「香典や花は、送れる?」
「そう、いい考えだ。けれど、オレの方で送っておく。あの家族とは、
そのくらい親しいので」
「オレが集めようか?」と、マーティ。「うう、コンガ氏は?別に送り
たいのでは?」
ウィロービィ氏は言った。「知らない、マーティ。彼が来たら、訊い
てみる。だから、あんたはやらなくていい。たぶん、彼も一般的なもの
を送りたいと思う。どのくらいマックスと、個人的に、親しかったかは
知らないが」
オレは、その朝、オフィスを入ったり、出たりしていた、ほとんどは、
出たりだった。ふつうより、雑用が多かったように思う。しかし、オフ
ィスにいた時間は、なんと陰気に感じたことか!たくさんしゃべること
もなく、だれも、からかったりもしなかった。ウィロービィ氏さえ、い
つもの自分でなかった。
銀行の雑用を済ませて来ると、みんなは昼食で外出するところだった。
ウィロービィ氏に銀行通帳と預金伝票を渡して、ほかに雑用がないか訊
いた。
「食べに行っていい」と、彼。正午の時報が鳴り始めた。
「マックスについて」と、オレ。「オレにできることは?」
「あんたにできること?戻って、彼とチェスをする?それには、もう、
遅すぎた」
彼は、オレの顔を見て、やわらかくなった。「オレは、そんなこと言
うべきじゃなかった、フレッド。自分を咎めるな。結局、あんたは1度
しか彼に会わなかった」
「オレは自分を咎める」と、オレ。「戻るのが怖かったんだ」
「いずれにせよ、あんたは戻らなかったさ。自然に振舞えなかったから、
たぶん、彼の居心地を悪くした。忘れることだ。さぁ、行って、食べて
来い」
マーティも少し遅く出ようとしたので、いっしょに階段を降りて、ふ
たりでランチをとりに行った。彼がいつも行く店は、オレもたまに行っ
たことがあった。
「いつ、香典を集めるんだい?」と、オレ。隣合った席にトレイを置い
たときに訊いた。
「もう集めたよ」と、彼。「フレッド、あんたは出さなくていい。ほか
のみんなは彼を知っているが、あんたが来る前に彼は辞めた」
「けれど、オレは彼と会ったことがある。いっしょに午後を過ごした」
「いつ?」彼は、知りたがった。オレは、ウィロービィ氏が風邪で休ん
でいて、書類を届けに行った午後のことを話した。「みんなは、いくら
入れたんだい?」と、オレ。
「1ドルか2ドル。コンガ氏は、別に花を送ることはしないで、代わり
に、10ドル。19ドル集まった。あんたがどうしても出したいんなら、
ちょうど20ドルにできる。それで、いい花が買える」
オレは言った。「そうしたい」そして、財布を出した。そのとき、た
めらった。このランチ代を支払うと、ちょうど、1ドル残る。明日が、
給料日だ。もしも、マーティに、オレの1ドル分も入れといて、あとで
返すからと言う代わりに、1ドル渡してしまえば、今夜の夕食と明日の
朝食なしで過ごさなければならない。
そのとき、突然、オレは、それがしたかったことだと決心した。たと
え、1食か2食抜いたところで、すぐ病気になるわけではない。そうす
ることで、マックスに会いに行かなかった自分の、多くはないが、少し
は、罪を報いられるなら、それでいいと。マックスはオレにまた会いた
いと言ったのに、2勝2敗のタイだったチェスのゲームさえしてあげな
かったのだ。
それで、オレは、マーティに最後の1ドルを渡した。彼は受け取り、
ポケットの封筒の19ドルに加えた。自分のカネと分けて持っていたの
だ。
オレは言った。「マックスは、オフィスで働いていたとき、みんなか
ら好かれていたように思う。なぜだれも、彼のことを話さなかった?」
マーティは言った。「彼のことは、よく話していた。毎日、1回は。
みんな彼が好きだった。しかし、あんたが彼と会ったことは知らなかっ
たから、だれも、彼のことを話題にしようとはしなかったんだと思う」
「彼が病気のあいだ、だれか会いに行った者はいる?」
「オレは、2・3回行った、たぶん、3回。一度は、メアリーとステラ
もいっしょだった。しかし、ほとんどは、ウィロービィ氏がオレたちに
連絡してくれた。近所に住んでいて、家族とは知り合いだったから。な
ぜ?」
「疑問に思っただけ」と、オレ。
オレが死に掛けたら、みんなのうちだれが、オレと連絡を取り合って
くれるか、疑問に思った。しかし、死のことを考えたくなかったので、
疑問に思うのはやめた。
それが、マックスとのチェスのゲームに決して戻りたくなかった、本
当の理由だった。オレは臆病だったのだ。
午後のあいだじゅう、オレは、その花束の1ドルに参加したことがう
れしく、その1ドルが、オレの最後のなけなしのカネだったことも、う
れしかった。その1ドルを出したら、夕食と朝食を食べられなくなると
知っていて、そうしたことも、少し誇らしく感じた。
午後のあいだじゅう、つまり、5時にオフィスの終了時間になって、
みんなが帰り始めるまでは。そのとき、オレは急に腹が減って、修行僧
のようなマネは辞めようと、決心した。
ウィロービィ氏に、明日まで1ドル貸してもらえるか訊くと、貸して
くれた。
12
トラブルが始まる前に、みんなはそれを知っていた?もちろん、知ら
ない。ほんとうには、だれも知らなかった。今まで、人間は、ほんとう
には、だれも知らなかった。しかし、オレたちの知識の表面を、引っか
くことはあった。しかし、だれが、そのことに気づいた?
たぶん、ジョージスパーリングだ。彼は、もっとも表だたない、シャ
イで、簡単に見過ごされる。しかし、見過ごされる代わりに、観察して
みよう。彼の防衛力をなくしてしまう、いい機会だ。
そのとき、彼はベッドの中で、妻といっしょだった。しかし、ふたり
に起こるなにかを捜していたわけではなかった。朝の2時少し過ぎで、
3時間は眠っていた。ふたりの間には、1枚のシーツがあった。なぜな
ら、初夏の暖かい湿度の高い夜だったので、ジョージは、上下のショー
ツだけで、シーツの上で眠っていた。妻のエイダは、もっと少なく、事
実上、なにも着てなかった。ナイトガウンが嫌いで、夏は、決して着な
かった。いつも、シーツの下で眠っていた。なぜなら、とてもカゼを引
きやすく、少しでもシーツを引いてしまうと、彼女の裸の体は、すぐカ
ゼを引いてしまうからだった。
ふたりとも、規則正しく息をしていて、そのときは、深く眠っていた。
エイダは、いつもそんなふうに眠っていた。ジョージは、よく寝返りを
打って、長く同じ姿勢でいることは、めったになかった。仰向けで眠っ
てるときは、いつも、いびきをかいていた。しかし、やさしいいびきで、
眠っているエイダを起こしてしまうほどではなかった。彼女が起きてい
るときでも、邪魔するほど大きくはなかった。
ふたりは、この特別なベッドに、4年、いっしょに寝ていた。その前
は、別のベッドに5年。このベッドは、古い鉄製で、一部ペンキで塗ら
れていた。スプリングは使い古され、マットレスは、まぁまぁ、がまん
できた。レース通りにある古いアパートの、ふたりが借りている2DK
の室の、つまらないものだが、ふたりの所有で、残りの家具も、そうだ
った。
建物やその地区は古いものが多かったが、スラム街ではなかった。し
かし、ふたりには、落ちぶれて来たようで、不満だった。安い場所に住
み、カネが無かった。ある種の慰めがあった。
ジョージにとっては、慰めはなかった。
(つづく)