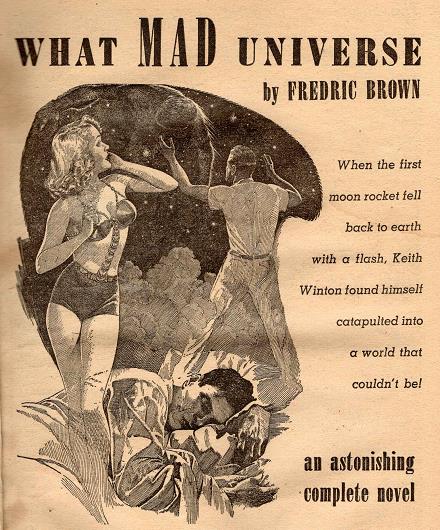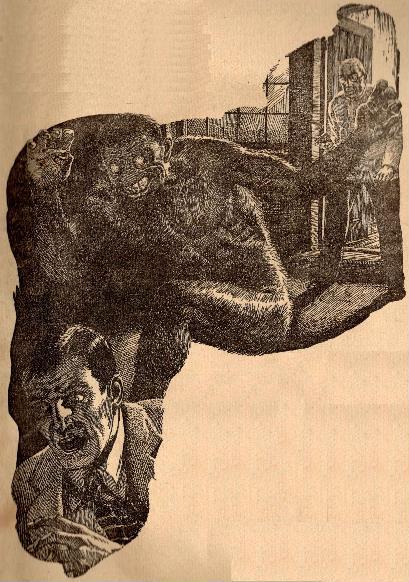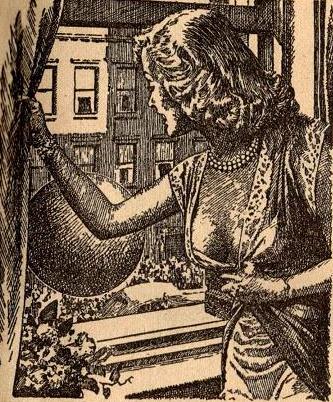ファマドユニヴァース
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
登場人物
ボーデン氏:ボーデン出版社の経営者、広い別荘を所有する。
ケイスウィントン:編集者、サプライジングストーリー担当。
ベティハードレイ:ラブストーリー担当、フェアリー社から移って来る。
マリオンブレイク:速記タイピスト兼受付。
ドッペル:驚くべき青年、27、地球防衛軍の総司令官、メッキー作成。
メッキー:機械知能、テレパシー・テレキネシスが使えて瞬間移動可能。
アルクトゥルス:アルクトゥルス恒星系第3惑星、突然地球へ襲来する。

プロローグ
月へロケットを送る最初の試みは、1954年、操作メカニズムの構
造的欠陥によって失敗した。地球に戻って来ると12人の犠牲者を出し
た。ロケットに爆発物はなかったが、月での着陸を地球から観測するた
め、バートン型分圧モーターが積み込まれ、宇宙を航行しているあいだ
に、とんでもない量の電力を作り出した。月に到達して、それらが放た
れると、稲妻の数千倍明るいフラッシュが発生し、分裂によって、さら
に、その数千倍のフラッシュとなる予定だった。
幸運にも、ロケットは、住宅の少ない、カッツキルの丘陵地帯にある、
雑誌をいくつも出版している裕福な出版人の土地に落下した。
出版人と彼の妻、2人の来客と、8人の召使が、電気的放電により死
亡した。それは、家を完全に破壊し、1マイル四方の木々をなぎ倒した。
発見された死体は11。来客のひとりは、編集者だったが、フラッシュ
の中心近くにいたため、体は完全に分解されたと思われている。
つぎの、最初に成功したロケットは、1955年に送られた。
もくじ
1 フラッシュ
2 紫モンスター
3 見たら殺せ
4 マド・マンハッタン
5 夜歩き
6 暴走ミシン
7 カリストカクテル
8 メッキー
9 ドッペル情報
10 WBIのスレード
11 ジャンプ・ザ・銃
12 スペースガール
13 ジョー
14 宇宙監視官フー
15 月って?
16 アルクトゥルスから来た物体
17 ハックルベリーインフィニティ
18 ロッキーティアばんざい
1 フラッシュ
ケイスウィントンは、テニスの1セットが終わったとき、かなり疲れ
たが、そんな素振りは一切見せなかった。なん年もプレイしてなかった
のに、テニスというものは、今、分かったが、本来、明らかに若者のス
ポーツだった。彼は、どう見ても、年寄りではなかったが、31ともな
れば、いつも体調を管理してない限り、疲れ切ってしまう。ケイスはや
ってなかったにも関わらず、ゲームに勝とうとして本気でがんばってし
まった。
今、また、ネットを飛び越えるほど、がんばろうとしていたのは、向
こう側にいる娘のせいだった。彼は、ハァハァ言いながらも、彼女に笑
顔を送ろうとした。
「もうワンセットできる、時間は?」
ベティハードレイは、金髪の頭を振った。「残念ながら、ない、ケイ
ス。今でも遅れそう。ボーデン氏が運転手に、ニューヨークまで戻るた
めに、グリーンビル空港まで送らせてくれると約束してくれない限り、
もう、長くはいられない。彼は、そのくらいのことはしてくれそう?」
「うむむ」と、ケイス。ボーデン氏のことは、まったく考えてなかった。
「戻らないとだめ?」
「絶対だめ。それは、わたしの母校の同窓会パーティで、スピーチしな
きゃならないし、ラブストーリー雑誌をどう編集するか、話すつもり」
「それなら」と、ケイス。提案した。「SF雑誌の編集について話すと
いい。あるいは、ホラー雑誌とか。ボーデンに、『サプライジングスト
ーリー』に回される前は、『ブルーディングテイルズ』をやっていたん
だ。その仕事は、かつて、オレに悪夢を運んで来た。あんたの同窓生た
ちも、聞きたいはず、どう?」
ベティハードレイは、笑った。「そうね、でも、それは、静かな女だ
けのパーティだから、ビックリするようなことはだめ。明日、オフィス
で会えるわね?これが、世界の終わりでは?」
「そう、ノー」と、ケイス。否定した。彼は、ある意味、間違っていた
が、まだ気づいてなかった。
ベティがテニスコートから、雑誌のボーデンシリーズの出版人である
L・A・ボーデンの夏用の大きな家に向かって歩き出すと、彼も脇をつ
いて歩いた。
彼は言った。「けれど、ほんとうはここにいて、花火を見るべきだと
思う」
「花火?ああ、月ロケットのこと?なにか、見える、ケイス?」
「そう言われている。それについての記事を読んでは?」
「少しだけ、知ってるのは、月に衝突すると稲妻フラッシュのような閃
光を出すということ。それを見ようとしているみんなに、裸眼でも見え
るそう。衝突は、9時15分過ぎだとか?」
「16分過ぎ、見るつもりだったので知ってる。あんたも見る機会があ
れば、月のど真ん中を見てればいい。三日月の角と角のあいだ。なにも
見えないなら、それは新月で、暗い部分にあたる。望遠鏡がなければ、
かすかな小さなフラッシュ、だれかが1ブロック先でマッチを擦ったく
らい、もっと近づいて見なきゃならない」
「爆発ではないらしい、ケイス。フラッシュは、どうして?」
「今までだれも見たことのない規模の、電気的放電。バートン教授の開
発した最新式の装置で、加速の反動を電気的エネルギーに変換する。一
種の静電気のようなもの。ロケットそのものが、巨大なライデン瓶のよ
うになる。真空の宇宙を旅してるあいだ、なにかに衝突するまでは、光
を発することも漏れ出すこともない。衝突が起こると、光は内部にとど
まらない、回線ショートのオンパレードのようになる。巨大稲妻の電圧
の3・4千倍の、地上では見たことのない稲妻フラッシュのようになる」
「複雑に聞こえる、ケイス、爆発させた方が、簡単では?」
「そう、確かに。しかし、核弾頭よりも、もっともっと明るいフラッシ
ュを作れる。学者たちにとって、興味があるのは、爆発そのものでなく、
明るいフラッシュなんだ。もちろん、それは、少し景観を壊すかもしれ
ない、原爆ほどではないにしても、ブロックバスターよりはもっと、し
かし、それは、付随的なこと。それに、フラッシュを、地球の夜の側に
あるすべての大型望遠鏡を通して、スペクトル分析にかけることで、月
の表面の物質の正確な組成を調べられる。さらに」
家の脇のドアに近づいて、ベティハードレイは、手を彼の腕において、
さえぎった。「中断して悪いんだけど、ケイス、急いで行かなくちゃ、
ほんとうに飛行機に遅れそう、バイ!」
彼女は、手を離して行こうとしたが、ケイスウィントンは、代わりに
彼女の肩に手を掛けて、引き寄せ、キスをした。息つく暇もない一瞬だ
ったが、彼女のくちびるは、確かに、彼のくちびるに触れた。それから、
彼女は離れた。
しかし、彼女の目は輝いていた━━━少し霧がかかったように。彼女
は言った。「バイ、ケイス、ニューヨークでまた会う?」
「明日の夜、デートは?」
彼女はうなづいて、家の中へ入って行った。ケイスは、その場に立っ
たまま、ドアポストに寄りかかって、ぼんやりした笑いを浮かべていた。
また、恋に落ちた。しかし、今度は、今までのものとは全く違ったも
のになった。突然で、暴力的だった、まるで、今夜9時16分の月のフ
ラッシュのように。
◇
ベティハードレイを知ったのは、3日前だった。実際、このすばらし
い週末前に、彼女を見たのは、1回だけだった。木曜に、彼女は初めて、
ボーデン社へ来た。彼女が編集していた雑誌『パーフェクトラブストー
リー』を、ボーデン社がシリーズごと買い取ったからだ。ボーデン社が
賢いのは、雑誌シリーズだけでなく、その編集者もいっしょに買い取っ
てしまうことだ。ベティハードレイは、そのシリーズに3年間携わり、
順調に利益を生んでいた。フェアリー社がそのシリーズを売ろうとした
唯一の理由は、ドキュメンタリーのダイジェスト雑誌に転換を図ってい
たからだ。『パーフェクトラブストーリー』は、フィクション雑誌の最
後の生き残りだった。
それで、ケイスは、ベティハードレイに木曜に会って、今、ケイスウ
ィントンにとって、木曜は、彼の人生で、おそらく、もっとも重要な日
になった。
金曜、彼は、フィラデルフィアに、彼の作家のひとりに会いに行った。
その男は、書くことはできるのだが、メインノベルの前払いはもらって
おきながら、なにも書き始めていないようなのだ。ケイスは、プロット
をスタートさせて、うまく書けるように持って行こうとした。
しかし、結局、ジョードッペルバーグには会えず、同じ金曜に、ニュ
ーヨークに戻って、電話するためにボーデン社にいた。ジョードッペル
バーグの手紙から判断すると、実際に彼と会えなかったことは、むしろ、
良かったようだ。
そして、きのう、土曜の午後は、L・A・ボーデンの招待で、ここに
いた。ケイスがここへ来たのは3度目だが、ボスの別荘でのほかの週末
は、ベティハードレイが、ほかの2人の招待客のうちのひとりだと分か
った瞬間、かすんだ記憶となってしまった。
ベティハードレイは、背が高く、しなやかで、金髪だった。ソフトに
日焼けした肌、編集オフィスにいるよりは、テレビスクリーンにいるよ
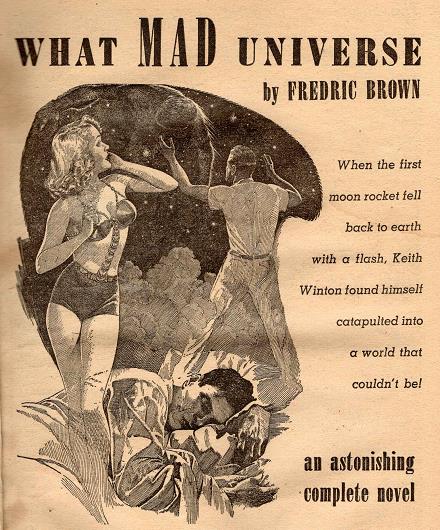
うな顔と容姿をしていた。
どういう経緯で、編集者になんかなったんだろう?
ケイスは、ため息をついてから、家の中へ入った。
ウォルナット材でできた広いリビングルームに、L・A・ボーデンと
会計責任者のウォルターキャラハンがジンラミーをしていた。
ボーデンは顔を上げて、うなづいた。「ハイ、ケイス、このゲームが
終わったら、ここを使いたい?もうすぐ、終わる。オレは手紙を書く用
事があるし、ウォルターもたぶん、すぐに、あんたのカネをオレのもの
にするはず!」
ケイスは頭を振った。「する用事があって、ミスターボーデン、ロケ
ットトークコーナーの原稿を書いてしまわないと、ロケットトークファ
イルを持って来ている」
「ここまで来て、仕事なんてしなくていい。明日、オフィスでやればい
い?」
「そうしたいのだが、ミスターボーデン」と、ケイス。「オレのミスで、
明日の朝、10時ジャストに印刷に回さなくてはならないものが、でき
てない。その締め切りが正午なので、まったく余裕がない。しかし、2
時間で済む仕事なので、今、やってしまって、夜はゆっくりしたい」
彼は、リビングルームを抜けて、階段を上がった。自分の室で、ブリ
ーフケースからタイプライターを取り出すと、デスクに置いた。ロケッ
トトークコーナー宛ての、最近の手紙がファイルされたホルダーも出し
た。
ジョードッペルバーグの手紙は、その一番上にあった。そこに置いた
のは、ジョードッペルバーグは、訪ねて来るかもしれなく、最初に済ま
せたかったからだ。
タイプライターに紙をセットし、タイトルに、ロケットトークコーナ
ーと打った。そして、仕事に入った。
◇
さて、宇宙パイロットのみんな、今夜は━━━つまり、これを書いて
いる夜は、あんたが読んでる夜ではない━━━ビックイベントの夜、ビ
ックリナイトだ、担当者は、外に出て、それを見るつもり。月の影の部
分での光のフラッシュは、人の手によるロケットが、初めて宇宙を旅し
て月に到達した証拠となる。
彼は、書いたものを批判的に見て、紙を引っ張り出すと、新しい紙を
セットした。今のは、ファンに対して、あまりに形式ばって、型にはま
り過ぎていた。タバコに火をつけてから、また、書いた。今度のは、良
くなったか悪くなったか、どちらかだった。
ひと息ついてから、読み返していると、ドアが開いて閉まる音がして、
ハイヒールの靴音が階段を降りて行った。ベティが帰る音だった。立ち
上がってドアまで行ったが、戻って、また、座った。だめだ、ボーデン
もキャラハンもいるところで、今また、グッバイを言ったら、クライマ
ックスが台無しだ。大急ぎの、息もつかせぬキスと明日の夜に会う約束
だけ残して、そのままにしておいた方がいい。
彼は、ため息をついて、一番上の手紙を取り出した。ジョードッペル
バーグは言っていた。
◇
親愛なるロッキーティア様
手紙は書くべきではなかったかもしれない。あんたの最後のコラムは、
後馬の話を除いて、アルクトゥルスをずいぶん刺激している。あんなこ
と言えるのは、ゴームリーくらいしかいない?彼の宇宙ナビで?長身の
東洋人でも、天気のいい日にそんな泥のクリークを手漕ぎボートで渡れ
ない。
それにフーパーの表紙、娘はオーケーで、いいけど、表紙に娘をのせ
ないやつがいるか?しかし、彼女を追うものと言ったら、後馬の話に出
て来る、火星のデビルか?フーパーに言っといてくれ!オレなら、まっ
たくのしらふでも、金星のべたべたするナメクジがなくたって、もっと
怖いベムを描ける。
彼女は、ぐるっと回って、なぜやつを追わないんだ?
中にあるフーパーのさし絵はいい、特に白黒のは、表紙には別のやつ
を雇ったら?ロックウェルケントやダリとか、オレはダリはいいと思う。
ダリのベムはすばらしい。覚えておいて、ダリはすばらしい!
ロッキー、聞いて!天王星の安っぽいジュースを用意しておいて、氷
を入れて、というのは、今週のいつか、訪ねに行くつもり。ロッキー、
ニューヨーク宇宙ポートには迎えに来ないで!そのことでうぬばれない
ように、なぜなら、火星人にオレは会ってシリウスについて聞いたから
だ。オレは町にいるから、あんたがみんなが言うくらい醜かったら会う
つもりだ。
ロッキー、あんたの最近のアイデアは、最高だ!手紙の返信に、半カ
ラムピクセルを使うという、それで、あんたを驚かせようとして、オレ
も手紙を書いている。これを投函するつもりだが、その前に着いてしま
うかもしれない。コラムは、印刷に回す前に、失われてしまうかもしれ
ない。
では、ロッキー、太った月の子牛を殺さないで!すぐにではないが、
そのうち会いに行く!
ジョードッペルバーグ
◇
ケイスウィントンは、また、ため息をついて、ブルーの鉛筆を取った。
ニューヨーク宇宙ポートのところに印を付けた。それは、多くの読者に
は興味がないだろうし、オフィスに忘れて来たアイデアを彼らに与えた
くもなかった。そんなことで時間をムダにしたくなかった。
手紙の別の部分にある、そんなにすれてない部分に、いくつかしるし
を付けた。それから同封されていた写真を手に取って、また、一瞥した。
ジョードッペルバーグは、あの手紙を書くような人物には見えなかっ
た。醜くなく、むしろ知的に見えた。笑顔が似合う、16か17の子ど
もに見えた。たぶん、人間としては、手紙が厚かましいのは、シャイだ
からなのだろう。
確かに、彼は写真映りがいいのかもしれない。それを写真印刷に回す
か迷ったが、それまで、まだ時間はある。原稿に半カラムピクセルを使
用とメモ書きして、写真の裏に1/2カラム ドッペルバーグと書いた。
ジョーの手紙の2ページ目をタイプライターにセットすると、末尾に、
こうタイプした。オーケー、ドッペルバーグ、つぎの表紙は、ロックウ
ェルケントに頼むことにする。あんたが彼に支払って!グラマーな娘に、
昆虫眼モンスター(あんたの言葉では、ベム)を追わせる件に関しては、
それはありえない。ストーリーでは、娘は、いつも追われる立場だから
だ。お分かり、ドッペルバーグ?追うものと追われるもの。それは、あ
んたのダリはすばらしいの半分も悪くはないが。
◇
そのページをタイプライターから取り出すと、サインして、つぎの手
紙に取り掛かった。
6時に終わって、夕食まで、まだ、1時間あった。すぐにシャワーを
浴びて、服を着ても、まだ、30分あった。ぶらぶら下へ降りて行き、
フランス製のドアから外へ出ると、庭園になっていた。ちょうど暗くな
り始めた頃で、晴れ渡った夜空に、すでに新月が上っていた。良く見え
そうだ、と彼は考えた。そして、悩むのは、ロケットフラッシュは、肉
眼で見えてくれないと困る、それがだめなら、ロケットトークコーナー
の新しい章を書き出せなくなってしまう、ということだった。そう、9
時16分まで、時間があった。
彼は、庭園の中央通りの脇の枝編みベンチに腰掛けた。都会から離れ
た田舎の空気を胸いっぱい吸って、周りの花の匂いを嗅いだ。
ベティハードレイのことを考えた。そのことは、ここでは、記録する
必要がなかった。
しかし、考えることは、彼を幸せにした。この幸せとか哀れなといっ
た修飾子は、もっともよく使われる形容詞だ。そのうち、フィラデルフ
ィアにいる小説家のことを考え始め、いつになったら、やつは、ストー
リーに取り掛かって、しっくいで塗り固め始めるのだろう?
また、ベティハードレイのことを考えた。24時間後には、月曜の夜、
ニューヨークで、カッツキルの日曜の夜の代わりが始まるのだ。
腕時計を見ると、あと数分で、夕食のベルが鳴ることが分かった。そ
れは良い知らせで、恋してるにせよ、恋してないにせよ、彼は空腹だっ
た。
空腹は、理由もなく、考えをめぐらせる。『サプライジングストーリ
ー』の表紙のほとんどを描いた、クラウドフーパーのことを考えた。フ
ーパーを表紙の担当にし続けるかどうか。フーパーは、いいやつで、か
なり優秀なアーティストだった。娘を描かせれば、よだれが出そうなの
を描いた。しかし彼女たちを追うモンスターは、じゅうぶん怖ろしいと
は言えなかった。たぶん、彼は、怖ろしい悪夢を見たことがなく、とて
も幸せな家庭環境あるとか、そんなところだ。ファンの多くが抗議して
いた。ドッペルバーグのように。ドッペルバーグは━━━
月ロケットは、地球に戻って来た。音よりも速いスピードで、彼から
2ヤードのところに墜落したが、ケイスは、それを見ることも、聞くこ
ともできなかった。
フラッシュがあった。
2 紫モンスター
次元が転移したり、瞬間移動した感覚も、時間が経過した感覚もなか
った。それは単に、明るいフラッシュと同時に、枝編みベンチを彼の下
から引き抜いたかのようだった。ベンチの背もたれに寄りかかっていた
が、地面にぶつかる衝撃はなかった。うしろに完全にのけぞった姿勢の
まま、水平に横になって、夜空を見上げていた。
もっとも驚くべきことは、空を見ているということだった。枝編みベ
ンチが彼の下で壊れてしまった、あるいは、単に消えてしまったことも
ありえなかったが、ベンチは木の下にあったのに、今、彼とどんよりし
た青い薄暗がりのあいだに、木は1本もなかった。
彼は、頭を先に上げて、それから起き上がった。しばらく頭を、身体
的にでなく、精神的に振った。歩き出す前に、方角の分かる磁石が欲し
かった。
彼は、芝生の上に座っていた。なめらかに刈り取られた芝生で、庭の
中央だった。背後に、頭を回すと、家が見えた。ふつうの家屋で、ボー
デン氏の家のような広くて凝ったデザインでは全くなかった。誰も人は
住んでいないように見えた。少なくとも、生活している跡はなく、どの
窓にも灯りはなかった。ボーデン氏の家がどうなったか捜したが、見つ
からなかった。数秒して、別の方向を向いた。その方向100フィート
先に、そこは彼が座っている芝生の端だが、垣根があった。垣根の向こ
う側は木々が、2列にきちんと並んで立っていた、まるで、道路の両脇
であるかのように。木々は、高い木で、とても美しいポプラだった。
カエデの木はなかった。彼がさっきまで座っていたのは、カエデの木
の下だった。見える限り、どこにもなかった。枝編みベンチのかけらも
なかった。
頭をはっきりさせるために振ると、警戒しながら、立ち上がった。一
瞬めまいがしたが、それが収まると、大丈夫だった。なにが起こったに
せよ、ケガはなかった。めまいが収まるまで、静かに立っていた。それ
から、垣根の門へ向かって、歩き出した。
腕時計を見た。7時3分だったが、それは、あり得ない、と彼は考え
た。ボーデン氏の庭で、ベンチに座っていたのも、ちょうど7時3分だ
った。今いる場所がどこにせよ、一瞬でここへ来ることはできない。
腕時計を耳にあててみた。ちゃんとチックタック言っていた。しかし、
それは、なにも証明してない。それは、止まったのかもしれない。なに
が起こったにせよ、そのあと、彼が立ち上がって、歩き出したとき、ふ
たたび動き出したのだ。
時間の経過を調べるために、空を、また、見上げた。経過は分からな
かった。前も薄暗かったが、今も薄暗かった。銀色の新月は、同じ位置
にあった。少なくとも、天頂から同じ距離だった。ここでは、ここがど
こであるにせよ、彼の方角と方向感覚について、確かなことは何も言え
なかった。
垣根を抜けると、道は、舗装された片側3車線の高速道路へと続いて
いた。ここから、車は1台も見えなかった。
垣根の門を閉めて、ふたたび、背後の家を見た。そのとき、前は気づ
かなかったなにかが見えた。玄関の柱の1つに、看板があった。こう書
かれていた。
『売り物、R・ブレイスデル、グリーンビル、NY』
それなら、彼は、まだ、ボーデン氏の敷地の近くにいるに違いない。
グリーンビルは、ボーデン氏のところから最も近い町だった。しかし、
それは、もともとそうだった。遠くまで来るはずなかった。ほんとうの
疑問は、ほんの数分前に座っていた場所から、そこが肉眼では見えない
ところまで、どうやって来たかだ。
頭は大丈夫そうだったが、また、クリアにするために振った。突然の
記憶喪失になったのか?気づかぬうちに、ここまで歩いて来たのか?そ
れもあり得ないように思えた。特に数分の間には、あり得なかった。
彼は、どの道を歩こうか迷いながら、高いポプラの木の間から、広い
アスファルトの道路が上ってまた下るのを眺めた。道路は、まっすぐ走
っていた。ほとんど1/4マイルが見えた、つぎの上りまで、どちらの
方向にも、しかし、人間が住んでる跡はなかった。だが、この近くのど
こかに、農家があるはずだった。手入れされた牧草地が、ポプラの木の
列の、はるかかなたまで続いていたからだ。たぶん、木々が邪魔になっ
て、近くにあるはずの農家が見えないのだ。牧草地と道路を分けている
垣根まで歩けば、それが見えるはずだ。
◇
道路を半分横切ると、まだ、視界の外だったが、左の上りの向こうか
ら、近づいて来る車の音が聞こえた。この距離から聞こえるのは、とて
も騒々しい車だった。道路を渡り切って振り返ると、車が見えた。その
車の運転手の服装からして、農家の服装だった。それは好都合で、うま
く説得すれば、ボーデン氏のところまで乗せてくれるだろう。少なくと
も、その方向に行くなら。
車は、旧式のモデルTだった。たまたま、彼は知っていた。大学時代
にヒッチハイクをした経験から、車に乗せてくれる可能性は、運転手の
年令と車の古さに比例することを知っていた。
この車の古さは、疑いもなかった。登り坂に苦労して、ぷすぷすと音
を立てた。
ケイスは、近づくまで待って、道路に出て、手を振った。フォードは
速度を落とし、彼の前で停まった。
車の男は、前かがみになって、ケイス側の窓をあけた。窓にガラスは
なかった。ケイスは何気なく見た。「乗るかい、ミスター?」と、彼。
彼は、ケイスには、とても農民らしく見えた。髪の毛の色のような長
い黄のストローをかんでいて、彼のかすんだ青の目のような、かすんだ
青の作業着を着ていた。
ケイスは、踏み台に足を掛けて、あいた窓から車の方にかがんで、エ
ンジン音や車が停まってから車体のあらゆる部分が、がたがた言い出し
た音に負けずに大声で言った。
「道に迷って困っている。LAボーデン氏の家は、分かる?」
農民は、ストローを口の逆側に移動させて、よく考えつつ、努めて顔
をしかめた。
「いんや」と、彼。やっと答えた。「聞いたことねぇ。このあたりの農
家じゃねぇ。道の向こうだろう。あっちの方まで知っちゃいねぇ」
「農家じゃない」と、ケイス。説明した。「大きな別荘で、彼は雑誌社
のオーナー。この道はどこへ?グリーンビル?」
「そうじゃ、あっちへ、オレも行くところ、10マイルぐらい。後ろへ
行けば、カルテレットでアルバニーハイウェイに出る。グリーンビルへ
行く?そこへ行けば、ボーデン氏の住所も分かるじゃろう」
「たしかに」と、ケイス。「サンクス」彼は、車に乗り込んだ。
農民は、おごそかに彼の前に手を伸ばすと、取っ手を回して、ガラス
のない窓を閉めた。「がたがた言うのさ」と、彼は説明した。「あけた
ままにしておくと」
クラッチペダルを踏んで、ギアを入れると、車はうなりを上げて走り
出した。車体のがたがたは、ブリキの屋根にヒョウが降っているような
音がした。車は、トップスピードに達した。ケイスは、車がこのまま進
めば、10マイル先の目的地に、30分かかるだろうと試算した。
なにはともかく、グリーンビルに着ければ、少なくとも自分のいると
ころが分かる。夕食にかなり遅れているから、と彼は考えた、ボーデン
に電話して、彼を安心させてから、町で食事して、それからタクシーを
拾うか、なんらかの車で、別荘まで運んでもらえばいい。遅くとも、9
時には戻れるから、16分過ぎからの月の花火を見る準備をするのに、
かなり時間がある。そこには、彼が見逃したくないなにかがあった。
ボーデン氏には、なんて説明しよう?言えることは、散歩をしていて、
道に迷い、車に乗せてもらい、自分の居場所を知るために、グリーンビ
ルへ行った。その言い訳は、バカらしく聞こえた。真実としては、そん
なにバカらしくはないが。そして、上司には、彼が正気でないとか記憶
喪失にかかったとは思われたくなかった。
ぷすぷすと音を立てながら、古い車は、長い直線道路を走った。彼の
恩人は、おしゃべりが嫌いらしく、ケイスにはありがたかった。互いに
すでにエールを送り合ったのだから、考える時間が欲しかった。なにが
起こったのか知るために。
ボーデン氏の別荘は、広くて大きいので、近所の人たちには良く知ら
れていた。旧式のボロ車の運転手は、道路沿いのみんなを知っているな
ら、ボーデンの別荘のことを、そこが閉鎖されていたとしても、聞いた
ことがないのはあり得なかった。それが20マイル以上離れていること
も、あり得なかった。なぜなら、ボーデンは、グリーンビルから10マ
イルのところに住んでいて、ケイスは、町からどの方角にいるのか分か
らなかったが、道路沿いで車に乗った場所が、やはり、グリーンビルか
ら10マイルのところだった。その2つの10マイルの地点が、直径で
見て、ちょうど逆側だったとしても、20マイル以上離れていることは
あり得なかった。その距離でさえ、時間的ロスがほとんどゼロだったこ
とを考えると、あり得なかった。
車は、町のはずれに来て、彼は腕時計をまた見た。7時35分だった。
彼は、どこか店の窓に時計が見えるまで、車の窓からビル群を眺めてい
た。彼の時計は正しかった。止まって、また動き出したのではなかった。
数分後、車は、グリーンビルのビジネス中心地区に着いた。運転手は、
カーブを曲がって停めてから、言った。「町の中心地さ、ミスター。電
話帳で仲間の場所を見つけられるはず、それであんたもオーケーじゃ。
タクシー乗り場もあるから、どこへでも行きたいところへ行ける。料金
はおったまげじゃが、どこでも好きなところへ行ける」
「いろいろサンクス」と、ケイス。「電話する前に1杯どう?」
「いんや、ノーサンクス。馬が子どもを産みそうなんじゃ。弟を拾いに
来た、やつは獣医じゃから、急いで乗せないと」
◇
ケイスは、またサンクスを言って、車を降りた場所からすぐの角にあ
るドラッグストアへ入った。裏の電話ボックスで、ブースからチェーン
に吊るされた薄い電話帳を手に取った。それをめくって、『ボ』の項目
を捜し━━━
ボーデンの名前は、どこにもなかった。
ケイスは、顔をしかめた。ボーデンの電話は、グリーンビル交換台の
ナンバーだった。仕事でニューヨークのオフィスから、なんども電話し
てるから、それは確かだった。
しかしもちろん、その番号を、電話帳に載せてないことはあり得る。
それを覚えている?もちろん、3桁ですべて1だった、グリーンビル1
11。ボーデンは、覚えやすいようにその番号を、電話局からコネで得
たのではないかと疑ったことを覚えている。
ブースのドアを閉めて、ポケットの小銭入れからニッケル硬貨を取り
出した。しかし、電話は、今まで見たことのないタイプだった。硬貨の
投入口がなかった。まわりをすべて調べてから、こう結論付けた。ちょ
っとハイカラな町では、もう、硬貨電話はなくなって、料金は、あとで、
ドラッグストアの店主に払うのだろう。
受話器を取り上げると、「番号を、どうぞ」と、交換手の声。番号を
告げると、1分の間。それから、交換手の声が電話線を通じて返って来
た。「その番号はリストにない、サー」
一瞬、ケイスは、自分がどうかしてしまったのではないかと疑った。
その番号を間違えるはずはなかった。グリーンビル111、あんたは、
そのような番号を忘れたり、間違って覚えたりはしないだろう。
彼は、訊いた。「それなら、LAボーデンの電話番号は?その番号の
はずだが、電話帳には載ってなかった。電話があることは確かで、なん
ども電話している」
「ちょっと待って、サー━━━いいえ、記録には、その名前はない」
「サンクス」と、ケイス。受話器を戻した。
彼は、まだ、それが信じられなかった。ブースの外は少し明るかった
ので、チェーンを伸ばせるだけ伸ばして、電話帳を外でひらいた。『ボ』
の下を見て行って、やはり、ボーデンの名前はなかった。ボーデンが別
荘を、フォーオークスと呼んでいたのを思い出して、その下を捜したが、
フォーオークスもなかった。
突然、彼は電話帳を、ピシャっと閉じると、表紙を見た。グリーンビ
ル、NYとあった。一瞬、間違ったグリーンビルにいる気がした。しか
し、ニューヨークには、グリーンビルは1つしかなかった。もうひとつ
の、もっとかすかな疑いは、表紙の町の名前の下に、小さく『1954
年春』とあるのを見て、消えた。
LAボーデンが電話帳にないことが、まだ信じられず、名前が『あい
うえお』順でないかもしれない、1ページ、1ページ捜して行こうとす
る衝動と戦わなければならなかった。
◇
代わりに、ソーダカウンターまで歩いて行って、旧式の足が広がるタ
イプのスツールに座った。カウンターの向こうの店主は、背の低いグレ
ーの髪の男で、分厚いレンズのメガネをしていた、グラスを磨いていて、
顔を上げた。「イエス、サー?」
「コークを」と、ケイス。質問をしたかったが、なにを聞いたらいいの
か思い付かなかった。店主がコークを混ぜて、彼の前のカウンターに置
くのを見ていた。
「外は、いい夜」と、店主。
ケイスは、うなづいた。それが、彼に、月ロケットのフラッシュを、
その時間にどこにいようとも、見なければならないことを思い出させた。
腕時計を見た。8時になるところだった。あと1時間と15分後には、
月が見える外のクリアな場所にいなければならなかった。今は、その時
間までにボーデンのところへ戻れそうになかった。
彼は、コークを、ほとんどひと口で飲み干した。冷たくて、うまかっ
た。それが、空腹であることを思い出させた。8時なら驚くことはない。
ディナーは、ボーデンのところでは、もう、終わっているだろう。その
上、昼のランチは軽く済ませてから、ずっとテニスをやっていた。
ソーダ噴水ディスプレイのうしろで、店主がサンドイッチかなにか軽
い食事を用意している跡を捜したが、見たところ、それはなかった。
ケイスは、ポケットから25セント硬貨を出すと、それをソーダ噴水
の大理石の上に置いた。
ガシャンという音がして、店主が磨いていたグラスを落とした。店主
は、分厚いレンズの奥の目を見開いて、怖がった。彼は、そこに立った
まま体を硬直させ、頭を後ろから前へ回転させ、店の一方の端から端へ
見渡した。グラスを落として割ったことは、気にしてないか気づいてな
いように見えた。タオルも、彼の指から落ちた。
それから、彼は、手を慎重に伸ばして、硬貨をおおい、拾いあげた。
ふたたび、両方向を見て、店内にいるのは、自分とケイスだけなのを確
認した。
それから、やっと、硬貨を見た。両手でカップ状にシールドした深い
底にある硬貨を、目を近づけて見た。それをひっくり返して、裏側も観
察した。
彼の目は、驚きながらもうっとりしつつ、ケイスを見た。
「美しい!」と、彼。「まったくすり減ってない。しかも、製造は、1
928年」声は、ささやきに変わった。「しかし、だれが送って来た?」
ケイスは目を閉じて、また、開いた。彼か店主、どちらかが、どうか
してるに違いない。彼は、別の可能性、ある場所から別の場所へ、突然、
瞬間移動が起きて、LAボーデンが電話帳から消えたり、電話会社の記
録からも消えてしまったということは、考えなかった。
「だれが送って来た?」と、店主。ふたたび、訊いた。
「だれからも」と、ケイス。
背の低い店主は、ゆっくり笑った。「言いたくないらしい。Kに違い
ない。違ってても、気にしないで!オレの言い値は、それに、1000
クレジット出す!」
ケイスは黙っていた。
「1500」と、店主。彼の目は、とケイスは考えた、スパニエルみた
いだ。空腹のスパニエルの目が、骨を見つけて、跳びついたところ。
店主は、深く息をついた。彼は言った。「それなら、2000、それ
よりもっと価値があることは知ってるが、出せるのはそこまで、オレの
ワイフが━━━」
「いいだろう」と、ケイス。
硬貨をつかんでいた手は、店主のポケットへ、まるでプレーリードッ
グが穴へ飛び込むように、飛び込んだ。グラスの破片を踏んで割れる音
がしても気にもせず、店主は、カウンターの端のキャッシュレジスター
に行くと、キーを打った。ガラスの窓に、『準備中』が掲示された。店
主は、また割れたグラスを踏みながら、戻って来ると、札束を数えるの
に夢中だった。
「2000」と、彼。「これが意味するのは、今年予定している休暇の
一部をあきらめなきゃならないということ。しかし、それだけの価値は
ある。オレは、ちょっとイカれたようだ!」
ケイスは、札束を持ち上げて、一番上の1枚をよく見た。真ん中に見
慣れたジョージワシントンの肖像画があった。隅の数字は、100、ワ
シントンの長円形の肖像画の下に、100クレジットと書かれていた。
これはバカげている、とケイスは考えた、ワシントンの画は、ここでは
事情が異なるのでなければ、1ドル紙幣専用だ。
ここ?ここは、なにを意味する?これは、緑の紙幣で、ニューヨーク、
USA、1954年。電話帳もそうだった。ジョージワシントンの画も
そうだった。
もう一度よく見て、印刷をもっと読んだ。アメリカ合衆国、連邦準備
紙幣。
それは、新札でなかった。すり減るほど流通していた本物だった。馴
染みのある細いシルクの糸が見えた。シリアル番号は青のインク。画の
右に、1945年発行、大蔵省秘書官というきれいなタイプの上に、サ
インのコピー、フレッドMビンセン。
ゆっくりと、ケイスは薄い札束を2つに折って、コートのポケットに
入れた。
顔を上げると、店主と目が合った。厚いレンズの奥から、心配そうに
彼を見ていた。
店主の声は、目と同じくらい心配そうだった。彼は言った。「大丈夫
かい?あんた、当局の者じゃないよね?つまり、もしそうなら、すでに
オレに収集の疑いを持った。いつでもオレを逮捕できるし、それで終わ
らせてくれ!つまり、オレはチャンスをもらって、それを逃したら、疑
いのままオレを放っておくのはおかしいだろ?」
「いや」と、ケイス。「大丈夫だ。そう思う。コークのお代わり!」
今度は、少しして、店主が大理石カウンターにグラスを置くと、コー
クは滑り出て来た。また、店主の靴がグラスの破片を踏んだので、彼は
済まなさそうにケイスに笑い、隅からほうきを出してきて、カウンター
の後ろを掃き始めた。
ケイスは、コークをすすりながら考えた。頭の中のことを、事象のつ
むじ風と呼ぶかどうか。それは、おもちゃの風車に乗るようなもんだ。
店主がそうじを終えるまで、見ていた。
「聞いて!」と、彼。「いくつか訊きたい、あんたが変に思うかもしれ
ないようなことを。訊く訳は、ちゃんとある。それらに答えてくれる、
どんなに変に思っても?」
店主は、慎重に、彼を見た。「どんな質問?」彼は知りたがった。
「そう、じゃ、今日の正確な日付けは?」
「1954年6月10日」
「AD?」
店主の目は大きくなったが、答えた。「確かに、AD」
「ここは、ニューヨーク州のグリーンビル?」
「イエス、あんたが知りたいのは━━━」
ケイスは言った。「オレが訊く。州に2つグリーンビルはない?」
「オレの知る限りない」
「この近くに広大な別荘を持っている、雑誌社のオーナーのLAボーデ
ンという男を知らない?」
「知らない。このあたりの、すべての人を知ってるわけでない」
「彼が出版している、雑誌のボーデンシリーズを知らない?」
「そう、それなら、売っている。今日、何冊か、新しいのが入った。7
月号が、そこのスタンドに置いてある」
「あと、月ロケット。今夜は、着陸する?」
店主は、混乱して、まゆにしわを寄せた。「言ってる意味が分からな
い。今夜は、着陸する?毎晩、着陸している。今では、ふつうだ。毎分、
お客を迎えるし、中には、ホテルへ泊まるのもいる」
答えは、その質問までは、そんなに悪くはなかった。ケイスは、目を
閉じて、数秒間、閉じたままにしていた。目をあけると、背の低い店主
は、まだ、そこにいて、彼を心配そうに、のぞき込んでいた。
「あんた、大丈夫か?」と、店主。「つまり、病気かなにかでは?」
「オレは、大丈夫」と、ケイス。自分がほんとうのことを言ってると願
った。もっと訊きたかったが、それも怖くなった。なにか、安心させて
くれるものが欲しかった。それがなにか分かった気がした。
スツールを降りて、マガジンラックへ歩いて行った。最初に、『パー
フェクトラブストーリー』を見つけて、手に取った。表紙の娘は、編集
者のベティハードレイを思い出させた。ただ、ベティほどは美人ではな
かった。編集者が、表紙の娘よりも美しい雑誌って、いくつあるのだろ
う?たぶん、1つだけだ。
しかし、ベティの夢を見ている場合でなかった。心から、彼女を断固
として追い出した。自分の雑誌の『サプライジングストーリー』を捜し
た。見つけて、手に取った。
7月号の馴染みのある表紙、まったく同じ━━━
では、ない?表紙の絵は、まったく同じシーンだった。しかし、アー
ト作品に、わずかな違いがあった。もっと良くなっていた。鮮やかさが
増した。フーパーの作品だったが、フーパーが高度なレッスンを受けた
ように見えた。表紙の娘は、透明な宇宙服に身を包み、表紙絵の校正で
見た時よりも、もっと美しくなっていた、ずっとセクシーになっていた。
さらに、彼女を追うモンスターは━━━
ケイスは、身震いした。
全体的な構成は、同じモンスターだが、微妙な違い、怖ろしい違いが
あった。それに指を触れられなかった。指を触れたいとは思わなかった。
石綿手袋をはめていてもイヤだった。
フーパーのサインがそこにあった。モンスターから、目を離すことが
できて、やっと気づいた。Hが小さく湾曲して特徴的なサインが、彼の
作品のすべてにあった。
それから、下の右端に、ロゴで値段があった。それは、20cでなか
った。
2crだった。
2クレジット?
ほかにあり得る?
ゆっくりと、慎重に、彼は2冊の信じられない雑誌を、さっき『パー
フェクトラブストーリー』も2crだと確認した、丸めて、ポケットに
入れた。
ひとりでどこかへ行って、気違いじみた群衆を離れて、この2冊の雑
誌を、一語一語、ゆっくり堪能したかった。
しかし、まず、2冊の支払いをして、それから、ここを出た。それぞ
れ2クレジットなら、2冊で4クレジット。しかし、4クレジットって、
いくら?店主は、25セント硬貨に、2000クレジット払った。しか
し、これはほんとうの基準でない気がした。25セント硬貨は、なんら
かの理由で、彼からそれを買った男にとって、希少で、高価な対象だっ
た。
そう、雑誌は、いい基準になる。それらの価値が、近似的に、クレジ
ットでもドルでも同じならば、2クレジットは、少なくとも、大雑把に、
20セントに一致する。そして、それが正しいなら、店主は、彼に、少
し計算すれば分かるが、25セント硬貨に対して、200ドル支払った
ことになる。なぜ?
ソーダカウンターに戻ったとき、ポケットの小銭入れを、ガチャガチ
ャ言わせていた。手で硬貨の中から、50セント硬貨を見つけた。店主
は、これを見せたら、どんな反応を?
彼は、そんなことをすべきじゃなかった。もっと、注意すべきだった。
しかし、彼の雑誌の表紙が、似て非なるものだったショックが、彼を少
しハイにさせていた。
なに気なく、50セント硬貨を大理石のカウンターへ投げた。「雑誌
を2冊分」と、彼。「それと、あんたが作ってくれたコーク2杯分」
店主は、硬貨に手を伸ばした。手がひどく震えたので、硬貨の縁をつ
かめなかった。
突然、ケイスは自分を恥じた。そんなことすべきじゃなかった。さら
に、そのことが、早くここを出て、雑誌を読みたいという、しゃべりに
つながった。
彼は、無愛想に言った。「取っておいて!25セントと50セント硬
貨どちらも、その代金として!」彼は、さっと振り返ると、店の外へ急
ごうとした。
走り出そうとして、それで止まった。
1歩踏み出して、凍った。なにかが、ドラッグストアのあいたドアか
ら向かって来た。なにかは人間ではなかった。ずっとずっと人間からは
離れていた。
なにかは、背丈が、7フィートをゆうに越えていて、ドアは身をかが
めないと通れず、手と足と顔を除いて、全身が、明るい紫の毛皮におお
われていた。その部分は、やはり、紫だったが、毛皮の代わりに鱗でお
おわれていた。目は、平たい白ディスクで、瞳孔がなかった。鼻はなく、
歯はあった。多くの歯を持っていた。
ケイスが凍ったように、立ちつくしていると、背後から手で腕をつか
まれた。店主の声が、突然、荒々しく、金切り声で、叫んだ。「194
3年製の硬貨!やつは、1943年製の硬貨をくれた!やつは、アルク
トゥルスのスパイだ!やつを捕まえろ、ルナン!やつを殺せ!」
紫のものは、ドアを入ったところで、一度止まった。今、金切り声を
出したが、ピッチがほとんど超音波だった。太い紫の腕を広げると、8
フィートあった。ケイスには、ガルガンチュアに襲われた悪夢を見てい
るみたいだった。紫の口から、2インチはある
牙が出ていて、口をひら
くと、緑の
洞窟だった。
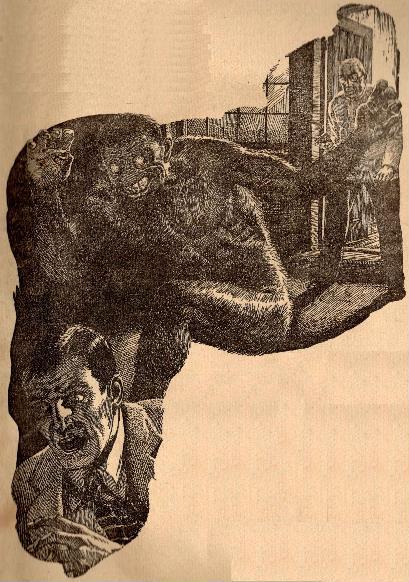
店主は、「殺せ!殺せ!ルナン!」と叫びながら、ケイスの背中に這
い上がろうとした。手はケイスの喉に掛かって、窒息させようとした。
しかし、ケイスは、前から来るものを見て、店主のことは気にもせず、
振り返って、別の方向へ走り出し、店主を振り払って、裏のドアから逃
げた。店の裏にドアがあったことは知らなかったが、あったに違いない。
ドアは、1つにすべきだった。
3 見たら殺せ
ドアはあった。
ドアを通るときに、なにかが背中にツメを立てた。引っ張って逃れた
が、コートが裂ける音がした。ドアをバタンと閉めると、苦痛の叫び声
が聞こえた。人間ではないものが、背後に迫っていた。だが、謝ろうと
して振り返りもせず、走った。
半ブロック先に行くまで、振り返らなかった。背後で拳銃の音がして、
突然、痛みを感じた。まるで、真っ赤な引掻き棒が、腕をかすめたかの
ように。
そのとき、1秒だけ、後ろを振り返った。紫のモンスターは、まだ、
追って来ていた。今出て来た、裏のドアとケイスまでの中間あたりにい
た。長い足にもかかわらぜ、モンスターはゆっくりと不格好にしか走れ
なかった。明らかに、簡単においてけぼりを食わせられた。
紫のモンスターは、武器を持ってなかった。ケイスの肩を焦がした弾
丸は、背の低い店主が撃ったものだった。手に、旧式の大きなリボルバ
ーを持って、引き金に指を掛けて、こちらを狙っていた。
2つのビルの間に飛び込んだとき、また、銃声がした。弾丸は、彼に
当たることなく、過ぎて行った。
ビルとビルの間で、袋小路にはまったのではないかと、一瞬、心配に
なった。突き当りは、なにもないレンガの壁だった。高すぎて、登れな
かった。しかし、そこまで行くと、両側のビルに、それぞれドアがあっ
た。1つのドアは、半分、開いていた。閉じてるドアには触れもせず、
急いで、開いてるドアに入り、閉めて、後ろ手に鍵を掛けた。
廊下の薄暗がりに立って、ハァハァ言いながら、まわりを見た。通り
側には、上り階段があった。他方には、また、ドアがあり、明らかに、
路地へ通じていた。
突然、彼が今、入って来たドアを叩く音がして、興奮した声が聞こえ
た。
ケイスは、後ろのドアへ走って、そこを通って、路地へ出た。ビルの
間を走って、正面に、つぎの通りが見えた。歩道に近づくとペースを落
とし、ふつうのペースで歩いた。
メインストリートに出られそうな方向へ向かったが、あと半ブロック
のところでためらった。かなり混んでいて、人が多かった。
人ごみの中は、安全なのか、危険なのか?彼は、角から10歩あまり
先の木の影に立って、見ていた。
一瞬、ふつうの小さな町の、ふつうのメインストリートの人混みを見
ている気がした。そのとき、手に手を取って、2頭の紫モンスターが通
り過ぎた。どちらも、ドラッグストアで彼を襲ったやつより、少し大き
かった。
モンスターは、十分、奇妙だったが、もっと奇妙なことがあった。彼
らの前後を歩く人々が、まったく注意を払わなかったことだ。彼らが、
どんな姿をしていても、受け入れられていた。彼らは、ふつうで、ここ
に、受け入れられていた。
ここ?
また、あの言葉だ。ここは、どこ?なに?いつ?
SF雑誌の表紙から、いやらしい目つきで、こっちを見ている最悪の
ベムよりもっと怖ろしいエイリアンが、許されている、ここは、なんと
ファマドユニヴァースであることか!
25セント硬貨に200ドル払ったくせに、50セント硬貨を見せた
だけ彼を殺そうとした、ここは、なんとファマドユニヴァースであるこ
とか!だが、それらクレジット紙幣の肖像画はジョージワシントン、今
日の日付も今、そしてラッキーなことに、ポケットには、丸めた、少し
違う、今月号の『パーフェクトラブストーリー』と『サプライジングス
トーリー』が、まだ、入っていた。
ぜんそく気味のモデルTフォードの世界って、宇宙旅行?
宇宙旅行は、あるに違いない。あの紫のものには、地球上では決して
進化し得ない━━━ここが、地球として。そして、店主に、月ロケット
のことを訊くと、「毎晩、着陸している」と、言った。
それから、店主が紫のものに彼を攻撃させる前に叫んでいたのは、
「やつは、アルクトゥルスのスパイだ!」しかし、それはバカらしい。
まだ、モデルTフォードを使っている技術が、月への旅行は完成できて
も、アルクトゥルスへは無理だ。その言葉を、誤解しているのでは?
また、店主は、モンスターを、ルナンと呼んでいた。正式な名前なの
か、あるいは、ルナの住人を指すニックネーム?つまり、月の住人?
「毎晩、着陸している」と、店主は言った。「今では、ふつうだ。毎分、
お客を迎える」
明るい紫の7フィートの背丈のお客?
急に、ケイスは、肩をケガしていたことを思い出した。上腕がヒリヒ
リして、刺すような痛みがあった。見ると、スポーツジャケットの裾に、
血が溜まっていた。血は、薄暗がりで見ると、赤よりは黒に近かった。
服は、弾丸を通ったところが裂けて、溝ができていた。
出血を止めるために、傷の処置をする必要があった。
警官を捜したが、歩いてなかった。(ここに警官はいる?)あきらめ
て、ほんとうのことを言う?
ほんとうのことって?
彼が、ほんとうのことを言うなら、こうなる。「あんたたちは、みん
な、間違ってる!ここは、USA、地球、グリーンビル、ニューヨーク、
6月、1954年、そう━━━しかし、今夜これから、着陸する実験的
なロケットを除いて、まだ、宇宙旅行はない。ドルが通貨で、クレジッ
トじゃない。いくらそこに、フレッドMビンセンのサインがあろうとも、
ワシントンの肖像画があろうとも━━━そして、あの紫のモンスターが
メインストリートを歩いているなんて、ここではあり得ない。LAボー
デンという名前の男が、あんたの方がオレよりずっとうまく彼を見つけ
られる━━━オレが誰かを説明してくれる。そう、望む」
不可能だ、もちろん。彼が見たり聞いたもの、それを信じられるのは、
ここには、たったひとりしかいない。名前は、ケイスウィントン、彼は、
自分から、一番近くの病院に入ろうとする。
いや、だめだ。彼は、まだ、医師に、まったく信じられないストーリ
ーをしゃべりに行けない。まだ、だめだ、とにかく。なにが起こってい
て、ここがどこなのか、それをもっとよく知るには、もう少し時間がい
る。
どこかで、数ブロック先、サイレンが聞こえて来た。やつらは、近づ
いて来た。
サイレンが意味するものが、ここでも同じなら、ずっと馴染みのある
宇宙で、警察の車で、彼を追って来ているのだろう。
コートに血がある事実から、ほかに理由がなければ、メインストリー
トは通らないと決心した。急いで、静かな脇道へそれた。もう一つの路
地を抜けて、できるだけ影に沿って、メインストリートまで数ブロック
を維持した。
緊急車両が、サイレンを鳴らしながら角をまわったとき、彼は、別の
路地の影に身を隠した。
それは、通り過ぎて行った。
彼らは、彼を捜しているのかもしれないし、そうでないのかもしれな
いが、リスクはあえて犯さない方がいい。彼は、どこかホテルを捜さね
ばならなかった。裾に血があることを、長い間、気づかなかった。今、
思い出した。コートの背中も、紫モンスターに引き裂かれていた。
通りの向こうに、『空室あり』という看板があった。室を借りられる
のか、やってみるべきだろうか?肘を伝って血が流れている感覚は、そ
うすべきだと言っていた。
誰も来ないのを確認してから、通りを渡った。看板のあるビルは、貸
家と安ホテルの中間のように見えた。舗道に接した、レンガ造りのビル
だった。彼は、ドアのガラスを通して、中を見た。
小さなロビーのデスクに、事務員はいなかった。デスクの隅に押しボ
タンがあって、『用があれば押して!』と紙に書かれていた。彼は、ド
アをできるだけ静かにあけて、同じように、閉めた。デスクにつま先立
ちで行くと、後ろの書棚を調べた。箱の列があり、中には郵便や鍵が入
っていた。
慎重に、周りを見て、デスクに寄りかかり、一番近くの箱を取り出し
た。201号室だった。
また、周りを見た。誰も見てる者はいなかった。
階段まで、つま先立ちで行った。階段はカーペットが敷かれ、きしみ
音はしなかった。もっといい室の鍵は取って来れなかった。201号室
は、階段のすぐ隣だった。
室に入ると、鍵を掛けて、明かりをつけた。201号室の住人が、3
0分、帰って来なければ、チャンスはある。
コートとシャツを脱ぐと、傷を調べた。まだ痛むが、感染しなければ、
危険はなかった。傷は、かなり深かったが、出血は、すでに弱まりつつ
あった。
201号室の住人はシャツを持っていることは、ドレッサーの引き出
しを捜して明らかだった━━━幸運にも、彼のサイズと0・5サイズ違
うだけだった━━━それから、今、脱いだばかりのシャツを引き裂いて、
包帯として使って、腕をぐるぐる巻きにして、出血があってもゆっくり
ひたるようにした。
それから、ドレッサーから暗いブルーのシャツを見つけて、自分のが
白だったので逆に暗い色にして、ラック棚からネクタイも見つけた。
クローセットを捜すと、3着のスーツが吊るされていた。自分の明る
い茶のスーツと逆に、暗いオックスフォードブルーのスーツを選んだ、
コートは、どうしようもなく引き裂かれ、血が染み込んでいた。クロー
セットには、ストローハットもあった。最初、大き過ぎる気がしたが、
紙を丸めて、汗止めバンドに敷くと、ちょうどよかった。完全に服を変
え、ハットも被って━━━前はハットがなかった━━━店主に、遠くの
通りから見つけられる心配がなくなった。そして、警察は、破れた茶の
スーツの男を捜すだろう。店主は、そのコートの破れを見逃さないだろ
う。
彼が取ったものの価値を、すばやく計算し、換算して、500クレジ
ットを机の上に置いた。50ドルあれば余るだろう。スーツが主な値段
で、高くも新しくもない。
自分の服は、包帯として、クローセットにあった新聞も巻いた。彼が
どれほど読みたかったか知れない新聞、どんなに古かろうが、ここを出
て、安全な場所に行ったら、真っ先に読もう!ここでは、室の住人がい
つ帰って来るか分からない。
ドアをあけて、耳を澄ました。階下の小さなロビーからは、なにも聞
こえて来なかった。彼は、来るときと同じに、できるだけ音がしないよ
うに、降りて行った。
ロビーで、今、ベルを鳴らして、ふつうに室を借りようか迷った。だ
めだ、と彼は決めた。ここでは、だめだ。事務員は、彼が、オックスフ
ォードブルーのスーツやストローハットを着けて、包帯の束を運んでい
ることに気づくだろうし、夜になって、そうした衣類の持ち主が帰って
来て、なにがなくなったかを事務員に話せば、彼はすぐに2つの事実を
結び付けるだろう。
ドアを出て、通りを歩いた。すぐには気づかれないような場所、しば
らくは安全な場所に着いたら、すぐに包帯の束を取り出そう。誰かに話
し掛けたり、常識内でおとなしくしていれば、安全だ。常識を破ること
は、ロープに寄り掛かるまでは、ずいぶんたやすかった。1943年製
の50セント硬貨をあげれば、スパイとして殺されそうになる。店主は、
はっきりと、アルクトゥルスのスパイだ!と言った。それなら、ふつう
の会話の中にもあるかもしれない、別の落とし穴を、簡単に推測できる。
グリーンビルまで乗せてくれた男とは、ほとんどしゃべらなかったこと
に、感謝したい。確かに、遅かれ早かれ、彼は、悪い常識はずれに出会
っていただろう。
彼は、今、いつもそうだった感覚を呼び覚まして、信頼のおけるビジ
ネスマンのふりをしながら、メインストリートに向って歩いた。メイン
ストリートの手前の角にあるゴミ箱に、腕に巻いていた服の束をはずし
て、捨てた。
彼は、自分の見た目が良くなったことから、あえて、夜のためにホテ
ルを捜すことに決めた。そこが見つかったら、ポケットにある2冊の雑
誌を、楽しみながら読もう。彼には予感があって、2冊の雑誌をよく調
べれば、なにがどうなっているのかを知る手掛かりが得られるはずだ。
災害が彼に降り掛かって来たドラッグストアとは、逆の方向に向かっ
て、歩いた。紳士用の装身雑貨店を過ぎ、スポーツ用品店を過ぎ、2か
月前にニューヨークで見た映画をやっている映画館を過ぎた。すべてが
ノーマルでふつうに見えた。
一瞬、すべてはノーマルでふつうだったのではないか、という疑いを
持った。違いを想像しようとした。たぶん、店主の頭がおかしくて、す
べてのことは、合理的な説明がつくのだろう、紫モンスターでさえも。
そのとき、正前に新聞のラックが置かれた、ニューススタンドが見え
た。グリーンビルの地方新聞が2誌ともあり、ニューヨークの新聞も置
かれていた。すべてが、ごくふつうに見えた。見出しを、たまたま、見
てしまうまでは。それには、こうあった。
アルクトゥルス、火星を攻撃
カピ破壊
植民地は不意をつかれた
地球防衛軍報復を誓う
近づいて、日付けを見た。手のひらより馴染みのある活字の、ニュー
ヨークタイムズの今日付けだった。
ラックから1部取って、スタンド店員に100クレジット出すと、9
9クレジットおつりが来た。彼が持っていた紙幣は、貨幣単位を除いて、
すべて100クレジットだった。新聞をポケットに押し込んで、急いだ。
数軒先に、ホテルがあった。チェックインでは、サインするときに、
ペンが手につかなかったふりをして、2回ためらい、ほんとうの名前と
住所を書いた。
ベルボーイはいなかったので、受付は、鍵を直接、手渡しして、室が
どこか説明した。2階の廊下の正面突き当りだった。
2分後に、ドアを閉めて、後ろ手で鍵を掛け、期待の息をはずませて、
ベッドに座った。ドラッグストアで危険な目にあってから初めて、彼は、
ほんとうに安全を感じた。ポケットから、新聞と雑誌を取り出して、ベ
ッドに並べた。それから、立ち上がり、コートを吊るし、ハットはハン
ガーに掛けた。
ドアの横の壁の上に、2つのノブとダイアルが、6インチちょっとの
服の循環エリアになるように注意して配置した。明らかに、服がスピー
カー出力をカバーすれば、組み込みラジオを形作った。
加減抵抗器に見える、実際、そうである、ノブを回した。かすかな、
ハム音がスピーカーから聞こえて来た。チューニングダイアルを回して、
局がクリアで力強くなるまで、デューニングダイアルを回した。それか
ら、ボリュームを回して、一番低くした。いい音楽が聞こえてきた。ベ
ニーグッドマンのようだ、どの局だか分からないが。
ベッドに戻って、リラックスするために靴を脱ぎ、枕を叩いて、ベッ
ドの頭の部分に置いた。最初に、自分の雑誌『サプライジングストーリ
ー』を取り上げた。
また、表紙を、驚きをもって、よく調べた。表紙は、信じられないく
らいに同じ絵だったが、信じられないくらいに違う絵だった。
しばらく、それを眺めていたが、それほど突然ではない考えが沸いて
きて、すぐに目次のページを開かせた。一番下に、きれいにタイプされ
ていた。こんなふうに。
ボーデン出版社発行、LAボーデン、編集及び出版。
ケイスウィントン、編集長━━━
自分の名前を見つけるまでは、息を止めていたことに気づいた。ここ
がどこであれ、彼には、ちゃんと仕事があった。ボーデン氏も、ここに
いたが、彼の夏の別荘に、なにが起こった?今夜の7時数分過ぎに、文
字通り、彼の下から落ちて消えてしまった。
別の考えが浮かんで、ラブストーリー本をつかみ上げ、もう少しで破
ってしまうところだったが、目次のページを開いた。そう、ベティハー
ドレイは、編集長だった。しかし、困ったことがあった。雑誌が、ボー
デン出版社から発行されていることだ。この号、7月号は、フェアリー
社の発行と印刷されているはずだった。それは、単に、ボーデンがその
雑誌を買い取った日付だけの問題だった。8月号の発行でさえ、まだ、
フェアリー社のはずだった。しかし、これは些細なことだった。
重要なことは、ここが、なんとファマドユニヴァースは、ベティハー
ドレイが、ここにいるということだった。
ホッとして、ため息をついた。ベティハードレイが、ここにいるとい
うことは、たとえ、月の紫モンスターがいるとしても、そんなに悪いと
ころでないようだ。それに、もしも彼、ケイスウィントンが、まだ、大
好きなサイエンスフィクション雑誌『サプライジングストーリー』の編
集者なら、まだ、仕事はあって、食べて行けるのだ、ドルの代わりにク
レジットで支払われることは、それほど気にならなかった。
ラジオ放送は、突然、中断した、まるで、だれかが、レコード針を引
き上げたかのように。声が割り込んだ。
「特別ニュース公報、グリーンビルとその周辺の市民へ2度目の警告。
30分前のアルクトゥルスのスパイは、まだ、捕まってない。すべての
鉄道駅、道路、宇宙ポートは閉鎖され、1軒ごとの捜索が始まった。全
市民は、警戒するよう要求されている。
全員武装して、見たら殺せ!間違って撃つことはあっても、スパイを
逃して、なん百万人の地球人の命が奪われるよりは、100名の市民の
命が奪われる方がましだ。
少しでも怪しかったら、撃ち殺せ!
スパイの特徴は━━━」
息をひそめて、ケイスウィントンは、その特徴を聞いた。
「身長、約5フィート9インチ、体重、160パウンド、茶のスーツ、
白のスポーツシャツ、カラーなし、ハットなし、目は茶、髪は、ウェー
ブした茶、だいたい30━━━」
彼は、息をゆっくり吐いた。服を変えたことは、バレてないようだ。
傷については言ってなかった。店主は、自分が発砲した1発がヒットし
たことに気づかなかったようだ。
身体的特徴は、かなり近かったが、どんな服で、また、上腕に包帯を
巻いていることが知られてなければ、それほど危険はなかった。
もちろん、彼が盗みを働いた室の住人が帰って来て、自分のオックス
フォードブルーのスーツとストローハットが盗まれたことを報告すれば、
危険性はかなり増すだろう。
損失を補うために500クレジット置いて来たにも関わらず、もしも
放送を聞けば、それらを報告するだろう。彼は、カネを置いて来たこと
を、今、後悔した。ふつうのドロボーだったら、自分が盗んだものを補
うカネを置いて来ることはないので、そうしたことは、より当局の注意
を引くことになった。彼は、今、悟ったが、ふつうの室荒らしのように、
もっと別のものも盗むべきだった。スーツケースにあった3着のスーツ
を全部盗んでおけば、当局は、どの服を着ているのか推測するしかなか
っただろう。
つまり、当局が、その貸室でなにが起こったかを知れば、ふたたび彼
の特徴について、正確な情報を提供できることになる。
しかし、なんてことだ、彼は、どこへ逃げ込めばいい?見たら、殺せ!
彼は、真剣に、あきらめることを考えた。
そう、『見たら、殺せ!』命令は、明らかに、彼に自首させることを
目的としていた。ある程度、彼は、死の危険に直面して、説明する機会
も与えられないかもしれなかった、どう説明するか分かったとして。
道路も駅も監視されていても、ニューヨークに戻って、用事を済ませ
なければならなかった。しかし、ニューヨークはどうなっているのだろ
う?知ってるとおり、それとも別の?
ホテルの室は、風通しが悪く、暑かった。窓に行って、あけて、立っ
たまま、下の通りを眺めていた。ふつうの通りで、ふつうの人々だった。
そのとき、3頭の紫モンスターが見えた。手をつないで、劇場ロビーか
ら出て来て、通りを渡った。だれも、やつらに注意を払わなかった。
突然、彼は窓から下がった。それは、紫のものの1頭に、見覚えがあ
って、ドラッグストアで見たやつと同じだった。モンスターは、すべて、
彼には同じに見えた。しかし、やつらが人間に慣れてきたら、やつらが
そうあるように、彼を見た1頭は、明らかに、彼をふたたび認識するだ
ろう。
紫モンスターの光景は、突然の思い付きに、彼を身震いさせた。オレ
は正常?あるいは、おかしい?もしもそうなら、彼が見聞きしたものは、
大学の精神異常の授業で扱われるような、特別な症例になる。
もしも彼がほんとうにおかしいなら、彼が今いる世界もまぼろしにな
って、あるいは、彼の記憶も?
彼の心から、考えられるように、世界の間違った記憶を排除してみよ
う。宇宙船をやめて、月から来る紫モンスターもなし、クレジットでな
くドル、アルクトゥルスのスパイもなし、火星の地球植民地もなし。
すると、その世界は、彼がずっと慣れ親しんできた生活の場、慣れ親
しんできた世界、記憶通りの世界になる。彼の心のまぼろし?
しかし、もしも、これがほんとうの世界で、彼の記憶、今夜の7時ま
での記憶が間違っていたら、それらに彼は対応してゆける?彼は、アル
クトゥルスのスパイ?それは、ほかのなによりも、もっともあり得ない
気がした。
突然、ドアのすぐ外の廊下に、数人の重い足音がした。大声で命令的
に、ドアが叩かれた。
「警察だ!」と、声。
4 マド・マンハッタン
ケイスは、深いため息をついて、急いで考えた。ラジオがさっき、1
軒ごとの捜索が始まったと言っていた。たぶん、これは、その捜索だ。
ホテルにチェックインした者を、最初に、調べて行く。チェックインの
時間を別にすれば、疑われるようなことはない。
捜索されて、逃げなければならないようなものは?ある、彼のカネだ。
店主がくれたクレジット紙幣でないもの、ドルの通貨単位の財布や小銭
入れだ。
急いで、ポケットからおつりの小銭、25セントや10セント、1セ
ント硬貨を取り出した。財布から紙幣━━━10ドルが3枚に、数枚の
1ドル紙幣、クレジットでないものを取り出した。
ドアがまた、叩かれた、少し強く。
ケイスは、硬貨を紙幣で包み、小さくて硬い包みにして、窓のところ
へ行って、窓から突き出た棚の隅の見えないところに隠した。
それから深呼吸してから、ドアへ行って、あけた。
3人の男たちが、ふたりは警察の制服を着て、立っていた。制服のふ
たりは、リボルバーを手に持っていた。もうひとりのグレーのビジネス
スーツの男が、しゃべった。
「ソリー、サー。オレたちは、捜索中、放送を?」と、彼。
「もちろん」と、ケイス。「どうぞ、入って!」
ケイスがまだ話す前に、男たちは入って来た。警戒しながら。拳銃の
2つの銃口がケイスの腰をねらっていた。ふたりともまったく緊張して
なかった。グレーの男の冷たい疑るような目も、ケイスの顔から逸らさ
なかった。しかし声は、努めて、礼儀正しかった。「名前は?」
「ケイスウィントン」
「職業は?」
「編集の仕事。『サプライジングストーリー』の編集をしている」ケイ
スは、ベッドの上にある雑誌を、何げなく身振りでしめした。
彼をねらっていた銃口のひとつが、少し下がった。たぶん、1インチ
くらい。笑い顔が、輪から広がって、その後ろに平らな顔があった。
「そうか」と、彼。「あんたは、ロケットトークコーナーの担当者に違
いない。ロッキーティア?」
ケイスは、うなづいた。
「それなら、たぶん」と、警官。「オレの名前を覚えてる?ジョンギャ
レット、4通手紙を書いて、2通を載せてくれた」
彼は、すばやく、拳銃を左手に持ち替えると、まだ、ケイスをねらっ
たまま、右手を差し出した。
ケイスは握手した。「そう」と、彼。「中のイラストをカラーにして
くれと言って来た人だね、1ド」すぐに言い直した。「1クレジット、
値段を上げてでも」
男の笑い顔は、もっと広がって、拳銃を脇で回した。「そう!」と、
彼。「それが、オレ!あんたの雑誌のファンさ、ずっと前から━━━」
「銃をちゃんと上げて、巡査!」と、グレーの男。「注意して」
拳銃は、また、上がったが、巡査は、ニヤニヤしたままだった。彼は
言った。「この男は大丈夫、警部。もしも、彼が自分の身分を偽ってい
たら、オレが雑誌に送った手紙のことを知ってるはずない」
警部は、訊いた。「あんたの手紙は、載った?」
「ええ、ま、しかし」
「アルクトゥルスは、記憶力が非常に優れている。もしも編集者になろ
うとするなら、雑誌の過去の号もすべて調べるだろう」
巡査は、顔をしかめた。「ええ、ま、しかし」と、言って、右手でハ
ットを後ろにずらし、頭をかいた。
警部は、室のドアを閉めて、それに寄り掛かった。ケイスの顔と巡査
の顔を見てから言った。「しかし、そのアイデアはいい。巡査、ウィン
トン氏が本物かどうか、載ってないものを使って、チェックできる?」
巡査は、前にも増して、困った顔をした。ケイスは言った。「巡査、
最後に送った手紙を覚えてる?約1か月前だったと思う」
「確かに、あんたが言ってるのは、オレが提案した━━━」
「言わないで!」ケイスは、遮った。「オレに言わせて!あんたが言っ
たのは、コミックブックが絵をすべてカラーにして、パルプ雑誌より安
い値段でもやって行けるのに、なぜ、カラーにすることも、同じ値段で
はできないのか、理解できない」
銃口が、また、下がった。巡査は言った。「その通り!警部、オレが
言ったそのままだ。その手紙は、まだ、載ってない!この男は本物、そ
うでなければ、知らないはず。できない、でなければ━━━」彼は、ま
た、ベッドの上の雑誌を見た。「それが今月号に載ってなければ、オレ
は、まだ、それを見てない。今月号は、今日、スタンドに乗ったばかり」
「その通り」と、ケイス。「しかし、あんたの手紙は、載ってない!手
に取って、見れば!」
ギャレット巡査は、上司を見て、了解を得た。彼は、ケイスを回って
行って、雑誌を手に取り、ページをめくって、末尾のロケットトークコ
ーナーに来ると、目はケイスを見たまま、同時に、読み始めた。
グレーの男は、うっすらと笑いを浮かべ、肩のホルスターから短銃身
のリボルバーを出して、言った。「銃をしまって、今やってることに集
中しろ、巡査。バークとオレで警戒を続けるから」
ギャレット巡査は言った。「ええ、警部、サンクス」拳銃をホルスタ
ーにしまった。両手と両目が使えて、雑誌を楽に扱えた。
読者コーナーをまだ見ながら、ギャレットは言った。「中もカラーを
使った方がいいと思う、ミスターウィントン。そうすれば、ベムがもっ
と引き立つ!」
ケイスは笑った。「できることなら、そうしたい、巡査。しかしそう
すると、オレたちの本は、他社に勝てなくなる」
警部は、ふたりの顔を、不思議そうに見た。「なんの話?」と、彼。
「ベムって?本って?雑誌の話じゃなかった?」
ケイスは言った。「雑誌を本と呼ぶのは、パルプ雑誌の編集や出版で
は、共通の習慣、警部。たぶん、彼らは雑誌は本だと思ってるから。ベ
ムについては、ファンの間のスラッグで、語源は、昆虫の眼をしたモン
スター。ギャレット巡査が見ている表紙にいるのが、ベム」
「よく描かれている」と、巡査。「アルクトゥルスの第3惑星のベムの
1匹?」
「そのストーリーは、記憶通りなら」と、ケイス。「金星にいるやつ」
巡査は、心の底から笑った、ケイスが、とてもおもしろいジョークを
言ったかのように。ケイスは、なにがおもしろいのか分からなかったが、
いっしょにニヤリとした。巡査は、ロケットトークコーナーのページを
めくり続けた。
1分後に、顔を上げた。「ほら、ミスターウィントン、バーグマンが
書いたメインノベルが好きじゃないプロビンスタウンの男の手紙だが、
そんなたどたどしい男のことは、気にしないで!バーグマンは、外部の
作家として、最高さ、たぶん━━━」
「巡査!」警部の声は、氷のようだった。「あんたのフィクションの好
き嫌いを、聞いてるヒマはない。手紙のサインなり見出しだけ見て、今
月号にあんたの手紙があるかどうかだけを見ろ!そんなことに一晩中、
掛けられない!」
巡査は赤くなって、ページをめくった。
「ない!」彼は1分後に言った。「ここにはなかった、警部」
グレーの男は、ケイスに笑顔を見せて、言った。「あんたは、大丈夫
のようだ、ミスターウィントン。しかし、ルーチンとして、身分証は?」
ケイスは、うなづいて、財布を出そうとした。しかし、グレーの男は
言った。「待って、もしよければ━━━」
ケイスが気にしようがしまいが関係なく、後ろに回って、手をすばや
く動かして、ケイスのすべてのポケットを調べた。見たところ、財布以
外に、興味を引くものはなかった。彼は、それを取り出して、中身をす
ばやく調べ、返した。
彼は言った。「オーケー、ミスターウィントン。大丈夫だが━━━」
クローセットに行くと、ドアをあけ、中を調べた。ドレッサーの引き
出しも調べ、ベッドの下も見て、室じゅうをすばやく、しかし徹底的に
捜索した。
彼の声には、ふたたび、疑いの感触があった。「荷物がない、ミスタ
ーウィントン?歯ブラシさえない?」
「歯ブラシさえない」と、ケイス。「グリーンビルに泊まる予定はなか
った。しかし、ビジネスが考えていたより、長引いてしまって」
グレーの男は、捜索を終えた。彼は言った。「煩わして、申し訳ない。
徹底的な捜索が要求されていて、逃げようがなかったもので。そして、
あんたはここで正式に登録された。あんたとギャレット巡査が、いっし
ょに、あんたが誰か証明してくれた。そうでなかったら、もっとチェッ
クすることが多かった。しかし、なんとか」
彼は、うなづくと、もう一人の制服の男は、拳銃をホルスターに戻し
た。
ケイスは言った。「まったくオーケー、警部。疑いが晴れて、よかっ
た」
「あんたは、ここではオーケーだが、スパイが捕まったわけでない。グ
リーンビルからは出てないだろう。蚊一匹抜けられない非常線を張って
いる。アルクトゥルスが捕まるまでは、非常線を維持する」
「ニューヨークに戻るのに、問題は?」と、ケイス。
「そう、駅では、かなり細かい検問がある。通してもらうよう言うこと
はできる」彼は笑顔になった。「特に、警官の中に、あんたのファンを
見つけられれば」
「それは、ありそうもない、警部。朝までに戻りたいと考えている。そ
れだとオフィスに戻るのが遅すぎるので、気が変わって、今夜、戻るか
もしれない。かなり疲れていたので、ここに泊まろうとしたが、今、気
分は良くなった。ニューヨーク行きのつぎの列車は?」
「9時半だと思う」と、警部。自分の腕時計を見た。「あんたは間に合
いそうだが、すぐに、検問を通してもらえるかは分からない。そのつぎ
の列車は、朝の6時」
ケイスは顔をしかめた。「9時半の列車に乗りたい、警部、たとえば、
駅の検問にいるだれかに電話して、オレが捕まったり、列車に間に合わ
なかったりしないように保証してくれることは、可能?あるいは、行き
過ぎたお願い?」
「いや、できると思う、ミスターウィントン。ここから、電話しよう」
◇
10分後、ケイスは、駅に向かうタクシーの中にいた。30分後、彼
は、あまり混んでないニューヨーク行きの列車にいた。
彼は、深い安堵のため息をついた。最悪の、差し迫った危険は去った
ようにみえた。確かに、彼は、ニューヨークでは安全だろう。非常線を
通れたことが大きかった。それだけでなく、警官が去ってから、窓の敷
居に隠したカネを財布に戻した。警部の電話は、相手が誰だろうと、駅
の検問にいる警察官に、彼がすでに確認された身分証を見せれば、ふた
たび、捜査の対象にはしないことを約束してくれた。
そして、なにがどうなっているのか分かるまでは、これらの紙幣や硬
貨をあきらめたくなかった。それらは、たぶん、危険なものだったが、
一部は価値があった。店主は、1枚の硬貨に200ドルに相当するもの
をくれて、ほかの者はもっと高い値を付けるだろうと言った。なぜ、店
主は、25セント硬貨が、彼が支払ったよりももっと価値があると言っ
たのだろう?
しかし、50セント硬貨は━━━彼は、心の中で、肩をすくめた。推
測は、意味がない。なにがどうなっているのか分かるまで、待つしかな
い。そして、しばらくは、できるだけ注意することだ。ホテル代と列車
代を支払ったあと、彼には、まだ、240ドル相当のクレジットが残っ
た。これで、しばらくは、やって行ける。注意すれば、しばらくは。ク
レジットでない紙幣や硬貨は、小さく丸めて、ズボンの時計を入れるポ
ケットに押し込んであるので、買い物で、不注意に間違った硬貨を出す
ことはないだろう。硬貨は、紙幣で固く包まれていて、ガチャガチャ音
がすることはなかった。
それらを持っていることは、疑いもなく、危険だった。しかし、それ
らの価値よりも、もっと強い理由があった。それらは、彼が正気だとい
う、わずかな希望だった。彼の記憶は、彼の作りごとかもしれない。し
かし、それらの硬貨は、硬い物理的存在だった。それらは、ある意味、
少なくとも、彼の覚えていることは、ほんとうに事実だという証拠だっ
た。彼のポケットの小さなふくらみは、心のよりどころ、安心だった。
列車の窓の外の景色は、速度を上げて行き、グリーンビルの光はだん
だん小さくなって、ついには瞬いて、田舎の闇に消えて行った。
少なくとも、この瞬間だけは、彼は安全だった。2時間余りのあいだ、
2冊の雑誌と彼が買った新聞に、ゆっくり、目を通した。
新聞の見出しは、こうだった。
アルクトゥルス、火星を攻撃
カピ破壊
それは、ニュース、大きなニュースだった。注意深く読んだ、カピは、
火星に作られた地球の植民地だった。そこで建設された7つの植民地の
4番目で、1939年に作られた。1番小さい植民地だった。840人
余りの地球人の居住者がいた。全員殺された、と見られている。推定1
50人の火星人労働者と同様。
ここで、ケイスが分かったことは、地球からの移住者である居住者と
は別に、ネイティブな火星人もいるということだった。ネイティブな火
星人って、どんな?いつもの戦争の速報のような簡単な記事には、手掛
かりとなるものはなかった。たぶん、『ルナン』は、結局、まったく1
つの名前だった。紫モンスターが火星人で、月の住人ではないのだろう。
しかし、それよりももっと驚く重要なことがあった。記事を読んだ。
アルクトゥルスの宇宙船1隻が、宇宙防衛ラインを突破し、地球防衛
軍に見つかる前に、1発の魚雷を発射した。彼らはすぐに攻撃し、アル
クトゥルスは恒星間ドライブに切り替えたが、捕えて、完全に破壊した。
準備は、とニューヨークタイムズは言っている、報復のためになされ
た。詳細は、もちろん、軍事機密だった。
その論説の中には、多くの人や物の名前が登場するが、ケイスには、
なんのことか全く理解できなかった。よく知っている名前が、全く知ら
ない文脈に登場するのは、奇妙だった。例えば、ドワイトDアイゼンハ
ワー将軍が、金星部門担当だった。
この記事の最後は、攻撃されやすい都市の防衛力の増強を提案し、あ
とはケイスウィントンには全く不明のことが書かれていた。良く出て来
るが、全く不明のことは、繰り返し述べられる『全都市の霧中』、何度
か言及のある『裏切り者』と『夜歩き』だった。
メインの記事は、コラム欄が2つあって、ふつうとは違って、新聞を
前から後ろへ読んで行き、見出しはすべて見て、おもしろそうだったり
変わったストーリーの最小限のところを読んだ。ふつうの生活の詳細と、
驚くほど違いがなく、特に、国内の事柄に関しては、ほとんど違いがな
かった。
社会欄のニュースは、彼はいつも読む習慣があったので、そこに登場
する名前の多くは分かったし、疑いもなく、認識できた。セントルイス
は、1つのメジャーリーグのトップで、新しいヨークが、もう1つのト
ップだった。それは、彼は覚えていたが、正確なパーセンテージが同じ
だったかどうかは確信がなかった。広告は、みんな馴染みのあるもので、
価格が、ドルやセントでなく、クレジットである以外は、同じだった。
子ども向けの宇宙船や原子力おもちゃはなかった。
彼は、広告を特によく調べた。住宅事情は、覚えているものより、か
なり良かった。それは、たぶん、『火星への移住』という宣伝文句で売
り出されているアパートや家の供給のせいだろう。セール広告が金星コ
ロニーだったり、別のものが月のものだったりした。
1時少し過ぎに、時刻表通りなら、列車は、グランドセントラル駅に
着く。ケイスは、もっと詳細はあとで調べることにして、新聞を丸めた。
まだ読んでない2冊の雑誌が、すごく気になった。
徐々に、列車が速度を落として駅に入ると、ケイスはいつもと違うな
にかに気づいた。指で数えられないなにか違うもの、その場所の雰囲気
にあるなにか。明かりがなかったわけではなかった。駅には、通常の明
かりはあった。たぶん、彼が覚えているよりも、もっと多くの明かりが
あった。
また、彼は、乗って来た車両の客が1/4だけで、混んでなかったこ
と、そして、降りるとき、その車両が、客が降りて来る唯一の車両であ
ることに気づいた。すべての赤帽は、仕事を終えて帰っていた。
ケイスのすぐ前を、背の低い男が、3つのスーツケースを、両手と脇
で苦労して運んでいた。いかにも重そうだった。
「ひとつ持つ?」と、ケイス。
背の低い男は言った。「ありがたい、サンクス」声には、感謝の気持
ちが込められていた。重いスーツケースの1つをあきらめて、ケイスに
渡した。そして、ふたりは、列車の間のセメントの歩道を降りて行った。
ケイスは言った。「今夜は、人が少ない?」
「最終列車だからだと思う。そんなに遅くは、走らせるべきでない。家
に帰れないとしたら、列車に乗る意味がないだろ?そう、朝にいいスタ
ートを切りたいが、長期的になんの意味がある?」
ケイスは言った。「それほどの意味は」そして、なんの話なのか疑問
に思った。
「昨夜、87人殺された!」と、背の低い男。「少なくとも、それだけ
の死体が見つかった。川になん人入ったのか分かっていない」
「ひどい!」と、ケイス。
「それが、ふつうの平均的な夜。少なくとも、100人が殺される。た
った一晩で!なん人が、路地で薬漬けにされて、殺されないで殴られて
いるか分からない」彼は、ため息をついた。「ブロードウェイさえ、安
全だったときを覚えている」
彼は、突然、立ち止まり、スーツケースを置いた。「少し休もう」と、
彼。「先に行きたいなら、置いて行っていい」
ケイスは、運んでいたスーツケースを置くチャンスができて喜んだ。
左肩を負傷していたので、運んでいた右手を替えられなかったのだ。ス
ーツケースの取っ手で、締め付けられていた右手を伸ばした。「別に急
いでない」と、彼。「家に帰るのを、急いでない」
背の低い男は、すごくおかしいことを言ったかのように、笑った。ケ
イスは、あまり関わりたくないかのような笑いを浮かべた。
「そうさ」と、背の低い男。「急いで帰らなくていい」手で自分の太腿
をぴしゃりと叩いた。
ケイスは言った。「うう、しばらくニュースを見てなかった。あんた
は?なにかニュースがあった?」
「ああ、ちょうど1つあった!」背の低い男は、急に怖がって、死ぬほ
ど真顔になった。「国内に、アルクトゥルスのスパイがいる。あんたも
聞いたはず、夕方早くのこと」彼は、少し震えた。
「いや、聞いてない」と、ケイス。「詳細は覚えてる?」
「グリーンビルの北部の町、オレたちも通って来た。覚えてない?列車
のすべてのドアはロックされ、チェックされた者以外、だれも乗れない
ようにした。駅じゅう警官とガードマンでいっぱいだった」
ケイスは言った。「オレは停まっているあいだ、居眠りしていたらし
い。グリーンビルと言った?」
「そう、グリーンビル。そこで降りないでよかった。駅じゅう大騒ぎだ
った」
「そいつは、なぜ追われることに?」と、ケイス。
「ニセの硬貨を売ろうとしたらしい。アルクトゥルスが偽造した硬貨で、
製造年が間違っている」
「おお」と、ケイス。あのときの50セント硬貨は、それだったのだ。
頭が良ければ、その現在価値やありうる価値にも関わらず、硬貨の残り
は、すべて下水道からなにかに捨てていただろう。さもなければ、たぶ
ん、彼は、グリーンビルにいたときにそうしたように、窓の敷居に置い
たままにしていただろう。
いや、だめだ。それは、まずいことになる。もしもそれが発見されれ
ば、彼に辿り着く。ホテルの宿帳には、本名を書いたし、幸運にも、別
の理由で、室に来た警官にも、本名を告げた。そう、室の外の窓の敷居
に隠した硬貨が見つかれば、捜索の手は、ニューヨークにいるケイスウ
ィントンに伸びて、どのように入手したのか説明しなくてはならなくな
る。窓の敷居に隠した硬貨を財布に戻すときは、そこまで考えてなかっ
たが、その硬貨で、また、儲けようとしたのは、少し向こう見ずだった
と考えていたが、今、そうしようとしたことが、逆に、いかにラッキー
だったかに気づいて、冷や汗をかいた。
彼は訊いた。「スパイをニセ硬貨で発見して、どうやって捕まえる?」
「捕まえるだと!」背の低い男は、見るからに、ショックを受けたよう
だ。「だめだ、アルクトゥルスを捕まえることなどできない。殺すだけ
だ。実際、殺そうとした。店主と、近くにいたムーニーが━━━しかし、
どちらも取り逃がした」
「おお」と、ケイス。
「そのせいで、グリーンビルで2・30人殺されたと賭ける!」と、背
の低い男。憂鬱そうに。手をこすり合わせると、2つのスーツケースを
持ち上げた。「あんたが良ければ、このあとは、オレひとりで運んで行
ける」
ケイスは、もう1つのスーツケースを持ち上げて、ふたりは、駅のロ
ビーへ向かった。
「小屋が残っていることを祈ろう!」と、背の低い男。
ケイスは、口をぽかんとあけて、そして、閉じた。なにか質問しても、
それが知っていることなら、知らないふりをしなければならないかもし
れなかった。それで、ユーモラスに暗い声で、「たぶん、ないかも」と
言った、それなら、言ったことが間違っていても、ジョークと受け取っ
てもらえるからだ。
しかし、背の低い男は、うなづいて、曖昧に同意しただけだった。ロ
ビーの近くに来ると、赤帽がいた。3つのスーツケースを赤帽に渡して
から、ホッとして、ため息をついた。
「小屋?」と、赤帽。「少し残ってる」
「よかった!2つ、お願い!」と、背の低い男。それから、ためらいな
がらケイスを見た。「これは、あんたの分じゃないんだ。まだ、座って
る者たちがいる」
ケイスは、闇の中を綱渡りしている気がした。小屋を選ぶか、座るの
を選ぶか、どんな意味がある?どちらも、イヤだった。
彼は、遠慮がちに、言った。「その辺を、ぶらついて来る」
いくつかのドアを通って、駅のメーンホールに来ると、驚いて、小屋
を見た。長く、順序良くに並んだ、軍隊ふうの小屋の列があった。列の
あいだを通る廊下を除いて、全体のフロアの驚くほど広い空間を小屋が
占めていた。小屋にいるほとんどが、横になって眠っていた。
住宅不足が、この悲惨を招いた?いや、違う、それはあり得ない。ポ
ケットにあるニューヨークタイムズの貸家広告の数から言って、あり得
ない。しかし━━━
背の低い男は、ケイスの肩に触った、たまたま、ケガしてる方だった
ので、ケイスは跳び上がった。背の低い男は、それには気づかず、言っ
た。「ちょっと、待って、ポーター!」と、数歩先に行っている、赤帽
に。
彼は、ケイスに近づいた。「うう、もしもクレジットが足りないなら、
ミスター、少し貸してあげられるけど」
「サンクス」と、ケイス。「しかし、ただ、走りたいだけ」
「外に出る、ということ?」ホラーと驚きが、男の顔に浮かんだ。
彼は、また、間違ったことを言うかもしれなかった。それが、なんな
のか分からないが、なぜ、グランドセントラル駅に小屋があるのか、こ
こに泊まるかどうかが、なぜ重要なのか?とにかく、背の低い男から早
いところ遠ざかった方がよさそうだった、彼が疑いを持っていないあい
だに、疑惑が生じる前に。
「もちろん、違う」と、彼。「そんなバカじゃない。ここで会う予定が
あって、そいつを捜さなくてはならない。たぶん、あとで小屋を借りる。
しかし、今は、眠れそうにない。心配しないで!クレジットを貸してく
れると言ってくれたことを、ありがとう。しかし、たくさん持っている
から」
質問される前に、急いでその場をあとにした。駅のメインホールの明
かりは、薄暗かった。明らかに、明るい光が彼らの目にギラついて、眠
りをさまたげないようにするためだった。ケイスは、薄暗がりで、行く
方向を判断して、眠っている者たちを邪魔しないように、できるだけ静
かに歩いて行かなければならなかった。42番通りの出口を目指した。
◇
そこに近づくと、ふたりの警官が、ドアの前に立っているのが見えた。
しかし、今、止まることはできなかった。彼が近づくと、警官は、見
ていた。警官のいるドアへ、まっすぐ歩いて行った。ここで急に歩く方
向を替えたら、まっすぐ行くよりもっと警官の注意を引いてしまうだろ
う。遠くから見ていて分かったが、ここで外へ出ようとしても、許され
そうになかったので、ガラスから外を見る振りをした。
なに気なく、歩いてゆくと、ドアはガラスの外から、黒のペンキで塗
られていた。
ふたりの警官の大きい方が、ケイスが近づくと話し掛けた。声は、敬
意を払っていた。
「拳銃は、サー?」
「ない」
「外は、かなり危険。あんたに留まるよう、命令する権利はないが、助
言はできる」
ケイスは、安心を感じた。怖かったが、ここにいる気はなかった。理
由はなんであれ、グランドセントラル駅で、夜をムダに過ごしたくなか
った。
しかし、警官の言う意味は、なんだろう?危険?最終列車で夜遅く到
着した、なん千人の者には分かって、彼には分からない危険は、どんな
危険?ニューヨークになにが起こった?
今、戻るには、彼にとっては、もう、遅すぎた。その上、ぼんやり考
えていたが、状況がはっきりするまでは、どこにいても危険だった。
彼は、できるだけ、何げなく言った。「すぐ近くだし、大丈夫!」
「それは、あんたの自由だが」と、警官。
もうひとりは、ニヤニヤしていた。「あんたの葬式を出すことになら
なきゃいいんだが。オーケー、ミスター」彼は、ドアをあけた。
ケイスは、もう少しで後ずさりするところだった。ドアのガラスは、
外から黒のペンキを塗られていたわけでなかった。外は、黒だった。今
まで見たことのない、漆黒の闇だった。かすかな光さえ、どこにもなか
った。駅の薄暗い明かりでは、この黒を切り裂くことなど、まったくで
きそうになかった。下を見ると、開いたドアの端から、1・2ヤードの
足元の歩道の舗装は見れた。
そして、外の黒が、少し、ドアから駅へ流れ込んでいて、まるで、闇
ではなく、手でさわれる黒、ガス質の黒のように見えるのは、ただの想
像なのか?単なる明かりの欠如以上のなにかであるかのように?
しかし、それがなんであれ、彼はその正体を知らないと、認めること
はできなかった。それがどこへ導くとしても、ドアを通って行かなけれ
ばならなかった。
歩き出すと、ドアは、彼のうしろで閉まった。クローセットの中へ歩
き出したみたいだった。灯火管制を越えた、灯火管制だった。このこと
が、彼は思い出した、ニューヨークタイムズの『霧中』だったのだ。
見上げたが、星や月らしきものはなかった。グリーンビルでは、少な
くとも、明るい月夜だった。
ドアの外へ2歩、歩き出して、うしろを見たが、なにも見れなかった。
ガラスの光の面さえ見えなかった。しかし、ぼんやりとは光っていて、
闇へ進んで行っても、こんなふうには見れるはずだった。もちろん、ガ
ラスが、ほんとうに外側から黒のペンキで塗られているのでない限り。
近づいてみると、とてもぼんやりした四角形として見れた。もっと近づ
くと、手に触れた。それよりもっと離れると、まったく見えなかった。
1歩、踏み出すと、見えなくなった。ポケットからマッチ箱を出して、
1本擦った。手を伸ばすと、光のかすかな1点は見えた。目から2フィ
ートでは、はっきり見えた。しかし、それより離れると、もう見えなか
った。
マッチは燃え続け、指の先まで来たので、下に落とした。歩道かどこ
かに落ちても、燃え尽きたかどうかさえ分からなかった。たぶん、コン
クリートの上で燃え尽きたのだろう。
彼は、今、駅内の小屋へ戻りたかった。しかし、ふたたび戻るには遅
すぎた。外に注意を集中させた。しかし、なぜ、背の低い男の助言に従
わなかったのだろう?みんなを真似た方が、ずっと安全だった。
ビルの壁に触りながら、手探りでたどりながら、西に向かって歩き出
し、バンデルビルト通りの角を目指した。目を大きくあけて、黒に集中
しながら、同時に、目を閉じても、同じようにうまくできるようにしな
がら。盲目の男の気持ちが、今、分かった。つえで、見えない歩道を叩
きながらなら、なんとかできそうだった。しかし、目の見えるイヌは、
うまくできそうにない。ネコでさえ、足くらいしか見えない、この黒の
霧の中では難しい。
手探りの手が、ビルの角で、空を切った。この先、進むか、迷った。
駅に戻ることはできない。しかし、歩くのを休んで、ビルに寄り掛かっ
て、朝まで待っては?朝になれば、黒の霧は消失するなら。
ビレッジにある彼のアパートまで辿り着ければ、まったく問題なかっ
た。タクシーは、走ってなかった。合理的に考えて、それ以外の移動手
段はなかった。まったくのバカか、彼のように、無知な者が、そして、
それらのカテゴリーに全く含まれない者たちが、こんなふうに、どこか
へ行こうと試みるのだろう。
彼は、歩道に戻ることに決めた。巡回パトロールに、なぜ駅にある小
屋に泊まらないで、近くをブラついているのか、訊かれるかもしれない。
そう、座って夜を明かすのはだめだ、ここでは、出発点とあまりに近過
ぎる。もっと離れた場所で訊かれたら、少なくとも、駅から家に帰る途
中だと答えることができる。
それから、足が動く方向へ、ビルから角へ、そして、通りを渡ろうと
した。なにかが走ってきても、分からなかっただろう、レーダーでもな
い限り。その考えが、通りのもう半分を渡るのを、急がせた。レーダー
もなしに、走って来るなにかをどう知る?
少し下った、外側に、カーブが見えた。彼は気を取り直し、歩道を横
切って、手を交差させた。42番通りに沿って、右手をガイドに、ビル
を触って、ふたたび歩けるように。
42番通りは、タイムズスクエアやブロードウェイから数ブロックに
あり、歩いて行けた、このような月夜でも━━━月は出てなかった。そ
こには、きっと、紫モンスターの会社があるのだろう。ここにもある?
そのことを疑問に思うのは、やめた。
耳を研ぎ澄ましていたが、聞こえてくるのは、彼自身の足を擦る、や
わらなか音だけだった。無意識のうちに、このぞっとする静寂を、でき
るだけ乱さないように、つま先で歩いていた。
マディソンまでの短い1ブロックを歩き切り、渡って、5番通りを目
指そうとした。
彼は、どこへ行こうとしている?疑問に思った。タイムズスクエア?
なぜ、だめ?
ビレッジは、問題外だった、あまりに遠すぎて、このようなヘビ歩き
では、一晩中かかっても辿り着けなかった。しかし、どこかへ、方向を
定めなければならなかった。なぜ、物事の中心ではだめ?もしも、ニュ
ーヨークにどこかへ開かれたなにかがあるなら、そこへ向かうべきだろ
う。
どこかへ、辿り着くために、この手でさわれる黒の外へ。
通り過ぎるときに、ドアをチェックすることにした。すべて、鍵が掛
かっていた。それを始めて、ポケットにボーデン出版社のオフィスの鍵
があったことを思い出した。それは、ここから、わずか3ブロック南だ
った。しかし、だめだ。ビルの外側のドアは、鍵が掛かっているだろう。
その鍵は持ってなかった。
5番通りを渡った。渡るとき、左には、公立図書館があった。通りを
横切りながら、そこまで足を延ばして、夜の残りをそこで過ごそうか考
えた。そうしないことにした。タイムズスクエアを歩きながら、だんだ
ん目的地が定まりつつあった。たしかに、宇宙の中心には、無料宿泊所
がいくつかあるだろう。それが、ただの明かりのついた地下鉄の入口だ
ったとしても。
5番通りから6番通りへ。長い1ブロックがあって、ここをアメリカ
通りと呼んだらどうかと思った。しかし、その長さのどこも、鍵の掛か
ってないドアはなかった。すべてを試した。
6番通りを横断して、ブロードウェイに入った。
別のドアを試した。ほかのドアと同じに、鍵が掛かっていた。しかし、
彼が足を止めて、ノブを回した、わずかな瞬間、グランドセントラル駅
を出て以来、初めて、自分の足音でないものが聞こえた。
それは、彼の足音のように、やわらかく注意深い足音だった。内側の
なにかが、その足音には危険があると教えてくれた、死につながる危険。
5 夜歩き
足音が、擦れて近づいて来たとき、彼は凍ったように立ち尽くした。
だれであれ、それがなんであれ、彼の方で引き返して、別の方向へ戻ら
ない限り、出会いを避けることはできなかった。ケイスに突然分かった
ことだったが、それは、1次元の世界だった。ビルの壁に沿って進む方
向を決めている、彼と未知の者にとって、前に進むか、後ろに戻るかの
2つしか選択の余地はなかった。ヒモの上を這うアリのように、どちら
かが引き返さない限り、出会って進むしかなかった。
そして、戻ることを決心する前に、もう、時すでに遅かった。つかも
うとする手が伸びて来て彼に触れ、哀れっぽい声が聞こえて来た。「オ
レを襲わないでくれ、ミスター!オレには1クレジットもねぇ!」
ケイスは、安心して、ため息をついた。「オーケー」と、彼。「オレ
はじっと立ってるから、回って行け!」
「わ、分かった、ミスター!」
手が軽く触れてから、男が過ぎる際、強いアルコールのにおいがして、
彼をオェッとさせた。闇の中で、つぶやく声が聞こえた。
「ちょうどバカ騒ぎ中」と、声。「ローリングはすでに2時間前に終わ
った。チップを賭けてもいい、夜歩きは終わった。ギャングたちは、タ
イムズスクエアにはいない。行く方向に、こだわるな!これは警告!」
男は、彼を過ぎたが、まだ、ケイスのすそをつかんでいた。
「あんたを襲ったのは、あいつらか?」と、ケイス。
「あいつら?ミスター、オレは生きている?夜歩きに襲われたら、オレ
は生きているか、逆に訊きたい」
ケイスは言った。「その通り!忘れていた。そう、たぶん、この方向
は行かない方がいいかもしれない。地下鉄は、あいている?」
「地下鉄?あんたは、ほんとうに、トラブルに会いたいらしいな!」
「安全な場所は、どこ?」
「安全?長いあいだ、そんな言葉を聞いてなかった。どういう意味?」
酔っぱいの笑い声を出した。「ミスター、オレは惑星直列の日に、火星
と木星の間にいた。船員は、エアロックを閉める前の最後の儀式だと言
った。この霧中の周りのゴミ溜めや夜歩きの役を演ずるのは、あのとき
に戻ったみたいだ」
ケイスは言った。「オレが夜歩きでないと、どうして分かる?」
「からかってるのか?男が夜歩きになれるのは、そいつがギャングども
とアームロックしてビルからビルへあさり歩き、叩いているのを聞いた
ときだ。こんなときに外出してるオレたちは、バカだ。あんたとオレ、
どちらも。もし、オレが酔っていたら━━━マッチある?」
「ああ、箱でよければ、ホラ、あんたは━━━」
「オレは、手が震える、金星湿地熱で。火をつけてくれる?霧が消えた
とき、安全な場所を教えられる、夜の残りを、安全に過ごせる場所」
ケイスは、マッチを箱の
縁で擦って、火をつけた。突然の炎が、黒の
霧に、半径1フィートのグレーの影を作った。ぞっとするような目をし
た、
怖ろし顔が浮かび上がり、バットを振り上げていた、バットは、火
がついた瞬間に振り下ろされた。攻撃をかわす時間はなかった。ケイス
は、その瞬間、本能的に同時に行動することで、無事だった。ブローの
下をかいくぐって、マッチの炎を
醜い顔に突き刺した。

男の腕は、バットではない、ケイスの頭にかするようにヒットした。
その衝撃で、バットは手から落ち、歩道に当たって、ドスンと音がした。
そのとき、ふたりは必死に闇の中で取っ組み合って、手で強くケイス
の喉を締め付け、汚い息を顔に吹きかけ、もっと汚い言葉を耳につぶや
いた。彼は、締め付けて来る腕を、ぐいと引いて自由になると、ステッ
プバックして、パンチを放った。手首は、闇の中に突き刺さった。
相手が倒れる音がした。ノックアウトではなかったが、まだ、ぶつぶ
つ言っていた。その音の向こうに、ケイスは3つの明かりを見て、すぐ
にステップバックして、壁から離れて、闇に隠れた。音を立てないよう
に、静かに立っていた。
男がこっちにやって来る、荒々しい息使いが聞こえた。1分間、その
息使いだけが、この世の唯一の音だった。
それから、別の、新しい音がした。それは、別の種類の音だった。遠
くで、100人くらいの盲人たちが杖で叩くソフトな音だった。まるで、
盲人の集団が、闇の中で叩いているように。音は、ケイスが向かおうと
していた、ブロードウェイやタイムズスクエアの方向から来た。
押し殺したようなつぶやきが聞こえた。「夜歩きだ!」それから、さ
っきの攻撃者が消えたあたりから、急いで擦れるような足音。彼の声は、
もはや、ののしっても好戦的でもなかった。濃い闇から戻って、言った。
「逃げろ、パル、夜歩きだ!」
叩く音がだんだん大きくなって、近付いて来たとき、引きずったりバ
タバタする足音は、消え去った。音は、信じられないくらいのスピード
で、近付いて来た。
夜歩きって、なに?人間?今まで見聞きしたり本で読んだ断片のピー
スを、つなぎ合わせようと試みた。怖がってる顔をした男は、なんて言
った?ギャングどもとアームロックしてビルからビルへあさり歩き、叩
いているのを聞いた。人間、それとも別のもの?殺し屋たちの組織され
たギャングで、霧中の通りをあさり歩いているに違いない。ビルからビ
ルへ、お互いの腕をアームロックして、叩く杖を案内に、長い列を組ん
で。
杖も武器なのか?それで叩く以外に、別の武器もあるのか?
叩く音は、わずか数ヤードに迫っていた。闇の中を歩くスピードより
ずっと速かった、ほとんど走ってる、組織化されたスピードだった。
ケイスは、もう、待っていられなかった。振り返って、ビルの並びの
線に対角的に走り出した。手がぶつかって、ざらざらしたもにに触れる
と、それと平行に走った。目に見えないものが降って来る危険にも関わ
らず、走った。
闇の中を走る危険よりも、背後に迫って来るものの危険の方が大きか
った。怯えた顔の男の声が含む恐怖は、伝染性があった。その男は、ど
んなに不潔だろうと、もはや、卑怯者ではなかった。彼は、夜歩きがな
んなのか知っていて、怖れていた。ひどく、怖れていた。彼自身も殺人
者であり、叩く音が来たとき、ライオンの群れに囲まれたジャッカルだ
った。
ケイスは、30歩から40歩のペースで走り、止まって、耳を澄まし
た。背後の音は、少し遠ざかった。彼があえて走れば、やつらは追いつ
いては来ない。そのとき、逆の方向から、彼が走って来た方向から、怖
ろしい、しゃがれ声の悲鳴が聞こえて来た。彼は思った、そしてそれを
確信した、その声は、怖ろし顔の男の声だった。悲鳴は、死の苦しみの
高いピッチまで上がり、それからバタバタして、静かになった。怖ろし
顔の男は、なにに向かって走った?死因は?ケイスは、怖ろし顔の男は
死んだと、確信した。死の苦しみの果てに?それは、まるで、ジャッカ
ルはライオンから逃れたが、ボアの大蛇に絞め殺されたかのようだった。
巨大な大蛇に絞め上げられ、死ぬ前の最期の長い悲鳴を上げた。
ケイスウィントンの後ろ髪が、首の後ろにちくちく痛んだ。その瞬間、
右腕を明かりにさらした、明かりが照らすものがなんであろうと。今、
恐怖がどんなものか知った。喉でたっぷり味わった。
背後に、叩く音。ダッシュすると、5か10ヤードでなく、20ヤー
ド離れる。また、走るか、走り続ければ、一定の距離を保てる。しかし、
なにに向って走っている?
怖ろし顔は、ビルの並びに沿って走っていた。そこで、なにに捕まっ
た?ケイスは、対角的にカーブに向って走り、通りへ下りた。それから、
カーブに平行に、走って回り、夜歩きの叩く列から、ふたたび、離れよ
うとした。また、30歩から40歩のペースで走り、止まって、耳を澄
ました。そう、また、叩く音は彼のさらに背後になった。
あるいは、それは?瞬間、方向を勘違いして、闇を回って、同じとこ
ろに戻ったように思えた。そのとき、事実に気づいた。叩く音は、背後
に聞こえ、前方にも、叩く音が聞こえた。
2つの列があり、逆方向から追い詰めて、彼は、間に挟まれていた。
それが、やつらの狩りのやり方だった。獲物がどこへ行こうと、さえぎ
って追い詰めて行く。叩く音で獲物に逃げる方向を教えてしまっては、
どう捕まえるのか疑問に思っていたが、今、ようやく分かった。
立ち止まった。心臓の動悸が早くなった。夜歩きは、その正体がなん
であれ、彼は、列に挟まれた。どこにも逃げ場はなかった。
◇
そこに立ったまま、ためらっていた。背後の叩く音が、前方の叩く音
より近くなり、あまりに接近したので、なにかしなければならなかった。
立ったままでいれば、1分以内に捕まる。前か後ろに走っても、もっと
早く捕まってしまう。
右方向を向いて、通りの南側のビルの並びの方へ走った。怖ろし顔が
死に至った地点の逆側だった。カーブについては、心配してなかった。
足で捜している時間はなかった。そこへ行ってみて分かった。足でさぐ
ったり、歩道を突っ切って、一番近いビルの正面に数歩踏み出した。一
旦止まって、耳を澄ました。叩く音は、右も左も同じ距離だった。
ドアに向かって、進んだ。ドアノブを見つけて、鍵が掛かっているか
ではなく、内側からあけられる場所にあるか確認した。脇のガラスに、
こぶしをスウイングした。
ナックルをひどく傷つけてもおかしくなかったが、傷つかなかった。
その幸運に勇気をもらって、内側に手を伸ばせるよう、ガラスをこわし
て、小さな窓をあけた。窓ガラスの残りの部分は、ドア枠からヒビが入
ったり、落ちたりしないようにした。
ガラスの内部に、厚いカーテンが降ろされているのがチラリと見えた。
急いで手を伸ばし、ドアノブを回して、つまづきながら中へ入った。
ドアを背後で閉めると、中の明かりに目がくらんで、ほとんどなにも
見えなかった。
声は言った。「止まれ!動くと撃つ!」
ケイスは止まり、肩より上に両手を上げた。目が見えるようになるま
で、目をまばたいた。小さなホテルのロビーにいた。デスクの向こう、
12フィート離れたところに、とても驚いた様子の顔が真っ白な事務員
がデスクに寄りかかっていた。手には、ノズルがキャノン砲のように見
える、繰り返し撃てるショットガンを持って、真っ直ぐにケイスの腰を
ねらっていた。事務員は、ケイスより息が荒かった。
声は少し震えていた。「近づくな!出て行け、すぐに、出て行け!あ
んたを撃ちたくはないが」
どちらの方向にも動かず、手も下げないまま、ケイスは言った。「で
きない。夜歩きが、今、外にいる。もしもドアをあけて、外へ出たら、
やつらが入って来る」
事務員の顔は、さらに、白くなった。1秒間、彼は、怖ろしすぎて口
がきけなかった。そのあいだ、ふたりとも、叩く音を聞いた。
事務員の声は、気づいたとき、ささやきより少し大きい声だった。
「ドアのところへ行って寄り掛かって、壊れたガラスから明かりが漏れ
ないように、カーテンで覆って」
ケイスは、後ろに戻って、ドアに寄り掛かった。
ケイスと事務員は、黙ったままだった。ケイスは、汗をかいた。夜歩
きは、ガラスの穴を見つけるだろうか?あるいは、なんとなく感じたり
するだろうか?ナイフか弾丸、あるいは、なにかが穴を通って、彼の背
中に突き刺さるだろうか?肌がムズムズした。時間がのろのろ過ぎた。
しかし、穴を通って、なにもやって来なかった。
その瞬間、叩く音が大きくなって、もごもご言う声がした。人間の声
に思えたが、確信はなかった。それから、音が消えた。
ケイスも事務員も、外の音が消えてから、少なくとも3分間は、動か
ず、口をきかなかった。それから、事務員は言った。「やつらは、行っ
た。さぁ、外へ出ろ!」
ケイスは、声を下げたまま、事務員にぎりぎり聞こえるように言った。
「まだ、近くにいる。外へ出たら、捕まるだろう。オレは、泥棒じゃな
い。銃も持ってない。そして、カネならある。壊した窓ガラス代は、払
いたい。空きがあれば、ひと室、借りたい。もしも、空きがなければ、
ロビーに一晩、居させてもらうフェアな料金を払いたい」
事務員は、疑わしそうに、彼を見た、銃は上げたままだった。
それから、訊いた。「外でなにを?」
ケイスは言った。「グリーンビルから来た。最終列車で、グランドセ
ントラル駅に着いた。弟が病気の一報で、12ブロック先の家に帰ろう
とした。外へ出たら危険なことを知らなかった。今、それが分かった。
朝になってから出発すべきだった」
事務員は、彼を近くで調べた。それから、言った。「手は上げたまま」
ショットガンは下げて、カウンターの上に置いた。しかし、手はそれに
触れたまま、指を引き金のガードの中へ入れたまま、もう一方の手で、
デスクの後ろの引き出しから拳銃を出した。
彼は言った。「後ろを向け!背中をこちらへ!銃がないか確認する」
ケイスは、後ろを向いて、静かに立って、事務員がカウンターの端を
回って来る音を聞いていた。事務的な拳銃の先が彼の背中の1か所に押
し付けられて、事務員の手がポケットを軽くさぐっているあいだ、さら
に静かに立っていた。
「オーケー」と、事務員。「あんたは大丈夫のようだ。とにかく、チャ
ンスをやろう。イヌを外に放したくはない」
ケイスは、やっと安心して、ため息をつき、こちらを向いた。事務員
は、デスクの向こうへ歩いて行き、銃は、彼をねらってなかった。
彼は、訊いた。「窓ガラス代は?空きがあるなら、室代は?」
「ああ、室はある。2つで、100クレジット。しかし、最初のものに
ついては、手助けが要る。雑誌やポケットブックのラックを動かして、
ドアのところに移動するので手助けしてもらいたい。ガラスの壊れたと
ころを十分ブロックして、カーテンがめくれるのを防げる。カーテンが
めくれなければ、外から壊れたところは見えない」
「いいアイデア」と、ケイス。ラックの一方の端を、事務員はもう一方
の端を持って、持ち上げることなく、ドアまで滑らした。
ケイスは、マガジンラックにあるポケットブックの、いくつかのタイ
トルが目に入った。1冊は特に━━━そのタイトルは、『霧中は価値が
あったのか?』なん冊かは、室へ持って行って、読みたかった。本は、
2・5クレジット。1クレジット10セントで計算すると、妥当な値段
だ。
同じように、窓ガラス代とホテル代の、100クレジットは10ドル
は、かなり、リーズナブルだ、いや、ほとんどバーゲンだった。ほとん
ど?いや、正真正銘のバーゲンだ。もしも今夜これから、42番通りの
霧中へ出て行けと言われたら、室代に1000ドルでも、持ってるクレ
ジットすべて払うだろう。
小さなミステリーに気づいた。彼がよく知ってることは、42番通り
の南側、6番通りとブロードウェイのあいだには、ホテルはなかった。
特に、安い、このようなホテルは。つまり、彼がいた場所には、いかな
るホテルもここにはなかった。だから━━━
彼は、あれがどうしたという考えはやめて、デスクにいる事務員に従
った。登録カードにサインした。財布から100クレジット紙幣を出し
て、さらに、その上に50クレジット紙幣を置いた。
彼は言った。「読むために、ポケットブックを2・3冊ラックからも
らうつもり。釣りは取っておいて!」それは、換算すると、事務員に4
ドルプラスチップを渡したことになる。
「ええ、サンクス、ミスターウィントン、これが鍵、307号室、3階
正面。階段で上がれば、すぐ分かる。日没で鍵を閉めるので、ベルボー
イはいない。オレはガードマンとして、ここにいなければならない」
ケイスは、うなづいて、鍵をポケットに入れた。彼は、歩いて、本と
雑誌のラックに戻った。
最初に、『霧中は価値があったのか?』を取り上げた。間違いなく、
読みたい本の筆頭だった。彼は、ほかのタイトルも目で追った。なん冊
かは馴染みがあり、なん冊かは馴染みがなかった。
HGウェルズの『歴史の概要』は、すぐにつかんだ。その本から、知
りたいことの多くを得られるだろう。
3冊目は?フィクションが多かったが、彼が欲しいのは、もっとフレ
ッシュな肉だった。情報を、たっぷり届けてくれるなにか。
気づいたのは、ドッペルというだれかの名前の本が、6冊あった。前
にどこかで、ドッペルを見た?そう、ニューヨークタイムズで、地球の
宇宙艦隊の将軍だった。
『ドッペル、その人』『ドッペル、そのストーリー』『ドッペル、宇
宙のヒーロー』そのような、あと数冊。
ラックのノンフィクションコーナーは狭かったが、なん冊もドッペル
についての本があるということは、ドッペルは、知っておくべき人物だ
ということだった。『ドッペル、そのストーリー』を取り上げた。書い
たのは、ポールガリコと知っても驚くことではなかった。
彼は、取り上げた本を高く掲げて、取り上げた本がなん冊なのか、事
務員が分かるようにして、すぐ階段に向かった。また、なん冊か取り上
げたい、あるいは、彼がすでに持っている2冊の雑誌にまた雑誌を追加
しようとする誘惑に負ける前に。2冊の雑誌は、グリーンビルで買った
もので、表紙とタイトルページは、彼が見たことのない出来栄えだった。
夜の残り、どんなに浅く読むことになろうとも、眠る時間が、どんな
に少なくなろうとも、全力を尽くしても読めないくらいの本の量があっ
た。
読む本がどんなに興味深くても、最初少し眠っておくべきだった。3
階まで上がるのに息切れがして、とても疲れていることに気づいた。ケ
ガした肩が、今までより痛んだ。さらに、右手のナックルが、悪魔のよ
うに痛み出した。ガラスで傷ついてなかったが、打撲傷になって痛み、
右手の指を曲げることができなかった。
廊下の薄暗い明かりで、室を見つけ、中へ入り、明かりをつけた。き
れいで、居心地の良さそうな室だった。ベッドは歓迎するように置かれ
ていた。それを、切望して見つめたが、ベッドにもぐりこむ前に、買っ
た本からいくつか学んでおく必要があった。そのいくつかが、今夜、グ
ランドセントラル駅を去るという大まちがいやってしまったようなこと
から、明日、彼を救ってくれるかもしれなかった。大まちがいから、生
き残れたのは、ただ運が良かっただけだった。
◇
ローマは、暗転は完璧だったが、シカゴと同じ道をたどった。しかし、
幸運にも、そのアルク船は、ローマを破壊した船だったが、ドッペルに
捕まって、数名の生存者を残すのみになった。メッキーという、だれか、
あるいはなにかの干渉によって、(『霧中は価値があったのか?』の著
者は、読者はメッキーについては知っていると仮定しているため、説明
は省かれていた)船に生存していたアルクトゥルス人から分かったこと
だが、彼らは検出器をもっていた。検出器は、未知の光線、それも光で
はなく、電子的熱線の発射によって検出する。
彼らは、光がビルの内部を照らすように、検出器を通して、都市を発
見することができた。それは、イプシロン光線は、ラジオ波のように、
ビルの内部を透明にしたからだ。
しばらくの間は、地球の都市を安全にするには、ろうそくやガス灯の
時代に逆戻りするのが唯一の方法だと思われた。(電気的光は、昼間に
室内を照らす明かりとして使う分には安全だった。それは、太陽光線が、
イプシロン光線を、大気中に出て行く前に、消散させてしまうからだっ
た)
しかし、ドッペルは、退官して研究室に戻ってから、その問題を研究
し続けた。彼は、イプシロン光線の性質を発見し、日々発行される論文
誌に載せ、彼の研究を世界中の科学者に発表した。彼からの要請は、太
陽光が昼間、イプシロン光線を消散させるように、夜でもイプシロン光
線を消散させる方法を見つけることだった。
ドイツの学者が、すでに発見されていたものだったが、実際的解決法
を示した。イプシロンガスによって、霧中を形成するというものだった。
それは、現在、連邦地球会議によって、人口10万人以上の全都市に要
求されている。
それは、実際、奇妙な性質の実体で、カートエビング教授の発見だっ
た。無臭で、動物や植物に無害で、光もイプシロン光線も通さなかった。
コールタールから安価に製造できた。1つの工場で、数時間あれば製造
できて、毎晩、空気と混合させることで、都市を完全におおい隠すこと
ができた。そして、夜明けに、太陽光が、10分か15分で消散させた。
霧中の発見によって、アルク船は、非常線を突破しても、地球の主要
都市は、攻撃されなかった。霧中が働いたのだ。
しかし、12の小さな都市が攻撃された。アルク船が、彼らの検出器
が見つけた最大の都市を攻撃対象にすれば、12の大きな都市が救われ
た。12の小さな都市の損失と12の大きな都市の損失━━━それは霧
中がなかったからだったが━━━のバランスの問題だった。示されたこ
とは、霧中は、おそらく1000万の命を救い、あるいは、犠牲を最小
限に抑えた。ニューヨークやロンドンは、もしも霧中がなかったら攻撃
されていただろうから、多くの命が、1000万の最低値の数十倍が救
われた。
◇
しかし、霧中は、生命を奪う面もあった。ほとんどの主要都市の警察
は、増大する犯罪集団と戦うには無力だということを認めた。霧中に覆
われた場所では、ほとんどの大都市の通りは、日没後は、無人の場所と
なった。ニューヨークでは、警察が、夜間パトロールをやめる前に、5
000人の警察官が殺された。
別の方法が試され、失敗した。
状況は、犯罪に特化した戦闘集団がつぎつぎに現れて、さらに悪化し
た。いわゆる、犯罪の第3世代が屈服したサイコシス集団。
大都市の多くは、特に、パリやニューヨーク、ベルリンでは、夜の秩
序を守る、あらゆる試みを、ついには、すべて放棄した。暗くなれば、
ギャングや犯罪者たちは、自由だった。尊敬できる市民は、外出は避け、
家にいた。公共輸送サービスは、機能を停止した。
奇妙なことに、だが、ラッキーなことに、犯罪のほとんどは、戸外で
の略奪に制限されていた。侵入盗は、霧中以前より増えることはなかっ
た。ドアや窓の鍵を締めて、在宅する市民は、かつてより危険ではなか
った。都市犯罪のほとんどを占める、いわゆる、霧中のサイコシスの性
質は、濃い怖ろしい闇の中で行われる略奪を要求しているように見えた。
ひとり狼の犯罪と、ギャングのものがあったが、ギャングがもっと悪
かった。あるギャングは、ニューヨークの夜歩き、ロンドンの血まみれ、
モスクワのレーニー(ケイスは、読んでいて、これってレーニンから?
と思った)は、専門的技術で高度に組織化されていた。
大都市では、夜に数百人が殺された。状況は、襲われたり殺されたり
するのは、家にいる正直な市民よりは、不良やよたものだという事実を
除けば、さらに悪くなった。
霧中は、本が指摘しているように、宇宙からの攻撃から都市を守るた
めの代償だった。たぶん、100万人が霧中の犯罪で殺された。しかし、
最低でも1000万の命が、疑いもなく、救われた。霧中ゆえに、12
の炎の地獄で焼かれ、シカゴやローマは、小さな、代償となった都市で
あった。『霧中は価値があったのか?』イエス、と著者。少なくとも、
900万人にとって、おそらくは、それより多い人々にとって。
ケイスは、『霧中は価値があったのか?』を置くと、少し震えた。も
しも、この本をグリーンビルで買っていたら、列車の中で読んで、グラ
ンドセントラル駅を去ろうとするよりは、もっと賢明な知識を得ていた
だろう。そこで小屋を買って、もしも小屋が売り切れなら、床の上で眠
っていただろう。
まさに明らかなことだが、ブロードウェイの夜の生活は、彼が前にい
た場所とは、まるで違っていた。
窓のところに歩いて行って、立って見た。そう、正確には外ではなく、
窓ガラスの向こうの、何もない黒を見た。カーテンは下まで引かれてな
かったが、1階の窓でなければ、問題はなかった。
数フィート先の外は、明かりのついた窓ひとつ見えなかった。薄気味
悪い黒だった。1度も外へ出てなかったら、それを信じなかっただろう。
42番通りの闇で、今、起ころうとしていることは、タイムズスクエ
アから半ブロックのところだが、宇宙の中心なのか?
うつろに当惑しながら、彼は、頭を振った。犯罪者が42番通りを乗
っ取っている!紫の月の住民が、グリーンビルのメイン通りをブラつい
ている!アイゼンハワー将軍が、地球艦隊金星部門担当で、アルクトゥ
ルスとの戦争を指揮している!
彼は、なんて、ファマドユニヴァースにいることか!
6 暴走ミシン
そう、この宇宙がどうであれ、彼はここにいて、なんとかやって行か
なくてはならない。ロープをうまく使いこなせるようになるまでは、つ
ぎつぎに危険な目に遭うだろう。毎回、なにかするか言うかして、致命
的にならないように危険を回避しなくてはならない。
回避しても、安全だとは言い難い。まったく挑発もしてないのに、見
たら殺せとスパイの疑いを掛けられるところでは。自分の無知ゆえに、
暗くなってから、グランドセントラル駅からタイムズスクエアへ歩こう
として、危うく殺されそうになるようなところでは。
もっと起きていて、少しでも読んでおくことにした。
決然として、HGウェルズの『歴史の概要』を手にした。今まででか
なり疲れていたので、座っていられず、ベッドに横になって読むことに
した。もしも、眠ってしまったら、それでも、朝、昼間のニューヨーク
に出て行く前に、少しは読めるだろう。そして、昼間のニューヨークが
どうであれ、夜のニューヨークよりは、過ごしやすいはずだ。
枕を折って、頭の下に置いて、HGウェルズを読み始めた。最初の章
は、ざっと読んで、キーになる言葉だけ注意して、あとでなんどでも戻
れるようにした。
彼は、たまたま、数か月前に、同じ本を読んでいて、とても馴染みが
あった。再読になるが、今まで読んだところは、まったく違いがなかっ
た。写真さえ、いっしょだった。
ディノサウルス、バビロン、エジプト人、ギリシア人、ローマ帝国、
シャルルマーニュ、中世、ルネッサンス、コロンバス、アメリカ、アメ
リカ革命、産業革命━━━
宇宙へ。
最初の章の9/10のところだった。ざっと読むのをやめて、数ペー
ジ戻って、ちゃんと読むことにした。
1903年、ハーバード大学のアメリカの科学者、ジョージヤーレイ
教授は、スペースワープドライブを発見した。
偶然に!
彼は、いろいろな物を使って、実験していた。そのときは、壊れて、
捨てるつもりの、妻のミシンだった。なんとかミシンを動かそうとして、
踏み板を踏んでいた。踏み板は、小さな家庭用の発電機になっていて、
物理クラスの実験に使えそうな、高周波の低い電圧の電流を作れた。
彼は配線を済ませた。ラッキーなことに、彼は、あとで、どう配線し
て、どこで間違えたか思い出すことができた。踏み板を踏んで作業を始
めると、予想外に、足が床にぶつかり、イスからもう少しで前に落ちそ
うになった。
ミシンは、踏み板も発電機もすべて、そこにはもうなかった。
著者のウェルズは、ユーモラスに、教授がこのときしらふだったのか
どうか指摘してるが、すぐに撤回した。その後、彼がしらふのとき、妻
の新しいミシンを借りて、注意深く、踏み板を踏み外した発電機を複製
した。このときは、前に配線を間違えた箇所に気づいたが、同じ間違い
をするように、慎重に、配線をした。
踏み板を踏んだ━━━すると、新しいミシンは消えた。
◇
彼がなにをしたのか分からなかったが、なにかをしたことは分かった。
◇
自分の銀行口座から預金を降ろし、新しいミシンを2台買った。1台
は、妻の裁縫用、もう1台は、最初の2台がやったことを、正確にやり
直すために。
今回は、目撃者を呼んだ。大学の学長に、学部長もいた。目撃者であ
るとは、言ってなかった。ただミシンを見てくれと言っただけだった。
彼らは見ていた。そして、ミシンは、そこに、もはや存在しなかった。
それが、手品ではないことを確認させるのは、容易ではなかった。し
かし、学部長の妻のミシンに同じことをして、妻の裁縫室からミシンが
消えてしまったのを見て、やっと確認した。みんなは、彼がなにかをや
ったことを認めた。
学部長たちは、ヤーレイの担当する授業数を減らして、さらなる実験
ができるように、財政的に援助した。彼は、さらに6台のミシンを失く
したが、もう、ミシンを使うのはやめて、必要最小限の物だけに集約さ
せることにした。
分かったことは、必要な物は、ぜんまい式モーターで、特別なつなぎ
方をして、発電機に間違ってつながっていることだった。踏み板は、本
質的でなかったが、電動モーターが発電機を動かして、なにかをキャン
セルして、物が働かないことが重要だった。糸巻きも、はずみ車も必要
なかったが、ボビンケースは必要だった。さらに、それが鉄で作られて
いる必要があった。
電気が発電機を動かすことを除いて、別のことでできるか試した。足
で踏み板を動かしたり、ぜんまい式モーターではなく、水車や息子のお
もちゃの蒸気エンジン(息子には新しいのを買ってあげた)を試した。
そして最終的に、比較的シンプルなレイアウトの箱に、必要なものを
集約できた、箱はミシンより安かった、安価なおもちゃの巻き上げ式モ
ーターが動力源で、全部合わせて5ドルにならなかった。数時間あれば、
作れた。
することは、モーターを巻き上げ、レバーを押す、それだけで、箱は
どこかへ飛んで行った。どこへ飛んで行ったのか、なぜ飛んで行ったの
か、彼には分からなかった。しかし、実験を続けた。
それから、ある日、最初、隕石だと思われたもののニュースが流れた。
シカゴの高層ビルの側壁に、なにかが突き刺さった。その後の調査で、
そこには、木製の箱と、奇妙な一揃いのぜんまい式モーターと電気機材
が残されていた。
ヤーレイは、つぎの列車でシカゴへ行き、彼が作ったものであること
を確認した。
彼がそのとき知ったのは、物体が宇宙を旅したこと、なにかを動かす
ことができたことだった。物体がシカゴのビルにぶつかった時間をだれ
も計測してなかったが、時間はほとんどかかってなかった。ヤーレイは、
こう結論した。物体がケンブリッジからシカゴまで旅した時間は、近似
的にゼロだったと。
大学は、彼の助手を増やし、彼は精力的に実験を始め、かなりの数の
物体を放出した、それぞれにシリアル番号を付けて、さまざまな変数の
正確な記録をつけた。巻き上げ数や、ぜんまい式モーターの正確な回転
数、箱が向いていた方向、そして、秒の端数まで正確な、消えていた時
間。
また、彼のしていることを公表し、世界じゅうの人に知らせた。
送った数千のうちで、2つが報告された。記録を比較することで、本
質的なことが分かった。1つは、マシンは、正確に、発電機の軸の方向
へ旅したこと。2つ目は、巻き上げ数と旅した距離に関連があること。
今、彼は、本格的に、仕事をすることができた。1904年までに、
彼が結論したことは、マシンが旅した距離は、発電機の端数まで含めた
回転数に比例し、旅に要した時間は、実際上、正確に、ゼロ秒だった。
また、発電機を指ぬきサイズまでに小さくすることで、マシンを、数
マイルのような、比較的短い距離で送ることができた。町の外の野原に
着陸させられた。
それは、ふつうに考えたら、革命的な輸送手段だったが、マシンは、
着地の際に、かならず、内部的にも、外部的にも、本格的なダメージを
負っているという事実があった。ふつうは、残されたものはわずかで、
識別のためにも十分でなく、多く残されることは、めったになかった。
武器にすることもできそうになかった。爆発物は、決して、届かなか
った。途中で爆発して、ワープ中にどこかへ行ったに違いなかった。
やがて、実験を始めて3年の間に、現象を表す方程式が見つかり、背
景の原理が理解され、結果を予測できるようになった。
物体が破壊される理由は、旅の終わりに、物体が急に、空気中で、物
質化されるからだと結論された。空気は、かなり物質的な存在である。
移動するものがなんであれ、ダメージを与えることなく、空気のかなり
の量を、0秒の間に、移動させることはできない。物体としてダメージ
を与えるだけでなく、分子構造にまでダメージを与えてしまう。
明らかに、物体を送り込めて、無事に到着できる、唯一の具体的な場
所は、宇宙だった。なにもない、宇宙だった。
キューブの巻き上げ数を増やせば、飛行距離を増やせるので、月や他
の惑星に行くのにさえ、大きなマシンは必要なかった。
恒星間旅行も、とんでもない怪物ではなかった。特に、物体は、何度
か中継点で、ジャンプできて、そこですることは、パイロットがボタン
を押すことだけなので、時間も掛からなかった。
さらに、時間はゼロ時間なので、軌道を計算する必要はなかった。単
純に、目標にねらいを定め、距離パラメータを調整し、ボタンを押せば、
そこにいて、惑星から安全な距離の宇宙空間に物質化され、あとは、降
下と着陸の準備をするだけだった。
もちろん、月が最初のターゲットだった。
着陸方法の検討に、数年要した。気体力学は、まだよく知られてなか
った━━━ライトという名のふたりの兄弟が、キティホークNCで数年
前に、空気より重いマシンを浮かせることに成功したが━━━同じ年に、
実際、ヤーレイ教授が最初のミシンを失った。そしてなにより、月には
空気があるとは、思われてなかった。
しかし、着陸の問題が解決され、1910年、月に最初の人間が着陸
して、安全に、戻って来た。
居住可能な惑星には、すべて、翌年までに到達した。
◇
つぎの章は、惑星間戦争だった。しかし、ケイスは、それ以上読めな
かった。朝の3時半だった。長い1日だった。多くの物事が、彼に起こ
った。単に、目をあけていられなかった。
すでに脱いでいた服より多く、脱ぐことはしなかった。ただ、明かり
に手を伸ばして、スイッチを切った。頭が枕に戻る前に、すでに眠って
いた。
目覚めたのは、正午近くだった。目をあける前に、少し横になったま
ま、とんでもない夢のことを考えていた。宇宙旅行のできる世界、それ
もミシンで、アルクトゥルスと戦争、ニューヨークが霧中。
寝返りを打つと、肩の傷がひどく痛んだ。それで、目をあけた。頭の
上の見慣れない天井。それが、ショックで、完全に目覚めた。ベッドの
上に座り、腕時計を見た。11時45分!仕事に数時間も遅刻!
あるいは?
ひどく混乱して、方角を見失った。ベッドから出て、奇妙なベッドだ
った、窓のところへ歩いて行った。そう、彼は42番通りにいた、3階
で、いつもの通りの景色を眺めていた。ふつうの交通量で、歩道の混み
具合もいつも通り、ふつうの服を着たふつうの人々だった。それは、彼
の知るニューヨークだった。
あれは、夢だったに違いない、あのすべてが。しかし、そのとき、ど
のようにして、彼は42番通りにいる?
そこに立ったまま、困惑しながら、ニューヨークにいる、物事の経緯
を思い出そうとした。現実にあった、思い出せる最後のシーンは、ボー
デン氏の庭園でイスに座ってる場面だった。そのあと━━━
思い出せる以外の方法で、ニューヨークに戻って来たのだろうか?旅
の記憶としてよみがえって来るのは、悪夢の記憶だった。もしもそうな
ら、精神科医に診てもらった方がいい。
彼は正常でないのだろうか?そうに違いない。だが、なにかが彼に起
こった。受け入れがたいものを受け入れるのでない限り、どうやってボ
ーデン氏の別荘からニューヨークに戻ってきたのか、分からない。ビレ
ッジにある自分のアパートに戻らないで、アップタウンのホテルに泊ま
っているという事実も、説明がつかなかった。
彼の肩も、かなり痛かった。手を置いて、シャツの下に巻いた包帯に
触れた。傷ついているが、悪夢で見たような奇想天外な方法では、決し
てないだろう。
よし、ここを出ることにしよう。家に帰ってみないと、その後の計画
が立てられない。まず、家に帰る、それから決めよう。
向きを変え、服を置いてあるイスに歩いて行った。ベッドの脇の床に
あるものに気づいた。HGウェルズの『歴史の概要』ポケット版だった。
拾い上げて目次ページをひらくときに、少し手が震えた。最後の3つ
の章のタイトルを見た。宇宙へ、惑星間戦争、アルクトゥルスとの戦争。
本は、手から滑り落ちた。それを拾おうとして、ベッドの下に半分潜
り込んでる別のを見つけた。『霧中は価値があったのか?』というタイ
トルだった。
イスに座って、しばらくなにもできなかった。あれは悪夢ではなかっ
た、現実だったという事実に向き合うために、あれこれ考えていた。
あるいは、合理的なそのコピーを。
自分が正気を失ったか、すべてほんとうに起こったことなのか、どち
らかだった。紫モンスターに追い掛けられた。野蛮なジャングルの霧中。
イスに掛けたズボンのポケットに手を伸ばして、財布を取った。中に、
クレジット紙幣が入っていた。ドル紙幣でなかった。1000クレジッ
トちょっとあった。
考えながら、ゆっくり服を着て、窓のところに戻った。そこは、依然
として、42番通りで、いたって普通に見えた。今、それは、彼をだま
してなかった。それが、昨夜の1時ではどう見えたかを思い出して、少
し震えた。
そこを見ながら、さっきは気づかなかったものを捜した。店の並びは、
ほとんど馴染みがあった。しかし、いくつかは奇妙で、以前はなかった
と、ほぼ断定できた。
さらに、人混みの中に、紫のフラッシュを見つけた。紫モンスターだ
った、ふつうに、通りを渡って本屋へ入って行った。通りの別の人と同
じで、だれも注意を払わなかった。
彼は、深くため息をついて、出発の準備をした。『歴史の概要』に
『ドッペル、そのストーリー』を詰め、2冊のパルプ雑誌をいろいろな
ポケットに入れた。『霧中は価値があったのか?』は置いて行くことに
した。必要なものだけにして、きのうのニューヨークタイムズもいらな
い。
階段を降りて、ロビーを抜けた。別の事務員が受付にいて、彼の方を
見もしなかった。正面ドアの前で、一瞬立ち止まって、ガラスが新しく、
端が新しいパテで固定されているのに気づいた。
今、完全に目が覚めて、空腹だった。食べることは、ビジネスの第一
歩だった。きのうの正午から、なにも食べてなかった。東へ歩いて、公
立図書館へ曲がる角に、小さなうまそうなレストランを見つけた。
横にある一人用の小さなテーブルについて、メニューを調べた。12
の料理からの選択だった。3つ以外は馴染みがあった。その3つはリス
トの最後に置かれた高級料理だった━━━火星リゾット、マルセイユ風。
ローストクライル、カピソース添え。ガリーラ、ルナ風。
最後の料理は、彼のスペイン語から、意味は、月のチキン。いつか、
月のチキンや火星リゾットやローストクライルを食べるだろうが、今は、
あまりに空腹すぎて、試していられなかった。シチュー料理を注文した。
シチュー料理は、1つには、集中がいらなかった。食べているあいだ、
『歴史の概要』の最後の2章をざっと読んだ。
◇
HGウェルズは、惑星間戦争については手厳しかった。それを、侵略
者地球による侵略戦争とみなした。
月や金星の住人は、友好的で扱いやすく、いいように使われた。背が
高い紫のルナンの知能は、野蛮人程度だったが、とても素直だった。彼
らは、優秀な労働者になった。また、最初に、機械作業の要領を教えれ
ば、いいメカニックになった。工場で働けるようになると、賃金を貯金
して、地球見学に来たが、長くは留まれなかった。2・3週間が、地球
で彼らが健康でいられる最大時間だった。同じ理由から、彼らを地球で
雇うことは実際的でなく、労働者として地球で雇われた数千人のルナン
が、数か月で死亡したあと、法律で禁止された。
ルナンの寿命は、ルナでは20年くらいだった。それ以外の地球、金
星、火星、カリストでは、だれも、6か月以上は生きられなかった。
金星人は、地球人と同じくらいの知能があったが、まったく違う性質
を持っていた。もっぱら、哲学や芸術、抽象代数に興味を持っていて、
地球人を歓迎した。文化やアイデアの交流に熱心だった。実際的な文明
はなく、都市を持たず(家さえも)、所有の考えがなく、機械も武器も
なかった。
人口は少なく、流浪の民だった。精神活動を別にすれば、動物と同じ
に、原始的に暮らした。金星での地球人の植民地化や侵略に問題はなく、
労働力が足りないときは、あらゆる手助けをしてくれた。金星に4つの
植民地を作り、100万弱の人々が暮らした。
しかし、火星は違っていた。
火星人は、植民地化されたくないという愚かな考えを持っていた。彼
らは、分かったことだが、オレたちと同レベルの文明を持っていた。し
かし、宇宙旅行を発見してなかった。それは、おそらく、服を着ること
はなく、ミシンもなかったからだった。
火星人は、地球からの最初の訪問者に、おごそかに、礼儀正しく、あ
いさつし、(火星人は、なに事にも、おごそかだった、また、ユーモア
のセンスはゼロだった)そして、家に帰って、そこに留まるよう言った。
2回目と3回目の訪問者は、殺された。
3つのチーム(最初のを除いて)が乗っていた宇宙船を拿捕したが、
それらを使おうとしたり、機械をまねしようとはしなかった。火星を離
れる気はまったくなかった。事実、ウェルズが指摘するように、惑星間
戦争のあいだでさえ、火星を生きて離れた火星人は、ひとりもいなかっ
た。
生きたまま捕えられ、展示や火星の研究のために地球船に乗せられた
少数の者たちは、船が火星の薄い大気を離れる前に、自ら命を絶った。
自らの惑星を離れては、たとえ数分でも生きる意志はなく、生きられ
ないことは、火星の動植物にも及んだ。火星の動植物の、たった1つの
種でさえ、地球の動植物園で展示されたことはなかった。
いわゆる惑星間戦争は、それゆえ、もっぱら火星の表面で戦われた。
それは虚しい結果で、火星人の人口は、指数累乗で減少していった。し
かし、絶滅寸前に降伏し、地球人による火星の植民地化を許した。
太陽系におけるすべての惑星や衛星のうち、4つのみ━━━地球、月、
金星、火星━━━が、知的生活に適していると判明している。土星は、
奇妙な形のプラント生活が可能だった。木星のいくつかの月でも、プラ
ント生活が可能で、野生動物がいた。
人類が、激しい戦い、知的生命体との植民地戦争に直面したのは、太
陽系を出て行ったときだった。アルクトゥルス人は、数世紀前から、恒
星間ドライブを持っていた。彼らが、太陽系の惑星を訪れてなかったの
は、広大な銀河の、単なる偶然だった。やつらが、オレたちに気づいた
のは、プロキシマケンタウリの近くで出会ったことによる、すぐさま、
やつらの見逃しを修正にかかった。
アルクトゥルスとの現在の戦いは、たまに招集可能な攻撃的戦略も含
まれるが、地球側の防衛戦だった。ずっと戦いは手詰まりで、どちらの
側も守備的戦略が、相手のどんな攻撃もブロックするのに適していた。
両サイドとも、たまに防衛ラインを越えてくる船が、相手にダメージを
与えられるだけであった。
幸運にも、戦争初期に拿捕した数隻のアルク船によって、頭初あった
数世紀の技術的遅れを、地球は、すぐに取り戻すことができた。
現在、ドッペルの才能とリーダーシップのおかげで、戦いは基本的に
消耗戦ではあったが、地球は、少し有利だった。
◇
ドッペル!また、出て来た。ケイスは、HGウェルズを置いて、『ド
ッペル、そのストーリー』をポケットから出そうとした。そのとき、食
べ終わってからずいぶん経つのに、追加注文もしてないことに気づいた。
食事代を払って、店を出た。通りの向かいの図書館の階段が、彼を呼
んでるように見えた。そこに座って、先を読むことはできる。
しかし、仕事のことが気になった。
彼は、ボーデン出版社に、ここでも、今も、勤めている?もしそうで
も、月曜の朝は休んでも、許されないことはないだろう。1日休んだら、
まずいだろうが。
すでに、1時をかなり過ぎていた。
実際に姿を見せる前に、電話して、できるだけ情報を得ておくべき?
それをするには、論理的に、微妙な問題があった。
つぎの角にある、タバコ店に入った。電話ブースの前に、短い列が出
来ていた。列に並ぶか迷いながら、硬貨のない世界で、電話代の支払い
をどうしているのかという些細な疑問の答えが分かった。彼の前の電話
を掛けた者は、それぞれ、電話ブースを出るとキャッシュレジスターの
前で、電話ブースの上に表示された料金だけ、紙幣で支払いを済ませる
と、ボタンを押して、レジスターはゼロに戻った。
グリーンビルのドラッグストアでも、おそらく、電話ブースの上に料
金は表示されていたのだろう。それに気づかなかったから、彼の電話は、
まだ清算されてなく、電話ブースの上の料金は残されたままなのだろう。
運良く、列の前で長電話する者はなく、数分でブースに入れた。
ボーデン出版社の番号を、ダイアルした。待ってるあいだに、ああだ
ったら、こうしようとか、いろいろ考えたことを心に留めながら、彼の
知ってる番号が違うこともあり得る。
しかし、受付のマリオンブレイクの声のようだった。
「ボーデン出版社」
ケイスは言った。「ミスターウィントンは?ミスターケイスウィント
ン?」
「いいえ、サー、ミスターウィントンは不在。どちらさま?」
「気にしないで!明日、また、電話する」
彼女がまた質問して来る前に、急いで、電話を切った。彼の声は、気
づかれてないことを望んだ。気づいたようには、見えなかった。
キャッシュレジスターで半クレジット払った。そして、この半クレジ
ットを、もっと価値あるものできたし、そうすべきだったと、今、気づ
いた。ケイスウィントンは、ランチに出ているのか、町の外に出ている
のか訊くべきだった。あるいは、どこにいるのか分からないのか。しか
し、列の最後にまた並ばない限り、もう遅かった。
そして突然、彼はそこを出て、最悪なことを見つけようと急いだ、そ
れがどんなに危険なことであろうと。
急いで数ブロック歩いて、ボーデン出版社が10階のすべてのフロア
を占めるオフィスビルに入った。
上りのエレベータに乗り、出るときに一度深呼吸した。
7 カリストカクテル
彼がいつも、そう称賛している、馴染みのある美しいドアの前に立っ
た。それは、かなり現代的なものの1つで、取っ手は未来的なクロム製、
1枚のガラスでできたドアだった。蝶番は、隠れてるか見えないか、ど
ちらかだった。ボーデン出版社の文字は、ちょうど目の下の高さで、小
さく簡潔に、黄色の活字で、厚いガラス内部に正しく吊るされていた。
ケイスは、取っ手をとても慎重に取り、いつもそうするように、なに
もない美しいシートに指紋が残らないように、ドアをあけ、中へ入った。
マホガニー製の同じレールがあり、壁には、同じ狩猟の絵があった。
そして、同じ太った背の低いマリオンブレイクが、とがらした赤の唇、
巻き上げたブルネットの髪で、レールの後ろの速記タイピスト兼受付の
デスクに座っていた。彼女は、あれ以来、彼が出会った、最初の知って
いる人間だった━━━なんと、それは、たったの、きのうの夜7時から
だった。なん週間にも思えた。めまいがすると、レールの上でジャンプ
して、マリオンブレイクにキスしてしまいそうだった。
馴染みのある物や馴染みのある場所は見たが、まだ、馴染みのある人
には、今まで会ってなかった。確かに、『サプライジングストーリー』
(2クレジット)の目次のページにある住所は、ボーデン出版社が、ま
だ、ここにあって、同じビジネスを続けていることを物語っていたが、
実際に、マリオンブレイクが受付であることを見るまでは、まったく、
信じられなかった。
その瞬間、彼女のいつもの姿を見て、オフィスのすべてが記憶通りで
あるという事実が、過去18時間の記憶に疑いを持たせた。
あれは、あり得ないし、単純に、あり得なかった。
そのとき、マリオンが、こちらに振り返って見たが、彼に気づいた様
子はなかった。
「はい?」と、彼女。少し、イライラしたように。
ケイスは、咳払いをした。彼女は、からかってる?彼を知らない?あ
るいは、冗談のふりをしている?
彼は、また、咳払いをした。「ミスターケイスウィントンは?彼に会
いたいのだが」
彼女に投げたギャグで、彼女が、すぐ笑えば、彼も笑い返せる。
彼女は言った。「ミスターウィントンは、今日は外出中、サー」
「うう、ボーデン氏は?いる?」
「いいえ、サー」
「べティ━━━ミスハードレイは?」
「いいえ、サー。1時には、ほとんどの人が、帰った。それが、今月の
通常終了時間なので」
「通常━━━うう」
良く知ってるものを疑って、ヘマをする前に、彼は自制した。「忘れ
てた」と、彼は不完全に終えた。なぜ、午後1時が通常終了時間なのだ
ろう?なぜ、今月なのだろう?
「それなら、明日来る。ミスターウィントンにうまく会える時間は?」
「7時ごろ」
「7━━━」危うく、彼女の言葉を繰り返すところだった。朝の7時、
それとも、夜の7時?朝に違いない。夜の7時は、霧中の時間だ。
そのとき急に、答えが分かった。こんな簡単なことが、なぜ、すぐに
分からなかったのか不思議に思った。
当然、霧中のある都市によって、労働時間は異なるだろう。夕暮れの
あとは、通りから人が消える都市もあれば、ふつうの夜の生活のない都
市もある。労働時間は、労働者の私的生活を守るために異なっているだ
ろう。安全を守るために、暗くなる前に、十分余裕をもって、帰宅しな
ければならないため、物事は、完全に違ったものになるだろう。仕事は、
朝の6時か7時から━━━夜明け後1時間か、太陽光がミストを分解し
たあとから━━━午後の1時か2時までになるだろう。そうすることで、
夜と同じに昼を、人々にレクリエーション時間として与える。
もちろん、そうあるべきだった。本で霧中について読んだときに、な
ぜ、そこまで気づかなかったのだろう?
これは、いいニュースをもたらした。ブロードウェイは、かならずし
も、彼が思っていたようにすたれてしまってなかった。ショーやダンス、
コンサートも、夜の代わりに、昼に行われているのだろう。たぶん、マ
チネーは、昼でなく、朝、上演されてるのだろう。ナイトクラブの代わ
りに、アフタヌーンクラブがあるのだろう。
みんなは安全に家に帰れる、たとえば、7時や8時までに、そして、
4時か5時まで眠って、夜明けまでに起きて、服を着る。
夜明けや夕暮れは、1年を通じて、同じ時間には来ないから、労働時
間も1年の季節に応じて、変わって来る。これが、今月は1時が終了時
間となる理由だった。たぶん、それは、地方の条例で定められていて、
マリオンは、彼は当然知っていると思ってたのに、知らなかったので驚
いたように見えたのだ。
マリオンは、帰る準備をして、物を彼女のデスクの引き出しに入れて
いた。彼がまだそこにいたので、驚いたように、顔を上げた。
彼は言った。「あんたの名前は、ブレイク?マリオンブレイク?」
彼女の目は、少し大きくなった。「なぜ、そうだけど、しかし」
「あんたのことを思い出したが、正しいか確信がなかった」と、ケイス。
マリオンが自分の話をしたこと、友人のことや、どこに住んでるとか、
なにをしたとかを急いで思い出そうとした。
彼は言った。「友人の名前は、エステラ、苗字は忘れた、ダンスホー
ルで、オレたちを紹介してくれた。クィーンズだった?」彼は少し笑っ
た。「オレは、その夜、エステラといっしょだった。おかしなことに、
彼女の苗字は思い出せないのに、一度しかダンスしてないあんたの名前
は両方思い出せる」
彼女は、そのおせじに、彼に、えくぼを見せた。彼女は言った。「あ
なたの言うことはきっと正しい、わたしは覚えてないけど。クィーンズ
に住んでるし、そこのダンスホールに行った。エステラランボウという
友人がいる。記憶がごっちゃになってるんだと思う」
「オレの名前は、忘れているだろうと思った」と、ケイス。「数か月前
のこと、オレはカールウィンストン。あんたの印象は強かったらしい、
それで、出版社に勤めていると言ったことを覚えていた。出版社の名前
は忘れた、ここに来て会えるとは思ってなかった。あんたは、詩を書い
ていると言ったのを覚えている」
「詩とは言ってない、ミスターウィントン、ただの韻文、それだけ」
「カールと呼んで」と、ケイス。「オレのことを覚えてなくても、前か
らの友人だ。今から帰る?」
「そうだけど、なぜ?1時過ぎから2通の手紙をタイプした。ボーデン
氏が、2通とも終えたら、明日の朝、30分遅れてもいいと言ったから」
彼女は、デスクの上の時計を見てから、悲しそうに笑った。「取引には
応じたけれど、手紙は2通とも長くて、1時間かかった」
「とにかく、あんたに会えてうれしい」と、ケイス。「1杯、いっしょ
にどう?」
彼女はためらった。「そう、1杯だけなら。2時半までにクィーンズ
に戻らないと、デートがあるので」
「良かった」と、ケイス。彼女にデートがあって都合が良かった。1杯
飲む間に、いくつか知りたいことを聞き出せるし、午後じゅういっしょ
にいる気はなかった。
エレベータでいっしょに降りて、マリオンに店を選んでもらった。そ
の店は、マディソンにある小さなバーで、前に来たことはなかった。
カリストカクテルをいっしょに飲みながら、(マリオンが注文したあ
とで、ケイスも同じものを注文した。甘すぎたが、飲めないことはなか
った)彼は言った。「あの夜に言ったと思うが、オレは作家で、いろい
ろ今まで書き溜めて来たが、これからパルプ雑誌に書いて行こうと思っ
ていて、少し書いている」
「それで、オフィスに?」
「そう、ウィントンとしゃべりたかった、あるいは、ボーデン氏やミス
ハードレイに。今、書いてもらいたい題材とか、長さとか訊くために」
「それなら、わたしでも少しは話せる。西部劇や探偵ものは、かなり在
庫がある。ミスハードレイは、彼女のラブストーリーのために短編を捜
している。冒険ものなら、短編でも長編でも使ってくれるはず」
「サイエンスフィクションは?一番オレに合っている」
マリオンブレイクは、驚いて、彼を見た。「どうして、それを?」
「どういうこと?」
「ボーデン社は、サイエンスフィクション雑誌を始める予定」
ケイスは、ポカンと、口をあけた━━━そして、足をその中に入れて
しまう前に、閉じた。なにごとにも、驚くべきでなかった。カリストカ
クテルを、ゆっくり、すすってから、考えた。どこかに、ワナがあった。
なぜ、マリオンは、ボーデン社は、サイエンスフィクション雑誌を始
めると言ったのだろう?すでに、ボーデン社は、『サプライジングスト
ーリー』を発行していて、その証拠に、ポケットに1部入っている。そ
の出版社は、ボーデンだと確認している。なぜ、マリオンは、ボーデン
社は、別のサイエンスフィクション雑誌を始めると言わなかったのだろ
う?
理由は分からなかったが、彼は、慎重に、答えた。「そんな噂を聞い
た。ほんとう?」
「ほんとうだけど、大丈夫。すでに最初の号は、できていて、あとは印
刷するだけ。季刊発行で、秋号から出す。スタンドでよく売れれば、月
刊にする。原稿を募集していて、最初の号は、メインノベルが1つに、
短編が1つか2つ。それを越えるものを欲しがっている」
ケイスは、うなづいて、ひと口すすった。「サイエンスフィクション
分野を、どう思う?」と、彼。
「サイエンスフィクション雑誌は、もっとずっと前に出すべきだったと
思う。雑誌で読めない、唯一の、最も重要な分野」
ケイスは、何げなく、後ろのポケットに手を伸ばし、『サプライジン
グストーリー』の丸めた雑誌を取り出した。それは、グリーンビルで買
ったもので、先に、ニューヨークタイムズや『霧中は価値があったのか
?』やHGウェルズを読む必要があったので、まだ、読んでなかった。
マリオンがそれについてどう言うか聞きたいので、何げなく、テーブ
ルの上に置いた。ボーデンが、まだ、サイエンスフィクション雑誌を出
していないと言った直後だった。
彼女の顔に近づけてよく見せ、雑誌の表紙越しに彼女を見ていた。
彼女は言った。「一番売れている、冒険小説を読んでいたのね」
それは単純なことだ、とケイスは考えた。答えは、じゅうぶん予想で
きたはずだった。惑星間ドライブや恒星間戦争、紫モンスターがすでに
ふつうの世界で、そのような話は、冒険ものであっても、サイエンスフ
ィクションでは、全くない。
しかし、そのような話が単なる冒険なら、サイエンスフィクションは
どうなるのだろう?彼は、心のメモに、サイエンスフィクション雑誌を
買うチャンスがあったら、真っ先に買おうと記した。それは、ほんとう
に読みたいものだった。
彼は、『サプライジングストーリー』を見ていた。「いい雑誌だ」と、
彼。「そこに書いて載せたい」
「ミスターウィントンは、原稿を必要としている。明日の朝、来れば、
喜んで会うと思う。見せられるストーリーはある?」
「まだ、完成版はない。いろいろアイデアはあるのだが、見せる前に、
彼と会って話したい。間違ったふうに書きたくないので」
「ミスターウィントンは、ご存じ?ミスターウィントン?あなたの名前
は、似すぎ!ケイスウィントン、カールウィンストン。たぶん、あまり
良くない」
彼は、この疑問に先に答えた。「いや、ミスターウィントンに会った
ことはない。そう、ふたりの名前は似すぎている、同じイニシャルだし。
オレは、カールはKと書く。しかし、なぜ良くない?」
「ペンネームのように聞こえる、ただ、それだけ。つまり、カールウィ
ンストンのストーリーがケイスウィントンの雑誌に現れたら、多くの読
者は、同一人物が、薄く偽装したペンネームで書いていると思い始める。
それに、たぶん、彼は、そう思われるのが好きじゃない」
ケイスは、うなづいた。「それは、分かる。いずれにせよ、あまり重
要でない、小説は別の名前で書くので。メインのものは、自分の名前で。
ゴーストライターをする場合を除いて。小説用のペンネームは、すでに
決めてある」
彼は、ほとんど具合が悪くなるほど甘いカリストカクテルを、すすっ
てから、決してお代わりしないと決めた。
彼は訊いた。「ついでに、ケイスウィントンについて教えて!」
「なぜ、そんなことを?」
彼は、あいまいに、ジェスチャーした。「彼のことが知りたいだけ。
誰に似ている?朝食はなにを?編集者として、どのくらい辛抱強い?」
「そうね」と、マリオンブレイク。考えながら、顔をしかめた。「背が
高い、あなたより少し。スレンダー。暗い。シェルぶちメガネをしてい
る。30くらい、と思う。まじめそうな見掛けをしている」急に、くす
くす笑った。「最近、いつもより、真剣そう、でも、それを責められな
い」
「なぜ?」
彼女は、いたずらっぽく、笑った。「彼は、恋してるらしい」
「あんたに?」
「わたし?こっちを見たこともない。違う、新しいラブストーリーの編
集者、ウルトラ美人のミスハードレイ。それは、彼にとって、もちろん、
良いことでない」
ケイスは、理由を知りたかったが、「もちろん」が彼に警告した。
「もちろん」を使うとき、相手は、すでに知ってることを前提にしてい
る。彼はすでに、ケイスウィントンは知らないと言ってしまっているが、
ベティハードレイは知ってるとは言ってなかった。しかし、ベティハー
ドレイと恋に落ちることが、ケイスウィントンに良いことをもたらさな
いことを知っていると、なぜ思われるのだろう?
マリオンにこのまましゃべらせておけば、訊かなくても、理由が分か
るかもしれない。
「彼が辛抱強いところは、どう?」と、彼。
「今から言う」アリオンは、深くため息をついた。「ギー!、世界中の
女の子は、ベティハードレイと、歯と右手を交換したいと思ってるわ」
彼は、なぜと訊けなかったので、獲物をそのまま泳がせた。「あんた
も?」と、彼。
「わたし?からかってる?ミスターウィントン?偉大なフィアンセがい
るのに?スマートで、ハンサムで、勇敢で、もっともロマンティックで、
ああ」
「うう」と、ケイス。少し元気なく。
ドリンクの残りを飲み干した。ほとんど吐きそうになった。指でウェ
イトレスに合図して、ブースに来たとき、マリオンに訊いた。「もう1
杯?」
「時間がないからいい」彼女は腕時計を見た。「今のが半分あるから、
お代わりは、あなただけどうぞ。わたしはいらない」
ケイスは、ウェイトレスを見て言った。「マンハッタン1杯、プリー
ズ」
「ソリー、信じられないが、それを今まで聞いたことがない!新しい飲
み物?」
「マティーニは?」
「それなら、ある、ブルー?それともピンク?」
ケイスは、肩が重くなった。「ウィスキーのストレートは?」
「もちろん!お好みのブランドは?」
彼は、頭を振った。これ以上、悩まされたくなかった。ウィスキーが
ピンクでもブルーでもないことを願った。
振り返って、マリオンを見た。もっと彼女にしゃべらせて、ベティハ
ードレイのフィアンセが誰なのか言わせられるだろうか?見掛けでは、
知ってるふりをしていた。そんなふうに、彼は知っていたのだ。なにか、
怖ろしい疑念が、やって来た。
「ギー!」彼女は、つぶやいた。「ドッペル!」それは、敬虔に響いた、
まるで祈りのように。
8 メッキー
そう、ケイスは考えた、最悪なことを知ってしまったと。とにかく、
彼女は婚約していて、結婚は、まだだった。おそらく、チャンスは、ま
だある、どんなにわずかなチャンスだとしても。
マリオンは、また、ため息をついた。彼女は言った。「けれど、彼女
はバカだと思う、戦争が終わるまで結婚を延ばすそうよ。戦争がいつま
で続くか、分かりゃしない。編集者としての仕事も続けると主張したそ
うよ。ドッペルが、いくらだってカネを持っているというのに。それに
きっと、する仕事がなくなったら、どうかなってしまうと思う。うう、
ドッペルを待っているだけで、どうかなってしまいそう、仕事があって
も」
「あんたは、仕事をゲットした」
「しかし、ドッペルはゲットしてない」マリオンは、自分のドリンクを
ひと口すすり、ため息を深くついた。ケイスは、彼女がほかの客の注意
を引いてしまうんじゃないかと心配した。
ケイスのウィスキーが来た。色は、琥珀色で、ブルーやピンクでなか
った。さらに、ひと口飲んでみて、ウィスキーのような味がするだけで
なく、本物のウィスキーだと確信した。グラスをゆっくり置くと、マリ
オンはカリストカクテルの最後のひと口を飲み終えたところだった。そ
れが彼を、すごくではなく、少しいい気分にさせてくれた。
マリオンは、立ち上がった。「行かなくては」と、彼女。「おごって
くれてありがとう、ミスターウィントン。明日、オフィスに?」
「明日か、つぎの日に」と、ケイス。訪問するときには、ストーリーも
持って行こうと決めていた。すぐに準備できるなら、2つか3つ。すぐ
に持って行けば、どう書き直したらいいかも分かる。
◇
マリオンを地下鉄の駅まで見送り、それから、公立図書館へ向かった。
行きたかったのは、そこではなく、さっき出て来たバーへ戻りたかった。
あるいは、別の店に入って、1杯やりたかった。しかし、常識は、それ
は致命的だと彼に告げた。たぶん、文字通りに、致命的だった。彼は、
まったくのしらふの時でも、ここで、トラブルを抱えていた。
さらに、すでに、2発の辛いパンチを受けていた。1つ目は、彼には
仕事がなかった。ボーデン社のケイスウィントンは、彼でないというだ
けでなく、彼に似てさえいなかった。同じ年ではあったが、それだけだ
った。2つ目は、ベティハードレイは、婚約しているというだけでなく、
信じられないくらいロマンティックなだれかと、婚約していた。それが、
信じられなかった。
図書館では、2階の一般読書室へ行って、空いたテーブルの1つに座
った。本は借りに行かなかった。午後じゅう掛けて読める以上の読み物
が、すでに、あったし、読む前に、これからのプランを立てたかった。
ポケットにある、買ってあったが、まだ読んでない3冊の読み物を出
した。『サプライジングストーリー』と『パーフェクトラブストーリー』
とポールガリコの『ドッペル、そのストーリー』。
彼は、ポケット版に顔をしかめた。ドッペルについては、ほとんど聞
いたことも本で読んだこともなかった。それは、この奇妙なところに来
て、まだ、20時間もたってなかったからだった。その男が、彼のポケ
ットに全太陽系を入れているのだ。実際に、彼は、そこを走りまわり、
そして、ベティハードレイも手に入れていた。
その本を取り上げたが、また、置いた。一度読み始めたら、全部読み
たくなって、今日の午後、全部使っても足りないだろう。
パルプ雑誌の編集者でなかったので、なにか書いて生計を立てなけれ
ばならない、今すぐに書き始めなければならない。グリーンビルで得た
カネが残っているが、すごく長くは続かない。
生計を立てるアイデアは、この2つの雑誌、あるいは別の雑誌を調べ
て臨時に学ばなければならない。
最初に『サプライジングストーリー』を取り上げた。もくじのページ
を開いて、彼の記憶にある7月号のもくじと比較した。すべての作家は、
同じで、同じ順番だった。ストーリーのタイトルは、いくつかは、同じ
で、いくつかは、違った。
読み始める前に、パラパラめくって、イラストを見た。イラストのそ
れぞれは、表紙で気づいたのと同じわずかな違いがあった。それらは、
同じアーティストによって描かれていた。あるいは、同じ名前の同じス
タイルを持ったアーティストによって。しかし、それらは、もっと鮮や
かで、もっと躍動感があった。娘はもっと美しく、モンスターはもっと
恐ろしかった。恐ろしく、身の毛もよだった。
短編の一番短いものから読み始めた。注意深く、分析しながら。プロ
ットは、覚えているのと同じだった。しかし、設定と周りの環境に違い
があった。読み終えたとき、気がついたアイデアは、まだ、曖昧なまま
だったが、それが、かすかに輝いていた。
イスに座って、数分、考えて、アイデアは、明らかになった。ほかの
ストーリーは、きちんと読まなかったが、ざっと読んで、プロットやキ
ャラクターではなく、設定とバックグランドに注意を払った。
アイデアは正しかった。これらのストーリーと実際に自分で発行した
記憶にあるものとの違いは、バックグランドと設定が、すべて一致して
いることだった。それぞれの作家は、火星人の記述は同じで、金星人も
同じだった。宇宙船も、すべて同一の原理で動いていた。それは、HG
ウェルズの本で読んだものと同じだった。宇宙戦争を扱ったストーリー
は、初期の惑星の植民地化における地球・火星戦争か、現在の地球・ア
ルクトゥルス戦争を扱っていた。
マリオンブレイクの言ったことは、『サプライジングストーリー』を、
サイエンスフィクションでなく、冒険雑誌に分類する点で、正しかった。
バックグランドは、このとんでもない宇宙で、本物であり、状況や設定
も、本物で、互いに一貫性があった。
冒険物語だった、純粋に、シンプルに。
彼は、本をテーブルに叩くように置いたので、図書館のほかの者たち
から、とがめるような視線を受けた。
しかし、と彼は考えた、サイエンスフィクション雑誌は、ここにもあ
るに違いない、そうでなければ、ボーデン社がそれを始めようとしない
だろう。そして、これらのストーリーが、みんなサイエンスフィクショ
ンでないなら、なにが、サイエンスフィクションなのだろう?それを、
何冊か買って、解明したい。
彼は、ドッペル本を取り上げて、また、苦い顔をして見た。ドッペル!
彼は、その男を憎んでいた。しかしとにかく、その名前をどう発音する
のか分かった。マリオンが言うのを聞いたからだ。それは、フランス語
のドッペルのように、2音節のみで、後ろにアクセントがあった。
その本に顔をしかめて、憎みながらも、つぎに読む順番が来た。しか
し、ここで今読み始める?大きな図書館の時計を見上げて、やめておこ
うと決めた。まだ、しなければならない重要なことがあって、みんな、
暗くなるまでに、霧中の前にしておかなければならない。彼は、泊まれ
て、食べて行けるカネを稼げる仕事を捜さなければならなかった。今あ
る資金は、もっとカネを稼げる仕事が見つかるまで、手を付けないこと
にした。
財布を出して、グリーンビルのドラッグストアの店主がくれた200
0クレジット、だいたい200ドルから、いくら残っているか数えた。
ちょうど、半分残っていた。
注意して過ごせば、1週間は、じゅうぶん生活できる。
たしかに、もうそれ以降はもたないので、服を買ったり、洗面用品を
そろえたり、といったことで、新しく出直すしかない。
あるいは、この宇宙で、グリーンビルビレッジのグレハム通りの2L
DKのアパートに住んで、クローセットや服がいっぱいの衣装ダンスの
生活を始める?
その可能性を考えたが、あまりにわずかな可能性しかなかったので、
まじめに考えられないとして、却下した。ここのケイスウィントンは、
仕事もアパートも持っている。今までのことから、この宇宙は、彼にと
って、居心地のいい場所ではないことを知っていた。自分のために、な
にかしなくてはならない。当てにならない仕事になりそうだ。
しかし、自分はどこにいるのだろう?どうやって、やってゆく?なぜ?
そうした疑問符は、決然として、すべて脇に押しのけた。答えはある
に違いない。たぶん、元に戻れる方法も。しかし、生き残る方が先だっ
た。自由に、計画できなくてはならない。しかも、かしこい計画を。1
00ドルの価値のあるクレジットを、未来につなげるベストな方法とは?
彼は、よく考えて、計画を練った。しばらくしてから、図書館員のデ
スクへ行って、紙と鉛筆を借りて来た。自分のテーブルに戻ると、必要
なもののリストを書き始めた。その長さに、ぞっとなった。
それぞれのだいたいの値段も書いて、すべて合計すると、怖れるほど
の額にはならなかった。400クレジットでなんとかなりそうだった。
残りの600を生活費にあてられる。安いホテルに泊まって、高くない
レストランで食事すれば、10日はもたせられる。2週間でも行けそう
だった。
図書館を出ると、数時間前に電話を使った、タバコ屋へ向かった。
最初にしておくと良いのは、小さな可能性を排除しておくことだ、と
彼は考えた。電話帳でケイスウィントンを捜した。名前は登録されてい
て、番号も住所も同じだった。
ブースに入ると━━━今は、順番待ちの列はなかった━━━番号を呼
び出した。
声は言った。「こちら、ケイスウィントン」
彼は、静かに受話器を置いた。やはり、いた。
つぎに、一番近い雑貨店に向かい、買い物を始めた。手持ちのカネだ
けでやって行くなら、より好みはできなかった。初めに、厚紙製のスー
ツケースを買った。ここにある一番安いもので、29・5クレジットだ
った。リストに沿って、靴下、ハンカチ、髭剃り、歯ブラシ━━━
ガーゼに包帯、肩の傷用防腐剤、鉛筆、消しゴム、白紙を一束、黄紙
を一束━━━リストは永遠に続くように見えた。安い紳士用装身具店で、
数枚のシャツを入れたところで、スーツケースは、ほぼ一杯になった。
着ていたスーツは、クリーニング店で待っている間に、きれいにプレス
してもらった。
最後の買い物は、12冊のさまざまなパルプ雑誌だった。残ったクレ
ジットは、600を少し下回った。明確な目的を持って、パルプ雑誌を
選ぶのに時間を掛けた。
◇
最後の買い物を終える頃、外は、群衆が集まり始めていた。ドラッグ
ストアを出ると、歩道の端は、12インチの幅の線が引かれていた。通
りを1ブロック下ったあたりから、大きな歓声が聞こえて来た。
ケイスは、一瞬ためらい、ドラッグストアの窓を背に、そこに立った
ままでいた。なにが来るのか知りたかったが、カーブの近くまで出て行
っても、特に、スーツケースや雑誌が邪魔になるので、そこに立って、
群衆の頭越しに見ていた方が、よく見えそうだった。
なにか、あるいは、だれかが、近づいて来た。歓声は、近くなった。
すべての通行は止められて、カーブの向こうに押しやられていた。2台
の白バイが道路に沿って、併走し、背後に警官が乗った車がついて来た。
車の後ろの席にはだれもいなかったが、その空中に、車から10フィ
ート上空に浮かび、同じペースで移動する、なにかがあった。
それは、丸く、無表情の、バスケットボールより少し大きい、のっぺ
りした金属製の球体だった。
歓声は、それが近づいて来たとき、大きくなった。車のクラクション
が鳴り響き、騒音が耳をつんざいた。
歓声とは別の言葉が聞こえた。「メッキー、メッキー、メッキー!」
そして、彼のそばにいるだれかが叫んだ。「アルクをやっつけろ!メッ
キー!」
そのあと、信じられない事が起こった。
歓声の上か下に、ケイスは、突然、声を聞いた。それは、歓声でも、
叫び声でもなかった。静かでクリアな声が、すべてのところから聞こえ、
あるいは、どこからも聞こえてないかのようだった。
「おもしろい状況だ、ケイスウィントン」と、声。「いつか会いに来い、
いっしょにそれを調べよう」
ケイスは、暴力的になって、周りを見た。彼の近くのだれも、彼を見
てなかった。隣の男に向いて、その男を見た。
「今のを聞いた?」と、ケイス。
「聞いたって、なにを?」
「なにか━━━ケイスウィントンについて?」
「どうかしてる」と、その男。その男の目は、ケイスを離れ、通りにま
た戻り、声の限りに叫んだ。「メッキー、メッキー、光を!」
ケイスは、ビルからよろよろと出て、カーブで群衆が集まっていると
ころと、歩道の背後の群衆のあいだの狭いオープンスペースへと歩き出
した。歩くペースを、その車と車の上に浮かんでいるバスケットボール
サイズの物体のペースに合わせようとした。さっき彼に話し掛けて来た
のは、その物体だという奇妙な感覚を持った。
もしもそうなら、それは、彼を名前で呼んだ。彼以外だれも聞いてな
かった。そう考えると、声は外から来たのでは、決してなかった。頭の
内部で聞こえた。また、それは、フラットな機械的音声だった。人間の
声では、決してなかった。
彼は、どうかしてしまったのか?
あるいは、彼は、すでに、おかしかったのか?
しかし、いずれにせよ、説明がどうあれ、彼は、盲人の感覚を持った。
視力を失ったのではなく、バスケットボールの正体がなんであるかの盲
人の感覚。それは、彼を名前で呼んだ。
たぶん、それは、彼がここにいる答えを知っていたのだ。彼、ケイス
ウィントンが遭遇したような世界になにが起こったのかに関する、2つ
の世界戦争はあるが、惑星間戦争のない、まともな世界に関する、彼が
サイエンスフィクション雑誌の編集者で、それがここでは冒険雑誌で、
彼とは似ても似つかないケイスウィントンという名前のだれかが編集し
ている世界に関する、答えを知っていたのだ。
「メッキー!」群衆は叫んだ。「メッキー!メッキー!」
メッキーは、球体の名前に違いない。そして、たぶん、メッキーが答
えを知っていた。メッキーは、「いつか会いに来い、いっしょにそれを
調べよう」と言った。
いつかだと!答えがあるなら、今、知りたかった。
彼は、群衆の中へ、よろよろと出て行った。スーツケースが足に当た
り、にらまれたり、怒鳴られたりした。しかし、気にも掛けずに、歩き
続けたが、通りのクルマのペースには、すごく離されたのではないが、
追いつけなかった。
すると、声が、ふたたび頭の中で聞こえた。「ケイスウィントン」と、
声。「止まれ!ついて来るんじゃない!後悔することになる」
歓声より大きな声で、彼は叫び出した。「なぜ?」と、彼。「あんた
はだれ?」
すると、彼は、みんなが彼の声を聞いて、歓声より大きいので、じろ
じろ見られた。
「注意を引いてはダメだ」と、声。「そう、オレは、あんたの考えが分
かる。そう、オレはメッキーだ。あんたの計画を実行して、3か月後に
会おう!」
「なぜ?」と、ケイスは、絶望しつつ考えた。「なぜ、そんなに長く?」
「戦争に、危機が迫っている」と、声。「人類の生存は、崖っぷちだ。
アルクトゥルスが有利だ。今は、あんたに割ける時間がない」
「しかし、オレはなにを?」
「あんたの計画通りに」と、声。「それから、注意しろ!今までよりも
っと注意しろ!あんたは、どう行動しても、いつも危険にさらされてい
る」
ケイスは、答えを捜して特に知りたい質問には、絶望しつつ、心の中
でフレームで囲った。「だが、なにが起こった?オレは、どこにいる?」
「あとで」と、心の中の声。「あとで、あんたの問題を解決しようと思
う。今、答えは分からない、あんたの心を通じて、問題は、はっきり見
えているが」
「オレは、気が変?」
「いや、違う。また、致命的間違いは、1つもしてない。これは現実だ。
あんたの想像の産物ではない。ここでの危険は、現実の危険、この世界
は、現実だ。ここであんたが殺されれば、あんたは死んでしまう」
2回目の休止。「あんたのために割ける時間は、今ない。ついて来る
のはやめろ!」
突然、ケイスの心に、つぎの重要な質問をフレームで囲む前に、また、
ふたたび、彼が歓声やクラクションの騒音を聞く前に、沈黙の感覚があ
った。心の中のものがなんであれ、撤退してしまった。どう知ったのか
分からないが、さらなる質問を考えるのはムダで、返答は来なかった。
◇
最後の指示に従って、歩くのをやめた。あまりに急に立ち止まったの
で、だれかがドスンとぶつかり、怒鳴った。
彼は、うまくバランスを取り、その男が行ってしまうと、立ったまま、
群衆の頭の上を見た。球体は、浮遊しながら彼から去った、彼の生涯か
ら。
それは、なんだ?なんで、浮いていられる?生きているのか?なぜ、
彼の心を読める?
それがなんであれ、彼がだれか知っていたようだった。彼の問題のこ
とも、そして、解決できると言った。
それに去って欲しくはなかった。3か月も待つ?それは不可能だ。今、
その答えを知る、リモートチャンスがあるのに?
しかし、球体は、すでに、半ブロック先に行ってしまった。とても追
いつけなかった。歩道は群衆で溢れていて、スーツケースと腕いっぱい
に抱えた雑誌がじゃまになった。周りを見ると、タバコ店の前に来てい
た。
彼は、走って、タバコ店に入ると、入口近くのソフトドリンククーラ
ーの下に、雑誌とスーツケースを置いた。
彼は言った。「すぐに戻る。この荷物を見ててくれることに感謝する」
そして、店主がなにか言う前に、また走って店を出た。もしかしたら、
今、買ったばかりのものすべてを失うかもしれなかった。しかし、今は、
球体を追うことが、彼の生涯でもっとも重要なことだった。
外に出ると、先を急いだ。早足で歩きながら、容赦なく前を押しのけ
て進んだ。車や白バイから半ブロックまで追いついた。さらに、少し距
離を詰めた。
彼らは、3番通りで南に向きを変え、37番通りへと入り、さらに東
に向きを変えた。角を曲がるときに、彼は群衆に追いついた。白バイと
車は、群衆の端に停まった。
しかし、車の上に浮かんでる球体は、止まらなかった。歓声を上げる
人々の頭の上空へと上がっていった。通りの北側にある、アパートの4
階の開いている窓のところまで上がった。
女性が、窓枠にもたれて、窓から体を乗り出していた。ベティハード
レイだった。
ケイスウィントンは、群衆の端まで来ると、押しのけて先へ進もうと
しなかった。ビルに近づくより、ここからの方がよく見えた。
歓声は、猛烈だった。メッキーと叫ぶ歓声とは別に、ベティハードレ
イやドッペルへの歓声も聞こえた。ドッペルは、ここに?しかし、世界
の偉大なヒーローであるような人物は、見当たらなかった。群衆の目は、
メッキーという球体と、窓からもたれて笑顔のベティハードレイに注が
れた。彼女は、彼が今まで見ていた彼女より、ずっと美しく、ずっと希
望に満ちていた。
彼女は、ドレス姿で、彼が見たかった服だった、サイエンスフィクシ
ョン雑誌の表紙のヒロインのようなドレス、緋のブラは、完璧な半球体
を描き、(やはり、完璧な)肩や腕を露出させ、胴の中央、さらに、そ
の下━━━そう、彼は、そこにもなにか見た記憶があったが、今は、そ
れほどは窓から体を乗り出してなかったので、彼には描写ができなかっ
た。
球体は、ちょうど、ベティハードレイがもたれている、開いた窓と同
じ高さに浮かんで、彼女の白い腕から数インチのところで、ホバリング
した。それが、ベティハードレイを見ているのか、下の群衆を見ている
のかは、無表情の球体からは、ケイスには、推測できなかった。
それは、話した。このときは、最初から、群衆全体の心にであって、
彼ひとりにではないことが、ケイスには分かった。
歓声は、止まなかった。それにとっては、みんなに聞いてもらう必要
はなかった。言葉は、心を通じて聞こえ、耳からでなかった。人には、
歓声と球体の言葉と、両方が聞こえ、互いに干渉することはなかった。
「友よ」と、声。「オレの主人であり製作者でもあるドッペルから、ミ
スハードレイへのメッセージを伝えよう。当然、それは、プライベート
なメッセージになる。
あんたが受け入れてくれたことに、感謝する。主人からのこのメッセ
ージを、みんなに伝えよう。状況は、まだ、厳しい。全力を尽くさなけ
ればならない。勝利の望みはある。オレたちは、勝たなくてはならない
し、勝つだろう!」
「メッキー!」群衆は歓声を上げた。「ドッペル」「ベティ!」「勝
利!」「アルクトゥルスを倒せ!」「メッキー!メッキー!メッキー!」
ベティハードレイは、と彼は見た、まだ、笑顔で、群衆の歓声に顔を
赤らめた。彼女は、おじぎをもう1度して、頭と肩を窓の中へ引っ込め
た。球体は、彼女の後について、中へ入った。
群衆は、帰り始めた。
ケイスは、うめき声を上げた。球体に向って、投げつけたが、遅すぎ
たことが分かった。それが彼の考えを受け取ったとしても、なんの注意
も払わなかった。
そう、それは、彼に警告していた。彼の心の中に入り込めるのなら、
ベティハードレイへの思いにも気づいていて、それで、ついて来るなと
警告した。ベティハードレイの先程のような姿を見たら、彼がどう感じ
るかを知っていたのだ。それは、彼を痛みや絶望から救おうとした。
それは、それほどの意味はなかった。マリオンブレイクから、ベティ
は婚約していると聞かされていたからだ。実際に、結婚してない限り、
と彼は考えた、まだ、望みはある。彼女に、ドッペルをあきらめさせら
れると、彼はあえて考えた。
しかし、どれだけのチャンスがあるのだろう?重要なヒーローについ
て、彼が読んだり聞いたりする以上に、先程、見たような場面は、ドッ
ペルの人間性もすばらしいに違いないと思わせるに十分だった。「主人
であり製作者」と、奇跡の球体、メッキーは呼んでいた。そして、ニュ
ーヨークの歓声は、彼がそこにいないにも関わらず、ほめたたえていた。
彼、ケイスウィントンに、どれだけのチャンスが?この宇宙では、存
在してないも同然、非存在のさらに下の彼に、そのような男のフィアン
セを奪える?
9 ドッペル情報
彼は、モヤモヤしながら、スーツケースと雑誌を置いて来たタバコ店
に、歩いて戻って来た。それらはまだ、そこにあって、店主に、先程の
無礼を謝って、お詫びに、タバコ1カートンを買った。
通りは、先程タバコ店を出たときより、だいぶ空き始めていた。夕暮
れが近づいていて、泊まる場所を見つけなくてはならなかった。
40番通りの8番アベニューで、安いホテルを見つけ、120クレジ
ット前払いして、1週間、室を借りた。スーツケースと雑誌を室に置い
て、また、町に繰り出して、安いメキシコ料理店で食事すると、長い夜
を読書と勉強に費やすために、室に戻った。
パルプ雑誌の1冊を手に取った。彼の計画の有効性を調べるために、
もしも、テストする必要があるなら、球体のメッキーが、計画通りに進
めてくれというのは、正しいに違いない。
しばらく、長いしばらくだが、なかなか集中できなかった。ベティハ
ードレイの顔が、金髪のオーラを持って、滑らかでクリーミーな肌、キ
スしやすそうな赤の唇、そんな場面を思い描いていた。窓で彼が見たよ
うな、ベティハードレイの美しい体を語るまでもなく、形がピッタシの
緋のブラを着ていた(彼が語れるのはそこまで)
ついて来るなという球体の命令に、なぜ、彼は従わなかったのだろう?
このようなムードに浸って、今までよりも、もっとクリアに考えること
ができるときに。
長い間、ベティは、彼と雑誌のあいだを行き来していた。彼女への望
みのなさが、なにをしてもうまくゆかずにムダに終わるように思われた。
しかし、やっとしばらくしてから、自分のことは脇において、読むこと
に集中し始めた。そして、望むことが、実際、実現可能かもしれないと
思え始めた。
そう、彼は、生活のために書けるようにすべきだった。これらのうち、
いくつかの雑誌のために、たとえ、他がダメでも。5年前、ボーデン社
で働き始める前、ケイスは、フリーランスで作家活動をしていた。多く
のストーリーを売ったが、売れないものもかなりあった。
実際、平均打率は、フィフティフィフティだった。それほど多産では
なく、プロットを考えるのも楽ではない作家にとって、50対50は、
あまり良くなかった。その上、ストーリーはなかなかやっては来ないし、
汗水たらして、生み出さなければならなかった。そんなときに、編集の
仕事が来たので、思わず跳びついてしまった。
しかし今、5年編集をやってみて、前よりももっといいストーリーを
書けると思えた。今、彼の間違いの多くがなんだったか、分かっている。
特に、怠惰が良くなかった。しかし、怠惰は、治療可能だ。
さらに、このとき、彼には出発点としての、プロットがあった。その
すべてが、売れなかったストーリーのプロットだった。今、それらを、
5年前より、もっとうまく書ける。かなり良くできる。
彼は、買った雑誌を、積み上げて、すべてのストーリーをざっと読み、
いくつかは、ちゃんと読んだ。外は暗くなり、霧中のなにもない黒が、
窓ガラスに貼り付いた。彼は、読み続けた。
1つのことが、だんだん、明らかになった。それは、彼には、今の彼
のまわりのような馴染みのない世界を、ストーリーの設定にすることが
できないし、あえて、したくないということだった。彼は、間違いをす
るだろう、大きくはないが、小さな間違い、ここでの生活の詳細に馴染
みがないことから来る、見当違いを犯すだろう。現在の時代のストーリ
ーは、明らかに、不向きだった。
幸運なことに、まだ、2つの分野が残されていた。HGウェルズの
『歴史の概要』を読んだので、ここでのすべての相違は、1903年に、
ミシンが消えたことから起こったことを彼は知っていた。1903年以
前の服装や土地を舞台にストーリーを書けば、彼にとっての確かな土台
となるだろう。ラッキーなことに、大学で歴史を習っていたし、18世
紀や19世紀の、特にアメリカの歴史は、かなり得意だった。
パルプ雑誌は、かなりの割合を、歴史ストーリーやその衣装ものに割
いていることに、注目した。それは、彼の前の世界のパルプ雑誌よりも、
ずっと高い割合だった。たぶん、その理由は、ここでは、今日の生活が、
植民地や開拓時代の生活とは、大きな違いがあったからだ。18世紀や
19世紀の設定は、冒険雑誌のいくつかでは、よく使われる設定だった。
『サプライジングストーリー』は、その例外で、現代の宇宙の冒険物に、
もっぱら特化していた。それとバランスを取るために、ボーデン社は、
別のパルプ雑誌、『ロマンティックアドベンチャーストーリー』を出し
ていて、それは、市民戦争や革命戦争といった歴史物に特化していた。
それの編集も、ケイスウィントンであることにも、注目した。
恋愛物のパルプ雑誌でさえ、ラブストーリーのかなりの割合を歴史的
設定で書かれていることに驚き、それを学ぶことがうれしかった。それ
は、彼が予想もしなかった分野で、書けそうなのが、3分野あった。
もうひとつは、もちろん、サイエンスフィクションだった。3つのサ
イエンスフィクション雑誌を調べて、それらについては、間違いようが
なかった。それらは、遠くの未開拓の銀河の冒険物語だったり、遠い未
来や、あるいは、遠い未知の過去の物語だったり、タイムトラベルや、
心の未知の力の物語だったり、歴史的設定での狼バンパイアの純粋なフ
ァンタジーものさえあった。彼は、この土台では、安全だった。
10時に、雑誌の調査を終えた。それから深夜まで、室の小さなデス
クに座って、鉛筆を手に、前に紙を置いた。今は、まだ、書かない、そ
のためには、タイプライターが要る、今まで書いて売れなかった、すべ
てのストーリーのメモを書き留めておく。
彼が思い出せるのは、その夜の時間では、20のストーリーだった。
あとで思い出せるものは、ほかにもあった。20のうち、6つは、歴史
的冒険や恋愛物だった。6つのうちの4つは、短く、比較的すぐに書き
出すことができるものだった。ほかの6つは、歴史的設定やファンタジ
ーに変えることがかなり簡単だった。
12のストーリーは、タイプライターが手に入り次第、すぐにでも書
き始められた。12のうち1つか2つが、すぐに売れれば、彼は、なん
とかなりそうだった。もちろん、いつまでもストーリーの書き直しばか
りしてられない。遅かれ早かれ、新しいものへ向かい始めなければなら
ない。しかし、編集での経験が、スタートさえ切れれば、新しいものを
書いて行けると思えた。売れなかったストーリーの後ろ盾によって、爆
発的スタートが切れるだろう。
彼が文無しになる前に、ストーリーが1つも売れなかったら、そう、
ポケットにある硬貨を売る可能性を調べなければならない。25セント
硬貨が、グリーンビルでは、2000クレジットをもたらした。しかし、
同時にそれは、彼を、危険なワナに陥れた。同じことを再びすれば、ま
た、同じ危険を犯すことになる。落とし穴が、どこにあるか調べること
が先決だった。
深夜になって、あまりに眠く、売れなかったストーリーのプロットを
思い出せなくなった。しかし、したいことのすべては、まだ、終わって
なかった。ポールガリコの『ドッペル、そのストーリー』を取り上げた。
◇
さて、ライバルがどんなやつなのか、知るときが来た。
ライバルは、つぎの1時間で分かったのは、はなはだしいを越えた、
言語に言い尽くせないやつだった。あり得なかった。
ドッペル(ファーストネームがあるようにはまったく見えない)は、
ただ、信じられなかった。つぎの人物の最高のキャラクターをすべてあ
わせ持ち、悪いキャラクターは一切なかった。ナポレオン、アインシュ
タイン、アレクサンダー大王、エジソン、ドンファン、ランスロット。
年令は、27だった。
彼の生涯の最初の17年間の描写は、簡潔だった。彼は、学校では輝
かしく、多くの学年を跳ばし、17才でハーバードを優等で卒業した。
大学の生徒会長で年少にも関わらず、人気者だった。
天才は、ふつう有名にはならなかったが、ドッペルは例外だった。勉
強は、まったくしなかった。大学で秀でていたのは、読んだり聞いたり
したことをすべて完全に記憶している能力による。勉強する必要が、ほ
とんどなかった。
授業のタイトなスケジュールにも関わらず、(大学の授業を取れるだ
け取っていた)不敗を誇るフットボールチームのキャプテンを務めた。
大学に通いながら、自分流の仕事をして、それによって、金銭的に独立
していた。暇な時間に、6つの冒険小説を書いて、1度、ベストセラー
になり、その分野の古典的作品として、今も位置付けられている。
これらの本で稼いだカネで、(すべては、もちろん、映画化されて大
ヒットした)自分用のプライベート宇宙船と研究所を所有し、大学の最
後の2年間、宇宙旅行と宇宙戦争における、いくつかの重要な技術的改
良を行った。
それは、ドッペルが17才のことで、比較して言えば、ただのふつう
の若者だった。彼のキャリアは、そのとき始まった。
彼は、ハーバードから宇宙飛行士訓練センターに進み、中尉から始め
て、1年少しのあいだに、跳び級で階級を上げた。21のとき、逆スパ
イの指令を受けて、アルクトゥルス太陽系にスパイとして潜入し、生き
て帰った、ただひとりの人間となった。アルクに関する、地球の知識は、
ほとんどが、彼がその旅で持ち帰ったものだった。
彼は、とても優秀な宇宙戦士であり、宇宙飛行士だった。そのとき、
ふたたび、彼の宇宙艦隊は、アルクトゥルス攻撃に向かった。ドッペル
は、艦隊を指揮すると同時に、先頭に立って戦った。彼の優秀な科学的
知識ゆえに、将軍たちは、彼に戦闘には参加しないように、個人的に懇
願した。しかし、そのときまでに、すでに、将軍たちより上だったが、
彼は、チャンスがあれば、かならず戦った。彼は、しかし、魅力的な人
生を歩んでいるように見えた。彼の明るい赤の宇宙船、ベンジェランス
号は、弾が当たることがなかった。
23のとき、彼は、地球防衛軍の総司令官になった。しかし、彼の行
動には、総司令官であることは、あまり重要でなかった。危機のときを
除いて、総司令官を別の者に委任して、自分の時間を、スパイ活動のエ
キサイティングな冒険や、月にある秘密研究所で働くことに費やした。
その月での彼の研究によって、地球が、アルクトゥルスより技術的に同
じか、少し先を行くことを可能にした。
彼がその研究所で達成したことのリストは、ほとんど信じ難かった。
中でも最たるものは、たぶん、機械知能、メッキーを作り上げたこと
だろう。メッキーの中に、ドッペルは、人間を越える精神的パワーを入
れた。メッキーは、人間ではなかった。しかし、彼は、(ガリコは、メ
ッキーは形式的には『それ』だが、あえて、いつも『彼』と呼ぶと指摘
している)ある意味、人間を越えた、スーパーヒューマンだった。
メッキーは、心を読むことができ、テレパシーを使って、人と、個人
的に、あるいは、集団的に話すことができた。彼は、さらに、狭い範囲
では、アルクトゥルス人の心を読めた。人間のテレパスたちは、それを
やったことがあったが、決まって、見つけたものを報告する前に、頭が
おかしくなってしまった。
また、メッキーは、電子計算機が解を出せるような問題の、どんなに
難しくても、すべての要素を与えてやれば、解を導くことができた。
メッキーの中には、テレポーテーション能力が組み込まれていて、宇
宙船に乗る必要なしに、宇宙のどこでも自由に、瞬時に、移動できた。
これが、彼を密偵として価値あるものにした。ドッペルに、彼がどこに
いても、宇宙艦隊および地球政府と常に接触することを可能にした。
手短かに、触れる程度に、本の終わり近くで、ガリコは、ドッペルと
ベティハードレイとのロマンスを語っていた。ふたりは、婚約し、互い
に深く愛し合っているが、戦争が終わるまで結婚は待つことを決心した。
また、ミスハードレイは、その業界でもっとも人気のあるラブストー
リー雑誌の編集者としての仕事を続ける。その仕事は、彼女とドッペル
が出会い、恋に落ちたときにしていたものだった。そのとき、彼は、お
忍びで、ニューヨークにスパイの仕事で来ていた。今、全世界は、ふた
りを愛し、戦争の終結とふたりの結婚を、心待ちにしていた。
ケイスウィントンは、本を置くと、のろった。彼がベティハードレイ
を愛することより、望みのないものがこの世にあるだろうか?
しかし、ある意味、まさに、物事の望みのなさが、彼に望みを与えて
いた。カードは、彼に対して、そんなに悪く積まれていることは、たぶ
ん、ないだろう。どこかで、チャンスが生まれるかもしれなかった。
◇
寝ようとして、服を脱いだのは、1時を過ぎていたが、ホテルのフロ
ントに電話して、6時に起こしてくれるように言った。明日は、忙しい
日になりそうだった。それは、1週間後も彼が食べて行けるかどうかが、
掛かっていた。
彼は眠り、かわいそうなまぬけ、ベティの夢を見た。ベティの服は、
(多かれ少なかれ)37番通りのアパートの窓で見た彼女と同じで、別
の世界の荒れ果てた不気味な景色を横切って、昆虫の眼をした、両側に
それぞれ9本足で、太さ1ヤードの触覚のある、40フィートのモンス
ターに追い掛けられていた。
ただ、そのあと、夢の混ざり合う機能によって、彼、ケイスは、ベテ
ィを追うグリーンのベムになり、彼女をもう少しで捕えられるときに、
邪魔が入った、背が高く、さっそうとした、ロマンティックな若い男性
で、その筋肉は鋼鉄製で、一見、エロールフリンに見えたが、ドッペル
に違いなかった。
ドッペルは、ケイスウィントンであるグリーンのモンスターをつまみ
上げ、言った。「アルクトゥルスに帰れ、スパイめ!」そして、宇宙の
かなたへ投げた。そこでは、彼は紡ぎ車で、(全部で18あった)惑星
のあいだ、恒星のあいだのなにもないボイドに頭を出していた。猛スピ
ードでベルが鳴る感覚が、耳にあった。音はどんどん大きくなり、アル
クトゥルス人であることをやめて、電話のベルだと気づくまで続いた。
電話に出ると、声は言った。「今は6時、サー!」
また横になることも、眠りに戻ることもせずに、ベッドに座って、し
ばらく、考えて、夢を思い出していた。それは、結局、彼に起こってい
ることに比べたら、ぜんぜんバカらしくなかった。
ドッペルは、なにに見えた?夢では、エロールフリンに見えた。似て
ないと、なぜ言える?たぶん、ドッペルはエロールフリンだった。その
ことを忘れなかったら、そこで、エロールフリンがいるかどうかを調べ
ればいい。
いなくても、驚かないだろう。
現実の亜空間の1つに迷い込んだのは、ファンタスティックな映画か
ストーリーか本だということもあるのではないか?そうでないと、なぜ
言える?ドッペルは、と彼は考えた、あまりに完璧すぎて、現実のキャ
ラクターとしては、あまりにファンタスティック過ぎた。パルプ雑誌か
ら出て来たなにかだとしても、妥当なものでなかった。まともに考えた
ら、どんな編集者でも、これほどありえないキャラクターが登場するス
トーリーは、受け入れないだろう。コミック本の精神的レベルを越える
ものを出しているどんな編集者でも、ドッペルをキャラクターとして受
け入れないことは、確かだった。
彼がいるこの宇宙が、フィクションとしてもあまりに奇妙すぎるなら、
どうやったら、現実として受け入れられる?
だが、彼とは少し接触しただけの、機械知能メッキーは、このような
考えを予想しているだろうか?『━━━致命的間違いは、1つもしてな
い。これは現実だ。あんたの想像の産物ではない。ここでの危険は、現
実の危険、この世界は、現実だ━━━』
メッキーは、メッキーの存在自体がファンタスティックだが、今、彼
が考えていることを、予想しただろうか?メッキーは正しかった。この
宇宙は、彼が置かれた地点は、じゅうぶん現実であり、それを疑うなら、
もっともいい証明は、逆に、今この瞬間の、空腹、朝食を食いたいこと
だった。
服を来て、外へ出た。
◇
朝、6時半のニューヨークの通りは、彼がいた世界の10時か11時
の混みようだった。短い昼間は、霧中によって、必然的に早いスタート
となった。
新聞を買って、朝食を食べるあいだに読んだ。
ビッグニュースは、もちろん、メッキーがニューヨークに来て大歓迎
されたことだった。第一面の4分の1を使った写真が出ていて、あいた
窓の外の空中に球体が静止し、ベティハードレイが窓に持たれて、群衆
におじぎしていた。
10ポイント太字の囲み記事は、メッキーが群衆にテレパシーで語っ
た言葉で、そこにいたケイスも頭の中で聞いたのと同じだった。『友よ、
オレの主人であり製作者でもあるドッペルから、ミスハードレイへのメ
ッセージを伝えよう━━━』
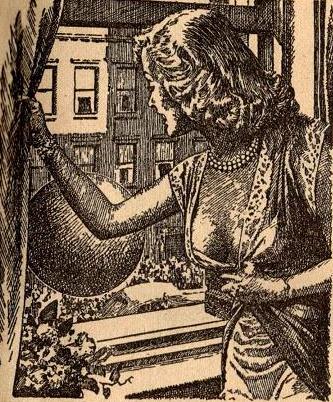
そう、一字一句。見たところ、それは、機械知能が伝えた、唯一の公
のメッセージだったらしい。1時間後には、ニュースとして宇宙の彼方
にまで伝えられた。
新聞の残りも、ざっと読んだ。戦争の記事はなかった。メッキーが
(個人的にケイスに)語ったような戦争の差し迫った危機についての記
述はなかった。
もしも戦況が悪かったら、明らかに、それは公にはされない。メッキ
ーが彼に話したことが軍事上の秘密であったら、メッキーは彼に話す前
に、彼の思考をざっと調べて『おもしろい状況だ、ケイスウィントン』
ケイスは、秘密を、彼が望んでも、外に漏らすような立場にはいないこ
とを知っていたからだ。
家庭欄に、硬貨を持っていたことで、5000クレジットを得た男の
記事が興味深かった。注意して読んだが、なぜ硬貨を持つことが違法に
なるのかの答えはなかった。心のメモに、もしも時間ができたら、すぐ
に、公共図書館で硬貨について調べようと記した。しかし、今日ではな
い。今日は、することが、すでに、あまりに多かった。
1つは、タイプライターを借りることだった。
レストランを出る前に、電話帳で、一番近いタイプライターのレンタ
ルショップの場所を調べた。
ケイスウィントンの名前を使い、財布にあった身分証で、保証金なし
で1台借りられたので、ホテルの室に運んだ。
彼の生涯で、もっともハードな1日の仕事に取り組んだ。
それを終えたとき、7時で、死んだように疲れ、中断するしかなかっ
た。完成させたのは7000ワード━━━4000ワードと3000ワ
ードのストーリーだった。、
たしかに、それらは、ずっと前に書いたものの書き直しだった。しか
し、今回は、前よりうまく書けた。1つは、市民戦争の設定で、ストレ
ートなアクションもの、もう1つは、キャンサスの初期開拓時代をバッ
クグランドにした、軽いロマンスものだった。
ベッドに倒れるように横になり、あまりに眠かったので、フロントに
電話して、モーニングコールを頼むのを忘れた。12時間でも睡眠が足
りないくらい疲れていた。7時というのは、あまりに早すぎる起床時間
だった。
しかし、早く目覚めた。5時少し過ぎだった。窓から、太陽の光が霧
中の黒を消散させるところを見るのに間に合った。それを見て、幻想的
な気分になり、服を着て、ヒゲを剃った。
6時に朝食を食べ、室に戻って、2つのストーリーを読み返した。そ
れらは満足以上のできだった。よく書けていた。前は、なにが悪かった
のだろう?前に書いたときに売れなかった理由は、プロットではなかっ
た。彼のプロットは、いつもまともだった。それは、文体だった。編集
者としての5年が、実際、彼になにかをもたらした。
彼は、生きた文体を手に入れた。それを、今、確信した。記憶にある
古いストーリーを書き直す以外は、この2つのストーリーを売り込み続
けるのではなく、そんなに早く売り歩く必要もないだろう。12のスト
ーリーを書き直したら、あるいは、書き直したストーリーがあれば、そ
れが、後ろ盾になる。その後は、週に短編2つか中編1つを出せれば、
狼をドアの外へ追いやっていられる、たとえ、売れる打率がフィフティ
フィフティだったとしても。しかも、前よりいいのは、もっとよく書け
ているからだ。明らかに、良くなっていた。
あと1つストーリーを書いたら、と彼は決心した、それらの売り込み
を始めよう。最初は、もちろん、ボーデン出版社から。それは、前にそ
こでのロープ使いに慣れているからというだけでなく、ストーリーが気
に入ったら、小切手をすぐ切ってくれるからだ。作家は、たまに、すぐ
にカネが必要なことがあるが、保証人を通じて請求すれば、編集者が読
んでストーリーにオーケーを出せば、24時間以内に小切手を郵送して
くれる。
この3つ目の書き直しは、前に1度試した、サイエンスフィクション
のプロットで、たったの2000ワードだった。プロットを頭の中では
っきり覚えていたので、2時間あれば書き上げられるだろう。マリオン
ブレイクが言っていたように、ボーデン社は、サイエンスフィクション
市場に参入して新雑誌を刊行するので、それを売り込むチャンスは大い
にある。
そのストーリーは、大きな書き換えは、まったく、必要なかった。タ
イムトラベルもので、ある男が有史以前の時代にタイムスリップする。
そのタイムトラベラーと出会った、洞窟人たちのある男の視点から語ら
れる。現代の設定はまったく出て来ないので、そのままで大丈夫だった。
ふたたび、彼はタイプライターを打ち始め、もう少し長くかかりそう
だったにも関わらず、9時に終えた。キャラクターと雰囲気を高め、も
っと力強く、鮮やかなストーリーに仕上げた。自分は、とんでもないや
つだと感じた。
◇
30分後には、ボーデン社の外側のオフィスのマホガニー製のレール
をまたいで、マリオンブレイクに笑い掛けていた。
彼女は、笑い返した。「イエス、ミスターウィントン?」
「3つ、ストーリーを持って来た」と、彼、誇らしげに。「1つは、ミ
スハードレイのラブストーリー雑誌に。もう1つは━━━あんたが話し
てくれた、新しいサイエンスフィクション雑誌の担当は?」
「ケイスウィントン、とりあえずの臨時に。それがスタンドに実際出て
から、だれかが担当になる」
「いいね。1つは、それ用に。『ロマンティックアドベンチャーストー
リー』の担当は?」
「それも、ウィントン氏が担当。それと『サプライジングストーリー』
が彼のレギュラーの担当。今、彼は時間があると思う。会えるかどうか
訊いてみる。ミスハードレイは、今、忙しく、あなたとウィントン氏の
面会が終わる頃には、時間が取れるかもしれない。ミスターウィントン、
ところで、自分のペンネームは、決まった?」
彼は、困ったように、指を鳴らした。「忘れてた!署名は、カールウ
ィンストンにしてある。そう、そのうち、ウィントン氏の気持ちが分か
るだろう。彼と話して、将来の作品には、本名は使わないし、もしも、
ノンデプルームがいいならそれで行く」
マリオンは、すでに、スイッチボードの1つの穴にプラグを差し込ん
で、マウスピースになにか言った。ケイスには、なにを言ったのかは聞
こえなかった。
彼女は、プラグを引き抜き、彼に、ふたたび笑い掛けた。「彼は会え
る」と、彼女。「あなたはわたしの友人と、言ってある」
「いろいろ、ありがとう」と、彼。気持ちを込めて。時として重要にな
る、そのようなことにはまったく気づいてなかった。なにかを使えば、
売れなかったストーリーを売れるようにできるわけでなく、すぐに読ん
でもらえるようにして、売れたら、すぐに小切手をもらえるようにする。
ケイスウィントンのオフィスに行き掛けて、マリオンがヒントを出し
たその方法を聞いてないことに気づいたが、思い出した時には、もう遅
く、そのまま歩き続けた。
少ししてから、ケイスウィントンは、ケイスウィントンと、デスクを
挟んで向き合って座っていて、握手をしてから言った。「オレがカール
ウィンストン、ミスターウィントン。あんたのために、2つストーリー
を持って来た。郵送することも、もちろん、できたが、町にいるあいだ
に会いたいと思った」
10 WBIのスレード
ケイスは、しゃべりながら、ウィントンを観察した。ウィントンは、
見掛けの悪い男でなかった。ケイスと、だいたい同じ年だった。1イン
チ背が高く、数パウンド体重が軽かった。髪はもっと黒く、少しカール
していた。顔については、まったく似ていなかった。そして、シェルぶ
ちメガネをしていた。かなり、レンズが厚かった。ケイスは、生涯で一
度もメガネを掛けたことはなく、完全な視力だった。
「あんたは、ニューヨークに?」と、ウィントン。
「イエスでありノーでもある」と、ケイス。「つまり、住んではないが、
今から、ずっといようと決めるかもしれない。さもなければ、ボストン
に帰るかもしれない。そこで新聞の仕事をしているが、一方で、フリー
ランスの仕事もしようとしている」ストーリーのことを話すことをため
らわなかった。「しばらく不在にしてるが、もしも、ニューヨークでフ
リーランスでやって行けるのなら、たぶん、戻らない。
見てもらいたくて、2つの短編を持って来た。1つは、ロマンティッ
クアドベンチャー向け、もう1つは、マリオンが話してくれた、これか
ら刊行する新しいサイエンスフィクション雑誌向けに」
包みから、3つのストーリーのうち、2つを出して、デスク越しに手
渡した。
「頼むと負担になるだろうが」と、彼。「すぐに読んでくれたら、感謝
する。というのは、この路線での作品を、いくつか書きたいのだが、あ
んたの反応次第で、正しい路線なのかを判断したいので」
ウィントンは笑った。「持ち込み原稿の山に置いておこう」
2つの原稿の表紙の、右上の数字を見た。「3000と4000ワー
ド。そう、ちょうどいい長さだ。どちらの雑誌も、ふさわしいストーリ
ーを広く募集している」
「すばらしい」と、ケイス。その幸運を利用しようと決めた。「このビ
ルで、あさっての金曜に別の約束がある。あんたがそれを読む時間があ
ろうがなかろうが、それを知るためだけに、このビルに寄った際に連絡
しても?」
ウィントンは少し、顔をしかめた。「そんなすぐに読めるかどうかは、
確かな約束はできない。やってはみるが。あんたがこのビルに寄る用事
があるなら、連絡をくれてもいい」
ケイスは言った。「よかった、サンクス」約束したわけでないのに、
ケイスは、金曜までに読まれることが確実だと思った。2つの原稿が、
1つあるいは両方、アクセプトされるレベルにあるなら、すぐにチェッ
クしてもらう保証をもらって物事をすすめる時だろう。すぐにカネが必
要になることを考えて、もう1つストーリーを持って来ている。
「そう、ついでに」と、彼。「筆者名について━━━」カールウィンス
トンがケイスウィントンに似ている点を挙げ、もしもウィントンがそう
すべきと考えるなら、ペンネームを使う意思があると説明した。
ウィントンは笑って、言った。「それは、それほど重要ではない。カ
ールウィンストンがあんたの本名なら、それを使う権利がある。オレは、
なにか書く気はないし、そもそもだれが、雑誌の編集者の名前を気にす
る?」
「ほかの編集者とか」と、ケイス。
「もしもずっとパルプ雑誌でやって行くつもりなら、ストーリーを送る
のはあんただから、カールウィンストンがオレのペンネームでないと分
かる。そのことは気にしなくていい、もしもあんたが、どうしても小説
の仕事にはノンデプルームが使いたいというのでない限り」
「そして」と、ケイス。「オレが筆者名でストーリーを売るのでない限
り」彼は立ち上がった。「いろいろサンクス!金曜に、同じ時間に、立
ち寄るかもしれない、グッバイ、ミスターウィントン」
◇
マリオンブレイクのいる、受付デスクに戻った。
彼女は言った。「ミスハードレイは、今、空いてる。会えると思う、
わたしが呼び出したら」しかし、彼女は、プラグを差し込まなかった。
彼を、好奇の目で見た。「ミスターウィントンのオフィスのドアを、ど
うやって知った?」
彼はニヤリとした。「サイキネスを使って、心が読める」
「そう?おもしろそう」
「ほんとうは、ミスターウィントンの名前が出たとき、あのドアを、あ
んたがチラッと見た。たぶん、あんたは覚えてないだろうが、見たんだ。
それで、そこが彼のオフィスと分かった。それに、もしも間違っていた
ら、あんたが呼び戻してくれると思った」
彼女は、えくぼを見せた。今回の試験は、なんとかパスしたが、と彼
は考えた、毎秒ごとに、ガードしてなければならない。今回のようなわ
ずかなミスが、すべてをダメにしてしまうかもしれない。
彼女は、プラグを差し込んで、また、聞こえない声で、マウスピース
になにか言った。そして、プラグを引き抜いた。「ミスハードレイが会
える」と、彼女。
そしてこのときは、正しいドアを指さしてくれるまで、待っていた。
そこへ歩きながら、厚い糖蜜を通って、やっと進んだ気がした。彼は
考えた。「こんなことすべきじゃなかった。頭を整理すべきだ。そのス
トーリーを彼女に残すか郵送するか、別のラブストーリー編集者に渡す
か、検討すべきだった」
彼は、深呼吸してから、ドアをあけた。
そのとき、逃げるべきだと分かった。彼女がデスクに座ってるのを見
たとき、心臓はダブル宙返りしそうだった。彼女は、彼を見上げ、軽い、
見知らぬ人にするように微笑んだ。
驚くことに、彼女は、37番通りのアパートの窓で姿を見せたときと
同じ衣装を着ていた。ただし、このときは、グリーンのブラだった。デ
スクの表面より上に、ほかには、なにも身につけてなかった。
そして、至近距離では、彼の記憶にあるよりも2倍、美しかった。し
かし、もちろん、そんなことは、バカなこと━━━
ほんとうに、バカなことなのか?ここは、ある意味、完全に違う宇宙
だ。その中の、ケイスウィントンは、まったく別人だった。ベティハー
ドレイも、少し違うことも、あり得なくはない。数日前は、オリジナル
よりもっと美しいベティは、想像できなかった。しかし、ここにいる。
衣装は、もちろん、彼女の魅力を下げるどころか、さらに美しくしてい
た。
そして、彼は、オリジナルに恋するのと同じの、2倍恋した。
彼女を見ていることに気づかずに、違いはどこか疑問に思いながら、
見つめていた。姿かたちは、まったく同じだった。もちろん、目の前の
ベティハードレイは、衣装のせいで、もっと姿かたちがよく見えるが、
それを考慮しなくても同じだった。
雑誌の表紙の娘は、ここの表紙の娘と、微妙な違いがあった。ここで
は、もっとよく描かれていて━━━ということがあった。
ベティについても、同様だった。彼女は、同じ娘で、微妙に2倍美し
く、2倍希望に満ち、彼は彼女に恋すると同じの、2倍恋した。
しかし、ゆっくりと彼女の微笑みは消え、「はい?」と訊かれて、彼
は自分がどれだけ彼女を見つめていたかに気づかされた。
彼は言った。「オレの名前は、ケイ━━━カールウィンストン、ミス
ハードレイ。オレは、うう━━━」
彼女は、彼が、ひどくまごついていたので、助け舟を出した。「ミス
ブレイクは、あなたが友人で作家だと言った。座ったら、ミスターウィ
ンストン」
「ありがとう」と、彼。デスクに向かい合ったイスに座った。「さて、
オレはストーリーを1つ持って来た」一度しゃべり始めると、知的にし
ゃべり続け、事実上、ケイスウィントンにしゃべった内容とまったく同
じことをしゃべった。
彼の心は、しゃべってる内容とは別のところにあったけれど。
それから、いわば、自分の足で立ち上がることも早々に、逃亡し、面
会を終えて、ドアの外にいた。
そのとき、彼は、彼女のそばにいるという拷問を、2度と繰り返さな
いと決心した。もしも万に1つでもチャンスがあれば、拷問の価値もあ
ったのだろうが、万に1つもなかったからだ。あり得なかった。
自分が、あまりにみじめだったので、なにもしゃべらずに、盲目的に
スイッチボードの前を通り過ぎた。しかし、マリオンブレイクが呼び止
めた。「ミスターウィンストン!」
彼は振り向いて、笑顔を見せて、言った。「いろいろ、ありがとう、
ミスブレイク、友達で作家だと言ってくれて━━━」
「いいえ、どんでもない、ところで、ミスターウィントンからメッセー
ジが来てる」
「ふん?さっき話したばかりだが」
「ええ、知ってる。少し前に彼は、重要な用事で外出したが、なにか訊
きたいことがあるそうで、12時半に戻るそう。そのときに電話して欲
しいと、つまり、そのときから、終業の1時までのあいだに」
「もちろん、喜んで、そして、もう一度、ありがとう」
彼は、なにかまた一杯飲みに誘うとか、あるいは、ショーかダンスに
行かないかとか、訊くべきだと分かっていた。もしも3つのストーリー
の1つでも売れれば、そうしただろうが、それまでは、減って行く資金
のことを考えると、彼女の彼への親切に応えることができなかった。
◇
彼はドアの方へ歩きながら、ケイスウィントンは、なにを、そんなに
早く話したがっているのだろうと、不思議に思った。ベティのオフィス
にいたのは、15分足らずだった。ウィントンは、2つのストーリーの
うち1つさえ、まだ、読んでないだろう。
しかし、なぜなんだろう?12時半に電話すれば分かることだった。
ボーデン出版社の外の廊下から、エレベータに向かって歩きながら、
上りのエレベータのドアがあいた。LAボーデン夫妻が、出てきて、う
しろでドアが閉まった。
無意識に、ケイスは、うなづいて、ふたりと言葉をかわした。ふたり
とも、少しうなづいたり、ボーデン氏は、聞き取れない声でなにか言っ
た。名前を思い出せない人に、話し掛けられたときにするように。
ふたりは、彼を通り過ぎて、彼が今出て来たオフィスへと入った。
ケイスは、下りのエレベータを待っているときに、顔をしかめた。ふ
たりが彼を知らないのは当然で、彼は、話し掛けるべきでなかった。そ
れは、ほんの些細なミスだったが、彼は、そんな些細なミスさえしない
ように、しなければならなかった。
ベティのオフィスでも、悪いミスを1つするところだった。自己紹介
を、カールウィンストンでなく、ケイスウィントンで始めかけたのだ。
今、考えてみると、彼がミスをしかけると、彼女は、かなり特別な目線
を送った、彼が気づく前に、「ケイ━━━」と言った限りにおいて。ま
るでそれは━━━しかし、それはバカらしい。その考えを、心から追い
出した。
けれど、なぜ、ベティハードレイは、あの衣装を着ていたのだろう、
ボーデンオフィスでも衣装がない?彼は、今まで、あのような衣装を着
た女を見たことがなかった。それを、確かに、心に留めた。彼が出会っ
た、小さなミステリーのうちのもっとも当惑したものの1つだった。だ
れかに訊くことなく、答えを見つけるには、どうしたらいいだろうか?
このような大きな相違点もあれば、このような驚くべき類似点もあっ
た。エレベータに向って歩きながら、気づいたことは、この宇宙の類似
点の方が、彼にとって、相違点よりもずっと危険だということだった。
馴染みのあるものが、無意識の反応を誘発して、彼をワナに掛けるのだ。
先程の、ボーデン夫妻に話し掛けたときのように。
個別のことは、明らかに、重要ではない。しかし、なんと軽々と、重
要なことにも同じミスを繰り返してしまうことか!そのことが、生き残
るために、彼に、完璧なまでに、にせものの振りをすることを強いるこ
とになった。大きな間違いを犯すかもしれない可能性は、ずっとあって、
それが心配だった。
彼が、すでに、大きな間違いを犯していたことに気づいていたら、も
っと心配していただろう。
ビルの外に、しばらく、立ったまま、つぎになにをすべきか考えてい
た。ホテルに戻って、別のストーリーを書く気にもならなかった。まだ、
やらなくていい。午後遅くになって、夜になれば、霧中のために室内に
いなければならず、時間はたっぷりある。3つのストーリーは、すべて
書き直しで、とても短いものだったが、2日間の仕事としては、かなり
量が多いものだった。それらのできは、かなり良かった。このまま質を
維持して、高めてゆくべきだ。そう、午後は休んで、夜の執筆に備えよ
う。
今夜、1つ書けて、明日、もう1つ書ければ、そのあと、会う約束で
ボーデン社に行った際に、さらに手土産が増える。垣根のこちら側にい
て、と彼は考えた、作家やエージェントに作品を持って来させる代わり
に、ストーリーを持参するというのは、奇妙に見えた。たぶん、彼はエ
ージェントになるべきかも?いや、それは、作品が1つか2つ売れるま
で、待とう。そうすれば、ドアの内側にいる気分がどんなものか報告で
きる。
彼は、ブロードウェイを越えて、タイムズスクエアを北へブラブラし
た。タイムズビルで立ち止まって、見上げた。奇妙なことを疑問に思っ
た。電光掲示板に流れた、今のニュースヘッドラインから、今までのよ
うな、点滅をやめたことを知った。なぜ、だめなのだろう?
たぶん、ニューヨークは、昼間は、電気の使用を最低限に抑えている
からだろう。電光板から放たれた光線が、どうであれ、夜は霧中によっ
て守られていても、昼間は太陽光によって、完全に守られていないので、
たぶん、アルクトゥルス船によって検知されてしまうからだろう。その
ことは、彼が昼間に寄ったレストランやオフィスや店の比較的弱い電光
板に対しても、同じだった。そう考えて来ると、それらすべてにおいて、
電気の使用は、減らし得るギリギリ最低限に抑えられていた。
彼は逃げ続けるために、そのような小さなことにまで気を配って見て
行く必要があった。彼は、昼間、仕事したり読んだりする、ほとんどの
時間、ホテルの室の照明は、つけっ放しだった。幸運にも、そのことで
注意されたことはなかった。しかし、今後は、デスクやイスを離れて窓
にいるときは、夜でなければ、照明は消すことにしよう。
ニューススタンドの前を過ぎるとき、ゆっくり歩いて、ヘッドライン
を読んだ。
艦隊、アルクトゥルス前哨基地破壊
防衛軍大勝利
このニュースは、彼を大喜びさせるはずだった。しかし、とケイスは
考えた、そうではなかった。彼は、アルクトゥルスを憎めなかった。ま
だ、どんな姿をしているのかさえ知らなかった。アルクトゥルスとの戦
いは、現実かもしれないが、そうは思えなかった。そう、信じることも
できなかった。まだ、夢のように思えた。目覚めれば消えてしまう悪夢
のように見えた。ここへ来てから4回、目覚めたが、アルクトゥルスと
の戦いは、まだ、続いていた。
◇
立ち止まって、暗い気持ちで、手描きネクタイのショーウィンドウを
見ていた。なにかが肩に触れ、振り返った。彼は跳び上がって、もう少
しで窓ガラスにぶつかるところだった。背の高い、紫の毛だらけのルナ
ンだった。
ルナンは、キーキー声で言った。「失礼、マッチある?」
ケイスは笑いたかった。手は、マッチ箱を渡すとき、少し震えていた。
ルナンは、タバコに火を点けるとマッチを返した。
「サンクス」と言うと、歩いて行った。
ケイスは、その背中が歩いて行く方を見ていた。盛り上がった筋肉に
もかかわらず、腰まで浸かった水の中を歩くように歩いた。もちろん、
重い重力のせいだと、ケイスは考えた。月では、ガルガンチュアを投げ
飛ばすほど強いが、ここの地球では、いつもそのように、重力によって、
どすんと落ちたり引っ張られたりしていた。8フィート1インチの身長
でなく、月では、たぶん、8フィート5インチか9フィートあるのだろ
う。
しかし、月には空気はないと仮定されてはいないのだろうか?その仮
定は間違っていたに違いない。少なくとも、ここでは。ルナンは呼吸す
る必要があり、そうでなければ、タバコは吸えない。呼吸しないで、タ
バコが吸える生物はいない。
突然、実際初めて、ケイスは、なにかに気づいた。彼が望めば、月へ
行けるのだ!火星へも!なぜ、だめなんだ?彼は、宇宙旅行ができるこ
の宇宙にいるなら、その有利性を利用してもいいのではないか?興奮か
ら、かすかに、冷たいものが背筋を走った。ここにいる数日間、宇宙旅
行が彼と関係するとは、まったく考えてなかった。今、その考えが彼を
ワクワクさせた。
すぐにできるわけでは、もちろん、ない。カネもかかるだろうし、た
ぶん、多くのカネが。たくさん書かなければならない。しかし、宇宙旅
行ができないことはない。
さらに、もう1つの可能性があった。そのチャンスに辿り着けるロー
プを教えてもらえば、例の硬貨は、まだ、手元にあった。25セント硬
貨が、たまたま、彼に2000クレジットをもたらした。たぶん、別の
硬貨の1つが、かなりレアだと分かれば、惑星旅行の資金源に十分なる
だろう。思い出してみると、グリーンビルの店主は、25セント硬貨が
2000クレジット以上の価値があることを認めたが、彼には、それ以
上払えなかった。
ほかの硬貨にも、どこかに、闇市場があるに違いない。しかし、よく
そのことを調べてからでないと、あまりに危険すぎる。
◇
彼は、46番通り沿いのブロードウェイをブラついて、店の窓から時
計を見た。ほとんど12時半だった。ドラッグストアに入って、ボーデ
ン出版社のケイスウィントンに電話した。
ウィントンの声は言った。「あ、はい、ミスターウィンストン、あん
たと話したいと言った以外のことを考えていて、うちの雑誌にあんたが
できそうななにか、前に論説やノンフィクション記事をやったことがあ
ったと言ったね?」
「ええ」
「始めたいと思っていることに、ノンフィクション記事がある。それに
ついてあんたと話して、あんたがそれに取り組む気があるのかどうか判
断したい。1日か2日のあいだに、する必要があるというだけ。興味は?
そして、そんなに早く始められるかな?」
ケイスは言った。「もしもやれるなら、すぐに始められる。しかし、
よくわからないのは、テーマはなに?」
「少し混み入ってるので、電話ではちょっと。今日の午後はあいてる?」
「ええ」
「オレはすぐここを出るので、あんたがここへ戻るまで待てない。しか
し、あんたは直接、ビレッジにある、オレの家に来ないか?一杯やりな
がら、ゆっくり話せる」
「いいね」と、ケイス。「場所と時間は?」
「4時では?ビレッジの南のグレスハム318のアパート6に住んでる。
そのあたりの地理に詳しくなければ、タクシーで来た方がいい」
ケイスは、ニヤリとしたが、まじめな声は続けて言った。「そこは見
つかると思う」
見つかるはずだ、4年、住んでいたのだから。
受話器を戻すと、また、ブロードウェイに戻り、今度は南に歩いた。
旅行会社のショーウィンドウで立ち止まった。
「休暇旅行はいかが?」宣伝を読んだ。「火星と金星へのツアー、すべ
て込みで、1か月5000cr」
たったの500ドルで、と彼は考えた。なんという安さ!すぐにでも、
500ドルなら稼げる!そして、その旅が、ベティのことを忘れる助け
になるかもしれない。
突然、彼は、居ても立ってもいられず、また書き始めたくなった。急
いで歩いて、自分のホテルに戻った。ケイスウィントンとの約束の時間
までに、3時間の仕事ができるだろう。
タイプライターに紙をセットし、インクリボンを入れて、4番目のス
トーリーに取り掛かった。ぎりぎり最後の1分まで仕事して、急いで、
ダウンタウンから地下鉄に乗った。
ケイスウィントンが急いで書いて欲しいという特集記事は、なににつ
いてだろう、と疑問に思った。できるなら、それは、彼が扱えるもので
あって欲しかった。そうなら、合理的に考えて、確信が持てるし、すぐ
にチェックできるからだ。もしもその特集が、彼がまったく知らないで
あるときのみ、例えば、宇宙艦隊の訓練や、月の状態のようなものであ
るなら、すぐに取り掛かる準備ができるような説明が必要だった。もち
ろん、それが分からなくても、扱えるチャンスをもらえるなら、朝の時
間を、公共図書館での調べものにあてることはできる。
しかし、地下鉄に乗ってるときと、グレスハムへ歩いているときは、
記事が彼が扱えないテーマである場合に、もっともらしく断る方法を考
えていた。
ビルは馴染みがあった。1階の廊下にあるアパート6の郵便箱にある、
ケイスウィントンという名前も馴染みがあった。彼は、ボタンを押して、
待った。ロックが解除されてから、ボタンから指を離した。
ケイスウィントン、もうひとりのケイスウィントンは、ケイスが廊下
を歩いて行くと、ドアのところに立って待っていた。
「どうぞ、入って、ウィンストン」と、彼。後ろに下がって、ドアを広
くあけた。ケイスは歩いて入ろうとして、急に、立ち止まった。
鉄のようなグレーの髪、冷たい鉄のようなグレーの目をした大男が、
本棚の前に立っていた。手には、死神のような45口径オートマティッ
クを持って、ケイスの腰の真ん中のボタンを狙っていた。
ケイスは、静かに立ったまま、ゆっくりと両手を上げた。
大男は言った。「彼を調べてくれ、ミスターウィントン。ただし、後
ろから。彼の前には出るな!気をつけて!」
ケイスは、手が軽く、服の上から触られて、すべてのポケットを調べ
られたのを感じた。
声は、できるだけ平静を装って訊いた。「訊いてもいいかな、これは
なんの調査?」
「銃はない」と、ウィントン。彼は、ケイスが見れる場所に出て来たが、
ケイスと大男のオートマティックのあいだの直線の外にいた。
彼は、そこに立って、困ったような目で、ケイスを見て、言った。
「あんたは、オレに説明を求めていると思う。あんたもオレに説明して
欲しい。そう、カールウィンストン、それが本名だとして、WBIのジ
ェラルドスレードを紹介する」
「知り合えて、うれしい、ミスタースレード」と、ケイス。WBIって?
と彼は疑問に思った。世界調査局?たぶん、そんなところだろう。主人
の顔を見て、言った。「説明は、それだけ?」
どこで、こんなことになる間違いをしたのだろうと、絶望的に考えた。
ウィントンは、スレードを見て、それから、ケイスを見て、言った。
「あんたに質問するあいだ、スレードに、ここにいてもらうのがベスト
だと思った。あんたは、今朝、ボーデン社のオフィスに、2つのストー
リーを持って来た。これらをどこで手に入れた?」
「手に入れた?オレが書いたものだ。それと、さっき言っていた、特集
記事を書いてくれというのは、ただのギャグ?」
「そう」と、ウィントン。ニヤリとした。「あんたに質問したいのを気
づかれないで、ここに来てもらうには、一番、手っ取り早い方法だった。
ミスタースレードに電話して、あんたがしたことを話したときに、彼が
アドバイスしてくれた」
「ところで、オレがなにをしたか、訊いても?」
ウィントンは、奇妙な顔をして、彼を見た。
「法的な罪は、剽窃。しかし、信じられない方法で、盗まれたので、な
ぜ、あんたがそんなことをしたのか、調べるために、WBIに来てもら
った」
ケイスは、ぽかんとして、彼を見た。「盗んだ?」繰り返した。
「あんたが置いて行った、この2つのストーリーは、5・6年前に、オ
レが書いたものだ。あんたは、いい書き直しの仕事をしている。あんた
のために言うが、オリジナルよりずっと良くなっている。しかし、なに
を考えて、オレが書いた2つのストーリーを、オレに売りつけようなど
としたんだ?オレが今まで経験したなかで、もっとも信じられないでき
事だ」
ケイスは、口をあけて、そして、また、閉じた。上アゴが渇いて、な
にをしゃべろうとしても、しゃがれ声しか出ないのではないかと考えた。
それに、なにをしゃべったらいい?
今、考えてみると、それは、完全に、当然なことだった。なぜ、ここ
に住んでいるケイスウィントンも、仕事も同じで、住むアパートも同じ
で、同じストーリーを書いていたことに気づかなかったのだろう?
その可能性をまったく考えてなかった自分を、アホだったと責めるし
かない。
沈黙が長く続いた。彼は、舌で唇を湿らせた。なにか言わなければな
らなかった。さもなければ、沈黙は、罪を認めたと解釈されるだろう。
11 ジャンプ・ザ・銃
ケイスウィントンは、舌で唇を湿らせた。2度目だった。それから、
弱弱しく言った。「ストーリーのほとんどは、同じようなプロットだ。
偶然、一致する場合もあって━━━」
ウィントンは、さえぎった。「これらは、同じようなプロットの、た
だの偶然の一致ではない。それなら、オレにも分かる。しかし、重要で
ない部分の、あまりにも多くが完全に一致している。2つのストーリー
の1つでは、ヒーローとヒロインの名前が同じだった。1つでは、前に
使ったのと同じタイトルだった。2つを通じて、あまりに多くの、詳細
な部分が、完全に一致していた。一致は、洗い流せない、ウィンストン。
一致は、かなり近い類似でも、類似とみなせるかもしれない。しかし、
ほとんどの名前や詳細な部分が、すべて一致していれば、もはや、そう
ではない。
そう、これらのストーリーは、盗まれたものだ」彼は、本棚の横のフ
ァイルキャビネットに手を伸ばして、仰いだ。「それを証明するために、
オリジナル版のコピーを取ってある」
彼は、ケイスに顔をしかめた。「1つのストーリーの最初のページを
読み終わる前に、疑いが生じた。2つのストーリーを全部読んでみて、
それを確信した。しかし、どうしても分からないことがあった。なぜ、
盗んだ者が、それらを書いた本人に、盗んだものを売ろうとしたのだろ
うか?あんたがそれらを、どのようにして、あるいは、いつ盗んだにせ
よ、そのことがオレには分からなかった。あんたは、オレに気づかれる
ことが分かっていたはずだ。ところで、別のことだが、ウィンストンは
本名?」
「もちろん」
「それも、おかしい。カールウィンストンという男が、ケイスウィント
ンによって書かれたストーリーを提出している。それが偽名だったとし
て、同じイニシャルで、苗字も1字加えただけの、そんなに近い名前を、
なぜ使ったか分からない」
ケイスも、自分のそこが疑問だった。唯一の間違いは、マリオンブレ
イクとしゃべっているときに、その場で思い付いた名前を使ったことだ
った。そうだとして、名前が必要な場合に、もっといい名前を準備すべ
きだった。
オートマティックを持ってる男が、訊いた。「身分証は?」
ケイスは、ゆっくりと頭を振った。なにか、出口が1つ見つかるまで、
なんとか誤魔化さなければならなかった。そんなものがあったとして。
「身分証はないが、身分は証明できる。ワトソニアホテルに泊まってい
るので、そこに電話してくれれば」
スレードは、冷淡に言った。「そこに電話したら、カールウィンスト
ンは登録されていると言うだろう。それは、知っている。すでに電話し
たから。ミスターウィントンに渡したストーリーに、返却先住所があっ
た」咳払いをした。「それは、あんたがそこで登録したカールウィンス
トンという名前を、この2日間使っているということ以外、なにも証明
してない」
彼は、大きなオートマティックの安全装置をはずした。彼の目は、厳
しくなって、言った。「冷酷に人を撃ちたくはないが━━━」
ケイスは、反射的に、バックステップした。「オレはやってない」抵
抗した。「たとえ、オレが盗んで、有罪だとしても、それだけで撃つ理
由に?」
「盗まれたことは、気にしてない」と、スレード。ニヤニヤした。「ア
ルクのスパイの疑いのある者は、見たら殺せという命令が出ている。そ
れに、ひとり逃げている。最後に目撃されたのは、グリーンビルの北部
の町、そいつの特徴や似顔絵は、あんたに似ている。たとえ、そいつが
あんたでなくとも、命令に従うしかない━━━」
「ちょっと、待って!」と、ケイス。絶望的に。「どこかに、単純明快
な説明があるはず、みんなが納得するような。それに、もしもオレがス
パイだったら、編集者の書いたストーリーを盗んで、本人に売り戻すよ
うな、アホな曲芸飛行をしようとするはずない」
ウィントンは言った。「彼の説明だが、スレード、それは、オレも全
体の中でも、もっとも腑に落ちない点だった。それに、スパイだという
確証がないまま、撃ち殺すのは後味が悪い。撃つ前に、1つか2つ、彼
に訊いてみたい」
彼は、ケイスに向き直った。「聞いて、ウィンストン、誤魔化してる
時間がないことは、分かると思う。そんなことしても、あんたがもらう
のは弾丸だけ。もしもアルクなら、あんたがこれらのストーリーを持っ
て来た理由は、神のみぞ知る。たぶん、オレは、違った反応をする。W
BI調査員を呼ぶ以外のなにかを。
しかし、あんたがアルクでないなら、説明があるに違いない。説明が
あるなら、すぐに説明した方がいい」
ケイスは、舌で唇を湿らせた。3度目だった。絶体絶命の瞬間では、
1つのアイデアが浮かんだが、5年前にそれらを最初に書いてから、そ
れらを提出した場所を、1つも思い出せなかった。そのとき、1つ思い
出した。
彼は言った。「考えうる1つの可能性に過ぎないが、あんたは前に、
これらのストーリーを、ガーデンシティのパルプ雑誌のゲブハートシリ
ーズに提出しなかった?」
「ううむ、1つは、とにかく出した。もしかしたら、両方。記録がある」
「5年前?」
「そう、そのころだ」
ケイスは、深い息をついて、言った。「5年前、オレはゲブハートで
投稿チェック係を務めていた。それらが投稿されて来たとき、オレはあ
んたのストーリーを読んだに違いない。気に入って、たぶん合格させた
が、最終チェックを担当していた編集長が、買い取らなかった。しかし、
オレの潜在意識がそれらを覚えていたに違いない。あんたが言う詳細部
分についても、同じものを使った」
彼は、当惑したように、頭を振った。「そうだとしたら、書くのはす
ぐやめた方がいい。フィクションは、とにかく、ダメだ。それらのスト
ーリーを書いたのは、最近で、オレはオリジナルだと思っていた。もし
も、ずっと前に読んだストーリーを潜在意識が覚えていたのだとしたら」
スレードの拳銃を握る手が、それほど強くなくなったのを見て、ホッ
とした。
スレードは言った。「あるいは、いつか盗むために、それらのメモを
取っていたのかもしれない」
ケイスは頭を振った。「もしも意図的に盗んだのだとしたら、少なく
とも主人公の名前くらいは変えただろう?」
ウィントンは言った。「それは、もっともだと思う、スレード。潜在
意識は、おかしなことをする。彼を信じる方に傾いている。彼が言うよ
うに、もしも意図的に盗んだのだとしたら、少なくとも、主人公の名前
は変えただろう。重要でない部分についても、そうだ。しかし、すべて
が、そのままだった」
ケイスは、ホッとしてため息をついた。最悪の事態は過ぎた。もしも
ストーリーに執着させられれば。彼は言った。「ストーリーは破いた方
がよさそうだ、ミスターウィントン。カーボンコピーも破く。もしも、
心が、オレをこんな魔法にかけるのなら、特集記事を専門にした方がよ
さそうだ」
彼の主人は、彼を奇妙そうに見た。「おかしいのは、ウィンストン、
あんたが書き直した、これらのストーリーは、かなりよく書けている。
プロットはオレで、書いたのは、あんただから、共作として、買い取っ
て、出版させたい誘惑に駆られないとしたら、ウソだ。言葉を変えると、
折半でいきたい。このへんは、ボーデン社にオレから説明する。あと」
「ちょっと、待ってくれ」と、スレード。遮った。「ビジネスの話をす
る前に、オレは、まだ確信できないところがある。90パーセントの確
信しかない。10パーセントでも疑いが残れば、撃てと言われている。
それは、分かっているだろうが」
ウィントンは言った。「彼のストーリーは、チェックできる、スレー
ド。一部は、とにかく」
「チェックは、オレが指揮する。日曜までに、40の方法でチェックす
るまで、彼に向けた拳銃を下ろせない。手始めに、ガーデンシティに電
話してチェックしたいだろうが、すでに数時間前に営業は終わっている。
霧中の外だとしても、ニューヨークの労働時間に合わせたエリアに入っ
ている」
ウィントンは言った。「1つ思い付いたことがある、スレード。数分
前に、彼のボディチェックをしたときに、そのときは、銃を捜していて、
それはなかったが、財布はあった」
彼を見つめるスレードの目が、前よりもっと厳しくなった。彼の指は、
ふたたび、しっかりと銃の上に置いた。
「財布?」と、彼。冷淡に。「そこに、身分証がない?」
そこには、とケイスは考えた、身分証がたくさんある。しかし、カー
ルウィンストンのものはなかった。
◇
スレードは、財布の中の身分証が、ケイスウィントンのもの、あるい
は、彼になりすまそうとするものであることを知ったら、銃を撃つのを、
1秒でも、ためらうだろうか?
その身分証は、グリーンビルでは彼の命を救ったが、ニューヨークシ
ティでは、代償として彼の命を要求しつつあった。ケイスウィントンと
いう名前を使うのをやめたときに、身分証は捨ててしまうべきだった。
ボーデン社のオフィスを最初に訪れて以来、ずっと続いている間違いの
連鎖が、今、はっきり見えた。
そして、どれかを修正しようとしても、今となっては遅すぎた。たぶ
ん、あと数秒しか生きられないだろう。
WBI調査官は、財布の中に身分証がなぜないか、彼が説明するのを
待たなかった。それは、繰り返しになる質問だったからだ。彼は、ケイ
スから目を離さずに、ウィントンに言った。「また、やつの背後に回っ
て、財布を取れ!それから、ポケットに、ほかになにがあるかさぐれ!
これが、やつに与える最後のチャンスだ。オレは気持ちがやさしい。や
さしい気持ちで、そいつをやり遂げなけりゃならない」
もうひとりのケイスウィントンは、円を描いて背後から彼に近づいた。
ケイスは、深く息をついた。まずいことになった。財布の中の身分証
に加えて、まだ彼は、違法な硬貨を紙幣に包んで持っていた。たぶん、
紙幣も違法で、それでガチャガチャ音がしなかった。それらを、ホテル
の室に置いておきたくなかった。それは、ズボンの時計を入れるポケッ
トに、小さい固いかたまりなっていた。
必要なものではなかった。財布の中味だけで、じゅうぶんだった。
そう、その時が来た。彼は、ここで、今、死ぬか、あるいは、あの銃
にジャンプしてみるかだった。彼が買ったストーリーのヒーローたちは
━━━まともな宇宙に戻れば、彼はアルクトゥルスのスパイでなく、ボ
ーデン社の編集者だった━━━必要があれば、いつでも、銃に向かって
ジャンプしていた。ジャンプ・ザ・銃。
実際にやってみて、チャンスは1000に1つもあるだろうか?
もうひとりのケイスウィントンは、今、背後にいた。ケイスは、銃口
に真っ直ぐねらわれて、とてもおとなしく立っていた。心は、水車小屋
の水路のようだったが、あと1分か2分後には撃たれると固く約束され
ているときに、別のことを考えていられなかった。財布をあけられて、
その中にある身分証を見られたら━━━
ケイスの注意はすべて、オートマティックに向いていた。そのような
銃は、と彼は知っていた、鋼で覆われた弾丸を発射し、近距離では人体
を貫通した。スレードが、今、撃てば、おそらく、ふたりとも死ぬだろ
う。ふたりのケイスウィントンともに。
それで、どうなる?まともな世界のグリーンビルにあるボーデン氏の
農場に戻って、目覚める?いや、機械知能メッキーを信用しないのは、
ダメだ!『ここでの危険は、現実の危険、この世界は、現実だ。ここで
あんたが殺されれば━━━』
メッキーの存在自体のように、とてもあり得そうになかったが、なん
となくケイスにも、メッキーの言うことが正しいと分かった。なんとな
く、2つの宇宙があって、ふたりのケイスウィントンがいて、ここのひ
とりも、彼が育った宇宙と同じくらい現実だった。もうひとりのケイス
ウィントンは、彼と同じに、現実だった。
1発撃てば、ふたりとも死ぬのは、事実だろうが、もうひとりのケイ
スウィントンは、彼の背後にいるので、WBI調査官の指が引き金を引
くのが1秒遅れる?遅れるか、あるいは、遅れないかどちらかだった。
手が尻ポケットに来た。指が財布を引っ張り出した。ケイスは、彼が
息を止めているのに気づいた。手がズボンポケットの横に来た。明らか
に、彼の主人は、見つけたものが調べられる前に、ボディチェックを終
わらせようとしていた。
ケイスは、考えるのをやめて、行動した。
手でウィントンの手首をつかむと、回転させて、彼とスレードのあい
だに投げた。ズボンのポケットは裂けた。ウィントンの肩越しに、WB
I調査官が、良く見えるように横に動くのが見えた。彼も、ウィントン
を盾にすべく動いた。
目のすみにウィンストンのこぶしが顔めがけて来るのが見えたので、
ぐいと引くと、肩をかすめた。そのとき、ウィントンはまだ彼とスレー
ドのあいだにいた、低く踏み出して、頭を、ウィントンの腰にぶつけた。
両手と全体重を突進させたせいで、ウィントンを後ろに突き飛ばし、ス
レードにぶつかりそうになった。
スレードは、後ろに突き飛ばされ、ブックケースにぶつかってガラス
が粉々になった。オートマティックは暴発して、限られた室の中で大型
爆弾のような音を出した。
ケイスは、両手でウィントンのえりをつかんで、ウィントンの足の横
から、オートマティックを上に蹴った。それは失敗したが、靴の先がス
レードの手首に当たった。オートマティックはスレードの手から、カー
ペットの上にドスンと落ちた。ケイスは、ウィントンを最後に一突きし
て、彼とスレードを、傾いたブックケースまで突き飛ばし、銃にジャン
プした。それを奪った。
銃をふたりに向けたまま、後ろに下がった。荒い息遣いをして、今、
とりあえずのアクションは終わり、手は震えていた。うまく行った。銃
に向って、ジャンプできた。まさに、前に買ったストーリーと同じに、
ジャンプ・ザ・銃は、やって失うものはなにもなかった。
◇
ドアにノックの音がした。
ケイスは、銃を威嚇して動かした。ウィントンとスレードは、おとな
しく立っていた。
声は言った。「だいじゅうぶ、ミスターウィントン?」ケイスは、声
が隣の室のフランダーズ夫人だと分かった。
ドアの消音効果で、大きな音を別の音のように偽装できると信じて、
声をできるだけ、もうひとりのケイスウィントンに似せて、言った。
「なんでもない、ミセスフランダーズ、銃のそうじをしようと思って、
暴発しただけ。その反動でドタンと倒れた!」
なぜ、ドアをあけないのか、彼女が疑問に思ってることは分かってい
たが、静かに立ったまま、待っていた。全神経は、目の前のふたりの男
に集中していて、1秒でも目を離せられなかった。
ウィントンの目に、当惑した表情が浮かんだのが分かった。フランダ
ーズ夫人の名前や声をどうやって知ったのか?
数秒の沈黙のあと、フランダーズ夫人の声が、ドアを通して聞こえた。
「分かったわ、ミスターウィントン、わたしは、ただ━━━」
服を着てないから、ドアをあけられなかったと言おうと思ったが、し
かし、言わないことにした。今度は、もっと声を注意して聞くだろうか
ら、彼女の知るケイスウィントンの声と違うことに気づかれるかもしれ
なかった。さらに、服を着ないで銃の手入れをするというのも、あまり
に不自然だった。
彼女に疑問に思わせておいた方がいい、そのうち忘れるだろう。彼女
の足音が、自分の室へ戻って行った。そのゆっくりしたペースが、彼女
が疑問に思ってるせいだと分かった。なぜ、彼はドアをあけない?反動
で倒れただけで、あんな音がする?
彼女がすぐに警官を呼ぶとは、思えなかった。ずっとしばらくは、疑
問に思ってるだろうが。しかし、アパートのほかの住人が、銃の音がし
たと、報告するかもしれない。すぐにでも、ウィントンとWBI調査官
をなんとかしてから、警官の来る前に逃げなくてはならなかった。
問題があった。ふたりを撃つことはできないし、そのままにして逃げ
れば、すぐに追跡が始まってしまう。縛り上げるのも、時間がかかり過
ぎて、危険だった。
逃走を始めるには、少なくとも、数分の余裕が欲しかった。どこへ逃
げる?迷ったが、その考えを心から追い出した。今すぐのことで手一杯
で、数分以上先のことは思い描けなかった。
「後ろを向け!」と、彼。命令した。声を、ニヤけさせ、冷淡にした。
まるで、スレードの声が、銃を持っていたときにそうであったように。
ふたりが後ろを向くと、銃口をWBI調査官の背中に向けたまま、一
歩近づいた。ウィントンよりもスレードを、ずっと怖れていた。左手を、
スレードの尻ポケットにあてた。そう、そこには予想通り、手錠が2つ
あった。それを取り出すと、また、一歩後ろに下がった。
彼は言った。「よし、その位置からアーチ状にまたげ!あんた、ウィ
ントン、その下に手を伸ばせ!それから、自分で手錠を掛けろ!先に、
手錠の鍵を投げろ、スレード!」
手錠がカチッと2回鳴るまで、ふたりの動きを監視した。
それから、ドアまで後ずさりして、手でつかんだまま、親指で安全装
置を掛けて、銃をポケットに滑り込ませた。ドアをあける際、囚人を見
ていたが、騒ぐなと言ったところで騒ぐだろうと、考えた。とにかく、
叫び出すだろう。
彼がドアを引いて、外から閉めると同時に、ふたりは叫び始めた。ド
アがどちらも開き始めたので、廊下を玄関へ向かって、大またで歩いた。
外へ出ても、早歩きで、走らないようにした。だれも、と彼は考えた、
警察へは、疑いもなく、1つのアパートより多く、通報しているだろう
が、彼を止めようとはしなかった。
だれも、彼を、止めなかった。通りを歩き、早歩きを続けた。サイレ
ンが聞こえたのは、1ブロック行ってからだった。歩くスピードを速め
る代わりに、ゆっくり歩いたが、つぎの角で、グレハム通りへ曲がらな
かった。
緊急車両が、アパート方面に向って、通り過ぎた。まだ、心配はいら
なかった。5分か10分後に、彼の手配書が配布されると、事情が変わ
って来る。しかしそのときまでには、5番通りに出て、ワシントンスク
エアを北に歩いているから、そのあたりに彼らが来ても、人混みで、彼
を見つけることはできない。あるいは、もっといいのは、タクシーに乗
ってしまうことだった。
タクシーが空車で走って来た。それを捕まえようとして走ったが、す
ぐに、腕を降ろして、運転手に見つかる前に、脇道に入った。自分をの
のしった。興奮のあまり、ウィントンから財布を取り戻すのを忘れてい
た。
なにより困ったことは、彼は破産したことだった。地下鉄にも乗れな
かった。
先程の状況では、有利に立って、幸運に乗じて、さらに状況を優位に
押し進められたのにと考えて、ふたたび、自分をののしった。なぜ、ウ
ィントンの財布や、さらに、スレードのも、自分のと同様、奪わなかっ
た?通常の正直者のルールは、見たら殺せのペナルティを受けて攻撃さ
れてる者には、守る義務はないのだ!
自分とウィントンとスレードの財布を全部合わせれば、支払い能力が
できる。カネがあってさえ、この状況は今でもじゅうぶん、絶望的だっ
た。彼のみじめな少ない服や所持品を返してもらうために、ホテルにさ
え戻れなかった。
北に向かって歩き続けた。14番通りを渡るころには、彼を捜してい
る緊急車両からは、かなり安全だと感じ始めた。数台、通り過ぎた。熱
心に、5番通りを流れる通行量を観察した。
歩道は、まだ、混んでいた。彼が歩き始めたころより、今は少し多か
った。それは、たぶん、町の中心に近づきつつあったからだ。しかし、
理由はそのためではない気がした。
そして気づいたのは、人々の歩き方が変わったことだった。ただ、歩
いている人はいなかった。みんな、どこかへ向かうように歩いていた。
無意識に、彼も歩くペースを速めて、みんなに合わせた。ひとりだけた
だ歩いていると目立つからだ。なんとなく、ただ、急いでいるように見
えた。
突然、なぜかが分かった。夕暮れが近づいていた。ここの人々は、暗
くなる前に家に着くために急いでいたのだ。
霧中の前に。
12 スペースガール
ここの人々は、大急ぎで家に向かっていた。カーテンを閉め、アパー
トのドアに鍵を掛け、かんぬきを掛け、外の通りを、殺人者たちの漆黒
の闇にしたまま。
アパートから逃走してから初めて、立ち止まって、どこへ行くか、ど
こへ行けるか、真剣に悩んだ。
手書きの住所が、正しい住所になってない場合のみ、彼のホテルで警
官が待ってることはないだろう。大きい悩みに見えるが、少しの悩みは、
1週間分先払いした事だった。
その事は、ポケットにある硬貨を、カネに換えようとしているように
見えた。昼間の早い時間なら、図書館へ行って、硬貨について調べ、内
容を理解することができた。なぜ、図書館にいたときに、チャンスはあ
ったのに、調べなかったのだろう?なぜ、そのことについて、いくらで
もできることがあったのに、なにもしなかったのだろう?硬貨を売って
カネを得ることは別にして、考えうるもうひとつの可能性があった。メ
ッキーに接触できさえすれば!メッキーは、彼の心に入り込めた。メッ
キーは、彼の身分を保証できるだろうし、法律の力が使えて、彼は、な
んであろうと、アルクトゥルスのスパイでないと命令できるだろう。
そう、確かに、メッキーからのメッセージをもらっていて、メッキー
は、彼を苦境から救うことを拒絶しないだろう。
彼は、まだ、20番通りを、北に向かって歩いていた。そのとき、ど
こへ行かなければならないか気づいた。早足で歩き出した。
27番通りのアパートに着いたのは、夕暮れだった。通りには、何人
かいたが、ほとんどは大急ぎで走りながら、霧中から逃れようとしてい
た。
ケイスが外のドアをあけたとき、管理人は鍵を掛けようとしていた。
男は、すばやく後ろのポケットに手をやったが、銃を出さず、なにも出
さなかった。疑わしそうに訊いた。「だれに会いに?」
「ミスハードレイ」と、ケイス。「少し会うだけ」
「オーケー」と、管理人。脇にどいて、彼を通した。
ケイスは、エレベータらしきドアに向かったが、管理人の声が追い掛
けて来た。「電気は止まってるから、階段しか使えない、ミスター!す
ぐにドアを閉めるから、帰りたいなら、すぐ戻らないと」
ケイスはうなづいて、階段を上った。急いで上がったので、5階に着
いたときは、立ち止まって、しゃべれるようになるまでハーハー言って
いた。
1分後に、正面の室のベルを鳴らした。ドアに向かって足音がして、
ベティハードレイの声は言った。「どなた?」
「カールウィンストンだ、ミスハードレイ。邪魔して悪いが、重要なこ
と、生死に関わること」
チェーンが付いたまま、ドアは、あいた。3インチの隙間から、ベテ
ィの顔がこちらを見ていた。彼女の目は、少し驚いたようだった。
彼は言った。「遅いことは承知している、ミスハードレイ。しかし、
今すぐ、メッキーと接触しなければならない。おそろしく重要なこと。
接触できる方法はある?」
ドアは閉まり始めた。一瞬、ひとこともなく、彼女がドアを閉めよう
としているのかと思ったが、チェーンのガチャガチャ言う音がして、チ
ェーンをはずすために、彼女がドアを引いていたと分かった。、
ボルトもはずされ、ドアがあいた。
ベティは言った。「どうぞ、ケ━━━ケイスウィントン」
彼は、最初、彼女が正しい名前で呼んだことに気づかなかった。彼女
は、まだ、その朝のボーデン社のオフィスと同じ衣装を着ていた。そう、
グリーンのトランクスにグリーンのブラだった。まさにブリーフトラン
クスで、いい形をしていた。グリーンのブーツもはいて、形のいいふく
らはぎを半分持ち上げていた。ブーツとトランクスのあいだに、えくぼ
のあるヒザと丸々とした腿が黄金色の肌を見せていた。
彼女は、後ろに下がった。彼は息する間もなく、室へ入った。ドアを
後ろで閉めると、ドアに寄り掛かって、まったく信じられないように、
ベティを見た。
室は薄暗く、シェードはすでに降ろされていた。光は、ベティの後ろ
のテーブルにある燭台の2本のろうそくから来ていた。顔は影が掛かっ
ていたが、後ろのやわらかい光がブロンドの髪を黄金のオーラに見せて、
スリムな美しい体をシルエットに見せていた。アーティストは、彼女を、
これ以上美しく描けないだろう。
彼女は言った。「トラブルにあった、ケイスウィントン?警官に追わ
れている?」
彼女の声は、少しかすれていて、彼を驚かした。「どうして、オレの
名前を?」
「メッキーが教えてくれた」
「そう、メッキーはなんて?」
答える代わりに、彼女は訊いた。
「メッキーのことを、だれかにしゃべった?ここに来ることを、だれか
知ってる?」
「いや」
彼女はうなづいて、振り返った。ケイスは、ドアから離れたところに、
黒人のメイドが立っていることに気づいた。ベティは言った。「もう、
だいじょうぶ、デラ!室に戻っていいわ」
「しかし、ミス━━━」メイドの声は、心配そうだった。
「だいじょうぶ、デラ」
メイドの後ろのドアが、静かに閉まり、ベティは、こちらに向き直っ
た。
彼は、一歩踏み出したが、止まって、訊いた。「覚えてない?━━━
オレには分からない。あんたは、どちらのベティハードレイ?メッキー
が教えたって、どうやって知った?」
それは、言葉がはっきりせず、彼にとっても混乱していた。
彼女の言葉は、冷静だったが、フレンドリーだった。彼女は言った。
「座って、ミスターウィントン。わたしの知るケイスウィントンと混乱
しないために、あなたをそう呼ぶ。なにが起こった?あなたを追ってる
のは、ケイス?」
ケイスは、憂うつそうに、うなづいた。「そう、オレが提出した2つ
のストーリーは、彼のストーリーだった。それらはオレのものでもあっ
たが、説明しようともしなかった。そんなこと、彼には意味ないし、オ
レにも大きな意味はなかった。それが事実だと知っていたとしても。本
当のことを言おうとして、宙ぶらりんのまま、ずっとほうり出してきた」
「なにが、本当のこと?」
「分からない、あんたは?メッキーは言った?」
「彼は、どっちか分からない。ストーリーって、なに?彼がそれらを書
いて、あなたも書いたって、どういうこと?」
「このようなこと。オレが来た宇宙では、オレがケイスウィントン。こ
こでは、彼がケイスウィントン。オレたちの人生は、先週の日曜の夕方
までは、ほとんど同じように、平行して進んでいた。
しかし、オレのストーリーについては━━━今朝、あんたに手渡した
ものは、破り捨てて!技術的に、それは剽窃されたものになってしまう
ため。しかし━━━メッキーには会える?オレは会う必要がある。なに
か方法は?」
彼女は、頭を振った。「あなたは、たぶん、メッキーには会えない。
彼は、戦闘員。アルクは━━━」彼女は、少し言い淀んだ。
「アルクは、攻撃して来る」と、ケイス。「メッキーは、戦争の危機だ
と言った。アルクが勝つかもしれない」彼は、皮肉っぽく、笑った。
「しかし、戦争について、興奮できない。興奮するほど、信じてない。
実際、ここのすべてを信じてるように見えない、あんたを除いて━━━
いや、あんたも信じられない━━━その衣装のせい。それはなに?いつ
も、それを着ている?」
「もちろん」
「なぜ?つまり、ここの、ほかの女も?」
彼女は、驚いたように、彼を見た。「もちろん、すべての女ではない。
実際は、ごくわずか。スペースガールだけ」
「スペースガール?」
「もちろん。宇宙船で働いている、あるいは、働いていた女。あるいは、
宇宙戦闘員の男のフィアンセの女。ドッペルのフィアンセのわたしは、
着る権利がある。ボーデン社から休みをもらって、宇宙を探検したこと
がないとしても」
「しかし、なぜ?」と、彼。まごついて。「つまり、宇宙船の中は、そ
んなに暑い?そんな、省略された衣装が必要なくらい?あるいは、別に
理由が?」
「なにが言いたいのか分からない。もちろん、宇宙船の中は、暑くない。
ほとんどは、体温調整型プラスチックコートを着ている」
「透明のプラスチック?」
「自然よ、ミスターウィントン、なにを考えてるの?」
彼は、右手を自分の髪の中に入れた。
「知りたいのは、その透明のプラスチックの衣装って、『サプライジン
グストーリー』の表紙のような?」
「もちろん、そう。実際に着てなければ、『サプライジングストーリー』
の表紙になるわけない。なぜ?」
彼は、答えを思い浮かばなかなかった。なにひとつ。
◇
とにかく、ここに数分間、滞在しただけで、重要なことを知った。今
から、24時間以内に、彼が生きるか死ぬかを左右する重要なことだっ
た。
決然として、彼は、彼女の衣装だけを見た、覆われてない部分ではな
く。それが、わずかな助けになった。とんでもなく、わずかだったが。
彼は訊いた。「メッキーは、オレのことをなんて?」そこは安全な場
所だった。その上、彼は知る必要があった。
「彼自身も、よく知らないらしい」と、彼女。「あなたの心の表面より
深くさぐるには時間がなかった、と彼は言った。しかし、あなたが、ど
こか別の場所から来たことは、分かったらしい。どこからなのか、どの
ようにして来たか、なにが起こったのかは、分からない。あなたが、別
の人に、自分のことを説明したりすると、正気でないと判断されてしま
うが、あなたは、正気だと、彼は言った。そのことは、確かだそうだ。
あなたが来た場所では、ケイスウィントンと呼ばれ、編集者だったこ
とは彼は知っている。ここで会ったケイスウィントンとは、あなたは似
ていないけれど、あなたは頭がいいので、別の名前をを使った」
「しかし、それほど頭よくなかったので」と、ケイス。「似たような名
前を使ってしまった。そして、ケイスウィントンに、彼自身のストーリ
ーを売ろうとしてしまった。それが、続いている」
「彼は、あなたがここでトラブルに巻き込まれていることを知っている。
それは、あなたが、ミスを犯さない方法を知らないから。よほど注意し
ないと、スパイとして撃ち殺されるそうよ。そのことを、あなたに警告
したと言ってる」
ケイスは、前に体を傾けた。「メッキーって、なに?彼は、ほんとう
に、ただの機械?ロボット?あるいは、ドッペルは、本物の脳を球体に
入れた?」
「彼は、機械。あなたの言うような意味での、本物の脳ではない。しか
し、ある意味、機械を越えている。ドッペルでさえ、一部だとしても、
そのすべてを理解してない、どうやって作ったのか。しかし、メッキー
には感情があり、ユーモアのセンスさえある」
ケイスは、彼女がドッペルと言うときの、強調された人称代名詞、大
文字化したような、敬けんなしゃべり方に気づいた。イヤなやつめ、と
彼は考えた、彼女は、やつをほとんど崇拝している。
彼は、1秒間、目を閉じ、目をあけたとき、彼女を見てなかった。別
の方を見たことが、ふたたび彼女を見たとき、もっと強く彼女のことを
考えさせた。彼女が質問したことに気づくまで、彼女がしゃべり続けて
いたことさえほとんど分からなかった。
「わたしになにができる?メッキーは、わたしに、あなたはもしも物事
が絶望的になったら、ここへ来るかもしれない、と言った。そして、わ
たしに危険が及ばなければ、あなたを助けて、助言を与えても構わない
と言った」
ケイスは言った。「あんたに頼むことはしない。だれかに後をつけら
れたり、疑われたりするので、ここへ来ないつもりだった。ただ、どの
ようにしたらメッキーと連絡できるか知りたいだけ。オレの仮装は、タ
コよりも高く舞い上がってしまった。もしも警官に訊かれたら、疑われ
ないような答えを知らない」
「しかし、艦隊に行かない限り、メッキーに連絡する方法はない」
「艦隊は、どこ?」
彼女は、答える前に、ためらい、顔をしかめた。「あなたに言っても
問題にならないと思う。公式には、公にしてないが、多くの人々は知っ
ている。土星の近く。しかし、そこへは行けない。メッキーが戻るまで、
待つしかない。カネはある?」
「ない。しかし、借りるわけには━━━待って!教えてもらいたいこと
がある。明日、図書館で調べようと思っていたが、今、教えてもらえた
ら、時間の節約になる。硬貨の価値は、どのくらい?金属製の硬貨?」
「金属製の硬貨?1935年まではあった。その年に、ドルやセントの
通貨をクレジットに転換するように求められた」
「なぜ?」
「クレジットに変えたか?世界的規模の貨幣基準を作るため。すべての
国が同時に転換を行った。それで、戦争努力が━━━」
ケイスは、遮った。「そうでなく、なぜ金属製の硬貨がなくなった?」
「アルクが、硬貨を偽造した。そうすることで、我々の経済を壊滅させ
るのに、ほとんど成功し掛けた。紙幣通貨も偽造した。やつらは、地球
は資本主義経済であることを発見し━━━」
「すべて?ロシアは?」
「もちろん、すべて。ロシアって、なんのこと?」
「気にしないで!」と、ケイス。「続けて!」
「やつらは、通貨を偽造できた。専門家でさえ、本物と区別できなかっ
た。インフレーションが始まって、世界経済を崩壊へと導くかのように
見えた。
それで、国々の戦争会議が科学者に訴えて、科学者たちのグループが、
アルクが偽造できないある種の紙幣を作り出した。その通貨の秘密がな
んなのか、知らない。各国の印刷局のトップの数人を除いて、だれも知
らない」
「なぜ、偽造されない?」と、ケイス。
「紙に、なにか秘密がある。アルクが分析できる成分ではなく、製造過
程が、紙に暗闇でも淡い、黄色っぽい、光を放つ性質を与えている。今
では、だれでも、暗闇で見るだけで、偽造された通貨を見破れる。アル
クを含めた偽造者は、淡い光を放つ紙を複製できなかった」
ケイスは、うなづいた。「そのことが、ドルをクレジットに転換させ
ることを可能にした」
「そう、すべての国で、同時に、新しい紙幣が導入された。各国は、独
自の通貨を持っているが、すべてクレジットになって、同一の比率で、
いつでも交換可能になっている」
「古い通貨は回収され、その所有を違法とした」
「そう、持っていただけで、かなり厳しい科料があり、いくつかの国で
は禁固刑もある。しかし、硬貨収集家がいて、数も多く、趣味に関して
はとても熱心で、チャンスを捜している。硬貨の流通が、ブラックマー
ケット化しているために、高額で取引される。硬貨収集は,違法で危険
だが、多くの人々には、重大な犯罪だとは思われていない」
「禁酒法下の飲酒のように?」
ベティは、困った顔をした。「今、なんて?」
「気にしないで!」と、ケイス。ポケットから、硬貨を紙幣で包んだ小
さなかたまりを出した。それらを開いて、調べた。初めに紙幣を、つぎ
に硬貨を調べた。
彼は言った。「製造日付が1935年以前のものが、硬貨が5つに紙
幣が2枚ある。これらに価値はある?」
それらをベティに手渡した。彼女は、ろうそくの近くで見て、言った。
「どのくらいするのか、分からない。日付や条件による。しかし、大雑
把に、1万クレジット、昔のドルなら、1000ドルの価値はあると思
う」
「全部で?」と、ケイス。「グリーンビルの店主は、たった1つの硬貨
で、2000クレジットくれた。彼は、それよりずっとすると言ってい
た」
彼女は、硬貨と紙幣を彼に返した。「それは、たぶん、日付が珍しい
もの。もちろん、その中のひとつも珍しいものかもしれない。日付けの
珍しさは、発行個数によるのかもしれない。けれど、そのうちの1つは、
日付が珍しければ、1万クレジットの価値があるだろう。それらと別に
した紙幣や硬貨は?」
「オレに深刻なトラブルを引き起こした、1935年以降に製造された
もの」
「それなら、アルクが偽造したものに違いない。それらを捨てて、持っ
ているところを見つからない方がいい」
ケイスは言った。「そこが分からない。これらは、アルクに偽造され
たものではない。ところで、なぜ、アルクは、地球の政府が硬貨の製造
をやめた以降の日付で、硬貨を偽造したんだろう?」
「やつらは、輝かしいこともやるが、間抜けなこともする。通貨の転換
で、ふつうのやり方では、偽造のチャンスは無くなったあと、やつらは
スパイを送り込んで、収集家に硬貨を売る方法で、カネを稼いでいた。
ただ単に、やつらは、現在の日付で、古いタイプの硬貨や紙幣を作り続
けるという間抜けなことを続けていた。
20人のアルクのスパイが、捕まった。それは、間違った日付の硬貨
を収集家に売ろうとしたからだ。そう、先週の日曜も、州の北側で、ア
ルクのスパイが、売ろうとして━━━」しゃべるのをやめて、彼を見た。
「あ、それは、あなたね?」
「たぶん、オレだ」と、ケイス。「ただ、オレはアルクのスパイでない
し、硬貨は、アルクにもだれにも、偽造されてない」
「しかし、もしも偽造されてないなら、なぜ、35年以降の日付?」
ケイスは、ため息をついた。「その答えを知っていたら、ほかの多く
の質問にも答えられる。とにかく、ここを出たら、最初の下水溝に、売
ることのできない硬貨や紙幣は捨ててしまう。ところで、アルクトゥル
スは、人間?オレたちと似ている?人間の特性がある?」
娘は、肩を震わせた。「やつらは、おそろしく異なる、モンスター。
見た目は、かなり昆虫で、もちろん、大きくて、知能は、わたしたちと
同じくらい。しかし、悪い。戦争の初期に、やつらは、数人の人間を捕
えた。それから、やつらは人間に乗り移って、やつらの心を人間の肉体
の中に入れて、スパイとして、破壊工作をさせた。
今は、そう多くはない。スパイのほとんどは、殺された。遅かれ早か
れ、スパイは心はエイリアンで、市民社会の仕組みを完全には理解して
ないから、どこかへ行ってしまう。姿を現すときに、間違いを犯してい
る」
「どんなふうに現われるか、見てみたい」と、ケイス。ニヤニヤしなが
ら。
「とにかく、その危険はなくなりつつある。防衛軍の守りは万全で、人
間が捕らわれてから、なん年もたっている。時々、スパイは殺されるが、
捕まることはない。戦争の初期に捕まった人々が、生きて帰ることはめ
ったにない」
「そうだとしても」と、ケイス。「なぜ、疑いだけで殺す?なぜ、逮捕
しない?心は確かにエイリアンだとしても、精神科医は、アルクトゥル
スかどうか見分けられるはず。疑わしきは殺す作戦で、多くの無実の者
たちが殺されなかった?」
「もちろん、ひとりのほんとうのスパイのために、100人が殺された
かもしれない。しかし、スパイたちはとても危険で、ひとりを逃したら、
100万の人々が死ぬ結果に至ったかもしれなかった。ひとりのスパイ
を殺す、わずかなチャンスも見逃さないようにすることが、賢明だった、
ほんとうに賢明だった。たとえ、ひとりのアルクのスパイを殺すために、
1000人の人間が犠牲になっても、それだけの価値はあった。
もしも今までの科学に、ほんの少しでも新しい発見が加われば、戦争
の潮目が変わることは、分かると思う。今は、ちょうど、優劣が均衡し
ている。つまり、今は、メッキーがわたしに言ったように、あなたにも
言ったように、ちょうど今が、危機でもある。たぶん、すでに、危機の
先端にいる。もしも、戦争に負ければ、それが意味することは、人類の
滅亡。やつらは、人類を支配さえしたくない。皆殺しにしたら、太陽系
を乗っ取って、自分たちのものにするだけ」
「それが、やつらの、イヤらしいとこだ!」と、ケイス。
ベティの顔は、紅潮して、突然、怒り出した。「そんなジョークはや
めて!人類の終わりを冗談だと思ってるの?」
「悪かった」と、ケイス。深く反省して。「ちょっと、オレには分から
なかっただけなんだ。スキップしてくれ!スパイがどんなに危険かは、
分かった。まだ、分からないことは、撃ち殺す前に確認しても、失うも
のはない。銃を突き付けていれば、スパイは逃げられないはず」
「おお、それが、逃げられる、ほんの0・1秒あれば。最初、逮捕を試
みたが、多くが牢獄へ送られる途中で逃げられた、あるいは、鍵を掛け
た牢獄からも。やつらには、肉体的にも精神的にも、特別なパワーがあ
って、ひとりのスパイに銃を突き付けてるだけでは、じゅうぶんでない」
ケイスは、皮肉っぽく、ニヤついた。
「そのひとりは、WBI調査官に銃を突き付けられていても、逃げ出す
ことができた。そう、オレのことだが、今日の午後の前に、彼らは、疑
いを持ったが、今は、持ってない」
彼は、立ち上がった。長い間、ベティを見ていた。ろうそくの淡い光
の中で、黄金の髪や黄金の肌、信じられないほど美しい顔、信じられな
いほどの驚きの肉体。もう2度と見れないかのように、彼女を見つめて
いた。そう、たしかに、それもありそうに思えた。
彼女の姿を心に焼き付けた。その絵とともに歩いてゆこう、これから
の残りの人生を、それが40分なのか、40年なのか分からないが、前
者であることもじゅうぶんあった。
振り向いて、窓を見た。ベティがメッキーが来たときに寄り掛かてい
た窓だった。窓ガラスは、黒、なにもない漆黒だった。
霧中が始まっていた。
彼は言った。「サンクス、ミスハードレイ、グッバイ」
彼女は立ち上がった。目は、彼がしたように、窓を見た。「しかし、
どこへ?注意すれば、1・2ブロックは行けるかもしれない、しかし」
「心配しないで、銃があるから」
「しかし、どこも行くところがないのでは?デラとわたしだけだから、
ここには、泊まれないけど、下に空いてるアパートがある。管理人とい
っしょに泊まれるようにできる。それなら━━━」
「いや!」
ケイスの返答は、爆発的で、言ったあと、後悔した。
彼女は言った。「明日、わたしがWBIに話せる。メッキーがあなた
を保証すると話せる。メッキーが戻る数か月後まで、逃げ回るのは危険
だ。しかし、わたしが話せば、メッキーが戻るまで、保護のために拘置
される」
それは意味があったが、疑いの影が、ケイスの顔に現れていたに違い
ない。数か月間の保護拘置の考えも、ほとんど好きになれなかった。永
遠に続くわけでないし、殺されるよりは、生きてる方が良かったが。
彼女は、どこを強調すればいいか気づいたように見えた。「WBIが
わたしを信用してくれることは、ほとんど、間違いない。少なくとも、
あなたを疑うよりは、利益があると、ドッペルのフィアンセとして」
「いや!」と、ケイス。彼女には理由は分からないだろうが、口にも出
せなかった。はっきり、頭を振った。
「ここにはいられない」と、彼。「説明できないが、とにかく、いられ
ない」
彼女を、ふたたび、見た。最後になるかもしれないので、目いっぱい
に彼女の姿を焼き付けた。「グッバイ」と、彼。
「グッバイ、それなら」と、彼女。手を差し出した。彼は、それが見え
ないふりをした。彼女の手に触ったら、自分が信用できなかった。
急いで、出て行った。
◇
階段を降りているとき、なんてアホなんだ、と気づき始めた。アホだ
ったことがうれしかった。ベティハードレイからの申し出を、すべて断
ったことがうれしかった。助言はイエス、これは、問題なかった。問い
は、彼女とメッキー以外、だれにも訊かなかった。この宇宙の描写は、
今、かなり、鮮明になった。特に、硬貨に関する事柄について。
ほかのことは、まだ、謎だった。彼女が着ていた衣装。彼女は、そん
な衣装を着ていたら、男たちを狂わせてしまうことに気づかないのだろ
うか?だが、その衣装は、彼女にとって、とても自然で、なぜ彼が疑問
に思うのか、理解できなかった。
その事に関しては、未来の検討事項として心の中にファイルしておけ
ばよい。たぶん、メッキーは、重要でないことについても、いろいろ説
明してくれるだろう、メッキーに会ったときに、メッキーが重要なこと
に関して、彼に説明してくれる時間が取れたときに。
とにかく、ベティの助けの申し出を受けないガッツがあったことがう
れしかった。
受けなかったのはアホでもあったが、彼は疲れた。このとんでもない
宇宙で、変装したアルクトゥルスや空飛ぶミシンが行き交う宇宙を駆け
巡るのに、とても疲れた。
疲れるほどもっと注意し、慎重になればなるほど、犯すミスはもっと
多くなり、巻き込まれるトラブルももっと増えた。彼は、今では、正気
でない。ポケットには銃があり、でかい銃で、45口径オートマティッ
ク、8フィートのルナンでさえ止められる。
その銃を使いたい気分だった。霧中でトラブルを仕掛けてくる者は、
だれであろうと撃退してやる。夜歩きに追い掛けられても、自分がやら
れる前に、なん人かは殺してやる。注意しながら、地獄を進もう。失う
ものなんて、なにもなかった。
管理人は、階段の先の廊下で、まだ、待っていた。ケイスが降りて行
くと、驚いたように見えた。
「外へは、出ない、ミスター?」彼は、知りたかった。
ケイスは、彼にニヤリとした。「行く、球体の男に会いに」
「メッキーに会いに?ドッペルにも会う?」声には、畏敬の念があった。
管理人は、尻ポケットからリボルバーを抜くと、ドアをあけに行って、
言った。「もしも彼と知り合いなら、あんたがミスハードレイに会いに
来たときにそう思ったが、自分のすることが分かってるようだ、そう、
望む」
ケイスは言った。「オレたち、ともに、そう望む」
暗闇の中へドアをあけ、ケイスが出ると、後ろで、急いでドアがバタ
ンと閉まる音が響いて、ボルトが閉まった。
彼は、ドアのすぐ外に立ったまま、耳を澄ました。ボルトが閉まる音
のあと、なんの音もしなかった。沈黙は、暗闇と同じくらい、ギッシリ
詰まっていた。
しばらくして、深い息をした。一晩中、ここに立っていられない。前
と同じように、行くかもしれない。今回は、日曜の夜に、グリーンビル
から着いて霧中を横断した行き方よりは、もっとスマートな行き方をし
よう。
カーブまで、感覚で行くと、ここに座って、十分時間を掛けて、靴を
脱ぎ、2つを靴ヒモで結んで首から掛けた。靴をはかなければ、足音は、
彼を襲おうとする者に聞かれることはなかった。
立ち上がると、不器用だが簡単な方法を見つけた。カーブしている道
に一方の足をそえ、もう一方の足は溝に沿って歩く方法だった。
足の下できしる下水溝の感覚が、間違った日付の硬貨や紙幣を捨てる
ことを、思い出させてくれた。それらを捨てるときにマッチを擦らない
でいいように、1つのポケットにまとめておいたものを取り出して、下
水溝の格子の中へ落とした。数フィート下の水へ落ちる音がした。
それを終わらせると、耳を澄まして、進んだ。45口径オートマティ
ックをコートの右ポケットに移して、右手でつかみ、いつでも安全装置
を外せるように、親指を掛けていた。
前に、霧中にいたときと同様、怖ろしくなかった。銃があることも支
えにはなったが、それだけではなかった。前は、霧中がなぞだったが、
今は、その正体も背景も理解していたという理由だけではなかった。
違いは、もっと単純だった。前は、狩りの獲物だったが、今は、ハン
ターだった。役割が能動的で、受動的でなかった。霧中は、友達で、敵
ではなかった。
計画は、必然的に、あいまいで、状況に合わせる必要があった。最初
のステップは、明らかだった。カネが必要なので、数ドルのドルを売っ
て、1万クレジットほどを得るチャンスを捜す。出会った者は、犯罪者
だろうから━━━霧中を歩き回ってるのは犯罪者だけだ━━━説得して、
必要なら45口径で脅して、違法な硬貨や紙幣を買ってくれる場所に案
内させる。
そう、彼は、狩られるのではない、狩る側のハンターの立場が気に入
った。生きるためにストーリーを書くよりも、もっと活発な役につける
ことが楽しかった。彼は、いつも、書くことを憎んでいた。
狩りは、もっと、楽しい。この種の狩りは、特に。今までは、一度も、
人間を狩ったことはなかった。
13 ジョー
5番通りを、南に向かった。最初の数ブロックは、チチェンイッツァ
やカルデアのウルの遺跡を手探りで進んでいるようだった。そのとき、
突然、獲物の音が聞こえた。
それは、ビルの正面に立っていた者が、ケイスのように、靴を脱いで、
静かに歩く足音だった。聞こえたのは、かすかだが、はっきり鼻をすす
る音だった。
彼は、静かに立ち止まったまま、音がふたたび聞こえるまで、息音も
させなかった。男は南へ移動していた。2回目の鼻をすする音がして、
その方向へ、さらに進んでいた。
スピードを上げて、獲物の位置を捕えたと確信できるまで、ほとんど
走った。歩道を直角に横切り、手を前に出して、手探りしながら、ビル
の正面に来た。そのとき、獲物が近づいて来る方を向いて、ポケットか
らオートマティクを抜いて、立って待っていた。
その瞬間、なにかが銃の銃口に当たり、ケイスは左手を伸ばして、逃
げようとする男のコートをつかんだ。
「動くな!」と、彼。鋭く。「よし、こっちを向け、ゆっくりと!」
答えは無かったが、鋭く息を吸う音がした。男は、ゆっくり振り向い
た。ケイスの手は、男をつかまえていた。男の背中がこちらにあるとき
に、ケイスは左手で手探りして、右の尻ポケットにあるリボルバーを抜
いた。それを、自分の左ポケットに滑り込ませ、すぐに、手を男の肩に
戻した。もっとも危険なところは、終わった。
彼は言った。「まだ、動くな!おしゃべりしよう!あんたはだれ?」
固い声は言った。「オレがだれだか、気になる?取れるものは、30
クレジットとその銃だけ。それを持ってけ!カネも!そしたら、逃がし
てくれ!」
「おまえの30クレジットはいらない!」と、ケイス。「情報が欲しい。
すぐ情報を得られたら、銃も返してやる。このあたりに、つては?」
「どういう意味?」
ケイスは言った。「セントルイスから着いたばかり。ここのやり方が
分からない。防御柵を見つけたい。今夜」
間があった。それから、少し固くなくなった声は言った。「宝石?あ
るいは?」
「硬貨と、数枚の紙幣。前の35ドル分。そいつを、このあたりで扱っ
てるのは?」
「オレの報酬は?」
ケイスは言った。「あんたの命、1つには。たぶん、銃も返す。それ
と、もし邪魔しないなら、100クレジット。もしもいい値を付けてく
れるやつを紹介してくれたら、200クレジット」
「いいね、500にしてくれ!」
ケイスは笑った。「駆け引きが、うまいね。230にしてやる。あん
たは、すでに30はもらっている。一度オレが、あんたの30を取って、
そして、返したから」
驚いたように、男も笑った。「あんたの勝ちだ、ミスター。ロスを紹
介する。ほかのだれより、あんたを悪く、だますことはない。こっちだ」
「最初に1つ」と、ケイス。「後ろを向いて、マッチを擦れ!おまえの
顔を見たい。別れても、また会ったら、分かるように」
「オーケー」と、声。今はリラックスして、フレンドリーだった。
マッチが擦られ、火がついた。
ケイスが捕えた者は、彼が見たところ、背が低いやせた40くらいの
男で、それほどひどい服装ではないが、ヒゲを剃る必要があった。ニヤ
リと笑い、体が一方に傾いていた。
「あんたは、オレを知ることになる」と、彼。「あんたにもハンドルネ
ームが必要だ。オレは、ジョー」
「オーケー、ジョー。ロスというやつは、ここから近い?」
「2ブロック先。やつは、ポーカーゲームをやってる」マッチが消えた。
「教えて、セントルイ、それは、いくらになるんだい?」
「ある者が言うには、1万クレジット」
「それなら、あんたは、5千もらえる。ロスは、いつも、半々。だが、
聞いて!銃があるにせよ、ないにせよ、オレを仲間にした方がいい。そ
こには、別の男たちがいる。あんたは、オレがあんた側にいないと、い
いように扱われる」
ケイスは少し考えてから、言った。「たぶん、あんたはそこで助けに
なってくれる。10パーセント━━━5千なら、500━━━で、あん
たを仲間にする。十分、フェア?」
「ああ、かなり、フェアだ」
ケイスは、1秒だけ、ためらった。仲間は必要だったが、ジョーの声
には、彼にチャンスを与えさせるようななにかがあった。もともと、彼
の計画全体は、絶望的なギャンブルで、今の、わずかな危険は、後で、
大きな危険になるかもしれなかった。衝動的に、ジョーのリボルバーを
ポケットから出すと、ジョーの手に握らせて、銃を返した。
しかし、ジョーの声には驚きはなく、言った。「サンクス。2ブロッ
ク先。そこまでオレが先に行くので、ついて来い。手は、オレの背中に
置いておいた方がいい」
ふたりは、ビルの正面に沿って、ひとかたまりになって移動し、2つ
通りを渡るときは、腕を固定した。
ジョーは言った。「もっと体を寄せろ!角から2つ目と3つ目のビル
のあいだを路地に入る。オレに触れてないと、通り過ぎてしまう!」
路地に入ると、ジョーはドアを見つけ、3回ノックしてから、2回ノ
ックした。
ドアがあくと、明るい光に、ケイスは、一瞬、目がくらんだ。ふたた
び目が見えるようになると、ドアのところにいる男は、短銃身ショット
ガンを下げていた。彼は言った。「ハイ、ジョー、こいつもいっしょ?」
ジョーは言った。「ああ、セントルイスから来た、友人。ロスにビジ
ネスの話がある。彼は、ゲーム中?」
ショットガンの男は、うなづいた。「中へ」
狭い廊下に沿って行くと、突き当り近くに、マシンガンを持った男が、
閉じたドアの脇のイスの前に立って、銃口をこちらに向けていた。「は
い、ジョー」と、男。イスに座って、銃をヒザの上に乗せた。「ゲーム
の参加者を連れて来た?」
ジョーは頭を振った。「いや、ビジネスの方。ゲームはどう?」
「ロスは、今夜はついている。よっぽどラッキーでなければ、参加しな
い方がいい」
「しない。ロスがついていて良かった!たぶん、いい値をつけてくれる」
彼は、ガンマンが座っている横のドアをあけて、煙でブルーの室へ入
った。ケイスは続いた。
グリーンのポーカーテーブルの周りに、5人の男がいた。ジョーは、
そのひとりのところへ歩いて行った。太った男で、分厚いメガネを掛け
て、髪の毛はなかった。彼は親指を上げて、ケイスを指した。
「セントルイから来たオレの友人、ロス」と、彼。「いくつかの硬貨と
紙幣を売りたい。あんたは、相応のカネで買ってくれると、言ってある」
厚いメガネの男は、ケイスの方を向いた。ケイスは、うなづいた。ポ
ケットから硬貨と紙幣を取り出して、太った男の前のグリーンのテーブ
ルに置いた。
ロスは、それぞれ調べてから、顔を上げた。「すばらしい」と、彼。
「5つまとめて、取引したい」と、ケイス。「1万の価値がある」
ロスは、頭を振って、配られたばかりのカードを手にした。「1ヤー
ド離れて!」と、彼。
ケイスは、だれかが腕に触ったのを感じた。ジョーは、彼を引いて、
テーブルから1歩下がらせて、言った。「前に言っただろ、ロスは1プ
ライスだって。彼が4千と言ったら、4千と1はくれない。彼の言った
値段か、あるいはやめるしかない。値段交渉はしない」
「オレがやめたら?」と、ケイス。
ジョーは肩をすくめた。「ほかに2・3人知っている。しかしそれは、
彼らに会いに、霧中を歩かなければならないということ。彼らに会える
か、あるいは、溝でオレたちが死んでるかだ。たぶん、彼らも、ロスの
付けたカネ以上は出さない。それらが1万と言ったのは、査定のエキス
パートかなにか?」
「いや」と、ケイス。認めた。「オーケー、ロスの言い値を受け入れよ
う。すぐに、現金で?手持ちは多い?」
ジョーはニヤリとした。「ロス?彼が10万以下しか持ってなければ、
オレはアルクを1匹丸ごと食べてやる。現金のことは気にしなくていい。
4つのグランドピーナッツを彼に!」
ケイスは、うなづいて、テーブルに向き直った。ポーカーの手が終わ
るのを待って、言った。「オーケー、グランド4つで、どう?」
太った男は、ポケットから太った財布を出して、千クレジット紙幣を
3枚に、百クレジット紙幣を10枚、数え上げた。ケイスの硬貨を、慎
重に、紙幣の内側に包み戻すと、それらを、チョッキのポケットに入れ
た。
「しばらく、ゲームに参加しないか?」と、彼。
ケイスは、頭を振った。「ソリー、することがあるもので」
彼はジョーを見た。ジョーは、カネの勘定を終えて、ここでは取り分
をもらわない意味で、かすかに、頭を振った。
ふたりは、また、外へ出た。マシンガンをヒザに置いた男と、外のド
アの横の短銃身ショットガンを持った男の脇を通り過ぎた。外のドアは、
ふたりが出ると、ボルトが締められた。
◇
ふたたび、霧中だった。ドアの音から遠ざかると、ジョーは言った。
「4千だから、オレは400だ。あんたが数えるあいだ、マッチの火を
持ってて欲しい?」
「オーケー」と、ケイス。「一杯やって、数分、話しができる場所を、
あんたが知らなければ。たぶん、もっとビジネスの話しができる」
「アイデアがある」と、ジョー。「とにかく今夜は、400あれば、楽
しめる。明日もそうなら、明日の夜が楽しみだ。ああ、ノドが渇いた」
「どっちの方向、ジョー?」
「肩に手を置いて!分け前もらうまでは、いっしょにいてくれ!」彼は、
ため息をついた。「早く、ムーンジュースの香りをかぎたい」
「オレも」と、ケイス。非文法的に、まったく真実でなかったが。カリ
ストカクテルの味とは違っていてくれ、と願った。
ジョーの手をつかんでから、肩を見つけた。ジョーは言った。「よし、
出発」ふたりは、路地から出て、南に向かった。たった半ブロック行っ
ただけ、今回は、通りも渡らなかった。ジョーは止まり、言った。「こ
こだ、ちょっと待ってて」
また、ドアをノックした。今度は、2回のあと3回だった。今度は、
ドアは内側に、薄暗い廊下へ開いた。だれも、いなかった。
ジョーは言った。「オレだ、レロ。ジョーだ。それと、友人」中へ入
って、廊下を進んだ。ケイスは続いた。
「レロは、プロクシーなんだ」ジョーは、廊下を歩いてるときに説明し
た。「ドアの上の棚の上から見ていて、廊下を歩くあんたを知らなけれ
ば、後ろから跳び掛かる」
ケイスは、振り向いて、肩の上を見た。いないことを願った。ドアの
上の棚の上になにがいたにせよ、暗い影におおわれて、よく見えなかっ
た。たぶん、見えない方が、心のやすらぎには良かった。悪魔のような
触覚を持ったカメのように見えた。目は、大きな赤のレンズをバックに
フラッシュ光バルブのように、明るく赤に光っていた。見たところ、武
器は持ってなかったが、必要もないこぶがあった。
プロクシーは、プロキシマ・ケンタウリから来た生物なのか?ジョー
に訊きたかったが、たぶん、飲み物を頼んで座ったあとで、レロの話題
に持って行けるだろう。
彼は、振り返り、廊下を歩いているあいだ、のぞき穴のあるドアに着
くまで、背筋に冷たいものを感じた。禁酒法の時代のようだ、と彼は考
えた、あやうく口に出し掛けたが、ベティが禁酒法と聞いても、無反応
だったことを思い出して、ギリギリ口に出すのを思いとどまった。
ジョーは、また、2回のあと3回のノックをした。ふたりは、のぞき
穴から調べられた。ジョーは、指を彼の肩の上にあげて、言った。「オ
レといっしょだ、ハンク。彼は大丈夫」すると、ドアが、ふたりのため
にあいた。
レストランのバックルームへ入った。あいたドアから、ケイスは、バ
ーや薄暗いグリーンとブルーのネオンが見えた。ふたりが通された室は、
テーブルがいっぱいで、そのうちの3つで、カードゲームが進行中だっ
た。
ジョーは、入って来たときに顔を上げたなん人かに手を振ってから、
振り返ってケイスを見た。「ここに座る?」と、彼。「それとも、バー
の方へ行く?向こうの方がしゃべりやすいかも、もしも、ビジネスの話
があるなら」
ケイスは、うなづいた。「バーの音楽の方がいい」
ふたりは、ドアを通って、グリーンとブルーの光のバールームへ入っ
た。バーテンダー以外には、3人の女がバーカウンターのスツールに座
っているだけだった。3人の女は、ふたりが来ると、顔を上げた。ケイ
スは、ひとりの女が、ベティが着てたような、ものすごく生地の少ない
簡単なコスチュームを着ているのに気づいた。ブルーのシルクのブラと
ショーツに、ブルーの皮のブーツ、それだけだった。しかし、彼女は、
それ以外は、まったくベティに似てなかった。少なくとも、20は年上
で、太って、だらだらしていて、少し酔っていた。ブルーグリーンの光
が、彼女を幽霊のように見せていた。
ジョーは、彼女に手を振って、言った。「ハイ、ベッシー!」そして、
もっとも遠いブース席に行って、イスのひとつに座った。ケイスは、向
かいのイスに座った。
ケイスは、ジョーの400クレジットを出そうとして財布を出したが、
ジョーはすぐに言った。「まだだ、パル。女たちがここへ来るまで待っ
て!」
女たちは、もう、来ていた。スペースガールの衣装を着た女でない、
ほかのふたりの女たちが。ふたりとも若く、ブルーグリーンの光が肌に
当たっていても、魅力がないわけでなかった。
幸運にも、ジョーはふたりが座る前にうまくごまかして、言った。
「ビジネスの話があるんだ、ガールたち。少ししたら呼ぶので、それま
で、オレのおごりだと言って、スペックになにか作ってもらって!ベッ
シーの分も!」
ひとりが、「いいわ、ジョー」と言って、ふたりはバーカウンターの
スツールに戻った。
ケイスは、財布を、また、出して、スペックが注文を聞きに来るまで
に、400クレジットを手渡すのに成功した。ジョーは、100クレジ
ットの1枚をテーブルに置いた。
彼は、言った。「ムーンジュース2つ、スペック。あと、女たちに1
杯づつ。レロは、今夜は調子はどう?」
バーテンダーは笑った。「悪くないよ、ジョー。廊下を2回そうじし
なきゃならなかった。早い時間に」
彼は、バーカウンターに戻って行った。チャンスだった。彼は言った。
「レロに興味がある、ジョー。彼について、なにか教えて!」それは、
トラブルに会わないための、一般常識だった。
ジョーは言った。「レロは、レニーなんだ。群れでも、もっともタフ
なやつ。ニューヨークでも、とにかく、もっともタフだった。ケンタウ
リでの小競り合いのとき、潮目を変えるために連れて来た、最初のプロ
クシーの1匹だった。彼に会いたい?」
「いや、別に」と、ケイス。「疑問に思っただけ」彼は、口に出さなか
ったが、レニーは裏切り者の俗語なのか?と疑問に思った。もしも、レ
ロが、戦争の潮目を変えるために連れて来たプロキシマ・ケンタウリの
生き物なら、彼が裏切り者であることには意味があった。
ジョーは言った。「自分を責めるな!しかし、もしもあんたが、また
いつか、ここへ戻ってきたいんだったら、会っておいた方がいい。20
フィート先から、彼は、1つの目で、あんたを見る。そう、兄弟、もし
も、彼が両目を使ったら、モップ掛けを邪魔するどころではなくなる。
オレは、あんたにチップをやる」
「そう?」
「ドアを通るときに、彼に話し掛けてみな!彼にみつめられるまで、待
たないで、そうでないと手遅れになる。ここのほとんどのやつらに起こ
ったことが起きて、また、そうじをしなきゃならなくなる」
ジョーは、ハットを頭の後ろまで上げて、ニヤリとした。「あんたは
いいやつだから、みんなしゃべった━━━ところで、オレたちは、もっ
とビジネスの話ができる」
「それについては」
「まだだ」と、ジョー。さえぎった。「ムーンジュースを1杯飲むまで
は、とにかく、だめだ。オレは、あんたの仲間になるべきか、あるいは、
あんたとビジネスしたいのか、分かるか?あんたは、ひとのことを信用
し過ぎる、それで、トラブルに巻き込まれる」
「オレに仲間になれと?」
ジョーはうなづいた。
「ならなかったら?」と、ケイス。
ジョーの手は、自分の無精ひげのアゴを、やすりのような音を立てて、
こすった。それから、ニヤリとした。「その点については、正しくない、
セントルイ。もし仲間にならなかったら、あんたを乗っ取るだろう。あ
んたがロスとしゃべっていたとき、オレは後ろで、合図を送っていた。
もしもあんたが仲間でなかったら、オレは合図を送らない。ここでもそ
うだ、パル、あんたに長くいて欲しくなければ、長くはいられない」
スペックが、軽いミルクのような液体の入ったショットグラスを2つ
持って来たので、しゃべるのをやめた。ジョーの100クレジット紙幣
を拾い上げると、おつりを紙幣で置いた。
ジョーはグラスを上げた。「アルクに死を!」と、彼。ひと口すすっ
た。
「急に来る!」と、ケイス。ジョーもミルクのような液体を、たったひ
と口すすっただけで、同じことをした。ひと口すすると、ノドが燃える
ように熱くなった。まるで、ジンをタンブラーで半分飲んだときのよう
に。チリパウダーのように熱く、逆説的だが、クールでもあった。シロ
ップのように濃厚だが、甘かった。口の中で、舌はクールになって、か
すかにミントの味がした。
「本物だ」と、ジョー。「すぐに、宇宙の貨物船の気分になる。こんな
味の経験は?」
「少しは」と、ケイス。注意深く。「この味そのものは、初めてだが」
「どんな気分?」
「フェアな気分」と、ケイス。なるべく、しゃべらないようにしたかっ
た。しかし、1音節の返答を続けるのは、危険だった。ムーンジュース
のグラスを見ながら、なにでできていて、どんな効果があるのか、と疑
問に思った。
ひと口飲んだだけでは、なにも感じなかった。
「どこに、泊まる?」
「どこにも」と、ケイス。「ブラついてるだけ。霧中の前に、泊まる場
所を決めるべきだったが、つてがなかった。しかし、たいした問題でな
い。ゲームをやっていて、手持ちのクレジットをすべて失った。それが、
今夜、硬貨をカネに替えたかった理由。それがなかったら、オレは、無
一文だった。それに賭けて、収集家に直接、いい値で売りたかった」
それが、とケイスは考えた、ジョーに、なぜ霧中にひとりでいたか説
明したことになった。すぐに売りたかった硬貨の説明には、なってなか
ったが。そして、外面上は、それでよかった。ジョーはうなづいて、言
った。「そう、あんたが夜遅くまで穴にこもりたいなら、ここにいられ
るようにできる。付きの室か、付きでない室」
ケイスは、なに付きなのか、訊かなかった。「あとで、借りる。夜中
の子犬」と、彼。そして、ほんとうにそうだったことに気づいて、驚い
た。暗闇が来てから、まだ、1時間半もたってなかった。
ジョーは、心から笑って、言った。「夜中の子犬。いい表現だ。今ま
で聞いたことないが、いい。知ってる、パル、あんたが好きだ。そう、
準備は?」
準備って、なんの?と思ったが訊かなかった。「確かに」と、ケイス。
ジョーは自分のグラスを持ち上げた。「それじゃ、出発だ!戻ったら、
会おう!」
ケイスも自分のグラスを持ち上げた。「ハッピーな着陸」
ジョーは大声で笑った。「また、いいね。ハッピーな着陸。盛り上げ
方を考えてる、パル。ほんとによく盛り上げ方を考えてる。耳に泥が詰
まってる?」
彼は、飲み物を下にこぼした。そして、ポーズを取った。銅像のよう
に、グラスを口にあてたまま。目は、開いてはいるが、ガラスをはめた
ようだった。ケイスも自分のグラスを口に持って行ったが、飲み物を下
にこぼさなかった。今は、まだ。彼はテーブルの先の幻想的なジョーを
見た。ジョーはこっちを見てなかった。ジョーはこの世のなにも見てな
かった。
ケイスは、急に、バーカウンターの下を見た。バーテンダーも3人の
女も、彼の方を見てなかった。テーブルの下へ行くと、ムーンジュース
の残りを床にこぼした。それから、グラスを口にあてた。
彼は、ちょうど、間に合った。ジョーの目は、一度、瞬いた。それか
ら、突然、生気が戻って、硬直が解けた。グラスを下に置くと、深い溜
め息をついた。
彼は言った。「うう、金星にまた、戻っていた。泥だらけの沼地だっ
た。しかし、そこが好きだった。スペースガールがひとりいた」驚いた
ように、頭を振った。
ケイスは、興味深そうに観察していた。副作用は、なんであれ、まっ
たくなかった。10秒か20秒間、彼は完全に麻痺していた。今は、完
全に元に戻っていた。前とどこも変わらなかった。
ジョーは、ポケットからタバコを取り出すと、ケイスに1本差し出し
て、言った。「1本どう?それから、ビジネスの話がしたいなら、オー
ケー!」
「オレの方なら、大丈夫」と、ケイス。彼は、バーカウンターの下をチ
ラッと見て、今度は、バーテンダーと目が合った。指を2本上げると、
バーテンダーはうなづいた。見た通りに、それは、どこでも通用するシ
グナルだった。ここでさえ。
ケイスは、自分の紙幣を1枚、テーブルの上に置いた。自分の中で盛
り上がる興奮に気づいた。今度は、自分で、ジョーがやったように、ミ
ルクのような液体をこぼそうと決心した。あの10秒か20秒の間に、
ジョーになにが起きたのか解明しようとした。ジョーは、そこから飛び
出て行ったが、大丈夫だった。ジョーができたのだから、オレにもでき
るだろう。限界があることだけ気をつけよう。
ムーンジュースが来た。70クレジットの釣りが置かれていた。
ジョーは、自分のグラスを持ち上げた。ケイスもそうしたが、ジョー
は、ただ、ひと口味わって、唇をぴしゃっと言わせただけだった。ケイ
スもそうした。
見たところ、最初にちょっと味わい、それからちょっと話すのが儀式
で、飲み物を、すぐにこぼす行儀の悪さが必要なのだろう。
2杯目は、1杯目よりうまかった。そんなに燃えるほど熱くないし、
後味のミントの香りもまったくしなかった。なんの味か分からない味だ
った。
とにかく間があったので、彼は、気持ちがビジネスの方へ向かうのを
妨げられないと思った。テーブルに少し寄り掛かった。「ジョー」と、
彼。「オレがどこで、ほとんどカネを稼げそうにない元宇宙パイロット
を見つけたか分かる?」
ジョーは、笑いそうになって、それから、目を細めた。「ふざけてる
のか?」と、彼。
つまり、それは悪い質問だったらしい。ケイスには、なぜ悪いのか分
からなかった。とにかく、今はそこに向かっていたので、間違ってると
言われても、引き返すことができなかった。
なんとなく、手を、オートマティックを入れてあるポケットに入れた。
どうやったら、撃ってでも、ここから逃げ出す方法がないか考えた。プ
ロクシーのレロが守っているドア以外のドアから。ジョーがシグナルを
送ったら、あまり良い結果をもたらさない、と彼は考えた。しかしたぶ
ん、なにか間違っていても、ジョーがシグナルを送る前に、ジョーから
逃げなければならなかった。
彼は、冷たく、ジョーを見た。指先が、すでにオートマティックの台
座に触れていた。
「どうして、オレがふざけてると?」と、彼。
14 宇宙監視官フー
ジョーがニヤリとしたので、ケイスは、ホッとした。彼は、親指でコ
ートのえりを上げた。ケイスは、前に自分も付けていた、破れガモのエ
ンブレムがあるのに気づいた。
「あんたは、目が節穴か、セントルイ?」と、ジョー。
ケイスは、手をポケットから出した。あぶなく、大間違いをしでかす
ところだった。「気づかなかった、ジョー」と、彼。「目が節穴かも。
オレたちは、ほとんどの時間を霧中で過ごしていた。そこでは、そんな
に目立たなかった。隊には、どのくらい長く?」
「5年。ほとんどは、基地勤務だった。おもに、火星のカピにいたんだ。
数日前にそこにいなくて良かった」頭をゆっくり振った。「カピには、
もう、なにも残ってない」
ケイスは言った。「また、再建できる」
「かもな」
「悲観的だな、ジョー」
ジョーは、別のタバコに火を点けて、深く吸って言った。「もうすぐ、
ショータイムが来る、セントルイ。でかいやつだ。うう、オレはなにも
知らないし、なにも語れないが、とにかく、前線のあいだになにがある
か、読み取ることはできる。アルクに突撃して、そこへ行ってみれば、
なにが起こっているか感じ取れる。大規模な攻撃が来る。オレは、アル
クは準備を進めていると考えている。手詰まりは終わった。戦争も、も
うすぐ終わる。どちらかの勝利で。オレが怖れているのは━━━」
「なに?」と、ケイス。うながした。
「オレが怖れているのは、やつらが、なにか新しいものを作ったことだ。
今までは、ちょうど均衡が取れていた。もしも新しい兵器が━━━言っ
てる意味分かる?」
ケイスは、おごそかに、うなづいた。その話題にこだわって、自分は
できるだけしゃべらない方が良いことを思い出した。戦争について、イ
ンテリぶって語れなかったので、ジョーに安全な場所にいてもらって、
彼がしゃべりたい話題へと導いてもらう方が良かった。ジョーがほんと
うに宇宙船のパイロットだったのか、あるいは、ただの機銃砲手かなに
かだったのか知りたかった。
「最近、月へは?」と、彼。
「1年前」ジョーの唇は、曲がっていた。「その頃はまだ、霧中が始ま
ってなかった。オレは、多くのみんなより、ずっと長く戦争に行ってい
た。引退したチャンピオンのように、行儀の良い生活ができると思って
いた。しかし、月に関しては、違った。金持ちの男を、彼の所有する船
で、月へ連れてった。なんという旅だったことか!」
「悪かった?」
「いや、良かった、パーティ参加者は6人で、休日の炭坑夫のように酔
っぱらっていた。アーリング船で宇宙を旅するのは、6才の子どもでも
簡単にできた。しかし、6人のだれも、操縦できるほど素面のやつはい
なかった。彼らが行き着いた果ては、スバル星だった。
オレはタクシーを運転していて、ある日の午後、タイムズスクエアで
彼らを乗せ、ジャージーにあるプライベート宇宙ポートへ連れて行った。
船を所有していた男は、オレの銅ニワトリエンブレムを見て、1千で彼
らを宇宙へ連れて行ってくれと言って来た。オレは、2年間、地球を離
れていなかったので、宇宙船を操縦したくてうずうずしていた。たとえ、
アーリング船のような子どもだましの船でも。それで、自分のタクシー
をジャージーの道路脇に乗り捨てて行ったので、タクシーの仕事と免許
を失って、戻って来たときには、霧中をさまようことになった。だが、
彼らを月へは連れて行った。なんという旅だったことか!オレたちは、
洞窟探検へ行った」
「オレもいつか、行きたい」と、ケイス。
「カリストよりいい。しかし、よほど洞窟探検のことに詳しくなければ、
やめておいた方がいい。オレたちは、そこに2週間行っていた」唇を曲
げたまま、ニヤリとした。「オレの千クレジットは、ちょうど1日もっ
た。それは、買い物はすべて彼らがしてくれたからだ。しかし、オレを
片時も離さず、そこにいるあいだずっといっしょで、支払いはすべてし
てくれた」
ケイスは、話題をもとに戻した。「アーリング船の操縦は、ふつうの
船とは違う?」
「同じ。違いは、ローラースケートとレーシングカーくらいのもの。ア
ーリング船は、すべてがビジュアル化されていて、目標物を直接見なが
ら、ボタンを押せる。宇宙に飛び出て、翼を広げたり、滑空したりでき
る。自動的に誤差を補正し、自動ジャイロスコープを備え、すべてが自
動化されている。ムーンジュースを飲むくらい複雑ではあるが。それで、
思い出した!準備は?」
「オーケー!」ケイスはグラスを上げた。「アルクトゥルスに死を!」
「出発だ!ハッピーな着陸!」
ケイスは、今度は、飲み物をこぼした。
◇
燃えるような熱さは、まったくなかった。たぶん、いっぱい口にふく
み過ぎて、燃えるには多すぎたのだ。起こったことは、大きなハンマー
でアゴを殴られて、同時に、ロープを首に掛けられ、上に吊るされ、天
井を抜け、霧中の漆黒を抜け、上空の冷たいブルーの空に抜けると、一
気に晴れ渡り、下の霧中が、巨大な黒のディスクのようになった。一方
の側では、月が町や野原を照らし、別の側では、大西洋が平坦に広がり、
ちらちら光っていた。
それから、首に巻き付いていたロープがゆるみ、消えて、しかし、彼
の体は、上へ上へと昇って行き、渦巻きのようにゆっくり回転し、ある
時は地球が見え、ある時は星や大きな三日月が見えた。地球は、ボール
のように縮み、巨大な暗いボールが、片側から照らされ、地球が三日月
のようになり、だんだん小さくなって、一方、月は大きくなって行った。
星のいくつかは、明るく、ディスクのようで、いろいろな色で燃える小
さなディスクになった。
月も、彼の回転で見ると、1つのボールだった。地球のように大きく
はなかったが、今まで見たものより、ずっと大きかった。彼は、大気の
外、宇宙にいたが、本で読むような冷たい宇宙ではなかった。暖かく、
楽しく、今まで聞いたことがないような音楽まで流れていた。すばらし
い音楽で、彼の回転をタイミングを取って支えてくれていた。あるいは、
彼が回転しながらタイミングを取って、音楽を支えていた。どっちなの
かは重要でなく、どっちでもよかった。浮かび、回転し、今までのもの
からすべて自由であることの、すばらしい感覚以外は、どうでも良かっ
た。
それから、回転しているとき、月の影になにかあるのを見つけた。長
く、葉巻のような形をしていた。それは、宇宙船だった。そう、つぎに
回転したとき、そこにいくつかの光るポートがあるのが見えた。両側に、
伸縮自在の翼があった。
そして、彼は、それに向かって、ぶつかって行った。
実際にぶつかったが、傷つかなかった。その片側にある壁に沿って右
に進み、厚いカーペットの上に、無傷のまま、座った。美しく飾られ、
ロココ調家具が置かれた、上流階級の居間のようだった。宇宙船の中に
居間?白のペンキが塗られた鉄製の壁に収縮すると、それは、いつでも
寝られるように、黒のシルクのシーツが敷かれたベッドだった。
彼は、すぐに立ち上がった。起きて、立ち上がるのは、おそろしくや
さしかった。いつもより、体重が半分くらい軽くなったのを感じた。そ
して、前より2倍強くなった。やろうと思えば、山でも動かせる気がし
た。重力が軽くなった、と彼は考えた。
それから、考えるのをやめた。なぜなら、ドアがあいて、鉄製のパネ
ルが鉄製の壁に入り、そこから、ベティハードレイが出て来たからだ。
彼女は、また、スペースガールの特権だと言った、衣装を身につけて
いた。今度は、白のシルク製だった。狭いが、すばらしい2つの丸い白
のシルクのブラ。とても短い白のシルクのトランクス。あまりにピッタ
リなので、ペンキで描かれたと思われそうだった。だれか偉大な画家に
よって。そして、輝く白のエナメルのブーツ、半分の高さまで、美しく、
なん頭かの牛が彫られていた。
ほかにはなにもなかった。ベティハードレイを除いて。黄金の肌、黄
金の髪、大きくてブルーの目、やわらかく赤の唇、顔は、天使よりも美
しかった。
彼女は、信じられないくらい美しく、信じられないくらい望まれてい
て、数フィートのところからこちらを見ていて、彼は、ほとんど息がで
きなかった。
彼女は、見たところ、彼がそこにいるのに気づかないまま、ドアから
出てきた。そして、彼を見て、彼女の顔は輝き出した。彼の方に白の腕
を伸ばして、言った。「ダーリン、おお、わたしの愛する人!」
彼の方に走って来て、腕を彼に回し、体を強く押し付けた。彼女の顔
は、彼の肩にうずもれた。それから、キスのために唇を上げた。目は愛
に潤み━━━
◇
「うう」と、ジョー。「あんたは、40秒か50秒も行ったきりだ。今
までムーンジュースを飲んだことないのか?」
グラスは、まだ、唇にあった。口に火のような熱さがあって、ノドの
下も、横隔膜まで熱かった。彼の目は、ゆっくりと、ジョーの醜い顔に
焦点が合ってきた。だんだん、彼の体は、下のベンチや肘をついてるテ
ーブルの感覚を感じ始めた。ふたたび、徐々に、体重は変化し、前と同
じくらいの体重まで増え、もはや、強くは感じなかった。
光は、ブルーグリーンのネオンで、それを通して、背の低い元宇宙パ
イロットを、ポカンと見ていた。
「飲んだことなかったんだろ?」と、ジョー。
ジョーが言ってることが分かるまで丸1分かかり、頭を振ろうと決心
するまで丸1分かかり、それを行動に移すまで丸1分かかった。
ジョーはニヤリとして、言った。「そう、おかしな飲み物だろ?なん
ども飲むうちに、すぐノックアウトされて、しかし、行ってる時間は、
長くなる」
(つづく)