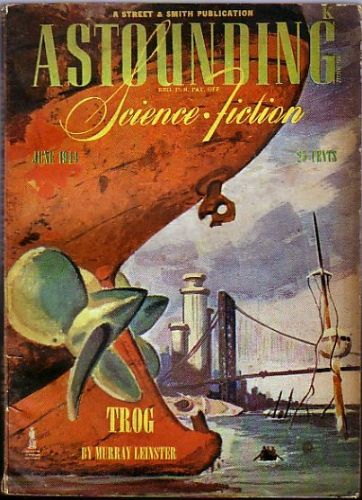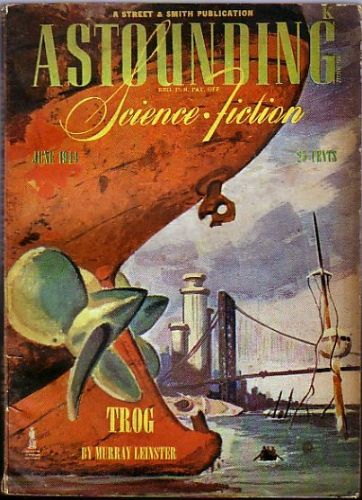アリーナ
原作:フレドリックブラウン
アランフィールド
プロローグ
カーソンは目を
開けると、自分が点滅する青のほんやりしたドームの
ようなものの下にいることに気づいた。
暑く、砂の上に寝ていたので、砂に埋もれた岩が背中に当たって痛か
った。横向きになって岩をよけると、結局、起き上がって、座る姿勢に
なった。
まったくどうかしている、と彼は考えた。とんでもない!それとも死
んだのだろうか?あるいは、別の。
砂は青だった。明るい青。地球には、いや別の惑星にも、こんな明る
い青の砂のようなものはない。青のドームの下の青の砂。空でもなく、
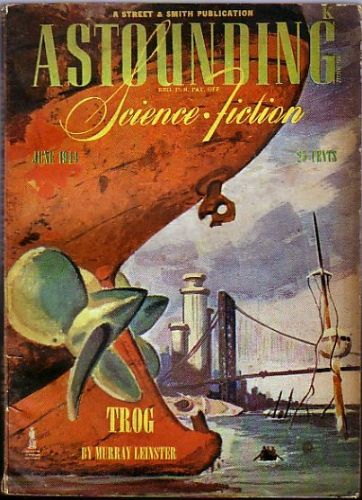
室でもなく、有限のエリア。まわりの状況が分かってきた。有限だが、
天井は見えなかった。
手で砂をつかんで、指の間から砂を下へこぼした。それは、彼の裸の
足の上に落ちていった。裸?
彼は、完全な裸だった。体からは、ぐったりするような暑さから、汗
がしたたり落ちていて、砂にまみれているところは青になっていた。そ
れ以外の体の部分は、白だった。
つまり、と彼は考えた。この砂は本当に青なのだ。もしも、青の光で
青だったら、オレ自身も青になるはずだ。しかし、オレは白だ。つまり、
砂は青だった。青の砂。どこにも青の砂などなかった。オレがいるここ
のような場所は、どこにもなかった。
汗が目を伝わって落ちた。暑かった。地獄よりも暑かった。地獄は、
祖先の人々のいる場所は赤で、青ではなかった。
しかし、この場所は、地獄ではなかった。どこなんだ?惑星の中では、
水星がこのくらい暑いが、ここは水星じゃない。水星は、ここから40
0万マイル先だ。ここから?
1
そのとき、彼がどこにいたのか思い出した。ひとり乗りの偵察艇で、
冥王星の軌道の外側で、せいぜい100万マイルを偵察していた。そこ
は外宇宙からのアウトサイダーを食い止めるための、地球艦隊が引いた、
ぎりぎりの防衛ラインだった。
彼のレーダー範囲内にアウトサイダーの偵察艇が入り込んたことを知
らせる、かん高い警報ベルが、突然、鳴り響いた。
アウトサイダーがなにものなのか、誰も知らない。どんな姿をしてい
るのか、どの銀河から来たのか、スバル星の方角から来たこと以外、な
にも分かってなかった。
最初は、地球の植民地や前哨基地に散発的な襲撃があった。地球のパ
トロール船とアウトサイダーの宇宙船の間で、孤立した戦いがあった。
戦いは、時に勝ち、時に負けた。しかし、一度も、エイリアンの宇宙船
を拿捕できなかった。攻撃された植民地の誰も、船から降りたアウトサ
イダーの姿を証言できる生き残りはいなかった。アウトサイダーが船を
降りたとして。
最初は、それほど深刻な事態ではなかった。襲撃は多くはなく、破壊
的でもなかった。個別で見れば、宇宙船の装備は、こちらの最新の攻撃
艇に比べて、少し劣っていた。しかしアウトサイダーは、スピードと操
作性については、いくらか優っていた。それで、包囲したのでない限り、
逃げるか戦うかの選択は、アウトサイダーに委ねられた。
それにもかかわらず、地球は、深刻な事態を予想して、過去、最強の
艦隊を建造して準備した。艦隊は、長い間、待機していた。もうすぐ、
ショーダウンはやって来る。
200億マイル先の偵察艇は、アウトサイダーの強大な艦隊の接近を
感知した。偵察艇は一隻も戻らなかったが、無線メッセージが残ってい
た。1万の艦船に50万の宇宙戦士が乗り込んだ、地球艦隊は、今、出
動し、冥王星の軌道の外側で、アウトサイダーをインターセプトする、
地球存亡の決戦のために、待機した。
敵艦隊の戦力配置は、最前線の偵察艇が死ぬ前に必死に伝えてきた報
告で判明した。その戦いが始まろうとしていた。
微妙なバランスを保っている太陽系の、唯一の支配者を巡っての戦い。
チャンスは1回だった。最後のただ1回のチャンス。地球と、アウトサ
イダーがその挑戦を実行したらその慈悲にすがるしかない、すべての植
民地にとって。そう、ボブカーソンは今、思い出した。かん高い警報ベ
ルが鳴り響き、あわててコントロールパネルに跳びつき、大急ぎでシー
トベルトを締めた。スクリーンの点が、見る見る大きくなっていった。
口が渇いた。この戦いが、自分にとっては、真の戦いだということが分
かっていた。主要艦隊は、互いにまだ遠く離れていたとしても。
この戦いの最初の交戦!3秒以内で、彼が勝利者になるか、黒焦げの
燃えカスになるかが決まる。ワンヒットで、偵察艇のようなひとり乗り
小型艦は完全に破壊された。
大慌てで━━━彼の口は、「ワン」の形になっていた━━━スクリー
ンのくもの巣状の中心点が、見る見る大きくなっていくのに集中してい
た。手はコントロールパネルに、足は、ボルトファイアの発射ペダルの
上でタイミングを図っていた。一撃で仕留めなければならない。さもな
くば━━━チャンスは2度と巡って来ないだろう。
「ツー」そう言ったのかどうか、分からなかった。スクリーンの点は、
もはや点ではなかった。たった数千マイル先のものを、スクリーンは、
まるで数百ヤードしか離れてないもののように拡大して映し出した。そ
れは、彼のものとほとんど同じサイズの高速小型偵察艇だった。
そう、エイリアンの船だった!
「スリー━━━」
足は、ボルトファイアの発射ペダルを踏み込んだ。
そのとき、アウトサイダーは身を翻し、寸前で攻撃をかわした。カー
ソンは、大慌てでコントロールパネルを叩いた。
0・1秒で、やつはスクリーンから完全に消え、彼の偵察艇は、やつ
の背後を追尾し、ふたたびやつを見つけたとき、地面へ真っ逆さまに跳
び込んでいた。
地面?
それは、ある種の光学的な幻想を映し出す装置だった。そうに違いな
い。惑星は、どんなものであれ、今スクリーンに映し出されているよう
なものは、存在しなかった。たぶん、ありえなかった!海王星の近く3
0億マイルは、いかなる惑星もなかった。冥王星は、太陽の反対側で、
最も遠いところにあった。
船のレーダーによれば!惑星サイズのいかなる物体も、捉えてなかっ
た。小惑星サイズでさえ、まったくなかった。
それは、そこには存在しえなかった。どのようなものであれ、それは、
船が跳び込んだものであり、数百マイルに亙って、船の下に広がってい
た。
船がクラッシュしたのではないかという心配から、アウトサイダー船
のことを忘れていた。減速用のフロントロケットを噴かした。すると突
然の速度変化で、シートベルトに引っ張られて前面につんのめった。さ
らに緊急ターン用のロケットをいっぱいに噴かした。ロケットを静め、
下降させた。分かったことは、クラッシュは逃れて、ターンもできる、
船に異常はないということだった。そして突然、しばらく記憶を失った。
しばらくの、ブラックアウト。
2
それが、すべてだった。今、彼は、熱い青の砂の上に座っていて、完
全な裸だった。しかし。傷は負ってなかった。宇宙船の姿は見えず、そ
れゆえ、宇宙も見えなかった。上空のカーブは、なんであるにせよ、空
ではなかった。
足で歩いてみた。
重力は、地球よりすこし重いが、それほどでなかった。
平らな砂が広がっていて、やせこけたブッシュが、あちこちにあった。
ブッシュも青だが、その陰影によって、濃淡があり、砂の青より明るか
ったり、暗かったりした。
一番近くのブッシュから、小さな動物が走り出てきた。足が4本以上
あることを除けば、トカゲに似ていた。色は青で、明るい青だった。ト
カゲは彼を見ると、また、ブッシュの下に走って行った。
彼は、上がどうなっているのか調べるために、また、上を見た。それ
は正確には屋根ではなく、ドーム状だった。点滅していて、よく見えな
かった。しかし明らかに、カーブして地面に降りていた。青の砂へ。彼
の周り、すべてそうだった。
彼は、ドームの中心から、さほど離れてないところにいた。たぶん、
もっとも近くの壁まで、100ヤードある。それが壁だとして。それは、
円周が250ヤードくらいの何かでできた青の半球が、砂の平面に、引
っくり返ってかぶさってるようだった。
そして、すべてが青だった。1つを除いて。遠くのカーブしている壁
の近くに、なにか、赤の物体があった。ほぼ球体で、直径がだいたい1
ヤードに見えた。遠すぎて、点滅する青を通して、彼には、はっきりと
見えなかった。
しかし、なにか分からないが、彼は身震いをした。
彼は、手の甲で、額の汗をぬぐった、あるいは、ぬぐおうとした。
◇
これは、夢なのか?悪夢?この暑さ、この砂、あの赤の物体を見たと
きの、漠然とした恐怖の感情は?
夢?いや、眠ってなかったし、宇宙戦争の真っ最中に、夢を見るはず
ない!
死んだのか?いや、決してそうじゃない!不死があるとしたら、この
ような意味のないようなものではあり得ない。青の熱さ、青の砂、赤の
恐怖のような。
そのとき、彼は声を聞いた。
それは、耳からでなく、彼の頭の中から聞こえてきた。どこからとい
うわけではなく、あるいは、すべてのところから。
「空間と次元を抜けて、彷徨い」言葉が、彼の心の中に響いた。「そし
て、この空間、この時間に来た。ふたりの人間を見つけた。互いに殺し
合いを始めようとしている、一方は他方よりとても弱く、すぐに退化し、
運命を全うすることなく、朽ちて、もともとの埃へと戻ろうとしている。
オレは、これはあってはならないと言う」
「あんたはだれ?それとも、なに?」カーソンは大声を出さなかったが、
質問が頭の中で形を成した。
「完全には理解できないだろうが、オレは」声がなにかを、カーソンの
頭の中で捜しているかのような、間があった。存在しない言葉を、彼が
知らない言葉を。「オレは、とても古代の時代にいた、ある生命種の進
化の究極、あんたの心に対応する意味の言葉が見当たらない、生命種が、
唯一永遠の存在へと進化したもの。
あんたのような原始的種の存在は、今から時間をかけて━━━また、
言葉を捜して━━━究極になろうとする。同様に、あんたが━━━また、
言葉を捜して━━━アウトサイダーと呼ぶ種も、究極になろうとする。
それでオレは、戦いを中断させることにした。両艦隊が激突して大きな
破壊に至る前に。一方が生き残り、進歩し、進化する」
「一方?」カーソンは考えた。「オレ、それとも?」
「オレの力で戦争をやめさせ、アウトサイダーを彼らの銀河へ追い返す
ことはできるが、彼らは戻ってくる。それがイヤなら、あんたらの種は、
遅かれ早かれ、彼らに服従するしかない。この空間と時間にとどまり続
ければ、互いに戦争しないように見守ることはできるだろうが、オレは
ここにとどまり続けることはできない。
それで、今、オレは介入することにした。一方の艦隊は無傷で残し、
他方の艦隊を完全に破壊する。1つの文明は、そうして生き残る」
悪夢だった。これは、悪夢に違いない。カーソンは考えた。しかし、
彼は夢でないことも分かっていた。バカげていて、あり得なかったが、
しかし現実だった。
彼はあえて、訊かなかった。どっちが?しかし、考えたことが質問に
なってしまった。
「強いものが生き残る!」と、声。「結果は変えられない、変えない。
オレは単に、完全な勝利に至るまで、介入するだけだ━━━また、言葉
を捜して━━━敗れたものに、勝利をもたらしはしない。
戦い寸前の辺境から、ふたりの個体、あんたとアウトサイダーを拾い
上げてきた。あんたの心をのぞいて分かったことは、昔のナショナリズ
ムの戦いでは、チャンピオン同士が戦って、勝利した方がさまざまな争
いごとの決定権を持っていたそうだ。
あんたとあんたの相手は、ここにピットインして、互いに1対1で、
裸、武器は無く、対等な条件、お互いに慣れない場所、いずれにとって
も同じくらい不快な環境で相対する。時間制限はない。ここには時間は
ない。生き残った方が、その種のチャンピオン。その種は、生き残る」
カーソンは抗議しようとしたが、言葉にならなかった。声が答えた。
「対等だ。条件は、肉体的な力の強い方が、そのまま勝てるようには、
できていない。バリアがある。あんたには理解できないだろうが、頭脳
と勇気は、力よりも大切だ。とりわけ勇気、生き残るための意志」
「しかし、こんなことしてるあいだに、艦隊は━━━」
「大丈夫。あんたは別の空間、別の時間にいる。あんたがここにいる限
り、あんたの宇宙では時間は止まっている。この場所は現実なのか、と
疑ってるね?現実であり、非現実。あんたの限られた理解力では、オレ
が現実であり、非現実というのと同じ。オレの存在は、精神的なもので、
肉体的ではない。オレは惑星に見えるし、ちりにも、太陽にも見える。
しかし、この場所は、現実だ。ここであんたが傷を負えば、それは現
実。もしもここで死ねば、その死は現実。あんたが死ねば、その失敗は、
あんたの種の終わりになる。これでもう、知るべきことは十分」
そして、声はどこかへ行った。
3
ふたたび、彼はひとりになった。だが、ひとりではなかった。カーソ
ンが見上げると、赤のものが見えた。恐怖の球体は、今や彼は知ってい
た、それはアウトサイダーだった。彼に向かって転がってきた。
転がって。
それは、見たところ、足も腕もなく、形がなかった。それは、砂を転
がってきた。力が滴り、液体のようなすばやさで、前と同様、理解でき
ない方法で、むかつくような恐怖でうねりながら。
カーソンは、自分の周りを必死に捜した。石が、数フィート先の砂の
中にあった。武器になる最も近いものだった。それは大きくはなかった
が、角が鋭く、火打石の板のようだった。青味がかった火打石に見えた。
彼はそれを拾い上げ、攻撃に備えて、身をかがめた。やつは速く向か
って来ていた。彼が走るよりも速く。
やつとどうやって戦ったらいいのか、考えてる暇はなかった。やつの
力も、やつの特徴も、やつの戦い方も知らない相手に対して、どのよう
に戦うプランを立てたらいいのだろう?非常に速く転がって、完全な球
体以上のものに見えた。
10ヤードのところに来た、5ヤード。それから、やつは、止まった。
むしろ、やつは、止められた。まるで見えない壁にぶつかったかのよ
うに、やつの近い側が、突然、平らになった。やつは、バウンドした。
まさしく、バウンドして戻った。
やつは、また、転がって前進を始めた。前より、より慎重に。ふたた
び、同じ場所で止まった。やつは、また、試した。数ヤード場所を変え
て。
やつは、また、転がって前進を始めた。前より、より慎重に。ふたた
び、同じ場所で止まった。やつは、また、試した。数ヤード場所を変え
て。
そこには、ある種のバリアがあった。カーソンの心にクリックしたの
は、彼らをここに連れて来た存在が言った言葉だった。
「肉体的な力の強い方が、そのまま勝てるようには、できていない。バ
リアがある」
そう、フォースフィールドだ。地球の科学で知られている、雑音を除
去するネツィアンフィールドとは違って、これは、目に見えず、音もし
ない。
引っくり返った半球の側から側に走る壁だった。カーソンはそれを自
分で確認しなかった。回転ローラーが、それをやってくれていた。転が
りながら、バリアに沿って、少し場所を変えて、バリアがなくなる穴を
捜していた。
カーソンは、6歩前進した。左手を前にかざしながら、そして、バリ
アに触れた。滑らかで、曲がりやすそうで、ガラスよりゴムのシートに
近かった。温かいかんじだが、足元の砂ほどは熱くなかった。かなり接
近しても、完全に目に見えなかった。
彼は、石を落とし、両手をついて、押した。少しは曲がりそうだった。
しかし、全体重をかけて押しても、少し以上は曲げられなかった。鉄の
ように反発する、ゴムのシートのようだった。弾力は限られていて、力
は強い。
つま先立ちして、できるだけ高いところに手を伸ばしたが、そこにも
バリアはあった。
回転ローラーが、アリーナの一方の端まで行って、戻ってくるのが見
えた。カーソンはふたたび、むかつく感じに襲われた。やつが通り過ぎ
るまで、バリアから後ろに下がった。やつは、止まりもしなかった。
バリアは、地中にはないのだろうか?カーソンはヒザをついて、砂に
穴を掘った。砂はやわらかく、軽く、掘るのが簡単だった。2フィート
掘ったが、バリアはまだあった。
回転ローラーが、また戻ってきた。明らかに、やつは、どちらの側に
も穴を見つけられなかった。しかし、通り抜ける穴は、かならずあるに
違いない、とカーソンは考えた。そうでなければ、この決闘に意味はな
いからだ。
回転ローラーは目の前に戻ってきて、バリアをはさんで、たった6フ
ィートのところにいた。やつは、彼を観察しているようだった。人間の
生命と比べて、カーソンは、やつの生命組織の、外見上の特徴を見つけ
られなかった。目とか耳といったものは、まったく無く、口さえなかっ
た。ただ、溝の筋が、たぶん12本くらいあって、2本の触手が、2つ
の溝から伸びているのが見えた。それらを砂の中に降ろして、砂の状態
を調べているようだった。触手は、直径が1インチ、長さは、だいたい
1・5フィートだった。
触手は、溝の中にしまうことができて、使わないときはそこに収まっ
ていた。やつが転がっているときは、触手はしまわれていて、動力源に
はなっていないように見えた。カーソンが判断する限り、想像もできな
い方法で、中心にある重心の移動が行われているらしかった。
彼は、やつを見て、身震いした。やつは、エイリアンで、地球のいか
なるものとも、あるいは、太陽系の別の惑星で見つかった生命形態とも、
恐ろしく異なっていた。本能的に、彼は、やつの心も、やつの体と同じ
くらい、エイリアンであることが分かった。
4
もしも、やつがこの憎しみの波動を送って来てるのなら、やつは彼の
心も、彼の目的に叶うくらい十分に、読み取ることができるだろう。
ゆっくりと、カーソンは、唯一の武器である石を拾い上げた。それか
ら、あきらめたジェスチャーをしながら、石を下へ落とし、手のひらを
上にして、空の両手を上げた。
彼は、声を出してしゃべった。言葉は、目の前にいる生物には意味が
ないことは知っていたが、しゃべることで考えに集中できて、より完全
なメッセージにできた。
「オレたちの間には、平和はないのか?」彼は言った。静けさの中で、
彼の声は奇妙に響いた。「オレたちをここへ連れてきた存在は、戦った
あとでなにが起こるか話した。一方の絶滅、他方が弱くなって退化する
と。戦いがどうなるかは、存在が言うには、オレたちがここでなにをす
るかに依存するらしい。なぜ、オレたちは、永久に平和に暮らすことが
できない?あんたらは自分の銀河で、オレたちはここの銀河で?」
カーソンは、心を空白にして、返答を待った。
それは、来た。そして、カーソンを後ろにのけぞらした。赤のイメー
ジが彼に送ってきた、殺したいという意志の強さが、ホラーそのものと
なって、彼を数歩後退させた。永遠とも思える一瞬で、憎しみの衝撃に
対抗すべく努めた。心をクリアにするよう戦い、一度は侵入を許したエ
イリアンの思考を追い払った。彼は、吐き気を感じた。
彼の心は、ゆっくりとクリアになった。呼吸は荒くなり、自分はずっ
と弱いと感じた。しかし、彼は考えることができた。
彼は立ったまま、回転ローラーを調べた。それは、先程あっさりと勝
利を収めた心の対決では、なんの動きもなかった。今それは、一方向に
2・3フィート転がって、もっとも近い青のブッシュに近づいた。3つ
の触手が溝から伸びて、ブッシュを調べ始めた。
「オーケー」と、カーソン。「それなら、戦いあるのみ!」彼は、ニヤ
リとした。「あんたの答えをストレートに取れば、平和にはまったく興
味がないらしい」そして、彼は結局のところ若者で、劇的な展開には抵
抗できず、こう付け加えた。「死んじまいな!」
しかし彼の声は、このまったくの静けさの中では、彼にとってさえ、
マヌケのように響いた。死ねというのは、彼にとってもそうで、彼自身
の死、あるいは、回転ローラーと呼んでいた、赤の球体の死だけでなく、
1つあるいは他方の種族全体の死をも意味する。彼が失敗すれば、人類
という種の終わりを意味する。
それが、彼をとても慎み深くさせ、それについて考えるのをとても恐
ろしくさせた。信じる以上の知識があれば、この決闘を準備した存在は、
そいつの意図とパワーから言って、ほんとうのことをしゃべっているこ
とが分かった。人類の未来は、彼にかかっていた。それは、考えただけ
でぞっとした。彼は、今の状況に集中しなければならなかった。
バリアを通り抜ける、あるいは、バリアを通して殺す、なんらかの方
法があるはずだった。
心で?彼は、そうではまったくないことを望んだ。回転ローラーは、
明らかに、人類には未発達の、強いテレパシーパワーを持っていた。で
なければ、どうやって?
彼は、先程、回転ローラーの思考を、彼の心から操ることができた。
やつは、彼の思考を操ることができるのだろうか?もしも送信する能力
の方が強ければ、受信するメカニズムは、もっと傷つきやすいのではな
いか?
彼は、やつを見つめ、彼の思考をやつに集中させ、フォーカスを当て
た。
「死ね!」彼は考えた。「あんたは死につつある。あんたは死ぬ。あん
たは━━━」
彼は、そのバリエーションを試し、心の絵を変えてみた。汗が額から
吹き出した。彼は、震えるほど集中して努力したが、回転ローラーは、
ブッシュの調査を続けていた。カーソンが九九を暗唱しているかのよう
に、まったく影響を受けていなかった。
それで、その考えは捨てられた。
彼は、暑さと強く集中したことから、めまいを感じた。青の砂の上に
座って、全神経を使って、回転ローラーを観察した。観察によって、お
そらく、やつの力を判定し、弱点を見つけて、もしもつかみ合いになっ
たときに、知っておくべき大事な事柄を学ぶことができる。
やつは、小枝を折った。カーソンは、やつが作業している仕事の強さ
を見極めながら、注意深く観察した。あとで、と彼は考えた。こちら側
に同じようなブッシュを見つけて、同じ太さの小枝を折ってみて、彼自
身の腕や手と、やつの触手との、肉体的な強さの比較をしておこう。
小枝は折るのが難しかった。回転ローラーは、それぞれの触手で作業
していた。触手は、彼が見たところ、先がふたつの指に分かれていて、
それぞれツメのようなものが付いていた。ツメは、特に長いとか危険な
ようには見えなかった。少し伸びたとしても、彼の指のツメと比べても
大差なかった。
そう、全体として、やつは、肉体的に戦うのに、とても強いようには
見えなかった。もちろん、ブッシュがかなり強くできていたのでない限
り。カーソンは周りを見回した。手が届く範囲に、同じようなタイプの
ブッシュがあった。
小枝を折ってみた。それは、もろく、簡単に折れた。もちろん、回転
ローラーは、わざとそう演技していたのかもしれなかった。しかし、彼
はそうは考えなかった。ところで、やつの弱点はどこなんだ?チャンス
があったら、どうやったら、やつを殺そうとできる?彼は、やつの観察
に戻った。外側を覆っているものは、かなり手ごわそうだった。ある種
の、鋭い武器がいる。彼は、ふたたび、岩の破片を手に取った。それは、
だいたい、12インチの長さで、幅が狭く、一方の端が、かなりシャー
プだった。火打石のように削れば、それから使い勝手の良いナイフが作
れるだろう。
回転ローラーは、ブッシュの調査を続けていた。また、別のタイプの
一番近いところへ転がった。小さな青のトカゲが、カーソンがバリアの
こちら側で見たような足がたくさんあるものが、そのブッシュの下から
跳び出した。回転ローラーの触手が1本伸びて、それを捕らえ、つかみ
あげた。別の触手も伸びてきて、トカゲの足を引っ張り始めた。ブッシ
ュの小枝を引っ張ったのと同じ冷酷さで。その生き物は、必死に抵抗し、
キーキー鳴き声を上げた。それは、カーソンがここで聞いた、自分の声
以外では、最初の音だった。
カーソンは観察を続けた。彼の相手について学ぶなにかは、価値があ
るかもしれなかった。たとえ、不必要な冷酷さであっても。特に、と彼
は急に感情を伴って考えた、不必要な冷酷さ、やつはチャンスさえあれ
ば、なにかを殺すことが楽しみなのだろう。
足を半分もぎ取られて、トカゲは、キーキー鳴き声を上げるのをやめ、
回転ローラーの触手の中でぐったりした。
やつは、残りの足まで続けなかった。やつは、こちらを見下したよう
に、死んだトカゲをカーソンに向かって投げた。トカゲは空中を弧を描
いてから、彼の足元に落ちた。
トカゲは、バリアを通り抜けた!バリアは、もう無くなったのだ!カ
ーソンは、大急ぎで、ナイフを強くつかんで駆け出した。彼は、戦いを、
今、始めようとしていた!バリアは無くなったのだ━━━いや、無くな
ってはいなかった。それを強く思い知らされたのは、バリアに頭を打ち
つけ、反動で跳ね返されて、倒されたときだった。
彼は起き上がり、頭をクリアにするため振っていると、なにかが空中
をこちらに飛んできた。ふたたび砂の上に伏せて、起き上がろうとする
と、左足のふくらはぎに鋭い痛みが走った。痛みを無視して、うしろに
転がった。彼にぶつかったのは岩だと分かった。回転ローラーは、別の
を拾い上げ、2本の触手でつかんで、ふたたび投げる体勢で、後ろにス
イングバックしていた。
それは、彼に向かって空中を飛んできたが、かわすことができた。回
転ローラーは、見たところ、まっすぐ投げることはできたが、速く遠く
へ投げることはできなかった。最初の岩が彼に当たったのは、彼が倒れ
ていて、ぶつかるまで岩が飛んでくることに気づかなかったからだった。
やつが次に投げてきたものは、弱く、簡単に脇にステップしてかわし
た。カーソンは右手をうしろにスイングバックして、岩を投げようとし
た。もしもミサイルがあれば、とカーソンは得意げに考えた。バリアを
越えられる。ふたりで投球ゲームができる。
たった4ヤード先の、3フィートの球体を、はずすわけがないだろう。
実際、彼は、はずさなかった。岩は、ヒュー!と、回転ローラーが投げ
たミサイルの数倍のスピードで、まっすぐ飛んでいき、球体の真ん中に
命中した。しかし、当たったのは、岩の先端ではなく、平らなところだ
った。それでも、ボコッという音がして、明らかに傷を負わせた。回転
ローラーは別の岩をつかもうとしていたが、気を変えて、そこから遠く
へ後退した。カーソンがつぎの岩を見つけて投げるまでに、回転ローラ
ーは、バリアから40ヤードは後退し、強がっていた。
彼のつぎのミサイルは数フィートはずれ、3番目は、短かった。回転
ローラーは、深刻なダメージを受けるミサイルの射程外にいた。
カーソンはニヤリとした。このラウンドは、彼が取った。
5
彼は笑うのをやめて、体を曲げて、左足のふくらはぎを調べた。岩の
尖った先が、数インチカットしていた。かなり出血していたが、動脈ま
では深くないと思われた。なにもしなくても、自然に出血が止まってく
れれば良かった。そうでなければ、深刻なことになる。
けれど、傷の手当の前に、バリアの性質について、なにかひとつでも
発見したかった。
彼は、今度は両手を前に差し出して、ふたたび前進した。右手は前に、
左手には砂をつかみながら。砂はまっすぐ通り抜けたが、左手はダメだ
った。
有機物か無機物の違い?いや、違う。なぜなら、死んだトカゲは、通
り抜けた。トカゲは、生きていようが死んでいようが、確かに有機物だ
った。生きた植物は?彼は小枝を折って、バリアに突き刺した。小枝は、
なんの抵抗もなく、通り抜けたが、小枝を握った彼の手がバリアに達す
ると、そこで止まった。
彼は、通り抜けられなかった。回転ローラーも、ダメだった。しかし、
岩や砂や死んだトカゲは、通り抜けた。それなら、生きたトカゲは?
彼は、トカゲが見つかるまで、ブッシュを捜し、捕らえた。それをバ
リアに向かって投げると、トカゲは跳ね返って、青の砂の上を逃げてい
った。
そのことから、今、結論付けられる、答えが分かった。スクリーンは、
生きたものにはバリアとなった。死んでるか、無機物に対しては、通過
を許す。
そのあと、カーソンは傷の具合を調べた。出血は、少なくなっていた。
つまり、止血器の心配はいらないということだ。しかし、できれば水を
見つけて、傷口を洗いたかった。
水━━━そのことを考えて、ひどく喉が渇いていることに気づいた。
もしもこの試合が長引くなら、水を見つけなくてはならないだろう。
少しびっこを引きながら、アリーナの彼の部分のルートを調べるため、
歩き出した。左手をバリアに当てながら、カーブした側面の壁まで、右
に歩いて行った。壁は、目で見えて、近くでは淡いブルーグレイで、手
ざわりは、中央と全く同じだった。
試しに、砂をつかんで壁に投げつけてみた。砂は壁にぶつかると、通
り抜けて消えた。半球の壁も、同じフォースフィールドだったが、バリ
アのような透明ではなく、不透明だった。
彼は壁に沿って、バリアまで、ぐるりと歩いた。そして、バリアに沿
って、出発点に戻った。
水の気配はなかった。
心配になって、ジグザグなルートで、バリアと壁を戻ったり前進した
りしながら、中間の場所もすべてカバーして、歩き回った。
水はなかった。青の砂、青のブッシュ、そして、耐えられない暑さ。
それ以外は、なにもなかった。
6
これは、夢に違いない、と彼は自分に言った。のどの渇きから、わけ
が分からなくなっていた。どのくらい長く、ここにいたのだろう?もち
ろん、彼自身の時空のフレームでは、時間はまったく経ってない。存在
は、彼がここにいるあいだは、時間は止まっていると言った。しかし、
彼の身体のプロセスは、ここでも同じように、進行していた。彼の身体
の認識では、ここにどのくらい長くいるのだろう?たぶん、3・4時間
だろう。のどの渇きから言って、それほどの時間は経ってない。
だが、のどは渇いていた。のどはカラカラだった。おそらく、極端な
暑さが原因だった。暑く、だいたい華氏130度だった。乾燥して、暑
く、風ひとつなかった。
彼は、もっとひどく、びっこを引くようになった。こちらのエリアを
徹底して調べた、無駄な努力を続けた結果だった。彼は、向こうにいる
動きのない回転ローラーを、じっと見た。やつも、惨めな状態であって
欲しかった。存在は、条件は、同様になじみがなく、不快である点で、
両者にとって同等だと言った。たぶん、回転ローラーは、200度の暑
さがふつうの惑星から来たのだろう。彼が暑すぎるところが、やつには
寒すぎるのだろう。空気も、彼には薄すぎるところが、やつには濃すぎ
るのだろう。先ほどの調査をがんばったことで、彼はハーハー言ってい
た。大気は、火星と同じくらい薄いことに気づいた。
水はなかった。そのことで、彼のデッドラインが決まった。バリアを
抜ける方法を見つけるか、敵をこちら側から倒す方法を見つけない限り、
喉の渇きが、結局は、彼を殺すだろう。
それが、彼に絶望的な緊急事態の感覚を与えた。しかし、ゆっくり座
って休むことにした。考えるために。ここで、なにができるだろうか?
なにもできない。だが、非常に多くのものがある。たとえば、ブッシュ
にもいろいろな種類があって、確実なようには見えないが、可能性を調
べるために使えるだろう。それに、彼の足は、きれいにする水がなくて
も、なにか手当てをしなくてはならない。岩のかたちで弾丸を蓄えたり、
いいナイフになる岩を見つけたり。
足の傷は、かなり悪くなっていた。先にこれをやることにした。ブッ
シュの、あるものには、葉があった。つまり、葉に似たものが。それら
を、10数枚取ってきて、調べてから、止血に使ってみた。傷口から、
砂やゴミや固まった血を取り除き、きれいな葉をパッド代わりにして、
同じブッシュのつるでしばった。
つるは、予想外に、じょうぶで強かった。細くしなやかだったが、ま
ったく折ることができなかった。青の火打石の鋭い縁で、ブッシュから
つるを切り落とさなければならなかった。太いつるの、あるものは、1
フィート以上あり、未来に使うために、しっかり記憶した。太いつるを
束ねれば、かなりの負荷にも耐えるロープになることを。いつか、彼は
ロープとしてそれを使うだろう。
つぎに、彼はナイフを作った。青の火打石は、削ることができた。1
フィートの火打石の破片から、素朴だが殺傷力のある武器を、自分のた
めに作った。火打石ナイフをぶら下げられる、ロープベルトを腰に巻い
て、いつでも戦いに備え、両手は自由にできた。
彼は、ブッシュの調査に戻った。ほかに3つのタイプがあった。1つ
は、葉がなく、乾燥し、砂漠の回転草のように、もろかった。もう1つ
は、ソフトで、もろい木のようで、ほとんどがピンクだった。火を焚く
ときの、着火剤のほくちとして使えた。3つ目は、もっとも木らしかっ
た。やわらかい葉があって、さわるとしおれるが、茎は、短いがまっす
ぐで丈夫だった。
ひどい暑さで、耐え難かった。
彼は、びっこを引きながら、バリアのところまで行き、まだそこにあ
ることを、確かめようとした。それは、あった。彼は、立ったまま、回
転ローラーを見た。やつは、投石レンジの外で、バリアから安全な距離
を保っていた。やつは、そこからうしろへ動き回って、なにかしていた。
やつがなにをしているのか、彼には分からなかった。
それを一度やめて、近づいてきた。彼の方に、神経を集中させてるよ
うだった。カーソンは、また、吐き気と戦わなければならなかった。彼
は、やつに石を1つ投げた。回転ローラーは退却し、さっきまでやって
いたことに戻った。
少なくとも、彼は、やつに遠くにいるようにさせていた。そして、彼
は、自分に都合の良いことを、たくさん、必死に考えた。同時に、つぎ
の1・2時間は、投げるのにちょうど良いサイズの石を集めていた。バ
リアのこちら側に、石の山がいくつもできた。
喉の渇きは、今、焼けるようだった。水以外のことを考えることが、
難しくなった。しかし、彼は、ほかのことを考えなければならなかった。
バリアを通り抜けるには、上から?下から?赤の球体を捕らえて、殺す
には?この場所の暑さと喉の渇きが、彼を殺す前に。
バリアは、側面の壁まで続いていた。しかし、どのくらいの高さまで?
砂の下は、どのくらいの深さまで?
一瞬、カーソンの心は、あまりにぼんやりして、それらのことを考え
られなくなった。けだるく、熱い砂の上に座りながら、いつ座ったのか
も覚えてなかった、青のトカゲが、ブッシュの隠れ家から別のブッシュ
の隠れ家へ、這ってゆくのを見ていた。
2番目のブッシュの下から、そいつは彼を見た。
カーソンは、そいつにニヤリと笑い掛けようとした。火星の砂漠の入
植者たちの、古いストーリーを思い出していた。これは、地球の古いス
トーリーから作られたものだ。
「やがて、あまりの寂しさから、自分がトカゲにしゃべり掛けてること
に気づくさ。そのあと、トカゲが返事してくるようになるのも、まもな
くさ」
彼は、もちろん、集中していた、どうやって回転ローラーを殺すか、
しかし、彼は、代わりに、トカゲにニヤリと笑い掛けて、言った。「ハ
ロー、ゼア」
トカゲは、数歩、彼の方へ近づいてから、言った。「ハロー」
カーソンは、一瞬、唖然とした。それから、頭をのけぞらせて、笑い
ころげた。それで、喉の渇きがいえるわけではなかった。依然として、
喉は渇いていた。
なぜ、だめなんだ?存在は、この悪夢のような場所に、彼のパワーを
使って、ユーモアのセンスを持ち込もうとしたのだろう。しゃべるトカ
ゲ、オレ自身の言語で返事してくれる、トカゲとしゃべれるなら、ナイ
スタッチだ。
彼は、トカゲにニヤリと笑い掛けて、言った。「カモ〜ン」しかし、
トカゲは後ろ向きになって逃げ出し、ブッシュからブッシュへ、見えな
くなるまで、大急ぎで走り去った。
7
彼は、バリアを通り抜けなければならなかった。しかし、できなかっ
た。飛び越えることもできなかった。しかし、下から潜り抜けることも、
できないのか?そう考えると、掘ることで、水を見つけられるかもしれ
ないことに気づいた。
今、かなり痛みを感じながら、カーソンは、びっこを引いてバリアま
で行った。そして、一度に両手の砂をかきだしながら、堀り始めた。砂
が端に逃げて行ってしまうので、のろい作業だった。深く掘れば掘るほ
ど、穴の直径は大きくなった。何時間たったのか分からなかったが、4
フィート掘って、底に当たった。乾いた底で、水のサインはなかった。
バリアのフォースフィールドは、明らかに、底まで続いていた。
穴から這い出して、横になってハーハー言った。頭を上げて、向こう
で、回転ローラーがなにをしているか観察した。
ブッシュの木から、なにかを作っていた。つるを束ねて結び、風変わ
りな形をした、高さ4フィートでほぼ正方形の枠組みだった。もっとよ
く見るために、さっき掘って積み上げた砂の山に登って、立って眺めた。
後ろから2本の長いレバーが伸びていて、1本の先にカップのような
ものが付いていた。投石器のように見える、とカーソンは思った。
確かにそうだ、回転ローラーは、カップのところにちょうどよい岩を
乗せた。触手の1つが別のレバーを上げてから、しばらくして下げた。
それからマシンを少し動かして、ねらいを定め、石を置いたレバーを跳
ね上げ、前へ飛ばした。
石は、カーソンの頭上、数ヤードをカーブを描いて飛んで行った。か
なり上だったので、頭をすくめる必要はなかった。しかし、石が飛んだ
距離を見て、彼は軽く口笛を吹いた。同じ重さの石を、彼だったら、そ
の半分も飛ばせられなかった。彼の領域の後ろまで退避しても、回転ロ
ーラーがマシンをバリアまで押してくれば、その射程の外へ逃れられな
いだろう。
別の岩が、頭上をヒューッと飛んで行った。今度はそれほど離れてい
なかった。
バリアに沿って、端から端に動きながら、10数個の岩を投げつけた
ので、投石器は、彼を的に捕らえられなかった。それが、かしこいやり
方だとは、彼も思ってなかった。投げられるのは軽い岩ばかりで、重か
ったら、そんな遠くまで投げられなかった。回転ローラーは、その距離
で、簡単に、近くに飛んできた岩をかわせた。
それに、彼の腕は、かなり疲れてきた。体は、あらゆるところが痛か
った。アリーナの後方へ、よろよろしながら退却した。そこも安全では
なく、岩はそこまで飛んできた。休めるのは、わずかな間だけで、やつ
が、投石器をワインドアップさせるのに時間が掛かったときだけだった。
苦労しながら体を引きずって、彼は、バリアのところまで戻って来た。
なんども倒れ、足を動かすのもやっとだった。彼は、気づいていたが、
忍耐の限界に近づいていた。しかし、彼は動きをやめるわけにいかなか
った、投石器を破壊するまでは。もしも眠ってしまったら、2度と目覚
めることはないだろう。
投石器から飛んできた石のひとつが、アイデアに火をつけた。その石
は、バリアの近くで、岩の弾丸を蓄えた山のひとつに当たって、火花を
散らした。
火花!火だ!原始人は、火花を散らすことで火をおこした。着火剤の
ほくちになるような、乾燥した、もろいブッシュを使えば━━━。
そのタイプのブッシュが、近くに生えていた。それを引き抜き、石の
山の上に置いて、1つの石を別の石に打ち付けて、しんぼう強く、ブッ
シュのもろい木に火花が移るまで、続けた。炎が上がるのが、あまりに
早かったので、彼の眉毛は、チリチリ言って、数秒で灰になった。
彼の思いつきは、彼が築いた砂の山から、小さな炎を石につけて投げ
るというものだった。最初は、着火剤のほくちになるブッシュ。ほかの
ブッシュは、ゆっくりと、安定して燃え続ける。
丈夫なつるは、すぐには燃えなかった。投げるのが簡単な、ファイヤ
爆弾にした。薪の束を小さな石に縛って、それをおもりにして、つるを
回転させて、勢いをつけて投げられるようにした。
火をつける前に、それを6セット準備し、最初のものを投げた。それ
は、遠く飛んで行き、回転ローラーは、投石器を引っ張って、すぐに退
避を始めた。しかし、カーソンは、いくつも用意してあったので、つぎ
つぎに速射砲のように放った。4番目に投げたものが、投石器のフレー
ムに当たり、魔法を起こした。回転ローラーは、必死に砂を掛けて、火
を消そうとしたが、やつの触手のツメでは、一度にスプーン一杯くらい
しか掛けられず、やつの努力は無駄に終わった。投石器は、燃え落ちた。
回転ローラーは、火からは安全な場所に逃げ、神経をカーソンに集中
させてるように見えた。また、彼は、あの憎しみの波動を感じ、吐き気
がした。しかし、前より弱かった。回転ローラーが弱っているのか、カ
ーソンが心の攻撃に対して、防御の仕方を学んだのか、どちらかだった。
彼は、やつに向かって、鼻に親指を当てて、アカンベェーをして、投
石から安全な場所へ追い払った。回転ローラーは、アリーナの奥に行っ
て、ふたたびブッシュを束ね始めた。やつは、たぶん、また新しい投石
器を作り始めたのだ。
8
カーソンが確かめると、バリアは依然として、機能していた。気づく
と、彼はバリア近くの砂に座り込んで、急に弱って、立ち上がれなくな
った。
彼の足は、ずっと震え続け、喉の渇きは深刻だった。体じゅうの疲れ
に加えて、それらことが彼を苦しめた。
地獄は、きっとこんなだろう、と彼は考えた。祖先の人々が信じてい
た地獄。彼は目覚めていようと戦ったが、目覚めていることがムダに思
えた。というのは、バリアが攻略できず、回転ローラーが遠くにいては、
することがなかった。彼は、金属やプラスチック以前の時代の武器につ
いて書かれた、前に読んだ、考古学の本を思い出そうとした。石のミサ
イルは、最初だった、と彼は考えた。だが、すでに試した。
弓矢は?だめだ。彼は、一度アーチェリーをやったことがあったが、
現代スポーツのデュラスチール製の弓矢を使用しても、うまく当てられ
ないほど不向きだった。彼がここで作った手製の弓矢だったら、投げる
より正確に当てられるか疑わしかった。
やりは?やりなら、作ることはできる。遠くでは効果ないが、接近戦
になったら、手頃な武器として、使えるかもしれない。作り始めてしま
えば、迷っている気持ちを静めるのにはいい。
彼は、まだ、石の山のひとつの横にいた。石の山から、やりの先に使
えそうな、だいたい先が尖った石をより分けた。小さな石の、先端を尖
らし始めた。先端の両側に鋭い返しを付けて、一度刺したら、もりのよ
うに2度と引き抜けないようにした。もりは、たぶん、やりよりも、こ
のややっこしい試合には相応しかった。回転ローラーにもりを突き刺し
たら、ロープを付けておけば、バリア近くまで引っ張ってきて、ナイフ
の石の刃でバリアを越えて攻撃できる、両手が通り抜けられないとして
も。
もりの棒は、作るのが難しかったが、ブッシュの4つの太い茎を裂い
たり束ねたりして、細いが強いつるで包むことで、4フィートの丈夫な
もりの棒を作った。棒の先端に、刻み目を入れた石を結び付けた。単純
だが、強いもりができた。
つるから、20フィートのロープを作った。これは軽く、丈夫そうに
見えないが、じゅうぶん彼の体重を支えられるほど強かった。ロープの
端に、もりの棒を結び付け、他方の端を、右手首に結び付けた。これで、
もりを、バリアの向こうに投げて、失敗したとしても、少なくとも、ロ
ープを引いて、取り戻すことはできる。
立ち上がって、回転ローラーがなにをしてるか見ようとしたが、足が
思うように動かなかった。3回目に、やっとヒザをつけたが、ふたたび、
倒れてしまった。
「眠らなきゃならない」と、彼は考えた。「今、戦いが始まったら、オ
レはどうしようもないな。やつは、ここへ来て、オレを殺すことができ
る。それは分かってるが、眠って、元気を取り戻さなきゃならない」
ゆっくり、痛々しく、彼はバリアから這って戻ろうとした。
◇
彼の近くの砂に、なにかがドスンと落ちてきて、彼を、わけの分から
ない、ひどい夢から、もっとわけの分からない、もっとひどい現実へ、
目覚めさせた。彼が目を開けると、ふたたび、青の砂に青の輝きだった。
どのくらい眠っていたのだろう。1分?1日?
別の石が、もっと近くに落ちて、砂を巻き上げた。腕で体を支えて起
き上がると、回転ローラーが、バリアまで、あと20ヤードに迫ってい
た。
彼が起き上がると、やつは、急いで転がって離れて行った。できるだ
け遠く離れるまで、止まらなかった。
彼が眠ったのは、ほんの一瞬だったようだ。一方、彼は、回転ローラ
ーの投石の射程内にいた。彼が倒れたまま動きがないのを見て、やつは、
あえて、バリアまで来たのだ。幸運にも、彼がかなり弱っていることに
は、気づかれてなかった。そうでなければ、やつはそこにとどまって、
投石を続けただろう。
彼は、また、這って動き出し、できるだけ遠くまで行こうとした。ア
リーナの外壁の不透明な壁まで、あと1ヤードだった。
そのとき、ふたたび、目の前のものは、どこかへ滑って行った。
◇
彼が目覚めたとき、なにも変わってなかった。しかし、今度は、彼は
長い間、眠っていた。最初に気づいたことは、彼の口の中だった。乾い
て固まっていた。舌は膨張していた。
だんだんと完全に目覚めて来ると、なにかが良くないことに気づいた。
疲れは、あまり感じなかった。喉が渇くステージは過ぎていた。しかし、
苦しみ、もだえるような苦しみがあった。動こうとするまで分からなか
ったが、それは彼の足から来ていた。
頭を上げて、それを見てみた。ヒザの下がふくらんでいた。ふくらみ
は、ももの半分まで上がって来ていた。葉の保護パッドの回りに結んだ、
植物のつるは、肉に深く食い込んでいた。
食い込んだ結び目の下には、ナイフを入れられなかった。ラッキーな
ことに、最後の結び目は、向こうづねの上で、つるの食い込みが、他よ
り深くなかったので、苦労の末、結び目を解くことができた。
葉の保護パッドの下は、ちょっと見ただけで、最悪だった。感染症や
敗血症。薬もなく、水さえなく、彼にできることは、なにもなかった。
毒が全身に回れば、死ぬだけだ。
ヒューマニティを失ってしまったら、また、それがなければ、希望も
ないことが分かっていた。彼がここで死んだら、ここの外の、彼の知る
宇宙にいる、すべての友人、すべての人々も、いっしょに死ぬのだ。地
球や植民地の惑星は、赤の転がるエイリアン、アウトサイダーの家にな
るのだ。
その考えが、彼に勇気を与え、ふたたび、バリアに向かって、這って
移動を開始した。ほとんど目が見えず、腕と手で体を引っ張って、這っ
て行った。
彼が残っている力の限りを尽くして、もりを投げ、一撃で致命傷を負
わすのは、百万に1つのチャンスだった。回転ローラーがバリアまで来
てくれて、バリアが無くなってさえくれれば。
彼は、もう何年も、そこにいるように思えた。バリアは、無くなって
なかった。最初に感じた時とまったく同じに、通れなかった。
9
回転ローラーは、バリアにはいなかった。彼は、ひじをついて、体を
押し上げて、アリーナの奥にいる、やつを見つけた。木のフレームで作
業していた、それは、彼が破壊した投石器の完全なコピーで、半分、完
成していた。
やつは、動きがゆっくりだった。疑いもなく、やつも弱っているのだ。
カーソンは思った。2台目の投石器は必要ないのではないか?それが
完成する前に、と彼は考えた。彼は死ぬだろう。
◇
彼の心は、ふたたび、一瞬、滑ったに違いない。というのは、彼は、
自分の手首を、むだな激しさで、バリアに打ち付けているのに気づいて、
自分を止めたからだ。目を閉じて、自分を落ち着かせた。
「ハロー」と、声。
それは、小さな、かすかな声だった。彼は目を開けて、頭を向けた。
トカゲだった。
「あっちへ行け!」と、カーソンは言いたかった。「あっちへ行け!あ
んたは現実じゃないんだ!あるいは、そこにいるとしても、本当はしゃ
べってなんかいない。オレはまた、幻を見ているんだ」
しかし、彼はしゃべれなかった。のどと舌は、乾きすぎて、しゃべっ
ても抜けてゆくだけだった。彼は、また、目を閉じた。
「傷つけて!」と、声。「殺して!傷つけて!━━━殺して!来て!」
彼は、また、目を開けた。青の10本足のトカゲは、まだ、そこにい
た。トカゲは、バリアに沿って少し行き、戻って来た。また、少し離れ、
戻って来た。
「傷つけて!」と、トカゲ。「殺して!来て!」
また、少し離れ、戻って来た。明らかに、トカゲは、カーソンに、バ
リアに沿って、ついて来て欲しがっていた。
彼は、また、目を閉じた。声は続いていた。同じ3つの意味の無い言
葉。彼が目を開けるたびに、トカゲは、少し離れ、戻って来た。
「傷つけて!殺して!来て!」
カーソンは、うめき声を上げた。彼がついて行かない限り、静かにな
らなかったので、這って、トカゲについて行った。別の音、高音のうめ
き声が、聞こえてきた。砂の上に、なにかが横たわって、身もだえして、
キーキー鳴いていた。小さいなにか、青で、トカゲのように見えた。
それは、回転ローラーが、ずいぶん昔に、足を引きちぎったトカゲだ
った。トカゲは、死んでなかった。息を吹き返し、もだえ苦しんで、キ
ーキー鳴いていた。
「傷つけて!」と、もう1匹のトカゲ。「傷つけて!殺して!殺して!」
カーソンは理解した。彼は、火打石ナイフをベルトから抜いて、もだ
え苦しむ生き物を殺した。生きてるトカゲは、走って逃げた。
10
カーソンは、バリアに戻った。手と頭でバリアに寄りかかり、遠くで、
回転ローラーが新しい投石器で作業しているのを観察した。
「あそこまで行ける」と、彼は考えた。「もしもオレが通り抜けられた
ら。もしもオレが通り抜けられたら、勝てるかもしれない。やつもかな
り弱っているように見える。オレは━━━」
それから、希望のない反動がやって来た。苦しみが彼の意志をくじき、
殺して欲しいと思った。今、殺したばかりの、トカゲがうらやましかっ
た。トカゲは生きる必要がなくなって、苦しみもなくなった。
彼がバリアを手の平で押しているときに、自分の腕が細く、やせこけ
ていることに気づいた。彼は実際、長い間ここにいるに違いない。なん
日も、これほど細くなるまで。
しばらくの間、またヒステリーになりかけた。それから、深く冷静に
なって、考え始めた。
殺されたトカゲは、バリアを通り抜けた。しかし、まだ、生きていた。
トカゲは、回転ローラーの側から来た。回転ローラーは、トカゲの足を
引きちぎり、見下したように、彼に向かって投げた。トカゲは、バリア
を通り抜けた。
トカゲは死んでなかった。ただ、意識を失っていただけだ。生きたト
カゲは、バリアを通り抜けられなかった。しかし意識を失ったトカゲは、
通り抜けられた。バリアは、生きた生物に対してのバリアでなく、意識
のある生物に対してのバリアだった。それは、心的防御、心的ハザード
だった。
そう考えると、カーソンは、最後の絶望的なギャンブルに打って出る
ために、バリアに沿って、這い始めた。希望は、あまりに絶望的だった
ので、死に掛けた人間でなければ、あえてしないようなものだった。
バリアに沿って、砂の山の上に移動した、高さは、だいたい4フィー
トだった。その山は、バリアの下を掘って抜けられないか、あるいは、
水が見つからないかと、もうなん日も前に、彼が掘ってかき出した砂の
山だった。その山は、バリアにちょうど掛かって広がっていて、こちら
側の半分は急な斜面で、もう半分は向こう側のすそまで広がっていた。
近くの岩の山から、岩を1つ取り、砂の山の頂上まで這って上がり、
バリアのところに横たわった。これで、もしもバリアが無くなったら、
短い斜面を、彼は、敵の領域へと転がってゆくだろう。
最終チェックをした。ナイフは、ベルトにちゃんと下がっていた。も
りは左腕で抱きかかえ、20フィートのロープがもりと右手首に結ばれ
ていた。それから、右手で岩を高く持ち上げて、自分の頭を殴るのだ。
この一撃には、幸運が必要で、気絶するくらい強くなくてはならないし、
強すぎて長く目覚めなくてもダメだった。
彼は、回転ローラーが、こちらを見ているという予感がした。そして、
バリアを通り抜けて転がり落ちるのを見るだろう。そして、調べるため
に近づいて来る。やつは、彼が死んでると信じるだろう。彼は、そう望
んだ。やつもバリアの性質について、彼が考えたと同じ結論を導いてい
ると、考えられた。しかし、やつは、かなり注意しながら近づいて来る
だろう。チャンスは一瞬だ━━━。
彼は、自分を岩で殴った。
◇
痛みが、彼の意識を回復させた。突然、鋭い痛みが、お尻に来た。頭
や足の痛みと、まったく別だった。彼は、自分を殴る前に考えていたよ
うに、この痛みを予想していた。むしろ望んでいた。そして、目覚めて
も、急に動いたりしないように、鋼のように、心を張りつめていた。
薄目をあけて、自分の推測が正しいことを確かめた。回転ローラーは、
近づいて来た。20フィート先にいた。彼を目覚めさせた痛みは、やつ
が、彼の生死を確かめるために投げた石だった。彼は、まだ、倒れてい
た。やつは、さらに近づいた。15フィート、また、止まった。カーソ
ンは、ほとんど息をしなかった。
ほとんどあり得ることだが、彼は、心も空白にした。やつのテレパシ
ー能力で、彼の意識が感づかれないように。彼の心をそんなふうに空白
にしたことで、やつの考えが入って来たときの衝撃が、分散された。
彼は、そのエイリアン性に、全くのホラーを感じた。やつらの考え方
の違いに。やつらは、表現の仕方が、彼の感じ方とは全く違う、理解で
きない、言い表せない方法で行う。地球の言語には無い言葉で、地球の
頭脳では、それらに合ったイメージが見つからない。クモの心でさえ、
と彼は考えた、あるいは、カマキリや、火星の砂漠に住むヘビの心でさ
え、知性があって、人間の心とテレパシーでつながり得る。やつらのエ
イリアン性に比べたら、ずっと家庭的で親しみ深いものだろう。
彼は、今、存在は、正しかったことを理解した。人類か回転ローラー
か、宇宙は、両者が共存できる場所ではなかった。
もっと近く。カーソンは、やつが、わずか1フィートに近づくまで、
待った。やつのツメの触手が、こちらに伸びて来るまで━━━。
今、まさに、戦いのときだ!彼は、起き上がり、もりを構えて、残っ
ている力の限りを尽くして、突き刺した。回転ローラーは、もりを深く
刺されて、転がった。カーソンは、やつについて走ろうとしたが、でき
ずに倒れた。しかし、這い続けた。
ロープは、終端まで来た。彼は、ロープがある右手首を引いて、体を
前に押し出そうとした。やつは、彼を数フィート引きずって、止まった。
カーソンは、さらに、ロープでつながった、やつの方へ体を押し出そう
としていた。やつは、そこで、触手を虚しく振って、もりを引き抜こう
としていた。やつは、身もだえして、震えているように見えた。それか
ら、逃げられないと分かると、彼に向かって、ツメのある触手を突き出
して、転がって来た。
火打石ナイフを手に、彼はやつに対峙した。彼は突き刺し、なんども
なんども、突き刺し、やつは恐ろしいツメで、彼の全身から、肌を引き
裂き、肉を、筋肉を引き裂いた。
彼は突き刺し、めった裂きにした。そして、やっと、やつは静かにな
った。
エピローグ
ベルの音がした。それが、彼に、目覚めた後しばらく、彼がどこにい
て、なにをしているのかを告げていた。彼は、小型偵察艇の操縦席で、
シートベルトをしていた。スクリーンには、なにもない宇宙だけが映っ
ていた。アウトサイダー船や、ありえない惑星は、映ってなかった。
ベルは、通信ラインのシグナルで、誰かが、応答レバーを押するよう
促していた。条件反射で、彼は前かがみになって、レバーを押した。
偵察隊のマザーシップにいる、マジェラン隊の大佐、ブランダーの顔
がスクリーンに現われた。彼の顔面は蒼白で、興奮に黒い瞳が輝いてい
た。
「マジェランからカーソン」と、彼。「カモ〜ン!戦いは終わった!オ
レたちは勝った!」
スクリーンは消えた。ブランダーは、彼の部隊のほかの小型偵察艇の
応答に追われた。
ゆっくりと、カーソンは制御スクリーンに戻った。ゆっくりと、信じ
られないが、彼は、シートのベルトをはずした。そして、ウォーターサ
ーバーの水を飲みに行った。理由は分からないが、やたら、喉が渇いて
いた。6杯飲んだ。
彼は、そこで壁に寄りかかったまま、考えようとした。
なにが起こった?彼は、健康で、活発で、傷は無かった。喉の渇きは、
肉体的というより、精神的なものだった。彼の喉は渇いてなかった。
彼は、ズボンをめくって、ふくらはぎを調べた。そこには、白い長い
傷跡があった。しかし、完全に傷は直っていた。以前は、そこに傷跡は
なかった。シャツの前をあけて、胸や腹を調べると、細かい、ほとんど
見えないような、しかし完全に治った傷跡が交錯していた。
それは、ほんとうにあったのだ!
偵察艇は、自動運転で、すでに、マザーシップのハッチに入っていた。
かぎざおが偵察艇をつかんで、個々のロックに運び、ブザーが鳴って、
ロックに空気が満たされたことを告げた。カーソンはハッチを開いて、
外へ出て、ロックの2重ドアを抜けた。
彼は、ブランダーのオフィスへ着いて、中へ入り、敬礼した。
ブランダーは、まだ、ぼう然としていた。「ハイ、カーソン!」と、
彼。「見逃したのか!すごいショーだったのに!」
「なにが、あったと?大佐?」
「分からん、正確には!オレたちは、一斉射撃をした。そのあと、敵の
艦隊全体が、あっという間に爆破された。艦船から艦船へ、閃光が走り、
オレたちがねらってなかったものまで、射程外のものまで、爆破された。
敵の艦隊全体が、オレたちの目の前で、粉々になった。オレたちは、た
だの1隻も、引っかき傷さえ負わずに!
これがオレたちの手柄だと、主張するつもりはない。おそらく、敵が
使用していた金属に、不安定な分子が含まれていたに違いない。オレた
ちの一斉射撃が、引き金となったのだ。あんたは、このエキサイティン
グショーを見逃したのか?」
カーソンは、ニヤリとして、病んだ亡霊を追い払おうとした。まるで
今が、衝撃的な経験をする以前の日々であるかのように。しかし、大佐
は、その表情を、見てなかった。
「イエス、サー!」彼は言った。彼の常識が強く教えてくれたのは、も
しもそれ以上のことをしゃべれば、彼は宇宙一の大うそつきのレッテル
を、貼られてしまうに違いないということだった。「とても残念━━━
エキサイティングなショーを見逃してしまったとは!」
(終わり)