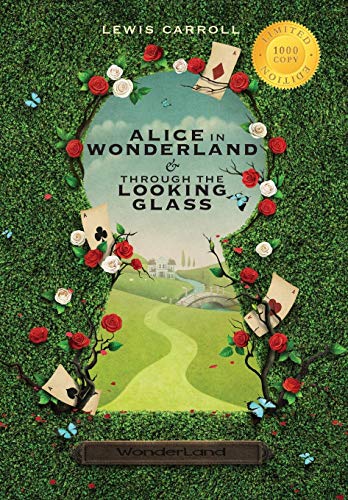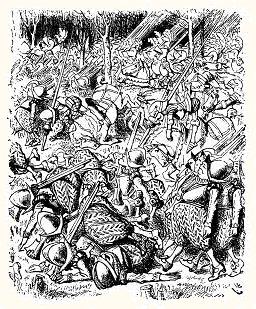アリスのルッグラン
原作:ルイスキャロル
アランフィールド
プロローグ
1つ確かなことは、いたずらは、白の子ネコでなく、黒の子ネコによ
るものだということだった。というのは、白の子ネコは、15分のあい
だ、ディナに(じゅうぶん過ぎるくらいに)顔をきれいにしてもらって
いたからだ。白の子ネコに、いたずらができる、自由な前足はなかった。
ディナが、子ネコの顔をきれいにするやり方は、こうだった。左の前
足で子ネコの耳を押さえ、右の前足で子ネコの顔全体をこする。子ネコ
の鼻から始めると、今の場合がそうだったが、うまくゆかずに、手こず
ってしまった。白の子ネコは、おとなしく座って、のどをゴロゴロ鳴ら
そうとしていたが、状況が悪いことを感じていた。
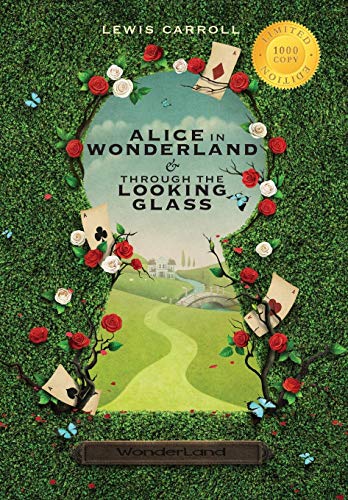
一方、黒の子ネコは、午後の早い時間に、きれいにしてもらっていた
ので、アリスとじゃれて遊んでいた。
アリスは、室のすみの大きなにアームチェアに足を上げて座って、自
分に話しかけたり、半分眠ったりしながら、毛玉のボールを投げたり、
ころがしたりして、黒の子ネコを遊ばせていた。ヒースのジュータンは、
そのうち、引っかかれたりもつれたりして、傷だらけになった。
「あら、なんて悪い子なの!」と、アリス。子ネコをつかまえて、悪い
ことだと言い聞かせるようにキスをした。「ディナが悪いことはダメだ
って教えたはずよ!ディナの言うとおりにしなさい!」
アリスは、ディナの方をチラッと見てから、また、アームチェアに座
って、子ネコをひざに乗せて、毛玉のボール遊びを再開した。ゆっくり
した動きになったのは、アリスがずっとしゃべりっぱなしだったからだ。
相手は、子ネコだったり、自分だったりした。子ネコは、アリスのひざ
の上でおとなしくしていた。たまに、おもしろがってるふりをして、毛
玉のボールに触れた。
◇
「あしたは、なんの日だか分かる、キティ?」と、アリス。「わたしと
いっしょに、窓枠に上がる日だと思ってない?ディナが、あなたを礼儀
正しく育てたから、それはないわ。男の子たちが、キャンプファイヤの
まき木を集めているのを見たわ。たくさんのまき木よ!キティ、とても
寒くて、雪になるかもしれない!心配しないで、キティ!わたしたちも
行くわ!キャンプファイヤを見ましょう!あしたよ!」
アリスは、子ネコの首のまわりに毛玉のボールをまわしてみたらどう
なるかやろうとして、2・3周したところで、子ネコは、イスをよじ上
ったので、毛玉のボールは床に落ちてころがった。数ヤード行って、毛
玉のボールは止まった。
「わたしは、完全に怒ったわ、キティ!」と、アリス。毛玉のボールを
取って戻ってくると続けた。「キティのいたずらを見てると、窓をあけ
て外の雪の中へほうり出したくなるわ!キティはちっとも悪いと思って
ないようだから、そうする価値はあるわ。どう言いわけするつもり?と
めないでちょうだい!」
アリスは、右手の人差し指を上げた。「キティのいたずらをあげるわ!
ひとつ目。ディナが朝、キティの顔をなめてきれいにしてあげてるとき
に、2回ニャーニャーと鳴いた。そうでしょう、キティ?わたしは、聞
いたわ!否定できる?」
(アリスは、キティが抗議するしぐさをした)「ディナの前足が目に入
ったの?それは、目をあけていたキティが悪いのよ!目をちゃんとつぶ
ってれば、大丈夫なんだから。言いわけはなし!聞いて!ふたつ目。子
ネコのスノードロップに、ミルクをあげようとしたら、キティは、尻尾
でミルク皿を押しのけたわ。キティは、喉がかわいていたの?スノード
ロップも喉がかわいていたとは思わなかったの?3つ目。わたしが見て
ないときは、毛玉のボールにじゃれようとはしなかった!」
アリスは、キティの顔を見た。「これで、3つよ。どれをとっても、
罰に値するわ。水曜以来、罰はためてあるのよ!この先もずっとためて
いられるかしら?」
アリスは、続けた。キティにというより、むしろ自分に。「1年たっ
たら、どうなってるかしら?牢獄行きかも?それがイヤなら、1つにつ
き、夕食なしにするなら、50日は夕食なしよ!厳しすぎるとは思わな
い。夕食なしでいるべきよ!」
◇
アリスは、話題を変えた。「窓ガラスにあたる雪の音を聞いたことあ
る、キティ?ソフトですばらしい音よ!だれかが外から窓に、いたると
ころキスしているかんじよ!雪は、木々や野原が大好きで、それで、そ
んなにやさしくキスしているんだと思う。居心地よく、白の掛け布団で
おおい、そして、たぶん、こう言ってるの。『夏がふたたび来るまで、
おやすみ、ダーリン!』そして、夏が来て、木々や野原が目覚めると、
みんな、緑のドレスを着ているの。風の吹くときはいつでも、みんなで
ダンスをするのよ!なんて、すばらしいんでしょう!」と、アリス。毛
玉のボールを弾ませて、手でピシャリとつかんで、叫んだ。「それが、
きっと真実よ。秋には、葉も紅葉して、木々は眠そうですもの!」
アリスは、間をおいた。「キティ、チェスはする?笑わないで!まじ
めに聞いているのよ!今からチェスをすれば、キティがチェスのルール
を分かってるのかどうか、分かるわ。わたしが『チェック!』と言った
ら、のどを鳴らしてちょうだい!だって、わたしが勝ちですもの!もし
も、憎たらしいあなたのナイトが、わたしの陣地に攻め込んでこなけれ
ばね!キティ、お願いだから、ふりをして━━━」
ここで、アリスのお気に入りの『ふりをして』の中味の半分でもお伝
えできれば、と思う。2日前にアリスは、姉のマギーと話していた。
『マギーが女王や王だとしたら』と、アリス。
『それは、おかしいわ!』と、マギー。マギーは、あいまいが嫌いだっ
た。『わたしは、ひとりだから、どちらかひとつにしかなれないわ!』
『マギーが』と、アリス。言いなおした。『女王や王のどちらかだとし
て、わたしが、それ以外のすべてだとしたら』
そのあと、アリスは、マギーに向かってこう叫んだので、自分でも驚
いた。
『わたしが腹ペコのハイエナだとしたら、マギーは骨なのよ!』
しかし、このことは、アリスがキティに話していたこととは、まった
く同じというわけではなかったもしれない。
「キティは、赤の女王だとしましょう!キティは、座って腕を組んでい
たら、赤の女王そっくりよ!やってみましょう!」
アリスは、テーブルの上の赤の女王をキティの前に持ってきた。
「う〜ん、キティは、腕を組めないから、赤の女王に見えないわ!キテ
ィは、すねてるように見えるわ!鏡の家に行ってみましょうか?どうな
るかしら?」
暖炉棚の上の鏡の前に、キティをおいた。
「キティは、おとなしくしてるだけで、なにも言わないから、わたしの
考えを述べましょうか?鏡の家は、ここと左右が逆というだけではない
のよ!イスの上に立てば、すべて見えるわ!暖炉のうしろが少し見えな
いわ。そうね、そこも見たいと願いましょう!冬に火をたいてるのか、
知りたいわ。キティには、ここの暖炉の火が煙を出す限りは、分からな
いわ。ここの煙が、向こうの室にも流れてしまうから。でも、これは、
ただの『ふりをして』みるだけだから、向こうにも火はあることにしま
しょう!そうしたら、向こうの本は、こちらと全く同じだけど、文字の
並びが逆なのよ。本を鏡に映したことがあるから、知ってるわ!」
アリスは、思いついた。「キティは、鏡の家に住んでみたいと思わな
い?向こうでも、キティは、ミルクをもらえるのかしら?向こうのミル
クは、まずいかもしれない。そう、それが通行キップよ!キティは、今、
居間のドアをいっぱいにあけたまま、鏡の家への通行キップまで来たの
よ!キティの知る限り、こことは全く違う世界への通行キップよ!鏡の
家へ行けたら、どんなにすばらしいでしょう!行く方法が分かった気が
する。その世界へ行ける方法がある、としましょう!鏡は、みんな、ガ
ーゼのようにやわらかくて、自由に通り抜けられるとしましょう!ほら、
霧のようなものが立ち込めてきた!今なら、行けるわ!」
アリスは、暖炉棚の上にあがったが、考えがあるわけではなかった。
そのとき、鏡が、明るいシルバーの霧におおわれて、溶け出した。
1
つぎの瞬間、アリスは、鏡を抜けた。鏡の世界の居間で、かるがると
暖炉棚から飛び降りた。
「火はあるのかしら?」と、アリス。暖炉を見た。「前の世界より、赤
々と燃えてるわ!これなら、前よりもっと暖かいわ!ここには、火に近
づくなとしかる大人もいない!もしも、ここへやってきたとしても、大
人たちに見つからないようにできる!なんて、楽しいんでしょう!」
アリスは、居間を見まわして、前とまったく同じものや、違うものを
見つけようとした。しかし、それ以外は、すべて全く違っていた。たと
えば、暖炉のとなりの壁にかかった花の絵は、絵ではなく、生きていた。
暖炉棚の時計は、(鏡からは、いつもうしろしか見えないものだが)、
小人の老人の顔だった。その顔が、アリスの方を見た。
「この室は、前の世界より片付けられてないわ!」と、アリス。自分に。
ヒースのジュータンは、燃え殻が散らかっていて、チェスの駒もいくつ
かあった。
「え?」と、アリス。驚いた声を出して、両手をヒザに置いた。チェス
の駒は、ふたりづつペアになって、歩きまわっていた。
「赤の王に、赤の女王もいるわ!」と、アリス。(気づかれないように、
ささやくような声だった)「シャベルのはしに座っているのは、白の王
と白の女王だわ!」そこには、白のキャッスルもふたり、手をつないで
歩いていた。「わたしには気づいてないわ!」アリスは、顔を近づけた。
「わたしは、見えないのよ!透明人間になったかんじだわ!」
アリスの後ろのテーブルで、ゴソゴソという音がした。
「なにかしら?」と、アリス。振り向くと、白のポーンのひとりがグル
グルまわって、キックを始めた。「なにが始まったっていうの?」
「わたしの子どもの声だわ!」と、白の女王が叫んだ。白の女王は、白
の王まで急いで走ってきたので、燃え殻の中へ白の王を突き飛ばした。
「かわいいリリー!子どもたち!」白の女王は、暖炉の囲いを急いでの
ぼり始めた。
「子どもたち!」と、白の王。秋になってかぜを引いた鼻をこすった。
白の王は、頭から足まで灰におおわれていたので、白の女王は、突き飛
ばしても気にもとめなかった。
「どうしましょう、リリーが、発作で叫び声をあげそうだわ!」と、ア
リス。白の女王をあわててつかむと、テーブルのリリーの近くに置いた。
白の女王は、つかまれて、座らされた。息つく間もない、瞬間移動だ
った。そして、1・2分後には、なにも言わずに、リリーを抱きしめて
いた。しばらくすると、白の女王は、灰まみれで、むっとしている白の
王に言った。
「火山に気をつけて!」
「火山?」と、白の王。心配そうに、暖炉の火を見上げた。「あの中に
火山が?」
「わたしを吹き飛ばしたのよ!」と、白の女王。まだ少し息切れしてい
た。「ふつうに歩いて来てちょうだい!吹き飛ばされないように!」
アリスは、白の王が、ゆっくり棒から棒へ渡ってくるのを見ていた。
「そのペースだと、テーブルまで来るのに何時間もかかるわ!わたしの
助けが必要かしら?」
白の王は、答えなかった。白の王には、アリスの声は届かず、姿も見
えなかった。
アリスは、そっと白の王をつまみ上げ、白の女王のときよりゆっくり
と移動させた。白の王を息切れさせたくなかったからだ。しかし、テー
ブルに置く前に、灰だらけだった服から少し灰を落とした。
「こんなふうに、人から無視されたことはなかったわ!」と、アリス。
白の王は、見えない手に導かれ、灰を落としてもらっても、一度もアリ
スの顔を見なかった。白の王は、あまりに驚いたので、叫ぶこともでき
なかった。白の王の目は、ますます大きくなり、口は、ますます丸くな
った。アリスは、笑いをこらえきれず、白の王を床に落としそうになっ
た。
「お願いだから、そんな顔をしないでちょうだい!」と、アリス。白の
王には聞こえないことも忘れて、大声で。「笑わせるから、落としそう
になったわ!口をそんなに大きくあけないで!灰がみんな入ってしまう
わ!さぁ、前よりきれいになったわ!」白の王の髪もきれいにして、テ
ーブルの白の女王の前に置いた。
白の王は、そのまま背中から倒れて、静かになった。アリスは、自分
のせいだとは思わなかったが、白の王の顔にかける水がないか、室を捜
した。インクつぼしかなかったので、それを持って戻ると、白の王は、
回復していた。そして、白の女王と、アリスには聞こえないヒソヒソ声
で、なにか話していた。
「ヒゲの先ほど、わしは、おびえておるのじゃ」と、白の王。
「あなたには、ヒゲはないわ!」と、白の女王。
「その瞬間の怖ろしさといったら、決して忘れることができない!」と、
白の王。
「忘れられるわ!」と、白の女王。「もしもそれを、メモ帳に記せば!」
アリスは、白の王がポケットから巨大なメモ帳を出して、書き始める
のを、興味深く見ていた。そして、急に思いついたのは、鉛筆の先を持
って、アリスが白の王の肩越しに、お手紙を書くということだった。
白の王は、最初、困ったようにみえたが、なにも言わずに、鉛筆を取
り戻そうと努力していた。
「もう少し軽い鉛筆はないのかのう?」と、白の王。アリスの力があま
りに強いので、たまらずに言った。「この鉛筆は、重すぎる!勝手に、
文字を書いておる!」
「どういうこと?」と、白の女王。メモ帳を見ながら。(そこには、ア
リスがこう書いていた。『白のナイトは、ポーカーまで進んだが、すご
く、バランスが悪い』)「あなたのメモではないわ!」
テーブルの手元には、アリスが持ってきた1冊の本があった。アリス
が白の王を見守っているあいだ、(白の王のことが心配で、また気を失
ったら、かけてあげようとインクつぼもあった)、本で分かる部分のペ
ージを折り曲げていた。
「この本は、全く知らない言語で書かれている!」と、アリス。自分に。
「あ、分かったわ!ここは、鏡の家だった!もう一度、鏡に映せば、読
める文字になるんだわ!」
本には、詩が書かれていた。
◇
ジャバウォック
夕暮れに トーブたちは
芝生に 穴をあける
かわいそうなのは ボロゴフ鳥と
ラースたち ふるさとを想う
「娘よ ジャバウォックに気をつけよ
強いアゴ 鋭いツメ
ジャブジャブ鳥にも 気をつけよ
怒り狂った バンダースナッチにも」
女子戦士は 剣を手に
はるかなる 追跡の旅
タムタムの木陰で 眠り
思いをめぐらして 立ち止まった
立ち止まった そのとき
「ガルゥールルルゥ!」
怒り狂った ジャバウォックが
タルシーの森から 襲ってきた
剣で裂き 剣で貫いて
「トゥーフ!」
ジャバウォックを倒した
野獣ののツメを 持ち帰った
「ついに ジャバウォックを
お手柄じゃ 娘よ
今宵は うたげじゃ」
王は 女子戦士を ほめたたえた
夕暮れに トーブたちは
芝生に 穴をあける
かわいそうなのは ボロゴフ鳥と
ラースたち ふるさとを
想う
◇

「すてきな詩ね!」と、アリス。「理解するのが難しい部分もある」
(ポケットのメモ帳にすべて書き写した)「頭にいろんなイメージが浮
かんだわ!その正体は定かではないけれど、とにかく、誰かがなにかを
殺したのよ!それだけは、確かよ!」
「そうだ!」と、アリス。とび上がった。「急がないなら、鏡を通って、
戻るべきよ!まず、急いで、庭を見ましょう!」アリスは、あっという
間に室を出て、階段をかけおりた━━━正確には、走ってではなく、ア
リスが発明した、すばやく容易に階段をすべり降りる方法ですべり降り
た。
アリスは、指の先を階段の手すりに触れているだけで、足を全く階段
に触れることなく、スムーズにすべり降りることができた。玄関もすべ
ったまま、ドアポストに触れることもなく、ドアの外へまっすぐに出た。
空中をすべっているあいだ、めまいはまったく感じなかった。外へ出て、
ふつうに歩けるのが楽しかった。
2
「庭は、遠くから見るといいのよ!」と、アリス。自分に。「丘の上か
ら見ましょう!ちょうど、丘に続く、まっすぐな道があるわ!いや、少
し違うかもしれない」(数ヤード歩くと、急なカーブがいくつも続いて
いた)「最後には、丘の上に行けるはずよ。でも、すごく曲がりくねっ
ていて、道というより渦巻きね!いいわ、この道が丘の上に行くとして
━━━いや、違う、この道は、まっすぐ家の裏に戻ってしまうわ!それ
じゃ、別の道で行きましょう!」
登ったり、下ったり、曲がりくねったりして、別の道を試してみたが、
どの道も、すべて、家に戻って来てしまった。実際、ある曲がり角を、
ふつうより速く曲がってみたが、止まらないで走っただけだった。
「話し合う気になれないわ!」と、アリス。家を見上げた。家は、アリ
スになにか言いたげだった。「もう一度、試してみる気はないわ。わた
しは、また、鏡を通って、もとの世界に戻るべきかも。でも、それじゃ、
冒険が終わってしまうわ!」
それで、アリスは、断固として家に背を向けて、ふたたび道を、今度
は丘の上に着くまで、まっすぐに歩いた。数分後に、すべてはうまくい
った。
「やった!今度はうまくいったわ!」と、アリス。道は、突然曲がりだ
して、震え出した。(あとで、アリスがそう表現した)つぎの瞬間、ア
リスはドアに向かっていた。
「また、最悪だわ!」と、アリスは叫んだ。「もう、あの家が目の前に
せまるのを見たくない!」
◇
しかし、目の前には、丘が広がっていた。それで、歩き始めることに
した。今度は、アリスは、一面のお花畑に出た。端の方はデイジーが咲
き、真ん中は1本のバオバブの木だった。
「オニユリだわ!」と、アリス。ある方向に誘うように、風に優雅にな
びいていた。「オニユリが口をきけたらいいのに!」
「おしゃべりしましょう!」と、オニユリ。「おしゃべりする価値があ
るならね!」
アリスは、驚いて、1分間口がきけなかった。息するのがやっとだっ
た。そのあいだも、オニユリは、おしゃべりしたそうに、風になびいて
いた。
「ここでは、花がしゃべれるの?」と、アリス。おどおどとした声で、
ささやくように。
「あなた程度にはね」と、オニユリ。「大声も出せる!」
「先にしゃべりかけることはしないけどね」と、バラ。「だから、あな
たにしゃべりかけられたとき、すごく困った!あまりかしこそうにはみ
えないけど、なにかを隠しているかもしれないからね。もっとふさわし
い色の服を着れば、すこしはましに見えるよ!」
「服の色は、どうでもいい!」と、オニユリ。「服がもっとカールした
かんじだったら、それでいいと思う!」
アリスは、人に評価されるのが好きでなかったので、逆に質問した。
「草花の世話人もなく、ここに植えられていて不安じゃないの?」
「バオバブの木がある」と、バラ。「なんのためだと思う?」
「危険が迫ったときに、なにができるの?」と、アリス。
「ほえてくれるのさ!」と、バラ。
「バオバブってね!」と、デイジー。「それが、バオバブの木の名前の
由来さ!」
「そんなこと、どこで知ったんだ?」と、別のデイジー。大声で。そし
て、みんながいっせいに叫び出したので、金切り声でいっぱいになった。
「静かに!」と、オニユリが叫んだ。左右にゆれながら、興奮から震え
ていた。「みんな、私がしかることができないと思っている」震える花
を、アリスに向けた。「だから、あんなふうに騒ぐんだ!」
「気にしないで!」と、アリス。なだめるような声で。そして、また騒
ぎ始めた、デイジーの方に身をかがめると、ささやいた。「静かにしな
いと、抜いてしまうわよ!」
一瞬で、みんな騒ぐのをやめた。ピンクのデイジーは、白に変わった。
「そう、それでよろしい!」と、オニユリ。「デイジーは、もっとも悪
い!ひとりが騒ぎ出すと、みんな騒ぐ!だから、ひとりを枯らそうとす
れば、みんな言うことをきく!」
「どうしたら、そんなにうまくしゃべれるの?」と、アリス。礼儀とし
て、オニユリのご機嫌をとるように言った。「いろんな庭を見てきたけ
ど、しゃべれる花なんてなかったわ!」
「地面に手を置いてみなさい!」と、オニユリ。「そうすれば、理由が
分かる!」
アリスは、地面に手を置いた。「むずかしいわ!なにがどうなのか分
からない」
「たいていの庭では」と、オニユリ。「ベッドは、ふかふかなのさ!だ
から、花はいつも眠っている!」
これは、まともな理由に思えたので、アリスは喜んだ。「そんなこと、
考えも及ばなかったわ!」
「あなたは、考えたことがなかったのでは?」と、バラ。皮肉をこめて。
「わたしは、他人をそんなに悪く言ったことはない!」と、スミレ。突
然、スミレが口をひらいたので、アリスはとび上がった。
「知ったような口をきくんじゃない!」と、オニユリ。「世の中のこと
をまるで知りもしないのに!花を葉の下に隠して、寝ていなさい!つぼ
みの頃より、世の中のことがよく分かるようになるまで!」
◇
「この庭には、わたし以外に、人間はいるの?」と、アリス。バラの言
ったことを気にもせず。
「そうね、あなた以外に」と、バラ。「もうひとり、自由に歩ける花が
いるわ!どうやったら自由に歩けるのか知らないけど、(オニユリが
「自由に歩く」と表現した)、彼女は、あなたよりずっと茂みっぽい!」
「わたしは、好かれるかしら?」と、アリス。熱心に。そして、心の中
で。「もうひとり、少女がいるんだわ!」
「そうね、彼女も」と、バラ。「あなたのように、みすぼらしいかっこ
うをしている!それに、もっと赤で、服はもっと短い」
「服は、ダリアのように」と、オニユリ。「上を向いて閉じていて、あ
なたの服のように乱れてはいない」
「でも、それは、あなたのせいではない!」と、バラ。親切に。「あな
たは、枯れ始めていて、服が乱れるのは仕方のないことだもの!」
「彼女は、ここへ来るかしら?」と、アリス。バラの言ったことを、気
にもせず。
「すぐに会える!」と、バラ。「彼女は、9つのスパイクを持つ花よ!」
「スパイクが?どこに?」と、アリス。興味をもって。
「もちろん、花のまわりさ!」と、バラ。「みんなそうだと思っていた。
あなたにないのが不思議だった!」
「彼女が来た!」と、ラークスパー。「足音がする!タムタムと、砂利
を歩く音が!」
アリスは、周りを見わたして、赤の女王を見つけた。
「ずいぶん大きくなったわ!」と、アリス。
赤の女王は、アリスが灰の中で最初に見つけたときは3インチだった
が、今は、アリスより頭半分、背が高かった。
「空気がフレッシュだ!」と、バラ。「外の空気は、すばらしい!」
「わたしはもう行くわ!彼女に会いに!」と、アリス。そして、心の中
で。「赤の女王と話す方が、花たちより、はるかに大切よ!」
「それは、たぶん、うまくゆかない!」と、バラ。「歩く方と、別の方
に歩くのよ!」
◇
「どういうこと?」と、アリス。心の中で。バラの言ったことを気にも
せず、歩き出した。すると、赤の女王から離れていった。
「あら、赤の女王が見えなくなった。また、ドアの前に来てしまった!」
と、アリス。今度は別に驚きもせずに、引き返した。そして、赤の女王
が見える場所から、(彼女を見つけるまで、長い距離を歩いたが)、ど
う近づくか考えた。
「そうだ!逆方向に歩けばいいんだわ!」と、アリス。
今度はうまくいった。すぐに、赤の女王のところに来た。ここからは、
丘がよく見えた。
「あなたは、どこから来たの?」と、赤の女王。「そして、どこへ行く
の?顔を上げて、きちんとしゃべりなさい!指をしょっちゅう触らない
ように!」
「ええ、そのようなしつけは受けてますわ!」と、アリス。「道に迷っ
てしまったんです!」
「あなたの道が、なにを意味するのか分かりませんが」と、赤の女王。
「ここの道は、わたしの領域です。なぜ、ここから出て行こうとするの
ですか?」そして、やさしい声で。「考えているあいだは、おじぎをし
なさい!時間の節約になります!」
アリスは、この言葉がピンと来なかったが、赤の女王をうやまう気持
ちから、疑問は持たなかった。「おじぎは、家に帰るときにするわ!」
と、アリスは考えた。「夕食に遅れそうになったときにでも!」
「答える時間がきましたよ!」と、赤の女王。腕時計を見ながら。「話
すときは、口を大きくあけて、かならず『陛下』とつけること!」
「庭がどうなってるのか見たいだけです、陛下!」
「よろしい!」と、赤の女王。アリスの頭を軽くたたきながら。アリス
は、これがイヤだった。「けれど、庭なのか庭園なのか、あるいは野原
なのか、あいまいですね!」
アリスは、言われたことは気にもせず続けた。「あと、丘の頂上へ行
く道を知りたい」
「あなたが、丘と言うとき」と、赤の女王。さえぎった。「続いている
丘なのか、谷のあとの丘なのか、あいまいですね!」
「とんでもありません!」と、アリス。赤の女王の言いがかりに腹が立
った。「丘と言ったら丘です!谷ではありません!あなたの言うことは、
ナンセンスです!」
赤の女王は、頭を振った。「あなたは、自分が好きでないことをナン
センスと言ってるだけです。辞書にあれば、ナンセンスではありません
!」
アリスは、赤の女王の強い口調に、自分の言い方を反省して、おじぎ
をした。そして、丘の頂上に着くまで、ふたりとも黙っていた。
数分後、アリスは、丘の頂上に立った。そこからは、視界がひらけて、
国のすべての領域が見渡せた。とても奇妙な領域だった。直線的に、狭
い小川が、上下左右に走っていて、地面は、無数の緑の小さな生垣の四
角に分かれていた。
「まるで、大きなチェス盤だわ!」と、アリス。「動いている駒がいる
かも━━━ちゃんと、いたわ!」アリスは、嬉しさから胸がドキドキし
た。「大きなチェスの試合だわ!これが国なら、国じゅうで開催された
大きな試合よ!なんて楽しいんでしょう!わたしも、駒のひとつになっ
て参加したい!ポーンでもいいわ。女王だったら、なおいいけど!」
アリスは、女王と言ってしまって、本物の赤の女王の顔色を見たが、
赤の女王は気にもとめなかった。
「簡単よ!」と、赤の女王。「つぎの試合では、白のポーンになれるわ!
白のポーンのリリーは、試合をするには幼すぎるから。8番目の試合で
は、あなたは女王にもなれるわ!」
ふたりは、走り出した。
◇
「いったいなにが、どうなったの?」と、アリス。試合がすべて終わっ
てから考えた。「試合がいつ、どのように始まったのか、どのように終
わったのか、さっぱり分からない。覚えているのは、みんな、手に手を
とって、走りまわっていたことだけ。女王は、ずっと、みんなを急がせ
ようとして、『早く!早く!』と叫び続けていた。でも、わたしは、も
う疲れて、これ以上早くなんてできない!」
もっともヘンだったことは、木や周りのものがまったく動かなかった
ことだった。みんながどんなに早く動いても、周りのものはまったく場
所を変えなかった。
「すべてのものは、わたしたちといっしょに動いているのかしら?」と、
アリスは考えた。
「早く!」と、赤の女王。「ムダ口をたたかないで!」
「早くなんて、もうムリだわ!」と、アリスは考えた。「口をきく元気
もない!」
「早く!早く!」と、赤の女王。アリスを引っぱった。
「わたしたちは、だいたいここにいるのかしら?」と、アリス。
「だいたいここに?」と、赤の女王。アリスの言葉を繰り返した。「も
う10分前に、ここは過ぎましたよ!早く!」
みんな、黙って走った。風がアリスの耳にヒューヒュー鳴って、髪を
ほとんど吹き飛ばしたように感じた。
「さぁ!さぁ!」と、赤の女王は叫んだ。「早く!早く!」
みんなは、あまりに早く走ったので、ほとんど足を地面につけずに、
空中をすべって行った。そして突然、アリスは、疲れきった。みんなも
立ち止まった。アリスは、地面に座ったまま、息が苦しく目まいがした。
「ゆっくり休みなさい!」と、赤の女王。アリスをささえて、木の根元
に座らせた。
アリスは、周りを見て驚いた。「わたしたちは、ずっとこの木の下に
いたわ!すべてがこのままだった!」
「もちろん、そうよ!」と、赤の女王。「なにが、おかしいの?」
「わたしのいた領域では」と、アリス。まだ少し息切れしていた。「さ
っきのようにずっと全力で走れば、ふつうは別の場所にいるわ!」
「スローペースの領域ではね!」と、赤の女王。「ここでは、さっきの
ような走りでは、同じ場所にいられるのがやっとよ!もしも別の場所に
行きたいのなら、少なくともさっきの2倍の早さで走らないとダメ!」
「もうこれ以上はムリだわ!」と、アリス。「ここにいられるだけでい
い!暑くてのどがかわいたわ!」
◇
「なにが欲しいのか、分かったわ!」と、赤の女王。やさしくそうに、
ポケットから小さな箱を取り出した。「ビスケットは?」
「欲しくはないけど、断わったら失礼になるかも」と、アリスは考えた。
それで、ひとつもらい、ムリして食べた。「パサパサだわ!今まで、こ
れほどノドがつまりそうになったことはなかった!」
「さて、元気になったら」と、赤の女王。「計測しましょう!」赤の女
王は、また、ポケットから、インチごとにメモリのあるリボンを取り出
した。そして、地面を測りながら、あちこちに小さなクイを立てていっ
た。
「2ヤードのところで」赤の女王は、そこにクイを立てた。「指示があ
ります。もうひとつビスケットは?」
「もう、けっこうです」と、アリス。「1つでじゅうぶんです」
「のどのかわきは、いえた?」と、赤の女王。そして、アリスの返事を
待たずに続けた。「3ヤードのところで、指示を繰り返します。指示を
忘れてるかもしれないので。4ヤードのところで、さよならを言います。
5ヤードのところで、去ります」
赤の女王は、すべてのクイをセットし終えた。アリスは、興味深く見
ていた。赤の女王は、木まで戻ると、クイの列に沿って、ゆっくり歩き
出した。
2ヤードのところで、1ラウンドが始まった。
「ポーンは」と、赤の女王。「最初、2マス進みますから、できるだけ
すばやく、おそらくレールをすべって、3マス目に進みます。そして、
ノータイムで、4マス目に来てるでしょう。この4マス目は、テュデュ
ルダムとテュデュルディに属します。5マス目は、ほぼ水です。6マス
目は、ハンプティダンプティに属ます。なにか質問ありますか?」
「わたしもなにかするんですか?」と、アリス。頭がフラフラした。
「もちろんです。言ったことをやってもらいます!」と、赤の女王。き
びしい口調で。「それはさておき、先を続けます。7マス目は、森です。
ナイトのひとりが、道を教えてくれます。8マス目は、いっしょに女王
になれます!宴の場所です!」
アリスは、立ち上がって、おじぎをして、また、座った。
赤の女王は、つぎのクイに進んだ。「英語で分からなくなったら、フ
ランス語でしゃべりなさい!進む方向に足を向けて、自分がだれなのか
思い出しなさい!」赤の女王は、アリスがおじぎをするのを待たずに、
つぎのクイに進んだ。「さよなら」と、赤の女王。すぐに、最後のクイ
に進んだ。
◇
「なにが起こったのかしら?」と、アリス。「赤の女王が、最後のクイ
に来た瞬間、消えてしまったわ!彼女は、すごく早く動けると言ってい
たから、森へ走っていったのかしら?」
それを知る手がかりは、なかった。
「あら、わたしはポーンだった。わたしの番がもうすぐ来るわ!」
3
「まずしなくてはならないことは」と、アリス。自分に。「この世界の
全体像を知るために、いろんなところを旅することだわ!まるで、地理
の勉強みたい!」
アリスは、つま先立ちをして、少しでも遠くを見ようとした。
「まず、川は」と、アリス。「ないわ!山は、ひとつ。今いるところだ
わ。でも、山の名前が分からない。町は━━━ところで、遠くの向こう
で、花の蜜を集めているのは、なにかしら?ハチではないわ。ハチは、
1マイル以内でも、まったく見てない!」
アリスは、黙って、立って見ていた。ハチは、花から花へ駆けるまわ
ったり、花へ口を差し込んだりしていた。
「ふつうのハチではない━━━分かったわ!ゾウよ!」アリスは、そう
思いついて息をのんだ。「あの花は、きっとものすごく巨大なんだわ!
屋根の代わりに茎を並べた小屋があるわ。あの花からどれだけの蜜がと
れるのかしら?降りてゆくべき?いいえ、今は、ゆけない!ゾウたちを
きれいにしてあげられるような、長い枝でもなければ!ゾウたちは、
『歩きはどう?』と聞くかもしれない。そしたら、『悪くはないわ!』
(ゾウたちは、ここで、わたしの頭を軽くさわるかも!)『少し暑くて、
ほこりっぽいけど!あなたたちは、ずいぶん気持ちよさそうね!』と答
えるわ!」
アリスは、少し考えて、決心した。「別の道で降りよう!ソウたちに
は、あとで会いにゆこう!それに、今は、3マス目に進まなくては!」
アリスは、丘をかけ降りて、6つの狭い小川をこえた。
◇
「キップを!」と、車掌。あいた窓から。車内のみんなは、すぐに、キ
ップを見せた。
「あなたのキップは?」車掌は、アリスを険しい目で見た。
「車掌さんを待たせるんじゃない!」と、みんな。
「まるでコーラスのようだわ」と、アリスは考えた。
「車掌さんの時間は、1分で千ポンド!」と、みんな。
「キップがないんです!」と、アリス。驚いたように。「ここへ来るま
で、キップ売り場を通らなかったので!」
「ここへ来るまで」と、みんな。また、コーラスで。「売り場がなかっ
た?土地の値段は、1インチで千ポンド!」
「あやまる必要はない」と、車掌。「機関手からキップを買いなさい!」
「機関手から!」と、みんな。「蒸気の値段は、1吹きで千ポンド!」
「それじゃ、考える必要はないわ!」と、アリスは考えた。声に出さな
かったので、コーラスはなかった。しかし、驚くことに、考えのコーラ
スはあった。(考えのコーラスがどういうものか、分かってほしい。作
者にはあまりピンと来ない)
「なにも言わないのがベストだ!」と、考えのコーラス。「言葉は、1
ワードで千ポンド!」
「今夜は、もう」と、アリスは考えた。「1千ポンドの夢を見たわ!」
車掌は、アリスを見ていた。最初は、望遠鏡で。つぎは、顕微鏡で。
それから、オペラグラスで。
「あなたは、旅行のしかたを間違えている!」と、車掌。窓を閉めて、
どこかへ行った。
「お子さんは」と、白の背広の紳士。アリスの向かいに座っていた。
「自分の名前を言えなくても、行き先は知っていなければ!」
「そうよ!」と、ヤギ。白の紳士の横に座っていた。「名前のスペルが
分からなくても、キップ売り場は知ってるべき!」
「荷物といっしょに送り返すべき!」と、ヤギの横のカブトムシ。
「とても奇妙な乗客ばかりだわ!」と、アリスは考えた。「順番にしゃ
べるルールでもあるのかしら?」
カブトムシのさらに横は、だれなのか見えなかったが、しゃがれ声だ
った。
「エンジンを変えて」と、しゃがれ声。「チョークをかけたら、発車す
べき!」
「馬の声だわ!」と、アリスは考えた。そのあと、小さい声が聞こえた。
「しゃがれ声のホースと馬のホースをかけてるわけね?」と、小さい声。
「少女は、割れもの注意の荷物のつもりさ!」と、遠くの声。
「スタンプがあるんだから、郵便として郵送されるべき!」と、別の声。
「いったい、この車両になん人乗ってるのかしら?」と、アリスは考え
た。
「電報のメッセージとして送るべき!」
「自分で列車を引いてゆくべき!」
しかし、白の紳士は、体をかがめて、アリスにささやいた。「みんな
の言うことは、気にしないでいい!ただ、列車が停まったら、帰りのキ
ップは買いなさい!」
「いやよ!」と、アリス。がまんできなくなった。「わたしは、旅なん
てしてない!森にいたのよ!もとの場所に戻りたい!」
「冗談かい?」と、小さな声。アリスの耳元で。「できるならしたい?」
「からかわないで!」と、アリス。声のした方を向いて。「冗談なら自
分に言って!」
◇
小さい声は、ため息をついた。深いため息だったので、アリスは、な
にか元気づけることを言おうとした。
「人のため息のようだけど」と、アリスは考えた。「すごく小さなため
息だから、耳の近くでないとぜんぜん聞こえない!耳がくすぐられてい
るようで、なにを言おうとしたのか忘れてしまったわ!」
「ぼくは、ずっと前からの友だちさ」と、小さい声。「ぼくは虫だけど、
傷つくのはイヤでしょ?」
「なんの虫?」と、アリス。そして、考えた。「ほんとうは、なんの虫
か知りたくない!刺すかどうかも知りたくない!訊くのも、失礼だし!」
「なんの虫かというと」と、小さい声。
「キーッ!」と、急ブレーキの音。小さい声は、かき消された。アリス
も含めて、みんな、悲鳴を上げてとび上がった。
「ただの小川があっただけさ!」と、馬。窓から出していた頭を、引っ
込めた。
みんなは馬の言ったことでホッとしたが、アリスは、小川と聞いて心
配になった。
「列車が」と、アリス。自分に。「3マス目に連れてきてくれたようね。
つぎの4マス目には、このまま楽に着けるはず!」
つぎの瞬間、車両が空中をジャンプした。アリスは、近くのものにつ
かまろうとして、ヤギのひげをつかんだ。
◇
ヤギのヒゲは、つかんだ瞬間、溶けて消えてしまい、気づくと、アリ
スは、木の下に座っていた。
アリスの頭の上の小枝には、蚊が、羽ばたきながら、とまっていて、
(さっきまで、アリスとしゃべっていた虫だった)、アリスに風を送っ
ていた。
「ずいぶん大きな蚊!」と、アリスは考えた。「にわとりくらいありそ
うだわ!」
ずっとしゃべっていたので、こわい気はしなかった。
「それでは、虫がキライですか?」と、蚊。なにごともなかったかのよ
うに。
「しゃべれる虫は、好きだわ!」と、アリス。「でも、わたしのいた領
域では、しゃべれる虫は、いなかった!」
「どんな虫が、喜ばせてくれたんですか?」と、蚊。
「だれも!」と、アリス。「むしろ、虫がこわかった。とくに、大きな
やつは。でも、名前が分からない!」
「虫は、訊けば、名前を教えてくれたでしょう?」と、蚊。
「どうか分からない」
「名前を教えてくれないなら」と、蚊。「なぜ名前があるんです?」
「虫には必要ないわ」と、アリス。「しかし人間には、虫に名前があっ
た方が便利だからだと思う。そうでないなら、なぜ物には名前があるの
?」
「分からない」と、蚊。「さらに言うと、そこに落ちてる木には名前が
ない!しかし、虫のリストを続けた方がいい!時間をムダにしている!」
「まず、ウマバエ!」と、アリス。指で数えながら、虫のリストを始め
た。
「そう」と、蚊。「茂みにすこし分け入れば、ロッキングウマバエが見
つかるさ!完全に木製で、枝から枝にゆれている!」
「どこに住んでるの?」と、アリス。すこし興味があった。
「樹液とか、がおがくずの中!」と、蚊。「虫のリストを続けて!」
アリスは、茂みの中に、ロッキングウマバエを見つけた。それはペン
キ塗りたてのように、鮮やかで、ベタベタしていた。
「つぎは、トンボ!」と、アリス。
「枝の上を見れば、ブドウつまみバエが見つかるさ!体は、プラムプデ
ィングでできていて、羽はヒイラギの葉で、その頭は、ブランディで燃
えている干しブドウでできている!」
「どこに住んでるの?」と、アリス。
「フルメンティとミンスパイ!」と、蚊。「クリスマスボックスに巣を
作る!」
「それから、チョウチョウ!」と、アリス。
頭の上を、ブドウつまみバエが燃えながら飛んでいた。
「虫が火の中に飛び込む理由が分かった!」と、アリスは考えた。「ブ
ドウつまみバエになりたいんだわ!」
「足元を注意して見れば」と、蚊。(アリスは、自分の足元を調べた)
「ブレッドアンドチョウチョウが見つかる!羽は、薄いブレッドアンド
バターで、体はパンの耳で、頭は砂糖のかたまり!」
「どこに住んでるの?」
「クリーム入りの薄い紅茶の中!」
「見つけられるの?」と、アリス。
「もちろん、溶けて死んでる!」
「めったに、死なないんでしょう?」と、アリス。
「いつも死んでいる!」と、蚊。
アリスは、1・2分の間、なにも言わなかった。
蚊は、おもしろがって、アリスの頭の上でブンブンと飛んでいた。
「名前を失いたくはないでしょう?」と、蚊。
「絶対にイヤ!」と、アリス。少し心配だった。
「名前がないというのも」と、蚊。軽率に。「家に帰れば、すごく便利
ですよ!たとえば、家庭教師が授業をしようとして呼んでも、『来なさ
い!』のあと名前を呼べないから、行く必要はない!」
「そうでもないわ!」と、アリス。「家庭教師は、名前を忘れても、召
使がするように、『ミス』と付けるから、授業がなくなることはない!」
「ただのシャレさ!」と、蚊。「『ミス』と、授業がなくなるのミスを
かけたのさ!分かってくれると思ったんだ!」
「分かるもんですか!」と、アリス。「悪い冗談だわ!」
蚊は、深いため息をついた。大つぶのなみだが、2つ、ほおを伝って
落ちた。
「そんなに悲しくなるジョークなら」と、アリス。「言わない方がまし」
悲しそうな小さなため息は、しばらく続いていたが、最後に深いため
息がして、静かになった。アリスが見上げると、蚊のすがたはなかった。
「長く座っていたから、寒くなったわ。少し、歩きましょ!」
アリスは、立ち上がった。
◇
すぐに、森の見える広々とした場所に出た。前の森より、暗く見えた。
「あの森を通るのは、気が引ける」と、アリスは考えた。「でも、行く
しかない!戻ることはできない!8マス目に行くには、ここを通るしか
ない!」
アリスは、森に近づいた。
「たしかに、森だわ!」と、アリス。自分に。「そこでは、ものに名前
がない。森に入ったら、わたしも名前を忘れてしまうのかしら?忘れた
くない!もしも別の名前が付けられたら、たいていはイヤな名前でしょ
うから!でも、アリスという名前を知っている誰かを、捜す楽しみはあ
るわ!イヌの名前を忘れた人たちに、グレーのイヌに『ダッシュ』と言
わせる、コマーシャルみたいに!誰かが答えられるまで、会うものすべ
てを『アリス』と呼んでしまうかもしれない!賢ければ、なにも答えな
いでしょうけど」
アリスは、ブラブラ歩いて、森の入り口に来た。森は、暗く冷たそう
だった。
「とにかく、ホッとするわ!」と、アリス。森に入った。「歩いて暑か
ったから、ここに入れて!ここって?」ワードが浮かばなかった。「こ
の下よ!どの下?」手を木のみきについた。「なんて言うんでしたっけ?
名前がないんだわ!たしかに、名前がないんだわ!」
アリスは、1分間、考えながら、静かに立っていた。そして、思いつ
いた。
「やっぱり、そうなってしまったんだわ!わたしは誰かって?もちろん
言えるわ!がんばればね!」
しかし、がんばっても出てこなかった。
「『リ』よ!『リ』で始まるんだわ!」と、アリス。悩んだ末に。
そのとき、道に迷った子ジカが現われて、アリスを見た。大きなやさ
しそうな目をしていて、驚いた様子はなかった。
「こっちよ!こっち!」と、アリス。手を広げて、つかまえようとした。
子ジカは、後ずさりして、また、アリスを見た。
「あなたの名前は?」と、子ジカ。やっと、口をひらいた。ソフトで甘
い声だった。
「もちろん分かるわ!」と、アリス。少し悲しくなった。「今は、分か
らないけど」
「もう一度、考えてみて!」と、子ジカ。「思い出せるかも!」
アリスは、考えたが、なにも浮かばなかった。
「あなたは、自分をどう呼んでるの?」と、アリス。おどおどと。「参
考になるわ!」
「もう少し進めば」と、子ジカ。「教えられるわ!ここでは、わたしも
思い出せない!」
ふたりは、いっしょに森を進んだ。アリスは、子ジカのやわらかい首
を両手で抱きかかえて歩いた。やがて、森を抜けて、広々とした場所に
出た。子ジカは、急に飛び上がって、アリスの腕を振り払った。
「わたしは、子ジカよ!」と、子ジカは叫んだ。喜んで。「そして、あ
なたは人間の子どもよ!」
子ジカの目に警戒心が現われ、つぎの瞬間、全速力で逃げていった。
◇
アリスは、子ジカが逃げてゆくのを見ていた。突然、仲のよい仲間を
失って、今にも泣き出しそうだった。
「でも、今は、自分の名前が分かる!」と、アリス。「少しホッとした
わ!アリスよ、アリス!2度と忘れたくないわ!さて、つぎは、指の方
向案内のどちらへ行けばいいの?」
この問題は、難しくはなかった。森を抜ける道は、1本だけで、2本
の指方向は同じだった。
「たぶん、うまくゆくわ!」と、アリス。「分かれ道に出て、2本の指
方向が違っていたとしても!」
そのようなことは、起こりそうになかった。アリスは、どんどん進ん
で、かなりな距離を進んだが、分かれ道ではいつも、2本の指方向が、
同じ方向を指していた。
ひとつは、
━━━テュデュルダムの家へ。
もうひとつは、
━━━テュデュルディの家へ。
「たぶん」と、アリス。「ふたりは、同じ家に住んでるんだわ!こんな
ややこっしいことは、今までなかったけど、長居はしない。呼び鈴を鳴
らして、『お元気?』と言って、森を抜ける道を聞くだけ!暗くなる前
に、8マス目に着ければいいのよ!」
歩いてゆくと、急な分かれ道に出た。その角に、背の低い太った少年
がふたり、並んで立っていた。あまりに突然現われたので、アリスは走
って戻ろうとしたが、すぐに思いついた。
「このふたりが、2本の指方向のふたりだわ!」
4
ふたりは、木の下で、お互いの腕を相手の首にまわして立っていた。
シャツのえりには、『ダム』と『ディ』の名前があったので、すぐにふ
たりを区別できた。
「たぶん」と、アリス。自分に。「えりのうしろ側には、『テュデュル』
があるんだわ!」
ふたりは、まるで生きてるのを忘れるくらい静かに立っていたので、
アリスは、背中にまわって、『テュデュル』を見ようとした。
「ぼくたちを」と、ダム。「ワックスがけ職人だと思ってない?そうな
ら、料金を払うべき!だって、ただでワックスがけはできないからね!」
「逆に」と、ディ。「ぼくたちが生きてるのか疑ってるなら、話しかけ
てくるべき!」
「ごめんなさい!わたしはアリス!」それだけ言うのがやっとだった。
アリスの頭の中では、まるで、時計がチックタック言うように、古い詩
が響き渡っていて、声に出して読んだ。
「テュデュルダムとテュデュルディは
けんかになった
テュデュルダムはテュデュルディに
新しいガラガラおもちゃを だいなしにしたと言った
そのとき 巨大なカラスが飛んできて
コールタールのように 真っ黒で
ふたりは 驚いて
けんかを忘れてしまった」
「なにが言いたいのかは、分かる」と、ダム。「でも違うね!まったく
違う!」
「逆に」と、ディ。「もしもそうなら、そうかもしれない。もしもそう
だったら、そうだったのかもしれない。しかし、もしもそうでないなら、
そうではない。それが、論理さ!」
「教えてほしいのは」と、アリス。ていねいに。「森を抜けるには、ど
ちらへ行ったらいいのかということ。すぐに暗くなりそうだから、教え
てほしい!」
しかし、ふたりは、互いの顔を見て、ニヤニヤするだけだった。
「ふたりは、大きな小学生にしか見えないわ!」と、アリスは考えた。
「テュデュルダムを指さして、『少年1!』と言ってしまいそうだわ!」
「まったく違う!」と、ダムは大声で叫んだ。そして、ピシャリと口を
閉じた。
「少年2!」と、アリス。ディを見て、たぶん、「逆に」と言うと思っ
た。
「逆に」と、ディ。「あなたは間違っている!会って最初は、『ごきげ
んいかが?』と言って、つぎに、握手するのが正しい!」
ふたりは、互いにハグしたあと、アリスと握手するために手を出した。
アリスは、最初、どちらかと握手すると、もう一方を傷つけるのでは
とためらった。しかし、いい解決法を見つけた。ふたりの手を、同時に、
つかんだのだ。つぎの瞬間、ふたりは、輪になってダンスを始めた。ダ
ンスはとても自然で、(アリスはあとで、そう思い出した)音楽が聞こ
えてきても、少しも驚かなかった。
音楽は、木の上から聞こえてきた。(アリスはあとで、分かった)枝
がこすれて、バイオリンと弓のように、音楽を奏でていた。
「それは、たしかに、少しおかしかったわ!」と、アリス。(アリスは
あとで、姉のマギーに物語のすべてを話した)「だって、『クワの茂み
のまわりで』を、いつのまにか歌い出して、まるで、ずっと前からよく
知っているように、歌っていたんですもの!」
ふたりのダンサーは、太っていて、すぐに息切れした。
「ダンスは4回踊れば、十分!」と、ダム。ダンスは、始まりとまった
く同じに、突然、終わった。音楽も、同時に止んだ。
ふたりは、アリスの近くに来て、1分間、アリスを見ていた。気まず
い沈黙。アリスは、今までいっしょにダンスしていたふたりに、なんと
声をかけたらいいのか分からなかった。
「ごきげんいかが?とは言えない」と、アリス。自分に。「もう、それ
以上の仲だわ!」
「それほど疲れてないわよね?」と、アリス。やっと口をひらいた。
「まったく!」と、ダム。「心配してくれて、ありがとう!」
「ほんとに、ありがとう!」と、ディ。「詩が好きなんですか?」
「ええ、そう!いくつかは、とても好き!」と、アリス。「森を抜ける
には、どちらへ行ったらいいの?」
「彼女になにを読んであげようか?」と、ディ。アリスの質問は気にも
せず、しんみりとした目でテュデュルダムを見た。
「『セイウチと大工』が一番長い!」と、ダム。弟のテュデュルディを
愛情をこめてハグした。
「陽がさんさんと」と、ディ。すぐに詩を、声に出して読み始めた。
「長い詩なら」と、アリス。思い切って、さえぎった。「その前に、道
を教えて!」
テュデュルディは、やさしくほほえんで、最初から、詩を、声に出し
て読み始めた。
「陽がさんさんと 海の上で輝く 強いエネルギーで
力の限り 大波はゆったりと ギラギラと
しかし これはおかしい 今は真夜中
月は輝く 怒りながら なぜなら
昼が過ぎて 陽が出てくるのは おかしい
『なんて無礼なの!』と 月 『楽しみを奪わないで!』
海は濡れに濡れ 砂浜は かわきにかわき
雲は見えなかった 空に 雲はなかったから
鳥も飛んでなかった 空に 鳥はいなかったから
セイウチと大工 ならんで 砂浜を歩いていた
ふたりは なにかを嘆いた 大量の砂
『砂浜をぜんぶ』と ふたり 『なくしてしまえばいい!』
『7人のメイドが7本のモップで 半年かけて そうじしたら
砂浜をすべて』と セイウチ 『なくせるだろうか?』
『ムリだな!』と 大工 苦々しい顔をした
『カキくんたち いっしょに歩こう!』と セイウチ
『楽しい散歩 楽しい会話 塩辛いビーチで
手をつなげるのは 4人までだけど』
年寄りのカキは セイウチを見た 黙ったまま
年寄りのカキは ウィンクして 重い頭をゆすった
ベッドを出たくなかった という意味だった
4人の若いカキたちは みだしなみ良く 急いだ
コートはブラッシングされ 顔を洗って 靴もみがかれ
カキに足はなくても 靴ははいていた
4人のカキたちが 続いた さらに4人
太ったカキたちも4人 続いた さらにさらにさらに
みんな泡だった波を抜け とびはねながら 海岸をよこぎった
セイウチと大工は 1マイルも歩いた それで
低い岩のところで 休むことにした
小さなカキたちも みんな 列を作って待った
『いろんなことを 話す時間だ』と セイウチ
『靴のこと 船 シーリングワックス キャベツ それに 王
なぜ海が煮立ってるのか 豚には 翼があるかどうか』
『ちょっと 待って!』と カキたちは叫んだ『話す前に
息を切らしてる者がいる みんな 太っているし』
『急がなくていいよ!』と 大工 みんなは大工に感謝した
『一片のパンが』と セイウチ『おもに 必要なもの
こしょうに おすも あったらなおよい
さぁ準備ができた カキたちよ 食事の時間だ』
『ぼくたちを 食べないで!』と カキたちは叫んだ 青ざめて
『親切にしてくれた後に ひどい!』
『夜はいい!』と セイウチ『この景色は すばらしい!
来てくれてありがとう きみたちは とてもおいしい!』
『もう1切れ くれる?』と 大工
『2度も頼んでいるのに 耳が遠くないことを 望む!』
『それは ずるい!』と セイウチ『トリックにかけるのは
遠くから連れてきて すばやく 料理してしまうとは!』
『パンにバターを 厚くぬりすぎ!』と 大工
『きみたちのために涙を流す』と セイウチ『深く同情する』
すすり泣きながら セイウチは 一番大きいカキをよりわけた
涙を流す前に ハンカチを広げた
『カキたちは』と 大工『みんな楽しく走った!
また 家に急いで帰るのかい?』だれも こたえなかった
別におかしくはなかった みんな 食べられた後だったから」
「セイウチが一番好き!」と、アリス。「カキたちに、感謝していたか
ら」
「セイウチは、大工より多く食べていた」と、ディ。「セイウチは、ハ
ンカチを前に広げていたから、大工は、セイウチが食べた数を数えられ
なかったんだ、逆に!」
「それは、ひどいわ!」と、アリス。怒って。「それなら、大工が一番
好き!セイウチより、少ししかカキを食べなかったから!」
「でも」と、ダム。「大工も、食べられるだけいっぱい食べたんだ!」
難しいパズルだった。
「それなら」と、アリス。しばらくしてから。「どちらも、ほめられた
キャラクターではないわね!」
◇
そのとき近くの森で、蒸気機関車の1吹きのような音がした。
「森には」と、アリス。おどおどと。「ライオンやトラのような、野獣
はいるの?」
「あれは」と、ディ。「赤の王が、いびきをかいてるだけ!」
「いっしょに、赤の王を見に行こう!」兄弟は、アリスの手をそれぞれ
引いて、赤の王が居眠りしている木の根元へ連れていった。
「かわいいでしょう?」と、ダム。
「赤の王の居眠りは」と、アリスは考えた。「ちっとも、かわいいとは
言えないわ!」
赤の王は、ふさつきの高い赤のナイトキャップをかぶって、散らかっ
たゴミの中に座って、大きないびきをかいていた。
「そんな草の上で寝て」と、アリス。「かぜを引かないか心配だわ!」
「赤の王は」と、ディ。「今、夢の中さ!どんな夢だと思う?」
「それは、誰にも分からない!」と、アリス。
「なぜ?」と、ディ。「アリスの夢かも?」勝ちほこったように、手を
たたいた。「アリスの夢から覚めたら、アリスはどこに行ってしまう?」
「もちろん、ここよ!」と、アリス。
「それは、アリスではない!」と、ディ。見くだすように、言い返した。
「アリスは、もうどこにもいない!なぜか?それは、アリスは、ただの、
赤の王が見ている夢の産物にすぎないから!」
「赤の王が目覚めれば」と、ダム。「アリスは消えてしまう!バ〜ン!
ろうそくのように!」
「そんなことありえない!」と、アリス。怒って。「それに、わたしが
赤の王の夢の産物なら、あなたたちはなんなの?知りたいものだわ!」
「同じく!」と、ダム。
「同じく!同じく!」と、ディは叫んだ。
「シー!」と、アリス。「そんな大声を出したら、赤の王を起こしてし
まうわ!」
「そんなこと言っても、意味がない!」と、ダム。「アリスはただの夢
の産物で、現実ではないから!」
「わたしは、現実よ!」と、アリス。泣き始めた。
「泣くことで、少し現実になろうとしても、ムダだ!」と、ディ。「泣
いても、なにも変わらない!」
「わたしが現実でなかったら」と、アリス。自分の涙を半分笑いながら。
「泣くこともできないはず!」
「それらが本当の涙だと、思ってないよね?」と、ダム。不満そうに。
「みんな、ナンセンスな話よ!」と、アリスは考えた。「そんなことで
泣く必要ない!」
アリスは、涙をきれいにハンカチでふいた。
「とにかく」と、アリス。とびきりの笑顔で。「そろそろ暗くなるし、
早く森を出たい。雨になりそうだわ」
テュデュルダムは、大きなカサを広げて、テュデュルディも入った。
「雨にはならないさ!」と、ダム。「ここではね!決っして降らない!」
「外では?」と、アリス。
「外では、分からない」と、ディ。「異論はない、逆に」
「なんて自分よがりなの!」と、アリスは考えた。それで、『おやすみ』
と言って、去ろうとすると、カサからテュデュルダムが飛び出てきて、
アリスの手首をつかんだ。
◇
「あれが見える?」と、ダム。声は、激情にかすれ、目を見ひらいて、
一瞬、黄色になった。震える指がさす先を見ると、木の根元に、白の箱
があった。
「ただのガラガラおもちゃよ!」と、アリス。白の箱を拾って、よく調
べた。「ガラガラヘビではないわ!」テュデュルダムが、『ただの古い
ガラガラおもちゃ、古いし、こわれている!』と、思っているかもしれ
ないと、心配しながら。
「あれが、なんなのか知っている!」と、ダム。声を荒げて髪をかきむ
しりながら。そして、テュデュルディを見た。テュデュルディは、すぐ
に地面に座り込んで、カサの下に隠れようとした。
「あんな古いガラガラおもちゃに、怒ることないわ!」と、アリス。テ
ュデュルダムの手をとって、やさしく。
「でも、あれは、古くなんてないんだ!」と、ダム。もっと、声を荒げ
て。「新しい!きのう買ったんだ!ぼくのかわいいガラガラおもちゃ!」
声は、叫び声になった。
そのあいだ、テュデュルディは、アリスの注意を怒った兄からそらそ
うとして、カサをたたんで、その中に隠れようとした。しかしそれはう
まくゆかず、カサに足をとられて地面にころがり、口や目を開いたり閉
じたりした。
「魚みたいだわ!」と、アリスは考えた。
「戦うことに、異存はないね?」と、ダム。静かな声で。
「ああ」と、ディ。カサから、はい出てきた。「アリスが、ぼくたちの
準備を手伝ってくれたらね!」
ふたりは、森の中へ入って行き、手にいろんなものを持って1分で戻
ってきた。当て布団や枕、敷物、テーブルクロス、お皿カバー、それに
石炭入れ。
「そんなものを体につけるうまい手があるんだろうね?」と、ダム。
「どれも、そのままじゃうまくゆかない!」
「こんなけんかは、今まで見たことないわ!」と、アリス。自分に。ふ
たりは、いろんなものを身につけるために、アリスの手を借りて、ひも
で結んだり、ボタンを留めたりした。「古着の束にしか見えない!そろ
そろ、準備ができたようね!」アリスは、当て布団を、テュデュルディ
の首のまわりになんとか結びつけた。
「首を切り落とされないように!」と、ディ。「決闘では、そういうこ
とが、たまに起こるからね!」
アリスは、大声で笑ってしまったが、うまくせきでごまかした。
「顔は青ざめてない?」と、ディ。ヘルメットを結んでもらいながら。
(ヘルメットは、シチューなべだった)
「そうね、少し」と、アリス。やさしく。
「ぼくは、ふつうは、勇敢なんだ」と、ダム。小声で。「たまたま、き
ょうは頭痛が!」
「ぼくは、歯痛さ!」と、ディ。すこし大声で。「ぼくの方が、ずっと
痛い!」
「それじゃ、きょうは、けんかをやめておいたら?」と、アリス。やめ
させる、いい機会だと思いながら。
「戦わなければならない!」と、ダム。「長くなろうが仕方ない。今、
なん時だい?」
「4時半」と、ディ。腕時計を見ながら。
「6時まで戦おう!それから、夕食」と、ダム。
「そうしよう!」と、ディ。少し悲しそうに。「アリスが、ぼくたちを
見ていてくれる!近くには来ないように!ぼくが怒り出したら、目に入
るものはなんでも切りつけるからね!」
「ぼくは、目に入らなくても、すべて切りつける!」
「たぶん、なんども木を切りつけることになるわ!」と、アリス。笑い
ながら。
「そんなことはない!」と、ダム。まわりを満足げに見渡した。「木は、
ちゃんと戦い終わるまで、そのまま!」
「たった、ガラガラおもちゃのために?」と、アリス。恥ずかしいと気
づいてくれることを願いながら。
「たしかにそうかもしれない」と、ダム。「新品でなかったらね!」
「巨大なカラスが飛んできてほしい」と、アリスは考えた。
「剣は1本しかない」と、ダム。「しかし、同じように鋭いカサがある。
すぐに始めよう。暗くなる前に!」
「暗くなっても!」と、ディ。
「急に暗くなったわ!」と、アリス。「きっと、雷雨が来るんだわ!な
んて厚い雲!すぐに雷雨よ!まるで翼があるように!」
「カラスだ!」と、ダム。悲鳴のような声を出した。ふたりは、あっと
いう間に逃げ出して、すぐ見えなくなった。
◇
アリスは、しばらく森をさまよってから、大きな木の下に来た。
「ここならだいじょうぶ!」と、アリス。自分に。「森で一番大きな木
だから、雷雨の力が及ばないわ!あら、誰かのショールが落ちている!
きっと、風で飛ばされてきたんだわ!」
5
アリスは、ショールを手にした。つぎの瞬間、白の女王が、森から走
ってきた。両手を広げて、まるで、空を飛んでるかのように。アリスは、
礼儀正しく、ショールを差し出した。
「突然、お会いできて、光栄です!」と、アリス。白の女王がショール
をつけるのを手伝った。
「パンとバター、パンとバター」と、白の女王。突然のことで、どうし
たらいいか分からず、ささやくように。
アリスは、このままでは会話にならないので、また、たずねた。
「白の女王さまと、お呼びしても?」と、アリス。むしろ、おどおどと。
「ええ」と、白の女王。「あなたがよければ、ドレスと呼んでもいいで
すよ。ピンと来ないけれど」
「また、会話が」と、アリス。自分に。「最初からつまずいてるわ!」
そして、笑いながら白の女王に。「陛下の考えを言ってくだされば、そ
のようにいたします!」
「そう呼んでほしくもない!」と、白の女王。「この2時間のあいだ、
このドレスをずっと着ているし」
「少しはましになってるわ」と、アリス。自分に。「わたしだって、誰
かがドレスを着せようとしたら、取り乱すところだわ!なにかひとつで
も盗まれたら、すべてピンで留めたくなるわ!」そして、大声で白の女
王に。「ショールをまっすぐにしてもよろしい?」
「なんのことか分からない!」と、白の女王。悲しそうな声で。「どう
かしてると思う。ショールを、ここやそこにピンで留めた。でも、楽し
んでやってない!」
「まっすぐに、なってないわ!」と、アリス。「ピンがすべて片側に留
まっている!」アリスは、そっとピンを直した。「それに、髪がひどい
ことになっている!」
「ブラシが髪のなかにからまったのよ!」と、白の女王。ため息をつい
た。「それに、くしも、きのう無くした!」
アリスは、注意深く、髪からブラシを取り出し、白の女王の髪をきれ
いに整えた。
「見て!これで、ずいぶん良くなったわ!」と、アリス。ショールのピ
ンも、またほとんど直した。「女性のメイドが必要だわ!」
「あなたは、どう?」と、白の女王。「週2ペンス、ほかの日は、いつ
もジャム!」
「わたしは、雇われたくない!」と、アリス。笑えなかった。「ジャム
もほしくない!」
「おいしいジャムよ!」と、白の女王。
「とにかく、きょうはいりません!」
「ほしかったとしても、食べれない!」と、白の女王。「ルールはこう!
ジャムは、きのうか明日。きょうはなし!」
「たまには、きょうはジャムになるはずでしょ!」と、アリス。反論し
た。
「いいえ!」と、白の女王。「ほかの日は、いつもジャムよ!きょうは、
ほかの日ではないわ!」
「分からない!」と、アリス。「おそろしく、ややっこしい!」
「うしろ向きに生きる効果よ!」と、白の女王。親切に。「最初は誰で
も、とまどう!」
「うしろ向きに生きる?」と、アリス。驚いて。「そんなこと、初めて
聞いたわ!」
「便利なことがあるわ。人の記憶は、双方向に働くから!」
「わたしの記憶は、1方向だけしか働かない!ものごとが起こる前には、
思い出せない!」
◇
「うしろ向きにしか働かないなら、貧しい記憶ね!」と、白の女王。
「今までで、一番良かった記憶は?」と、アリス。あえて訊いた。
「さ来週に起こること!」と、白の女王。不注意に。「たとえば、今」
大きなしっくいの断片を、指の上にのせながら。「白の王のメッセンジ
ャーのハッタが、罰で牢屋にいて、裁判は、来週の水曜までひらかれな
い。犯罪は、すでに行われている」
「ハッタが、犯罪とは無関係だったら?」と、アリス。
「もっとよいでしょうね?」と、白の女王。しっくいを指のまわりに結
びつけながら。
「否定するものは、ないわ」と、アリス。自分に。そして、白の女王に。
「もっとよいでしょうけど、ハッタが罰せられたら、もっとよくはない
んじゃない?」
「とにかく」と、白の女王。「あなたの言うことは、間違っている!前
に罰せられたことがあるの?」
「ええ、あやまちで」と、アリス。
「それでも、もっとよかったんでしょう?」と、白の女王。勝ち誇った
ように。
「そうね」と、アリス。「わたしがしてしまったことが罰せらた。これ
は、大きな違いだわ!」
「しかし、あなたがしなかったことだったら」と、白の女王。「それで
も、もっとよかった!もっと、もっと、もっと、もっと!」白の女王の
声は、「もっと!」ごとに、高くなって、最後は、きいきい声になった。
「なにか、変だわ!」と、アリス。
「オー、オー、オー!」と、白の女王は叫んだ。なにかを振り落とそう
とするように、指を振りながら。「指から血が!オー、オー、オー!」
白の女王の叫び声は、機関車の汽笛のようで、アリスは両手で両耳を
押さえた。
「どうしたのかしら?」と、アリス。「指をなにかで刺したんですか?」
「いいえ、まだよ」と、白の女王。「しかし、すぐに━━━オー、オー、
オー!」
「いつのこと?」と、アリス。笑いそうになりながら。
「ショールを、またつける時よ!」と、白の女王。「ブローチがはずれ
て、オー、オー!」ブローチを、何度かつかもうとした。
「気をつけて!」と、アリスは叫んだ。「曲げてつかもうとしている!」
白の女王は、ブローチをつかんだが、時すでに遅く、ピンがすべって、
指に刺さった。
「血が出るわね!」と、白の女王。笑いを浮かべて。「今、ここでなに
が起こるか分かったでしょ?」
「なぜ、今、叫ばないんですか?」と、アリス。耳を押さえようと身構
えながら。
「前もって、十分、叫んであるからよ!」と、白の女王。「また、繰り
返す必要はないわ!」
◇
「カラスは、飛び去ったんだわ!」と、アリス。思いついて。「飛び去
ってくれて良かった。もうすぐ、夜になるわ!」
「楽しんでもらえたでしょう」と、白の女王。「やり方は知りませんが、
あなたは、この森に住めて、とてもラッキーです!好きなだけ、楽しん
でください!」
「ここでひとりなんて、あまりにさびしいわ!」と、アリス。悲しそう
に。大つぶのなみだが、2つ、ほおを伝って落ちた。
「そんなに悲しそうにしないで!」と、白の女王は叫んだ。自分の手を
こすり合わせながら。「自信を取り戻しなさい!ここまでの長い道のり
を思い出しなさい!今、何時か考えて?とにかく、なにか考えなさい、
泣かないで!」
アリスは、思わず、笑ってしまった。「そんなこと考えてたら、泣く
ひまないわ!」
「それが、ねらいよ!」と、白の女王。「だれも2つのことを、同時に
考えられない。あなた、お名前は?今、いくつなの?」
「アリスです。7才半。ちょうど」
「『ちょうど』はなくても、信じます。わたしのことを言うと、あと、
5ヶ月と1日で、101才です」
「信じられません!」と、アリス。
「どうして?」と、白の女王。残念そうに。「もう一度、考えなさい。
深く息をしてから、目を閉じて!」
「ムリだわ!」と、アリス。笑いながら。「不可能なことは、信じられ
ません!」
「もっと練習が必要なようね!」と、白の女王。「わたしがアリスくら
いの頃は、毎日30分は練習したわ。朝食の前に、いつも6つの不可能
なことを信じたわ!あら、ショールがまた、はずれそう!」
ブローチがはずれ、ショールは風に乗って、小さな小川の向こうに飛
んでいった。白の女王は、また両手を広げて、ショールを追った。こん
どは、うまくつかんだ。
「つかまえたわ!」と、白の女王。勝ち誇ったように。「また、ショー
ルをつけてくださる、アリス?」
「ご自分でできますわ、陛下!」と、アリス。礼儀正しく。
アリスは、白の女王に続いて、小さな小川を越えた。
「オー、もっとうまく!」と、白の女王。繰り返すうちに、キーキー声
になった。「もっとうまく!もっとうまく!もっとうまく!もっとうま
く!」そしてついに、ヒツジのメェーと鳴く声になった。
白の女王は、羊毛のようなものに包まれて、輪郭がぼやけた。
◇
「どうなったの?」と、アリス。目をこすった。「なにが起こったのか
分からない!ここはお店の中だわ。向かいに座っているのは、ヒツジ!」
アリスは、小さな薄暗い店で、カウンターにひじをついて、座ってい
た。年とったヒツジは、ひじ掛けイスに座って、大きなめがねで編み物
をしていた。
「なにを買いたいの?」と、ヒツジ。一瞬、編み物から目を上げて。
「さぁ、分かりません」と、アリス。やさしく。「買うなら、その前に
すべて見たいわ!」
「正面から見てるわ!」と、ヒツジ。「両方から見たいなら、どうぞ!
でも、まわりのものすべて同時には見れないわ、頭のうしろに目がない
かぎり!」
アリスは、店の中のいろんな棚を見てまわった。
店は、おもしろそうなものでいっぱいだった。アリスがもっとよく見
ようと、棚に近づくと、そこにはなにもなくなった。ほかの棚は、入り
きれないほど、いっぱいだった。
「ものが、流れていったわ!」と、アリス。ふつうの声で。1分間見て
まわった。大きくてよさそうなものがあって、近づくと、みんななくな
ってしまった。あるときは、それは人形であったり、飾り箱であったり
した。
「なぜかよく分からないけど」と、アリス。突然、思いついた。「みん
な、一番上の棚へ上がっていってしまう!そして天井づたいに別の場所
へ逃げてゆくんだわ!」
「あなたは」と、ヒツジ。別のペアの編み針を手にしながら。「人間の
子ども?それとも、ティートゥタムのこま?目がまわるから、そんなに、
ぐるぐる回らないで!」ヒツジは、14のペアの編み針を同時に使って
いた。
「どうやったら、あんなに多くの編み針を使えるのかしら?」と、アリ
ス。自分に。「だんだん、ヤマアラシのようになってるわ!」
「ボートをこげる?」と、ヒツジ。2本の編み針を使いながら。
「ええ、すこしなら」と、アリス。「でも、陸の上ではだめ!編み針で
もだめ!」
◇
そのとき、編み針がオールになって、アリスはつかんでいた。ふたり
は、小さなボートの上で、岸と岸のあいだをすべっていた。
「羽!」と、ヒツジ。別のペアの編み針を手にしながら。
アリスは、なんのことか分からず、黙ってオールをこいでいた。
「なにか、水の中がおかしいわ!」と、アリス。自分に。「オールが水
より早く動く!」
「羽!羽!」と、ヒツジ。さらに、別のペアの編み針を手にしながら。
「カニを直接手でつかめるわ!」
「カニさん!」と、アリス。自分に。「小さなカニは、好きだわ!」
「『羽』と言ったのが、聞こえなかったの?」と、ヒツジ。怒って。多
くの編み針を手にしながら。
「聞こえたわ!」と、アリス。「なんども、大声で、そう言っていた。
カニはどこ?」
「もちろん、水中よ!」と、ヒツジ。手に持てない編み針を、髪にさし
た。「羽と言ってるのよ!」
「なぜ、羽と言うの?」と、アリス。イライラして。「わたしは、鳥じ
ゃない!」
「あなたは鳥よ!」と、ヒツジ。「小さなガチョウよ!」
アリスは、すこし傷ついて、1・2分、口をきかなかった。ボートは
静かにすべり、あるときは、岸辺の草のあいだを抜けた。(オールは、
水よりも、前よりもっと早く動いた)あるときは、木々の下を、しかし、
いつも川岸は高く、しかめっつらしたふたりの頭の上を過ぎた。
「ああ、なんていい香りの草かしら!」と、アリス。突然、喜んで。
「とても美しい!」
「プリーズなんて、わたしに付けることないよ!」と、ヒツジ。編み物
から目を上げずに。「そんなもの、わたしゃ、付けもしないし取り去り
もしない!」
「そういう意味じゃなくて」と、アリス。言い訳するように。「すこし
待って、香りを味わってみて!ボートをとめてくださる?」
「ボートをとめろって?」と、ヒツジ。「あなたがこぐのをやめれば、
とまるよ!」
ボートは、アリスがこぐのをやめると、流れのままに岸辺の草のあい
だに、静かに流れついた。アリスは、腕まくりをして水の中に、ひじま
で手を入れて、折ってしまう前に、香りのいい草をさわって、ゆっくり
ながめた。しばらくのあいだ、ヒツジや編み物のことを忘れて、ボート
の片側に体をあずけ、もつれた髪を水に濡らしながら、ひとつかみごと
に、いい香りの草を熱心に見ていた。
「ボートが酔ってしまわないようにしないと!」と、アリス。自分に。
「ああ、なんて、美しいの!でも、手が届かない!(まるで、誰かがわ
ざとしているように)美しい草をつかもうとすると、ボートがすべって
いって、つかめない!」
アリスは、ため息をついた。
「一番きれいなものは、決して、つかめないんだわ!」
アリスが、つみ始めた瞬間、香りや美しさといっしょに草は消え始め
た。夢の草は、雪のように、消え去った。
アリスは、このことに気づかなかった。もっとおかしなことが、たく
さんあった。オールは、やはり、水より早く動いて、水から出てこなか
った。(あとで、アリスがそう表現した)オールはアリスのあごにあた
って、シートをすべったあと、草地に落ちた。
「オー!オー!オー!」と、アリス。しかし、ケガはなく、すぐに起き
上がった。
ヒツジは、そのあいだずっと、なにごともなかったように、編み物を
していた。
「いいカニが取れたわね!」と、ヒツジ。
「え?カニが?」と、アリス。ボートから暗い水の中をのぞきこんだ。
「逃げてしまったのかも。そんな小さなカニを持って帰りたい!」
ヒツジは、見くだすように笑って、編み物を続けた。
◇
「ここには、カニがたくさん?」と、アリス。
「いろんなカニがあるよ」と、ヒツジ。「決めたかい?どれを買う?」
「買う?」と、アリス。驚いて。
オールもボートも川も、一瞬で消え、小さな暗い店に戻った。
「タマゴはあるかしら?」と、アリス。おどおどと。
「1つ5ペンス、2つで2ペンス」と、ヒツジ。
「2つが1つより、安いの?」と、アリス。驚きながら、財布を出した。
「2つ買ったら、2つとも食べること!」と、ヒツジ。
「それなら、1つください!」と、アリス。財布から代金を出して、カ
ウンターに置いた。「2つだと、1つはたいてい悪いのよ!」と、アリ
スは考えた。
「買ったものは、お客が自分で取るんだよ!」と、ヒツジ。代金を箱に
入れながら。
ヒツジは、店の奥へ行くと、タマゴを棚の右上に置いた。
「なぜ、そんなことを?」と、アリス。暗い店の中を、イスやテーブル
をよけながら、店の奥へ進んだ。
「タマゴは、近づくと、さらに、遠くへ行ってしまう!これは、イスか
しら?なぜ、こんなところに別れ道が?木も!小さな小川も!こんなお
かしな店は、見たことないわ!」
とまどいながら歩いてゆくと、すべてがとけて、1本の木になった。
「タマゴも消えたはず!」と、アリス。
6
しかし、タマゴは、どんどん大きくなって、人間になった。
アリスは、数ヤードのところから、見ていた。目ができ、鼻ができ、
口ができた。
「ハンプティダンプティだわ!」と、アリス。近づいて見た。「それ以
外のなにものでもないわ!顔に名前が書いてあるようなものよ!」
大きな顔は、100回でも簡単に描けた。
ハンプティダンプティは、トルコ人のように足を組んで、高い壁の上
に座っていた。
「あんな狭い壁の上で、どうやってバランスを取ってるのかしら?」と、
アリス。「目は反対に向いて、ちっともこっちを気にしてない!たぶん、
ただの人形よ!それにしても、タマゴにそっくりだわ!」手を広げて、
受け止めようとした。
「タマゴと呼んだら、おこるよ!」と、ハンプティダンプティ。
「タマゴのようだと言っただけです!」と、アリス。礼儀正しく。「そ
れに、タマゴはかわいいですし!」
「人間は、たまに」と、ハンプティダンプティ。「赤ちゃんと同じレベ
ルのことしか言わない!」
「どういう意味かしら?」と、アリス。自分に。「たぶん、木にしゃべ
ってるんだわ!」
アリスは、立ったまま静かに、詩を声に出して読んだ。
「ハンプティダンプティは 壁の上に 座ってた
ハンプティダンプティは 音をたてて 落っこちた
王の馬 王の兵士 みんなで力を合わせても
ハンプティダンプティを 壁の上に 戻せなかった」
アリスは、言い足した。「最後の1行は、詩にしては長すぎ!」ハン
プティダンプティが聞いてることも忘れて、大声で。
「そんなふうに、自分にしゃべったりしないで!」と、ハンプティダン
プティ。初めて、アリスの方を見た。「名前と職業は?」
「アリスです、あと」
「なんて変な名前!」と、ハンプティダンプティ。がまんできずに。
「どういう意味?」
「名前に意味が必要?」と、アリス。疑わしそうに。
「もちろん!」と、ハンプティダンプティ。笑いながら。「ぼくの名前
は、形をあらわしてる!ハンサムでいい形!アリスも、リスかなんかの
形じゃない?」
「なぜいつも、ひとりでここに?」と、アリス。話題を変えた。
「ほかにだれもいないからさ!」と、ハンプティダンプティ。「答えら
れないと思った?別の質問は?」
「地面にいる方が、安全じゃない?」と、アリス。ほかの謎を思いつか
なかった。しかし、アリスのやさしさから、ハンプティダンプティが心
配だった。
「なんという簡単な謎!」と、ハンプティダンプティ。「もちろん、そ
うは思わない。なぜなら、もしも落ちなかったら、そのチャンスがなか
ったということだし、もしも落ちたら」ここで、口をつぐんだ。そして、
今にも笑い出しそうになっているアリスを、冷たい目で見て、続けた。
「もしも落ちたら、王が約束したんだ。これから言うことが分かってな
いよね?王が約束したんだ、王の口に誓って」
「王の馬と王の兵士、すべてを送る」と、アリス。賢くなさそうに。
「ひどいじゃないか!」と、ハンプティダンプティ。怒りがこみあげて、
叫んだ。「盗み聞きしてたんだな!ドアのうしろで、木に隠れて、エン
トツの下で。そうでなければ、知ってるはずがない!」
「そんなことしてないわ!」と、アリス。「本にあるのよ!」
「へぇ〜、そうか、きみたちが書きそうなことだ」と、ハンプティダン
プティ。静かに。「イングランドの歴史とかいうものだろ?よく見てく
れ!ぼくが、王と話した本人さ。そんな人、ほかにいないよ!ちっとも
自慢じゃない。握手するかい?」耳から耳に歯を出して笑うと、(壁か
ら落ちそうになるまで)前のめりになって、アリスに手を差し出した。
アリスは、手を取るとき、心配そうにハンプティダンプティを見た。
「笑うと口が、頭のうしろまで裂けそうだわ!」と、アリスは考えた。
「頭のうしろでは、どうなっているのか心配!」
「さて」と、ハンプティダンプティ。「王の馬と王の兵士が、すぐにぼ
くを壁の上に戻してくれた。でも、これは先を、急ぎすぎ!前の会話に
戻ろう!」
◇
「なんだったか全く覚えてない!」と、アリス。礼儀正しく。
「もう一度、最初から始めよう!」と、ハンプティダンプティ。「ぼく
が質問する番だ!」
(「まるで」と、アリスは考えた。「ゲームのように話してる!」)
「きみに質問、年はいくつだったの?」
「7才と6ヶ月」と、アリス。しばらく計算してから。
「違う!」と、ハンプティダンプティ。勝ち誇ったように。「言葉の使
い方が違う!」
「年はいくつ?という意味かと思ったのよ!」と、アリス。
「もしそうなら、そう言ったさ!」と、ハンプティダンプティ。
アリスは、わけが分からず、黙っていた。
「7才と6ヶ月」と、ハンプティダンプティ。繰り返した。「切りの悪
い年だ!ぼくの助言を求めていれば、『7才だけでいい』と教えたが、
もう遅い!」
「大きくなるのに、あなたの助言は要らない!」と、アリス。怒って。
「えばりすぎ?」
「わたしが言いたいのは、だれでも大人になるのをとめられないという
こと」
「ひとりならね」と、ハンプティダンプティ。「でも、ふたりなら、い
い助言をすれば、7才でとめられた!」
「とてもいいベルトをしてるのね!」と、アリス。
(「年のことは、もう、たくさん!」と、アリスは考えた。「わたしが
話題を変える番だわ!」)
「つまり、ベルトでないなら」と、アリス。あたふたしながら言い足し
た。「いいネクタイを!」
(「あ、この話題はよくなかった!」と、アリスは考えた。「どこが首
で、どこからがウエストなのか分からない!」)
ハンプティダンプティは、怒って、1・2分、口をきかなかった。
「そのことは、ふれてはいけない話題だった!」と、ハンプティダンプ
ティ。低い声で。「ネクタイとベルトの区別もできない場合は、特に!」
「失礼をお許しください!」と、アリス。なだめるように。
「これは、ネクタイだよ!」と、ハンプティダンプティ。「いいネクタ
イだろ?近くにいる、白の王と白の女王からのプレゼントだよ!」
「そうなの?」と、アリス。結局、いい話題だったことに、ホッとした。
「ぼくに、くれたんだ」と、ハンプティダンプティ。左ヒザを右ヒザの
上にのせて、手をたたいた。「アンバースデイプレゼントとして!」
「なんて?」と、アリス。聞きなおした。
「怒ってないよ!」と、ハンプティダンプティ。
「つまり、アンバースデイプレゼントってなに?」
「もちろん、誕生日以外の日にもらうプレゼントさ!」
アリスは、しばらく考えた。「わたしは、バースデイプレゼントが一
番好き!」
「きみは、なにを言ってるのか、自分で分かってない!」と、ハンプテ
ィダンプティは叫んだ。「1年は、なん日ある?」
「365日」と、アリス。
「誕生日は?」
「1日」
「365引く1は?」
「364よ、もちろん!」
ハンプティダンプティは、疑わしそうに、アリスを見た。「紙の上の
計算を見たい!」
アリスは、笑いを浮かべながらメモ帳を取り出して、検算式を書いた。
ハンプティダンプティは、注意深く、アリスの書いた検算式を調べた。
「正しいように見える!」
「紙を逆に見てるわ!」と、アリス。
「たしかに!」と、ハンプティダンプティ。
アリスは、見やすいように、メモ帳をひっくり返した。
「どこかおかしいように見える。正しいようにも見える。よく調べて見
る時間はないが、きみがアンバースデイプレゼントを受けとれる日は、
364日あるようだ」
「ええ」と、アリス。
「そして、バースデイプレゼントを受けれる日は、1日だけ!これは、
きみの栄光だ!」
「栄光って?」と、アリス。
ハンプティダンプティは、見下すように笑った。「ぼくが言うまで、
きみは受け取れないということ。つまり、ナイスオッケーさ!」
「栄光はナイスオッケーという意味じゃない」と、アリス。
「ぼくが言葉を使うのは」と、ハンプティダンプティ。見下すように。
「それが意味するからさ!それ以上でもそれ以下でもない!」
「問題なのは」と、アリス。「言葉がいろいろな意味をもつこと!」
「問題は」と、ハンプティダンプティ。「どの意味がメインかというこ
と!それだけさ!」
◇
アリスは、わけが分からず、しばらく、口がきけなかった。
「言葉には、それぞれ性質がある」と、ハンプティダンプティ。しばら
くしてから。「特に、動詞は、一番えばっている。形容詞は、動詞には
できないことでも、力を貸してくれる。しかし、ぼくは、ほとんどの言
葉を使いこなせる。つまり、不可入性ということさ!」
「なんなの、それ?」と、アリス。
「頭が良さそうにしゃべるね!」と、ハンプティダンプティ。うれしそ
うに。「不可入性の意味は、もの事がよく分かるということ、きみがつ
ぎに話そうとすることや、きみのその後の人生で2度と使わないことに
した意味も含めて!」
「1つの言葉が、ずいぶん多くの意味をもってるのね!」と、アリス。
「そんなふうに、ある言葉にいろいろな意味をもたせる場合は、特別に
なにかを払う!」
「オー!」と、アリス。よく分からず、言葉が出てこなかった。
「土曜の夜に、見に来るといい!」と、ハンプティダンプティ。自信に
満ちて、頭を左右に振りながら。「言葉の使い方が分かる!」
(アリスは、なにを払うのか訊かなかった。それで、作者もなにを払う
のか伝えられない)
◇
「とても言葉に詳しそうね!」と、アリス。「ジャバウォックという詩
の意味を教えてくださる?」
「聞かせてくれる?」と、ハンプティダンプティ。「ぼくは、今まで書
かれた詩すべてを説明できる。まだ書かれてない詩のほとんどもね!」
「期待できそう!」と、アリス。メモ帳を見ながら、最初の1節を声に
出して読んだ。
「夕暮れに トーブたちは
芝生に 穴をあける
かわいそうなのは ボロゴフ鳥と
ラースたち ふるさとを想う」
「最初のとこだけで、じゅうぶん!」と、ハンプティダンプティ。「難
しい言葉が多いね。ブリリグというのは、午後4時ごろ、夕食用の煮炊
きを始める時刻」
「そう、そんなかんじ!」と、アリス。「スライティは?」
「スライティは、しなやかで泥だらけのこと。2つの違う意味を1つの
言葉にしている合成語さ!」
「そうね」と、アリス。「トーブは?」
「トーブは、アナグマやトカゲに似た、コルク栓抜きみたいな生きもの
さ!」
「きっと、おかしな見た目ね!」
「そうだね」と、ハンプティダンプティ。「日時計の下に巣を作って、
チーズに住んでる!」
「ジャイやギンブルは?」
「ジャイは、ジャイロスコープのようにまわること、ギンブルは、きり
のように穴をあけること」
「ウェイブは、日時計のまわりの芝生のことね?」と、アリス。自分に
感心しながら。
「そのとおり!ウェイブと呼ばれるのは、前も後ろも長く続いているか
ら!」
「両側にもね!」と、アリス。
「そう!ミムジーは、もろくて哀れなこと(もうひとつの合成語)。ボ
ロゴフ鳥は、羽をそば立てて、使い古したモップのような鳥のこと」
「モムラースは?」と、アリス。「たいへんでしょうけど」
「ラースは、緑のブタ。モムは、分からない。たぶん、フロムホームで、
ふるさとを離れて、道に迷っていることだと思う」
「アウトグレーブの意味は?」
「アウトグライビングは、うなり声と口笛の中間くらいで、あいだに、
くしゃみがはさまる声のこと。そのような声は、むこうの森へ行ったら、
耳にすると思う。一度聞いただけで、たくさんさ!そんな難しい詩を、
だれがきみに?」
「本の中で!」と、アリス。「ほかの詩は、もっとやさしかったわ。特
に、テュデュルディのは!」
◇

「詩なら」と、ハンプティダンプティ。左手をのばして、のびをしなが
ら。「民謡以外でも読める、さしつかえなければ」
「そのような必要はとくに」と、アリス。あわてて。始めないでほしい
と思いながら。
「これから読む詩は」と、ハンプティダンプティ。アリスの言うことは、
気にもせず。「きみを楽しませるため!」
「この場合」と、アリス。自分に。「おとなしく聞くしかなさそうね」
アリスは、座った。「どうぞ」と、アリス。悲しそうに。
「冬 野原が白に
あなたのために 歌う
実際には、歌わないけど」と、ハンプティダンプティ。
「そうね」と、アリス。
「ぼくが歌ってるのかそうでないか、するどい目で見てるね!」と、ハ
ンプティダンプティ。皮肉っぽく。アリスは、なにも言わなかった。
「春 木々は緑に
なにか言おうとして 口をひらく」
「いいわね」と、アリス。
「夏 日は長く
歌の意味を 理解し始める
秋 木々の葉は茶に
ペンとインクで 書き記そう」
「ずっと覚えてると思う!」と、アリス。
「そんなコメントは必要ない!」と、ハンプティダンプティ。「感覚的
でもないし、イライラさせる!」
「魚にメッセージ
『ぼくの望むもの』
海の小さな魚たち
メッセージを返した
それは『ぼくたちには
どうしようもない なぜなら』
「ぜんぜん、ピンと来ないわ!」と、アリス。
「先を聞けば、もっと分かる!」と、ハンプティダンプティ。
「また 魚にメッセージ
『従えば 楽になる』
ニヤリとして メッセージを返した
『どういう意味?』
1度 2度も 魚にメッセージ
まったく 聞いてくれない
大きくて新しいやかんを 用意した
これからやることに ふさわしい
胸がハラハラ ドキドキ
やかんを ポンプに
メッセンジャーが来て 言った
『小さな魚たちは もうベッド』
ぼくは メッセンジャーに
『小さな魚たちを また 起こして!』
大声で はっきりと
メッセンジャーの耳元で 叫んだ」
ハンプティダンプティは、悲鳴のような大声で、ここを繰り返した。
「メッセンジャーには、絶対なりたくない!」と、アリスは考えた。ぞ
っとして。
メッセンジャーは、動じず 言った
『そんな大声を出す必要はない!』
さらに、がんこに 言った
『私が 小さな魚たちを起こす もしも』
棚のコルク栓抜きを 手にしたら
小さな魚たちを起こしに 行く
ドアに カギがかかっていたら
引いて押して蹴って カギをあける
ドアが しまっていたら
ノブをまわす しかし
長い中断。
「それで、終わり?」と、アリス。おどおどと。
「終わり」と、ハンプティダンプティ。「さよなら」
「ふいに、終わったわ!」と、アリス。「わたしに行けという、意味が
あったようね!これ以上ここにいたら、失礼になる!」
アリスは、立ち上がって、手を差し出した。
「さようなら、また会う日まで!」と、アリス。できるだけ、陽気に。
◇
「また会っても、覚えていないと思う」と、ハンプティダンプティ。不
機嫌そうに。指1本だけ出して、握手した。「きみは、ほかの人間とま
ったく同じだ」
「そうね、顔の作りは、同じかも」と、アリス。
「そこが不満な点さ!」と、ハンプティダンプティ。「顔はみんなと同
じ。ふたつの目に、(親指で空中に顔を描きながら)鼻は真ん中、口は
下。みんな、同じ。もしも、2つの目が同じ側にあれば、あるいは、口
が一番上なら、少しはまし」
「きれいとは言えないわ!」と、アリス。
「きみが疲れるまで、待とう!」と、ハンプティダンプティ。目を閉じ
た。
アリスは、相手が口をひらくのをしばらく待った。しかし、ハンプテ
ィダンプティは目をひらかなかった。
「さようなら!」と、アリス。また、別れを告げて、歩き出した。
「そこが不満な点さ!」と、アリス。
(ハンプティダンプティの声音をまねて、歩きながら大声で繰り返した)
「そこが不満な点さ!今まで会った人間の!」
そのとき、森を駆け抜ける大勢の足音が響いてきて、アリスはしゃべ
るのをやめた。
7
兵士たちが、森を駆け抜けた。最初2人づつ、つぎに3人づつだった。
それから、10人20人がいっしょに現われ、やがて、兵士の大群が、
森全体をおおいつくした。
「こんなにたくさんの兵隊を、今まで見たことないわ!」と、アリス。
踏まれないように、木のかげに隠れて、通り過ぎるのを待った。
進む方向は、みんなバラバラで、ひとりが倒れると、いつも数人に踏
みつけられ、すぐに地面は、兵士たちの靴あとでいっぱいになった。
つぎに、馬に乗った騎兵隊がやってきた。騎兵隊は、徒歩の兵士たち
より、落ち着いていた。しかし、よく馬がつまづいた。馬がつまづくと、
決まりごとのように、乗っている者はすぐ落ちた。
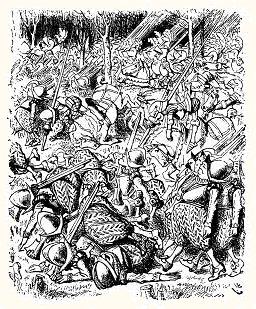
混乱ぐあいは、ますますひどくなったので、アリスは、森を逃げ出し
て、広々とした場所に出た。
「あら、白の王だわ!」と、アリス。「地面に座って、メモ帳をつけて
る!」
「わしの兵士を、全員、進軍させた!」と、白の王。うれしそうに。そ
して、アリスに。「森を通って来たときに、兵士たちに会ったかね?」
「ええ」と、アリス。「数千人は、いました」
「4207じゃ、正確には」と、白の王。メモ帳を見ながら。「馬は、
すべてではない。2頭は、チェスに必要なのでな。2名のメッセンジャ
ーも、まだじゃ。ふたりとも、町へ行っておるのでな。道に見えるはず
じゃ。だれか見えるかい?」
「いいえ、だれも見えません」と、アリス。
「遠くを見えるような目がほしいものだ!」と、白の王。不満そうに。
「だれもいなくても見えたり、すごく遠くが見えたり!なぜ、わしには、
この光で、本物の人間しか見えないのじゃろ?」
アリスは、左手をかざしながら、道を見ていたので、白の王の言うこ
とは聞いてなかった。
「だれか見えます!」と、アリス。「しかし、すごくゆっくり歩いてい
て、おかしな動きをしてる!」
(メッセンジャーは、スキップしながら飛び跳ねたり、うなぎのように
のたうったり、手を大きく広げたりした)
「まったく!」と、白の王。「あのメッセンジャーは、アングロサクソ
ンじゃ。そのしぐさは、アングロサクソン固有のものじゃ。楽しいとき
に、そうする。名前は、ハイヤじゃ」(白の王は、メイヤというような
発音をした)
「ハ行の言葉が好き!」と、アリス。つい、ハ行遊びの歌を始めた。
「彼は、ハッピーだから。でも、嫌いなのは、彼がハサンしたから。彼
を食べちゃった。ハ、ハ、ハムサンドにして。ヘイ!彼の名前は、ハイ
ヤ。住んでるとこは」
「ハイランド」と、白の王。歌に加わる気もなく。「もうひとりは、ハ
ッタじゃ。ふたり必要なのは、行きと帰りだからじゃ」
「どういう意味です?」
「お願いすることでもない」と、白の王。
「つまり、分からないのは」と、アリス。「なぜ、ひとりで、往復しな
いんです?」
「言わなかったかの?」と、白の王。「ふたり必要じゃ。メッセージを
届けるものと、返信を持ち帰るものの、ふたりじゃ」
◇
そのとき、ハイヤが着いた。ハーハー息をして、ひと言もしゃべれず、
手を振って、ひどく驚く表情を、白の王に向けるばかりだった。
「ここにいるアリスは」と、白の王。自分から注意をそらそうとして、
アリスを紹介した。「きみがとても好きだそうだ、ハ行で始まる名前な
のでな!」
しかし、まったく効果なく、アングロサクソンの表情はさらにおそろ
しくなって、目をギョロつかせて、左右に動かした。
「驚かせないでくれ!」と、白の王。「気を失いそうじゃ!ハムサンド
が食べたい!」
「まぁ、ほんとうにハムサンドだわ!」と、アリス。驚いて。
ハイヤは、首にかけたバッグをあけて、白の王にハムサンドを差し出
した。白の王は、がつがつと食べた。
「ハムサンドのおかわり!」と、白の王。
「もう、干草以外ありません」と、ハイヤ。カバンを見ながら。
「それなら、干草を!」と、白の王。かすかな、ささやく声で。
「あら、干草を食べて元気になったわ!」と、アリス。うれしそうに。
「気を失いそうなときは、干草に限る」と、白の王。むしゃむしゃ食べ
切った。
「冷たい水も」と、アリス。「あるいは、気付け薬とか!」
「よいものとは、言ってない!」と、白の王。「限ると言ったのじゃ!」
アリスは、あえて、言い返さなかった。
「道で、だれかに会ったかい?」と、白の王。ハイヤに、干草のおかわ
りをしながら。
「だれも」と、ハイヤ。
「そうか」と、白の王。「アリスは、だれか見たそうだ。だれも、きみ
よりゆっくり歩くことはできないのに!」
「ベストを尽くしてます!」と、ハイヤ。むっとして。「私よりはやく
歩く者はいませんでした」
「もしもいたら、そいつが先に着いておる!」と、白の王。「もう、ひ
と息ついただろうから、町でなにがあったか話してくれ!」
「耳うちします」と、ハイヤ。手を口にあてトランペットの形にして、
かがんだ。
「ニュースを聞きたかったのに」と、アリスは考えた。「がっかりだわ
!」
「あいつらは、また、戦ってます!」と、ハイヤ。ささやく代わりに、
大声で。
「それが、耳うちか!」と、白の王は叫んだ。飛び上がり、身を震わせ
た。「今度やったら、バターをぬるぞ!頭がジンジンして、地震のよう
だ!」
「ずいぶん小さな地震!」と、アリスは考えた。そして、あえて質問し
た。「だれが戦いを?」
「ライオンとユニコーンじゃ、もちろん!」と、白の王。
「王冠のために?」
「ああ」と、白の王。「ずっと、わしの王冠じゃ!みんなで見にゆこう
!」
3人は走りだした。走っているあいだ、アリスは古い詩を口にしてい
た。
「ライオンとユニコーン 王冠のために戦った
ライオンは ユニコーンを町じゅうでたたいた
だれかが白のパンを だれかが茶のパンを
だれかがプラムケーキをあげて 町から追い出した」
「だれかが、王冠を?」と、アリス。ハーハー息をして走りながら。
「いいや、だれも」と、白の王。「それは、ありえん!」
「できれば」と、アリス。「1分、休んでも?」
「わしは大丈夫じゃ」と、白の王。「強くはないがの。それに、1分は
すぐたってしまう!バンダースナッチを止めようとするようなものだ!」
「もう、息が切れて、走りながらしゃべれない!」と、アリス。3人は、
黙って走った。「あの人だかりは」と、アリス。「ライオンとユニコー
ンが戦っているところだわ!巻き上がるほこりで、どっちがどっちなの
か分からない!」
しかし、近づくと、ユニコーンの角が見えるようになった。
◇
3人は、もうひとりのメッセンジャーのハッタが戦いを見ているとこ
ろに来た。ハッタは、左手に紅茶を入れたカップ、右手にバターをぬっ
たパンを持っていた。
「ハッタは」と、ハイヤ。アリスに。「牢屋から出たばかりで、牢屋に
入る前に、午後のお茶をすませてなかったのさ!牢屋には、カキの貝殻
しかなかったので、お腹がすいてのどもかわいたんだ。ハ〜イ、ハッタ!
元気かい!」
ハッタは、まわりを見回して、うなづいた。
「牢屋はどうだった?」と、ハイヤ。
ハッタは、また、まわりを見回した。大つぶのなみだが、2つ、ほお
を伝って落ちた。なにも言わなかった。
「しゃべれないのかい?」と、ハイヤ。大声で。しかし、ハッタは、パ
ンをかじって紅茶をひと口飲んだだけだった。
「ハッタ!」と、白の王。「戦いは、どうだったのじゃ?」
「いい戦いです」と、ハッタ。必死な声で。「ふたりとも、87回ずつ
ダウンしてます」
「それなら」と、アリス。「すぐに白のパンと茶のパンが、運ばれてく
るはず!」
「今は」と、ハッタ。「パンを待っているところです!私が食べている
のは、その一部です」
そのとき、戦いは、ひと休みに入った。ライオンとユニコーンは、座
った。
「10分間、休み!」と、白の王。
ハイヤとハッタは、すぐに、白のパンと茶のパンのトレイを運んでき
た。
「パサパサだわ!」と、アリス。すこしかじってみた。
「ふたりは」と、白の王。ハッタに。「きょうは、もう戦えそうもない!
ドラムをたたけ!」
ハッタは、バッタのように飛び上がった。
1・2分、アリスは、ハッタを見ていた。
「見て、見て!」と、アリス。熱心に指さした。「白の女王が、領域を
横切って、走ってくる!あそこの森を飛び越えたわ!女王って、なんて
速いんでしょう!」
「敵に追われておるのじゃ、間違いない!」と、白の王。「あの森は、
敵でいっぱいじゃ!」
「白の女王を助けに、行かれないんですか?」と、アリス。白の王の冷
静さに驚きながら。
「ムダじゃ、ムダじゃ!」と、白の王。「白の女王は、おそろしく速い!
バンダースナッチをつかまえるようなものじゃ!一応、メモは取ろう!
彼女は、すばらしいイキモノ」メモ帳に書きながら。「『イキモノ』の
イは、2つ?」
◇
このとき、ユニコーンは、両手をポケットに入れて、みんなと散歩し
ていた。
「ぼくは、できるだけのことはしましたよね?」と、ユニコーン。白の
王に。じっと見ながら。
「まぁ、多少は!」と、白の王。イライラしながら。「相手に、角を向
けるべきじゃなかった!」
「傷つけてはいません!」と、ユニコーン。そのとき、たまたまアリス
が目に入って、ユニコーンはアリスの前に立った。驚いた顔をして、見
ていた。
「これは、何なんです?」と、ユニコーン。ついに口をひらいた。
「子どもさ!」と、ハイヤ。アリスの前に立って、ユニコーンに紹介し
た。アングロサクソン固有の、おおげさな身ぶりやおおげささな言い回
しで。「ぼくたちも、さっき見つけたんだ。人生なみの大きさで、自然
の倍はある!」
「子どもというのは」と、ユニコーン。「おとぎ話に出てくる、架空の
怪物だとばかり思っていた!生きてるの?」
「しゃべることもできる!」と、ハイヤ。重々しく。
「しゃべってみて、子ども!」と、ユニコーン。夢見るような目で。
アリスは、ずっと口を曲げていたが、ここでは、笑わずにいられなく
なった。
「わたしも」と、アリス。「ユニコーンは、おとぎ話に出てくる、架空
の怪物だとばかり思っていた!生きてるユニコーンを、初めて見た!」
「そう、それじゃ、やっとお互い出会えたわけだから」と、ユニコーン。
「きみがぼくを信じてくれるなら、ぼくもきみを信じよう。これで、お
あいこだ!」
「いいわ、あなたさえ良ければ」と、アリス。
「さて、ご老人!プラムケーキを運んでこよう!」と、ユニコーン。白
の王に。「茶のパンは、いらない!」
「そうだ、そうだ」と、白の王。ハイヤに合図した。「早く!それじゃ、
ない!それは、すべて干草じゃ!」
ハイヤが、カバンから大きなケーキを出して、アリスに預け、さらに、
お皿とケーキナイフを出した。「まぁ」と、アリス。「あんなにたくさ
ん、カバンにどうやって入れたのかしら?手品みたいだわ!」
◇
ライオンが、みんなのところへ来た。ライオンは、疲れて眠そうで、
目が半分閉じかかっていた。
「これは、なんだ!」と、ライオン。大きなベルのようなうつろな低い
声で。だるそうにまばたきして、アリスを見た。
「今ごろ、訊いてる!」と、ユニコーン。大声で。「きみには、分から
ないね!」
「動物?野菜?鉱物?」と、ライオン。ひと言づつ、あくびをしながら。
「おとぎ話に出てくる、架空の怪物さ!」と、ユニコーン。アリスが答
える前に、大声で。
「それで、怪物がプラムケーキを持ってるのか!」と、ライオン。横に
なって、アゴを前足に乗せながら。「ふたりとも座って!」(白の王と
ユニコーンに)「ケーキは、フェアに分けよう!」
白の王は、大きな獣のあいだに座っていて、居心地悪そうだった。し
かし、ほかに場所がなかった。
「こんな王冠のために、なんて戦いをしてたんだ!」と、ユニコーン。
白の王が頭に乗せている、王冠を見上げながら。
「オレは、簡単に勝てた!」と、ライオン。
「そうとも思えない!」と、ユニコーン。
「オレは、おまえを町じゅうでたたいたんだぜ!」と、ライオン。怒っ
て、半分立ち上がりながら。
「町じゅうで?」と、白の王。ふたりをなだめながら。声がすこし震え
ていた。「ずいぶん長い道を!古い橋もあれば、市場もある。古い橋は、
どこから見たら、一番よかった?」
「知らない!」と、ライオン。また、寝そべりながら、うなった。「巻
き上がるほこりで、なにも見えなかった。怪物は、ケーキを切るのに、
いつまでかかるんだ!」
◇
アリスは、小さな小川の川岸に座っていた。お皿のケーキは、すでに、
切り分けていた。
「なんていうこと言うの!」と、アリス。(ライオンが怪物と呼んだこ
とに、腹を立てていた)「ケーキは、もう、切ってあるわ!あとは、み
んなで分けて!」
「ここの領域での、ケーキの扱いがなってない!」と、ユニコーン。
「ここでは、初めに手渡して、あとで、切る!」
「ぜんぜん、意味が分からない!」と、アリス。しかし、素直に立ち上
がって、皿をみんなのところに運んだ。ケーキは、すでに、3つに切り
分けられていた。
「それじゃ、さらに、切ろう!」と、ライオン。
アリスは、空の皿を持って、もとの場所に戻った。手には、ナイフが
あったが、どうしたらいいか分からなかった。
「ぜんぜん、フェアじゃない!」と、ユニコーン。「ライオンに2つ渡
して、ぼくの倍だ!」
「怪物は、いらないようだ」と、ライオン。「ケーキは嫌い?」
アリスが答える前に、ドラムが鳴った。
「ドラムは、どこで鳴ってるのかしら?」と、アリス。「ドラムがうる
さくて、頭にガンガンひびいて、つんぼになりそうだわ!」
アリスは、恐怖を覚えて、走り出し、小さな小川を越えた。
うしろを振り返ると、ライオンとユニコーンが立ち上がったのが見え
た。食事をジャマされて、怒っているようだった。アリスは、かがんで
両手を耳にあて、ドラムの音を聞くまいとした。
「ドラムは、町からじゃなければ、どこから?」と、アリス。
8
ドラムの音は、だんだん小さくなって、まったく聞こえなくなった。
アリスは、注意しながら、顔を上げた。まわりには誰もいなかった。
「もしかしたら、ライオンとユニコーンは夢だったのかも?」と、アリ
ス。「それに、変なアングロサクソンのメッセンジャーも!でも、プラ
ムケーキを切った、お皿は、ちゃんと目の前にある。同じ夢の続きでな
ければ、夢ではなかったんだわ。できれば、夢は、わたしの夢であって
ほしい!赤の王の夢ではなく!別の人の夢に登場するなんて、ごめんだ
わ!」不満そうに。「その人を起こして、何が起こったの?と訊くなん
てまっぴら!」
「アッポー!アッポー!チェック!」と、赤のナイト。大声で。深紅の
よろいに大きなこん棒を持って、馬に乗って走ってきた。「きみは、捕虜
だ!」目の前にくると、馬は急にとまったので、赤のナイトは馬から落
ちた。
「馬に、また、乗れるのかしら?」と、アリス。驚くより、赤のナイト
が心配だった。
赤のナイトは、サドルの上に戻ると、また、繰り返そうとした。「き
みは━━━」
「アッポー!アッポー!チェック!」と、白のナイト。大声で。やはり、
馬に乗って走ってくると、赤のナイトと同じように、馬から落ちた。
白のナイトは、サドルの上に戻ると、ふたりのナイトは、黙ったまま
しばらく互いを見た。
「アリスは、私の捕虜だ!」と、赤のナイト。ついに口をひらいた。
「アリスを助けに来たのさ!」と、白のナイト。
「では、戦うことになるな!」と、赤のナイト。兜を取って、(それは、
馬のサドルに引っ掛けてあって、馬の頭の一部に見えた)かぶった。
「戦いのルールは、分かってるな?」と、白のナイト。同じように、兜を
かぶった。
「もちろん!」と、赤のナイト。
ふたりのナイトは、ドスンドスンと音をたてて、戦いを始めた。アリ
スは、打たれないように、離れた木のかげに隠れて、戦いを見ていた。
「戦いのルールは、何なのかしら?」と、アリス。「1つは、相手を打
ったら、相手は馬から落ち、もしも打ちそこねたら、自分が馬から落ち
るということ!もう1つは、パペットショーのパンチとジュディのよう
に、武器はこん棒を使うということのようだわ!馬から落ちたときの音
といったら、すごい音!まるで、熱した鉄を、いっぺんに、暖炉に落と
したような音だわ!それにしても、馬のおとなしいこと!落ちたり乗っ
たりしても、テーブルのようにおとなしい!」
戦いには、さらに別のルールがあった。それは、頭から落ちるという
こと。ふたりがつぎつぎに落ちて、戦いが終わった。立ち上がると、ふ
たりは握手をした。赤のナイトは、馬に乗り、ギャロップで去った。
「すばらしい勝利だった!」と、白のナイト。荒い息使いから、やっと
回復した。
「さぁ、どうかしら?」と、アリス。「わたしは捕虜にはなりたくない!
白の女王になりたい!」
「つぎの小川を越えたら」と、白のナイト。「白の女王になれる。森を
抜けるまで、送ろう!そのあと、私は戻らなくてはならない。私の役割
は、そこまでなので!」
「それは、どうも」と、アリス。「兜をぬぐのを、手伝いましょうか?」
白のナイトは、自分ではとてもぬげそうになかった。しかし最後には、
白のナイトの頭をゆすってぬがせた。
「これでやっと」と、白のナイト。「楽に息ができるようになった!」
両手でくちゃくちゃの髪をかき上げると、大きな目のすました顔をアリ
スに向けた。
「こんな変なスタイルのナイトは、今まで見たことないわ!」と、アリ
ス。
白のナイトは、体にまったく合ってない錫でできた鎧を着て、肩にか
けたひもに箱を付けていた。箱は、ひっくり返って、半分フタがあいて
いた。
「なんの箱かしら?」と、アリス。
◇
「この箱が気に入ったかい?」と、白のナイト。友達のように。「この
箱は、私が発明したんだ。服やサンドイッチを入れるために。逆にして
るのは、雨が入らないようにするため」
「でも、ものが落ちてしまいそう!」と、アリス。やさしく。「フタが
あいてるのをご存じ?」
「気づかなかった!」と、白のナイト。顔に投げやりな影が走った。
「それじゃ、中のものはすべて落ちてしまった!箱は、なんの役にも立
たない!」
白のナイトは、箱をはずして、茂みに捨てようとした。そのとき、思
いついて、箱を木につるした。
「なぜ、木につるしたか、お分かり?」と、白のナイト。
アリスは、首を振った。
「ハチが巣を作れば、ハチみつが取れるからさ!」
「けれど、あなたのサドルには、すでに、巣箱のようなものがつるされ
てるわ!」と、アリス。
「そう、あれはいい巣箱さ!」と、白のナイト。不満そうに。「もっと
もよくできた巣箱だけど、まだ、ハチが1匹もいない。ねずみ取りでも
あるんだ。ねずみがハチが逃げるのを見張ってるし、ハチもねずみが逃
げるのを見張ってる。どっちがどっちだか分からないけど」
「サドルにねずみ取りって、なんのためなの?」と、アリス。「ねずみ
は、馬の背中にはめったに来ないわ!」
「めったには来ないだろうけど」と、白のナイト。「もしも来たら、逃
がさないためさ!」
白のナイトは、しばらく間をおいた。「そうさ、すべてのことを考え
なきゃならない。それが、この馬の4本の足首にアンクレットが巻かれ
ている理由さ!」
「なんのために?」と、アリス。興味をもって。
「ヘビの攻撃から守るため」と、白のナイト。「私が発明したんだ。さ
て、森のはずれまで、お送りしよう!そのお皿で、なにするの?」
「プラムケーキ用!」と、アリス。
「ふたりで持った方がよさそうだ」と、白のナイト。「運びやすくなる
から、そのバッグに入れよう!」
バッグに入れるのは、長い時間がかかった。
アリスは、注意しながら、バッグをあけていた。それは、白のナイト
のやり方が、とてもユニークで、2・3回は、お皿でなく、白のナイト
がバッグに入ってしまった。
「バッグが狭すぎ!」と、白のナイト。「ろうそくがいっぱいすぎ!」
白のナイトは、バッグをサドルにつるした。すでに、サドルには、にん
じんの束や、炉道具など、いろいろなものが積まれていた。
「髪は、なにかでしばった方がいいよ!」と、白のナイト。出発時に。
「ふつうにしてるだけ!」と、アリス。ほほえみながら。
「まったくダメ!」と、白のナイト。心配そうに。「このあたりは、風
が強い。スープのように!」
「髪が乱れないようにする、なにか発明でもしたの?」と、アリス。
「いや、まだだ」と、白のナイト。「プランはあるけど」
「聞かせてほしい!」
「まず、頭のてっぺんに、上向きの棒が必要。そこに、アリスの髪をか
らませてゆく、果樹園のように。髪が乱れる原因は、下に下がってるか
らさ。上向きなら乱れない!ぼくの発明だけど、まねしてもいいよ!」
「どうもいいアイデアには思えない」と、アリス。口には出さずに、黙
って歩いた。白のナイトを助けるのもやめた。白のナイトは、あまりい
い乗り手とはいえなかった。
馬が止まるたびに、(それは、しょっちゅうだったが)白のナイトは、
前に落ち、馬が歩き出すたびに、(たいていは、急に歩き出した)後ろ
に落ちた。馬が歩いているあいだは、横に落ちる以外は、うまく乗って
いた。横に落ちるのは、たいていは、アリスが歩いている側だった。
◇
「馬からもう少し離れて歩いた方がよさそうね!」と、アリス。「もっ
と、馬に乗る練習をした方がいいわ!」5回目に、馬に乗るのを助けて
いる時に。
「なんだって?」と、白のナイト。サドルによじ上って、逆側に落ちな
いように、アリスの髪をつかんでいた。
「よく練習してれば、そんなにしょっちゅう馬から落ちないわ!」
「練習は、たくさんやった!」と、白のナイト。おごそかに。「たくさ
んね!」
「ほんとうに?」と、アリス。できるだけ、やさしく。
それ以降は、ふたりとも黙って歩いた。白のナイトは、ひとりでブツ
ブツ言っていた。アリスは、つぎに落ちるのを心配しながら。
「馬に乗る1番いい方法は」と、白のナイト。いきなり、大声で、右手
を振りながら。「バランスを」
白のナイトの大声は、始まったときと同じに、いきなり終わった。白
のナイトは、アリスの歩く方をめがけて、頭から落ちた。
「大丈夫?骨は、折れてない?」と、アリス。助けおこしながら。
「しーっ!黙って!」と、白のナイト。2・3本の骨は折れても、気に
しないかのように。「馬に乗る1番いい方法は、バランスを取ることさ!
こんなふうに!」
白のナイトは、また馬に乗って、手綱を引いて、両手をのばした。今
度は、水平のまま後ろに落ちて、馬の足の下になった。
「練習を、たくさん!」と、白のナイト。アリスが助け起こしているあ
いだも、繰り返した。「練習を、たくさん!」
「まったく、どうしようもない!」と、アリス。ついに、がまんの限界
になった。「車輪の付いた木製の馬にでも、乗ったら?」
「それって、スムーズに動くの?」と、白のナイト。興味をもって。白
のナイトは、馬から落ちないように、馬の首にしがみついていた。
「生きてる馬よりはね!」と、アリス。笑いをこらえ切れず、笑い出し
ながら。
「ひとつ買おう!」と、白のナイト。よく考えながら。「1つか2つ。
いや、もっと」
それから、ふたりは、黙って歩いた。
「ぼくには」と、白のナイト。しばらくして、口をひらいた。「発明の
才能があるんだ。さっき馬に乗るのを手伝ってくれているとき、ぼくが
考え事をしてるのに、気づいた?」
「ええ」と、アリス。
「まさにそのとき、ぼくは、門を飛び越える発明をしていたんだ。聞き
たい?」
「ぜひ!」と、アリス。
「発明の過程から話そう!」と、白のナイト。「まず、自分に言った。
『頭は、もともと上にあるから、唯一の困難は、足だ』と。そこで、頭
を門の上に乗せ、これで、頭は門の上にあるから、今度は、頭の上に逆
立ちで立つ。これで、足もじゅうぶん上になって、門は越えられた!」
「そうね」と、アリス。考えながら。「それで、問題解決と思ってるよ
うだけど、それがどれだけたいへんか、考えなかったの?」
「まだ、試してはいないんだ!」と、白のナイト。おごそかに。「それ
で、確かなことは言えないが、すこし難しいかもしれない」
白のナイトは、口に出したことを後悔してるように見えたので、アリ
スは、あわてて話題を変えた。
◇
「珍しい兜ね?」と、アリス。楽しそうに。「あなたの発明?」
「そう」と、白のナイト。サドルにつるされた兜を自慢するように。
「でも、もっといい兜も発明したんだ、シュガーローフみたいな。その
兜は、馬から落ちそうになっても、先に地面に落ちてくれるので、ぼく
は、馬から落ちないですむ。しかし、別の危険もあった。一度、先に落
ちた兜を拾う前に、別の白のナイトが来て、自分の兜だと思って、持っ
ていってしまった」
白のナイトは、そのことがとても残念そうだったので、アリスは、笑
いをこらえた。
「別の白のナイトを、攻撃してないでしょうね?」と、アリス。「頭を
蹴るとか?」
「もちろん、蹴ったさ!」と、白のナイト。真剣に。「そして、兜を取
り戻した。しかし、それには、何時間もかかった。雷のように、急いだ
のだが」
「それは、急いだとは、言わない!」と、アリス。
「ぼくは、ほんとうに急いだんだ」と、白のナイト。頭や手をふってい
たので、溝の中へ、頭から落ちた。
「ひどい落ちかただわ!」と、アリス。「ケガが心配!まっすぐのばし
た足しか見えない!」
「ほんとうに急いだんだ!」と、白のナイト。同じ声のトーンで繰り返
した。「他人の兜をつけて行くのも、どうかと思う!」
「頭が下で」と、アリス。「よく普通にしゃべれるわね!」
アリスは、白のナイトを足から引きずり出して、川岸に寝かせた。
「頭の位置が、しゃべることとなにか関係がある?ぼくは、どんな姿勢
でも普通に考えられる。むしろ、頭が下の方が、いいアイデアが生まれ
る!」
白のナイトは、すこし間をおいた。
「今、すごく頭がさえている!肉料理に合う、新しいプディングを発明
した!」
「つぎのコース料理で披露してちょうだい!」と、アリス。「今は、急
ぎの用があるわ!」
「つぎのコース料理では、だめなんだ」と、白のナイト。ゆっくり考え
ながら。「そう、やはり、だめなんだ」
「それじゃ、そのつぎの日にすれば?1つのコース料理で、2つのプデ
ィングは出せないでしょうから!」
「そのつぎの日も、だめなんだ」と、白のナイト。繰り返した。「ほん
とうに、だめなんだ」声は下がり、頭もますます低くした。「今まで、
作られたことのないプディングなんだ!そして、これから先も、決して、
作られることのない、かしこいプディングなんだ!」
「なにで、できてるの?」と、アリス。落ち込んだ、白のナイトの気持
ちを、盛り上げようとしながら。
「吸取紙」と、白のナイト。うなるように。
「まぁ、ステキだわ!」
「そうでもない!」と、白のナイト。さえぎるように。「ほかのものと
混ぜたらどうなるか?火薬やら、シーリングワックスなんかと。ここで、
お別れだ!」
ふたりは、森のはずれに来た。
「あら」と、アリス。「プディングのことばかり考えていたら、着いて
しまった!」
「元気がなさそうだね?」と、白のナイト。「元気になってほしいから、
詩を歌わせてくれ!」
「長いの?」と、アリス。そして、自分に。「今日は、やたら詩を聞か
される日だわ!」
「ああ」と、白のナイト。「長いが、とても美しい。みんな聞きたがる
し、涙を流す。さもなければ」急に黙った。
「さもなければ?」と、アリス。
「さもなければ、涙を流さない。タイトルは、『ハドックの目』」
「それが、タイトル?」と、アリス。少しでも、興味を持とうとした。
「違う」と、白のナイト。すこしイライラして。「それは、ニックネー
ムで、本当は、『年に年を重ねた男』」
「それが、ニックネームよ!」と、アリス。
「いや、違う!ほかの呼び方もある。『方法と手段』」
「それで、詩はなんなの?」と、アリス。わけが分からなくなったよう
に。
「そうそう」と、白のナイト。「本当は、『門の上に座って』なんだ。
詩のメロディは、ぼくの作曲さ!」
◇
白のナイトは、馬を止めて、手綱を自分の首にかけた。あまり賢そう
でない顔に薄笑いを浮かべ、右手でリズムをとりながら、音楽を楽しむ
かのように、歌い出した。
鏡の家の旅のあいだで、もっとも奇妙なことが、これから始まること
だった。アリスは、そのことをはっきり覚えていて、きのうのことのよ
うに思い出すことができた。白のナイトのブルーの目、やさしそうな笑
い、髪に光る夕陽、アリスを見つめる情熱の炎のような輝き。馬も、リ
ズムに合わせて足元の草を食べていた。背景は、森の大きな影、すべて
が、1枚の絵のようだった。アリスは、木に寄りかかり、右手で夕陽を
さえぎりながら、白のナイトと馬を見ていた。そして、まるで夢の中の
ように、悲しいメロディの歌を聞いていた。
「この曲は、白のナイトが作曲したものじゃないわ!」と、アリス。自
分に。「この曲は、『あなたにすべてを』だわ!」
アリスは、耳をすまして聞いていた。涙は、まったく浮かべなかった。
◇
「あなたにすべてを 話そう
話すことは 多くはない
年に年を重ねた男を 見た
門の上に座ってた
『あなたは 誰?』と わたし
『どうやって 生活を?』
男の言うことは、頭を したたる
ざるの中の 水のように
『チョウチョウを さがした』と 男
『小麦粉の中で 眠ってた
マトンパイにして
通りで 売りに出した
男たちに 売った
海で嵐に合っていた 男たちに
それが、パンを得た方法だ
あるいは トライフルを』
わたしは アイデアを考えていた
ヒゲを グリーンにする
さらにおもしろい トリック
ヒゲが 見えなくなる
それで 男の言ったことを
聞いてなかった
『なにをして 生活してる?』と わたし
男の頭を たたいた
男は甘い声で 話し始めた
『私のやり方がある』と 男
『山に 小川があったら
炎を ともしてみる
それが ローランドのマッカーサー石油
を見つけた やり方
2ペンスと半ペニーが
私の報酬のすべて』
わたしは アイデアを考えていた
人にバターを 食べさせる
毎日 つづけて
だんだん太らせる
それで、男をゆすった
顔が青ざめるまで
『なにをして 生活してる?』と わたし
『なにをしたら そうなれる?』
『ヒースの輝く 草原で』と 男
『ハドックの目を集めた
静かな 夜に
ウェイストコートのボタンにした
それらを 金貨では売らなかった
銀貨でも
しかし、半ペニーの銅貨で売った
それで 9こ売れた
ときどき バターロールパンをさがした
カニをつかまえるために 川に刺した枝に鳥もちを
ときどき 草地の丘をさがした
車で走るために
それが 私のやり方』(ウィンクした)
『それで 金持ちになった
上機嫌で 酒を飲もう
きみの健康のために』
わたしが男の話を聞いたのは
設計図を完成させたとき
メナイ橋を さびから守るために
ワインで煮て
男の話に感謝した
金持ちになった やり方を
男が わたしの健康を
願ってくれたことにも
そして 今 私の指を
ニカワに 入れることがあれば
あるいは 右手を足に
左手を靴に 入れることがあれば
あるいは 足の指に
重いおもりを落とすことがあれば
私は泣くだろう
思い出すのは
年を重ねた男のこと
かつて 知り合いだった
やさしい顔をして
ゆっくりとしゃべり
男の髪は
雪よりも 白
顔は すごく似ている
カラスに
目は リンゴ酒のように赤く
悩みをかかえ
体を前後にゆらして
低い声で ぶつぶつつぶやいた
パンをほおばってるように
バッファローのように いびきを
ずっと昔 夏の夜
門の上に座ってた」
◇
白のナイトは、バラードを歌い終えると、手綱を引いて、馬をUター
ンさせた。
「この先を行って」と、白のナイト。「丘を下り、小川を越えると、白
の女王になれる!ぼくのことを見送ってくれる?」自分が戻ってゆく方
を見ながら。「長くはかからない!ハンカチを振って、見送ってくれれ
ば、勇気100倍さ!」
「もちろん!」と、アリス。「ここまで、送ってくれて助かった。それ
に、歌も、とっても気に入ったわ!」
「どうも」と、白のナイト。「ぼくの期待ほどは、泣いてくれなかった
けど」
白のナイトは、アリスの手を握ると、森の方へゆっくり馬を歩かせた。
「見送りに、長くかからなければいいけど」と、アリス。自分に。「あ
ら、普通に乗ってるわ。まるでベテランのように、スムーズに。でも、
やはり馬から落ちた!今度は、逆側に落ちた!やっと、曲がり角まで行
ったわ!」
アリスは、ハンカチを振り、見えなくなるまで見送った。
「これで、白のナイトは勇気づけられたかしら?」と、アリス。丘を下
った。「最後の小川だわ!これで、白の女王になれる!いい響きだわ!」
小川の手前まで来た。「最後の8マス目!」アリスは叫んで、小川を飛
び越えた。
◇
アリスは、やわらかい芝生に座った。ところどころに花が咲いていた。
「ここまで来れて、嬉しい!頭にあるのは、なにかしら?すごく重いの
に、わたしの頭にピッタリだわ!それにしても、気がつかないうちに、
頭に乗っていた!」ヒザに置いて、よく見ると、分かった。
黄金の王冠だった。
9
「すばらしいわ!」と、アリス。「こんなにすぐ、女王になれるなんて!
ご報告します、陛下!」おごそかに。(自分に)「このような芝生の上
で、だらだらなさるのは、よくありません。女王は、もっと威厳をもつ
べきです!」
アリスは、立ち上がり、歩いた。最初は、王冠が落ちるのではないか
と、ぎこちなく。しかし、誰にも見られてないことが分かると、リラッ
クスできた。
「わたしが女王なら」と、アリス。また、座った。「女王であることを、
利用できる」
奇妙なことが、いつも起こっていたので、アリスのすぐ近くに、赤の
女王と白の女王が並んで座っていても、すこしも驚かなかった。
「なぜ、ふたりがここにいるのか聞きたいけど」と、アリス。自分に。
「聞くのは失礼かもしれない」そして、赤の女王に。「もしもよろしか
ったら」と、アリス。おどおどと。
「はっきり、おっしゃい!なにが聞きたいの?」と、赤の女王。
「もしもなんらかのルールがあって」と、アリス。「女王がしゃべり始
めるまで、みんなが待ってなきゃならないなら、女王は、みんながなに
をしゃべってるのか聞くことができずに」
「意味が分からない!」と、赤の女王は叫んだ。「どうして、あなたは」
顔をしかめた。しばらく考えてから、話題を変えた。「『あなたは、本
当に、女王なの?』と、聞かれたら、どう答えるの?なんの権利があっ
て、自分を女王だと?あなたは、女王ではない!正式な試験をパスする
までは!すぐに、試験を始めた方がいいようね」
「わたしは、聞いてみただけです!」と、アリス。自信なさそうに。
赤の女王は、白の女王と顔を見合わせた。
「アリスは、聞いてみただけだと」と、赤の女王。すこし身震いした。
「いいえ、もっと多くのことを言ってるわ!」と、白の女王。不満そう
に、手を鳴らした。「もっともっと多くのことを!」
「そうよ!」と、赤の女王。アリスに。「本当のことだけしゃべりなさ
い!しゃべる前に、考えて!メモに残しなさい!」
「本当でないことは、しゃべってない!」と、アリス。
「不満なのは、そこよ!」と、赤の女王。さえぎった。「意味すること
が分かってない!子どものおしゃべりと同じ!ジョークでさえ、意味が
あるのに!子どものおしゃべりには、もっと意味がある!どう?否定で
きないでしょ?両手を使っても!」
「否定はしません、両手を使っても」と、アリス。
「だれも、否定したとは言ってない!」と、赤の女王。「わたしが言っ
てるのは、否定しようとしても、否定はできないということ!」
「アリスは」と、白の女王。「否定したいものがなんなのか、分かって
ないのよ!」
「意地悪で、根性が曲がっている!」と、赤の女王。
気まずい沈黙。
「今夜のアリスのディナーパーティに」と、赤の女王。白の女王に。
「あなたをご招待しますわ!」
「わたしも」と、白の女王。小声で。「あなたをご招待しますわ!」
「今夜のディナーパーティって?」と、アリス。「まったく知らないけ
ど、わたしのパーティなら、ご招待は、わたしがするわ!」
「チャンスをあげているのよ!」と、赤の女王。「マナーの授業は、ま
だでしょうから!」
「マナーの授業は、ないわ」と、アリス。「授業は、全般的な概要だけ
ですもの!」
「足し算は?」と、白の女王。「1足す1足す1足す1足す1足す1足
す1足す1足す1足す1は?」
「知らない!」と、アリス。「数えてなかった!」
「足し算もできない!」と、赤の女王。「引き算は?8引く9は?」
「8から9は引けない!」と、アリス。すぐに。「けれど」
「引き算もできない!」と、白の女王。「割り算は?パンをナイフで割
ったら?」
「たぶん」と、アリス。答えようとしたが、赤の女王が先に答えた。
「もちろん、ブレッドアンドバターよ!」と、赤の女王。「ほかの引き
算は、どう?骨をくわえたイヌから骨をとったら、なにが残る?」
「骨は、もちろん、残らない」と、アリス。慎重に。「骨をとったら、
イヌも残らない。イヌはわたしをかんで、わたしも残らない!」
「それじゃ、なにも残らないわけ?」と、赤の女王。
「そう、それが答えだと思う!」
「ブー!」と、赤の女王。「イヌの『われ』が残る!」
「どういうこと?」
「なぜかというと」と、赤の女王。「骨をとられたら、イヌはわれを忘
れてしまうわね?」
「そうね、たぶん」と、アリス。慎重に。
「そして、イヌは、どこかへ行ってしまうから、『われ』が残る!」と、
赤の女王。勝ち誇ったように。
◇
「それは、ちょっと違う話だわ!」と、アリス。できるだけ、おごそか
に。そして、自分に。「なんてナンセンスなおしゃべりをしてるんだろ
う!」
「アリスは、足し算もできない!」と、ふたりの女王。声をそろえて。
「あなたは、足し算は?」と、アリス。白の女王に。人の欠点を見つけ
るのは、あまり好きではなかったが。
「まぁ、少しは」と、白の女王。かたく目を閉じたまま。「時間をくれ
れば。でも、引き算は、できない!時間があっても!」
「あなたは、もちろん」と、赤の女王。アリスに。「自分の名前のスペ
ルは言えるわよね?」
「ええ」と、アリス。
「わたしだって!」と、白の女王。小声で。「声を合わせてだってでき
るし、そっと教えることも。ワードは、みんな大文字なら読めるし。が
っかりしないことね!そのうち、できるようになるわ!」
「つぎの質問!」と、赤の女王。「パンは、なにでできている?」
「もちろん、分かるわ!」と、アリスは叫んだ。「小麦粉と━━━」
「花は、どこでつんだの?」と、白の女王。「庭?それとも、生け垣?」
「いいえ、つんではいないわ!」と、アリス。「地面の上に━━━」
「なんエーカーの地面?」と、白の女王。「説明を省略しすぎ!」
「頭が疲れてるのよ!」と、赤の女王。心配そうに。「考えすぎで」
ふたりの女王は、葉の付いた枝をあおいで、アリスの頭に風を送った。
「もう、十分です!」と、アリス。あおぐのをやめてもらった。
「これで、元気になったわ!」と、赤の女王。「フィデュルディディの
フランス語は?」
「フィデュルディディは、英語でない!」と、アリス。おごそかに。
「誰が言ったの?」と、赤の女王。
アリスは、困難を乗り越える方法を思いついた。そして、勝ち誇った
ように。「もしも、フィデュルディディが何語か教えてくれたら、その
フランス語を教えるわ!」
赤の女王は、もっとかたくなだった。「女王は、いかなる取引もしな
い!」
「女王は、いかなる質問もしないでほしい!」と、アリス。自分に。
「ケンカはやめましょう!」と、白の女王。心配そうに。「稲光の原因
は?」
「稲光の原因は」と、アリス。確信があった。「雷━━━いいえ」あわ
てて、訂正しようとした。「つまり」
「訂正は、もう、遅い!」と、赤の女王。「一度言ったことを、訂正し
たら、問題よ!」
「あ、思い出した!」と、白の女王。下を向いて、神経質そうに。「そ
んな雷雨があった、この前の火曜に━━━つまり、この前のひとつの火
曜に」
「わたしのいた領域では、火曜は、同時に1度だけ!」と、アリス。
「ずいぶん貧しいやり方ね!」と、赤の女王。「ここでは、昼も夜も、
同時に2・3日続く。時には、冬のあいだ、暖かくするために、5つの
夜しかないこともある」
「夜が1つより、5つの方が、暖かいの?」と、アリス。
「もちろん、5倍暖かい!」
「5倍寒いはず!」
「そうよ!」と、赤の女王。「5倍暖かいし、5倍寒い!わたしは、あ
なたより、5倍金持ち!そして、5倍かしこい!」
アリスは、ため息をついて、あきらめた。そして、自分に。「答えの
ないなぞなぞだわ!」
「ハンプティダンプティも分かってたわ!」と、白の女王。低い声で、
自分に言うように。「コルク栓抜きを持って、ドアまで来て」
「なにをしに?」と、赤の女王。
「中へ入ろうとして」と、白の女王。「カバを捜して!そのとき、それ
が起こった!その朝、そのようなものは、なかったのに!」
「なにが、あったの?」と、アリス。驚いて。
「火曜のみに起こる!」と、白の女王。
「ハンプティダンプティが、なにをしようとしてたのか、知ってるわ!」
と、アリス。「魚たちに、おしおきしようとしたのよ!なぜかというと」
◇
「それは、あなたたちが想像もできない、すごい雷雨だった!」と、白
の女王。
(「白の女王には、想像できなかった!」と、赤の女王)
「屋根の一部は吹き飛ばされ、雷が入り込んで、テーブルやいろんなも
のがグルグル舞って、わたしは驚きのあまり、自分の名前も忘れてしま
った!」
「嵐の最中に」と、アリス。自分に。「わたしだったら、自分の名前を
思い出そうとはしない!なんの役にも立たないし」白の女王を傷つけな
いように、大声では言わなかった。
「白の女王に、あやまりなさい、陛下!」と、赤の女王。アリスに。
赤の女王は、白の女王の右手を取って、やさしく差し出した。「悪い
意味でなかったにしろ、アリスが失礼なことを言ってしまったことの、
お詫びに」
白の女王は、おどおどとアリスを見て、なにか言おうとしたが、なに
も思い浮かばなかった。
「アリスは、育ちがよくなかったようね」と、赤の女王。「でも、ビッ
クリするほど、気立てがやさしい!アリスの頭をなでてあげれば、喜ぶ
わ!」
「それは、ご親切に!」と、アリス。勇気づけられて。「白の女王の髪
を、紙に押し当てれば、きっと驚くわ!」
白の女王は、ため息をついてから、頭をアリスの右肩に押し当てた。
「すごく眠い!」と、白の女王。
「あらあら、お疲れだわ!」と、赤の女王。「髪をとかして、ナイトキ
ャップをかぶせたら、子守唄を歌ってあげなさい!」
「ナイトキャップなんて持ってないし」と、アリス。「子守唄も知らな
い!」
「わたしが歌ってあげる!」と、赤の女王。歌い出した。
◇
「アリスのひざの上で お眠り
ごちそうまで 間がある
ごちそうが終わったら みんないっしょに
輪になって 眠ろう」
◇
「まだ、続きがある」と、赤の女王。頭をアリスの左肩に押し当てた。
「わたしにも、歌ってちょうだい!すごく眠い!」
ふたりの女王は、いびきをかいて、眠りに落ちた。
「どうしたらいいの?」と、アリス。すごく困りながら、重い頭をひと
つずつ、ヒザの上に移した。「こんなことって、今まであったかしら?
一度に、ふたりの女王が眠ってしまって、その世話をしなくてはならな
いなんて!イングランドの歴史にも、なかったことよ!一度にひとりし
か女王はいないのだから!重い頭たち、目を覚ましなさい!」
静かな寝息だけで、返事はなかった。
いびきは、だんだん大きくなって、歌のようになり、歌詞さえ聞き取
れそうになった。アリスは、耳をすましていたので、ふたりの女王が消
えてしまったことに、まったく気づかなかった。
◇
アリスは、アーチ型の門の前に立っていた。アーチの上には、大きな
活字で、『女王アリス』と書かれていた。アーチの両側には、ベルのひ
もがあって、右は『お客用』、左は『召使用』と書かれていた。
「歌が終わるまで、待ちましょう!」と、アリス。自分に。「それから、
ベルを鳴らすのだけど、どちらのベルを?」悩みながら。「わたしは、
お客ではないし、召使でもない。女王用のベルは、ないのかしら?」
そのとき、ドアが少しひらいて、長いクチバシの生き物が頭だけ出し
て言った。
「さ来週まで、休み!」
そして、音をたてて、ドアを閉めた。
アリスは、ドアをノックした。ずっとむなしく、ノックを続けた。す
ると、木のところに座っていた、年寄りのカエルが立ち上がり、びっこ
を引いて歩いてきた。明るい黄の服を着て、大きなブーツをはいていた。
「なにか、ご用で?」と、カエル。低いしゃがれ声で。
アリスは、振り返った。「ドアのノックに答える召使は、どこ?」怒
って。
「どのドア?」と、カエル。
アリスは、カエルのゆったりした話し方に、イライラして足を踏み鳴
らしそうだった。「もちろん、このドアよ!」
カエルは、大きなにぶい目でしばらくドアを眺めてから、近寄って、
親指でこすって、ペンキがはがれるかどうか調べた。
「ドアの返事は?」と、カエル。「なにか聞いてきました?」
カエルの声は、しゃがれ声で、よく聞き取れなかった。
「どういう意味?」と、アリス。
「私は、英語でしゃべってますよね?」と、カエル。「それとも、あな
たは耳が不自由?ドアは、なにか聞いてきました?」
「なにも!」と、アリス。「ノックしてただけ!」
「それは、やめた方がいい!」と、カエル。「イラ立たせるだけ!」
カエルは、ドアに近づいて、大きな右足でキックした。
「あとは、そっとしておくだけ!」 カエルは、また、びっこを引いて、
木のところに戻って行った。「そうすれば、あなたもそっとしておいて
もらえる!」
このとき、ドアがバタンとひらいて、かん高い歌声が聞こえてきた。
◇
「ルッグランの領域 しゃべってるのは アリス
『手には笏 あたまに王冠
ルッグランの生き物たち どんな生き物であれ
やって来て 食事をふるまいなさい
赤の女王 白の女王 そしてわたし』」
そして、なん百という声のコーラス。
「グラスにワインを いそいでそそいだら
テーブルには ボタンとブランをまいて
コーヒーにはネコ 紅茶にはネズミ
女王アリスを 歓迎しよう
30かける3!」
そして、喜びの歓声。
「30かける3は」と、アリス。自分に。「90だわ。だれが数えてる
のかしら?」
ふたたび、しばらく沈黙。
そして、前と同じ、かん高い歌声が聞こえてきた。
◇
「『ルッグランの生き物』と アリス
『近くに寄れ!
わたしに会えるのは 名誉だぞ 聞きたいか
夕食や紅茶を いっしょにできるのも 特権じゃ!
赤の女王 白の女王 そしてわたし』」
そして、前と同じ、コーラス。
「グラスに 糖蜜とインクをそそいだら
あるいは 飲んだら喜びそうななんでも
ミックスサンドにサイダー 羊毛にワイン
女王アリスを 歓迎しよう
30かける3!」
「30かける3!」と、アリス。絶望的に繰り返した。「そんなにやっ
てられない!今すぐにでも、中へ入りたいのに!」
アリスは、中へ入った。
◇
広いホールは、アリスが現われた瞬間、死んだように静まりかえった。
アリスは、ゆっくり歩きながら、並んでいるテーブルを眺めた。
「お客が50人はいるわ!」と、アリス。自分に。「動物や鳥、たまに
花まで。招待される前に来てくれて、よかった。誰を招待したらいいか
なんて、知らないもの!」
テーブルの正面に、3つのイスがあった。2つのイスには、赤の女王
と白の女王がすでに座っていた。真ん中のイスがあいていた。
アリスは、真ん中に座った。
「なんという沈黙!」と、アリス。自分に。「だれか、早くしゃべって
くれないかしら!」
やっと、赤の女王がしゃべり始めた。「スープと魚を忘れてるわ!骨
つき肉を持ってきて!」
ウェイターは、アリスの皿に、マトンの足を置いた。
「アリスは、恥ずかしがり屋だから」と、赤の女王。「わたしが紹介す
るわ。アリス、こちらマトン。マトン、こちらアリスよ」
マトンは、皿の上に立ち上がり、アリスに軽く頭を下げた。アリスも、
驚くことも忘れて、おじぎを返した。
「わたしが、切り分けるのかしら?」と、アリス。ナイフとフォークを
手に、ふたりの女王を見た。
「もちろん、違う」と、赤の女王。「紹介された相手をカットするのは、
エチケットに反します。骨つき肉を片付けて!」
ウェイターは、マトンを片付けると、代わりに大きなプラムプディン
グを置いた。
「プディングには紹介されたくない」と、アリス。「そうでないと、な
にも食べられない。さっそく切り分けましょう!」
すると、赤の女王は、ずるそうな顔をした。「プディング、こちらア
リス。アリス、こちらプディング。プディングを片付けて!」
ウェイターは、アリスがおじぎを返す前に、プディングを片付けた。
「なぜ、赤の女王だけが」と、アリス。自分に。「ウェイターに注文し
てるのかしら?わたしもお客なんだから、注文できるはずよ!」そして、
ウェイターに。「プディングを戻して!」すると、手品のように、また、
プディングが出された。そして、自分に。「大きなプディングだわ。エ
チケットに反するかもしれないけど、食べなければ損よ!」
アリスは、プディングを切り分けて、ひとつを赤の女王の前に置いた。
「ずいぶん大胆な!」と、プディング。「よっぽど、プディングがお好
きなんですね!」
プディングの声は、太く、脂ぎった声だった。
アリスは、なにも言わずに、プディングを見ながら、じっとしていた。
「なにか言いなさい!」と、赤の女王。「おしゃべりを、すべてプディ
ングに任せておくつもり?」
「今日という日は、みんなから詩を聞かされる日のようね」と、アリス。
アリスがしゃべり始めると、ホールのみんなは、しゃべるのをやめて耳
を傾けた。「それも、奇妙なことに、魚にまつわる詩ばかり!」
「魚の詩ですって?」と、赤の女王。ゆっくり、おごそかに、口をアリ
スの左耳に近づけて。「白の女王は、そういう謎解きが好きだから、魚
の詩を聞かせてあげて!」
「ご親切にどうも」と、白の女王。ハトの鳴き声のような声で、口をア
リスの右耳に近づけて。「わたしも詩を聞きたいわ!」
「ええ、お聞かせします」と、アリス。
白の女王は、笑顔になって、アリスの頬にさわった。
アリスは、声に出して、詩を読んだ。
◇
「『まず 魚は つかまる』
それはやさしい 簡単につかまる
『つぎに 魚は 売られる』
それはやさしい 1ペニーで売られる
『さぁ 魚を 料理しよう!』
それはやさしい 1分もかからない
『さぁ 魚を お皿に!』
それはやさしい すでに魚は皿の上
『さぁ 持ってきて 夕食に!』
それはやさしい すでに皿はテーブルの上
『さぁ お皿のおおいを取ろう!』
それはむずかしい 皿のおおいは取れない!
にかわのようなものが しっかりと
皿のおおいをくっつけていて 皿は謎の中
どっちが やさしい?
皿のおおいを取ること? 謎を解くこと?
◇
「謎を解く時間をもらうわ!その前に」と、赤の女王。「女王アリスの
健康に!かんぱ〜い!」できるだけ高い声で叫んだ。
ホールのお客は、みんな大喜びで、ワインを飲み始めた。メガネのも
のは、頭にかけておどけた。顔にワインをこぼすものがいれば、デカン
タを倒すものもいた。テーブルにこぼしては、はじからたらしてワイン
を飲んだ。3名は、(カンガルーらしかった)マトンのローストに集ま
って、グレイビーソースを熱心にかけていた。
「まるで、かいばおけに群がる豚のようだわ!」と、アリス。自分に。
「そろそろ、あなたのスピーチに戻りなさい!」と、赤の女王。顔をし
かめた。
アリスは、素直に立ち上がった。
「サポートは任せて!」と、白の女王。アリスにささやいた。
「ありがとう」と、アリス。「でも、大丈夫!」
「そう、うまくゆくかしら?」と、赤の女王。確信がありそうに。アリ
スは、それには、やさしい笑顔を返した。
(「ふたりは、わたしを押したのよ!」アリスは、あとで妹たちに、ホ
ールでの話をしながら言った。「どう考えても、わたしをぺちゃんこに
する気だったのよ!」)
アリスは、スピーチを続けながら、同じ場所に立っていられなくなっ
た。ふたりの女王は、アリスを右にばかり押すので、アリスは宙吊りに
なった。
「ありがとうの言葉から始めます」と、アリス。スピーチを始めた。体
が数インチ浮いていたが、テーブルのはしをつかんで、床に降りた。
「気をつけて!」と、白の女王は叫んだ。両手でアリスの髪をつかんだ。
「なにかが起こりそう」
そのとき、(アリスは、後でそう語った)あらゆることが、同時に起
こった。キャンドルが、いっせいにのびて天井に達した。まるで、先端
が花火の柱のようだった。キャンドルの根元では、お皿が2枚づつ翼の
ように、フォークは2本づつ足のようにくっ付いて、あらゆる方向へ飛
んでいった。
「まるで鳥のようだわ!」と、アリス。自分に。「混乱の渦が始まりそ
う!」
そのとき、馬の鳴き声が聞こえたので振り返ると、白の女王のイスに
マトンの足が座っていた。
「わたしは、ここよ!」と、白の女王の声。スープ皿の中から聞こえた。
反対側を振り返ると、赤の女王の大きなやさしそうな顔が笑ったよう
に見えて、すぐに、スープ皿の中に消えた。
すべてが消え去るまで、ほんの一瞬だった。お客の何人かは、お皿の
上で横たわっていた。スプーンがテーブルを歩いてきて、アリスに、こ
こから逃げるように、手招きした。
「もう、立ってられない!」と、アリスは叫んだ。アリスは、跳びあが
って、両手でテーブルクロスを引いた。お皿やお客や、ロウソク、すべ
てのものがテーブルをすべって、床の上にたまった。
「あなた!」と、アリス。赤の女王を責めるように見た。「あなたのせ
いね!」
赤の女王は、アリスの左にはいなかった。なにか小さな赤の女王人形
のようになって、自分のショールにからみつきながら、アリスの方にこ
ろがってきた。
「変なこと!」と、アリス。「でも、今日は、もっと変なことがたくさ
んあり過ぎて、驚く気になれない!」
アリスは、ボトルを飛び越えてころがってくる人形を受け止めた。
「あなた!」と、アリス。人形は、テーブルの上で照明にあたっていた。
「ゆすれば、キティになりそう!」
10
アリスは、赤の女王人形を持ち上げて、前後に力いっぱいゆすった。
赤の女王は、なんの抵抗もできず、顔は、だんだん小さくなって、目
は、だんだんグリーンになった。アリスがゆすり続けると、さらに、背
が低くなって、太ってフワフワになった。
11
最後には、人形は、キティになった。
12
「赤の女王陛下!そんなにのどを鳴らさないように!」と、アリス。目
をこすりながら、キティに向かって、すこしおごそかに。「あなたのせ
いで、目がさめてしまった!あんなにすばらしい夢だったのに!わたし
といっしょに、キティは、ルッグランの世界にいたのよ!覚えてる?」
なにか話しかけるたびに、子ネコがのどを鳴らすのは、(前にアリス
が注意したように)かなり不便だった。
「はいの時は、のどを鳴らして」と、アリス。「いいえの時は、ニャオ
と鳴くことにすれば、会話が成立する!でも、いつもゴロゴロ言うだけ
では、人との会話はできない!」
子ネコがいつものどを鳴らすだけなら、『はい』なのか、『いいえ』
なのかを判断することができなかった。
アリスは、テーブルの上のチェスの駒から、赤の女王を見つけ、敷物
に座ると、キティと向き合わせた。
「さて、キティ!」と、アリス。勝ち誇ったように、手をたたいた。
「向き合ってる人がだれか、言ってごらん!」
(「しかし、キティは見てなかったようね」と、アリス。後に、妹たち
に説明しているときに言った。「頭を振ったりして、見ていなかった。
けれど、相手は、恥ずかしがっているようにみえた。それで、赤の女王
だと確信したの!」)
「もう少し、ちゃんと座って!」と、アリス。楽しそうに笑いながら。
「それから、目の前で━━━ゴロゴロ言ってるものがなんなのか、考え
ているあいだは、おじぎをして!」アリスは、キティを抱き上げると、
軽くキスをした。「このキスは、赤の女王であったことへの尊敬よ!」
そして、ネコのトイレにいる白の子ネコに呼びかけた。
「スノードロップ!いつになったら、ディナは、あなたの世話をやめる
のかしら?あなたが、わたしの夢で、すごくだらしなかったのは、ディ
ナに甘えてばかりいたせいよ。ディナ、白の女王を引っかいたことを覚
えてる?あれはとても失礼だったわ!ディナは、つぎに何をするつもり
かしら?」
アリスは、とてもくつろいで、片ひじは敷物にアゴは手に乗せて、子
ネコたちを見守りながらしゃべっていた。
「ディナは、ハンプティダンプティを演じてたんでしょ?わたしはそう
思っているけど、確信はないから、ディナの友達には、そのことをしゃ
べらない方がいいわ!
キティ、あなたがもしもわたしの夢にいたんだったら、きっとひとつ
のことには、大喜びしたわ!それは、多くの詩を読み聞かされたこと、
みんな魚にまつわる詩よ!明日の朝になったら、キティに聞かせてあげ
る!朝食のあいだ、『セイウチと大工』の詩を読んであげる。カキがた
くさんいるシーンを思い浮かべられるわ!
さて、キティ、夢のすべてが、だれの夢だったのか考えてみましょ!
これは、大事なことよ!そんなふうに右の前足をなめつづけるのは、や
めなさい!今朝、ディナがきれいにしてくれたでしょ?夢は、わたしの
夢か、赤の王の夢だった。赤の王は、わたしの夢に登場したけど、わた
しも赤の王の夢に登場した。夢は、赤の王の夢だったのかしら?キティ
は、赤の王の妻だったのだから、知ってるんじゃない?キティ、どうか
この謎解きを手伝って!右の前足は、待ってくれるわ!」
キティは、今度は、左の前足をなめ始めた。答えは、聞けなかった。
だれの夢だったのか?
読者は、どう思う?
エピローグ
それは、リデル家の3人の姉妹と、初めてボート遊びに行った、夏の
日の思い出でもある。忘れもしない7月4日だった。そのとき初めて、
私はアリスに、彼女の冒険━━━ルッグランの話を始めたのだ。
ルッグラン
ボート 夏の日の空
夢のように いつまでも 心に刻まれた
7月の夕暮れ
熱心に 耳を傾ける 3人の子どもたち
身を寄せてきて 目を輝かせる
冒険ばなしに
やがて 夏の日の空は 色あせ
声も 思い出も 消えてゆく
秋の冷たさが 7月を殺したのだ
しかしまだ 彼女は私にとりついて
夏の日のアリスは 走りまわって
目を
覚まさない
子どもたちは
熱心に 耳を
傾け
身を寄せてきて 目を
輝かせる
冒険ばなしに
子どもたちがいるのは ルッグラン
夢のように
日が過ぎ去り
夢のように 夏が死んでゆく
どこまでも どこまでも 流れをくだり
黄金のかすかな光を 追い求め
そんな
生とは ただの夢?
(終わり)