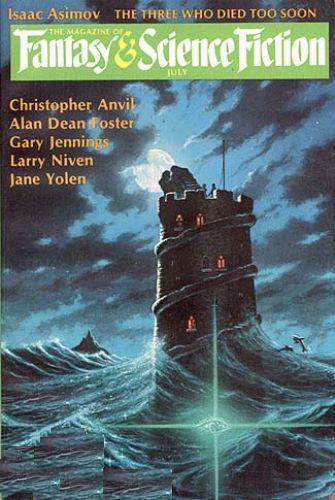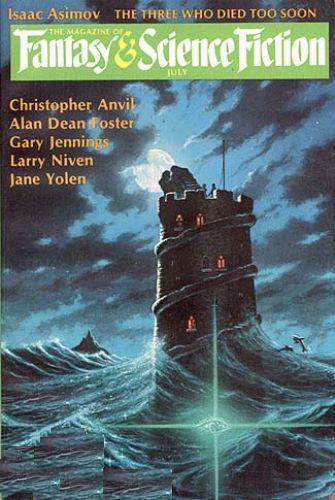レッドダイアモンド
原作:マークショア
アランフィールド
登場人物
レッドダイアモンド:私立探偵。
ロコリコ:闇の帝王。
フィフィ:謎の女。ロコから逃げている。
サイモン:オーナーキャブドライバー。ハードボイルド本の収集が趣味。
ミリー:サイモンの妻。夫の古本を処分したいと考えている。
ブラウン:不動産会社の経営者。用心棒を雇っている。
スウィート:ブラウンの用心棒。
アングリッチ:殺人課の刑事。
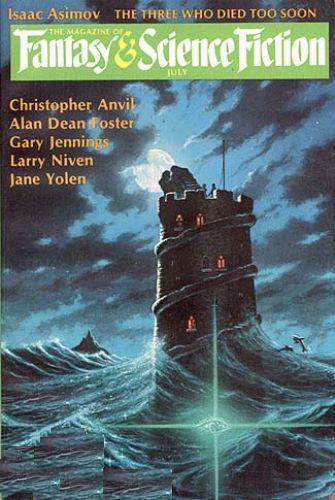
田中健似野:田中産業の社長。
片那:田中の用心棒。カンフーの達人。
ジェーン:女優志望のウェイトレス。ジョセフの店で働いている。
マンフレッド:退役軍人。ハイテク企業の経営者。
グウェン:マンフレッドの下の娘。
アリソン:マンフレッドの上の娘。
トッド:マンフレッド家の運転手。
ロザリー:マンフレッド家のメイド。
プロローグ
45口径のぶっとい弾丸が、かわいい女に口笛を吹くように頭をかす
めたとき、オレは暗くなった床にバタンと伏せた。さらに2発がかすめ
背後の壁にのめり込んで、ズシンズシンと音がした。
街のアラブ人の店で飲んだ安物のウィスキーが、オレの動きをにぶく
していた。オレはあわててトレンチコートの中の拳銃を手探りした。拳
銃の台尻に触れたとき、ホットなポーカーでロイヤルフラッシュがオレ
の手にすべり込んできたように感じた。目が暗闇に慣れると、ドアがひ
らいてギラギラした光が射しこんだ。ドアに、女のシルエット。
「レッド?」と、女。
「伏せろ!」オレは、大声で叫んで、体をひるがえして、銃の閃光が見
えた場所に2発撃ちこんだ。
38口径を食らった男のうめき声がした。
フィフィはドアに立ちつくしていた。背後からの光が、フィフィのブ
ロンドを太陽の暈のように見せていた。フィフィの大きな目のブルーは、
なにも知りたくないというかのようだった。
「だいじょうぶ」と、オレは、震えて立っているフィフィのところへゆ
っくりと歩いていった。「すべては予定どおりだ!」
1
「そこにいるのは知ってるのよ!」と、女の声。それは、とげとげしい
皮肉が込められていて、フィフィのやさしいハスキーボイスとは似ても
似つかなかった。ファンタジーは終わりだ。サイモンは机の上の本を閉
じた。
ミリーは、やわらかいピンクのスリッパで音もなく歩いてきて、未完
成の地下室で、薄汚れてはいるが詰め物がいっぱいで安楽そうな作りか
けのイスにいるサイモンを見つけた。サイモンは背筋をのばし、これか
ら始まる長い小言に耐える心の準備をした。
「あなたとそのゴミのような本!」と、ミリー。「ほかのだんなはみん
なまともな趣味を持ってるわ!家具木工とかにすれば、あなたもそのイ
スを直せるのよ?でなけりゃ、コイン収集とか。ジャスパーマードック
のコレクションは、2万ドルの価値があるって知ってた?」
ミリーは、サイモンが驚いて「ふ〜ん」と言うまで待った。
「ジャスパーは3千ドルしか使わなかったって、ローラが言ってたわ。
今、その価値が7倍になったのよ!」と、ミリー。「ジャスパーは、前
にそれらを売ってほしいと言われたそうよ。それらを売ることもできる
し、新たに買うことも━━━」
がみがみ言われながらも、サイモンはミリーをすばらしい女性だと感
じていた。化粧なしで目のまわりに眠たそうなくまがあっても、ミリー
は美しかった。
40才にして、ミリーは成熟した女性の美しさをもった。19年前に
結婚した頃より美しかった。19年が信じ難かった。
ミリーは年とともに数ポンド太ったが、うまく分散されていた。濃い
赤褐色の髪が顔を引き立てていて、ミリーもそれに気づいていた。サイ
モンが、レストランでウェイトレスをしていたミリーと知り合った頃は、
ミリーはいっしょに働いていた女子高生に感化されて、元気な子馬だっ
た。今、ミリーはサラブレッドだった。
「それに副業だったら」と、ミリー。「アニーが言ってたわ。ピーター
は夜間のデリバリーで週350ドル稼ぐんだって。来週、新しい車を買
うそうよ。聞いてるの?」
「アニーとピーターは新しい車を買おうとしている」と、サイモン。繰
り返した。
「そうよ!わたしの言うことをもっと聞いてほしいわ。今は、8時半す
ぎよ。あなたも副業かなにかしなさいよ!」
サイモンは、話しながら歩いているミリーのネグリジェ姿を美しいと
感じていた。たぶん、仲良くする時間はあったかもしれない。しかし、
サイモンはその考えを捨てた。動きだす必要があった。それに、ミリー
の方はまったく違うふうに感じていた。
サイモンは、立ち上がり、地下室の1番遠い壁の本棚へ行った。本棚
は、高校時代に作ったもので卒業制作だった。サイモンは、作業場での
できごとを除いて、普通の高校生だった。そこでサイモンは、のみを使
っていて手をすべらして、ひどい傷を負った。
高さ6フィートの本棚は、板がずれていたり汚れがあったが、サイモ
ンの宝物だった。
サイモンは、数千冊の本や雑誌を集めていた。もっと多くの本を持つ
者はいるが、だれも自分の本をそんなに愛してはいない。サイモンは、
すべての本を読んでいて、大半は2回以上読んでいた。お気に入りのシ
ーンを、パッとひらくことができた。
本棚には、古典が並んでいた。最高のものばかりで、残りはガレージ
に積み上げらたダンボール箱の中だった。
本棚に駆け上がれば、現実の作りかけの室はぼんやりかすみ、指を触
れれば、別世界へのパスポートが手に入った。
そこは、男が男であった世界、女にも会えた。サイモンはずっと都会
だった。西部劇はお呼びでなかった。SFは子どもだまし。ノンフィク
ションは教科書を読むのと同じ。サイモンのライブラリーはすべて、タ
フガイ専門だった。そこでは、トミーガンは音楽を奏で、ヒーローは、
相手のアゴにパンチを食らわせかならず報復した。
週間誌名でいうと、ブラックマスク、ダイムディテクティブ、クライ
ムバスター、ギャングワールド、スパイシーディテクティブ、スリリン
グディテクティブ、それに、ディテクティブフィクションだった。
ほとんどが破れやすいパルプ雑誌なので、破らずにひらくことはでき
なかった。しかし、表紙を見ただけで、引き金を引くレースウィリアム
スや、弾丸をかわすコンチネンタルオプや、警官を出し抜くマックスラ
ーティンを見ることができた。
ほかにペーパーバックスやハードカバーの本があった。サイモンがパ
ルプ雑誌で出会った者たちの冒険の続き、ハードボイルドものだった。
サイモンは自分の情熱に気づいた頃、別のミステリーも読んだ。しか
し、エラリースタンリーガードナーのペリーメイソンは、レスターレイ
スと相性が悪かった。ナガイオマルシャのロドリックアレインは、あま
りに紳士づらしすぎだった。英国ものにも問題があった。シャーロック
ホームズからネイランドスミスやジェームスボンドにいたる系列だ。彼
らは、高級料理より高いフランスワインを飲んで、殴り合いより、お茶
を飲むことに時間を割いていた。
ジョンダルマス、セリーニスミス、レースウィリアムス、マイクハマ
ー、マイクシャイン、リューアーチャー、ジョーガル、ディックドナヒ
ュー、ピートウェニック、オスカーセイル、チェスタードラム、そして
もちろん、キングたち。コンチネンタルオプ、サムスペード、トラビス
マクギー。フィリップマーロー、それに、レッドダイアモンド。拳銃と
女とガッツの冒険もの。
サイモンが朝読んでいたのは、レッドダイアモンドだった。ダイアモ
ンドは、無駄口をたたいて時間をつぶしたりはしなかった。さまざまな
口径の拳銃を流暢に使いこなした。いつも男のことや女のことを思い、
自分の義務を果たした。レッドダイアモンドは、冒険世界の最後のヒー
ローだった。なんてやつだ!
サイモンは、本棚から1歩下がって、タイトルを読み上げた。トリガ
ーハッピー、ブルードオンマイフィスト、マイジョブイズマーダー、テ
ラーインマイトレード、クリムゾンコープス、キラーアトザビーチ、レ
ディインザレイク。サイモンは、火薬のにおいをかげた。
もう1歩さがると、雑なつくりの家屋が目に入った。ヒックスビルの
未完成なままの雑なつくりの地下室。
サイモンは、この42年間毎日、別世界へのドアを捜して階段を上が
っていた。自分のイスに戻ってリラックスし、フィフィがどうなったか
ダイアモンドが語ってくれるのを心待ちにしていた。
未知の部分があったわけではなかった。この本は14回も読んだ。も
しも本を落としたら、そうしないよう注意していたが、本は自動的にな
んども読んだ最高のシーンをひらいただろう。
階段を上がりながら、1歩づつ足元で音がするのは、サイモンの体重
と雑なつくりの家のせいだった。
そこは、前はロングアイランドの湿地帯だった6エーカーの土地に建
てられた同じ造りの20区画のひとつだった。土地全体が徐々に、もと
の湿地帯に戻りつつあった。すべての家屋は、1年に1インチづつ沈下
していた。
サイモンの家は、中でももっとも沈下のスピードが速かった。それで
お隣りさんたちに、屋根裏を地下室に改造しているのかとからかわれた。
笑い事ではなく、天候がどうあれ家屋の荒廃はひどく、言い返す言葉も
なかった。
家は、7室の農場タイプの造りで、粗雑な木材で建てられていた。そ
のため建設会社は、連邦大陪審の調査局に犯罪と認定されて、業界の粗
雑な見本とされた。建設会社の2人の証人は殺され、3人目は、家を建
てたすべての記憶がなくなったと主張して、カナダに逃亡した。
証人たちになにがあったかを新聞で読んだあと、家主たちは、ここに
住み続けることにした。しっくいはひび割れて、壁はクレープのように
薄く、風が吹けば、家はきしんだ。
今では、14軒しか残っていなかった。6軒は、建設会社の親類の無
免許の電気工事ミスで、電気系統から出火して焼失した。この親類の会
社は、業界から追放された。家の契約書をよく読むと、家の改築費は家
主の負担となっていた。
サイモンは、家の改築に9千ドル使った。地下室に室内プールのよう
な広い空間を作り、屋根裏の梁を補強し、シロアリが出ないよう駆除業
者に予防処置をしてもらった。
家は、7年たった。
◇
「おはよう、ダディ」と、ショーン。階段を上がってきたサイモンに。
ショーンは、目はキラキラして、笑顔は温かく、18才の体に無駄な脂
肪はなく、歩くときも背筋をピンと伸ばしていた。母親と同じように足
音は静かだった。
「体調は、どう?」と、ショーン。
「いいよ、ショーンは?」と、サイモン。
「すばらしい!母さんにサンドイッチを急ぐよう言って!今日、授業の
前にコンピュータクラブのミーティングがあって、遅れたくない。でも、
朝食は食べたいので!」
「分かった」と、サイモン。
「よろしく」と、ショーン。急いで出て行った。
会話は、へたなテレビコマーシャルのようにいつもぎこちなかった。
息子とはこれといった話題がなかった。完璧な人間になにを話したらい
いのだろう?
たぶん、完璧ではなかったのだろう。しかし、それに近かった。ショ
ーンは、輝かしかった。フォーチュン500社の企業の2社から、すで
に内定が出ていた。初任給は、5万ドルだそうだ。ショーンは、東海岸
のチェス大会で5位だった。フランス語とスペイン語に堪能だった。ま
た、サイモンにも理解できない電子回路の特許を1つ持っていた。ショ
ーンは、ほんの3時間で、その原理と開発の経緯を話してくれたが、サ
イモンには、やはり理解できなかった。
しかしショーンは、科学に夢中のインテリというわけではなかった。
野球チームではピッチャーで、大学のフットボールチームでは第2クォ
ーターバックだった。ショーンは、サイモンより1インチ背が高く、6
フィート2インチで、20ポンドはスマートだった。ショーンは、アス
リートらしいしなやかさで、すばやく動いた。
ショーンは、男子のあいだで有名で、女子には人気があった。カリス
マ性があって、健康で、みんなから好かれた。サイモンは、みすぼらし
い父親から完璧な息子が生まれたことが不思議だった。
ショーンは、キャブドライバーの父親のことをどう思っているのだろ
う?そもそもショーンは、父親のことを考えたことがあるのだろうか?
サイモンが居間を通ると、キーンが描いたポップな瞳が笑いかけた。
ミリーの自慢は、そうした室内装飾だった。サイモンには目障りだった
が、口出しはしなかった。そのうちもっと資金を出せるようになれば、
上品な装飾に変わってゆくだろう。
サイモンは、2階のバスルームに入ってヒゲを剃り始めた。
「あなた、バスルームにいるの?」と、ミリーの声。バスルームの薄っ
ぺらなドアを通して聞こえた。
安全カミソリが、泡だらけのサイモンのアゴで滑って皮膚をキズつけ
た。グリーンのバスローブに、血が数滴したたった。
「ああ、終わったよ」と、サイモン。ティッシューで傷口を押さえて、
出てきた。
「ありがとう、あなた!」と、ミリー。階下から。
ミリーがバスルームを使う時間に、サイモンは口をはさむことはなか
った。なにか言えば、ミリーはもっと広い家で機能もいろいろあればと
いったサイモンの稼ぎの話になるからだ。
ヘビがくねるように、ミリーの不平もくねり、サイモンの稼ぎが少な
い、同年代のほかの人ならもっと稼ぐ、もっと成功した男と結婚できた
のに、さらに、ミリーのバスローブの不満にまでおよんだ。
サイモンは、未完成の地下室にある未完成のバスルームに退却するの
が1番だった。
地下室に降りるのは、いつでもすぐできた。そこは、サイモンの本が
1番近くにある場所だった。
本は、もとのまま、今、読んでいるページがひらかれたままだった。
本をそんなふうに十字架に張りつけれた異教徒のように残してゆくのは、
不注意かもしれない。
本を持って、小さなバスルームに入った。便座を閉じてすわり、ペー
パーバックの表紙のイラストを眺めた。
ダイアモンドインザローのタイトルの赤、女のブロンドに目のブルー。
レッドダイアモンドは、女に腕をまわし左手で肩をつかみ、右手で煙の
出ている38口径を握って、歯を見せて不敵な微笑みを浮かべていた。
表紙を眺めていると、サイモンの周囲はぼんやりかすみ、読み始めた。
◇
オレは、やつがかぶっているフードの布で靴を磨きたかったが、玄関
マットを自由に使えたのは、銃身を短く切ったショットガンを手にした
やつの方だった。
「壁を向け!」と、やつ。醜い二銃身のショットガンでこづいた。
オレは、言われたとおりにした。オレは壁を見た。それが、オレが見
た最後のものになるかもしれなかった。額に入れられたフランクリンル
ーズベルトの肖像画が、ベージュの壁にクギで吊るされていた。
ここは、スマートに死ねる場所ではなかった。黒の虫がはいまわる、
ボウェリの安宿。検死官が壁から死体をこすり落としているときに、ど
こに泊まっていたかなんてささいないことだ。
オレは、ショットガンの若造の方を向いた。貧乏な独身男の無精ひげ
についた2つのビーズ。
「向こうをむけ!」と、やつ。怒鳴った。
「どうする気だ?撃つのか?」
やつは、オレの予想どおりだった。
「引き金をひくときに、うしろにステップバックした方がいいよ!」
若造のショットガンがピクリとした。「なぜ?」
「引き金をひいたら、200ポンドのひき肉をだれかがふざけてぶちま
けたみたいになるからさ」
ショットガンがすこしふるえだした。
「新しいスーツに、オレの脳や目玉や腸をぶちまけたくないだろう?恋
人に会ったら、まるでゾンビみたいって言われるぜ!」
「黙れ!」と、やつ。大声で。ショットガンをもつ手がふるえ、上唇を
かんでいた。
「今だ、撃て!」と、オレ。やつのフード越しに大声で。これは、古い
手だったが、やつはひっかかった。
やつが振り向いた瞬間、オレは壁のフランクリンルーズベルトの肖像
画をつかんで、やつの頭に振りおろした。固い木枠がやつのショットガ
ンを払い落とした。
オレは、2回だけやつをたたいた。やつは、まるで大人の仕事をまか
された子どものようだった。眠らせたあとは、ずっと幼く見えた。
肖像画は、引き裂かれて床に落ちていた。いい目的のために引き裂か
れたのだから、フランクリンルーズベルトは許してくれるだろう。
大統領に命を救われた経験のある人間は、そんなにはいないはずだ。
◇
玄関のドアチャイムが、「雨に歌えば」を奏でた。サイモンは、ファ
ンタジーから戻った。ドアチャイムを聞かなかったことにしようとした
が、3回目が鳴り出した。
「今、出る!今、出る!」と、サイモン。大声で。本をトイレタンクの
布カバーの上に置いた。
階段を上がりながら、またすぐ本に戻れるだろうと考えた。感じとれ
るのは、漂う雰囲気だった。サイモンは、プロットは心では知っていた
が、多くのところは分からなかった。だれでも人を殺すときは正当な理
由があった。スペードやマーローは、最後でちゃんと説明した。しかし、
なにが起こっているのか分かっている者はいるだろうか?そんなことを
気にする者がいるだろうか?チャンドラーが嗅がせたのは、ジャカラン
ダの香りだった。あるいは、ハメットが聞かせたのは、ファットマンの
笑い声だった。それは、サイモンがすべり込む世界だった。意味がある
かどうかなんて、気にする者がいるだろうか?
メロニーが玄関にいた。サイモンは自分の娘のことを、いつもひざに
飛び乗ってきて物語をせがむ、おさげの幼い娘として記憶していた。
目の前の16才の少女が、サイモンが憶えてる幼い娘と同一人物だと
は信じがたかった。
メロニーの目は、徹夜明けのくまができて半分閉じかかっていた。庭
師が使うようなこてで塗られた化粧は、顔を引き立たせもせず、脂ぎっ
たブラウンの長髪には、グリーンの筋が入っていた。メロニーの着てい
る白のシルクのシャツはローカットすぎて、サイモンは不快感をおぼえ
た。
「ロジャーよ」と、メロニー。後ろに立っていた若者を紹介した。「ロ
ルフをやってるの」
「へぇ、プロのゴルファー?」と、サイモン。
ロジャーは、まったくアスリートには見えなかった。顔は太ってだら
しなく、肌も青ざめてニキビだらけだった。頭は、サイモンにはゴルフ
ボールに見えた。
「いや、ゴルフでなく、ロルフです」と、ロジャー。体型と同じくらい
不快に鼻をならして。「ロルフ式マッサージです」ロジャーは、メロニ
ーの後ろに回って身をかがめた。
サイモンは、ゴルフボール頭の首筋をたたいてやりたい気がした。こ
ういうことは、前にもあった。思い出すのは、ミリーがメロニーの味方
をする見苦しい場面ばかりだった。サイモンには、娘の突飛なおこない
を見るのがミリーの秘密の喜びなのではないかとさえ思えた。
ロジャーは、メロニーが落ち込んだときに元気を与えてくれる奇人変
人の行者の長い列の最新の者に過ぎなかった。ヨガ行者、超能力者、秘
密結社、それにわけの分からない新興宗教。彼らは、メロニーのメッカ
である寝室にこもってドアも閉めて宗教的儀式をした。
「カギはどうしたんだい、ヤングレディ?」と、サイモン。メロニーが
家に入ろうとするのを邪魔しながら。
メロニーがそばに寄ってきたので、サイモンは後ろに下がった。
「ロジャーとは、クラブで会ったのよ。家に行こうというので、カギを
渡したの。あとで、いっしょに過ごすうちに、ふたりにはカルマがあり
そうだったの」
カギを変える時期だと、サイモンは考えた。ロジャーは横を向いてニ
ヤニヤしていた。
「そのごほうびが、ペテン教師というわけか」と、サイモン。
「ひどいわ!」と、メロニー。ロジャーの手を引いて、父親の前を通っ
て家に入った。
ふたりは、階段を上った。メロニーが先に、ロジャーは後ろからジー
ンズを見ながら。
サイモンは、ドアをバタンと閉めると、家じゅうがゆれた。
ミリーの犬はペキニーズで、頭に黄のリボンをつけてコーチの下から
ドアに向かってキャンキャンほえながら走ってきた。見たところ、侵入
者はいなかった。犬用のドアを入ると、サイモンのひざに跳びついて攻
撃しようとした。
「ボッシーをひっくり返して、どうしようというの?」と、ミリー。階
段の上からどなった。
「べつに」と、サイモン。ボッシーの攻撃をかわしながら。ボッシーは
指にかみつこうとした。サイモンとボッシーは、いつも戦っているボク
サーどうしのように、相手の攻撃を容易に見抜いてかわせた。
サイモンはボッシーの首筋をつかもうとすると、ボッシーは後ずさり
してサイモンの左ヒザをかんだ。ボッシーの毛をつかむと、ボッシーは
キャンキャンないた。
ミリーは階段をドタバタ降りてくると、ボッシーを抱き上げてサイモ
ンをにらんだ。
「あなたは動物がきらいなの?やめなさい!」と、ミリー。言葉に毒を
込めて。ボッシーは、ミリーの腕のなかからサイモンをあざ笑った。
ミリーは寝室に戻り、ボッシーを犬用のベッドに寝かせた。サイモン
は、2階のバスルームでその日必要な用事を済ませた。
それから寝室で、ボッシーにクークー言っているミリーとは言葉をか
わさずに、服を着た。サイモンは、赤と黒のチェックのフランネルのシ
ャツを着て、すこしきつめのブルーのズボンに、縦じまのナイロンの靴
下をはいた。靴下は、伸びきって穴があきそうだったが、靴で隠して、
腰にはベルトを巻いた。
サイモンは「行ってくるよ」と言いそうになった。ミリーはボッシー
に夢中でサイモンには知らんぷりだった。
サイモンが通り過ぎるとき、メロニーのドアは閉まっていた。
地下室に降り、本の前を通るときにしばらくのお別れを言って、地下
室からガレージに直接出られるドアからガレージに出た。
2台の車があった。ミリーのは、3年前に買った、ガソリンを食うス
テーションワゴンで、サイモンのはキャブだった。
キャブは、ニューヨーク市標準の明るい黄でオレンジの筋が入ってい
た。12万3千マイル走っていて、5年たっていた。すべての部品は、
1回以上交換していた。
サイモンは、オーナードライバーだった。オーナードライバーは、ニ
ューヨーク市の11、787台のキャブのうち5千台だった。キャブは、
街中で乗客を拾うだけで、5万6千ドル稼げた。
15年間、サイモンは、残りの6、787台の1台をやっていて、1
日10時間、雇われの身だった。3年前、独立する権利を得て、中古キ
ャブを買った。しばらくは支払いに追われていたが、やっと自分のボス
になれた。
エンジンをかけるのに6回クランクをまわした。ウィンドウブレーカ
ーを引いて、運転席に座ると、クリップボードを調整して、ガレージの
ドアをあけると出て行った。
ミリーは、エンジンをかける前にガレージのドアをあけるようきつく
言っていた。
「あなたはそのうち、1酸化炭素中毒で死ぬわよ!わたしに借金を残し
て!」それが、ミリーのお決まりの文句だった。
ミリーは、サイモンがキャブに乗ってるところを近所の人たちに見ら
れたくないのが、理解できなかった。多くは、ただの会社員で、それ以
外は、中古車販売とかテレビの修理人だった。彼らは、オーナードライ
バーとただのキャブドライバーを区別できなかった。
サイモンは、ガレージのドアをあけっぱなしで街へ繰り出して行った。
それも、ミリーは気に入らなかった。ボッシーが逃げてしまうかもしれ
なかった。サイモンには、好都合だった。
サイモンは、すばやく運転して、家や近所からすぐに遠ざかった。今
日はいい日だった。だれにも仕事に出るところを見られなかった。
どんな日が、いい日だったか?空港までの客?かわいいミニスカート
の客?100ドルのチップ?酔っ払いがだれも吐かなかった?ほかのキ
ャブに客を奪われなかった?礼儀正しいほかのドライバー?
キャブは、ムチを使わずに都心までの道を知っている信頼できる愛馬
のように、ロングアイランドハイウェイに入った。しかしすこし疲れた
老馬で、道路の穴によろめき、サイモンがアクセルを踏むたびに咳き込
んでいた。
窓をあけると、風が顔にあたった。スピードは、「世界最大の駐車場」
として有名な道路だけあって、ほかでは味わえない喜びだった。サイモ
ンの数少ない喜びのひとつで、自分の時間として、あえてほかのキャブ
のようにラッシュアワーの混雑に逆らったりはしなかった。キャブのド
ライバー以外は、だれも理解できないだろう。サイモンは、行きたいと
ころどこへでも行けた。ブルックリンにさえ行けた。
「おっと!」と、サイモンは考えた。「本を持ってくるのを忘れた!」
ハードボイルド探偵といっしょなら、1日がすこしはましになった。た
まに、ウェストサイドハイウェイの片側に停めて本を読んでいた。ある
日サイモンは、走って仕事をしたのは2時間だけだった。ミリーは、サ
イモンの売上げがたったの23ドルだったのを見て、怒りくるった。
ミリーが正しいことは、分かってはいた。サイモンには、カネはどう
でもよかった。35ドルの客がいても、虹の向こうに金のつぼはないこ
とが分かっていた。あるのは、胆石くらいのもんだ。サイモンは、仲間
と週末に草野球をするのをやめた。ミリーと週1回、ダンスをしにゆく
のもやめた。タフガイの物語だけが、唯一の情熱となった。
選択は、ふたつにひとつだった。情熱に従うか、今あるもので満足す
るかだ。今まではひどかった。家、家族、結婚、幸せとは言いがたいも
のが続いていた。サイモンの若い頃のプランとは正反対だった。
2
営業中の表示は消したまま、南の都心へ向かうミッドタウントンネル
に入った。14番通りのバルモラルカフェの前の、長い黄の列にキャブ
を停めた。
回転ドアを押して入ると、騒々しい人の声、おもに男の声がして、ト
レイをガタガタさせたり、シルバーの服やらの人の流れにぶつかりそう
になった。葉巻やタバコの煙が、モクモク上がっていた。
サイモンは、カウンターに通じる列の一番後ろに並んだ。コーヒーの
おかわりをついでいる女店員、それを見ている店長、一日中カフェで時
間つぶしをして寝込んでいる老人、わずかな会社員、それに浮浪者のよ
うな人々であふれかえっていた。
騒々しさの中であいさつする大声は、キャブドライバー同士が互いを
見つけてのものだった。雨の日に、唯一ニューヨークでキャブを見つけ
られる場所は、バルモラルカフェしかないというのは、有名な話だった。
サイモンは、すり減ったプラスチックトレイを1枚取ると、そのまま
ステンレス製のカウンターの列を進んだ。
「ハイ、サイ!どうだい?」と、ペドロ。自分のトレイをスムーズにす
べらしながら。
ベニーは、5フィートしかないからだで、よく知られた病気━━━い
くつかは未知の━━━病気と戦っていた。24年前からサイモンはベニ
ーを知っていた。ベニーは、昼間の仕事、つまり不平を言うチャンスを
のがすことはなかった。
サイモンの返事を待たずに、ベニーは不平の数々を並べた。
「わしかい?元気さ。痔なんて、たいしたことないさ。ちょっと言えな
い苦しさがあったんで、医者に診てもらったら、わしの腎臓を見て、わ
しが生きてるのが不思議だってぬかしおった。わしの心臓は━━━」
「失礼!」と、サイモン。ベニーの話をさえぎって、列の先へ進んだ。
ベニーが腸の話になる前に、去りたかった。
サイモンの前の太った男は、サイモンが目をつけていたチーズケーキ
をトレイにのせた。最後の一片だった。サイモンは、カウンターの向こ
うにいる純白のエプロンの店員に、新しいチーズケーキがあるかどうか
訊かなかった。バルモラルカフェのサービスが悪いことは有名だったか
らだ。
サイモンは、ブラックコーヒーとまずそうなアップルパイでがまんし
た。
「サイモン、足元に気をつけろよ!」と、ベニー。サイモンが代金を払
うときに聞こえた。
サイモンは、混んだレストランでテーブルの間の狭いスペースを進む
うちに、コーヒーのほとんどをトレイにこぼした。
大きなポットの模型の横のテーブルには、ギリシャ人のニックに、ペ
ドロ、アレックス、エディフォングが座っていた。サイモンがイスにつ
くと、会話がしばらく中断して、サイモンにあいさつした。エディは、
もっともやせていて、プレートの食事を終えていたが、話に夢中だった。
「それで、オレは言ったんだ、女は5番街の水道橋にいるって。女はし
ゃべりながら歩いていた。最後に見たときは、ベルモントのジョッキー
といっしょだった。その後はどこへ行ったか━━━」
ペドロは、大きなゲップをしたのでみんな笑った。エディは、たまに
鋭い勘で競馬を的中させるので、ノミ屋に足を折られないよう注意して
いた。
ノミ屋は、ダーティドムという太った男で、店の反対側にいた。お客
たちは、ドムのところに来て、たましいを賭けていった。ダーティドム
は、ロングアイランドの北の25エーカーの土地に住んでいた。キャブ
ドライバーたちは、アパートか抵当入りの小さな家に住んでいた。サイ
モンは、損することもギャンブルが悪だということも知っていたので、
誘惑に負けることはなかった。
「サイ!来月から、いよいよオレたちの無線グループを始めるぜ!」と、
ペドロ。
「へぇ〜」と、サイモン。コーヒーをすすりながら。
「10台から、割引つきで始める」と、ペドロ。「街で2番目に忙しく
なるぜ。サイも配車係から無線を受け取れるよ。そのへんの酔っぱらい
からでなく、ウォールストリートからな」
「チップもねぇのか?」と、ギリシャ人のニック。
「街でひとりでいるときに」と、ペドロ。ニックを無視した。「無線で
助けを呼ぶこともできる。よたもんにナイフを首に突きつけられたらど
うする?」
「ああ、大丈夫だ」と、ニック。「ビビッて、すぐにカネを出すよ」
アレックスは、グループの最年長で61だが、なにか言った。アレッ
クスがしゃべることはめったになかったので、テーブルのみんなは静か
になった。
「先週、またピストル強盗にあった」と、アレックス。ほとんど聞きと
れない声で。「白人だった。ひどいだろ?シフトの終わるときに。87
ドルやられた」アレックスは、また黙ってコーヒーをすすった。
男たちは、泥棒の話になった。ニックとペドロの話は、まゆつばもの
だった。キャブの運転席は、弾が貫通できないパーティッションで区切
られていたので、安全だと感じていた。
「独房にいるかんじだ」と、エディ。「それでいつも持ってる」
「なにを?」と、サイモン。
「38口径さ。波止場の男から手に入れた。75ドルもした。強盗され
そうになったら、パンチを食らわせてやる!」
「ルイもそうだった」と、ニック。ルイは、6回ピストル強盗にあった。
それで拳銃を手に入れて、7回目にやっつけようとして、逆にやられた。
ルイの葬式は、3ヶ月前だった。
みんなが昔の仲間を哀悼していると、沈黙をサイモンが破った。
「オレたちは、誰からも一目もおかれてない!」と、サイモン。
「ロドニーダンガーフィールドは?」と、ニック。
「やつも含めてだ。ガキとケンカしてるようなもんだ」と、サイモン。
「トラック野郎や日雇い労働者がなんだっていうんだ?やつらがなにか
してくれたか?」
ニックがシャレたジョークを飛ばそうとしたので、サイモンはさえぎ
った。「なにかしてくれたか?撃ちまくる映画や飛行機の歌やテレビド
ラマだってそうだ!」
「サイ、その話は前にも聞いたぜ!」と、エディ。「それで、なにが言
いたいんだ?お客にチップをねだるのか?」
「まったく違う!」と、サイモン。「昔は、オレたちは神秘的な存在だ
った!」
「香水のような音とか?」と、ニック。
みんな笑ったが、サイモンは続けた。
「ブートレギングやノッキングアラウンド、ライクスチーブミッドナイ
トを見てみろ!私立探偵にはみんな自分専用のキャブがあったんだ!」
ペドロは、また大きなゲップをしたのでみんな笑った。サイモンは、
がっかりした。
話題は、スポーツから政治経済にわたった。サイモンは、また自分の
説を述べようとしたが、だれもサポートしてくれなかった。
ペドロは、グループの最弱年で31ですでに2回離婚していたが、ガ
ールフレンドの話を始めたので、サイモンは朝食を終え、仕事に戻った。
◇
最初の客は、ビジネスマンでずっとアタッシュケースを神経質にたた
いていた。つぎは、老婦人でペットのヨークシャーテリアを獣医に連れ
てゆくところだった。つぎは、ふたりのビジネスマンで遅いランチをと
りに派手なレストランに入った。
ファッション通りで、モデルの女を乗せて、イーストサイドの自宅へ
届けた。話しかけてもろくに返事もせず、チップもなかった。
「ビッチめ!」と、サイモン。女が降りると、つぶやいた。
イーストサイドを流していて、コカインの売人だと名乗るホモの乗客
をのせた。ウエストサイドを通って、食肉市場の横を通った。客は話し
たがったが、サイモンは黙っていた。ホモの客は、好きじゃなかった。
「支払いは、現金でなく別のものじゃだめ?」と、ホモの客。ゲイバー
の前で降りるときに。
「現金のみ!」と、サイモン。チップのことはあきらめながら。
「あら」と、客。首のチェーンを指にひっかけながら。「別のってコカ
インよ、おバカさん!」
「料金は、9ドル50セント、キャッシュで!」
客は、サイモンに10ドル札を投げて降りていった。
そのあとは数人のパッとしない客。政治のことをやたら話したがる男。
ひとりごとをつぶやく女は、3ドルの料金に2ドルのチップをくれた。
3時のブレイクタイムになった。
ウェストサイドのハンバーガーショップで、2台のキャブ仲間と話し
ていた。だれかがまた無線グループの買収のアイデアを持ち出した。サ
イモンは、「オレは、自由な方がいい!」と言ったが、論点がずれてい
ることは分かっていた。それで、また、仕事に戻った。
夕方のラッシュに向けて道が混み始めたとき、42番通りと2番通り
の角でサイモンは、客を乗せた。そこはいいスポットで、合衆国の外交
官やデイリーニュースの記者といったイーストサイドの上客がよく乗っ
てくる場所だった。サイモンは客を乗せるために、2車線をまたいだ。
「とまってくれて助かった!」と、客。バックシートにすべりこみなが
ら。客は、これといって特徴のない外観で、いいスパイになれそうだっ
た。電話ボックスに消えてしまうこともできただろう。
サイモンは、バックミラーで客が見えるようにシートをずらした。変
な客を相手してるヒマはなかった。
客は、まともに見えた。中年で、ふつうの体型で、ヒゲはきれいにそ
って、ブラウンの髪は薄くなりかけていた。クリーンニング済みだが時
代遅れのダークカラーのスーツだった。サイモンは、視線をそらした瞬
間に、客の顔を忘れそうだった。
「どっか行きやすか?それとも、話すだけ?話すだけなら、よそ行って
くんな!」と、サイモン。ありったけのタフガイの声音で。変な客をあ
つかうには、だれがボスかを教えとく必要があった。パッとしない表現
であっても。
「14番通りのブロードウェイ。バルモラルの近く」と、客。
客は急いでいただけらしく、サイモンはきつい言い方をしたことを後
悔した。バックシートにおとなしく座って、窓の外を見ていた。
「窓をあけてもいい!」と、サイモン。数ブロック走ってから。
特徴のない男は、ためらった。「知り合いのように感じる。悪い意味
ではなく。なにかをさがしているやつは、どこをさがせばいいか知って
るわけではない」
しばらく言いよどんだ。言葉をさがして、口が動いた。
「だれが、だれなのか、どうでもいい。わだちになにがあるっていうん
だ?テレビをずっとつけてるようなもんだ。そのままにしておけば、声
がしゃべり続ける」
男の言葉はあふれ、コニーアイランドのカーレースのようにぶつかり
あった。
「みんな緑の芝生にあこがれてる。カニの芝生。無機能。防臭。足の悪
臭。コメディ。嫉妬。プレッシャー。建設。崩壊。打つ手なし。チャネ
ルを変えろ!秒読み。友人の死。虚無。おまえとオレ」
サイモンは、バックミラーでまた観察した。男をベルビュー病院でお
ろしてしまうこともできた。男が乗ってきたのは、混雑が始まる前だっ
た。変に見えるが、言葉があふれだしたとしても、まともな気がした。
男は、急に頭をふった。
「あなたは聞いてくれると思う。オレの名前は、チャーリーフリットク
ラフト。結婚しててガキがふたり、クイーンズに家も買った。株で大損
した。妻が浮気してるの見つけた」
男はしゃべるのをやめて、窓の外を見た。
ふたりとも黙ったまま、キャブは騒音のなかを走った。
「すべてを放り出しそうになったことは?」と、男。突然、訊いた。
「もういちどやり直して、すべてを忘れようとしたことは?」
「イェ〜!」と、サイモン。その言葉が、たましいのゲップのようにサ
イモンの口から出た。
それ以上は、話さなかった。14番通りに着いて、男は降りた。料金
と20%のチップを置いていった。
サイモンは、不安を感じた。男の顔も、男が言ったこともよく覚えて
なかった。覚えていたのは、自分の心の叫びである「イェ〜!」という
言葉だけだった。
◇
夜、家に帰ってからも、「イェ〜!」という言葉がサイモンをとらえ
ていた。サイモンは、なんのためらいもなく無意識からのように、その
言葉を発した。夢の感覚を越える、なにか感覚が強すぎて、顔なし人間
しか完全に理解できないような感じがした。親しい友人にも、うまく説
明できないことが分かっていた。とにかく、話す相手はいなかった。ダ
ークカラーのスーツの客との会話以外のことを、考えようとしたが、そ
のときの自分の感覚を忘れられなかった。
ショーンの車が、家の正面に停めてあった。ショーンは、エンジンに
寄りかかって、フードつきコートを着ていた。車は、1968年型黒の
ムスタングを完全に再現したカスタムカーで、エンジン音はショーンの
うなり声のように響いていた。
サイモンは、ガレージにキャブを停めると、息子のところへ行った。
サイモンの動きはにぶく、それは、体重とキャブの座席のスプリングの
せいだった。
「調子いいかい?」と、サイモン。
「最高です、ダディ」と、ショーン。「キャブレターがすこし汚れてた
んで、磨いておきました。ついでに、燃料フィルターに詰まりがあった
んで交換しておきました」
「安全がベストさ」と、サイモン。
「そうです、そのとおりです!」と、ショーン。
サイモンは、息子を宝石のようによそよそしくあつかう自分のやり方
が嫌いだった。言行不一致のような気がした。できれば、男どうし心と
心でつきあいたかった。
「大学の方は?」
「きょう、メンバーリストを作りました!」
「チームの?」
「ブライアンが、ひざの故障でしばらく休むので、今シーズンは、ぼく
がクォーターバックをやることになりそうです。だれかが故障するのを
喜んでるわけではありませんが」
「もちろんさ。ガールフレンドの方は?」と、サイモン。ショーンにぞ
っとするウィンクを送りながら。
「ええ、メリーアンとは、本気で考えてます。彼女は看護学校を終えた
いと言っているので、結婚は、ぼくが卒業するまで待つつもりです」
サイモンに、悪い考えがしのびよった。なぜ、ショーンは、自信をな
くすことがないのだろう?あるいは、ドラッグをやるとか?性病にかか
るとか?そうなれば、サイモンは父親らしくふるまって、アドバイスの
1つでも与えてあげられたのに!
「こんどアルバイトをします!」と、ショーン。「大学の近くの電気店
で!」
「いいじゃないか!そんな時間があるとは思えないけど」
ショーンは、うなづいた。「たまに大変ですが、なんとかなりそうで
す」
「そう、願ってるよ!」と、サイモン。「夕食は?」
「食べました」
「それじゃ、また、あとで!」
「話せてよかったです、ダディ」
「オレもだよ!」と、サイモン。
家の中は、葉巻のにおいがした。だれがこの家で、葉巻を吸ったのだ
ろう?ショーンは、体にタバコのにおいが付くのを嫌っていた。メロニ
ーも、体にどんなにおいでも付くのを嫌っていた。ミリーは、サイモン
に聞かれて、どうかしてんじゃないのと言っていた。
1年くらい前から、サイモンは、ミリーが浮気している気がしていた。
面と向かって聞いたことはなかった。しかし、いつも葉巻のにおいがし
たし、こんなメモがあった。
「友人と出かけてきます。夕食は、冷蔵庫に。帰りを待たないで、先に
寝ていてください!」
葉巻を吸ったのは、だれなのだろう?このにおいは、サイモンの父親
を思い出させた。背が低く太った体型で葉巻を吸い、かつらをつけてい
た。フロリダから週2回飛行機で、息子のワイフと浮気しに来てるのだ
ろうか?
冷蔵庫には、ミートローフがあった。メロニーは、出かけていた。ど
こにいるかは、考えたくなかった。外で、ムスタングが出てゆく音がし
たので、ショーンが出かけたことが分かった。
サイモンは、静かな家を移動して、つけっぱなしだった室の電気を消
した。居間のプラスチックカバーのイスに座って、地下の石油ヒーター
のハム音を聞いていた。それは、心臓の鼓動のようで、たまに、止まっ
た。修理屋を呼ぶべきだったが、ぎりぎりまで待っていた。
目をつぶっていると、隣のテレビの音が聞こえた。隣の家族は、マー
ブグリフィンを見ていた。いつも、マーブグリフィンだった。
自分がなにをしたいか、分かっていた。急いで階段を降りて、地下へ
行った。電気をつけて本棚を見たとき、まるで自分の下で床がぬけ落ち
た気がした。
本棚は、カラだった。すべてカラッぽで、木がむき出しになっていた。
3段目に、メモがあった。
親愛なるサイへ━━━きょう銀行から別の小切手が届きました。それ
だけですが、いいことを思いつきました。本をコレクターに売るとい
うアイデアです。驚くことに、ガレージのガラクタが、マンガも含め
て、全部で、2300ドルになったんです!これで、スペースができ
た上、お金もです。これで、あなたの悩みのたねも解決です!
━━━ミリーより
メモは、ミリーの手書きで、句読点はハートマークになっていた。サ
イモンは、完全に理解するまで3回読み直した。
数秒間は、打ちのめされて立ち上がれなかった。ミリーは、ずっと前
から本をすべて処分するとおどしていた。ついに、それをやったのだ。
収集に30年もかけ、1000の幸せな思い出や愛してやまない登場人
物たちが、一瞬で抹殺された。
デッドハート、マイガンイズクイック、デッドイエローウーマン、テ
イクイットアンドライクイット、ザハイウィンドウ。すべてが失われた。
タフガイの友人たちが、たったひとりの女によって、一瞬で抹殺された。
サイモンは、バスルームに駆け込んで吐いた。
立ち上がったとき、トイレタンクの布カバーの上に、ダイアモンドイ
ンザローが置かれていた。サイモンは、ミートローフの残りもすべて吐
いた。ミリーは、彼女の虐殺から、この本だけ見逃したのだ。サイモン
は、本をきつく胸に抱きしめた。唯一の生き残りだった。ミリーでさえ、
レッドダイアモンドは倒せなかった。
サイモンは、トイレを出て、薄汚れたイスに行って座った。ブックカ
バーを見つめると、ブロンドの女がこっちを見返した。
本を抱えて、ひらく準備をした。本に刻印されたブックマーク。サイ
モンは、どこかの野蛮人のように、ページの端を折るようなことはしな
かった。
本のうしろにあるマーカーをはさみ、やさしく本をひらいた。そして、
お気に入りのページから読み始めた。
◇
拳銃の台尻は、床で倒れているブロンドと同じくらい熱かった。スカ
ートはめくれ、太ももが露出していた。生きてる女というよりは、死ん
だ女だった。人は死んでしまえば、美しい足もただの肉の断片だ。
彼女は、赤のブラウスを着ていた。背中の部分に、1フット角の暗い
赤の模様ができていた。それがなにを意味するかは、シャーロックホー
ムズでなくても分かった。
彼女の手はきれいで、ツメはみがかれ、着ているブラウスに合ってい
た。優等生だった。指は,すでに硬く、硬直が始まっていた。
ウィスキーの助けが必要だった。しかし味わえたのは、むなしい死の
味だった。彼女をひっくり返した。
フィフィではなかった。オレがずっと戦っていたおそれは、カウント
ダウンされた。
妹のルルラロッシュだった。もちろん犯人は、ルルがフィフィをねら
った弾丸で殺されたことを知らなかった。
オレは、落ちてたものを拾った。ブロンドではない。それは、38口
径だった。オレは、ルルもたぶんそうだったと思った。しかし、こっち
の方は硬かった。スミス&ウェッソンだった。銃口をかいだ。ついさっ
き、撃っていた。シリンダーをあけると、2発なくなっていた。1発は、
ブロンドの背中だ。もう1発は?
自殺ではなかった。農場を買おうというときに、だれが背中越しに自
分を撃てるだろうか?だれかが撃って、自殺に見せかけたのだ。オレは、
調べるべき時がきた気がした。
オレは、私立探偵だ。真相を調べる権利があった。しかし犯人は、オ
レが大事な証拠を荒らすのを喜ぶかもしれない。
汚い仕事だった。しかし、だれかがやらなきゃならない。14年もオ
レはこんなことをやってきた。保安官以外のものができることは、そん
なに多くはなかった。
オレは、拳銃を拾って、トレンチコートのポケットにすべりこませた。
この町のふたりの保安官は、そんなものは湾に放り込んでしまうだろう。
オレは、その拳銃がすぐ必要になる気がした。
◇
サイモンは、本をひざの上において、このシーンを味わった。火薬の
においがしたし、血のにおいもブロンドの香水の香りもかぐことができ
た。ダイアモンドのアゴが見えたし、報復を誓ったときの歯ぎしりも聞
こえた。
サイモンは、前に読んだときに、ルルは妹で、フィフィを訪ねてきて
悪い時に悪い場所にいあわせたことを知っていた。ロコリコの秘密を知
っていたのはフィフィで、ルルに彼女の命という代償を払わせてしまっ
た。
サイモンは、前になんども読んだので、犯人がだれかも知っていた。
しかしそのことが、読む楽しさを減らすことにはならなかった。その本
は、なんども訪れたなじみの場所だった。闇の帝王ロコリコに、なにを
期待すればいいか知っていた。フィフィラロッシュが、すべてのシーン
やタフな会話において、黄金のハートを持つことを知っていた。ダイア
モンドが、ロコの手下の裏をかいて、フィフィを助けることも知ってい
た。サイモンは、また、本をひらいた。
◇
外は雨が降りはじめた。オレはコートのえりを立てた。霧雨の冷たい
指が首筋をはった。雨は街から悪を洗い流して、帰るべき排水溝へと流
した。
壊れたカサが歩道にころがって、死にかけたこうもりのように羽をバ
タつかせていた。街灯がアスファルトの水溜りにちらちら光っていた。
オレは雨が好きだった。考える助けになった。
リコは、今夜は、宝石や毛皮やお世辞のうまい男が好きな別の女と出
かけているはすだった。死んだ女のことなんて気にもとめてなかった。
警察のこともだ。リコは警察を裏であやつれたからだ。
ラロッシュ一家には、ずっと前、スターを夢見ながら、スターには決
してなれなかった娘たちがいた。
フィフィは、逃亡中で、リコが自分の間違いに気づくのを待っていた
が、捜索犬が放たれていた。
オレは心配しながら、背中には死人の冷たい手を胃にはかたいものを
感じながら、霧雨の中を歩いていた。
フィフィは、妹が23才の成熟した年頃に殺されたことを知って、な
にができただろう?なんであれ、レッドダイアモンドが真相を解明しな
ければならないということだった。ロコリコや彼の2人の手下やかばん
持ちの警官や政治家たちが、オレを止めることはできなかった。
オレには、血のにおいがしたし、スキャンダルのにおいもした。アス
ファルトに降る雨が、それらを流し去ることはできなかった。
ロコとオレは、いつか対決する日がくるだろう。生き残るのは、どち
らかひとりだ。オレは、それがオレであることを願った。しかしオレは
いつも、大きくもうかる確率の少ない方に賭けてしまう。
キャメルに火をつけて、深く吸いこんだ。にがい煙が肺を満たし、ク
ールで青白い雲をはき出した。
◇
サイモンは、中学時代に一度タバコを吸ってひどい目にあって以来、
決してタバコを吸わなかった。しかし、ダイアモンドが火をつけると、
サイモンも吸いたくなった。
サイモンは、奇妙な頭痛を感じた。だれかと話したかった。サイモン
のぎくしゃくした考えを分かってくれるだれか。新鮮な空気が必要で外
へ出なければならなかった。
本を下に置いて、めまいがして立ち上がった。よろめきながら階段を
上がり、玄関にでた。しかし頭を外に出してもよくならなかった。マー
ブグリフィンが聞こえた。外出する必要があった。冷たい雨を気にせず
ガレージへ歩いていった。
キャブは、エンジンがまだ温まっていて、すぐにスタートした。走り
だすとタイヤが悲鳴をあげた。
初めて自分の車を持ったティーンエイジャーのように運転した。雨で
すべりやすいハイウェイを、時速85マイルで走った。ワイパーをまわ
しても雨粒が視界をさえぎった。
ほかの車は、サイモンの赤のブレーキランプが追い抜くごとにクラク
ションを鳴らした。サイモンは、下に地面のない水上飛行機のように運
転した。対向車の白のライトが、サイモンの目に反射した。
ラジオをつけてダイヤルをまわすと、グレンミラーオーケストラの演
奏が聞こえてきた。ラプソディインブルーのトランペットに合わせて、
サイモンは頭をふった。
都会に入った。歩行者は、空車のキャブが雨の中を走っているのを見
て、必死に手を振った。手を振るのは親愛からではなく、キャブに無視
されて指を立てた。
都会は彼のものだった。すべての道路の穴、すべての一方通行、すべ
ての鈍感な信号機の位置を知っていた。交通警察隊のいる場所や牽引車
が待機している場所も知っていた。クロスタウンやダウンタウン、アッ
プタウン、ミッドタウンをただ楽しむために流した。
サイモンは、いつもの景色を、形や色が変化する万華鏡を通して見た。
濡れた道路の矩形の反射。街灯の黄や赤や緑のクロム合金。
サイモンのなじみのある唯一の店は、バルモラルだった。店の前には、
キャブが停まり、明るい室内で運転手たちが食事をしていた。
夜の時間のキャブは、昼とは違っていた。彼らは、防弾パーティッシ
ョンの後ろにいて、銃やナイフやブラックジャックを携帯した。夜の客
たちのふるまいを、まねしていた。
サイモンのキャブは、ブロードウェイを北にむかい、ブスブス音をた
て始めた。34番通りでは、かぜをひいたようにせきをした。サイモン
は、車が停まるまで燃料ゲージがエンプティをさしているのに気づかず、
8番通りのポートオーソリティでエンジンは止まった。ニューヨークシ
ティのどまん中だった。サイモンは、なんとか銀行の車寄せに車を運ん
だ。かぎを掛けずに車を離れると、歩き始めた。そして、歩き続けた。
いろいろなネオンサインが点滅していた。
サイモンは、派手な映画看板の下を通った。
小男の客引きが、店の前でサイモンに入るよう声をかけた。
「いい女がいますぜ、だんな!ニューヨーク1!心は天国!」
街の女が、湿った通りでサイモンの手を引っぱってついてきた。
「寄ってかない?デート?それとも、パーティ?」
ホットパンツとミニスカートの女たちが、サイモンについてきた。
女の顔は、みんなくもっていた。サイモンは、酔ったように歩いた。
空気が薄く、肺に取り込めなかった。酸素は、どこへ行っちまったんだ?
女たちは、ペドロが夜のシフトで経験した冒険談を思い出させた。
サイモンは、街の女たちとつきあったことはなかった。街の女が、キ
ャブ代を体で払うと言ってきても、ただで乗せてあげていた。年取りす
ぎとか、太りすぎ、美人でないなどの理由で、避けてきた。どんな理由
で、サイモンと付き合いたい女なんているだろうか?サイモンは、ミリ
ー以外の女性と付き合ったことはなかった。
ミリーは、結婚したとき、サイモンが初めてではなかった。ミリーは、
10代の頃は人気があってもてたと自分では言っていた。
雨が強くなった。サイモンは、標識にもたれていた。ロングアイラン
ドに帰るべきだった。ミリーはもう帰っているだろうし、秘密の笑いを
浮かべているだろう。子どもたちも家にいるだろう。みんな不思議に思
っているだろうか?いったい、サイモンのことを考えているのだろうか?
1ミリセカンドの間、頭がブラックアウトした。標識のポールを持つ
手が、混乱の渦へ落ちてゆくことを防いでいた。
また、歩き始めた。
49番通りで、彼女を見た。ふたりの目が合った。目の前のブロンド
に、ためらいはなかった。
「フィフィ?」と、サイモン。
「それが、捜してる女?」と、彼女。「出て行ったの?」
彼女の声は、レッドダイアモンドが言っていたように、ビロードのサ
ンドペーパーのようだった。
◇
彼女は、25くらいで、成熟前のかたさがあった。赤のドレスが胸を
おおい、形はいいが驚くほど筋肉質の足を隠していた。ブロンドの髪は
雨でくしゃくしゃになって、イルミネーションに輝いていた。
しかし、フィフィは死んだ、いや、隠れている、いや、それは現実で
はない、いや━━━。
「夜どおしはいられないのよ、ハニー!」と、ブロンド。指をサイモン
の頬に走らせて。「フィフィとよろしくしたいんでしょ?」
「ロコと手下は?」
彼女は、1秒間ためらった。「あなたの旅がなんであれ、ハニー!高
くつくわよ!フィフィといっしょなら、それだけの価値はあるわ!」
「きみは死んでるんだろ?」と、サイモン。
「生きてるとこを見せましょうか?」と、彼女。腕を離して、通りを渡
った。「早く!夜どおしはいられないのよ!」
「フィフィがなぜ、ふつうの街の女のようにふるまっているのだろう?」
と、サイモンは考えた。「そうか、あれは演技だ!」サイモンは、ウィ
ンクを送った。サイモンは、演技につきあうことにした。通りには、危
険があった。ロコの手下が、巡回してるはずだった。
「わたしは最高よ!すこし高いわ。ストレートなら25ドル、ハーフア
ンドハーフなら50ドルよ。どちらにする?それとも、アラウンドワー
ルド?」
「う〜ん」と、サイモン。彼女の言うことをまともに聞いてなかった。
どうやって、彼女を家に帰すか考えていた。ミリーは、レッドダイアモ
ンドが迎えに来るまで、彼女をかくまうことを分かってくれるだろう。
ブロンドは、いつもの売り文句を繰り返した。
「アラウンドワールドがいいね」と、サイモン。「カナダには行ったこ
とがある」
「そうなの」と、彼女。笑った。「考えたこともない夜になるわよ!」
「そりゃいい!」
「世界中をめぐるのよ!フィフィといっしょに!そのまま歩いて!」
「どういう意味だい?」
「チャンスは1回きりよ!そのまま歩いて!」と、彼女。8番から51
番通りに曲がるところでサイモンの手を引っぱった。
彼女は正しかった。彼女を守るために、歩きつづけなければならなか
った。サイモンは、ロコの動きが気になった。
「ミリーに電話して、今夜はお客があることを言わなければ」と、サイ
モンは考えた。
LIDOホテルのOがピンクのネオンサインが輝いていた。LIDの
部分は点滅していた。階段はきしんで危険だったが、ふたりはまったく
気づかなかった。彼女は、その夜が5回目の仕事だったからだ。サイモ
ンは、彼女を安全に郊外に連れ出す方法を考えていた。
ホテルの案内係は、青白い顔をした青年で、ポピュラーサイエンスを
読んでいたが、フィフィが合図すると、カギのかかった2重とびらの向
こうでブザーを鳴らした。
「8番ドアがあいてます」と、案内係。視線をそらしながら。「どのく
らいご滞在で?」
「15分くらい」と、ブロンド。そして、サイモンに。「10ドル払っ
て!」
サイモンは、なにも考えずにさいふを出すと、10ドルを案内係に払
った。彼女がさいふをのぞくと、さいふには札束と緑紙幣があった。彼
女は、サイモンの腕をしっかりにぎった。
「あなた、いいショーを見れるわよ!」と、彼女。サイモンを狭い廊下
へ導きながら。案内係は、すぐに受け取った現金をカギのかかったレジ
へしまった。ふたりが8番ドアに入る頃には、雑誌の車記事に戻った。
緑の室の天井からバルブがむき出しになっていた。ベッドはイルミネ
ーションで、木のイスにしけたナイトスタンド、狭い洗面台があるだけ
の室だった。フィフィは、背後のドアをしめた。
ベッドは、乗りなれたロバの背のようだった。かつては白のシーツも
灰色に変色し、黄のしみがあった。軍支給のタオルが、ベッドのすみに
しわくちゃに掛かっていた。
室は、酒のにおいに、かびのにおい、それにやぎのにおいがした。塩
のような鼻をつく悪臭が、サイモンをファンタジーから目覚めさせた。
「聞いてくれ!」と、サイモン。「時間をムダにして悪かったが、オレ
は行かなきゃならないんだ。することがあって」
彼女は、サイモンを押してベッドに座らせた。彼女の香水のにおいは、
ほかのにおいにまさった。サイモンの両手を彼女の胸にあてて、サイモ
ンがぎこちなくさわると、声を上げた。
彼女は、サイモンの股間に手をのばした。サイモンは、まためまいが
した。
サイモンは、自制心が薄れた。こんなことは一度きりだし、だれにも
知れないだろう。
「電気を消したほうがいいかな?」と、サイモン。
「お好きにどうぞ」と、彼女。「ズボンをぬいでくれる?」
サイモンは、木のイスに座り、くつをぬいできちんとベッドの脇にそ
ろえた。
「早く!夜どおしはいられないのよ!」と、彼女。サイモンのズボンを
イスの背にかけた。
「いい男ね!」と、彼女。スイッチの音がして、室が暗くなった。
「そろそろ行くわよ!世界中をめぐるのよ!」と、彼女。不自然な大声
で。
サイモンは、それに気づかなかった。
「ふ〜」
ドアをたたく音がして、男の低い声が叫んだ。
「ポリスだ!みんな逃げろ!ポリスだ!」
「なんてこと!」と、ブロンド。「早く隠れて!クローゼットに!」
彼女は、サイモンを押した。サイモンは、おそれつつよろめき、クロ
ーゼットと思われるところへ行って、壁に頭をぶつけた。
サイモンは、めまいがして、なにが起こったのか分からなかった。ブ
ロンドは、ゴツンと音がしたところへ来て、サイモンをさらに押した。
サイモンは、手さぐりで壁をつたって、クローゼットを見つけて入り、
ドアを背後でしめた。
廊下のドアがしまる音がした。
サイモンは、クローゼットの床にうずくまり胸がドキドキした。
「フィフィが警官をうまくあしらってくれたらいいのだが」と、サイモ
ンは考えた。「もし捕まったら、ミリーや子どもたちになんて言おう?」
サイモンは、暗闇の中で待っていた。なん時間にも思えた。聞こえる
のは、自分の心臓の音と息づかいだけだった。
◇
サイモンは、ドアをあけた。室は暗かったが、すべてがはっきり見え
た。あるべきなにかが、無かった。
電気をつけて、明かりに目を細めた。
靴は、ぬいだ場所にあった。ボクサーショーツは、緑と白のリノリウ
ムの床にあった。イスの背にかけたズボンが無かった。
室のドアをあけた。廊下には、だれもいなかった。室に戻って窓をあ
け、シェードも引いてあけた。外の通りに、パトカーは来てなかった。
ブロンドは、いなかった。さいふも無かった。さいふには、93ドル
にチャージカード、運転免許証、それにいろいろなIDが入っていた。
サイモンは、狂ったように室をさがした。ベッドのシーツを裂き、マ
ットレスを持ち上げて、枕を床に投げつけた。どこにもなかった。ズボ
ンとさいふが、なくなっていた。
サイモンは、狭い洗面台に行って吐いた。ほんのすこし前にも、そん
なふうに吐いた記憶があった。
サイモンは、疲れるまで室の中をグルグル走りまわって、汚れたマッ
トレスにあおむけに倒れた。天井のひび割れをしばらく眺めてから、ベ
ッドからころがり出て、クローゼットへよろよろ戻り、ドアを引いて閉
め、床にころがった。リノリウムは冷たく、気持ちよかった。
サイモンは、床を押せば跳ねかえるように、世界がスピンしている気
がした。目の奥で、チカチカする映画が上映されていた。
レッドダイアモンド。サイモンの父。フィフィラロッシュ。ミリー。
ロコリコ。メロニー。ベニー。街の女のブロンド。ペドロ。ヨガ行者。
ショーン。ニック。
映像はスピードアップし、スローダウンし、暗くなった。小便がした
くなってトイレに行って、またクローゼットへ戻った。叫んでは、眠り、
また起きて、頭のなかで上映される映画を見た。
サイモンは、ブロンクスで過ごしたパッとしない子ども時代をしばら
く見た。頭がいいわけでもなく、強いわけでもなく、金持ちでもなく、
もてるわけでもなかった。群集にまぎれたただの顔。いつもだれかの方
がまさっていた。
サイモンは、中学時代に、決闘に使用する拳銃は38口径がいいか4
5口径がいいかということで友人と議論した。運転するゴーカートを、
ヘアピンカーブで時速80マイルに加速した。同じ中学時代に、ナオミ
という9年生の女子が黒のシルクのガターをはいていたのを思い出した。
サイモンに恥をかかせた教師たちが、銃撃を浴びて死んだ。波止場のバ
ーでエッグクリームを飲んで過ごした。サイモンは、また眠った。
3番目の映画には、ミリー、メロニー、ショーンが出てきたが、脇役
だった。ヨガ行者とキャブの仲間たちは、名場面に登場した。つぎの夢
で、サイモンは、フィフィという女といちゃついていた。
◇
声で目覚めると、クローゼットのドアの下から光が漏れていた。
「みんなうまくやってるわよ、あなた」と、女の声。若い黒人で、街の
女の声だった。
「そうらしいな、ベイビー。おまえもうまくやれてるようだ」と、男。
中年で白人、タフな男の声だった。「へっ!なんて室だ!爆弾が落ちた
のか?」
「気にしないで」と、女。「シーツがないけど、問題ないわ」窓のシェ
ードを降ろす音がした。
「街の女にしては、ずいぶんシャイなんだな!」と、男。
「暗いほうがいいと思ったのよ!」と、女。イライラしながら。「こん
なとこじゃだめ!こっちに来て!」
移動する音がした。
「ああ、強くつかみすぎ!落ち着いて!」と、女。ジッパーがあく音。
「うう、ちょっと待って!」
「準備オーケーって言ったろ!」
「あなたのズボンをイスの背にかけさせて!」と、女。「着るものをご
っちゃにしたくないでしょ?」
「どうでもいいよ」と、男。
「信用してないの?」
「8番通りで会う、25ドルの街の女をみんな信用してるさ!とくにオ
レの小物にいちいち気を使う女はな!いいかい?」
「その前に体を洗って!」と、女。
足音がした。
室のドアをたたく音がした。
「ポリスだ!みんな逃げろ!ポリスだ!」
この声は、聞き覚えがあった。しかしサイモンは、どこで聞いたか思
い出せなかった。
「早く!逃げて!」と、女が叫んだ。「ここを出るのよ!」
「からかってるのか、ビッチめ!」と、男がどなった。「やることを最
後までやれ!」
「なに言ってるの!逃げて!逃げて!」と、女。
「ギャーッ!」と、男。「噛んだな!」
殴る音がした。
「ジョーンズ!ジョーンズ!助けて!」と、女。
ドアがバタンとあいた。「手を上げろ、おっさん!」と、男の低い声。
つかみ合いの音がした。ふたりの男に女が、ののしり合ったりする声。
銃声が5発。さらに取っ組み合ったり、もがき苦しむ声。ののしり、
あえぎ、長いすすり泣く声。ため息。そして、静かになった。
サイモンは、そのあいだずっと、クローゼットの床で丸まってじっと
していた。それから静かに、ドアをあけた。
床の上に、3人倒れていた。全く違う色合いの6本の腕と足が、伸ば
したり絡みつきながら折り重なっていた。
3つの頭があった。黒人の女は口をおおきくあけて死んでいた。黒人
の男は、血だらけのアゴヒゲが短く刈り込まれていた。白人は、目をま
るくして笑いを浮かべたまま死んでいた。
ぽん引きの白のハットが、血で汚れて室のすみにころがっていた。女
のブラウスが、つかみ合いで裂けて、室じゅうに散らばっていた。ズボ
ンは床にあった。すそは、血で汚れていた。
ぽん引きの拳銃はクロム製の25口径オートマチックで、窓からの光
の筋に照らされて、床にころがっていた。それは、すばらしい道具のよ
うに輝いていた。
そのシーンのへりは、すりガラスを通したチーズケーキの写真のよう
にぼやけていた。ぼやけていても、へりは鋭く切り取られ、非現実的だ
った。血のかたまりは、気にならなかった。前によく見たシーンだ。サ
イモンの呼吸もふつうだった。タバコが吸いたくなった。
すそが血で汚れたズボンをひろい上げ、足をすべりこませた。すこし
短かったが、悪くはなかった。ポリエステルの生地はチクチクした。ベ
ッドの下から自分の靴を出してはいた。
ぽん引きの拳銃を、ポケットにすべりこませた。
「この町のふたりの保安官は、そんなものは湾に放り込んでしまうだろ
う」と、サイモンは考えた。その拳銃がすぐ必要になる気がした。
誰もいない廊下のドアを、バタンとあけた。銃声を、誰も聞いていな
かった。もしも聞いていたとしても、LIDOホテルの客は、警察を呼
ぼうとは誰も思わないだろう。ねずみ取りのわなは通りじゅうにあって、
そのひとつのわなというだけだった。ねずみシートはみんなが持ってい
て、他人の事には関心がなかった。
サイモンは、室に最後の一瞥をくれた。サイモンが見たほんやりした
映像は、ポストカードのようなものだった。「母親に送りたいようなポ
ストカードじゃないな」と、サイモンは考えた。「母親がティフアナの
安宿に家出したのでなければ」
ドアを背中でしめると、狭い廊下を歩いた。肩におもりを乗せたよう
な威張った歩き方だった。
長いあいだ、サイモンは自分を抑制してきた。今は、ジムへ行って昔
のごたごたを洗い流したかった。そう決断したのは、早すぎだったかも
しれない。しかし、バーボンの一杯は、早すぎではなかった。
ホテルのフロントを通りすぎた。案内係はいなかった。重い金属のド
アをあけて、外の階段を降りた。
レッドダイアモンドは、通りに現われた。
3
レッドは、目を細めまばたきした。太陽が目に入ったかのように、目
をこすった。タイムズスクエアの夜のネオンサインがギラついていた。
街の女たちは、最後のひと稼ぎのカモをさがしていた。ぽん引きは、コ
ークを飲みながら待っていた。どろぼうは、自分たちの場所に戻ってき
た。残りのくずたちは、わなを仕掛けたホテルや通りをブラついていた。
街の女たちのいる場所は、古い安宿のようだった。夜の暗がりで、わ
なが仕掛けられた。昼のあいだは、盲目の男にも、わなが見破れなかっ
た。
レッドは、古い友人にするように腰の拳銃に手をそえた。腰の周りに
は、脂肪がたまっていた。
めまいがして、レッドは立っていられなくなった。車に寄りかかって、
嵐のなかの若木のように体を震わせた。
女が道に立って、見下したようにレッドを見ていた。レッドダイアモ
ンドは、タイムズスクエアの街の女のように無視した。レッドは、気を
しっかりさせようとした。
「なにがあったのか?」と、レッドは考えた。その夜の記憶をはっきり
させようとした。
「図書館で、フィフィといっしょだった。数千冊の本。なにかをさがし
ていた。そのとき、ロコの女のひとり━━━ミリーかだれか━━━がオ
レをキャブに乗せた」
レッドは、記憶を整理するように、頭を手でおさえた。
キャブは、ヒューゴキャンドレスのネバダガスに出てきたようなやつ
で、ガソリンを入れて、死の旅に出た。3人いた。いや、もっとなにか
あったはずだ。ゴングはすでに鳴って、試合は始まっていた。
両手をポケットに入れると、右手が拳銃の台尻に触れた。レッドは拳
銃を取り出して、不思議そうに眺めた。
3メートル先から歩いてきた背広の男は、拳銃を手にしたレッドを見
て足早に歩いていった。
レッドは、拳銃をポケットに戻した。それは、25口径だった。女の
銃だ。フィフィに手渡されたに違いない。なんという女だ。
レッドは、店に入って、キャメルを1箱買った。
支払いを済ませてから、ズボンのポケットにあった財布をよく見た。
それは、見知らぬ黒い牛革だった。レッドがいつも持ち歩くのは、茶の
2つ折りだった。ケースには運転免許証と銃携帯許可証があった。
運転免許証の名前は、ジョンテールだった。別の名刺が数枚にテール
の名前のチャージカードに200ドルがあった。レッドは、運転免許証
の顔に見覚えがなかった。
「なにがどうなっているんだ?」と、レッドは考えた。「どこまで自分
を信じていいのか?」
レッドは、何度も打ちのめされ、ノックアウトされたミッキーフィン
チだった。最悪の状態で、頭は、ロッキーマルシアノに1週間殴られ続
けたパンチングバッグのようにズキズキした。
見知らぬ誰かに感謝しながら、タバコの箱をあけて1本くわえた。ど
うくわえてもしっくりこなかった。ロコにまつわることは、すべていい
ことはなかった。
それに、女の銃。優美なことなんてどこにもない。あるのはガッツだ
けだった。必要なものは、バーボンが満たされた1杯のグラスだった。
マッチをすってタバコの先端に火を近づけて、息をはいた。なにも起
こらなかった。それで、息を吸ってみた。
熱い煙がのどを通って、肺を焼いた。むせて、せきこんだ。レッドは
目に涙を浮かべてタバコを捨て、靴の裏で踏みつけた。
「肺が、昨夜のネバダガスのように焼けちまった」と、レッドは考えた。
「しばらく待たせておこう!今必要なのは、のどをうるおすことだ!」
シルバーシャムロックのネオンサインが気になった。ルとムロの部分
のネオンが消えていたが、たぶん、シルバーシャムロックだった。名前
でレッドが得意なことがあるとしたら、住んでる街のバーの名前だった。
ドアを引いて入ると、離陸しようとするジェット機ほどでないジュー
クボックスの爆音が、レッドの鼓膜にぶつかってきた。女が歌っていた。
それを、歌と呼ぶとすればだが。ドラムの音にあわせようとして、女は
息切れしていた。ハリージェームズではなかった。
バーは、ジミーウォルターがニューヨークマラソンを走った記念に作
られたかのようだった。今、室内は暗く、床のゴミが見えなかった。暗
くなければ、バーのオーク材に刻まれた名前も読めただろう。客がつけ
た名前ではなかった。
バーのすみでは、2人の中年の男性がビールを飲みながら、下を向い
てブツブツ言っていた。こんなふうなささやきを、レッドは前にも見た
気がした。犯罪者がするように、遠くからでは話しているようには見え
ないように、ブツブツ言っていた。どこのバーでもよく見るように、彼
らは、銀行強盗や電気店からテレビを盗むやり方をささやいて時間をつ
ぶしていた。
客の残りは、20代の若い黒人たちだった。通りで彼らを見かけたら、
なにをしているのかすぐ分かった。ピンクのスーツにダイアモンド付き
のカフス。つば広ハットに、コートのえりは毛皮、靴はピカピカでチッ
プをはずむやからは、ぽん引きだった。とるに足らないざこたち。吹き
出物。
テーブル席に、2人の女がいた。雰囲気は40才くらいで、ホットパ
ンツをはいていた。女はコークを飲んでいた。
「年齢からすると、酒を飲める年頃だが」と、レッドは考えた。「ぽん
引きは、自分の商品を大事に扱いたいらしい」
レッドがカウンターのイスにつくと、バーテンダーが来た。中年で、
ダニーボーイのようなアイルランド系の顔立ちで、鼻には殴られたのか
テープを貼っていた。
「バーテンダーには」と、レッドは考えた。「客を選ぶ権利がありそう
だ」
「最初に、バーボンをくれ!」と、レッド。
バーテンダーは、なにも言わずに、酒をついだ。
レッドは、1ドル紙幣を5枚、カウンターに置いた。
「初顔だな」と、バーテンダー。
レッドは、うなづいたが、なにも言わなかった。バーテンダーは、し
ばらく間をおいてから、カウンターをふき始め、レッドから離れていっ
た。
◇
まだ、話す時間ではなかった。レッドは、頭を整理する必要があった。
それにロコの手下が、どこをうろついているかも分からなかった。バー
ボンでのどをうるおしてから、周囲の会話に耳をすませた。
「つまり、あの女は分からせる必要がある」と、やせた若者。緑のチェ
ックのスーツを着て、ジェスチャーのたびに、指の装飾をギラつかせた。
「そう、あの女は追い払う方がいい。さもなければ、ずっとつきまとわ
れるぞ」
「そうか!」と、もうひとりの若者。金のイアリングにえび茶の服。
「前にもあんな女がいた。1晩に10人か12人の客がいたが、そいつ
は数をごまかそうとするので、クビにしてやった」
レッドは、自分のバーボンに戻った。前にしていた仕事のことを思い
出した。それは、ぽん引きを狭い室に投げ込むような仕事で、ぽん引き
のカネ目当てに多くの男たちが働いていた。やつらは、通行税と呼んで
いた。
仲介人、カフス上の取引き、ぶらぶら歩き。それは、とても悪く、直
す必要があった。水、悪い水で、橋の下を流れていた。
「バーボンのお代わり!」と、レッド。
バーテンダーは、レッドが考え事をしているあいだに、カウンターの
レッドの5ドルから1ドルをとっていた。バーボンの追加を持ってくる
と、もう1ドルとった。
仲間と同じギラギラした服の身長6フィートでやせた男が入ってきて、
バーのすみに行った。動きはすばやく、鼻でかわすようなかんじだった。
「よう、ブラッド!」と、緑のスーツ。「どこにいたんだい?」
「ピュー!ピュー!」と、ブラッド。トレーナーが笛を吹くようなジェ
スチャーをした。
「なにか分け前は?」と、緑のスーツ。
ブラッドは、頭を振った。「しかし、新しい雪女をつかまえたぜ」
ブラッドは、2・3歩さがってドアをあけると、女が入ってきた。
彼女のブロンドの髪はバブルカットで、5・5フィートのフレームを
3インチ上げていた。ナイスなフレームは、肌にピッタリのブラウスと
ミニスカートに包まれていた。年は22くらいで、ほめてくれる男には
無関心という目をしていた。
緑のスーツと金のイアリングが口笛を吹くと、ブラッドは、ほほえん
だ。
レッドは、市場の新鮮な肉を見るように彼女を2度見した。そんなこ
とがありえるだろうか?彼女には、安っぽいバーにまったく似合わない
非現実的な輝きがあった。
「フィフィ?」と、レッド。誰にも聞こえない声でつぶやいた。レッド
は、彼女が話したくないようなこともして、落ちぶれていった過去を知
っていた。レッドは、彼女を見つめた。顔つきは少し違っていた。体と
髪はそのままだった。
「なに見てんだ?」と、ブラッド。
一瞬レッドは、話しかけられたことに気づかなかった。レッドは、ブ
ラッドを無視した。
ブラッドは、レッドに近づいた。緑のスーツと金のイアリングは、ニ
ヤニヤしていた。フィフィは、あきあきしているように見えた。
「ケンカはやめてくれ!」と、バーテンダー。彼は、ブラッドの凶暴な
性格を知っていた。
「ケンカなんかしないさ!」と、ブラッド。「やつに、オレのレディを
じろじろ見たことをあやまってもらいたいだけさ!」
緑のスーツと金のイアリングは、声に出さずに笑った。フィフィは、
自分のツメを見ていた。
「よう、聞こえてんのか?あやまったらどうだ?」
ブラッドの周りから、客は離れ、何人かはシャムロックを出て行った。
ブラッドは、レッドに無視されてカッカしてきた。
「おい、オレの言葉を聞いてんのか?」
ブラッドは、レッドにナイフが届く範囲まで近づいた。声に危険な震
えがあった。
レッドは、バーボンから目を上げて、ブラッドを見て言った。
「オレは、おまえがあこがれるようなラストヒーローなのさ」
そして、目をバーボンに戻した。
ブラッドは、手をレッドの肩に置いた。「どういう意味なのか?」
「手をどけてくれないか?」と、レッド。
ブラッドは、手を後ろに引いて、レッドのあごをねらったパンチを打
った。レッドは、体をまわしてパンチをかわすと、ブラッドが2発目を
繰り出す前に、イスから降りて向き合った。
レッドは、ブラッドの2発目を右手でブロックして、左手で半分残っ
ていたバーボンをブラッドの顔に浴びせた。ブラッドが目をこすってい
る間に、腹を2発打ち、さらに、アゴに1発打つと、ブラッドは床に倒
れた。
「名前は、フィフィ?」と、レッド。ぼんやりした表情を浮かべている
女に聞いた。
「そうだったかも?キャンディ、トリクシー、ローラとか」
彼女の声は、まったくフィフィに似てなかった。ケンタッキー訛りが
強かった。
ブラッドはうめき声をあげ、緑のスーツが来て助け起こした。レッド
は、目のすみで見ていた。バーテンダーは、カウンターの下に右手を入
れていた。
レッドは、カウンターに座った。女は、隣に座った。
「どこかで会ったかしら?」と、女。レッドの足に手を置きながら。
レッドは、態度を急に変える人間を知っていた。しかし、この女はフ
ィフィだろうか?どこか安っぽさ、感情のなさがあった。たぶんそれは、
ドラッグのせいだ。彼女は、まるでゲームであるかのようにふるまった。
レッドは、時を見計らって動きだした。ブラッドは、ジャケットの下
に手を入れた。
「さいふを出そうというのでは、ないらしい」と、レッドは考えた。
「オレのすそをつかもうとしてるのか?それにしても、オレの動きはの
ろすぎる。ブラッドに着くまで1時間はかかりそうだ!」
そのとき、緑のスーツと金のイアリングが床をけった。女がドアに近
づいた。ひとりが姿を隠し、バーテンダーは、カウンターにかがんだ。
レッドは、ブラッドをつかもうとしてよろめいた。レッドの225ポ
ンドの体は、150ポンドのブラッドにぶつかって、ふたりとも倒れた。
ブラッドの手の銀のオートマティックが暴発してカウンターの後ろの鏡
が砕け散った。
レッドがブラッドのてっぺんをころがすと、ブラッドから空気を抜い
たように、重力が仕事をしてくれた。ブラッドは抵抗するひまもなく、
レッドに簡単に拳銃を奪われた。
「あんたの親切を朝食にさせてもらう」と、レッド。ブラッドを助け起
こしつつ、ブラッドの拳銃は、持ち主に向けたまま。「ランチの前には、
あんたに吐いちまうだろうが」
「腕がなまったようだ」と、レッドは考えた。「オレのアッパーカット
から、もう回復してやがる!」
バーテンダーは、カウンターの下から銃身を短く切った醜いショット
ガンを構えた。レッドに向けているようにも見えた。
「こっちに向けないでくれ!」と、レッド。「バーボンのお代わり!前
のはムダにしちまった!」
バーテンダーは、スマイルを浮かべてレッドの前にお代わりをおいた。
レッドの紙幣から代金をもらわなかった。
◇
レッドは、バーボンをすすった。カウンターの後ろの鏡に残った破片
には、緑のスーツがブラッドを助け起こして、バーを出てゆくのが見え
た。ほかのぽん引きもついていった。
「ムダな出費をかけちまったようだ」と、レッド。
「いつものことです。トイレは少しそうじがいりますが」と、バーテン
ダー。「あいつらは、なんにも注文してない」
「女はどこへ?」と、レッド。
「今夜は、ストリップショーに出るんでしょう」と、バーテンダー。
バーの奥でビールを飲んでいたやせた若い黒人は、唯一のほかの客で
あったが、レッドのところまで歩いてきた。
「ここ、いい?」と、彼は言って、レッドの返事を待たずに隣に座った。
「お好きに!」と、レッド。バーボンをすすってから、バーテンダーに
言った。「カネが入ったら、鏡代を払うよ!」
バーテンダーは、苦笑いしながらうなずいた。
レッドは、空中を見ながら考えた。「なにかしてカネを稼がねばなら
ない。しかし、なにを?ロコを捜して、車を流す?ロコはすべての背後
にいて、オレは、鏡代を心配しなくてはならない!」
「すこし眠る必要があるな」と、レッドは考えた。「酒もタバコも控え
て。ロコはパーティをするだろう。汚い仕事のために、強力な軍隊を持
っている。オレには、この両手以外に信用できる仲間もいない」
レッドは、隣の若い黒人の視線を感じた。
「なにかお気に入りのものでもあるのか?それとも、ただのウィンドウ
ショッピング?」
「あなたはいい動きをしてる」
「もうおいぼれだよ!動きがいいように、見えただけさ!」
若い黒人はうなづいた。「出身はどこ?」
「いろいろさ、いろいろ」
「初めてあなたを見たとき、警官だと思った」
「かつてはな。遠い昔さ!」レッドは、ゴミが付いてないかグラスを調
べた。
「12年前のことだ」と、レッドは、つぶやいた。「仕事で街の酒場を
なん軒も調べていた。イーストサイドのルーシーの安宿で、太ったニッ
キーを見つけた。ニッキーは、4発撃たれていた。オレは表彰されたが、
相棒を失った」
レッドは、水晶玉で占うジプシーのように、バーボンのグラスを覗き
込んだ。レッドのつぶやきは、感情的で大声になった。
「パトロール中でのことだった。ニッキーは、いくつもの州で指名手配
されていた。凶悪な銀行強盗犯だったが、宿代を払わなかったために安
宿で殺された。
いくつかの事件があった。そのうち、オレはデカと呼ばれた。安全を
求めて住まいを転々とした。数年はそこに、数年はハーレムや、チャイ
ナタウンや下町のイーストサイド。オレは、考えていることをみんなに
話す習慣を身につけた。これは、間違いだった」
レッドの話に、バーテンダーと若い黒人は耳をすませていた。
「オレは、悪ともうまくやる。これはもしかしたら間違いかもしれない。
金持ちになる一番いい方法は?オレはゲームを始めなかった。みんなは
安全にものごとを始めるだろう。オレの相棒は、どうなっているのか話
してくれない。それで、オレはまだゲームを始めてない。
誰かが、オレは警察の内部調査員だといううわさを流した。警察内部
の話だ。なん人かは、オレが穀物列車を転覆させるつもりだと考えた。
オレを酔わせて吐かせようとしたが、オレはちゃんと正義というカバン
を持つことになった」
レッドは、目の前のバーボンを一気に飲み干した。バーテンダーは、
すぐにお代わりをレッドの前においた。
「今は、なにを?」と、若い黒人。
「ちょっとしたこと。その辺で聞き込みをしたり、かぎまわったり。分
け前。誰かが、場所代を取ろうとしたら、そこにはロコの影がある」
「ロコってだれ?」と、バーテンダー。
「だれとも言えない。しかし、ロコは、この街のすべてを仕切っている。
どういう人物かほとんど分かっていないが、汚いカネにはすべて関わっ
ている。物事の背後にかならずロコがいる。オレはなんどもロコに危な
い目にあわされた。ロコはニュージャージーのどこかのマンションに住
んでいる。オレはいつか安酒を飲まされて、宿もなく、仕事もなく、カ
ネもなく、朝を迎えることになる」
バーテンダーは、自分の人差し指で頭の横で円を描いていたが、レッ
ドは気にしなかった。
「オレはスウィート、あんたは?」と、若い黒人。
「レッドダイアモンド」
「仕事が必要か、レッド?」
レッドは青い目で、スウィートを見つめた。スウィートは、きちんと
した服装をして、ヒゲもきれいにそっていた。
「どう思う?」
「オレは、ちょっとしたビジネスをしている人のもとで働いている。あ
んたの助けになるかも」
「オレは、街の女を使ったり、ドラッグ取引はしない。幸運にはすがり
たいが、オレにもやり方がある」
「オレもだ」と、スウィート。スウィートの声は、恩着せがましく偽善
的になったが、レッドは気づかなかった。朝食代わりに飲んだバーボン
がきき始めていた。
「ほかのうじどもも、とっ捕まえた!」と、レッド。
スウィートは、レッドを立たせた。「いっしょに行こう!」
「お好きなように!」と、レッド。
スウィートは、バーテンダーに言った。「ブラウンさんが鏡代を払いま
す」
バーテンダーは、疑わしそうだったが、うなづいた。
「迷惑かけたカネは、自分で稼ぐ」と、レッド。スウィートに、ぽん引
きの拳銃を渡した。「これを売って、鏡代にしてくれ!」
「オーケー」と、スウィート。スウィートは、レッドにはハスラー気質
が欠けると感じた。
「ブラウンって誰だ?」と、レッド。ふたりは、陽ざしの中へ出た。
「ボス。あとで紹介する」
レッドは、なにも言わなかったが、背を少し高く見せようとした。肩
をいからせて、もったいぶって歩いた。
用心深く目を細めて、青空を見上げた。
いい日になりそうだった。
4
街角のコーヒーショップで、ジャワコーヒーの最初の一杯が注がれて
いた。磨かれたばかりのグリルで作られるベーコンエッグのおいしそう
なにおいが、家庭的な店から漂った。
1日の最後なら古い油やタバコのにおいだったろうが、レッドとスウ
ィートが向かった朝は、新鮮なにおいがレッドの空腹を刺激した。
レッドは、太ったウェイトレスが運んできた、ベーコンエッグとトー
ストを2枚食べ終わるまで、なにもしゃべらなかった。ウェイトレスは、
レッドからお代わりとコーヒーを追加されて微笑んだ。
「ブラウンという人は、どんなビジネスをしてるんだい?」と、レッド。
お代わりを食べ始めると、尋ねた。
「不動産関係」と、スウィート。歯を見せてニヤニヤしながら。「ボス
のビジネスをそれほど長くは続けるつもりはない」
「しかし、全部話してくれないか?」
「ルールがいくつかあって、ルール1は、いっさいしゃべるな。取引の
内容も分からないし、あんたがどこから来たかも知らないが、それでい
い。なぜなら、あんたは十分ジャイブしてるから」
レッドは、ジャイブの意味が分からなかったが、スウィートは明らか
にいい意味で使っていたので、尋ねなかった。ジャイブは、自然なかん
じに思えた。
「それで、ブラウンさんはオレにどんな仕事をくれると思うかい?」
「ボスはまだ、あんたのことを知らない」と、スウィート。「すぐに紹
介するが、興味は?」
「今日は、まだ、ほかに仕事がない」と、レッド。皿から最後の一口を
たいらげながら。
スウィートは、朝食代は自分がもつと言ってきかなかった。レッドは、
強くは逆らわなかった。食事は、すべてスウィートのおごりになった。
レッドは、スウィートが好きになった。ただ、調子がよすぎるので完全
には信用できなかった。レッドは腹がすいていて、スウィートのおごり
で新鮮な朝食にありつけた。
「ホテルに1室用意する」と、スウィート。コーヒーショップを出ると
言った。「そこでゆっくりシャワーを浴びて、ひと眠りして。今夜、ブ
ラウンさんに会いに行こう!」
インタウンホテルに近づくと、眠るというアイデアは抵抗しがたいも
のになった。レッドは、ロビーへの6段の階段を、足をひきずるように
あがった。
ロビーでは、ふたりの老人が古い白黒テレビを見ていた。このホテル
の経営者は、老人たちが自由にテレビを見れるようにロビーを開放して
いた。鉢植えの大きな植物も、テレビを見る老人たちのように、どこか
不健康に見えた。すべては日々良くなりつつあったが、それは時々刻々
というよりは、日々の速さであった。
レッドがロビーを見ているあいだ、スウィートはホテルのフロントと
話した。ホテルのフロントは、疲れた目をしたヒスパニック系のやせた
男性で、スウィートの話にうなづいた。
「6時に戻る」と、スウィート。レッドに室の鍵を渡しながら。
エレベーターは、レッドの階までやっと上がり、レッドは室になんと
かたどり着いた。廊下のカーペットのかびのにおいが、鍵を鍵穴に入れ
るまで、レッドを眠りから防いだ。
レッドは、室に入るとドアを蹴って閉めると、バタンという音が終わ
るまでにベッドでいびきをかいて眠っていた。
◇
レッドは、カサブランカ空港にいた。フィフィの乗った飛行機の光が、
空気中の細かい霧を照らしていた。「時の過ぎ行くままに」が空港ロビ
ーに流れていた。ミリーがいて、出発の合図を求めていた。合図は、ペ
ーパーバックの本に隠されていた。ミリーは、レッドから本を奪いとり、
飛行機はレッドを乗せないまま飛び立とうとしていた。ノックの音でレ
ッドは目覚めた。
枕の下の拳銃をつかもうとしたが、なにもなかった。眠っているあい
だに盗まれたのか?
前日のできごとがよみがえった。夢とおなじくらい不確かであいまい
だった。ポケットにあった25口径をつかんで、ドアへ歩いた。
「だれだ?」
ロコに居場所が見つかったのか?レッドダイヤモンドは、場末のホテ
ルで死ぬ運命だったのか?
しかし、ロコの手下ならノックはしない。レッドはドアをあけた。
だれもいなかった。床にトレイが置かれていて、ヘアブラシに安全カ
ミソリ、マウスウォッシュ、新しいシャツに下着があった。レッドはト
レイを中に入れてドアをしめた。
レッドは、自分の不精ヒゲの顔を見てから、受話器を上げてフロント
にダイヤルした。
「今何時だ?」
「ダイアモンド様、起きられました?」と、ホテルのフロント。
「ああ、今何時だ?」
「ちょうど5時です。スウィートは、あなたを6時までにしたくさせる
ように言ってました」
「そのようだ。ありがとう」
「ええ、ブラウン氏がこのホテルのオーナーです」
「1時間で、スーツをプレスできるか?」
「ええ、手配させましょう」
レッドは、ボーイが来る前に、拳銃をマットレスの下に隠した。レッ
ドは、バスローブに着替えて、来ていた服をボーイに手渡した。
ボーイは、白髪の老人で背を曲げた姿勢をしていた。レッドは、服を
渡すときに、5ドル紙幣を出した。
「女が必要で?」と、ボーイ。新聞の売り子のような声で言った。「そ
れは、ボスがいい顔しません」
「いや、ボスについて教えてくれ!」と、レッド。
ボーイは、紙幣に手をのばしたので、レッドは、紙幣を離した。「ブ
ラウン氏についてだ!」
「彼は、ここのようなホテルをほかに2つ所有してます。6軒のバーと
かいろいろです。宝くじのノミ屋から始めて、名声はいいものばかりで、
タフな仕事もありますが、悪いうわさはありません。ドラッグに関わり
がありませんし、ギャンブルもしません。いつもソフトな仕事です」
レッドは、5ドルをボーイのしわくちゃの手につかませた。ボーイは、
それを靴の中にしまい、レッドに歯を見せて笑うと、服を持って出て行
った。
5
スウィートは、レッドとカーブに立って、激しく手を振ってキャブを
止めようとした。
「このキャブめ!」と、スウィート。「黒人を乗せる時間もないのか!」
「そう、責めないでくれ!」と、レッド。「つまり、オレが心配してる
のは、見られたり、そんなことがあったら━━━」
スウィートは、言葉を言い間違えているレッドを見た。
シティカーサービスのビュイックが止まった。
「乗るかい?」と、いかつい顔をした黒人の運転手。
「ジプシーには用はない!」と、レッド。
「つまり、イエスという意味です!」と、スウィート。ドアをあけて、
レッドをにらみつけた。
レッドは、いやいやながら乗り込みまっすぐ前を見ていた。運転手は、
バックミラーでレッドの様子をうかがっていた。レッドは、居心地悪そ
うだった。
スウィートも、ぼんやりした笑顔で黙ったまま、そわそわするレッド
を見ていた。
コロンバスサークルの北、数ブロックでキャブを降りると、スウィー
トは料金を払い、ブラウン不動産と窓に書かれた店の前まで、レッドを
連れて来た。
赤毛の胸の大きな秘書が、ふたりにあいさつした。
「お待ちしてました。中へどうぞ!」と、秘書。
秘書は、レッドにウィンクされたが気にするそぶりはなかった。レッ
ドは、女の扱いにはなれていたが、よくからかったりしてスリルを味わ
った。スウィートは、レッドの腕をぐいと引いて奥のドアへ向かった。
秘書が机のブザーを鳴らすと、スウィートはドアをあけた。
室は、すべてがブラウンで、木目の壁も、厚いカーペットも、フット
ボール場よりは広くはない机も、テーブルも、手彫りのイスも茶色だっ
た。机の後ろの革張りのイスに男が座っていた。
太い首が、広い肩を包むカスタムメイドの茶のスーツから突き出てい
た。まるでレモンを絞って飲まされているような顔をしていた。渋い顔
は、レッドを見ているあいだ変わらなかった、
「こいつが言っていた男か?」と、ブラウン。砂利を紙やすりでこすっ
たような声だった。「それほどのやつには見えん!」
「モデルをお捜しなら、場所を間違えたようだ!」と、レッド。「秘密
諜報員だったんで、ウェールズ王子には見えないのさ!」
「ブラウンさん、これがレッドダイアモンドです!」と、スウィート。
レッドは、1歩前に出て、手をさし出した。ブラウンは、無視した。
「ボディガードの経験は?」と、ブラウン。
「ああ」
「ふつうのセキュリティ?」
「ああ」
「探偵は?」
「ああ」
「道とかも詳しい?」
「ああ」
「よし、だいたいは分かった。オレについて知ってることは?」と、ブ
ラウン。イスに深く座った。
「オレをここへ連れてきたスウィートを雇っている。ついでに言うと、
カーペットを新しくする余裕がある。ホテルを他に2つ所有していて、
いくつかのバーも。かつては、宝くじのノミ屋だった。やりかたは、常
にクリーンで、フェアだと言われている」
スウィートは、まるで先生がスペルのテストでいい点をとった生徒を
見るように、笑いを浮かべていた。
「おまえが教えたのか?」と、ブラウンは、スウィートに訊いた。
スウィートは、頭を振った。
「どこで知った?」と、ブラウン。渋い視線を、レッドに向けた。
「あっちこちで、ちょこちょこと。もしもバラしたら、誰かにうらまれ
る!」
「保証しますが━━━」と、スウィート。ブラウンから波が来て、スウ
ィートを黙らせた。スウィートは、ポケットからキャンディを出して、
チョコレートのようにガリガリかじり始めた。
ブラウンがレッドを見ているあいだ、かじる音だけが室に響いた。
「室は防音に違いない!」と、レッドは考えた。通りのブレーキやクラ
クションの音が、はるか遠く、ネコのツメ音のようにしか聞こえなかっ
た。
見つめあいが続いていた。ブラウンは集中していたが、レッドはあき
てきた。スウィートは、チョコバーの包みを破いて食べ始めた。
ブラウンは、ニヤリとした。「よし、雇った!週500ドルに、経費
は別。今夜から!よければ、いっしょにがんばってくれ!」
レッドが手をのばすと、今度は、ブラウンはしっかり握り返した。
6
「今夜、2軒見回りに行きます」と、スウィート。通りに立ってる時に
言った。「なにか分かるかもしれません」
「ホテルの1室でボーッと見ていたのは、埃だらけの長イスさ」と、レ
ッド。タバコを吹くと、ハーレムのジャズホールの周りで地面を蹴って
遊んだ時のことを思い出していた。北を向いていたが、サックスの低音
や女たちの笑い声、酒をつぐ音が聞こえる気がした。
カーブで黒人のジプシーキャブに乗り込むときに、レッドはタバコを
投げ捨てた。ふたりは黙ったまま、キャブは、アムステル通りまで来た。
イエローキャブは見当たらなかった。
「87番通りにある道路の穴に気をつけろ!」と、レッド。
「なんですって?」と、中年のハイチ出身の運転手。そのときキャブは、
大砲の穴くらいの深さのクレーターに乗り上げてバウンドした。
「今のやブロードウェイと23番通りにあるやつに気をつけてないと、
そのうちサスペンションがイカれる!」
「どうして穴のことを知っている?」と、スウィート。
「それは」
「それは?」
「ただ、それはさ」と、レッド。窓の外へ顔を向け、夜の通りを見るふ
りをして、混乱した表情をスウィートに気づかれないようにした。
キャブが北へ行くほど、通りにいる上品ぶった顔は少なくなった。茶
のレンガ造りも少なくなった。通りに停められた輸入車は、派手な高級
車に置き換わった。高級そうな惣菜屋は、あぶらぎったリブステーキ屋
に道を譲った。通りの番号が3桁になると、たまに現われるオンボロ車
や板で囲まれた借地が目立ちはじめた。
多くの肉体労働者たちが暮らしていて、夜になると街の女や詐欺師や
ヘロイン中毒者が出てきた。
レッドは、ポケットに手を入れて銃に触れた。38口径がないことは
不安だった。あるのは25口径で、同じではなかった。なにがどうなっ
ている?レッドは、ジプシーキャブの後部座席で息が詰まリ、叫び出し
そうだった。車を停めてくれと言おうとしたとき、車は停まった。
「おい、大丈夫か?」と、スウィート。車を降りるときに訊いた。「顔
が真っ青だぞ!」
レッドは、ジャブをかわした。「たしかに青白いかもな」と、レッド。
ニヤリとして。「それは、白人の代償さ!」
スウィートは笑い、ふたりは、騒々しいバーへ入った。
天井にある赤の光が、踊りの渦や客の暗い顔にわずかな光を投げかけ
ていた。消防法の収容人数を、軽く20人は越える客がいた。みんな、
ジュークボックスのヘビーなソウルビートに合わせて、体をゆすってい
た。
スウィートは、バーテンダーのところまで行って、なにかを叫んだ。
客は、ほとんどが20代後半か30代前半で、すべて黒人だった。何
人かは、猟犬か紙幣コレクターのような視線でレッドを見た。
「景気はどうだい?」と、スウィート。バーテンダーに叫んだ。
「上々さ!」と、バーテンダー。ニヤリとすると、金歯が2つ見えた。
「2分で用意できます。今、ジミーが数えています!」
「ああ、手助けしてこよう」と、スウィート。そして、レッドを指さし
て。「相棒に、欲しがるものを飲ませてやってくれ!」
スウィートは、ソウル音楽に合わせて、知り合いの背中を叩きながら
客の中に消えた。
「バーボンのコーク割り!」と、レッド。
バーテンダーは、ドリンクを注ぎ、なにも言わずにレッドの前に置い
た。
レッドは、ひと口味わったとき、朝からなにも食べてなかったことに
気づいた。隣の男を飛び越えて手をのばすと、ボウルからプレッツェル
をひとつかみいただいた。
隣の男は、コーンローヘアのかわいい若い女と話していたのだが、前
に伸びてきた白人の手を見て、話すのをやめて、レッドをにらみつけた。
「ここには、白人の店員はいない」と、男。
「ああ、オレは店員じゃない」と、レッド。
男は、おもしろくなさそうにみえた。背はだいたいレッドくらいで、
やせていたが肩幅が広かった。ソフトな鼻をして、耳はカリフラワーだ
った。
「こいつは、ボクシングのリングに何回か立ってるな」と、レッドには
分かった。男は、トラブルを起こしそうに見えた。
「すぐにキャブを呼んで、早いとこ、ここからトンヅラしよう!」そう、
最初に思いついた。「しかし、オレは、レッドダイアモンドだ!私立探
偵だ!もっと悪い状況は、いくらもあった。マルセイユのバーでは、フ
ランス人にけしかけられた3人のナイフ使いに殺されかけた。アリゾナ
の渓谷では、6人の鎖を持った殺し屋たちに追い回された。ロコのふた
りのヒットマンにも撃たれた」
ロコのことを考えると、アドレナリンが一気に体じゅうに噴出するの
を感じた。
「今すぐこんなバーを出て、フィフィとロコを捜しにゆくべきだ!」と、
レッドは考えた。「ハーレムバーでケンカしてる場合じゃない!しかし、
捜すにもカネは必要だ!そのために、オレはここにいる。やっかいなヤ
ロウにからまれそうだ!」
「おい、聞いてるのか?」と、男。「気に食わねェツラしやがって!」
コーンローヘアの女は、男の肩越しに見ていたが、あきあきした表情
だった。しかし、女の目にはかすかな激情のきらめきがあって、獲物に
襲いかかるヘビのように、舌を唇のあいだで動かしていた。
レッドは、こんなシーンを前にも見ていた。リングサイドに座って試
合を見て、ボクサーが互いに相手をやっつけるのを期待する連中だ。連
中にとっては、誰が勝とうがどうでもいいのだ。血のにおいが、シャネ
ルの5番だった。レッドは、男が手加減しないことが分かっていた。も
しもやらなければ、彼女にフラれるからだ。
「オレも自分のツラが気に入らない」と、レッド。「たいしたもんじゃ
ないが、これが親からもらったすべてさ!」
「顔の形を変えてやるよ!」と、男。後ろに下がって、左肩を少し落と
し、レッドが立ち上がれるようにした。
男の顔が、1枚のステーキ肉のように見えたとしても不思議はなかっ
た。もしもボクサーがリング上のようにパンチを繰り出したら、レッド
は画学生が描くパンチングバッグのようになっていただろう。
レッドは、自分と男の間にバーのスツールを置いて、男のリーチくら
いのところにいた。男は動いて1歩踏み出した。レッドは、体をひねっ
て、男の鋭いパンチの届かない距離に移った。男は、また1歩踏み出し
た。男と目が合った。レッドは、レフェリーの警告を待っていた。
コーンローヘアの女は、息をひそめていた。他の客たちは、銃声で終
わるのを期待するかのようにささやいた。
「こんな暗い場所で、どんなやつらがやられたのだろう?」と、レッド
は考えた。「暗い路地で踏みつけられ、腹を打たれて、這いつくばって。
殺されるよりは、殴られた方がいいだろう。痛みは、生きてる証だから
だ!」
レッドの目に恐れがないのを、男は見た。もしも男がケンカを始めれ
ば、結果がどうなろうと、レッドは最後までやることが分かった。男は
ぶつぶつ言い始めた。自分から動かなければならなかった。
後ろから腕がのびてきて、男の筋肉質の肩をつかんだ。
「やつを許してやってくれ!」と、スウィート。低いが鋭い声で。「や
つは、ブラウン氏に雇われてる!」
男は振り返って、スウィートに気づくと顔をしかめた。
「ああ、そうなのか」と、男。また振り返ると、がっかりしてる連れの
女を見た。
「もう行くわ」と、女。「待ってる客がいるのよ!」女はイライラして
出ていった。
スウィートは、レッドの横のスツールに腰掛けた。
「ごたごたをすまない!」と、スウィート。
「問題ないさ!」と、レッド。ドリンクを飲みほした。
ふられたボクサーは、さびしそうにビールのジョッキをすすった。飲
み干すと、ジョッキの底を見た。
「もう1杯!」と、レッド。
「なんだって?」と、男。
レッドは、バーテンダーを呼んで、男の空のジョッキを指さした。ジ
ョッキにはビールが注がれた。
「女さ!」と、レッド。笑いを浮かべながら。「別の女とうまくやるの
さ!」
ボクサーも笑おうとした。
「オレは200人は女を見てきたが、さっきの女は、男が血だらけにな
るのを見たがるタイプさ。男の金を盗んで、親友と逃げてしまうタイプ
さ!」
「分かるのか?」と、ボクサー。ジュークボックスに誰かがコインを入
れて、ディスコソウルがやかましく響きだした。ボクサーは、スツール
をレッドに近づけた。「今までもそんなふうに?ボクシングの経験があ
るのか?」
「数え切れないくらいリングで気を失ったよ!」
「それにしちゃ、顔に傷が残ってないな」と、ボクサー。レッドの顔を
調べた。「どんなふうに?」
「ラッキーなだけさ。出血はよくした。2年くらいさ。オレのマネージ
ャーはやり手だった。イタリア野郎とやったときは、アッパーカットを
食らって、マックトラックにひかれたみたいに耳がガンガン鳴った!」
レッドは、右のこぶしで左の手のひらをたたいた。
ボクサーは、ニヤリとした。「そいつは、知ってるかもしれない。フ
ィリーで一度見た」
「フィリーで?」と、レッド。
「2週間前だ」
「私立探偵をやっていた頃、あの町へ行った。ある日、少女誘拐事件で
警官がやって来て、朝早く起こされた!」
ボクサーは、話の続きを待っていた。
「署長がこの件にからんでいた」と、レッド。「事件は最初、単純に見
えた。ほとんどの事件がそうだったように」
スウィートとバーテンダーは、片肘をついて聞いていた。
「依頼人の女が、事務所を訪ねてきた。赤のドレスの赤毛の女で、目を
そらすのを忘れるくらいの美人だった。唯一、緑だったものは、女の目
だけだった。話し方がゆったりしていて、内容を理解するのに2日くら
いかかりそうだった」
「それで?」と、ボクサー。
「女の依頼は、とても簡単なことで、幼い娘を捜すだけだと言った。娘
はまだ12才で、2日前にいなくなったそうだ。写真を見ると、顔は、
かわいいが、いたずら好きでトラブルを起こしそうだった」
レッドの近くのテーブルの客たちは、遠くから首を伸ばして、レッド
の話を聞いていた。
「家出人捜しは、とるに足らない仕事だった。たいていは、娘はボーイ
フレンドの家にいて、真実の愛を見つけたと思っている。しかし今回は、
写真を見せて、若者に聞き込みをすると、娘には数人の仲間がいること
が分かった」
6人がレッドの周りに集まってきたが、レッドは自分の話に夢中で気
づかなかった。
「10ドルくらいの経費で、娘はフィリーにいることが分かった。見知
らぬ町では、聞き込みもままならない。石を蹴って、方向を知るような
もんだ。娘が滞在した安宿へ行ったが、室で見つけたのは殺された男で、
その男はろくに服も着ないで、ネクタイピンのあるべき場所に、ステー
キナイフが刺さっていた!」
音楽が大音量になった。
「なんて音だ!」と、男が叫ぶと、別の男がジュークボックスのプラグ
を引き抜いた。2ダースの耳が、レッドの話の続きを待っていた。
「殺された男は、市会議員だったことが分かった。保守的タイプで、必
要がなくても、週に2回は教会へ行くようなタイプだ」
レッドは、強調するところでは、身振り手振りで話していた。真摯さ
は明らかだった。レッドはタバコに火をつけた。
「話のつづきを!」と、後ろにいた男が叫んだ。
「目撃者もなく、証拠もなかった。それで、オレは市会議員の事務所へ
行った。秘書は、ブルドッグのような外見だった。しかし、かわいくは
なかった。オレを中へ入れてはくれず、警察を呼びに行くところだと言
った。オレは、夜遅くに出直すことにした」
レッドは、鍵をピッキングする動作をした。
「男は、脅迫されていたようだった。1週間たっても進展がなかったの
で、オレは、高級住宅街にある邸宅に住む未亡人に会いに行った。壁紙
がすべて、ドル紙幣でできてるような邸宅だった」
レッドは、少し間をおいた。
「執事に応接間に案内されて、オレはソファに座っていた。未亡人は、
香水の匂いがして心痛からか落ち着きがなかった」
レッドが好色そうな表情をすると、周りからブーイングやら口笛が聞
こえた。
「まじめにやれ!」と、男。
レッドは、いやらしい目つきをして続けた。
「オレは忙しいので未亡人の悩みには答えられないと言って、彼女に分
かってもらった。未亡人は、夫が署長と共謀して少女誘拐事件に関わっ
ていたことを知っていたらしく、実際に取引した共犯者の名前を聞きだ
した。オレは未亡人にまた来ると言って、ベラカヌイドの共犯者の居所
に向かった!もう一杯、くれ!」
バーテンダーは、急いでレッドのグラスに注いだ。レッドは、緊張を
ほぐすように、プレッツェルを少しかじった。
「それで、どうなったのさ?」と、青のシルクのドレスの女。目を見開
いて。周りから、「そうだ!」という叫び声がこだました。
「共犯者の若者は、ただの知ったかぶりで、自分のマンションのドアま
で来ると、Tシャツの笑いを浮かべたワニと同じ表情をした。
オレの知ってることをぶちまけて、ヤツから関係者や見逃したことが
ないかさぐろうとしたが、殺された市会議員の情報は、ほとんど得られ
なかった。
ヤツは、オレに、なにをさがしてるのかと訊いた。オレは、12才の
娘だと答えた。ヤツは、オレを変態と思ったらしく、アルバムを出して
きて、オレに示せと言った。オレは、もちろん、娘の写真を指した。
ヤツは、その娘がどんな問題を起こしたかを話し始めた。
オレは、別居して暮らしている夫婦を多く知っているが、子どもに悪
影響を与えなかった例はなかった」
タバコが、フィルターまで燃え尽きた。レッドは、ゆっくり慎重にタ
バコを灰皿に押し付けた。レッドは、精一杯のタフガイの笑みを浮かべ
た。
「オレは少しムカッとしたので、ヤツを殴り、テニスボールのように壁
にバウンドさせてやった!」
「そんなヤツ、もっとブッとばせばいいのよ!」と、女。
「そうだ!」と、男。
「長い話を簡単に済ますが、オレは、娘を助け出した。新聞社の友人に、
洗いざらい話し、連邦裁判所は、重罪を課した。新聞社は、購読者を増
やし、オレは、自分の仕事に戻った」
「だれが市会議員を殺したのさ?」と、青の女。
「オレは、たぶん、12才の娘だったと思うが、別に警察が知らなくた
っていい話さ!」
誰かが、拍手かっさいを始めた。レッドはすぐにスタンディングオベ
ーションにこたえた。笑いを浮かべ、客たちにグラスをかかげた。何人
かは、後ろから背中をたたいた。ふたりの女性が来てキスをした。スウ
ィートも頬の緊張をゆるめた。
「赤毛の依頼人の女は、どうなったんだい?」と、男。前歯が2本抜け
ていた。
「とても感謝していた」と、レッド。笑いを浮かべ、昔の幸せな気分に
浸りながら。
客たちは、散り始め、ひとりがジュークボックスのブラグを入れた。
青の女は、ぐずぐずしていた。
青の女の茶の目が、レッドを見ていた。見ているものが好きな場合が
多い。女の黒い肌が、黄金の腕輪のように輝いていた。厚く光沢のある
唇から、鋭い小さな歯が見えた。
「わたしは、カルメンよ」と、女。「あなたは悪いと思う」
レッドは、顔をしかめた。「そうならないように努力はしているが」
「ひざまづきなさい!」と、カルメン。
レッドは、ゴミが散乱している床を見た。「それは、できない!」
カルメンは、自分の親指をかじりながら近づいた。「フィラデルフィ
アにいたことはないわ!」
「きみは誰も失ってない!」
「あなた、キュートだって言われたことない?」と、カルメン。なめた
指をレッドの頬に這わせながら。
「いつもさ。この前、スピード違反で止められて、45マイル制限を9
0マイルで走るなんて、とってもキュートだって言われたよ!」
「首もステキね!」と、カルメン。
「引き立つだろ?」
「安らぎを感じるわ!」カルメンは、口をとがらせた。
スウィートが、割って入った。「これから行くところがある!」
「迎えに来てくれる?」カルメンは、腕をレッドの腕にからませた。
「もちろん!」レッドは、腕をほどいた。「今夜はダメだが、また、来
るよ!」
外へ出た時、レッドは、スウィートのコートがふくらんでいるのに気
づいた。それは、淡い茶のバッグで、中は5ドル、10ドル、20ドル
紙幣でいっぱいだった。レッドは、驚いて、口笛を低く吹いた。
「これは、ただの差額さ!」と、スウィート。「ブラウンさんに届けた
ら、次は、もっとずっと多いよ!」
7
ふたりは、リブステーキ屋のあと、バーとクラブ2軒に寄った。レッ
ドは、スウィートのバッグには2万ドル以上の現金があるとにらんだ。
「だれかが、その現金に襲いかかってきたら?」と、レッド。大きな茶
のリムジンに乗りこんだ時に、スウィートのヒザの上のバッグを指さし
た。
「だれも、ブラウンさんを襲おうとはしないさ!」
「だれも、現金輸送車を襲おうとはしないが、やったやつはいる!」と、
レッド。「装甲車や銀行よりも頑丈だとは、いえないだろう!」
スウィートは、運転手のコンパートメントの窓が閉まってることを確
認した。ダウンタウンを道案内してるとき、運転手の頭のうしろだけが
見えていた。運転手は帽子をかぶっていなかった。弾丸のような形の頭
は、ドラム缶くらいある太い首につながっていた。
「予定を変更しよう!」と、スウィート。「待ち伏せしてるやつがいれ
ば、いつ来るか分からなくなる!」
「そりゃ、いい!」と、レッド。「でも、まるで、彼女が愛してると言
ったからって、独身パーティの踊り子を信用してるみたいだな!」
「なんて言ったって?」
「ゆっくり眠らせてくれるような話じゃない」と、レッド。
「これじゃ、どうだ?」と、スウィート。腰のあたりで手を動かした。
黒のベレットが姿を現した。銃口は、偶然、レッドの腹のど真ん中をね
らっていた。
レッドは、やはり偶然らしく、銃口をそらせた。「悪くない!口径は、
9ミリ?」
スウィートは、うなづいた。
「いいけど、抑止力として十分じゃない!25口径のオカマのケツをど
かして、男の銃がほしいな」
「紹介したい男がいる。最後に寄るとこで」
スウィートは、微笑んで、車がコロンバス通りの営業時間外の店の前
で停まるまで、口をきかなかった。
「ここで待っていてくれ!」と、スウィート。リムジンを降りると、白
のキャデラックの男のところへ歩いて行った。
レッドは、運転席のパーティッションをあけた。
「名前は?」と、レッド。運転手は、茶のスーツを着ていた。
「ミッチさ!」と、運転手。挑発的で威圧的なしゃべり方だった。
「オレは、ダイアモンド。さっきの2つの停留所で、いつもオレたちを
拾ってくれるのか?」と、レッド。ミッチの敵意に満ちた口調を気にし
なかった。
「おめぇの知ったことじゃねぇ!」
スウィートは、車の横をコツコツたたいて、ミッチの言葉をさえぎっ
た。
「レッド、来てくれ!」と、スウィート。ミッチをとがめるように一瞥
した。
「おしゃべりできてよかった!」と、レッド。ミッチに、歯を見せて笑
いかけた。
レッドは車を降りると、スウィートといっしょにキャデラックに向か
った。腹の出た小男が、窓から左肩を出していた。
「レッドがあんたのブツに興味があるそうだ」と、スウィート。
「ヴィックと呼んでくれ!よろしく!」と、小男。レッドの手を握り、
肩をたたいた。「うしろにまわってくれ!」
ヴィックは、トランクをあけた。中には、小さなゲリラ部隊なら十分
すぎる武器があった。フタの裏には、拳銃が22口径デリンジャーから
44口径マグナムまで並んでいた。トランクの底のショーケースには、
短銃身ショットガンが2挺、ウジ短機関銃、トンプソン、それにサブマ
シンガンが2挺あった。
レッドは、通り過ぎる車を見た。
「気にしないでいい。好きなものを手にとって、買うだけさ!」と、ヴ
ィック。
「サツは?」
「こんなところに銃があるなんて、だれが思う?」ヴィックは笑った。
レッドは、短銃身の38口径を指さした。「いくらだ?」
「美しい銃です。持ち主は、キューガーデンに住む老婦人でした。ビン
ゴゲームで当てたそうです。幸運をもたらすと言われてます。常に勝つ!
強盗も追い払う!」
「なぜ、売った?」
「老婦人はトラックにひかれました。娘が売りに出したのです」
「オレには、あまりラッキーとは思えないな!いくらだ?」
「ブラウンさんのご友人だそうで、特別にたったの300ドルです!さ
らにサービスで、弾丸6発もつけます、追加料金なしで!」
「レッドは」と、スウィート。「マグナムのような圧倒的な銃が好きな
のかと思っていた」
「38口径が好きなのさ!」と、レッド。「使い慣れているし、この豆
鉄砲よりましだ!」
レッドは、ポケットに手を入れて、まわりを見た。
「いいだろう」と、スウィート。「通行人のことは、気にするな!通り
の第1法則は、自分のビジネスに集中しろ!さもないと、誰かに感づか
れる。ここでつぶされ、こぼれたジュースだらけになり、ついには、爆
発して、ブロックが飛び散り、ボスは配置変えになる」
レッドは、25口径を取り出して、ヴィックに渡した。ヴィックが査
定しているあいだ、レッドは目のすみでスウィートを見ていた。
レッドは、この若者が分からなかった。あいまいにへりくだったり、
おどしたりする話し方や態度には、なにかがあった。レッドは、これか
ら屠殺場に送られる、背中に刻印された牛のように感じた。その感覚を、
体をゆすって追い払った。
「悪くない小口径の銃だ!」と、ヴィック。銃の弾装を戻した。「この
銃はいったん戻すが、100ドルとこの銃で、38口径はあんたのもん
だ!」
レッドは、スウィートを見た。スウィートは、うなづいた。
「売った!」と、レッド。
取引が済むと、ヴィックはキャデラックに戻り、揺れると走り去った。
ヴィックのライセンスボードにはGUNNとあった。
8
ふたりは、ブラウンのリムジンに戻り、乗り込んだ。ミッチは、車を
発進させてダウンタウンに向かった。
「ヴィックにホルスターがあるか聞くべきだった」と、レッド。38口
径が、レッドのジャケットをストリッパーの巨乳のように見せていた。
「携帯許可証は?」と、スウィート。疑わしそうに。
「ない」と、レッド。「サツに持ってかれた。アヘン窟でコミッショナ
ーの息子をつかまえた事件のあと」
「聞いたことのない事件だ」と、スウィート。
「うまくもみ消された!」
「そうか、とにかく、銃を違法に持ち歩いているわけだから、ホルスタ
ーもないほうがいい。サツにつかまったときに始末しやすいからな」
レッドは答えなかった。銃を違法に持ち歩いているという考えが、気
に食わなかった。38口径なしのレッドダイヤモンドは、クラリネット
なしのベニーグッドマンと同じだった。違和感があった。
「ここだ」と、スウィート。レッドの思考をさえぎった。リムジンは、
インタウンホテルの前に停まった。
「金を渡すときに、いっしょにいなくていいのか?」
「いなくていい」と、スウィート。
レッドは外で出た。リムジンは、まずいイモムシを吐き出した魚のよ
うに、カーブを曲がって走り去った。「少なくとも、ミッチとどこにい
るのか推測する必要はなくなった」と、レッドは考えた。ホテルの向か
いの新聞スタンドの方へ歩いた。
砂漠の夜のような黒髪のやせたアラブの少年が、レッドに笑いかけた。
レッドは、ラックから『ザ・ニュース』と『ザ・ポスト』を抜いて、ガ
ムを要求した。レッドが防弾ガラスのパーティッションから5ドル紙幣
を差し出すと、少年は、ガムをすべらした。
「あんた、ダイアモンドさんでしょ?」と、少年。レッドは、おつりを
受け取った。
「だから?」
「ブラウンさんのところで働いている白人だよね!」
レッドは、新聞を腕に挟んで、タバコに火をつけた。レッドが少年を
また見たときに、少年のテンションが変わった。
「草はいる?」と、少年。
「草?」
「芝生」
「メヒシバのような雑草?」
「違う!リーファ」と、少年。「ジバ、ジバ、ガンジャ、シンジー。あ
んた、のろま?」
「リーファって、大麻のことだろ?」
「リーファって言ったら、リーファさ。混ざり気なし!最高級!コロン
ビア産より上!」
「糞尿?芝生の肥料の話をしてるのか?あるいは、ホップ?」
「ホップ?」
「メリージェーンだよ!」と、レッド。怒って。「オレがマリファナ依
存に見えるのか?」
「欲しそうな白人に見えた」と、少年。
「どういう意味だ?」
「買う?」
「情報なら買う!草はいらない!」レッドは、もう1枚5ドル紙幣をパ
ーティッションに入れた。少年は、ポケットに入れると、慎重に言葉を
選んだ。
「黒人に追いつこうとする白人は、トラブルを追い求めてるのと同じ!」
「5セントの価値もない!」
「それじゃ、これは?かしこいやつは、ブラウンさんとはうまくゆかな
い!うわさでは、ブラウンさんは宗教かなにかに凝っている。数人の商
売相手が、チンピラでなくても撃たれている。だれかが、別のやつを警
官に密告した。ブラウンさんのようなだれか」
「ほう、なかなかだな!」と、レッド。あざけるように言って歩いてい
った。
「なぜ、白人を雇ったと思う?」と、少年。
レッドは戻ってきた。「なぜだ?」
「のろまを捜していたからさ!そうでなければ、ブラウンさんとはうま
くやってけない!」
「1セントの価値のないものをありがとう!」と、レッド。ホテルへ歩
いて行った。
◇
レッドは、ホテルのロビーの灰皿にタバコを捨てた。テレビがついて
いた。ロビーのカウンターの従業員が、レッドにおおげさな挨拶を送っ
た。
レッドも、おおげさに挨拶を返した。新聞スタンドの少年の言葉が、
二日酔いのように残っていた。エレベータがレッドを乗せて、永遠のよ
うに上がって、フロアに運んだ。鍵をあけようとガチャガチャやると、
けっとばされたように室に入った。
クローゼットの暗闇の形に気づいて、ゆかに伏せた。ポケットの銃を
出した。引き金を引く直前、ぎりぎりで、指を離した。
起き上がって、電気をつけた。死人のようにこちらをねらっていた人
影は、茶のスーツだった。茶のスーツを着るように、ボスが命じたのだ
ろう。震える手で、銃を落としそうだった。
なにかまずいことが?レッドダイアモンドは、前にももっとタフな場
面に出くわした。ブラウンさんのトラブルは、ロコのことを思い出させ
た。
レッドは、服を脱ぎ捨て、38口径を枕の下に隠し、ベッドに横にな
った。口にガムを放り込み、新聞を広げた。
「3人の殺害事件に当惑する警察」と、ザ・ポスト。1面記事の下に、
見覚えのあるホテルから運び出された、ひとりの写真。死体仮置き場の
ふたりは、歯を出して笑っていた。
レッドは、ふたたび、震えを感じた。
◇
ぽん引きに売春婦、その客と思われる男が、タイムズスクエアのホテ
ルで、当惑するとされる警察によって、昨夜死体で発見された。ひとり
目は、エルモ・ジョナシ・ジョンソン、32才、住所不詳。ふたり目は、
コラ・キャンディ・トーマス、23才、同じく住所不詳。3人目は、ジ
ョンテール、41才、住所はパルシパニー、NJ。警察によると、この
3人は昨夜、リドホテルで銃殺体で見つかった。「3人は、まるで協力
しあったように殺されていた。しかし肝心の証拠が見つからない」と、
殺人課の刑事、ピートアングリッチ。証拠がなんなのかは明言しなかっ
た。
検死は、明日の予定だが、アングリッチは死後7時間たっているとみ
ている。
「そのホテルは、どこかの室でなにかが起こってるにせよ、知りたくな
るようなホテルではない」と、アングリッチ。
2ヶ月前に、ホテルの屋上から14才の家出少女が飛び降り自殺をし
た。警察によると、事件後行方をくらましたぽん引きから1セントも報
酬をもらっていなかったという。
警察によると、ジョンソンは、タイムズスクエアで窃盗、強盗、売春
で捕まる常連で、強盗の7年の刑期を2年で終えて、去年出てきたばか
りだった。
警察によると、トーマスは、売春で4回、盗品の授受で2回逮捕され
ていた。
ティールは、衣料品のセールスマンで、ニュージャージーに妻と2人
の子どもと住んでいた。近所の人の話では、がさつで時として粗暴であ
ったが、たいていは、紳士的だった。
「夫がそのようなホテルでいかがわしい人たちとなにをしてたかなんて、
知りたくもない!」と、ティールの妻。ファーストネームを明かすこと
を拒んで、すぐに電話を切った。
3人に殺人の容疑はかけられてない。
アングリッチは、室にはほかに誰かいて、証拠品を持ち去ったとみて
いる。
「男か女かも分からないし、ただ居合わせただけなのか、殺人に関わっ
てるのかも分からない」と、アングリッチ。捜査は続けるという。
◇
レッドは、最後のくだり、ミッドタウンの犯罪を追うデカのタフなせ
りふに、ムカムカして手が震えた。
新聞を下に置いて、ザ・ニュースを手にした。3面にその記事があっ
た。ガムをかみながら、さっと読んだ。
だいたい書いてあることは同じだった。こっちは、殺された者の名前
は伏せられていることを除いて。記者は、その地域での最近の殺人事件
にページを割いていた。今週に入ってから、27人目、28人目、29
人目の犠牲者だったと締めくくっていた。
それが、おおごとなのか?レッドダイアモンドは、アーリントン墓地
に埋められる遺体も見たことがないのか?おおごとさ!2つの遺体袋。
自分の灰を浴びたジョンQパブリック。
しかし今回は違った。「ジョナシ」だった。爆発。山積みの死体。弾
薬の香り。死。レッドは、額の汗をぬぐった。死んでしまえばそれまで。
葬儀屋を除いて、だれも気にかけない。
しかし、なんだってサイモンは、そんなとこへ行ったのか?
男の名前は、サイモンではなかった。ジョンサイモンテールだった。
そう、テールだ。ロングアイランドからだ。ニュージャージーじゃない。
芝生は手入れが必要だ。銃には弾が必要だ。フリーサービス。フェアで
はなく、フリー。
レッドは震えながら新聞を下に置くと、立ち上がってテレビをつけた。
ヤコビ船長が、倒れそうになった。腹にしこたま弾を食らって、手に
は爆薬。ガッツマンだ。キャスパーガッツマン。ファットマン。
レッドはベッドに横になった。最もタフな事件を思い出して、歯を食
いしばった口元から笑みがもれた。黒の鳥。マルタの鷹。スペードのお
手柄にしてあげた事件だった。スペードはよくやった。
ボガードは悪くはなかった。少し背が低いが、りっぱに映画の役をこ
なした。映画では演技が誇張されてはいたが、現実もだいたいそんなも
んだった。レッドは、横になったまま映像に酔った。
レッドは、そこから1ペニーも得ていなかった。そしてまだ、ブリジ
ットに会いたかったが、彼女にも落ち度があった。どんな女でも、レッ
ドダイアモンドから搾り取ることはできなかった。ブリジットは、フィ
フィとは違った。たいした女だった。ファットマンを投げられないよう
に、ブリジットを信用することはできなかった。
テレビを見ながら、レッドのたるんだアゴに笑みが浮かんだ。
その事件のあと、登場人物たちはどうなったんだろうと考えた。ブリ
ジットがベガスにいたといううわさを聞いた。そして刑務所で会った男
とカイロへ逃げたそうだ。ファットマンは、ロコに会ったあと、近くに
戻ってきた。
レッドは、映画の最後のクレジットが消えるまで、静かに見ていた。
黒の鳥は、どこへ行ったのだろう?たぶん、タイムズスクエアの質屋
のどこかだ。そこには、だれにも知られてないお宝が、薄板の下に隠さ
れている。ガッツマンは、国際捜索網に資金を出している、ロコに雇わ
れているかもしれない。
ブラウンとは、いったいだれだ?今までその名前は聞いたことがなか
った。突然とらえられ、なにかのまっただ中に放り込まれた。レッドは、
横になったまま天井を見つめた。
ブラウンに言われるがままにふるまって、どこに行き着くか見てみよ
う。今は多少の金が必要だし、もしも裏取引に関わっていれば、そのう
ちロコにも会える。
レッドダイアモンドは、自分が自分でないことに気づいていた。レッ
ドダイアモンドは、口にさるぐつわなしにスーパーで安売りされていた。
セントラルパークのギリシャサブレーのホットドッグから、高級フレン
チ子牛のぶどう酒煮まで、心をそそるものはなにもなかった。
会いたいのは、フィフィとロコだった。それぞれ全く違うあいさつに
なるだろう。
フィフィには、ゆっくりと笑顔で。シャンペンにベッド、モーニング
コールは無用。
ロコには、すばやく。レッドダイアモンドは、サディストではなかっ
た。ロコに、切符にパンチを入れたのはレッドダイアモンドだと、しっ
かり知ってもらう時間が欲しかった。そして、フィフィに戻って、ゆっ
くり時間をかけてシャンペンを、そして。
9
その後数日は、同じルーチンを繰り返していた。正午まで働いて、イ
ーストサイドで簡単なランチをとってから、ロコを捜した。夜は、ブラ
ウンの息のかかったホテルで過ごした。
レッドの記憶にある場所でも、ギャングの店は見つからなかった。ロ
コは、大規模な手入れを予想して、足取りをくらましたのかもしれない。
そうだとすれば、レッドを始末する方法をリニューアルしたことをうま
く説明している。
バーテンダーやビリヤードの主人、ナイトクラブのフロント係りは、
訊いてもロコを知らないと答えた。しかし、10ドル紙幣を振ると、し
ゃべり始めた。
「ロコという男を知っている。ブルックリンで手広くノミ屋をしている」
と、靴磨き屋。
食堂で会った男は、ロコはいくつかのバーを所有していたが、フロリ
ダへ移ったと言った。
雑貨店の女は、ニュージャージーの不動産屋でロコという人を知って
いると言った。
バス停にいたふたりのチンピラは、ロコがブロンクスの自動車窃盗組
織を仕切っているとレッドにしゃべって、それぞれ5ドル稼いだ。
ロコはうまく足取りをくらました。レッドは、黒の手帳にメモを取り
ながら、そう考えた。
しかし、レッドダイアモンドが事件に乗り出したのだ。恋わずらいの
ティーンエイジャーのように、振り払うのは難しい。警察や裁判所は、
ロコのような男をどうすることもできなかった。はじめから裏工作がし
てあったのだ。ロコにも分かる唯一の正義は、銃口にあった。
午後、レッドは、聞き込みの仕事が終わると、マルドーンジムへ行っ
た。ジムのオーナーはアイルランド訛りのイタリア人で、ユダヤ人コー
チがプエリトリカンやブラックにボクシングを教えていた。
「おこらないでほしいんだが、あんたは、リングに上がったら心臓発作
で倒れそうだ!」オーナーのビトは、レッドがジムに現われて、スパー
リングを申し出ると言った。
ビトは、ジムと寝食をともにする、元ウェルター級のファイターだっ
た。彼がジムのために投資しなかったお金は、ジンのボトルを買うため
のお金だった。かつて試合相手を倒すための情熱は、ジンで自分でノッ
クアウトを食らった。
レッドは、腹を立てた。元海兵隊でヘビー級のレッドダイアモンドが、
ボクサーの体型でないと言うとは、無神経にもほどがある。しかし、ビ
トは、頑固に言い張るので、それが正しいのかもとレッドは考えた。
さらにレッドがジムのパンチングボールやサンドバッグを叩こうとす
ると、あらゆる医学的な権利放棄書にサインするように、と言った。名
前と年齢の書かれた身分証が見たいと言った。レッドは、自分は元チャ
ンピオンのレッドダイアモンドだと名乗ったので、ジョンティールの身
分証が使えなかった。
レッドは、数十ドル渡して、身分証はホテルに忘れてきたと言ったの
で、ビトはサンドバッグを使わせてくれた。レッドは、その夜、スウィ
ートに書類を用意してほしいと頼んだ。
「自分のはどうした?」と、スウィート。顔に恩に着せるような笑みを
浮かべて。
「内緒だ」と、レッド。
「問題ない。数日かかるが」
3日後に、レッドは、書類を手に入れて、自分の価値を証明した。
スウィートは、その日、11時半にレッドを呼び出した。
「ミッチが風邪を引いて、運転手が必要だそうだ。オレは運転できない。
おまえさんは?」
「ああ、できる。オレの身分証は用意してくれたか?運転免許証とか」
「ああ」と、スウィート。「ブラウンさんが、用意してあるはずだ。キ
ャブでオフィスへ行ったら、ガレージで2時半に待ってるそうだ。ハワ
ード海岸へ行くという」
◇
レッドは、約束の時間前に、タイムズスクエアのギフトショップに寄
った。アイラブニューヨークTシャツに、キューピー人形、ハレンチな
灰皿、小から特大サイズまでのナイフ、それにホルスターを買った。ス
ウィートの助言にもかかわらず、腹クリップのある茶の皮のホルスター
だった。レッドは、ポケットをふくらませた、安っぽいガンマニアでい
たくなかった。
レッドは、ブラウンのビルに2時15分に着いて、ガレージで待った。
買ったものをチェックしながら、紙袋からホルスターを取り出し、腰の
周りに巻いた。
ポケットから銃を出して、シリンダーを回して弾装をチェックした。
それは、まるで、回転するルーレットが00に止まったような音だった。
銃をホルスターにすべり込ませると、上からジャケットのボタンをしめ
て、ブラウンを待った。
ブラウンは、やってくるとレッドといっしょにリムジンに向かって、
さっさか歩くあいだに、社会保険カードといっしょにクリップされたニ
ューヨーク州の運転免許証を投げてよこした。ブラウンは、車の前で、
レッドがドアをあけてくれるのを待っていた。一瞬の気まずさがあった。
アゴをあげて、ドアを指さした。
「なにか?体が不自由なんですか?」と、レッド。運転席についた。
ブラウンは、ドアの外で待った。
レッドは、エンジンをかけた。
ブラウンは、リムジンに乗った。
「気に食わない!」と、ブラウン。声は低く、不快そうだった。
「聞いてほしいんだが、オレは、レッドダイアモンドだ。何回かブロッ
クのところで撃たれ、刺され、こん棒で殴られた。そのうち、うまくや
り過ごせるようになった。オレは、かばん持ちじゃない。そのうち嫌わ
れて、クビにされるかもしれない。しかしそれまでは、いい買い物をし
たと思われるように、ベストを尽くす」
ブラウンは、一瞬、レッドをクビにすることを考えたが、言った。
「レッツゴー!」
レッドは、ギアを入れた。
運転に慣れるまで、数分かかった。街中を走ってるだけでは、しっく
りこなかった。しかし、イースト川沿いの高速を走るころには、エンジ
ンを吹かし、軽くブレーキに触れて、リムジンのタッチに慣れてきた。
ステアリングホイールは、手にいい感触だった。プレイを楽しむよう
に、打ったり、こねたり、ねじったりした。ブラウンは、後ろの席で新
聞をチェックしていたが、レッドの運転には気づかなかった。
レッドは、運転席の窓を少しあけていたので、イースト川の湿気が顔
を横切った。60マイルの速度を維持したまま、高速をすり抜けた。
たいていのやつらは、ブルックリンへ行きたがらない。稼ぎが少なく
なるそうだ。しかし、オレの場合は━━━。
考えが中断された。前を行く巨大なビュイックを運転する女がブレー
キを踏んだからだ。レッドは、スムーズに車線変更すると、過去の映像
を見るように、運転する女を横目で見た。
ブルックリン橋を渡ろうとすると、日射しが、張り巡らされた橋脚を
くもの巣のように見せた。しかし、彼はすばやく飛んだので、USAの
4番目の都市に向かってビッグアップルをあとにしても、くもの巣にと
らえられることはなかった。
10
東に向かうと、若者のにきびより多いこぶが道に現われることを、ふ
たりとも忘れていた。
レッドは、ハンドルに手を置いて、頭のなかのジャズのタイトルを思
い出そうとしながら、ブラウンはなぜ不機嫌なのだろうと考えていた。
ブラウンは、ニューヨークタイムズを読んでいた。
レッドは、マルタの鷹以来、新聞を読むのをやめた。新聞なんて必要
あるか?どうせ正しい情報はない。
警官は、記者に真実を語ることはない。警察は、記者に真実を語るこ
とはない。かしこいやつは、記者に真実を語ることはない。もしも真実
が語られたとしても、記者がウソでごちゃませにしてしまう。新聞は、
ラップした魚を、鳥かごに並べてるだけだ。
レッドダイアモンドは、観客ではなく、選手だった。
ハンドルにヒザをあてて、軽くヒジでついて、楽々とリムジンを操っ
た。まるで、テレパシーで動かしているかのように。もともと、レッド
はプロのレーサーだった。友人が6重衝突事故で170ポンドのマシュ
マロのように焼け死んで、それでやめた。
レッドは、ポケットからタバコを出して、口にくわえ火をつけた。吸
わずに、ふかした。
ブラウンは、運転席のパーティッションをあけた。
「タバコを消してくれ!車内は禁煙だ!」
レッドは、ゆっくりタバコを口からはなして、未使用の灰皿に押しつ
ぶした。
「悪い習慣だ」と、レッド。「恵まれない子ども時代からの」
「安っぽいお涙頂戴は、やめてくれ!」と、ブラウン。「ハワード海岸
へ着けばいい!」
ブラウンは、パーティッションを閉め、ウォールストリートジャーナ
ルを手にした。
こんなことは続かないだろう。レッドは考えた。人から命令されたこ
とはなかった。大きな探偵社とはおさらばして、自立してやってきたか
らだ。バックアップしてくれる組織がないと、タフではあったが、だれ
かに命令される方がもっとタフだった。
レッドは、自立の原因となった事件を思い出した。ボスは、手を引け
と言った。依頼料を使い果たし、探偵を雇った男は、会社員の男で、ハ
ートは大きかったが、もっと大きい借金があって、貯金を使い果たして
しまった。
レッドは、その男が9時5時の仕事中に、姿をくらました妻と子ども
の行方を追った。ボスは、仕事しなければカネは出せないと言った。レ
ッドは、納得しなかった。レッドは、その男の妻と子どもを見つけた。
セールスマンと逃げていたのだ。セールスマンは、仕事を失った。
◇
リムジンはベルトパークウェイを、スムーズに南下した。レッドの自
動操縦による、2トンのデトロイト製鉄骨のかたまりだった。
ブラウンは、スライド式のパネルをあけた。
「予定通りだ」と、ブラウン。声にうれしさはまったくなかった。「ブ
ルバード湾入り口で降りて、南に1マイル行ってくれ!」
タイヤはキュッキュッと鳴って、リムジンは坂道を下った。
「もうすぐ公園の裏、キャンディダの湾入り口15125番地だ」ブラ
ウンの声は、初めてのデートのティーンエイジャーのようだった。
ランチを食べにきた客たちは、仕事に戻り、夕食の客は、どこへ行こ
うか決めかねている時間だった。レッドは、駐車場に車を停めた。
そこは、1階建ての化粧しっくい造りの別荘に似せた店だった。
駐車場には、数台の車しか停まってなかった。黒の1983年型エル
ドラドは、ドア付近にあった。レッドは、ナンバープレートをメモした。
「いっしょに」と、ブラウン。その先は、JFK空港に向かう飛行機の
騒音でかき消された。
「なんです?」と、レッド。機体の影が通り過ぎた。
「来てくれ」と、ブラウン。店の重い木製のドアの真鍮の取っ手を引い
た。
レッドは、ホルスターの上に手をおいたまま、店にいる12人の客を
見た。フランネルのシャツを着た工場勤務のグループが2つに、5人の
家族だった。
室内は暗く、目が慣れるまで時間がかかった。なかを見渡すうちに、
細かいところが見えてきた。ところどころテープがはられた、過度に装
飾された、使い古しの赤のブースが見えた。赤と白のチェックのテーブ
ルクロスの上には、イタリアの地図の書かれた紙のマット。空のシャン
ティボトルが何本かに、古びたシシリーの絵が壁にかかっていた。発泡
スチロールの天井。テーブルの上に造花。しかし、キッチンから流れて
くるトマトソースやコショウやガーリックのにおいは、本物だった。
客たちは、入ってきたブラウンを、KKKの会合に乱入した珍客のよ
うに見た。ずんぐりしたブルネットで、緑と赤のブラウス、白のミニス
カートのウェイトレスは、ふたりを小さなサイドルームに案内した。
ここの花は本物で、装飾はつぎはぎではなく、きれいにそうじされて
いた。
レッドは、客のいる唯一のブース席の横に立っている男に注目した。
その男は、6フィートくらいの身長で、冷蔵庫のような体格をしていた。
髪は黒で、ひたいからオールバックにしていた。左肩にふくらみがあっ
たが、レッドは、これは聖書のふくらみではないと考えた。
レッドは、見張りが立っているそのブース席に向かって歩き出した。
もうひとりの男が、レッドに背中を向けて座っていた。その男の耳は赤
で、グレイの後ろ髪は、きちんとカットされていた。
ブラウンは、そのブース席に座った。その男のボディガードがレッド
に近づいて、空のブース席に座るよう手振りで示した。ボディガードと
ブラウンのいるテーブルに顔を向けて、レッドは座った。席が離れてい
て、ブラウンのテーブルの静かな会話までは聞こえなかった。
レッドは、気をつけながら、ボディガードに微笑みかけた。その男の
表情は、凍りついたように動かなかった。鼻の穴はマグナム級で、目は
BB弾だった。
若いものおじするウェイトレスは、同じイタリアの国旗の制服で、両
方のテーブルに、パンとバターを運んできた。レッドと無表情の見張り
のあいだにバスケットを置いて、急いで出ていった。
男は、バスケットのパンをつかむと引き裂いた。レッドは、時間をか
けて、やさしくナイフを使って、パンにバターをぬった。食べるときに
は、小指を立てた。
食事は、ずっとこんなかんじだった。ボディガードは、なにも言わず
に、しかし、かいばおけのブタのように、ブーブー音をたてながら、ピ
カタを引き裂いた。スパゲティを攻めたときは、トマトソースが飛び散
って、赤の吹雪のようだった。
レッドは、すばらしい子牛のぶどう酒煮をこころゆくまで味わった。
ワイングラスを食事仲間に向かって持ちあげた。
「カンパーイ!」
反応はなかった。レッドは、ワインの香りをかいで、口のなかでまわ
して、それからぐっと飲んだ。
「いいかい」と、レッド。「レジャースーツで50ドルのチンピラのよ
うにふるまっていい場合もあれば、上流階級の紳士のようにふるまうべ
きときもある!」
ボディガードは、げっぷをした。
「スピーチをありがとう」と、レッド。「オレがクランペッツを食べよ
うとして、ウィンザー公が言った言葉を思い出した」
レッドは、しゃべるのをやめた。ブラウンが急に立ち上がったからだ。
ブラウンはナプキンを投げ捨て、レッドに向かってどなった。レッドは、
銃を手にもって、立ち上がった。
ウェイトレスは、スカートと同じくらい蒼白だった。
「なんでもない」と、レッド。左手で10ドル紙幣を彼女の手にすべり
込ませた。レッドは、後ずさりをはじめた。「料理はうまかった。次回
は、ここにいるスピーチのうまい友人はなしで来るよ!」
ボディガードは、テーブルから立ち上がった。
「いいかい」と、レッド。「鉛とパスタじゃ、相性が悪い!」
レッドは、ボディガードがボスのところへ行くまで、後ずさりを続け
た。レッドが外へ出るとき、ボディガードは、ブースに寄りかかってい
た。
◇
ブラウンは、リムジンの中でぷんぷんに怒っていた。
「レッツゴー!」と、ブラウン。レッドは、リムジンをスタートさせて、
ブルバード湾入り口の北に向かって駐車場を出た。そのとき2台のレン
タカーが入ってきて、2台とも2人の男が乗っていたことに、レッドは
気づいた。
ベルトパークウェイに入ると、ブラウンはしゃべり始めた。
「とんでもないやろうだ!オレをだれだと思ってるんだ?初めて賭け事
に手を出した、靴磨きの黒人か?あいつにカネを稼がせてやったのに!
あいつはもう引退したから、オレのビジネスを受け継ぎたいそうだ!ヤ
クの取引に1枚かませてやると言いやがる。オレがヤクに手を出したが
るとでも言うみたいにな!」
レッドは、ブラウンのおしゃべりと、バックミラーに注意を払ってい
た。
2台のレンタカーが速度を上げて、後ろに迫ってきた。レッドは、ア
クセルを踏み込んだ。
リムジンが加速すると、ブラウンはおしゃべりをやめた。
「なにしてる?」と、ブラウン。
「ゼブラナンバーの車に乗っていた黒人を見ました?」
「なに?」
「2台の車が、さきほどの店からついてきてます。アラバマの保安官の
ように協力し合って。ゼブラナンバーのレンタカー。後ろです!」
ブラウンは、後ろを振り返った。
「ほんとうか?」と、ブラウン。
「見せましょう!」
スピードメーターが120を越えて、レンジ外で針が動かなくなった。
スピードオーバーのビープ音が、怒ったように鳴った。
後ろの車の1台は、年代ものですぐ2台から引き離された。もう1台
は、ベージュのフェアレーンで、ぴったりついてきた。
ヴェラザノ橋に近づくと、道がすいてきた。フェアレーンが追いつい
てきた。
「振り切れると思えない」と、レッド。「銃は?」
「この数年、持ったことがない」
「オーケー」と、レッド。スピードを70に落とすと、ホルスターから
38口径を出した。
「貸してくれ!」と、ブラウン。パーティッションに身を乗り出した。
「レッドダイアモンドは、自分の仕事をするだけだ。後ろに下がってい
てくれ!」
レッドは、銃を助手席のシートに置いて、運転席の窓をあけて、真ん
中の車線に移った。時速60マイルに落とすと、フェアレーンが追いつ
いた。窓からパイプのようなものを出していた。
ラッシュアワーの混雑が、逆方向で始まっていた。ブルックリンの南
西の角をまわると、マンハッタンに向かう道は、比較的すいていた。
レッドは、追っ手の顔を、サイドミラーで見れた。ニヤけながら歯を
くいしばった暗い顔。幸せというよりは怯えてるように見えた。うさぎ
はきつねから逃げる。スピードを落とせない。
パイプのようなものは、銃身を短く切ったショットガンだった。レッ
ドは驚かなかった。アメリカンエクスプレスカードの決まり文句━━━
ご存知?ショットガンで撃てば、10フィート一帯にひき肉をぶちまけ
られる。荷物をまとめてきな!
フェアレーンは、左の車線の背後にいた。
最初にオレを撃つように見えた。つぎにブラウンを撃つか、車のクラ
ッシュにまかせるつもりだ。さぁ、どうだ!レッドは、考えながら、シ
ートの38口径をヒザの上にすべらせた。
フェアレーンが左に来ると、レッドは、38口径を持ち上げた。ブレ
ーキを踏むと同時に引き金をひいた。3発、撃った。
◇
フェアレーンは前に行き、レッドが追う形になった。ショットガンを
構えたチンピラの顔は、恐怖でゆがんだままマンガのように誇張されて、
レッドの記憶に残った。それは、以前の冒険より、リアルだった。これ
は、もちろん、起こったばかりだったからだ。
レッドは、喜びを感じた。あのチンピラは、1度も撃てなかった。今
度は、うさぎがきつねを追った。
オレは、運転の仕方が分かっていた。オーケーだった。オレは挑戦が
好きなのだ。徐々に差がせばまった。
胃の奥で感じるような感覚だった。レッドは、この道は以前から知っ
ている気がした。ハイウェイポリスが待っている場所は、もうすぐだっ
た。60マイルにスピードを落とすと、フェアレーンは先にハイウェイ
ポリスが待つ場所へと飛んでいった。
叫び声がして、赤ランプの点滅が見えた。きつねは、猟犬につかまっ
た。
「ニューヨークのいいところは世話好きなところだ!」と、レッド。笑
いを浮かべながら。「万事めでたし!」
ブラウンは、座り直して、スーツの折り目を正すと、クリケットの試
合を見物した帰りのように、しゃべり出した。
「スウィートがあんたのことを話したとき、正直言って、まったく信じ
なかった。何か忘れ物をしたかのように、プレッシャーでもクールだっ
た。オレは、しかし、あんたのやり方が好きだ。黒人なら目立つ場所で
も、白人なら行けると思った」
「そうかも」と、レッド。
「降りてリラックスしたい」と、ブラウン。「提案がある」
レッドは、つぎの出口でハイウェイを降りて、69番通りを桟橋にむ
かった。
レッドは、ブラウンといっしょにリムジンを降りて、散策した。海風
が潮の香りを運んできた。ニューヨークの有名な看板が見えた。
「あんたの週給を、千ドルにアップしたい」と、ブラウン。「集金の仕
事は、もう、しなくていい。これからは、オレの右腕だ。あんたさえ良
ければ」
「最初の仕事は?」
「まず、だれがオレを始末しようとしたのか、調べろ!そして、その理
由も」
「今日会った人物は?」
「トニーということしか知らない。連絡は、スウィートを通じて来る。
大きな取引をしているという話だ」
「ナンバープレートから車を調べられる知り合いは?」
「もちろん」
レッドは、先ほど駐車場でメモしたナンバープレートの番号を書き写
して、ブラウンに渡した。
「どうしてメモをした?」と、ブラウン。
「今回の会合を計画した人物が乗りそうな車は、これしかなかった」
「しかし、どうしてメモする気になったんだ?」
「前にあった事件だが、セントラルパークに身元不明の死体が見つかっ
た。オレは、壁にぶつかったが、そこの駐車場にあったすべての車のナ
ンバーを控えて、ひとつづつ調べて、男の身元を突き止めた。それ以来、
ナンバープレートを控えるのが習慣になった」
ブラウンは、賛成するようにうなづいた。「今のことは、どう考える
?」
「手下のだれかが、あんたを始末しようとしたんだと思う。あんたがヤ
ワになったと考えたんだ。オレたちは、殺し屋が来るまで、あそこにい
るはずだった。ところがオレたちは早く帰って、殺し屋は遅れてきた。
やつらは、すべてにおいていい加減で、つまり、しろうとのやり方だ」
「イタリア人ファミリーか?」
「大きな仕事には、ファミリーを使うが、あいつらは小奇麗なうえ、う
まい食事をあてがったあとに、耳のうしろに2発くらわせる。アマチュ
アの仕事だ」
ふたりは、5・6分桟橋を散歩してから、リムジンに戻り、都心へ向
かった。
◇
「ミッチがやったと思うか?」と、ブラウン。突然きいた。
「レガシーを重んじる風習がある。アルバートアナスタシアは、床屋の
イスで最後を迎えたとき、手下は、たまたま休みをとっていた」
「ミッチは、今日は非番だった」
「偶然の一致だろう」と、レッド。別のことを考えながら。
「黒幕を突きとめてくれ!」
「見舞いに行ってみよう」
ブラウンは、深く座り直した。「それに、スウィートはいっしょに来
たがらなかった」
「それも、偶然の一致だろう」
「オレは、イースターの贈り物になるところだった。ふたりとも、オレ
のところに5・6年いる。分かるまでは、無罪としよう。そのあとは、
始末する」
「安全なところにいてくれ。オレが黒幕を突きとめるまで、場所を見つ
けておいてくれ」
「ニュージャージーに姉がいて、そこに滞在できる」
「家族の絆を深めるいい機会だ。さて、きょうの会合について教えてく
れ!」
「スウィートが1週間前に、トニーという男が不動産屋をやっていると
言った。組織に関わりがあって、カネがある。オレの縄張りを乗っとる
か、爆弾で吹き飛ばすそうだ。あそこへ行ったとき、麻薬の取引を持ち
かけてきた。さらに、こちらのすべての不動産まで乗っ取ろうとした。
オレが、ブラック社会から尊敬されていると聞いたそうだ」
「あんたのことをよく知ってそうだな」
「すべてを知っていた」
「う〜ん、やつは、ロコという名前を出さなかったか?」
ブラウンは、思い出そうとした。「いや」
「たぶん、うまく姿を隠してるんだ。ロコの手口のようにみえる」
ブルックリン橋の近くにきた。
「なぜ、タバコに火をつけない?」と、ブラウン。
レッドは、笑って、キャメルを取り出して、火をつけた。吸わずに、
ふかした。
11
ニューワークでブラウンを降ろしたあと、車内でブラウンが話してく
れたことを考えた。
ミッチは、31で未婚だった。高校を途中でドロップアウトしたあと、
ベトナムへ行き、窃盗で2回の逮捕歴があった。ブラウンは疑っている
が、プロのフットボール選手になりかけたと言っているそうだ。恋人は
なく、96番通りの西に住んでいた。
スウィートは、30で、離婚しているが、それ以外はよく分からなか
った。ある夜、のみ屋でブラウンに会い、雇ってほしいと言った。街の
事情にくわしく、ビシネスセンスもあって、ブラウンには宝だった。息
子のように思っていた。たまにマリファナを吸う。チェーンスモーカー
のように、ガールフレンドを変える。数週間前に、自分のポルシェをつ
ぶした。
スウィートは、あきらかにあやしかった。レッドは、スウィートに恩
は?たしかに、仕事をくれたが、それはブラウンを始末するためだった
かもしれない。
ミッチなのか、スウィートなのか。だれかが、レッドダイアモンドを
わなにかけようとした。墓地は、レッドダイアモンドをわなにかけよう
とした者たちであふれていた。
もしもスウィートが黒幕だとしたら、すでに身を隠すか、辻つまの合
う話を作り上げているだろう。ミッチだったら、ずっと単純だった。レ
ッドは、96番通りで駐車場をさがしながら考えた。
ミッチは、レンガの階段のある4階建ての3階に住んでいた。天井は
高く、家賃も高く、メイフラワー号で来たようなゴキブリが出た。建物
は、8室のアパートになっていた。
レッドは、ミッチの室以外のすべての室のチャイムを鳴らした。だれ
かが、レッドを建物の中へ入れてくれた。レッドは階段をすばやく上が
った。そして、ミッチの室の木のドアを激しくたたいた。
ドアはすぐにひらいた。ミッチは誰かが来たと思った。
レッドがミッチを押して中へ入ってきたとき、ミッチの顔は、驚きと
恐怖の表情だった。
しかしすぐに気を取り直して、ドアの横のテーブルの上にあったオー
トマティックをつかんだ。レッドは、すでに38口径を出していて、ミ
ッチの手から45口径を叩き落とした。フローリングの床で弾んだが、
暴発しなかった。
「病気の友人を見舞いに来た同僚に、たいした歓迎だ!」と、レッド。
「なにがほしい?驚かしやがって」
「そうだな。オレは、診察に来たと思ってくれ!座れ!」と、レッド。
38口径を持った手で、ブルーのベロアのソファをさした。
「あんたの友人たちに痛めつけられた。ジェシージェイムズの二の舞を
踏まされるところだった。現代では、あまりお勧めできない」レッドは、
笑い、歯とガムのかけらを見せた。笑いは、腹ペコの集金人のように暖
かかった。レッドは、ドアを閉めて、室の奥へ進んだ。
「おまえはなにも言ってない」と、ミッチ。「警告もない!」
「オレは、デカじゃない」と、レッド。「これがオレの警告さ」銃をブ
ラブラさせた。「座れ!」
ミッチは、ソファに座って、唇をかみ、必死に話すことを捜した。
「オレはやってない。やってない。なんのことだか分からない!」
「素直に答えろ!誰があんたに指示した?あんたは誰かの助けなしに、
駐車場のメーターも壊せないことは知っている」
ミッチは、反抗的な目で、45口径が転がっている床をちらっと見た。
距離を計算した。
「それは、うまくゆかない!」と、レッド。「一歩下がって、チャンス
をあげよう。しかし、あんたを撃つのは、障害者から盗むよりやさしい」
レッドは一歩下がった。そして、ふたたび歯を見せた。
ミッチは、ソファにもたれて、ため息をついた。
「教えてくれ、ミッチ君!ブラウン氏を始末して、なにをするつもりだ
ったんだ?」
「1万ドルだ。おまえもおこぼれにあづかれるぜ!」と、ミッチ。望み
を抱いた。
「悪くはない。しかし、ユダを演じればもっとカネになる。さぁ、誰に
指示された?」
ミッチは、さらに唇をかみ、ドアの方を期待するように見た。レッド
は、子どもと賭けポーカーをしている気がした。
「よし。誰が来るんだ?」と、レッド。
「なぜ、分かった?」
「オレはサンタクロースのように、あんたがいい子にしていたか悪い子
だったか分かるのさ!」と、レッド。木のイスを、ミッチとドアが見れ
る場所まで引いてきた。
レッドは座って、銃を半分つかんだまま、すぐに持ち直せるようにヒ
ザの上に置いた。ミッチを見ていたが、ミッチの方は目を合わせられな
かった。
「オレは、敵を投げ飛ばせるほどでかくはない」と、レッド。「加えて、
あんたがうまくやれるとも思ってない。すこし疲れている。だから、こ
こで訪問者が来るのを待っていよう。リラックスして、楽な姿勢で」
ミッチは、床の銃をまた見た。レッドは、ふたたび歯を見せて笑い、
ふたりとも座っていた。
ミッチを目の片隅におきながら、レッドは、室を見渡した。雑誌や汚
れた服が、わずかばかりの家具のあいだに散らばっていた。木製でない
唯一の家具は、ミッチが座っているベロアのソファだった。汚れたしっ
くいの壁には、ビキニの女優やフットボール選手のポスターが貼ってあ
った。
「そのソファは、どこで買ったんだ?」と、レッド。「まるで、映画館
にいる修道女のようだな」
ミッチは、なにも言わなかった。
「インテリアデザイナーか家政婦がいるな!」
ミッチは、にらんだ。
「おしゃべりするのは、どうだい?そのうち誰に指示されたか言いたく
なるかもしれない。そいつが、もうすぐ、ここへ?図星だろ?」
答えがなかったので、レッドは、「中国行きのスローボート」をハミ
ングした。
◇
陽が傾き始めていた。最後の陽ざしが、窓にこびりついた汚れの影を
ふち取っていた。ミッチがいらいらし始めた。
ミッチは、頻繁にドアを見るようになって、ソファに座り直したり、
骨を前にしたイヌのように唇をもぐもぐさせた。
「どうした、相棒!今にも爆発しそうに見える!」と、レッド。立ち上
がった。「男に言うのは初めてだが、寝室へ行け!」
ミッチは、いやいや立ち上がった。それから、狭い、服の散らかった
廊下を通って、寝室へ行った。
キングサイズの金属製のベッドがあった。アクリル製のひょう柄のカ
バーが半分かかっていた。壁には、化粧以外ほとんど身に着けていない
女性のポスターが、ピン止めされていた。
「ガールフレンドを見つけてやる必要があるな」と、レッド。女性のポ
スターを見ながら言った。
ミッチはこの瞬間を、クォーターバックのレッドに対して、ミッドラ
インバックを演ずることに選んだ。レッドは、パス道をふさぐと、ミッ
チの頭を38口径で殴った。ミッチはよろめいて、ベッドの上に倒れた。
レッドは、クローゼットの中をあさって、はでなネクタイを引っぱり
出した。
「あんたは最悪の味がする!」と、レッド。ミッチの足を縛った。
ミッチの頭は、レッドが考えていたよりもかたく、起き上がって銃を
つかもうとした。ふたりの男は、銃を奪い合った。ひょう柄のカバーで
もみあった。枕や毛布が宙を舞った。
ミッチは若く強かったが、足を縛られていたので、うまく動けなかっ
た。レッドは、お気に入りのおもちゃのように、銃を離さなかった。ミ
ッチの首に押し付けて、ハンマーのように振り下ろした。
「アプローチされても、オレの好みではないんでね!」と、レッド。ベ
ッドカバーを払いのけて、起き上がろうとした。
ミッチは、最後の賭けに出た。レッドは、ベッド脇に落ちた。ミッチ
はレッドの上になって、左手はレッドの喉に、右手で銃をベッドに押さ
えつけようとした。
ふたりの男は、取っ組みあって、叩きあった。レッドは、喉の手をは
ずした。ふたりはベッドの上をころがった。パンチを応酬し、上腕をつ
かみあった。
ミッチは、レッドの銃を持つ右手にかみついた。レッドが右手を引い
たので、歯は38口径の回転弾装にぶつかった。ミッチは、悲鳴を上げ
た。前歯2本と1本の犬歯がワイングラスのように砕け散った。
レッドは、銃をミッチの額にジャブしたが、ミッチはあきらめなかっ
た。銃をつかむと、レッドの指を引き金にかかるようにねじ曲げた。
暴発が、ミッチの肉を切り裂いた。表情が驚きから笑いに変わり、痛
みやその他すべての感情は、体から抜けていった。
レッドは、起き上がって、ベッドから離れた。ミッチに固いパンチを
食らった場所が1ダースは痛かった。首は、たたかれてやわらかくされ
たようだった。
室は、なにが起こったのかほとんど分からなかった。血もほとんどな
かった。ミッチは、やすらかな表情を顔に浮かべて横たわっていた。し
わくちゃのベッドも、生死を賭けた争いというよりは、情事のあとのよ
うにみえた。
レッドは、かすかなめまいを感じた。レッドは考えた。生き残るのは、
やつかオレかだった。それが、オレだった。そうでない、3つ目の考え
方があったか?なにが3つ?ホテル。クローゼット。重なり合った死体。
死んだ頭。フェアじゃない。家に帰る。本がない。だれがやった?だれ
もやってない。
トイレへ行って、吐き気がした。冷たい水を顔にかけ、口をゆすいで、
死のにおいを消そうとした。廊下をよろめきながら、壁つたいに歩いた。
居間に来て、指紋をそこらじゅうに残したことに気づいた。歩いた場
所を正確にたどりながら、さわったところをていねいにペーパータオル
で拭いて歩いた。
ふたたび居間に戻ってきたとき、まだ、なにか忘れている気がした。
スウィートが居間の中央に立っていた。キャンディバーをしゃぶりな
がら、右手に、ミッチの45口径を持っていた。
12
「シューティングゲーム、それとも、スマートゲーム?」と、スウィー
ト。45口径は、レッドの胸元をねらっていた。レッドは、オッズを計
算したが、50対1で不利だった。38口径をだらりと下へむけた。
「少しでも脳みそがあるなら」と、スウィート。「そいつをこっちに蹴
りな!」
レッドは銃をスウィートに蹴った。スウィートは、45口径をレッド
に向けたまま、キャンディバーをポケットに入れて、かがんで38口径
をつかんだ。
「ミッチは死んだのか?」
「やつは、オレに向かってきた!」
「オレは法廷じゃない!正当防衛かどうかなんてどうでもいい!」
スウィートの声は、少し震えていた。
「最後のタバコをいいか?」
スウィートは、うなづいたので、レッドはゆっくり1本出して、火を
つけた。
「タバコは健康に悪いなんて気にしてなくていいわけだ」
「早く吸え!」と、スウィート。レッドよりイライラしていた。
「なせ、オレを巻き込んだ?」
「車を修理工場に持って行ったときに、トニーに会った」と、スウィー
ト。「トニーのファミリーは、ヤワになった。ブラウンもヤワになった。
オレたちは手を結ぶことにした。もしもブラウンが取引に応じれば、そ
うした。しかし、ブラウンは断った」
「それで、プランBが始まる前に、出て行ったのか?」
「やつらは、ミッチの知り合いの殺し屋だ。あんたたちがレストランか
ら出たところを襲うつもりだった。ヴィックから、あんたの25口径を
返してもらった。やつらはそれでブラウンをやっつけてから、争ってあ
んたが撃たれたように見せるつもりだった」
「それでオレをマヌケのように扱ったんだな。オレは、マヌケを演じさ
せられたわけだ」
「誰でもよかった。たまたま、それがあんただった。ブラウンが白人を
捜していたと知っていた。そのとき、あんたが目の前に現われた」
「ブラウンはどうなる?」
「どういう意味だ?」
「あんたがオレを殺すと、ブラウンは安心できなくなる。街の尊敬を保
って、あんたの仲間の影におびえて暮らさないでいいように、あんたを
つけねらうぞ」
「それは、あとで心配することにしよう。いろいろやり方はある」
スウィートは、38口径をポケットにしまい、キャンディバーをまた
出した。
「なぜ、裏切った?」と、レッド。「誰にけしかけられた?」スウィー
トに1歩近づいた。
「うしろに下がれ!」45口径を持った右手を振った。
「おまえには、死んでもらう!」と、スウィート。自分に確認するかの
ように。
レッドのくわえたタバコは、半分の長さになった。
「なぜ、そうする?」と、レッド。「あんたは頭がいいし、ブラウンも
気に入っている。ゆっくりと乗っ取ることだってできる」
「ゆっくりしてる時間がない。ガールフレンドといっしょに、一晩に1
00ドルはマリファナを吸う。彼女は毛皮が好きで、オレは、車。乗馬
も趣味。週千ドルのために、オレは働きづめだ。オレにはもっとカネが
いるのさ!」
キャンディバーがなくなったので、スウィートは、38口径を左手に
戻した。レッドは、スウィートが、引き金を引くために自分を励まして
るように感じた。スウィートの声のへりが、カミソリの刃のように鋭く
なった。
「いままで、人を殺したことがないんだろ?」と、レッド。
スウィートは、右手の銃の握りを強めた。
「きたない仕事さ。特に、45口径で殺すと。血といっしょに骨のかけ
らも飛び散る。人が死ぬと長い間、糞尿をたれ流す。殺す前にトイレへ
行かすべきだ。においもひどい。動脈に当たったら、血が10ヤードか
15ヤードも」
「やめろ!」と、スウィート。
「それは、たいしたことではないかもな。もちろん、逮捕されたら、長
い間、ワインも女もマリファナもなしで過ごすことになる。しかしそれ
も、たいしたことじゃない、ブラウンにバレたら」
「黙れ!」と、スウィート。
レッドは、さわることなく、ピンと張った糸をはじいた。タバコの最
後のひと吹き。煙の先が、地獄の入り口のように輝いた。
「うしろを見てみろ!」と、レッド。
スウィートは、古い手に引っかかった。ためらったが、一瞬だった。
後ろを向いたスキに、火のついたタバコをスウィートの顔にはじき飛ば
した。スウィートがたじろぐと、レッドは頭から飛びかかった。
スウィートが45口径の引き金を引くと、電灯が忘却のかなたに吹き
飛んだ。室は暗くなった。レッドの頭をスウィートの鼻にぶつけると、
スウィートの顔の下半分は血で染まった。スウィートの45口径を持っ
た腕を、レッドは、頭の上にひっぱった。38口径が床に落ちた。
ふたりの男は、倒れ、38口径を奪おうと蹴ったり引っ張ったりした。
レッドが上になって全体重をかけると、スウィートはあえいで空をつか
もうとした。
スウィートは苦しくなって、限界まで力を出した。レッドは、激高を
感じて、全身にアドレナリンが放出された。
スウィートの手から45口径を取り上げようとした。スウィートは、
38口径をすばやくつかんだ。しかし、レッドの方が早く、45口径の
引き金を引いた。スウィートは、静かになった。
簡単なように見えた。なん回こんなことが?銃には、いくつ刻み目が?
45口径の指紋を拭きとると、スウィートの脇にころがした。
自分の銃をスウィートの指からこじあけると、ホルスターにしまった。
オートマチックの銃声が、まだ耳に残っていた。ベルの音に加えて、
サイレンが聞こえたように感じた。急いで、思い出せるすべての場所を
ふきとった。
玄関のドアをあけた。廊下には誰もいなかったが、下から物音が聞こ
えた。レッドは、1階上へかけ上がった。
屋上のドアに鍵はかかってなかった。ひじでドアをあけて、殺風景な
屋上のへりまで走って、下を見ると、パトカーが見えた。警官が出てき
た。
太った女が、警官に応対していて、手を大きく振っていた。警官は、
彼女について行くとき、うんざりしているように見えた。
◇
レッドは、屋上の遠いサイドへ走った。隣のビルまで、20フィート
はあった。屋上に張りめぐらされた、暗闇の絞首台のようなアンテナ線
をよけて、別サイドへ走った。
そこは、隣のビルまで6フィートだった。レッドは追い詰められて、
ジャンプして隣のビルの屋上にどすんと着地した。階段へ出る鍵のかか
ってないドアが見つかるまで、あと3回ジャンプした。そして、ブラブ
ラ散歩のように通りへ出た。
2台目のパトカーが、ミッチのビルの前に停まっていた。ふたりの警
官が、集まってくる群集を押し戻していた。子どもたちが指で銃を撃つ
まねをして、目撃した死体の話を友達にしていた。
警官は、正当な呼び出しだったことが分かって、よりてきぱきと動い
た。そのうち殺人課の刑事たちがやってきて、「なにを見た?」という
せりふで、パトロール警官から主役の座を奪い取るだろう。警官たちは、
刑事たちより先にテレビクルーが到着して質問されることを期待した。
レッドは、気づかれないように群集の裏を通った。救急車が到着して、
人々は、いくつ遺体袋が運ばれてくるか見ようとした。群集は高揚して
きた。テレビにインタビューされて有名になる日が近づいたのだ。
リムジンに戻ると、ブラウンのガレージに向かった。ブラウンのオフ
ィスまでは歩いた。
「なにをしているところで?」と、レッド。ブラウンのオフィスに通さ
れると、きいた。
ブラウンは、しゃべっていた受話器を元に戻した。
「いろいろ手を打っているところだ。社会保障番号を入手できる友人と
話していた。ひとつだけ警察から番号を入手できたそうだ」
ブラウンは、デスクの下のボタンを押すと、壁の小区画が上にあいて、
テレビが現われた。別のボタンで、テレビがついた。
「オゾンパーク近くで見つかった死体は、トニールッチーニ、42才、
クイーンズ在住、と判明。警察の話では、至近距離から3発撃たれ、ギ
ャングの犯行が濃厚。シェリー、マイクを返します!」と、テレビ。が
れきが散らかった映像が消えた。
「アッパーウエストサイドで、さらに死体」と、テレビのブルネットの
女性。「96番通りにいるフレッドコックスさん!」
コックスは、テレビに映ろうとするふたりの若者を押しとどめていた。
「シェリー、現場は騒然としています。日が暮れてすぐ、警察が、2件
の殺人を、そのひとりのミッチフリーマンのアパートで発見した」
カメラは、警察が玄関付近をガードしているショットに切りかわった。
「駆けつけた刑事によると、物盗りが動機ではないそうです」と、コッ
クス。「今、刑事が来ました」
カメラは、警官の方へ進んだ。くわえタバコがなかったとしても、ラ
フな格子じまのジャケットにピン留めされた警察バッジがなかったとし
ても、脇からのぞくホルスターがなかったとしても、刑事は、チワワの
群れにいるグレートデンと同じくらい目立っただろう
「アングリッチ刑事、どうでしたか?」と、コックス。マイクをタバコ
の横に押し出した。
アングリッチは、タバコの灰をはじき飛ばした。「死体のひとつは寝
室。もうひとつは居間。どちらも若く、黒人の男。至近距離から撃たれ、
到着したときにはすでに死んでいた」
「どちらも同じ銃で?」
アングリッチは、ニヤリとした。「今は秘密だ、フレッド。いずれす
ぐに公表する」
「容疑者は?」
アングリッチは、タバコをかんだ。「捜査は始まったばかりだ。見込
みはある」
「ヤクがからんで?」
「ノーコメント!」
アングリッチは、警察の規制線の中に戻って行った。
「特別捜査本部のピートアングリッチ刑事でした。シェリー、マイクを
返します!」
ブロンドがテレビから微笑みかけた。「進展があり次第━━━」
ブラウンがボタンを押すと、テレビは消えた。
「時間をムダにしなかったようだな?」と、ブラウン。認めるように。
「なぜ、あのふたりだと?」
「なんの話なのか分からないが、スウィートは、ただの欲ばりだったと
思う。ミッチは、うまい話に乗っただけ」
ブラウンは、デスクの上に、20枚の札束を置いた。
「よくやった」と、ブラウン。札束をレッドの方へすべらした。
「なんですか?」
「分かってるはずだ」
「いいえ。なにかが起こるべくして起こった。だれかが、レッドダイア
モンドにマヌケを演じるように仕向けたからだ。もしも彼がその報酬を
受け取ったら、ほんとのマヌケだ」
「そんなふうに感じてるんなら」
「そうです」
「よろしい。いいか、アングリッチはよい刑事だ。街じゅうの事件を扱
って、ローマ法王より多くの密告者をかかえている。逃げてしまうのは、
いいかもしれない」
「オレは、だれからも逃げない」
「それもいい。捜査情報を得るまでは、目立たないようにしてくれ!」
「軽く食事したら、睡眠をとるつもり。長い1日だった」
「スウィートがどんなやつと関わってるのか、まだよく分からない。気
をつけるように!」
「いつものこと」と、レッド。
◇
レッドは、キャブでポートオーソリティのバスターミナルまで行った。
ロッカールームの空いているエリアで、他人に見られないように、銃を
ロッカーにしまった。キーを封筒に入れて、ヒルトンホテルの自分宛に
郵便で送った。それから、イーストサイドへキャブを走らせた。運転手
のおすすめは、国連ビル近くのフランス料理店、ジョセフの店だった。
この2日間の国際的な上流階級に接する仕事のおかげで、ギャルソンを
ファルコンと言わないや、エスカルゴを出されても、「ゲーッ!かたつ
むり!」と言わないをならった。自分も上流階級になった気がした。
レッドは、6か国語は話されているロウソクのともされたテーブルを
抜けて、支配人に後ろのすみの席に案内された。
ウェイトレスは、シルクのガウンを着て、スーツやダシキ、ターバン
やバーノスを身に着けた客の間を動き回っていた。ほの暗い明かりが国
際的な雰囲気を自然に盛り上げていた。それはレッドに、ジェノヴァで
の事件を思い出させた。
「ご注文は?」と、ウェイトレス。後ろの天井に埋め込まれたバルブ状
の灯りが、ブロンドの髪にバックライトをあてていた。
顔は、暗くてよく見えなかったが、鮮やかな口紅が、ドレスの赤とマ
ッチしていた。そして、声には聞き覚えがあった。
「ご注文は、お決まりで?」彼女は繰り返した。「まだ、決まっては?」
体にぴったりの赤のガウンが、別の食欲をそそった。野性味を帯びた
空腹が、レッドの顔に現われた。
「なにがおすすめ?」と、レッド。彼女の顔を恥ずかしげもなく見つめ
た。
「お好みにもよります」と、彼女。髪に入れた手が、言葉以上になにか
を語った。
レッドは、バックミュージックとして流されている音楽に気づいた。
いろいろな国の言葉のおしゃべりや、レストランのいつもの雑音の向こ
うに、かすかに聞き取れた。「魅惑の宵」の甘い調べが、彼の耳をくす
ぐった。
自分が会っているのは、見知らぬ他人ではないかもしれないという思
いが、彼のなかで大きくなった。フィフィだ。彼女のリードに従って、
自分はクールでいようと決めた。
「それでしたら、2・3日中に決まりましたら、お呼びください」と、
ウェイトレス。
「いや、すまない、きみがオレが知っている女性に似ていたので」と、
レッド。「あるいは、知っていた女性に」
「大丈夫、お客さんもわたしの友人に似てます」と、彼女。「つまり、
特別な友人。彼は刑事」
「オレも探偵」と、レッド。フィフィも刑事と付き合っていたことを知
っていた。しかし、ずいぶん前のことだ。その刑事は、フィフィをロコ
に売り渡した。彼女はなにかを言おうとした。
「ご注文がまだ」と、彼女。自分が、危険地帯に初めて足を踏み入れた
農家の息子のようにレッドに感じさせるような仕草で、腰をひねらせた。
「おすすめは?」と、レッド。
「メニューのどれでも」と、彼女。自信ありげに微笑んだ。
「おまかせしよう!」
彼女は、キッチンに戻るところで、「きみの名は?」と聞かれた。
「ジェーン、ジェーンデュ。あなたは?」
「レッドダイアモンド」
「よろしく、レッド!」彼女は、立ち去る前に言った。
なんて女だ!彼女は、おとり捜査の専門家になれる!いや、彼女は、
おとり捜査の専門家だったに違いないと、レッドは考えた。クリーブラ
ンドでの張り込みのあいだ、ふたりでゆっくり過ごしていたことを思い
出した。しかし、彼女のしぐさからでは、そこまで分からないだろう。
どこにいたにせよ、年月は、彼女によいことしかもたらさなかった。
レッドは、彼女が2・3才しか若くないことを知っていたが、とても3
0過ぎには、見えなかった。薄化粧しかしてないことが、驚きだった。
「ジェーンデュ?」と、レッド。彼女が食事を運んできたときに、笑顔
で言った。軽めのソースのヒラメステーキに、ガーリックパン、それに、
千切りのサヤエンドウ。
「ほんとうの名前よ!」と、ジェーン。
よく気がつくところが、気に入っていた。
「分かってる」と、レッド。ウィンクした。「このあと会って、共通の
友人について話すっていうのはどうだい?」
ジェーンはためらっっていたが、恋人に言うかのように、イエスと言
った。「あと1時間で非番よ」
「長い1時間になるな」
料理はおいしく、レッドは、ジェーンデュと名乗るウェイトレスを見
て楽しみながら、ゆっくり食事した。そう、フィフィはそんなに想像力
が働く女ではなかった。寝室を除いて。そこでは、まるでマジシャン、
フーディニのようだった。
ジェーンを見ている客は、レッドだけではなかった。彼女は見た目が
やさしく、男客の多くは、彼女のリズムのある動きに引きつけられた。
レッドは、だれがロコの手下なのか考えようとした。タシキを着た背
の高い黒人は、ゆったりした服の下にあらゆる武器を隠していそうだっ
た。三つ揃えのスーツを着た、浅黒い肌の男は、顔に、明らかに非外交
的なキズがあった。ターバンを巻いたふたりの男は、レッドがカルカッ
タに逃げたときのふたりのちんぴらを思い出させた。
今日は、これ以上殺しはいい。だれが手下か知らないが、見逃してお
こう。レッドは、銃を置いてきたことを後悔した。しかし、銃は持って
歩くにはあまりに危険だった。サツに手をまわして、銃の携帯許可証を
返してもらおう。
それからだいたい45分後に、ジェーンはレッドのテーブルに戻って
きた。
「数分早く帰っていいと、上司に言われた」
それはよかったと、レッドは考えた。彼女の予定を知っているだれか
の裏をかける。
「静かでいい店を知っている」と、レッド。ふたりが最初に会った、ガ
レリックの店を考えていた。
外へ出ると冷たい雨だった。強盗が初めてナイフを使うように、夜を
切り裂いた。すぐに、ずぶ濡れになった。
「わたしの室へ行きましょう?」と、ジェーン。「ふつうはこういうこ
とはしないけど、ずぶ濡れでどこへも行けない」
「あやまらなくていい。なにか持ってゆくものは?」
「あなただけだけでいいのでは?」と、ジェーン。女優のメイウエスト
を誇張したような笑顔を見せた。
キャブのバックシートに座ると、震える彼女に腕をまわした。なにか
いいにおいがした。料理の香辛料をほどよく混ぜあわせた香水のようだ
った。
「いい香水だ」と、レッド。
東70番街のアパートに着くまで、ふたりは寄り添っていた。
13
室は、思った通りだった。そこの住人のように、暖かく、甘く、女性
的だった。カーペットは厚く、椅子はビーンバッグチェアで、大きなラ
ガディアン人形がふたつ。鉢植えの緑が、黄やオレンジや赤の装飾のな
かで、唯一の自然の色だった。
薄暗くなるスイッチを半分にすると、鮮やかな色があたたかい雰囲気
に変わった。
「わたしが着替えるあいだ、飲み物を用意しておいて!」と、ジェーン。
寝室に向かった。
「飲み物はなにを?」と、レッド。好みは分かっていたが、きいた。あ
るいは、少なくとも、彼女の好みが、最後に会ったときのままなら。
「驚かしてみて!」と、ジェーン。寝室から叫んだ。
レッドは、ジェーンにトムコリンズを作り、自分はスコッチのストレ
ートを作った。ずぶ濡れの上着を脱いで、飲み物を寝室に運んだ。
「紳士ならノックして!」と、ジェーン。ネグリジェ姿を隠そうともせ
ずに。
「ドアはあいていたし、オレは、紳士ではない!」レッドは、ジェーン
の美しさを目にした。あるべきものがあるべき位置にあることを知って
喜んだ。「それに、驚かしてくれって言ったろ?」
「なにもかも見たんなら、なにが魅力的か言ってみて!」
「麻袋を着ていても、魅力的さ」
飲み物を渡されて、ジェーンは笑顔を見せた。
「あたり!」と、ジェーン。一口すすりながら。「好みの味だわ!なぜ、
分かった?」
「オレは、私立探偵!」
「プライベートデカって、呼ばれない?」
「ときどき」
「映画の影響よ」と、ジェーン。顔に垂れ下がる濡れた髪の束をブラッ
シングした。「たしかに、わたしも本以外では、私立探偵がほんとうに
存在するのか知らない。もしかしたら、それは、ホテルの廊下をうろう
ろしている脂ぎった小男のことかも」少し間をおいた。「ハンフリーボ
ガードとローレンバコール主演の『大いなる眠り』」
ジェーンは、映画を思い出して、歯を出して笑いながら、ナイトガウ
ンに身をすべりこませた。それが、1ヤードのセロファンだけだった体
のほとんどを隠してしまった。
「トリビアは、お好き?」と、ジェーン。
「トリビア以外のなにかだ。よく覚えている。スタンウッドの事件だっ
た。気の変な娘たちが出てくる話だ。チャンドラーのおかげで、有名に
なった。しかし、タフな事件だった。エディマースの手下だ。キャニノ
がオレにカネの投資先を教えてくれた」
ジェーンは、不思議そうにレッドを見た。
「キャニノは、ロコの仲間ではなかった。マースは、ロコの幹部だった。
今ではよく分かっているが、当時は、ただの推測だった。幸運なことに、
友人のマーロウがオレを助けてくれた」
レッドは、トムコリンズを強めに作ったが、ジェーンは、よた話を聞
きながら、一気に飲みほした。
「ほんとうに、私立探偵なの?」と、ジェーン。もう一杯作りに歩き出
した。
「ほんとうさ」と、レッド。ベッドに座った。ジェーンは戻ってくると、
となりに座った。ももとももが触れ合った。室に盗聴器が仕掛けられて
いるから、彼女はゲームを続けるのだろうか?
「きみは、なにを?」と、レッド。
「女優」
「きみらの演技には敬服している」
ジェーンは、くすくす笑って、お代わりを飲み干した。
「映画と、コマーシャルにも。レストランでは、ウェイトレスを演じて
いる。せりふは、まだないけど、モデルの仕事も」
ジェーンが話すたびに胸が上下し、発情したヤギの群れのような気分
にさせた。
「あなたの話をして!」と、ジェーン。
「話すことは多くはない。大都会の水面に顔を出して、ある種のやつら
をやっつけようともがいている」
「それは、ロコ?」
「もう、ゲームはおしまい!」と、レッド。飲み物を床におくと、ジェ
ーンの手から、ほとんど空のグラスを受け取った。
ミリーは、ジェラシーから顔をしかめた。ガールフレンド以上の女は
何人かいたに違いない。レッドは、ミリーのイメージが、狭い室で、タ
バコの煙の向こうに消えてゆくのを見た。
それから、フィフィに突き進んでいった。世界には、フィフィ以外の
だれもいなくなった。
レッドは、しばらくして、タバコに火をつけた。
ジェーンは、片足をレッドに乗せた。「タバコを吸い込んでない!」
「節煙してるんだ」
「いずれにせよ、体に悪いわ!」
レッドは煙をはいて、ジェーンにキスした。
「いい?今までこんな簡単に男を連れてきたことはなかった。でも、あ
なたには、なにかあるわ。輪廻再生を信じてる?」
レッドは肩をすくめた。
「過去の生で、あなたを知っていた気がする」
「演技はやめな、スイートハート!それは、おれだよ、レッド。ベイシ
ティで、きみの命を救った」
ジェーンは、当惑した顔をした。「それは、ロコから?」
レッドはうなづいた。
「あなたはハンフリーボガードね、わたしはローレンバコール?」
「きみは、ローレンバコール以上さ!しかし、演技の時間はない。ロコ
について情報は?今はどんな犯罪を?」
ジェーンは、くすくす笑った。「白人の奴隷ビジネスよ。映画館から
少女を誘拐して、中国人マフィアに売っている」
「う〜ん、ロコは、しばらく前に、シャスーハンとそのようなことをや
っていた。また戻ったとは驚きだ」
「この指輪は、公立の学生たちにドラッグを売って手にしたものよ。町
の中学生たちを相手に、キャンディを売って、中にヒロインを入れて薬
づけにして、あとでみんな売り飛ばすのよ」
「なんてやりかただ!」
ジェーンは、手をまたレッドに乗せたが、レッドの心は、ロコに向い
ていた。
「ロコがどこに隠れているか、情報はないか?」
「このゲームあきたわ、レッド!」と、ジェーン。イライラしたように。
「別のゲームにしましょ!ホイップクリームをコップのふちにつければ、
おもしろいことができる!」
「これは、ゲームじゃない、ドールフェイス!念には念を入れるため」
「遊びたい!」
「遊びはなし!」と、レッド。ジェーンの手を荒っぽく払いのけた。
◇
レッドのするどい口調が、酒とバラの楽しい雰囲気をだいなしにした。
レッドは、取りつかれた顔をしていた。まるで、モビーディック号で大
海原を駆けるアハブ船長だった。レッドは、ジェーンのからだがこわば
ったことに気づかなかった。
「あなた、本気なの?」と、ジェーン。
「45口径の弾丸くらい本気さ」
ジェーンの唇は、なにか言おうとしながら、震えていた。ジェーンは、
黙ったまま天井を見つめた。
「いいかい、スイートハート!ロコを始末してしまえば、すべてはバラ
色さ!きみはもっと話してくれなきゃ!」
「ロコについてはなにも知らないとしか、言えない!」
「ふざけてる場合じゃない!」と、レッド、ジェーンの肩を強くつかん
だ。「もしもきみじゃなければ、今ごろは、壁にたたきつけられてる!」
ジェーンは、レッドの言葉と口調の強さに震えた。
「怖がらないで、エンジェル!きみを傷つける気はない!」
レッドは、ジェーンの髪をやさしくなでた。ジェーンは、レッドに取
りついたものを追い払うように、レッドに乗せていた足に力を込めた。
「あとで時間はいくらでもある!」と、レッド。ジェーンの美しい足を
無視するように。「ロコについてほかに知ってることは?」
「なにも知らない!」
「なにも隠す必要はない。ロコから守ってあげる。いっしょに暮らすこ
ともできる」
「あなたとは会ったばかりなのよ!」と、ジェーン。少し大声になった。
「大声を出さないでいい」と、レッドはささやいた。「盗聴されている
かもしれない」
ジェーンは、一瞬、レッドを信じそうになって、室じゅうを神経質に
見まわした。レイプされないための授業を思い出しながら、落ち着きを
取り戻そうとした。
「最後に見たとき、きみは死んでいるのかと思った」と、レッド。「オ
レは、アルコール漬けの荒れた生活をしている。ノドに、スチュードベ
ーカー製トラックくらいのかたまりが詰まっていた。死んだのが妹さん
だと知っていたら━━━」
レッドのやさしい言葉が、いっそうジューンを警戒させた。
「彼女は、きみそっくりだった」レッドは続けた。「やつらの標的は、
きみだった。それはよく分かっている。もっとよく知ることもできる」
悲しい記憶がよみがえった。「死体は、てっきり、きみだと思った。
血だらけの人形のようだった。オレが来るのが遅すぎたのだ。ネグリジ
ェ姿のきみを見ている今でさえ、殺し屋たちにやられた傷を見つけよう
としてしまう」
「やめて、やめて、みんな誤解よ!」と、ジェーン。レッドの手が、傷
のない腹やももをさわった。「わたしは、あなたが考えている人じゃな
い。帰った方がよさそうよ!」
「教えてくれないか、ドールフェイス!ロコはどこに隠れている?やつ
をムショ送りにするまでは、おちおち寝てもいられない。やつは、どこ
に?」ジェーンのももを強く握った。
「なにするの!痛いわ!」と、ジェーン。
「悪かった、そういうつもりでは」
ジェーンは、勇気を出した。「帰った方がよさそうよ!」
「ロコのことをもっと聞くまでは、だめだ」
ジェーンは、ためらいながら言った。「わかったわ!ロコは、町を出
て行ったそうよ。そうよ、出て行った」
「どこへ?」
「知らない」
「考えて!」レッドは、また、無意識にジェーンのももを握っていた手
に力を込めた。
「カルフォルニアよ、そう、ロサンジェルス。ロコは、ロサンジェルス、
そう聞いたわ」
「でかい町だ」
「あした、あしたになれば、もっと情報が入る!」
レッドは、後ろにもたれた。「悪かった。傷つけるつもりはなかった。
自分の握力に気づかなかったようだ」
軽くキスされたジェーンのくちびるは、乾いていた。「聞いて!あし
たは、朝早く仕事に出なきゃならない。情報をチェックできるかどうか」
「いいさ。ここでいっしょに待っていられる」
「今夜は、だめ。このあと、いくらでも夜は来るわ」
「そのとおり!」と、レッド。ゆっくり起き上がって、服を着始めた。
「気をつけてさえいれば、心配することはない。きみは、ずっと、オレ
の監視下にいられる」
「そんな時間はない!」と、ジェーン。声になんらかの情熱を虚しくも
込めながら。
レッドは、小物を集めて、服を着た。ジェーンは、テリー織のバスロ
ーブをはおって、玄関まで見送った。
レッドは、キスをすると出て行った。
ジェーンは、ホッとしてため息をつくと、3つのスライドキーでかぎ
を掛けた。イスをドアに立てかけ、電気を消すと、もう2度とお客を室
に呼ばないと誓った。
14
なんて女だと、レッドはホテルに戻るキャブの中で考えた。変化球を
投げられたこともあったが、それは、彼女とかかわった代償みたいなも
んだ。彼女は、ふたりで過ごした日々をすっかり忘れたふりをしていた。
逃走中のロコの手下たち。夜、ボロボロのモーテルで、枕の下に銃を隠
して、ドアがノックされるんじゃないかと、びくびくしながら、夜がふ
けてゆく。
ホテルに戻ると、カウンターの後ろの受付係は、清楚な顔をしたプエ
リトリコの青年で、震えていた。寒くはなかった。レッドは、受付に歩
いていった。
「どうした?」と、レッド。やさしい口調だった。
青年は、腐った卵がはじけたように見えた。
「お客様に会いに、ふたりの方がいらして、上でお待ちです」
レッドは、気になった。
「たぶん、刑事です」と、青年。
「なぜ、そう思う?」
「バッジを見せました」
「鋭い推理だな」
青年は、うなづいた。「たぶん、本物です。しかし、お客様を存じて
はいません」
「オレの室へ入れたのか?」
「彼らは、なんでもくれると言ったんです」と、青年。つぶやきだした。
「ブラウンさんには言わないでください!コネもなく、仕事がいるんで
す!濡れ衣だったんです!」
「分かった、分かった!」と、レッド。青年をさえぎって、ホテルから
歩きだした。
歩き出してすぐに、男が、レッドの進む方向に現われた。レッドは、
反射的に38口径があった場所に手を置いた。
男は、動くなと言う前に、リヴォルバーをレッドに向けていた。
レッドは、立ち止まった。男は、アングリッチ刑事だった。
「そのまま!」
「聞いてくれ!オレは、私立探偵━━━」
「壁を向け!今すぐ!」と、アングリッチ。左手で、レッドを押した。
右手の銃は、レッドのわき腹をねらっていた。
レッドは、ホテルの外壁の雨ざらしの赤レンガに手を置いて、足を広
げていた。アングリッチは、足を蹴って、さらに広げさせた。バランス
を取るのがやっとだった。アングリッチは、服のあちこちをパタパタ叩
いたが、なにも見つけられなかった。
「よし、こっちを向け!」
レッドは、向き直った。アングリッチは、6フィートちょっと背があ
ったが、やつれた体型でもっと背が低く見えた。ペリカンのようなあご
で、腹が出始めていたが、脂肪は、筋肉を薄くおおっているだけだった。
火の消えた葉巻をくわえたまま、冷たい茶色の目で、レッドを見すえて
いた。
「友好的に進めよう」と、アングリッチ。「まず、オレが答えるから、
おまえも答えろ!オレは、ピートアングリッチ。殺人事件を捜査してい
る。おまえは、レッドダイアモンド。私立探偵を気取っている。オレは、
私立探偵が好きじゃない。ゴキブリも嫌いだ。だからって、すべて踏み
つぶしはしない。いくつかを除いて」
「つまり、オレの身元保証人になってくれないわけだ」と、レッド。
「気の利いたことを言いたいんなら、分署に連れて行って、みんなの前
で話させてやってもいい」
「そんなつもりはない。あんたは、自分の仕事をしているだけだ」
「いいだろう」と、アングリッチ。銃をホルスターにしまった。このタ
フな刑事は、身を守るのに銃に頼るタイプではなかった。
午前3時ごろだった。だれも、アングリッチがレッドを所持品検査す
るのを見てなかった。銃はしまわれていたので、ふたりの男が、ただし
ゃべってるように見えた。アングリッチは、どっから見ても、殺人課の
刑事にしか見えなかった。
「オレが声をかけたとき、手でなにを捜そうとした?」
「ただの習慣さ」
「答えになってない!」
「前は、銃を持ち歩いていた。今は、ない。声をかけられて、強盗だと
思った」
「オレが強盗に見えた?」
「知らないが、習慣って、怖いもので、ただの条件反射さ」
「それで、銃は今はどこに?」
「さぁ。3ヶ月前に、ジャージーでだれかに売った」
「それなのに、まだ、条件反射。なぜ、売ったんだ?」
「刑事さんたちが、通りを安全に守ってくれているので、必要がなくな
ったんだ」
アングリッチは、葉巻を唇のあいだで転がした。「そのレシートは?」
「今はない」
「ホテルの室にも?」
「あんたの部下が、すでに捜索している。警告もなしに」と、レッド。
「さいふにあったが、盗まれたんだ」
「IDは?」
レッドは、尻ポケットに手をのばした。
「ゆっくりとだ」と、アングリッチ。リヴォルバーの台尻に手をおいた。
「所持品検査はしただろ?」と、レッド。さいふをゆっくり出して、ア
ングリッチに渡した。
「それほど慎重ではないな」アングリッチは、運転免許証と札束を見た。
「印刷したばかりの運転免許証?」
「さいふを盗まれたって、言ったはずだ」
「そして、全財産をさいふに?」
「ちょうど給料日のあとだ」
「だれに雇われている?CIAか?」
「自分さ。オレは、ひとりオオカミ。ゴキブリのように這いずり回って、
あんたたちがこぼした、パンくずをあさっている」
「コルネリウスの右腕だって聞いたぜ?」
「だれ?」
「コルネリウスブラウン。すべてが汚物色の男」
「間違った情報だ」
「やつを知ってるか?」
「名前は聞いたことがある」
「住宅地で死体で見つかった、ふたりに面識は?」
「ひどい事件だな。テレビで見た。やつに聞けば?」
「もう、聞いた。なにも知らないそうだ。弁護士に話してくれと言われ
た」
「市民は、みんな、警察に喜んで協力します!」と、レッド。さわやか
な笑顔になった。
◇
「よう、スリムなお兄さん、あとこのくらいで、分署にしょっぴけるん
だぜ!」アングリッチは、親指と人差し指を1/4インチ離して見せた。
ツメ切りが必要なツメだった。
「96番通りの死体は、妙だった」と、アングリッチ。「ひとりは、4
5口径、もうひとりは、38口径で撃たれていた。38口径は見つから
なかった。45口径の近くに倒れていたやつのポケットには、25口径
の拳銃。このかわいこちゃんは、前にも使われて、3人が殺された。ど
う思う?」
「かなり忙しい銃らしいな」
「リドホテル。ぽん引きに売春婦、その客。2日前だ。思いあたるふし
は?」
レッドは、胃がひっくり返りそうだった。目はひきつったが、まばた
きして平静を保った。
「ちょうど新聞で読んだところだ」レッドの声は、弱々しく、かすかに
なった。
「元気なやつから見たら、おまえは犬の糞でも食らったような顔をして
るぜ。殺された3人に心あたりは?うわさでは、おまえが現われた頃に
起きた事件だそうだ」
レッドは、100万ドルの事件で、ネコどろぼうの老人がしてくれた
助言を思い出した。
『優秀な警官や、ウソ発見器は、腹が立つことや落ち込むを言う』と、
老人は言った。『そこから逃れる唯一の方法は、なにか別のことで、わ
ざと自分を興奮させて、ほんとうに正気を失ったように精神を高ぶらせ
ればいい』
老人のしゃべり方にはなまりがあったが、助言は正しかった。レッド
は、自分の恐怖を怒りに変えた。
「しゃべり過ぎだ」と、レッド。アングリッチに怒りをぶつけた。「逮
捕するなりすればいい。5分間で5件の殺人事件の犯人にしようとして
いる。リンカーンが撃たれた日にオレがどこにいたか知りたいのか?そ
んなことばかりしてないで、なんで、オレの財布を盗んだやつを捕まえ
てくれないんだ?」
「オレの仕事に口出しするな!」
「権利については?」
「今、言おうとしたとこだ」
「名前や階級や認識番号はそのうち教えるが、その前に、弁護士に会わ
せてくれ!」
アングリッチは、顔を近づけた。くしで梳かれた髪の1本1本を数え
られた。火の消えた葉巻の臭いが鼻をついた。殴ってくれと言わんばか
りにアゴを突き出した。
「そのうち、いっしょに行くことになる、ゴキブリくん」と、アングリ
ッチ。「這い回るべき場所へ」
「逮捕じゃないのか?」
「今はまだ。しかし、町から出るな」
「バハマ旅行は、キャンセルするよ」
「それがいい」アングリッチは、1歩下がった。
レッドは、インタウンホテルに続く階段を上り出した。
「外出するのかと思った」と、アングリッチ。胸の前で腕を組んで、薄
笑いを浮かべた。
「気が変わったんだ。通りでどんな人間と出くわすのか、分からないか
らな」
レッドは、受付を素通りして室へまっすぐ行った。ふたりの刑事が待
っていた。
「私はダンディ刑事です、部署は━━━」
「殺人課」と、レッド。「今、アングリッチ刑事と楽しい会話をしてき
た。1ダースの殺人事件の容疑で逮捕されたが、手続き上のミスで釈放
された」
「われわれは、ただ━━━」
「したいことは分かる」と、レッド。ジャケットをぬいだ。「逮捕状を
見せて、逮捕したまえ!それができないなら、出て行ってくれ」
「われわれの調査で、なにか役立つ情報を持っていると聞いて」
「そのうち電話するよ」と、レッド。服をぬぎ続けた。「ぴりぴりしな
いでいい。オレは、疲れているので眠る」
レッドは、ブリーフ1枚になった。
「まだいるなら、叫び声を上げる。質問があるなら、弁護士にしてくれ」
ふたりの刑事は、どまどいながら顔を見合わせて、出て行った。
なんて日だと、レッドはベッドに倒れこみながら考えた。
銃声。2件の殺人。フィフィに何年ぶりかで会った。悪くはなかった。
まったく悪くはなかった。
殺人課の刑事をふたりも、いじめたり追い返せることは、めったにな
い。たしかに、レッドは、あのブロックのあたりをウロついていたが、
若手の刑事たちは、手がかりを見つけられなかった。危険な目にあいな
がら、世界中を飛び回っていたころは、ふたりの刑事は、まだ、おもち
ゃのピストルで遊んでるころだった。
レッドは、顔に笑いを浮かべて、眠りについた。
15
「目が覚めたか?」
「ええ、今」と、レッド。ふらふらしながら、電話から聞こえてくるブ
ラウンのしゃがれ声を聞いていた。
「会って話す必要がある。電話でしゃべるのは好きじゃない。あまりに
事務的だ」ブラウンは一語一語を、まるでアンダーラインが引かれてい
るかのようにしゃべった。
「ええ、そうですね。時間は、いつごろが?」
「これから15分ほどで、用事がある。3時ごろならだどうだ?動物園
で。ここのオフィスにある小さな像を覚えているか?」
レッドは、目をこすって思い出そうとした。オフィスの端に、1フィ
ートくらいの茶色のクマの像があった。
「思い出しました。3時にクマの檻で」
ふたりは、同時に電話を切った。
◇
レッドは、スーツ姿でイーストサイドへ歩いていた。同じブロックを
2回まわり、時々、店の窓の反射で周りをチェックするために立ち止ま
った。これは、古いテクニックで、マイアミの退役軍人たちで運営され
ていた、暗殺グループをやっつけたときに学んだテクニックだった。尾
行されてないことを確認した。
ヒルトンホテルに立ち寄った。カウンターの受付は、レッドダイアモ
ンド宛の郵便は来ていないと言った。
マンゲチェズジョセフの店は、ランチタイムで混んでいた。
ビジネスマンは、フットボールや利ざやや女性の話をしていた。弁護
士は、ゴルフや裁判や女性の話をしていた。外交官は、サッカーや国際
情勢や女性の話をしていた。報道関係者は、テニスや専門店や女性の話
をしていた。女性だけのテーブルでは、社内関係や有名人のゴシップや
男性の話をしていた。
フィフィは、グレイのスーツを着た弁護士のテーブルで給仕をしてい
た。彼女は、レッドに気づくと、手に持った重いトレイを落としそうに
なった。ドライヤーでブローした銀髪の弁護士とのいちゃつきも短く済
ませて、料理の皿を置いた。
彼女は、電話ブース近くの静かな場所に立っているレッドに、ためら
いながら近づいた。
「ハーイ、天使ちゃん、おぞましい顔だな!」
フィフィは、目のまわりがはれて、くまができ、一睡もしてないドラ
ッグ患者のようだった。
「元気よ、元気いっぱい」と、フィフィ。電撃結婚する花婿のような情
熱を見せた。
「こいつらにちょっかい出されてないか?」と、レッド。弁護士の座っ
ている方を指差した。「すぐに追い出せるぜ!」
「大丈夫よ、レッド。常連さんよ」
「あいつらのきみを見る目が気に入らない。オレのかわいこちゃんに、
もっと敬意を払ってもらいたいね」
レッドは、抱き寄せようとして近づいた。彼女は後ろに下がって、ト
レイを盾のようにかざした。
「ここではダメ、レッド。今はダメ」
「オーケー、フィフィ。大丈夫?ロコとのことで、なにかあったのか?」
「わたしは、フィフィじゃない。ジェーンよ!」と、ジェーン。声には、
イライラ感と怒りが混ざっていた。
レッドは、ジェーンに大きくウインクをした。「きみはいい役者だ。
分かった、ジェーン。いいかい、物事は切迫している。刑事が、オレが
5人を殺害したと考えている。オレたちは、町から逃げなきゃならない」
「オレたち?」
「そう、きみは目の届く範囲にいて欲しい。この前のフリスコの件のあ
とでは」
「わたしは、サンフランシスコに行ったことはない!」
レッドは、また、ウインクをした。「ああ、そうだったな。今が、行
くチャンスかもしれない。あるいは、ロサンジェルスかシカゴかロンド
ンかパリ。世界中を探検しよう!ふたりだけで!オレがロコを始末した
あとで!」
「5人を殺したの?」と、ジェーン。レッドがどう答えるか知っていた。
「ぬれぎぬさ。それに、あいつらは殺されて当然のくずだった。オレが
やったことじゃない。すくなくとも、3人は」
おそろしくなって、ジェーンは、口を手でおおった。
「外は、タフな世界。だから、きみはオレが必要なんだ。オレたちは、
この町を去り、ロコを始末して、ふたたびお互いをよく知るために、世
界を旅しながら、いっしょに過ごそう!」
レッドは、ジェーンに、色っぽい愛らしい笑顔を送った。
レストランの薄暗い照明と自らの強い使命感から、レッドは、ジェー
ンの顔色が、白磁器のような白に変わったことを見逃した。
「なん時に出られる?」
「今夜は、9時」と、ジェーン。夢遊病者のように。
「オレはそれまで、ブラブラして来ようか?」
「いいえ、わたしは大丈夫」
「きみが元気なトマトだってことは知っている。ヤボ用があるので、済
ましたら戻ってくる。きみの室へ寄って、荷造りしたら、狩りに出よう」
「でも、わたしは行きたくない━━━」
「もしもも、そしても、しかしもない!すぐに逃げなきゃならない。ロ
コが手下を、ピクニックにたかるアリのように、差し向けてくる前に。
きっかり9時に戻る!」
ぼうっとしたままのジェーンの頬を突っつくと、レッドは出て行った。
◇
レッドは、キャブでマーシーの店へ行って、スーツケースと新しいス
ーツとトレンチコートを買った。荷物をホテルの室に置くと、歩いて動
物園へ行った。尾行されていないことを確認した。
ブラウンは、初めての遠足の子どものように、クマの檻を覗き込んで
いた。
「美しい!」と、ブラウン。岩の上に座っている2頭のクマを指差した。
檻の床は、ポップコーンの箱やコカコーラの缶が散らかっていた。ク
マたちの毛皮は、光沢とは無縁で、ボロボロのクマ人形のようだった。
しかし動き回ると、数千年の捕食動物の獰猛さをあらわした。岩を登る
だけでも、荒れ果てた周りからは隔たった、力強さや優美さを見せた。
「たしかに」と、レッド。「前に話したユーコン川では、ロコの手下が
オレをクマがうじゅじゃうじゃいる場所へほうり投げた」
「またの機会に」と、ブラウン。クマから目を離した。「ホテルのボー
イが言うには、昨夜、刑事が来たそうだな」
レッドは、うなづいた。
「ボーイの話では、刑事がおまえの室に入ったそうだな。訴えるべきだ。
なにか見つけたか?」
「汚いシャツだけ」
「よろしい!今日は、だれも来てないそうだ!よし!」
「今日は、だれにも尾行されてなかった。それは確認した。あの刑事た
ちは、タレコミなしには、朝のキツツキを見つけることも困難なようだ」
「そうだ、しかし、アングリッチは、抜け目がない。やつが心配だ。お
まえは、しばらく旅に出てこい!」
「アングリッチは、いい刑事だ」と、レッド。金属製の手すりに寄りか
かった。「やつは、決してあきらめない。手に入れてくれたライセンス
は、大丈夫か?」
「やつが徹底的に調べない限り、大丈夫だ」ブラウンは、レッドに厚い
封筒を手渡した。「ここに2千ドルある。しばらく休みを取れ!リラッ
クスして、太陽を浴びて、一週間かそれ以上楽しんで来い!」
レッドは、紙幣を受け取ることにためらいを感じた。しかし、それが
フィフィを助け、自分にもロコを見つける助けになると思った。
「ありがとう」と、レッド。封筒をポケットにしまった。
クマに夢中なブラウンを残して、レッドはホテルに戻った。
◇
ホテルの外で見張ってるものはいなかった。レッドは、アングリッチ
はどこを張ってるのか、と不思議に思った。捜査は別の方向に向かった
のか?別の殺人にいそがしいのか?あるいは、アングリッチはレッドを
ただ泳がせてるだけなのか?
「あんたがみすぼらしいからだで抵抗せずに、刑事を室へ行かせたとは、
ブラウンに伝えてない」レッドは、出勤してきたばかりの夜番の清楚な
顔をした受付の青年に言った。「しかし、もしもまた同じことがあった
ら、今度は職を失うことになる。オレの手で、箱のひとつに押し込んで
やる」カウンターの後ろの郵便箱を指差した。
「はい」
「よし。裏口は?」
「あります。エレベータで地階まで降りて、業務用扉から45番通りに
出られます」
レッドはうなづいて、エレベータで室に戻った。スーツケースをつめ
ると、忘れ物がないかどうか、室を見渡した。それから地階に下りた。
裏口を見つけ、汚れた布やゴミの缶でいっぱいのカートの脇を通って、
きしむドアを開けっぱなしにして、45番通りに出た。
9番通りのポートオーソリティのバスターミナルに行って、空いたロ
ッカーにスーツケースを預けた。フィフィを拾いにゆくまで、数時間あ
った。タイムズスクエアをぶらついて、時間をつぶすことにした。これ
から先しばらくは、ここに来ることはないのだ。
歩いていると、このあたりをホームとする20人以上から会釈された。
この地域は、もはや、デイモンラニアンの愛読者たちのテリトリーでは
なくなって、ハードなスタイルのハスラーたちが、カフカやダーウィン
の世界から集まって来ているように見えた。
人間のくずの適者生存が意味するところは、人道主義が無法地帯を歩
くほどバカげたことなら、土曜の夜スペシャルというドラッグの常習者
が、アルバートシュワルツァー博士より偉いということになる。正義の
ために破壊されないような、人間の威厳はなく、文明の兆候もなかった。
通りをそうじする風が吹いても、悪事まではなくならなかった。それは、
ただ、レッドの骨の髄に冷たさを送り込んだ。
レッドがブラウンの右腕だということが、裏社会のうわさとして広が
った。5つの殺人の容疑者であることも。このことは、裏社会では、株
式市場の参加資格よりも、もっと重要な意味があった。
レッドは、いわゆる仲間たちの半数は、自分たちの悪事の保険として、
レッドがどこでなにをしているかを、アングリッチに詳しくしゃべって
しまうことが分かっていた。それで、マッサージパーラーの店先で呼び
込みをしていた鼻たれのガキに、モントークに深海魚を釣りにゆくとし
ゃべった。
コーヒーショップでは、ホットドッグと脂っこいフレンチフライを食
いらげながら、情にもろそうなウェイトレスに、オハイオにいる叔母が
死にそうなんだと話した。
デューデュソーシャルクラブの用心棒には、シシリーのドンに会いに
ゆくんだともらした。
ほかの者たちは、ミルウォーキーやヒューストンやアトランタでの大
掛かりな、おとり捜査について聞かされた。なん人かは、レッドはフロ
リダやカリブに休暇の予定だと。
2時間の運動とすれば悪くはなく、通りをぶらつきながら、考えた。
それはきっと、アングリッチをしばらくは忙しくさせるだろう。
◇
44番通りと8番通りにはさまれたマッサージパーラーを通り過ぎな
がら、気分が良かった。このあたりの人々なら、店内の騒ぎを聞いても
無視して通り過ぎただろう。レッドは、しかし興味から、マッサージパ
ーラーの入口へむかった。
ぽん引きのブラッドが、か弱い少女の長いブロンドの髪をつかんで、
顔を叩いた。
「なんだと?やりたくねぇのか、このアマ!」ブラッドの黒い手が叩く
と、少女の青白い肌は、明るい赤に変わった。
「できない、わたしにはできない!」と、少女。
「店のなかでトラブルはごめんだよ!」と、ロビーの机にいた濃い化粧
の肥った女性。「彼女ができないなら、別の女性にさせればいい」
モノポリーゲームでは銀行役のような、ワックスをかけた口ひげのあ
るかっぷくのいい男は、神経質そうにレッドににやりとすると、すれ違
いに、ドアから出て行った。
「ほら、出ていった」と、ブラッド。少女の髪を引っ張った。「客を失
ってるぜ」
「商売も失う」と、肥った女性。「彼女をやめさせて!これ以上のトラ
ブルはごめん!」
その言葉がブラッドを増長させた。後ろ手に少女をつかんだ。殴ろう
とした手が、少女の歯に当たり、少女の唇とブラッドの手を切った。少
女の首をつかんで、押した。
「ホテルに戻ったら、いやというほど、ムチで打ってやる!」
レッドがやってきて、ブラッドの肩に重い手を乗せたとき、少女の顔
は青ざめた。
「あんたは、身体的欠陥でもあるんじゃないのか?」と、レッド。
ブラッドが振り返ると、レッドはアゴを強く殴った。2番目のパンチ
を腹に受けて、ブラッドは2つ折りになった。レッドは、ヒザで、ブラ
ッドの顔を蹴り上げた。
「警察を呼ぶよ!」と、肥った女性。脅すように。後ろのイスにいる3
人の売春婦たちは、飽き飽きした顔で見ていた。ベニア板の仕切り室の
物音が止んだ。
「年は?」と、レッド。少女は、そう聞かれて、顔色が戻った。
「15」
レッドは信じた。少女はまだ子どものようで、身に付けているホット
パンツやローカットブラウスの派手さよりも、哀れっぽかった。
レッドは、肥った女性に、歯を見せて冷やかな笑顔を送った。「あん
たは、十分気をつけて、売春宿をやってるんだろうが、へそ曲がりの刑
事は、未成年者の非行には厳しくあたってくるぜ。あんたのために、刑
事にお願いしておこうか?」
「トラブルはごめんだよ。健善な商売をやってるよ。あいつは、彼女は
18だって言ったんだよ」と、女主人。床で気を失っているブラッドを
指差した。
「聞いたことを、そのまま信じるのはよくない。あんたのためにこいつ
を、ゴミ箱に捨ててきてあげようか?」
「いいね、わたしゃトラブルはごめんだよ」
レッドは、ブラッドの毛皮に似せた襟巻きをつかむと、店から引きず
り出した。細身のぽん引きを持ち上げると、スチール製メッシュのゴミ
箱に放り込んだ。ぽん引きのかぶっていたギャンブラーハットを小さく
丸めて、口に押し込んだ。
「ここのゴミはどこだ?」と、レッド。店に戻ると女主人にきいた。
女主人は、机の下から、汚れたティッシュやキャンディの包み紙のつ
まったバスケットを引っ張り出した。レッドは、通りに出て、ブラッド
の頭にバスケットの中味をぶちまけると、店に戻った。
◇
「よし、児童保護局に連れていってあげる」と、レッド。少女の肩にや
さしく手をおいた。
「わたしはそこから来た。ブラッドがそこでわたしを見つけた」と、少
女。南に向かって歩きはじめると、言った。
「職員は助けてくれなかった?ブラッドに、どうやってつかまった?」
「ぽん引きたちは、外で待っている。職員は、ぽん引きを訴えたりつか
まえようとした。先週職員のひとりが撃たれてから、ぽん引きたちの数
が増えた」
少女は泣き始めたが、急に、泣くのをやめた。涙が、派手な化粧をひ
どくぎらつかせた。
「あなたは、ほんとうにかっこいいのね」と、少女。「鎧を着たナイト
のよう。名前はグウェン。あなたは?」
「レッドダイアモンド。オレは、ナイトじゃない。子どもがたたかれる
のを見たくないだけ」
グウェンは、落ち着きを取り戻したように見えた。回復が早いのは、
若さの特権だ。レッドは考えた。質屋の時計を、通り過ぎながら、チラ
リと見た。フィフィと会う時間まで、1時間を切っていた。
「ほんとうにかっこよかった!ボン、ボン!」と、グウェン。きゃしゃ
な手で、レッドのパンチをまねした。くすくす笑って、色っぽい目でレ
ッドを見た。
レッドは困って言った。「いいかい、マロニー、これからまっすぐ、
連れてゆかなきゃならない」
「名前はグウェンよ!」
「きみは、オレにはマロニーに見える」
「好きなように呼べば。マロニーになって欲しければ、なってあげる」
「別に欲しいものはない。出身は?」
「ロサンジェルス」
「なんだって?どうやって、ここまで来た?3千マイルも下水道を泳い
で来たのか?サンセット大通りを見学するのにあきたのか?」
「ニューヨークを見たかっただけ」
「今度は、ガイドを頼むんだな。じゅうぶん見学した?」
「たぶん」
「よろしい。児童保護局が、きみをパパとママのいる家に送りかえして
くれるさ」
「パパだけ。ママは恋人と逃げた。あなたのところに泊まれない?」
レッドは、信じられず、頭を振った。グウェンはそれがダメという意
味だと思った。
「結婚してるの?」
「いいや。しかし恋人がいる。きみをまっすぐ送ったら、すぐに会わな
きゃならない」
児童保護局の前まで来た。素人画家による、笑う子どもたちの大きな
壁画が描かれた、古いビルだった。
5・6人のぽん引きたちが、近くに停めた車にもたれていた。極彩色
の羽をもった派手なハゲタカたち。レッドに連れられて、グウェンが歩
いてくると、口笛を吹いた。
「中に入ってなさい!」と、レッド。グウェンに。「オレは、ここでや
つらにヤボ用がある」
グウェンは、2重のセキュリティのかかったドアを通ってブザーを鳴
らすと、振り返って、レッドを心配そうに見た。レッドは、一番大柄で
声も大きい、ぽん引きに近づいていった。
ぽん引きは、金のラメが入った服に、左耳に小さな金のイアリングを
していた。背は6フィートを越えていたが、体重は160ポンド以上で
はなかった。仲間たちに物知りなところを見せるのに夢中で、レッドが
来るのを無視した。
「よう、クズ野朗、口笛吹いたか?」と、レッド。
ぽん引きは、振り返った。5人の仲間は、黙っていた。
「なんて?」
「クズ野朗と言ったんだ。出産制限している人への侮辱になるかも」
「なんの用だ?」と、ぽん引き。レッドのレベルを見極めようとしなが
ら、イアリングをいじった。
「あんたのみすぼらしいケツを、通りに蹴り落としたいね。しかしそん
なことのために、靴を汚したくない」
「外へ出ろってか?」と、ぽん引き。前かがみの背筋を伸ばそうとした。
「もう、外にいるぜ、ケツの穴!」
レッドは、ぽん引きから2フィートのところにいた。両手はだらりと
下げて、目は細めて、ぽん引きの手の動きに注意を払っていた。
「オレのことを知ってるのか?」と、レッド。
「ブラウンさんのとこで働いている」と、仲間のひとり。
「5人を殺した」と、別のひとり。
レッドは、おだやかに笑った。「この数時間は、まだ、だれも殺して
ないから、イライラしてるんだ」
金ピカのぽん引きは、イアリングをはずそうとするように、耳を引っ
張った。「なにがしたい?」
「そうだな、通りをきれいにしたい。今すぐに、そして、永遠に。あん
たたちのひとりでも、このあたりで見かけたら、また、あたまをかち割
るかも。そうさせたいのか?」
「ここは自由の国だぜ。権利がある」と、金ピカのぽん引き。声の震え
が、その言葉に自信が持てないことを明かしていた。
レッドは、金ピカの服をつかんだ。「あんたには黙秘権がある。オレ
がそのかわいい顔を壁にぶつけたら、好きなだけ血を流す権利もある。
ほかの権利も読み上げようか?」
ぽん引きの3人は、レッドが金ピカを叱り付けているあいだに、こそ
こそ逃げていった。
「用事を思い出した」と、残りのひとり。もうひとりと逃げていった。
レッドは、金ピカのぽん引きとふたりだけになった。
「このあたりを、オレのブロックにする。もしもまたここで、あんたを
見かけたら、あんたは路傍の石の一つになるぜ」と、レッド。逃げよう
とする、ぽん引きを押した。「あんたのブロックに戻りな。もしもあん
たを見つけたら、それが、この世の最後の見納めとなるぜ」
ぽん引きは、あたふたと逃げた。安全な距離まで来ると、「おたんこ
なす!」と呟いてツバを地面にはいた。レッドが2歩近づくと、ぽん引
きは猛ダッシュで8番通りを北に走っていった。
◇
児童保護局の中から、ガラス越しに見学していた10人以上の顔があ
った。レッドがブザーを鳴らして入ってくると、職員たちに賞賛と笑顔
の輪で迎えられた。きちんとした身なりの男や女の職員たちは、モルモ
ンタバナクル合唱団のオーディション会場からやって来たかのようだっ
た。子どもたちは、緊張して、疑り深そうだったが、不思議に希望もあ
った。まだ消え去っていないあどけなさが、哀れっぽく見せていた。
レッドは、あいさつしてくるひとりひとりに、丁寧に会釈して、グウ
ェンの座っている仕切り室に行った。マッサージパーラーにも同じよう
な仕切り室があったが、ここのは、それほどのプロとは思えない大工が
あけた、大きな窓があった。床のマットレスの代わりに、中古で購入し
た机が置かれていた。
きちんとした身なりの職員が机の上に体を乗り出して、うしろに座っ
ているきびしい顔をした所長の耳になにかささやいていた。その職員は
話し終わると、レッドに、「神をたたえよ」と言うかのような笑顔を送
って、急いで出て行った。
グウェンは、責任ある大人たちに保護されて安全に感じながら、なに
を見るともなしに座っていた。
所長は、深くくぼんだブラウンの目をした、やせた牧師であった。ま
るで天国に祈りを捧げながら、地獄に住んでるかのように見えた。笑顔
を作るために、それに近い表情をした。
「私は、神父ドチャーティ」と、牧師。「グウェンがあなたのことを話
してくれました。外でなにがあったか聞きました。暴力は許せませんが、
あなたに感謝します」
「なにもなかったよ、神父。オレは、グウェンが良人の手にゆだねられ
ることを願っただけ。すぐに、失礼しなければならない」
「待ってください。グウェンのお父さんと話しました。彼は、あなたが
グウェンを家まで連れてきてほしいと言ってました。個人的に、お礼を
言いたいそうです」
「やらなきゃならない仕事がある。頭を軽くたたいただけで、カリフォ
ルニアまで飛んでゆける羽はない」
「お父さんが言うには、すべて手配済みで、ケネディ空港の今夜の便を
予約したそうです」
レッドは、顔をしかめた。「仕事がある」
「少女を助けることより重要な?」
「それは、あなたの仕事だ。オレの仕事は、それほどきれいじゃない。
職員の誰かひとりは、旅行が好きだと思うよ」
ドチャーティは机から立ち上がり、両手を広げた。「これは、あなた
にとって、この世のために少しでもなにか良いことをするチャンスです。
いたるところに、悪がはびこっている。疑いもなく、あなたにはそれが
見える。悪に加担しているかもしれない。このことで、少しはこの世の
役に立てるのです」
ドチャーティのしゃべりかたは、まるでセントパトリック大聖堂の祭
壇で語っているかのような熱を帯びていた。小さな室では、大げさすぎ
だった。長い間を置いて、言葉の1つ1つが壁に響き渡るのを待った。
「多くの人がざんげに来ます」と、ドチャーティ。「良い神父は、医者
がエックス線写真を読むように、魂を読みます。私には、あなたのタフ
そうな表面の殻奥深くに、なにか悩み事が見えます。それは、あなたが
自分で解決しなければならないなにかです。あなたを責めることはでき
ない。しかし、あなたにお願いします、子どもには、ダメと言わないこ
とを」
ドチャーティは、グウェンを指差した。彼女は、口をポカンとあけて、
牧師の言葉の合間に光る稲妻を待っていた。
「神父の言葉には、力がある。いいでしょう、その言葉に従おう」
牧師の顔に笑いのようなものが戻った。
「神父は、自分で自分の気高さを見つける手助けができるだけです」
グウェンは、ノアが洪水を心配するほど、目に涙があふれた。
「涙をぬぐえ、メロニー。出発するぞ!」と、レッド。
「名前は、グウェンだったはずでは?」と、ドチャーティ。少し混乱し
ながら。
「メロニーは、レッドがつけてくれたニックネーム」と、グウェン。ま
るで高価な贈り物をもらったかのように。
「そうですか」と、牧師。「ともあれ、荷造りしなさい」
「なにもないわ」と、グウェン。「ブラッドは、服を取り上げて、これ
を着せられただけ」自分のホットパンツを指差した。
ドチャーティは、うしろの段ボール箱に手をのばし、中から着古した
オーバーコートを引っ張り出した。
「これは高いものではありませんが、売春婦のような服装で歩くよりは
ましです」と、牧師。
レッドは立ち上がり、尻ポケットから財布を出した。
「少しはましなものが食べられるように」と、レッド。300ドルを出
した。
グウェンは、コートを着て、レッドは、紙幣を牧師の机に置いた。
「ここがこんなに高い店だと知っていたら、ここへは来なかったかもし
れない」と、レッド。かしこそうな笑いを浮かべることに満足しながら。
「それでも来たでしょう」と、牧師。紙幣を机の引き出しから作った金
庫に収めた。
「でしょうね」と、レッド。守るようにグウェンの肩に手を置いて、ド
アに向かって歩いていった。
「神のご加護を」と、ドチャーティ。目に涙をあふれさせた。
16
キャブを拾うと、レッドは腕時計を見た。8時45分だった。ずんぐ
りした背格好の厚い唇の運転手は、防弾パーティッションを通して、横
目でレッドを見た。
「かわいいレディといっしょに、公園のまわりへ行きますか?」と、運
転手。お世辞を込めた口調で、臆することなく、グウェンの布の少ない、
子どもっぽいからだをじろじろ見た。
「マンゲチェズジョセフの店へ。2番通りと41番通りの角だ。28番
街を抜けていけ!それが、最短だ」
ぶっきらぼうな指示でさえぎったが、運転手のニヤニヤ笑いまで止め
られなかった。グウェンは、レッドの肩に頭を乗せた。
「バックミラーを客でなく、外の車を見るために使わないのか?」と、
レッド。
運転手は、多感な少女への痴漢がどうのこうのとぶつぶつ言いながら、
目線を道路に戻した。
「もっと背筋を伸ばして」と、レッド。グウェンに。「コートのボタン
を留めろ!」
グウェンは顔を上げて、色っぽい目でレッドを見た。ボタン留めはし
たことにして、頭のうしろをレッドの肩に乗せて、ため息をついた。
「自分で言うほど、あなたは下品ではない」
「オレは下品だよ」と、レッド。ポケットからタバコを出して火をつけ
た。少し吸って、せきをして、すぐはき出した。レストランに着くまで、
2回腕時計を見た。
「これから会う人は、そんなに重要なの?」と、グウェン。
「彼女は、最高さ」と、レッド。グウェンの嫉妬心には気づかなかった。
マンゲチェズジョセフの店に着くと、ふたりは支配人に入口で止めら
れた。グウェンは意地悪く、コートの前を開いた。
支配人はレッドに軽蔑的な顔をした。普段は、チップの少ない客やス
テーキをよく焼いてと注文する客向けの顔だった。
「娘さんがドレスでしたら、よろしかったのですが」と、支配人。なめ
らかなフランス語の発音で。
「娘じゃないわ」と、グウェン。
「そう?」支配人は、鼻を高くした。
「ここでは食事の予定はない」と、レッド。「保健所の友人が言うには、
この手の店では照明が暗すぎて、ゴキブリにはサングラスの必要はない
そうだ」
支配人は、ショックを受けた。グウェンは、くすくす笑った。
「フィフィはどこだ?」
「だれ?」
「フィフィ、つまり、ジェーン。ブロンドの美人。ここでウェイトレス
をしている」
「ジェーンデュですか?彼女なら、やめました。お客さまもお帰りくだ
さい」
「帰る気になればな。彼女はどこへ?どのくらい前?」レッドは聞きた
がった。
「警察を呼びますよ」
「今夜、オレに警察を呼ぶと言ったのは、あんたでふたり目だ。最初の
やつの相棒は、1ヶ月もすれば、ベルビュー病院から出てこれる」
支配人は、レッドの細めた目に偏執的なぎらつきを感じた。
教えてあげることにして、フランス語の発音はやめた。
「ジェーンデュは、数時間前にやめた。女優になるために、この町を出
ると言っていた。カリフォルニアでコマーシャルをとるとか」
レッドは、ボディブローを食らった気がした。
◇
レッドは歩き出した。グウェンは、数歩あとからついて行った。
「ジェーンってだれ?フィフィは?」と、グウェン。ほんとうは聞きた
くなかったのだが、嫉妬心がまさった。「ガールフレンド?」
レッドは、カーブまで歩いて、ふたのあるゴミ箱の上に座った。肩を
頭の上までひっぱり上げて、考えようとした。
なぜフィフィは待たなかった?いっしょに逃げることができたのに。
おかげで、フィフィの代わりに、降って湧いた災難のように、卒業パー
ティを心配するガキを連れている。フィフィは行ってしまった。それで、
メロニーを大陸横断の旅に連れてゆかなけりゃならない。つまり、グウ
ェンを。女性たちは、なぜ、しょっちゅう名前を変えるんだ?
「あのう」と、皿洗いのエプロンのプエリトリコ人の青年。レッドの足
の近くに腐った魚の臭いのするゴミの箱を置いた。「このゴミをちゃん
と置かないと、持って行ってくれないんですよ」
レッドは、足を箱の上に乗せた。
レッドは、グウェンが気にしてる顔色に気づかなかった。フィフィを
行かせるべきでなかった。やつらが、フィフィに嫌がらせをしたのだろ
うか?あの女は正気を失って、逃げただけなのか?彼女は、レッドの女
だが、じゅうぶん変わった女だから。
彼女のアパートは、もぬけのからだろう。レッドは、戻って支配人に、
彼女がやめた正確な時間を聞きに行こうとした。プエリトリコ人の皿洗
いが戻ってきて、ワインの空き瓶の入った箱を置いた。
「フィフィを知ってる?」と、レッド。
「だれ?」
「ジェーンのこと。ウェイトレス。ブロンドの美人」
皿洗いは、低く口笛を吹いた。「ああ、すごい美人!」
「どこへ行ったか分かるか?」
皿洗いは、抜けめのない顔をした。今までなんども、殺人課の刑事や
欲深いホテルマンや飢えたスパイに見てきた顔だった。レッドは財布を
出した。
「知りません、だんな」と、皿洗い。
レッドは、5ドル紙幣を出した。
「彼女なら、73番通りに住んでた」
「過去のことは、買う気がない」
「支配人が言うには、ロサンジェルスに行くと」
レッドは、紙幣を渡し、もう1枚出した。「いつ店をやめたんだ?」
「今日の午後。たぶん3時半ごろ」
レッドは動かず、皿洗いは、期待して待った。
「彼女は支配人に、女優になると言ったそうです」と、皿洗い。「ぼく
には、ほんとうの理由を教えてくれなかった」
レッドは、もう1枚も渡した。
「だれかに追われていると言っていた。たぶん、ロコ。おそろしいと言
ってた。やつは、みんなを殺したと」
皿洗いは、紙幣をエプロンのポケットに入れて、急いで店に戻ってい
った。
これで説明がつく。レッドは考えた。ロコだ!やつが彼女をこわがら
せたのだ。手下を送り、彼女は逃げた。なにも考えずに、レッドダイア
モンドが唯一の救いだということも忘れて。
レッドは、ゴミ箱から立ち上がった。
彼女は、ロサンジェルスに向かった。たぶん、レッドより1便か2便
早い便で。なんてラッキーなブレイクタイムだ!ふたりにとって。レッ
ドは、ガキを送り届けたら、フィフィを見つけ、いっしょにロコをやっ
つけたら、めでたしめでたしだ!
「行くぞ、メロニー。フライトを予約しよう」
◇
ヒルトンホテルまで歩いた。レッドは夜の冷気を顔に浴びて楽しんだ。
グウェンがレッドの歩くスピードについてゆくのに苦労していることに、
しばらくは気づかなかった。
ヒルトンホテルの夜の受付は、赤味がかった顔色の男で、こげ茶のウ
ィッグをつけて、レストランの支配人と同じ高慢な表情でレッドを見た。
「その方と室まで行けません」と、受付の男。グウェンを指差した。
「指を食われたくなければ、鼻の後ろに隠しておいた方がいいよ」と、
レッド。「レッドダイアモンド宛ての郵便は?」
「ここにお泊りで?」
「隣りの騒音が大きかったので、今は、プラザホテルに泊まっている。
サービスがいい」
受付の男は、咳払いをした。ゆっくりと郵便箱をチェックした。そし
て、レッド宛の包みを見つけると、死んだネズミが入っているかのよう
に手渡した。
レッドは受付の男に1ドルのチップを渡した。「これで新しいウィッ
グを買いな。つぎからは、じゅうたんの下が汚れていてもそうじしない
ように」
◇
外に出ると、グウェンは、また、くすくす笑って、手をからませだ。
「あなたは、ひとの扱いが分かっている。あなたを叱りつける人なんて
いないはずよ」
「今まではな。オレの年になれば分かるが、メロニー、叱りつける人は、
叱りつけられるべき人なんだ」
「年はいくつ?」
「かなり上だ。あんたのお父さんよりも。さぁ、前のボタンを留めて、
2度とオレに色目を使うんじゃない。変質者としてオレを逮捕させるつ
もりか?」
ふたりは、キャブでポートオーソリティのバスターミナルまで行った。
狭いレインコート専門店で、レッドはグウェンに新しい服を買った。グ
ウェンは、まるでパリのデザイナーのガウンをもらったかのように身に
つけた。
写真店では、レッドはエックス線からフィルムを保護する写真ポーチ
を買った。
ロッカーからリヴォルバーを取り出すと、だれも見てないすきに、写
真ポーチにすべり込ませた。
「なにそれ、銃?」と、グウェン。目を見開いた。
「今見たことは忘れろ!」と、レッド。別のロッカーから出したスーツ
ケースにポーチをすべり込ませた。
「なにをしてるの?」
「腐らないように、ラップしている」
「もっと、まじめに!」
「金属探知機を通るときに、銃の形が分からないように、ラップしてる
のさ」
「頭がいいわね。今まで会ったなかで、もっとも切れ者だわ」
「どうしようもないやつと、いっしょだったんだな?」
グウェンは、侮辱されて、5分間黙っていた。空港に向かうリムジン
バスに乗ると、どんなに彼がかっこいいかしゃべりだした。
「あなたは、頭がいいわ。私立探偵ってみんな、そう?」
「みんなじゃない。なん人かは頭がいい。オレは、そんなに頭がよくな
い。ほかのやつの洗い残した汚い洗濯物で、もっときれいに洗う必要の
あるものを、ちゃんときれいにしてるだけ」
「でも、かっこいいわ。それに、タフだわ」
「オレがもしも頭がよかったら、金持ちになっていた。タフなやつは、
そこらじゅうにいる」
「わたしの父は金持ちだけど、かっこよくない」
「父のことを、そんなふうに言うもんじゃない」
「でも、ほんと。父の関心は、ビジネスだけ。父に出てゆくって言った
けど、止めもしなかった」
「お父さんは、まさかと思ったのさ。しかし、あんたは、出て行った。
ご満足?」
「そうね」グウェンは、レッドの肩に頭を乗せた。
「グウェンのお父さんのことを話して」
「パパは、軍隊にいた。あまり覚えていないけど、たまに、軍隊のこと
をしゃべってくれた。わたしのことを、グウェン少佐と呼んで、敬礼さ
せられた」
いい思い出ではなかった。グウェンは、涙を流しそうになった。
「今は、なにを?」と、レッド。
「大きな会社の経営者。いつも会議ばかり。特に、最近は。しゃべって
るのを聞くと、会社がうまく行ってないのだと思う。資金を動かせだと
か、支出超過だとか言ってるわ」
「ビジネスに夢中で、あんたに関心が薄いように見えるのだろうが、賭
けてもいいが、きっと、あんたのことを心配している」
「そうね」
空港に着いて、出発まで30分あった。グウェンは、トイレへ行って、
残っていた顔の化粧を落とした。
出発便のアナウンスを待っているあいだ、グウェンは、ますますイラ
イラさせられる子どものようになった。フライトがアナウンスされると、
コニーアイランドに初めて行く子どものように、タラップを上がった。
そのはしゃぎようが、レッドに自分自身の失われた子ども時代を思い
出させた。孤児院から逃げて街の通りで暮らし、もぐり酒場の主人にメ
モを届けたり、ブロンクスの街を笑いながらバイクでかけ抜け、逃げ足
が速くなり、パンチが早くなった。
そのころに、仲間の父親をゆすっていた警官を殴った。裁判官は、レ
ッドにどちらかを選べと言った。結局、刑務所より軍隊を選んだ。それ
から自身、警官になり━━━今となっては、薄れゆく過去の記憶の断片
にすぎない。
禁煙、シートベルト着用の表示。レッドは、シートを後ろに倒した。
レッドもグウェンも過去の記憶に埋もれた。
サムスペード、フィリップマーロー、シェルスコット、リューアーチ
ャー。チャンスがあれば、あいさつしたい。いっしょに酒でも飲もう。
その土地のことを教えてくれるだろう。戦争の話でもして、ロコの居場
所を教えてもらおう。なんという偉大なやつらだ。ラストアメリカンヒ
ーローたち。
レッドは、おそらく、彼らに接触しない方がいい。そう決めた。どの
くらい口が軽いか分かったもんじゃない。彼らの手柄については、多く
語られている。いいやつらだが、栄光を求めている。時として、手柄を
横取りされるかもしれない。
レッドは、自分のことは自分で解決しなくてはならない。ロコはすで
に彼らに接触してるかもしれない。やつは、悪いニュースだった。いや
なやつ。
旅客機は、轟音をあげて大陸を横断した。
17
レッドとグウェンが空港から出たとき、背後から太陽が昇ったばかり
だった。
ロサンジェルス。理解するまで少し間があった。それは、キャブだっ
た。緑と白、屋根の上に赤。すべてが違った。イエローキャブは1台も
なかった。どう考えても、ナチュラルに見えなかった。
やしの木が見えた。地面からはえた太ったパイナップルのようだった。
そう、たしかに、LAだ。車はみんな小さめで、デトロイト製でなく、
メイドインジャパンだった。だが、変わらないものもあった。有名では
ないが、少女が駐車場で発見された、赤のチューリップ事件を思い出し
た。
「早く!お迎えのリムジンは、あそこよ!」グウェンは、レッドの腕を
押した。
不機嫌そうな顔の青年が、カーブで停めた黒のリムジンのドアをあけ
て待っていた。グウェンにおざなりなあいさつをし、レッドのことは、
ほとんど無視した。
リムジンがサンジエゴ高速を北に走っているとき、グウェンは運転手
に質問した。運転手は簡単に答えた。レッドは目を閉じていた。耳はオ
ープンのまま、ふたりの会話を聞いていた。
グウェンは、若さゆえのスピード狂の興奮で、フライトのあいだしゃ
べり続けていた。レッドは、眠気と戦いながら、価値があると思える情
報だけ聞いていた。
運転手にニューヨークの彼女の冒険をしゃべり始めたときも、レッド
は居眠りをしていた。レッドの知ってることをくつがえすような話をし
た。レッドは、グウェンの感性を信じていた。
大人たちより多くの地獄を経験した子どもたちは、大人たちに貸しを
作ったようなもんだ。街の通りでパンチングボールで遊ぶ子どもたちは、
疲れた警官より、もっと多くの情報を持っている。
エドワードマンフレッドは、陸軍情報局長官の職を務めたことのある
など、長い間、軍隊にいた。退役後、民間の企業に移り、現在は、ハイ
テク産業協会の主任理事および理事長である。そこは、グウェンがよく
分からない先端技術を扱う企業グループであった。グウェンにも分かる
のは、彼が事業で問題をかかえていることだった。
マンフレッドは、64才で4度結婚し3度離婚した。娘がふたりいる
が、息子は生まれなかった。冷たい魚みたいだが、グウェンは、自分が
一番好かれてると思っている。
レッドは、リムジンが、黒の鉄フレームに鋳造された2頭のライオン
の門に着くまで、居眠りしていた。運転手は━━━グウェンは、トッド
と呼んでいた━━━車のボタンを押すと、門がゆっくりひらいた。高速
道路より短くて狭い、ドライブウェイを車が降りてゆくと、家に到着し
た。
レッドは、誘拐された南部の美人を追跡していたときに訪れた農園を
思いだした。
小さな像が6こあった。人工的に小さな照明で照らされ、白の記念碑
の前の広い芝生の周りに置かれていた。奴隷の出てこない『風と共に去
りぬ』の世界だった。
「バッグをお持ちしますか?」と、トッド。
「ありがとう、気にせずに」と、レッド。
「なんて?」と、トッド。分からないという顔をした。
「お好きに」
グウェンは、すでに、正面玄関の階段を駆け上がっていた。ベランダ
の柱のひとつにもたれて、レッドとトッドを待った。
トッドは先に歩いて、みんなのためにドアをあけた。黒の制服のメイ
ドがふたり、中で待っていた。
ひとりは、ずんぐりむっくりの体型で目立たない顔の中年の女性で、
髪を後ろに丸く束ねていた。グウェンがドアを入ると、すぐに大声で抱
きしめた。グウェンもそれにこたえ、ふたりで涙を流した。
もうひとりの女性は、きちんとしたブルネットの髪で、感情的なシー
ンを見て、冷淡に驚いていた。彼女の制服は、腰よりは低いが、ほかの
女性の太ももより上の高さだった。レッドを信頼するように見上げ、ト
カゲが空気を感じるように、舌で唇の赤をなめた。レッドがウィンクを
すると、よそよそしい表情に戻った。
「なぜなの?」と、家庭教師。すすり泣きの合間に繰り返した。グウェ
ンは答えられなかった。家庭教師はグウェンを連れてゆき、トッドもレ
ッドのバッグとともに姿を消した。
「名前は?ゴージャスさん」と、レッド。
「ロザリー。あなたはレッドダイアモンドでしょ?」
レッドはうなづいた。
「わたしはメイド。用があれば、口笛を吹いて!」
ゆっくり歩くと、制服がヒップを目立たせるようにぴったりとした。
レッドは低く口笛を吹いた。ロザリーは、ありがとうと言うように後ろ
を振り返ってから、歩いて行った。
◇
レッドは玄関を抜けて、広い室へ入った。そこは、アンティック家具
やいろいろな骨董品で散らかっていた。唯一の音は、凝った彫刻の施さ
れた振り子時計のチックタックいう音だった。外の日差しは強さを増し
始め、磨かれたフローリングの床に敷かれたペルシャジュータンのひと
つに光線の帯を作った。
レッドは、わずかなアンティック家具の知識を思い出そうとした。そ
れは100万ドルを横領したボストンの銀行家がからむブラックベイの
事件で、銀行家はルイキャトルズのイスで尋問されたのだ。そのとき、
トッドが足音もなく入ってきた。
「マンフレッド氏が会えるそうです」と、トッド。
「きみはなんの係り?」と、レッド。室を出るときにきいた。
「なんでも。運転手、執事、ボーイ、ボディガード、それに、ベビーシ
ッター」
最後の言葉には、嫌悪感が込められた。トッドは、グウェンが近くに
いるときよりもルーズに見えた。アスリートのような自然な優美さで、
スマートに自信をもって6つの室を通り抜けた。
「運動をしている?」と、レッド。後ろを歩きながら。
「少し」と、トッド。あきらかに、自慢そうだった。
「端から端まで歩くだけで、運動になりそうだな?」
「でかい家ですから」
「まったくそうだな。小さなフットボール場を見たことあるが、ここよ
りドアは少なかった」
トッドは、重いオーク材でできたドアの真鍮の取っ手を回して、東洋
家具で統一された室へ入った。床は中国製のジュータンで、カーリーと
シヴァのインドの像が台座に置かれていた。凝った彫刻の障子と屏風が
あった。壁には、なにかが吊るされていたらしい6・7のシミがあった。
「ここでなにが?」と、レッド。シミの1つを指差した。
トッドは、室の反対側の重いドアをあけた。
「将軍が会いたいそうです」レッドを手招きした。
山頂に降り積もった雪のような白髪の男性が、大きな19世紀風マホ
ガニーのデスクに向かって座っていた。男性は、読んでいる書類から顔
を上げなかった。
よく手入れされた銃が、濃茶の木の壁で、かすかな光を放っていた。
カスタム製のライフルや手製の銃身や銃床のショットガンが、デリンジ
ャーから44口径マグナムまでのさまざまな拳銃、決闘用のピストル、
リヴォルバー、あらゆる口径のオートマティックとバランスを保って飾
られていた。南部アメリカ人の将軍を満足させるに十分な、武器の量だ
った。
男性は、イスからゆっくり立ち上がった。堂々とした体格が、6フィ
ート6インチの背丈をより印象的にしていた。ゆっくりとした動作は、
年齢からくる疲労ではなく、王者らしい風格からだった。強そうなアゴ
が突き出ているのは、彫刻のためにポーズをとっているかのようだった。
レッドと握手したとき、手のにぎりは強いが冷たかった。
「娘を安全に送り届けていただいて、ありがとう」
「娘さんは、あんたが出迎えてくれたら、もっと喜んだ」
マンフレッドは、冷ややかにレッドを見た。
「娘は、私の気持ちが分かる。あとで話すつもりだ」
「彼女は、まだ子どもだ」
「彼女は、マンフレッド家だ」と、退役将軍。きびきびとした口調で。
「コーヒーはどうです?」
「いいですね、ブラックで」
マンフレッドが指で合図すると、トッドはドアから出て行った。
「名前は、レッドダイアモンド。なんとなく馴染みがある。前にお会い
した?」
「いいえ。しかし、オレのことが書かれた記事は読まれたかも。いろい
ろと書かれているから」
「口が堅いことは、信じていいんでしょうね?」
「その点は、大丈夫。チャンドラーやハメットといった作家たちは、オ
レやほかの優秀な探偵たちの話を書く。しかし、やつらは、よく事実関
係を間違えたり、名前を混同したりする」
「チャンドラーやハメット?」と、マンフレッド。玉座のような革張り
のイスに戻った。
「からかってるのか?ほんとうに私立探偵なのか?」
「もうなん年も、人をからかったりはしてない」と、レッド。「オレは、
私立探偵だ。48州ぜんぶで仕事をしてきた。海外の場所でも」
「50州という意味?」
「オレは、数学ができたためしがない。地理も」
「身分を証明するものは?」
レッドは、両手を挙げて、指の先で頭の横をたたいた。「オレは探偵
大学の学位はもらってない。それでも20年間、探偵をやってきた。撃
たれたり、刺されたり、頭をたたかれたり、半殺しの目にあったり、薬
を飲まされたりした。しかし、わいろを使ったり、ほらを吹いたり、雇
い主の信頼を裏切ったりしたことはない」
「身元保証人は?」
「今、言ったように、口は堅い。雇い主は、名前を公表されるのを嫌う。
それに、オレにはほかに仕事がある」
「じゅうぶんな報酬は払う」
「ええ。なにをしてほしい?東洋の絵画を盗んだやつを見つけるとか?」
「なぜ、分かった?」
◇
そのときノックがして、ロザリーが銀のトレイを持って室に入ってき
た。トレイの上には、小さなコーヒーポットと小さなパイがいくつか乗
っていた。
ロザリーは、必要以上に身をくねらせて、レッドにコーヒーを注いだ。
胸の色気をふりまいた。
「小さなパイはいかがです?」と、ロザリー。
「普通サイズの方がいい」
ロザリーは、トレイを置いて室を出て、ドアを閉めた。
レッドは、ロザリーがいるあいだ、マンフレッドを観察していたが、
彼女の色気には関心が薄いようにみえた。会話に早く戻りたいようだっ
た。
「彼女は、窓拭きを?」と、レッド。
マンフレッドは、質問の意味をしばらく考えた。
「ああ、する。彼女は、お客に慣れていない。それでああいう態度をと
るのだ。あとで、よく言っておく」
「オレには差し障りはない。彼女の仕事はなにか知りたかっただけ」
「寝ているかどうかということなら、それこそ、きみには関係がないが、
答えは、ノーだ。きみの態度ややり方を、私が好きだと思わないでくれ。
そのいやらしい考え方も」
「職業病だな。あまりに汚い仕事をしてきたせいで、あんたは自分の鼻
のにおいさえ嗅げなくなった。オレはあまり花園にいたことはないもの
で、しばらくすると、いろいろ想像してしまう。そのことをすまないと
は思ってない。そのために、アルコールに走るやつもいれば、堕落する
やつもいる。オレは、もう疲れた」
レッドは、コーヒーをすすった。濃くてうまかった。
「私の絵画コレクションが盗まれたと、どうやって知った?」
レッドは、パイをほおばった。それから、2つめをゆっくりかじった。
それから、待たせるように、コーヒーをゆっくり味わった。
「壁に付いたシミ。まだそうじされてなかった。それで、あれは最近の
出来事だと推測した。長方形のかたちから、日本か中国の絵画だと分か
った。東洋の家具と調和するようなものだったと。なにか、追加するこ
とは?」
「3日前の夜中、なにものかかが侵入した。私は、フェニックスに仕事
で出かけていた。最新の防犯システムにもかかわらず、およそ600万
ドルの絵画が盗まれた」
「ほかに盗まれたものは?」と、レッド。室の壁に飾られた、明らかに
高価な武器類を眺めた。
マンフレッドは、首を振った。「日本の絵画だけ、7つ」
「保険は?」
「いや」
「なぜ、保険をかけなかった?」
「きみとは関係ない」
「警察には?」
「知らせてない」
「なぜ?」
「それも、きみとは関係ない」
レッドは、コーヒーを飲みほした。
「マンフレッドさん、あんたに関係することは、オレとは関係がないと
いうことなら、これ以上は進めようがない。いろいろ、おもてなし、あ
りがとう」
レッドは、立ち上がった。
「座れ!」
「あんたは軍隊にいるわけではない、将軍。それに、オレは雇われてい
るわけではない。ある女性を捜していただけ。あんたに20の質問をす
る時間は、もうない。優秀な探偵をなん人か紹介できる。あるいは警察
に頼むとか。美術品どろぼうは、オレの専門外だ」
マンフレッドは立ち上がった。レッドは、相手が近づいてくるんじゃ
ないかと思ったが、堅い表情はなくなっていた。
「悪かった、ミスターダイアモンド」謝るのは、苦手そうだった。「ど
なって命令するだけの45年だったので、悪いくせが出たようだ」
「たしかに命令された」
「ある女性を捜しているとのことだが、娘を捜すことなら協力できるの
では?」
「上の娘?」
「そう、グウェンが話した?」
「いや」レッドはうそをついた。グウェンは姉のアリソンの話をしてい
た。年は29、知能はねずみ程度で、道徳感はティファナの売春婦以下、
妊娠中絶に使ったお金で、国中の貧困層の半分は養えたそうだ。レッド
は、偏見に満ちたポートレイトとして、信用しなかった。
「私は女性運には恵まれなかった」と、マンフレッド。「その証拠に離
婚費用が莫大になっている。全能の神のいたずらか、ふたりの前妻が、
新たなふたりの娘を残し、さらなるトラブルを生んでいる」
マンフレッドは続けた。
「グウェンは、とてもいい子で、ただのおてんば娘。男であったらと願
うことも少なくなってきている。しかし、アリソンは違う。いつも驚か
される。ある日などは━━━」
デスクにあったアリソンの額入り写真を手渡されたとき、マンフレッ
ドの声はレッドには聞こえなくなった。レッドは、マーローやアーチャ
ーやスコットといった、南カリフォルニアの焼けるような太陽にふさわ
しい優秀な探偵を、紹介しようとしていた。
しかし、5×7インチの額入りカラー写真を見たとき、言葉が口のな
かで凍りついた。
それは、フィフィだった。たしかに、鼻はもっと低くて、スマートだ
ったが、最近の美容外科でどうにでもなることだった。ヘアスタイルは
違って、もっと短かったが、ブロンドの髪のうっとりする雰囲気はその
ままだった。
フィフィは、前に、裕福な家庭の出であることをほのめかしていた。
いくらか反抗的ではあるが、写真からこちらを見つめてくる深いブルー
の目を見て、レッドは確信した。
「━━━いつも問題なのだ。男にとって、いまいましいことに」と、マ
ンフレッド。「たいてい故意でひどい。聞いてます?」
レッドは、うなづいた。写真入れをそっとつかんでいた。「いつから
いなくなった?」
「だいたい1週間前に出て行った。メイドが言うには、私が外出してい
るときに、赤のスポーツカーの日焼けした男性が連れていったそうだ。
私は、私立探偵に依頼したが、なんの手がかりもない」
「その探偵の名前と住所が必要だ。探偵に言って、情報の引継ぎをお願
いしてほしい」
「それじゃ、引き受けていただける?」
レッドは、うなづいた。
「そりゃ、よかった。依頼費用は?」
「それなりにいただければいい。金持ちになる気はない。見つけるだけ」
「手柄には報いたい。グウェンを無事送り届けてくれたことには、5千
ドルがふさわしい」
「オレは、報酬はあてにしてない。弁護士費用にでも使ってくれ。あと、
フィフィを連れ戻す費用とかに」
「フィフィ?」
「アリソン」
「そう。では、お疲れでしょうから、室を用意しますか?」
「それは、助かる」
マンフレッドは、デスクの上のボタンを押すと、数秒でトッドがノッ
クした。
2階の寝室に案内されてから、レッドは今までのことを整理しようと
した。マンフレッドは、フィフィが絵画を盗んだかもしれないことを怖
れていた。それが、警察に通報しなかった理由だ。そのあたりは明らか
だった。
つぎに、フィフィがどのように、またなぜ家出して、ニューヨークへ
行って、ウェイトレスをして、また、戻ってきたのか考えた。レッドは
あまりに疲れていたので、結論を得るにいたらなかった。
強い眠気がやってきて、レッドをノックアウトした。
18
レッドは、厚いベルベットのカーテンで遮られてはいたが、暖かいカ
ルフォルニアの日差しの中で目覚めた。ゆっくりと伸びをして、疲れて
いて無視していた室内を見回しながら起き上がった。
小さなライティングデスクに、イスが2脚、それにドレッサーがあっ
た。ベッドのヘッドボードも同様に、どれもが凝った彫刻が施され、古
色然とした木製だった。
レッドの服はクローゼットに吊るされてるか、あるいは、きちんと折
りたたまれてドレッサーにしまわれていた。銃は、ドレッサーの一番上
の引き出しにあった。弾装はカラだったが、新たに装填されていて、油
がさされていた。
ドアにノックの音がした。レッドが答える前に、ロザリーが入ってき
た。レッドは自分が裸だと気づいたが、隠そうともしなかった。
「トッドが服をぬがせた」と、ロザリー。「服を着るお手伝いをします。
起きる音がしたので」
レッドはただ笑った。「先にシャワーを浴びたい」
「背中を流せと?」
「ひとりで洗いたい」
ロザリーは、すぐに出てゆかなかった。「ほかにお手伝いは?」
「フィフィに最後に会ったそうだね?」
「だれ?」
「マンフレッドの娘、アリソン」
「あら、ブルネットはお嫌いでは?」
ロザリーの服は、少し乱れていた。
「冒険したい気分」と、ロザリー。「わたしはお嫌い?」
「ミツバチと同じで、蜜は好きだが、今は、情報が欲しい。アリソンは
だれといっしょに?」
ロザリーは1歩下がって、いらいらした。「グリーンの車の背の低い
男。免許証とかは見てない」
「ふん。マンフレッドのところには、いつから」
「3ヶ月くらい。15年間は同じ召使だったが、みんなやめさせた。マ
ンフレッドに嫉妬されるのが心配でも、大丈夫。月に一度くらいマッサ
ージをしてあげると、とても喜んでいた」
「それはよかった。フィフィだが、つまり、アリソン、去る前になにを
しゃべっていた?」
「少ししかしゃべってない。共通の話題がほとんどなかったので」
「盗まれた絵画についてなにか?」
「わたし以外は、すべてに興味あるのね?トッドの方がタイプ?」
「どういう意味?」
「考えてみて!絵画については、わたしにはアリバイがある。友人たち
と外出していた」
ロザリーの声から色っぽさが消えた。言葉も、とげとげした敵意ある
ものになった。
「今からシャワーだ。雨に歌えばがいい」
ロザリーは、シャワールームへ行くレッドを複雑な顔で見送った。ド
アを閉めて、全身くまなく洗ってから、冷たい水を浴びた。
アンドリューズシスターズの「そんな気分」を歌いながら出てくると、
タオルでふき取った。十代のころと同じで、女性のことを追い払うには、
冷たいシャワーがいい。
ロザリーのことが気になっていた。彼女は、バスケットチームのハー
レムグローブトロッターズより素早く動いていた。レッドは独身主義者
というわけではなかったが、ロザリーとゲームをするには、まだ早すぎ
るようだ。彼女には、星条旗の演奏で起立する群集のように、レッドの
首のうしろの髪を逆立たせるなにかがあった。
レッドが1階に降りると、狼の群れを養えるほどのご馳走が待ってい
た。家庭教師は、高齢の召使たちが解雇され始めてから、コックも兼ね
ているらしく、グウェンを連れ戻してくれたレッドに、感謝を込めて、
ターキーのようにたらふく食わせようとしていた。
レッドがふたつ目のサンドイッチをほおばっていると、トッドがダイ
ニングルームに入ってきた。
「よく眠れました?」と、トッド。
「ママの腕の中のベイビーのようにね!ボスはどこ?」
「ダウンタウンのオフィスです。絵画の盗難もすぐに調べるつもりです
か?」
レッドは笑った。「なぜ?」
「ただの好奇心です」
「マンフレッドが好奇心を持てと?」
トッドは笑い返した。「抜け目ないタイプですね」
「無駄口を叩いて、船が沈むこともある」
「マンフレッド氏から、調査を依頼した探偵会社が、センチュリーシテ
ィにあるウェリントンハーグレイブ調査会社だと伝えろと言われました」
と、トッド。淡々と。「外に停めてあるブルーのフォードは、自由に使
っていいそうです。あなたの探偵会社をお教えいただけたら、小切手を
用意するそうです」
「現金の方がいい」
「手配します」と、トッド。
トッドと入れ違いに、グウェンが入ってきた。落ち着いた白のシャツ
に、普通の丈の格子縞のスカートをはいていた。顔も洗って、紅い頬を
していた。
「まるでノーマンロックウェルの絵から飛び出てきたみたいだな」と、
レッド。
「だれそれ?」
「雑誌の表紙を描いていた人物さ。どう、元気?」
「ええ。ミスターダイアモンド、あなたは?」
「いいね。オレのことは、レッドと呼んでくれ」
「分かった、レッド」と、グウェン。神経質そうにくすくす笑った。
「乳母によると、わたしの今日の授業をなしだそうよ。つまり、あなた
にカリフォルニアを案内できる」
「天気予報を見ておいた方がいい」レッドは、グウェンに幻滅したよう
な顔をされた。これは、ロザリーの申し出を断ったときにも受けた。
「カリフォルニアに雨は降らないことを知らないの?」
「オレがいるあいだは、雨はない」と、レッド。
19
赤レンガに打ち付けられたブロンズ額の看板には、ウェリントンハー
グレイブ調査会社━━━国際本部とあった。小さな築40年のビルは、
ロサンジェルスとしては古かった。センチュリーシティタワーが見える、
最も高給の弁護士たちが住む高級住宅街にあった。
受付嬢は、高価そうな化粧に、黒髪にずきんをかぶった女だった。レ
ッドを見て、ガムをくちゃくちゃいわせてから、退屈そうな顔をした。
「おい、かわい子ちゃん、オレはクラークゲイブルでないことは知って
るが、そのくちゃくちゃいうのをしばらくやめて、ボスに、レッドダイ
アモンドが来たと伝えてくれ!」
「お約束は?」
「ない」
「フィップス氏は多忙でして、ご用件を述べていただければ、数日中に
お会いできます」
しかし、マンフレッドの名を出すと、すぐに受付嬢はガムをかむのを
やめて、インターフォンになにか言うと、レッドは、ブラッドリーフィ
ップスのオフィスに通された。
広いオフィスは、ショールームではきらびやかだが、使い勝手の悪い
現代家具で飾られていた。壁は、賞状や独身の顧客からの感謝状、弁護
士が多額の依頼料と同じくらい好きなドーミエのプリント画でおおわれ
ていた。
フィップスは、三つ揃えのカスタムメイドのスーツを着たやせた男で、
デスクに使っているクロム製の柱に置かれた、スモークガラス板の背後
から立ち上がった。完璧にマニキュアされたみごとに日焼けした手を広
げ、めがねをかけた顔にはあざけりのような薄笑いを浮かべていた。
レッドは、握手のときに必要以上に力を込めた。フィップスは、大げ
さにたじろいだ。相手が好かない気持ちは、お互い様だった。
「弁護士さんで?」と、レッド。
「会社の一員。調査を行う顧客の優先順位を決めている。あなたのレベ
ルは?」
「オレは、ガレリックバーの一員。殴るレベルをもらった。42クラス。
高校中退だ」
「ええ」
「人生はタフだ。バレー教室に戻ろうと思うが、足の親指の炎症が末期
状態だ」
聞こえてくる唯一の音は、天井に組み込まれたスピーカーから降りて
くるバックミュージックだけだった。レッドは、デスクの前のクロム製
の皮イスに座って、イスに飲み込まれるのを怖れて、前かがみでいた。
灰皿がないことに気づいて、タバコに火をつけた。
「それで、なにが分かった?」と、レッド。
フィップスは、デスクからファイルフォルダーを取り出した。
「アリソンマンフレッド、生年月日、1/2/53、女、白人、身長」
「そこはスキッップしてくれ!夢でも見れる。彼女の苦しむ悲鳴を聞く
必要はない。失踪については?」
「メイドのロザリーロドリゲスによると、背の高い白人の男といっしょ
だった。男の年齢40前後、車は黄のコンバーチブル。先週の日曜の1
7時頃。暴力の兆候なし。失踪者リストになし」
「ロザリーについては?」
「マンフレッドのところに3ヶ月。32、女、ヒスパニック系、離婚歴
あり。追加情報なし」
「マンフレッドについて、調査中のことは?」と、レッド。タバコの灰
をけば織のジュータンに落とした。
「なにも。なぜ?」
「ただの好奇心。マンフレッドの娘については?」
「銀行履歴やクレジット購入歴、その他を調べたが、履歴なし。調査員
は、最近のボーイフレンド6人に会ったが、新たな情報なし。すべて調
査済み」
「フィフィは仕事をしていた?」
「フィフィ?」
「アリソン」
「女優の職を希望していたが、一度もうまく行ってない。調査員は、前
のエージェントに会ったが、協力を拒否された。そのエージェントは、
シッドレビーという名で3流の映画会社で裏方をしていた」
「その調査員は、そいつを平手打ちしてやんなかったのか?」
「ミスターダイアモンド、今は20世紀。ここの調査員で、そんなネア
ンデルタール人的暴力に頼る者はいない。あなたには初耳かもしれない
が、モーテルのドアを蹴破ってあける連中はいなくなった。人々には権
利がある。イヤな顧客でさえ、そんな要求をする者はいない」
「そりゃよかった!それで、彼女は見つかった?」
「もちろん、ノー。でなければ、あなたに会ってない」
「たぶん、ドアの2つや3つ、蹴破ってれば、今ごろは、彼女を連れ帰
って、謝礼もたんまりもらっていた」
「ほかに質問は?」
「なし。ファイルのコピーが欲しい」
「ここの所有物です」
「マンフレッドに電話して、あんたとあんたの大卒の少年たちが失敗し
たことにオレが成功しそうなのを怖れて、協力してくれないと伝えても
いいのか?」
フィップスは、レッドをにらみけた。
「そんなことは彼は無視すると思うが、あなたのへまに助けが必要と見
えるので、会った者のリストと住所のフォトコピーをお渡ししよう。そ
れでご満足?」
「うれしい限りで」と、レッド。イスから立ち上がった。「それと、次
回、ネアンデルタール人って言う前に、電話を叩き切ったり、ガキをひ
っつかんだり、ゴミのように捨てたりしたことを思い出してくれ!きれ
いなオフィスを構えていても、程度の差こそあれ、仕事とは汚いものな
んだ」
20
シッドレビーのオフィスは、ハリウッドヴァインの南のビル、6階に
あった。受付はなく、レビーの散らかった仕事場へ直接入って行けた。
エージェントは電話中で、手振りでイスを示した。レッドは、座らず
に窓際まで行って、汚れた窓から外を見た。
ふたりの警官がパトカーから出てきて、通りで悪臭を放つ浮浪者を引
きずった。警官は、浮浪者の手振りや叫びを無視した。旅行者や通行人
は、ふつうのことのように見ていた。小説で有名な交差点は、デイモン
ラニアンの42番通りのように落ちぶれてしまった。
「━━━ああ、いいとも。きのう彼女が欲しかったことは分かってた。
ああ、すぐに。年金をもらっている太った女性が来なかっただけでもラ
ッキーだった」
レビーは、しゃがれたタフガイの声でしばらくしゃべっていた。中年
後半の男で、腹はぽっちゃりして、はげ頭だった。両足を傾いたデスク
の上に置いて、口にくわえた葉巻の灰は、ドリブルするように腹にこぼ
していた。
「分かった、分かった、取引は取引だ。すぐに、セッティングしよう、
じゃ、また」
レビーは、受話器を叩き切ると、ぶつぶつ言った。
「やつのコマーシャル撮影のために、美人の赤毛が必要で、全部で10
0ドルでやれと」
両足をデスクから降ろすと、レッドを見た。
「ご用件は?」と、レビー。
「オレは、レッドダイアモンド」と、レッド。デスクに体をもたせた。
「いい名前だ。しかし、だれかにすでに使われてるが。クリントイース
トウッドのお気に入りのカメラマンと知り合いで、彼に頼んで写真を撮
らせよう。腕利きの刑事の顔だから、キャスティングに紹介できる」
レッドは、エージェントの口から葉巻を引ったくって、デスクの紙の
上に押し付けた。
「腕利きの刑事の顔をしているのは、オレがそうだから」と、レッド。
ジャケットを後ろに引いて、銃を見せた。
「そして、あんたは、ハリウッドにわくダニの1匹だ」
「あんたは、ここへ入る権利はない」と、レビー。声が1オクターブ高
くなった。「先週、ハリウッドのチンピラにカネを払ったばかりだ」
「失踪した若い女を捜している」と、レッド。「女を見つけられたら、
あんたがおふくろを25セントで売ろうと気にしない」
「からかってるのか?まだ、IDを見てないし権利も読んでない!」
レッドは受話器を手にすると、ダイアルした。
「ハイ、チーフ。ダイアモンドだ。やはり正しかった。正面だ。そう、
売春斡旋。公務執行妨害。ああ、多少、殴った。護送車を寄こす?テレ
ビのやつらに知らせる?オーケー!いいえ、傷は見られない。護送車が
必要なら、また電話する。オーケー」
レッドは、天気予報の電話を切った。
「オレには女房と子どもがいる。そんなことやめてくれ!オレはおしま
いだ」
レッドは、エージェントの胸ぐらをつかんだ。
「女について教えてくれ。名前は、アリソンマンフレッド、ブロンド、
20代後半、美人。フィフィと名乗っているかもしれない」
「そんな特徴を持つ女は、ハリウッドボーリング場のレインの数くらい
いる。その女の特別なところは?数日前に、変なやつがその女を捜しに
きた」
「その女は、あんたのちゃちなビジネスを潰してしまうことになる」
「分かった、分かった、ファイルを調べてみる」
レッドがレビーを離すと、彼はグレイのファイルキャビネットへ歩い
て行った。引き出しをたどって、古新聞やソーダが半分残ったビン、汚
れたプレート、フリル付ピンク下着の束を引っ張り出した。
「ここのどこかにある」と、レビー。下着をゴミ箱に投げ捨てた。ゴキ
ブリがビンのソーダ水で泳いでいた。
「ダメだ。名前では一致しない。フィフィはふたり知っているが、ふた
りともブルネットだ。フランス人の顔だな」と、レビー。8×10イン
チの写真を手にした。大きな乳房の家庭的な中年女性が写っていた。
「この女を覚えている。顔とか体つき。仕事上で」
「警察署まで行けば、記憶を辿れるかもな」
レビーは両手を広げた。「オレを調べてくれ!オフィスも!ファイル
もすべて!もし女が見つかったら、オレは雷に打たれよう!」
「雷がする仕事じゃない」と、レッド。マンフレッドのカメラで撮った
アリソンのポラロイド写真を出した。
「あんたに5秒やる」
「ウソの会社名を名乗る悪の私立探偵も、同じものを見せた。金をくれ
ると言っていた。どんな金が絡んでいる?」
レッドは、エージェントの襟首をつかんだ。「あんたの医者代には足
りない」手首をねじ上げた。
「分かった、分かった、もう十分だ」
レッドは、レビーをファイルキャビネットまで押し戻した。レビーは
また捜し始め、男物のクツと1967年のサンフランシスコの電話帳の
入ったハンガーを出した。ページの間から、8×10インチの写真を引
っ張り出した。
「アリマローン、そう、名乗っていた」
レッドは写真を手にした。確かに、フィフィだった。しかし身に着け
ているものは、まつ毛だけだった。舌で口の端をなめていた。おぞまし
いものを感じ、すぐに写真をポケットにしまった。
「報酬は?オレは、ほかのやつが来たすぐ後に、写真を見つけた。オレ
は、顔とか体つきは忘れない。女について、からだを見ただけで、いろ
いろなことが分かる」
「どうしてそいつに、電話しなかった?」
「少しじらせたかった」
「頭がいいな。おかげでただで手に入った。住所は?いつ写真を撮った?
どのように彼女が来たのか、すべて、吐きな!」
「報酬は?」
レッドは、脅すように近づいた。
レビーは、また、早口でしゃべり始めた。今度は、声は高く半分泣き
べそをかいていた。
「やつが面倒を持ち込んだことを知っておくべきだった。ジェームズラ
ンダール。やつは、前にも何人か連れてきた。今度の女は、演技ができ
るようには見えなかったが、本物の美人だった」
「ランダールの写真は?」
「やつからもらったのは、これだ」と、レビー。レッドに名刺を手渡し
た。そこには、『ジミーランダール、タレントコンサルタント、パーテ
ィー専門』とあった。
「やつの人相は?」
「あんたぐらいの背丈で、もっとやせていて、髪はブロンド。35くら
い。賭け事やコカインや違法薬物をやってそうな、典型的なカリフォル
ニアのビーチボーイ」
レッドが出ていくと、ゴキブリが3匹、レビーのデスクプレートの上
を這いずり回った。
◇
レッドは、名刺にあったサンタモニカブルバードに車を走らせた。住
所には、2棟続きの化粧しっくいを塗った黄のビルがあった。いい日に
見えた。ランダールの名は、どの郵便箱にもなかった。レッドは、管理
人の室のチャイムを鳴らした。
「ああ」と、ドアを開けて答えたのは、だらしない50くらいのブロン
ドの女性。200ポンドを越える彼女の体重を、サイズの合わない明る
いフローラルなムームーに押し込んでいた。
「ジェームズランダールを捜している」
「わたしもだよ。2ヶ月分の家賃を踏み倒して、トンづらした。あんた、
刑事?」
「プライベートの。なぜきく?」
「あんたは優秀そうに見える。やつがどこか、皆目見当がつかない。テ
ナント商売でつちかった鼻が利かないのさ」
「あなたも優秀だと思う。大きな間違いはしていない」
「たぶんね」女性は、スクリーンドアをいっぱいにあけた。一度、レッ
ドは後ろに下がった。「あんたはまともな人間に見える。どうぞ、中へ」
レッドは、アパートの室をうろつく4匹のネコの1匹を、もう少しで
踏みそうになった。お客とは思わず、ネコたちは疑わしそうにレッドを
見た。室はネコや古いエサの匂いがした。
キッチンのトランプ台のテーブルに座ると、コーヒーをご馳走になっ
た。
「なぜ、あいつを捜している?」
「やつとそのガールフレンドが、オレのクライアントのカネを持ち逃げ
した」
「どっちが?」
「どういう意味?」
「どっちのガールフレンド?やつは、下着を変えるように、彼女を変え
る」
女性は、きまり悪そうに見えた。それから、はにかんだふりをした。
レッドは、笑って安心させた。ポケットからポラロイド写真を出した。
女性は、写真をしばらく見て、それから、おでこに貼った。「これは
最近ので、ぱりっとしているように見えるが、もっとぼろぼろのを見た
ことある。彼女が男からどう見られているのだろう?たぶん、人は若か
ったり惚れてたりすると、それで間違った選択をしてしまうんだ」
女性は、写真をおでこに貼ったまま、過ぎ去った、ほろ苦い思い出に
浸った。
「それは、なんとも言えない。あと、コーヒーはうまかった」と、レッ
ド。女性を夢から覚まそうと、ウソをついた。
「大丈夫だよ」と、女性。写真をレッドに返した。「そんな写真なんて
いらない」
「オレもだ。ふたりはどこに行ったと思う?」
「前の住所も知らない。わたしもやつを見つけたい。室を壊した上、2
ヶ月分の家賃を支払わずに逃げていった。大家は、室の修理代を請求し
てきた」
「まだある。ランダールはいつ出ていった?」
「3ヶ月前の真夜中」
レッドはがっかりした。女性の勢いから、逃げたばっかりのように思
えたからだ。
「進行中のことで、しゃべってないことは?」
女性はためらっていた。ネコがゴロゴロ言って、自分の足を舐めた。
「もちろん、口外禁止の上で」
互いの目が合った。それから、女性がしゃべりだした。
「やつは、定職にはつかなかった。カネができたのか、一度小切手で室
代を払った。ガールフレンドが何人かいて、売春婦のように見えた。夜
5時から出かけて、帰るのは翌朝の5時。うるさいから分かる。2回、
男たちを連れて帰ったことがあった。見には行ってない」
「ああ」
「室の出入りは、頻繁にあった。昼夜を問わず。シャレた車で乗り付け
て、15分か20分滞在するだけ。まったく忙しない話さ」
「車の種類や車体ナンバーは?」
「わたしのことをなんだと思ってるの?くの一じゃないのよ!それにこ
こからじゃ、車のナンバーは見えない。みんないい車に乗っていた。ロ
ールスロイス、メルセデス、コルベット、それにマウンテンライオンの
ような名前」
「ジャガー」
「そう」
「できるかどうか、ミス」
「コワルスキー、アンナコワルスキー」
「ミスコワルスキー、できるかどうか」
「アンナと呼んで!」
「ありがとう、アンナ。やつの室の中を見せてもらえる?」
「すでに別の人が入っている」
「そうか」
「なにもいいこと、なかったようね。3人のメキシコ人がいる。室の準
備だと言って、ゴミを捨てないように、入ってゆけるかもしれない」
レッドは、顔をしかめた。
「ちょっと待ちな、スノート」
「え?」
「スノート。車のナンバーの一種。カスタムプレート。メルセデスとか。
スノート」
レッドは立ち上がった。「いろいろありがとう。コーヒーに感謝する」
ドアに向かって2歩進んだ。
「なにも、おかまいできませんで」と、アンナ。会話が終わるのが残念
そうだった。「やつらが残したのは、請求書の山」
レッドは振り返った。「見せてもらえる?」
「まだ、あれば」と、アンナ。散らかった居間のドロップフロントデス
クへ歩いていった。2匹のネコが追いていった。あとの2匹は、レッド
を見ていた。コーヒーテーブルに置かれた白黒テレビのメロドラマの音
量を下げた。
アンナは、6通くらいの封筒を束から引っ張り出して、輪ゴムといっ
しょに持ってきた。2通は取立業者、1通はガス会社、その他の1つは
電話会社で、2つは、プライベートの手紙だった。
「開封しても?」と、レッド。
「わたしの重要なルールは、いかなる犯罪にも関わらないということ。
これは、税金をごまかして15ヶ月も留置所に入れられた前の夫から学
んだ。わたしは税金をごまかさないし、他人の手紙もあけない」
レッドは、右耳を引っ張ってから、包みをつかんだ。「分かってると
思うけど、これらの手紙はオレにとって大切だ。ランダールを捜してい
て、かならずこの手紙を彼に手渡す。そして、やつがアンナに借りてい
る借金は、ちゃんと返済させる」
「そうしてくれる?あいつには、いろいろ迷惑をかけられたということ
もあるけど、これはもう話した」
「オレはかならず、ランダールに返済させる。信じてもらっていい、ア
ンナ」
「あんたにとっては重要なものだからね。机の引き出しに眠らせておく
よりいい」
「お人形さんのようだ」
アンナは照れて、手で口をおおった。
「あとで連絡する」
「そうして!」と、アンナ。レッドは外へ出て行った。
レッドは、近くのデニーズに入って、苦いコーヒーの残る口を和らげ
るため、軽い食事を注文した。
注文を待つあいだ、包みをあけた。2通の取立業者の手紙は、いつも
の警告で、ランダールがすぐに支払いをしないと法的手段に出るという
ものだった。医者に287ドル、家具屋に306ドルの借金があった。
プライベートの手紙の1つは、女からのもので、丸っこい字で書かれ
ていた。文法もスペルもひどいものだった。シカゴに住んでいて、ラン
ダールから4才の娘の養育費をもらっていないと訴えていた。
彼女は、人生のどん底にいると、レッドは手紙を読みながら考えた。
絶望と貧困だ。せめて、見た目は美しい女性であって欲しいと思った。
もう1通は、ロンポック州刑務所に2年間麻薬密売で収監されて出て
きたばかりの男からだった。ランダールを責めてから、カネを要求して
いた。
麻薬に売春、これらが、とレッドは考えた。ランダールの室へ男たち
が頻繁に出入りしていた理由を説明していた。若者たちがおおっぴらに
麻薬の取引をしていたのだ。売春と同様に。
レッドは、電話会社の請求書をあけて驚いた。ロサンジェルス市内通
話が12件以上に長距離通話が5件あった。
レッドは封筒の束をポケットにしまい、ウェイトレスが運んできた食
事をたいらげると、相応のチップを置いた。レジで2ドルを小銭にかえ
てもらうと、車で公衆電話へ行って電話をかけ始めた。
21
最初の9回の電話は、なんの成果も得られなかった。なんども呼び出
し音を鳴らしているうちに通行人が出た公衆電話や使われてない電話番
号、経営者が変わったレストラン。ボーリング場では、ランダールの名
前を言った途端に電話を切られた。
レッドは、小さな黒手帳に、レストランやボーリング場の住所をメモ
した。
「ハロー」と、男。10回目の電話に答えた。
「オレはレッド。ジェームズの友人」
「この番号はだれにも教えないように言っておいたのだが」と、男。い
ぶかしがるように。
「重要な用件だ。ジェームズは困っている。オレはやつと同じ商売をし
ている。電話するように言われた」
「ああ」
長い間があった。サンタモニカブルバードの騒音を聞きながら、レッ
ドは待った。上下そろいの皮の服を着たゲイの男が歩いてきて、レッド
にウィンクをして、そのまま通り過ぎた。
「なにを持ってる?」と、男。電話線の向こう端からやっと答えた。
「電話でしゃべるのは好きじゃない」
「シャツ?パンツ?」
レッドはためらった。「どちらも」
「オレはシャツだけ。取引の前にサンプルとして、半シャツがいる」
「こっちは、直接ブツに触れたい。どこへ行けば?」
「ジェームズから聞いてないのか?」
「聞いてない」
「オーケー。ベルエア不動産は分かるか?」
「見つけられる」
男は住所を言った。「トーマスブラザース、32ページ、Dの5」
「は?」
「トーマスブラザース。地図さ。ロサンジェルスには?」
「5日前に着いたばかり」
「ジェームズとはどこで?」
「シカゴ」
「分かった。2時間以内に来てくれ!」
レッドは、トーマスブラザース地図を買ったり、ランダールの電話番
号にあったレストランに行ったりして時間を潰した。地図は役にたった。
レストランはすぐ見つかった。
◇
半シャツって?とレッド。ベルエア不動産へ車を走らせながら考えた。
シシリアン事件のことを思い出していた。そこではメンバーを、いろい
ろなコードネームで呼んでいた。ボーイやガール、シャツやパンツ、コ
カインやヘロイン。
シャツといても、衣料センターに向かっているのではなかった。
目的の場所は、スペインの王室なら喜びそうなスペイン風レンガ造り
の家だった。長い車寄せの端にある郵便箱の名前は、アンダースだった。
家は車通りからは、ほとんど見えなかった。イタリア糸杉の一群が、忠
実な番兵のように立ち並んで、オレンジの壁を隠していた。
レッドは、重い金属のノッカーでオーク材のドアをノックした。2度
ノックしても、応答はなかった。花壇の周りを歩いた。
レッドは急に立ち止まった。ドーベルマンが小走りにやってきて、鼻
をくんくん鳴らして、通り過ぎた。炭酸飲料のようにシューという音を
させて、ジャグジーにブロンドがいた。彼女は、ドーベルマンと同じく
らいの服を着ていた。ブラッディマリーをすすってから、レッドを退屈
そうに見た。酒を飲める年齢には見えなかった。
「服をぬいで、ジャグジーにいらっしゃいよ!」と、ブロンド。少し呂律
が回らなかった。
「今日はやめとく。あんたはいくつだい?」
「17」
「おまえの知ったことじゃない!」と、男の声。レッドの背後から聞こ
えた。
男は、5フィートくらいの身長で、緑のシルクの着物から腹を突き出
していた。髪は薄く、グルーチョマルクス風口ヒゲ、両手にオールドウ
ェスタンの6連発を手にしていた。どちらもレッドを狙っていた。
「用件を言え!早くしろ!指が引き金を引きたくてウズウズしてる!」
「それに、バスタブの少女は未成年なのに酒を飲んでる!銃をしまいな、
カウボーイ」
ジャグジーのブロンドは、くすくす笑った。
「グレッチェン、家に入りなさい!」と、アンダース。
「コカインが来る前に、お馬ちゃんごっこができるって言ったじゃない」
と、グレッチェン。不満そうだった。
アンダースはグレッチェンを睨みつけた。レッドは知らぬ顔をしてい
た。
「つまらないの!」と、グレッチェン。若い人魚のように水から立ち上
がった。家へふらつきながら歩くスリムな筋肉質の体に、水の筋が残っ
た。
「勝手に入り込んでるぜ、おっさん。説明しな!」と、アンダース。
「オレは、ジェームズの友人。たしかに不法侵入だが、地方検事が喜び
そうな、未成年者の非行や法に触れるレイプ、その他の犯罪を手助けす
るよりはましだ」
「30分早すぎた」
「それは犯罪じゃない。少なくとも、オレの出身地では」
アンダースは、右手の銃で左手の下をかいた。銃の使い方が分からな
い子どものように見えた。レッドはギャンブルをした。手をポケットに
入れて、タバコを出した。
「銃をしまいな!」と、レッド。「はしゃぎすぎの子どもみたいだ。ビ
シネスを済まそう!そうすれば、すぐ、お馬ちゃんごっこに戻れる!」
「おまえはコメディアンか?」
「銃をしまったら、拍手喝采!」
「オレは拍手喝采はしない。ジェームズに貸したカネが戻ってくるまで
は。1万5千ドル持ってきたのか?」
「電話ではなにも言ってなかった」
「もし言ったら、おまえが来ないと思ったのだ。やつはどこだ?オレの
カネはどこだ?」
「リー!」と、グレッチェン。家のスライドドアから呼んだ。服は着て
いた。
アンダースは、振り返った。レッドは38口径を抜いた。
「荒野の決闘みたいだな」と、レッド。
「だめだ」と、アンダース。「グレッチェン、家に戻りなさい!」
「授業に戻るわ」と、グレッチェン。向き直って戻っていった。ふたり
の男は、互いに銃を向けたまま残された。
「彼女は、UCLAのオレの学生だ。そうは見えないが。他にいろいろ
とプライベートの」
「教授か。授業の内容がどんなものか分かる。今までに人を撃ったこと
は?」
アンダースは答えなかった。
「ひどいもんだ。あと始末が大変だ。流れ出た血や内臓がそこらじゅう
に飛び散って。オレは知りたいね。オレは今までに37人撃った。撃た
れたことに気づいてから死ねたのは、9人だけだった」
アンダースの握る銃が、上下に揺れ出した。
「少女は行った。オレたちは撃ち合うか、話をするか。次はあんたの番
だ」
アンダースはためらった。それから、両手を下に降ろした。レッドは
銃を構えていた。
「あんたも銃を降ろすと思っていた」と、アンダース。
「それは違う。ゆっくり、銃を目の前の地面に置け!それから、ジェー
ムズのことを話してくれ!バカなまねはするな!」
アンダースは気が進まなそうに銃を地面に置いた。「ジェームズの友
人なら、なぜジェームズのことを聞く?」
「ウソをついた。オレは私立探偵だ。やつを追っている。いろいろ話し
てくれ!」
アンダースは歯を見せて笑った。「ほんとうか?そいつはいい!なん
でも手助けする。やつを引っ捕らえて来てくれ!」声が急に元気になっ
た。
「やつはどこだ?」
「オレが知ってるのは」
「なにを知ってる?」
「ジェームズランダールは、売人ジェームズとして知られている。扱う
のは、コカイン、マリファナ、クアールード、ヘロイン。なんでも手に
入れる。見かけはただのビーチボーイ、やつの目を見るまでは。その目
には、ねずみの狡賢さが宿っている」
レッドは、いろいろなねずみの目を思い浮かべて、うなづいた。
「おもにコカインを扱う。ふつうはかなり質のいいものを。50パーセ
ントとか、時には、75パーセントの純度のものを。混ぜ物はなし。そ
のおかげで、それまでは掃除さえさせてもらえなかった場所へ出入りで
きるようになった。ヤクがなくてもだ。ハリウッドスターやロック歌手
とかに。元ポルノ俳優としては悪くない」
「そんなことまで?」
「今はもうやってない。しかしそういう連中とまだつきあいがある。女
はいつも変える。ほとんどは、ただの宿無しだが、新しい女は絶品だっ
た」
「これか?」と、レッド。ポラロイド写真を見せた。
「そう。やつは火曜に大きな取引があったと言った。そのおまけとして、
女が付いてきたそうだ。やつに、その女にも貢がしてるのか訊いた。た
だの好奇心から。すると、こいつにはやらせねぇと言った。ほかの女に
はみんな貢がさせていたので、この女だけ特別だったようだ」
「粋なやつだ」
「いろんなやつがいるが、やつが一番頭がよかった。いつも『鍵は鍵だ』
と言っていた」
「意味は?」
「鍵は、コカインのキログラム数。1キロあれば、この町のどこへでも
出入りできる。美人のガールフレンドでもいれば、最強だ。そんな野郎
はいくらでもいるが、やつはほとんどのやつらより頭が良かった。少し、
頭が良すぎたかも」
「どうして?」
「やつがカネを持って来ない理由は、だます相手を間違えたからだ」
「だれ?」
「ビニーバーガス。マフィアの」
「ロコの手下のひとり」と、レッド。
「だれ?」
「いや、こっちの話。バーガスについて教えてくれ!」
アンダースは、あたりを見回した。まるでイトスギの影から、ヒット
マンに狙われているかのように。安全だと確認してから、しゃべり始め
た。
「バーガスは10年前に東からここへ来た。小さなプロダクション会社
をやっているコーヘンという名の男に会って、共同経営者になるはずだ
った。コーヘンは、バーガスにタマゴをぶつけるような無礼な口をきい
た」
アンダースは、ドラマチックに見せるために、ひと呼吸おいた。
「コーヘンは2日後に車のトランクで発見された。固ゆでタマゴにされ
ていた。バーガスは会社を買い取って、音楽ビジネスから始め、ほかの
ビジネスにも手を伸ばした。深夜番組のようなものに興味をもって、や
がて、ポルノ産業の大手会社となった。ジェームズはそのころにバーガ
スに会った」
「それでドラッグ取引をもちかけた?」
「そう聞いている。これはすべて口外禁止だ。いいね?」
「分かった。どうやったら、バーガスに会える?」
「今夜、やつのパーティに行く」
「なんだって?」
「やつは、知り合いになれば、いいやつだ。いろいろ助けになってくれ
る」
「そうか」
「あんたは、オレのボディガードだと紹介する。しかし約束してくれ!
勝手なまねはしないと。やつに敵だと思われたくない」
「パーティの時間は?」
「8時だ」
「7時半に迎えに来る」
アンダースは、興奮気味に言った。「もしもこれがうまくいったら、
いい取引ができる。オレは、いっしょにセキュリティチームをやる相棒
を捜していたんだ」
「なんのために?」
「オレは、リバタリアンの生存主義者なんだ」と、アンダース。レッド
が混乱した顔をしていると、続けた。「大きな政府はやがて行き詰る。
そのうち、性生活にまで干渉してくる。地震でも戦争でも革命でもなん
でもいいが、世界の終わりがやってきたとき、この国は強いリーダーシ
ップが必要になる。大きな政府は破綻して、人民が勝利する」
アンダースは、自己陶酔の極地にいた。「準備万端整えた者が国を支
配する。オレは1年分の食料を備蓄してあるんだ!」
「ひとつきいていいか?」
「なに?」
「固ゆでタマゴは入れた?」
22
レッドは中央図書館を簡単に見つけた。トーマスブラザース、44ペ
ージ、Cの3。しかしドーム型の建物の中で、2度迷子になった。迷路
で15分迷ったあげく、ハーレクインメガネをかけた中年の黒人女性の
図書館員が同情して、ガイドを買って出てくれた。
レッドは、そこでは年次報告書が義務付けられ、資料がマイクロフィ
ルム化されていることを教わった。マイクロフィルムの読み方も習った。
1時間、青地に白の文字を読んだせいで、レッドの目玉は震えだした。
車でマンフレッド家へ戻った。
トッドが出迎えた。「書斎でマンフレッド氏がお待ちです」
「シャワーを浴びて気分転換したい。将軍には、30分くらいで本部に
報告に行くと伝えてくれ」
レッドが着替えているとき、ドアにノックの音がした。すぐにドアの
裏に隠れた。ドアがあくとレッドは飛びのいたが、侵入者に背後からつ
かまれた。その手は柔らかく、女性の肌をしていた。
ロザリーは「ギャーッ!」と叫んで、レッドの手にかぶりつこうとし
た。
「あなたはわたしを避けている」と、ロザリー。
「いつもそんなふうに侵入してきたら、オレの反射神経が悲惨な結果を
生む!」
ロザリーは後ろに下がった。
「そう」と、ロザリー。好色そうに笑った。「シャワーが必要ね。心が
汚れて」
「熱いシャワーがいる。仕事で関わったやつらの臭いを消すために」
「今日は、なにか分かったの?」と、ロザリー。船に乗りこむ海賊のよ
うに近づいた。
「あれやこれやだ。まだ検討してない。なぜ聞く?」
「ただの好奇心」と、ロザリー。
「いろいろ言われると、頭がパンクする」レッドは、ロザリーを押し返
した。
「なにがどうなったか聞くのが好き。とてもエキサイティングだから」
「しゃべりたいことはたくさんあって、見せたいものはもっとあるが、
ビジネスの方が先だ。情報を聞き出そうとしてる?」
「たぶん。荒々しい気にさせる」
「ある意味、ずっとタフな尋問を受けてきた。もう少しのところでしゃ
べってしまうところだった」
「大変な1日だった?」
「今夜ほどではない」レッドは、ロザリーの腕を取って回れ右をさせ、
ドアへ突き返した。「すぐ出て行きな!」
「あなたは戻って来る?」
レッドは答えなかった。バスルームに入るとドアを閉め、長い冷たい
シャワーを浴びた。
◇
レッドが室から出ると、トッドが玄関ホールで待っていた。
「実りのある1日でしたか?」と、トッド。
「ああ、とても」
長い廊下を歩いている間、トッドは笑いながら、楽しい会話の時間に
しようとした。
「実にわくわくする仕事につきましたね」
「車を駐車させるわくわく感だ」と、レッド。マンフレッドに報告する
考えをまとめようとした。
「それぞれがジグソーパズルの1ピースにあたる人物に、みんな会って、
あなたがひとりで全体像を作り上げる。絵画については、どうやって取
り戻すんですか?」
レッドは、それが偶然紛れ込んだ質問のようにスルーしようとしたが、
舞台の踊り子のように目立っていた。
「そのうち分かって来るさ」レッドは、偶然そうに答えた。「オレが悪
事をあばくまでに、1週間とかからない」
「容疑者はすでに?」
レッドはウィンクした。「しゃべったら、あんたが最初になる」
トッドは、東洋の敷物の前に着いた。レッドは腕を広げて、トッドを
軽く抱いた。「よく見ていてくれ!さもないと、墜落する」
トッドもレッドの腕を握り返した。「もしもだれかが、警察に捕まっ
たら、助けてくれますか?」
「保障はない。しかしオレは、だれも傷つけないように捜査するやり方
を貫く。そいつがそれに値するなら。今まで助けてはきた」
トッドは、マンフレッドの室に入るレッドの後ろ姿を見送った。
◇
退役将軍は、AR−15のスナイパースコープを覗き込みながら、銃
コレクションの前に立っていた。愛おしそうに銃を壁のくぼみに戻した。
「今まで、自分の従業員に待たされたことはない」
レッドは、なにも言わずに座った。マンフレッドのデスクにあるクリ
スタル灰皿を引き寄せて、タバコに火をつけた。
「それ相応の理由があってのことだろうな?」
「オレは従業員じゃない。オレのサービスを売っている独立した存在だ。
注文が来るのを1日じゅうソファで待っていたわけじゃない」
「今まで、人からそんなふうな口をきかれたことはない」
「オレのサービスが欲しいなら、慣れることだな。レッドダイアモンド
は誰からも、くだくだ言われる筋合いはない」
「態度が気に食わない、ミスターダイアモンド」
「今日は忙しかった。エミリーポストのエチケット講習はパスしたい。
あんたがオレの態度をどう思っているのか、知りたくもない」
「そのような態度は決して」
レッドは立ち上がった。「一晩中こんなところに座っていたくないし、
あんたが気に食わない点を聞かされたくもない。オレが調べたことを聞
きたくないのか?これからパーティがある」
「仕事中にパーティだと?」
「依頼料はたしかにもらったが、オレのやり方に口出しする権利はない。
すべて返してもいい。あんたの家に寝泊りさせてもらってるが、ホリデ
ーインだと言うなら、チェックアウト時に10ドル紙幣を置いてゆく。
メイドのチップも忘れずに!」
ふたりは、にらめっこを続けた。アンティック時計が鳴り出した。マ
ンフレッドは瞬きして、腕時計を見た。
「こうしてる時間はない!」と、マンフレッド。
「ゲームに参加してほしいなら、オレは自分のやり方でやる。トレイの
代わりにハジキを持っている別の召使いがいいなら、フィップスのよう
な弱虫を雇うといい」
「フィップスに会ったのか?」
「忙しい日だった」
「なにが分かった?」
レッドは自分のノートを開いた。「手始めに、フィップスに会った。
こちらは強く出て、有利にことを進めた。これは、前にも使った手だ。
テキスト通りのルーチンで、やつは━━━」
「細かい話はいい。こちらの仕事に関わることは?」
レッドはぶつぶつ言いながら、1日やったことをかいつまんで話した。
マンフレッドは、まだ、なんの興味も沸かなかった。
「私の絵画は?」
「娘がどうなったかをもっと心配すべきでは?」
「それは違う」
「心配では?」
「心配はしている。出て行ってほしくなかったし、マンフレッドの名を
汚して欲しくなかった。しかし、娘は自由で、21才だ。出て行くこと
を選ぶなら、それは彼女のビジネスだ」
「こんな温かくてセンチな男からどうやったら出てゆけるんだ?」
「冷たいユーモアはやめてくれ、ミスターダイアモンド!娘たちは、教
育の価値は分かっているはずだ。アリソンであった時代に、なにも学ん
でなければ、それは仕方ない。盗難に関わってる証拠でもあったか?」
「まだ断言はできないが、オレはないと思う。彼女は、それほどワルで
はない」
「あんたは、彼女を信じすぎているように見える。それはともかく、つ
ぎの手は?」
「いろいろと聞きたいことがある。この事件の解決に役立ちそうなこと
や背景を。ジェームズランダールという名前は聞いたことあるか?」
「ランダール?ブロンドの髪、長身でやせている?」
「そんなとこだ」
「彼について、なにを知っている?」と、マンフレッド。
「今はオレが質問している」
マンフレッドは咳払いした。長い間があった。
「ランダールは1週間くらいここで働いていた。先月のことだ。私は彼
の態度が気に食わなかったので、クビにした」
「やつの仕事は?」
「ふつうの仕事。車の運転やボディガード。彼は執事にふさわしくなか
った。たぶん、ドラッグのせいだ。それに、アリソンを気にしすぎてい
た。なぜ聞く?」
「オレの考えでは、アリソンは、やつと駆け落ちしたか連れ去られたと
思う」
「しかし、彼は、ロザリーの言う特徴と合わない」
「ロザリーはいろんなことを言っている。彼女を雇った経緯は?」
「12年以上、同じ雇い人を使っていた。執事がメイドとカリブへ駆け
落ちした。運転手は、引退してパームスプリングスへ行った」
「それはいつごろ?」
「6ヶ月前だ。家庭教師だけ残った。ロザリーは、全米紹介サービスか
ら来た。トッドもそうだ。ジェームズランダールも。みんなりっぱな推
薦状つきだった」
「ランダールも?」
「そう」
「分かった。つぎは、絵画について」
「みんなオリジナル作品だ。日本の画家の浮世絵だ。北斎、芳年、春英、
広重、国芳。絵を見たことは?」
「北斎と広重くらいは」
「写真がある。本物よりは劣るが。線や流れや色彩の精巧な描写や芸術
性。とにかく、リストを渡す」
「なぜ保険をかけなかった?」
咳払いと沈黙。
「盗品とか?」と、レッド。
「盗品には関わってない」と、マンフレッド。「出典の問題だ。この意
味は分かるか?」
「ええ。盗品でなければ、どのように手に入れた?」
「40年前、日本に駐在しているときに買ったものだ」
「それなら間違いない。フィップスに鑑定を?」
「いや」
「なぜ?」
「ものごとは自然に明らかになるからだ。まだ、分かってないが」
「絵画を盗んだのはだれか知っている?あるいは、推測でもだれか?」
「もう十分しゃべった」と、マンフレッド。100ドル紙幣の束をレッ
ドの前に滑らした。
「だれが絵画を持っている?」
「知らん」
デスクの電話が鳴った。マンフレッドが受話器を持ち上げた。
「つなぐなと言っただろう?ああ、分かった」
受話器を手でふさぐと、レッドに向き直った。レッドは札束をポケッ
トに入れていた。
「明日、また、話そう。重要な電話だ」
レッドは立ち上がった。「分かってくるにつれ、みんなにとって良く
なればいい。さもなければ、あんたが調べられたくないことを調べるこ
とになる」
レッドが室を出るとき、マンフレッドは静かにしゃべっていた。
23
道は上りになり、山の間をぬって、ロサンジェルスの光は下の方で瞬い
た。アンダースは、饒舌に、リバタリアン運動のことや、文明の終わり
はもうすぐで、アンダースの私設軍隊に入れば安全に生き延びられると
まくしたてた。小さな教授は、鼻をつくオーデコロンを付けていたので、
車内に匂いが充満した。車がバーガスの家に着いて、レッドはホッとし
た。
家は巨大な六角形で、マルホランドドライブの山側に支柱で支えられ
て建っていた。駐車場からもパーティの音楽と騒音が聞こえてきた。車
は、メルセデスの後ろに停めた。ナンバーはスタッド。そこはジャガー
の隣で、ナンバーはリッチ。そこはロールスの後ろで、ナンバーはフェ
イモス。
「少し待って」と、レッド。バーガスの家に入る前だった。
レッドは通りを下って、ナンバープレートを見て歩いた。メルセデス
の赤のSEIを見つけた。ナンバーはスノートと読めた。
フィリッピン人のハウスボーイは、無表情で赤のジャケットを着て、
レッドたちにドアをあけた。
室内は、ホイールから延びるスポークのように放射線状に光線が走っ
ていた。1本のスポークは欠けていた。リビングルームは外側の壁に向
かって広がっていた。大きな窓から、ロサンジェルス、フリーウェイの
動脈が走る輝く巨大な都市を見ることができた。
少し低くなったリビングルームのまわりには、50人くらいの客が立
ったり座ったりしていた。女たちは、シースルーやミニスカートやスリ
ットの入ったドレスで、だれが一番胸の谷間や太ももを見せているかを
競い合っていた。男より女が多かった。ほとんどの女が20代中頃であ
った。
男は平均して女より20才年上で、総じて自分の肉体を見せたいと思
わなかった。なん人かは、やせて日焼けしたタイプで、髪に金のチェー
ンをして裸の胸を見せていた。残りは、成功して裕福な二重アゴの太鼓
腹だった。
「リー、来てくれてありがとう」と、胸毛タイプの男。首のネックレス
の金は、フォートノックスの金庫室よりは少なかった。
「きみのパーティは休んだことがないからね」と、アンダース。「ビニ
ー、こちら、レッド。レッド、ビニーだ」
レッドは、バーガスと握手した。レッドは、バーガスがレッドの腰の
銃のふくらみに気づいたことが分かった。ふたりの目が合ったとき、野
獣同士の火花が散った。
「リーの友人は、私の友人だ。どのようなお仕事を?」
「私立探偵」
「一度その映画を見た。『プライベートアイ』。きみも見た?」
「映画はあまり見に行かない」
「私の映画館の鑑賞券を2枚あげなくては。友人と楽しんで来て」
「あんたは製作と配給だけかと思っていた。映画館も持っていたとは」
バーガスは凍りついた。アンダースはどこかへ行っていた。
「ほかになにを知っている?」と、バーガス。トラのように吼えながら
親しそうにレッドの肩に太い腕を回した。「私がきみについて知ってい
るのは、ここへ銃を持ち込んでるということだ。そういうのは好きじゃ
ない」
「気になさらずに。必要がなければ、使いはしない」
「このパーティに来る種類の人間には見えない」
「パーティに来る種類というと?」と、レッド。バーガスの腕からすり
抜けた。
白いスーツを着た小男が、バーガスの前に現われた。「ビニー、また、
やったね!すばらしいパーティだ!ただ、ただ、すばらしい!」
バーガスが小男の賞賛に応対している間に、レッドは客たちの中へ逃
れた。バーガスが後でレッドを見つけに来ることは、分かっていた。
左手にブランデーグラス、右手に葉巻を持った太った男が、その巨体
の下でソファを揺らしていた。注目されて大袈裟な身振り手振りで小話
を披露して、12人くらいの客を楽しませていた。
「ローラは砂漠にいた。食べるためにヘビを捜したが、抜け殻しか見つ
からなかった。ローラがいくつもの抜け殻をふざけてまとうと、まるで、
ピンクのヤマアラシだった」
聴衆が笑う間をとった。
「オレたちは狩り出ていた。男も女も疲れきって、くたくただった。モ
ハベへ入った。ドクターは幸運だった。なぜって、予想もしないことが
起こるからだ」
レッドはバーでジャックダニエルズをもらうと、大きな窓の方へぶら
ぶら歩いて行った。酒をすすって、外を見た。
「美しいでしょう?」
女がすぐ近くまで来て声をかけた。女は40くらいで、よく化粧して、
着飾って、スタイルもよかった。自分の年齢から来る地震からバランス
を保つ戦いに四苦八苦しているように見えた。
「お名前は?」と、女。
「レッドダイアモンド」
「強そうな名前ね。強いの?」
「かなり」
女はレッドにもたれかかり、レッドの手から半分残ったグラスを受け
取ると飲み干した。
「汗の臭いが好き」と、女。
「ハンバーガーとポテトフライの臭いが好き」
「出すぎだと思う?」
「すこし」
「その気になれない?」
「特には」
「どうしたらその気になる?」
「雪の白、7人の小人、牛のムチ、2頭のヤギ、モルモンタバナクル合
唱団」
「からかってるの?」と、女。身を引いて、取り繕った。
アンダースがやって来て、女に腕を回した。「ローラ、元気?友人の
レッドには会ったね?」
「彼は、まったく無礼」
「彼女を連れてって、おしおきしてあげな、リー。オレは自分を守った
だけ」
アンダースは、レッドをとがめるように見て、酔っ払ってぶつぶつ言
っているローラを連れ去った。
◇
レッドが歩いてゆくと、数少ないスーツを着た若者のひとりが、4人
の男たちに身振り手振りでしゃべっていた。
「という具合に投資する。まるでポンジスキームだったので、そう、や
つに言うと、元金を保証するならどうだと言うので、それならオレも参
加したいと」
急にしゃべるのをやめた。4人の男たちは続きを聞きたがった。スー
ツの若者は黙って立っていた。ぼんやりした表情で、手には白ワインの
グラス。
「あんた、銀行家か?」と、レッド。
「いや。オレは、サミーホイト。ビッグサミーホイト」
レッドが、5フィート8インチを賞賛するように見上げると、若者は
笑った。
「バーガスの映画は、あんたにはおもしろくないと思う。12インチ程
度で勝負している話が多い」と、レッド。
「そう、オレは見ない」
ふたりは笑った。
「この客たちを見てみろ!」と、ホイト。「シドニーサリバン、300
パウンドの監督は、ふくれたヒッチコックのように座っている。今夜は
若者がいない。みんながっかりして帰ったか、あるいは、SとかMブル
バードに繰り出して行った」
ホイトは、メガネをかけた目で、キョロキョロ客たちを見回した。な
にかのドラッグの影響下にあったが、まだ、正気だった。
「パンチボウルの向こうにいるローラは、前はやつの妻だった。結婚は
よかったが、なにかの家庭内トラブルがあった」
「ローラには会った」と、レッド。
「あんたは、ローラに狙われる。ほとんどの男たちが毒牙にかかった。
ローラはいつも新しい━━━をさがして」
「顔」と、レッド。
「そう、顔をさがして。ここは、悪の軍団が1年は活躍できる場所だ。
オレは、6人のSやMフリークを見た。ヒッピーのカップルや、女優の
一群は気が向かないと演技しなかったり、FFAの創設メンバーだった
り、ヨガやオカルト信者がいた。その組み合わせには限りがなかった」
「ちょっと皮肉に聞こえる」
「ああ、フリークたちがオレに稼がせてくれる。コカインやクアールー
ドも届けてくれる。しかしある日、オレの手元にはなにもなくなって、
別の悪人がまぬけたちとスポットライトを浴びることになる」
ホイトはドリンクを飲み干した。
「あんたは、なにしに来た?」と、ホイト。「流れるシーンのカットか
ら、あんたがしゃべりかけてきた。少し変だ。映画についてスタッフと
話していただけで、オレの出番じゃない」
「オレの出番でもない。情報を捜していただけ」と、レッド。
ホイトは目の焦点を合わせようとした。身長は、そう見せようとして
いたほどは高くはなかった。「どんな情報?」
「ジェームズランダールについて」と、レッド。
「なぜ?」
「やつを見つける必要がある」
「この室の半分のやつらも、見つけたがっている」
かわいいブルネットがやってきて、レッドのことはよく知らないふう
に見えたが、ウサギの足のお守りを信ずるように、ホイトに抱きついて
きた。
「ビッグサミーはジニーとパーティに行くの」と、ブルネット。厚い唇
から甲高いセクシーな声を出した。
「今日はだめだ、ジニー。頭痛なんだ」
レッドはジニーの声に聞き覚えがあった。12の映画でうぶな娘役を
演じていた。しかし顔は、6回の高額の整形手術によって、引っ張りあ
げられたり平らにされて、デスマスクのようになっていた。
ジニーは顔をしかめて、大げさに体を動かした。
「ジェームズについて言える唯一ましなことは、コカインの取引で、バ
ーガスから法外なカネを巻き上げたってことだ。ジェームズにとっては
いつものことだったが、バーガスにとってはめったにないことだった。
限度を越えていたそうだ」
「ジェームズがどこか知っている?」
「姿を見かけなくなった。ある者たちは、やつは死んだと言っているが、
オレは、やつはうまく立ち回って━━━」
バーガスが近づいてくるのを見て、ホイトは凍りついた。雇われ用心
棒にしか見えない6フィートの大男を連れていた。大男は、ぎこちない
動きで、肩は上下に両手はバラバラに動いた。
「ジニーはおまえが頭痛だと言っていた」と、バーガス。
「ええ、そう言った」と、ホイト。
「ここにいるトニーは、頭痛の直し方を知ってる」バーガスは、6フィ
ートの大男にうなづいた。トニーはぎこちなく笑った。アゴは組み合わ
せが悪かった。
「いや、それは結構だ━━━」
トニーはホイトに長い腕をまわして抱きしめると、容赦なく締め上げ
た。
「ホイトはやめてくれと言っている」と、レッド。声は低く轟き、銃の
あたりから響いた。
「気にしないで。大丈夫だから」と、ホイト。肩をすくめた。
ホイトはジニーに手を振って、死刑囚の最後であるかのように隣の室
へいっしょに出ていった。
「ちょっと過酷過ぎないか?」と、レッド。バーガスに。
「雇い人にさせることは、ビジネス。トニーを紹介させてくれ。あんた
たちはまた、どこかで出くわす気がする」
トニーは、毛むくじゃらの手をレッドに差し出した。ふたりは無表情
のまま力の限りかたく手を握り合った。トニーが力を込めすぎたので、
レッドはトニーの足の甲を踏んづけた。トニーは悲鳴を上げた。
「悪かった。不器用なもので」と、レッド。
トニーは手を引っ込めた。レッドは上着のボタンをはずして、手を銃
の近くに垂らした。
「十分だ」と、バーガス。「今は」
◇
白のスーツの男は、レッドに近づいて来たが、バーガスとトニーが行
ってしまうまで待っていた。
「あんたはすごく勇敢だね。あるいは、すごくまぬけなのかも。オレは
マイクハート」手を差し出した。幸運にも、軽い握手だった。
「トニーって、何者?」と、レッド。
「昔スタントマンをやっていて、体のあらゆる骨を一度は骨折したそう
だ。雨だと、体じゅうが痛むという。ほんとうさ。幸い、このあたりは
そんなに雨は降らない。金属ピンが埋め込まれているせいで、空港の金
属探知機を通れない。しかしほかの多くの者たちと同じで、いろいろと
骨を折っている」
「すごいね」
「トニーはあんたが好きではないようだ」と、ハート。
ドアのあたりが騒がしくなって、4人の男と2人の女が入ってきた。
男の3人は、『公爵』と刺繍された黒の絹のジャケットを着ていた。ひ
とりは角刈りで、もうひとりはモヒカンで、もうひとりは紫に染めたア
フロだった。4人目は、禿げかけた黒髪で、黄のレジャースーツを着て、
バーガスと同じくらいの金のチェーンを付けていた。
ふたりの女は、太ったブルネットで、服はバラバラだった。化粧は濃
すぎて汚れていた。
モヒカンのひとりは、ブルネットのひとりを捕まえて隣の室へ出てい
った。レジャースーツ以外の残りは、バーからスコッチボトルをつかむ
と、ふたりに続いた。
黄のスーツは、ハートに向かって歩きながら、みんなと歓迎の握手を
かわした。
「マイク、マイク、どう元気?」
「ああ、元気さ、ビリー。患者のヘルペスの15パーセントを、まだ、
取り上げているのかい?」
ふたりは古くからの友人のように抱き合ったが、言葉はガラガラヘビ
の毒より悪意に満ちていた。
「キュートだね。あんたが患者同様、古いジョークも盗むとは知らなか
った」と、ビリー。
「ご心配なく!こっちには限度というものがある。若い女性のふたりを
どこへやったんだい?サンセットストリップでは見かけなくなった」
「あんたがサンタモニカブルバードへ行ってばかりだからさ。あのふた
りはヒッチハイカーだった。あとで、グループのファンだって分かった」
「いい趣味してる」と、ハート。皮肉っぽく。
「またいつか、ミーティングしよう。有名タレントに会うこつを教えて
あげるよ」
「こっちは、そんなに絶望的じゅない」
「絶望的ということか」
「死んじまえ!」
「やだね」と、ビリー。立ち去ろうとした。「しゃべれてよかった」
ハートはぶつぶつ言っていたが、レッドに向き直った。「能無しのね
ずみが大きくなった。ビリーウォルターズ。やつがブルバードで、酔っ
払いをペテンにかけていた頃を思い出す。コカインから始めて、タレン
トのマネージメントまで手を広げた。ああいうやつがいるから、この商
売が悪く見られるんだ」
「ジェームズランダールって、聞いたことは?」
「変わり者。2度会ったことがある。少し前から見てない。いなくても
支障はない」
ハートは、ビリーがお客たちの真ん中へ迎えられて、ジャケットから
厚い包みを取り出すのを、嫉妬心を抱いて見ていた。
◇
ミニスカートにハイブーツをはいたブロンドが財布から100ドル紙
幣を出すと、固く丸めて、一方の端を鼻孔に、他方の端を包みに当て、
別の鼻孔を指で押さえて深く吸い込んだ。ブロンドは後ろにのけぞって、
鼻をくんくんいわせて、幸せそうな叫び声をあげた。残りの連中も同じ
儀式を繰り返した。
青白いからだが丸見えの白のシースルードレスを着た、やせた赤毛は、
両鼻ともに吸ったあとに、ハートとレッドのところへ来た。
「参加する気はないの?」と、赤毛。ハートに。
「むしろ死にたいね」と、ハート。「ワンダ、こちらはレッド」
ワンダの両手は、生命体のごとく、髪から神経質そうな蝶々のように
舞って、ハートの手首や、レッドの肩に、そしてワンダの顔に漂った。
「レッドはどうなの?」と、ワンダ。両手を引いた。
「オレは、缶にあるコカインの方が好き」
「それは良かったこと!」と、ワンダ。レッドの頬を叩いた。「これが
初めてのバーガスパーティ?見たことない顔ね。パーティはフリークシ
ョーそのもの。でも、この町で商売するにはここしかない。そうでしょ、
ハート?」ワンダはハートの頬も叩いた。
「パーティでは得るものが多い。スタジオよりも収穫がある」と、ハー
ト。「少なくとも、ビジネス目的で」
「それじゃ、ここの道化たちは、コカインでいっぱいの鼻と酒でいっぱ
いのお腹で映画を作るのか?」と、レッド。「道理で1000万ドルを
ドブに流すわけだ!」
ワンダは両手を引いた。「そういう態度じゃ、成功しないわ」
「その気はない」
「いいところを突いている」と、ハート。「ウォルターズのような、う
じ虫を見てみろ!フリスビーのようにゴールドレコードを使う。コロン
ビアのコネなしに、いったいなにができる?」
「もっとなにが欲しいの?」と、ワンダ。早足で去って行った。
「ワンダは、なにをしている?」と、レッド。
「レコード会社で秘書をしていた。ビジネス上のコネを使いまくったと
聞いている。今はワンダは歌手で、みんなはもったいないと言っている」
「ここでは、みんながみんな、どんなビジネスをしてるのか知ってるの
か?」
「レッド、この町はレストランとドラッグで栄えている。だれかの家や
銀行やミドルネームを知らないかもしれないが、好みの食事やドラッグ
は知っている」
「フィフィラロチェっていう女を聞いたことは?自分では、アリマロー
ンやアリソンマンフレッド、あるいは、ジェーンデュと名乗ってるかも」
「多彩な形やサイズが、すべてがひとりの女とは!才能や野心があって、
うまく利用してのし上がりたいのかも」
「フィフィは、そういう女ではない」
「もしも彼女が、ここの連中に会ったら、きっと同じようになる。エン
ターテインメントには、いろんなレベルがある。オレたちは、トップか
ら3番目か4番目あたりにいる。ここにいる連中は、少しは成功してい
る。映画でせりふのあるシーンが2つくらいの役をもらったり、ドライ
ブインシアターで上映する低予算の映画を撮ったり、出したレコードが
トップテン入りを果たしたり。成功の香りを嗅いだだけで、まだ、十分
な成功はしていない」
「フィフィは、5フィート6インチくらい。ブロンド、美人、目は青」
レッドはハートにポラロイド写真を見せた。
「かわいい。しかし、ありきたり。この手の女は、みんなここへ来る。
水のきれいな故郷の町で、金持ちの彼氏を作れなかった高校のプロムク
イーン。映画に出るべきだとよく言われるウェイトレス。自分はスター
になるべきだと考える女。そういう女たちは、みんなここへ来てうろう
ろして、いろいろあってから、やがて故郷に帰るかする」
「そう、人生はタフ」
「たしかに、タフ。しかし、同時に収穫もつかめる。ここでは悪いこと
に、つらい杖だけでなく、おいしいニンジンもある」
ハートは手を振って、カールした茶髪にピッタリしたジーンズのひょ
ろ長い若者を呼んだ。
「しかし、人生は続く。希望を捨てることはない。この若者のように」
と、ハート。若者を指差すと、ライトスポットが当たった。「オレはこ
いつを、TVスポットの当たる場所に出した。そして、結構、喜ばしい
手ごたえを得た」
ライトスポットは突然消えて、7フィートのビデオスクリーンが壁に
現われた。ビッグサムとジニーが出演しているビデオで、リビングルー
ムの隠れたスピーカーから音が聞こえた。
「最悪のショーだ」と、ハート。「前回は、カメラに気づいてないふた
りの女が出ていた。最悪だ。ただ、最悪だ」
「賭けてみたい」
「おまえは女は好きでないだろ?」と、ハート。望みをもって。
「好きだよ。自分のプライバシーも大事だ」
「そんな古臭くなることない」
「オレはもともと古臭いタイプの男だ。どこかのログキャビンで薪を焚
いたりするのが好きだ」
「原始的。硝酸アミルもなしに?」
「さっきランダールを知っていると言った!」と、レッド。話しに割り
込んできた。
「変わり者。ゲームのやり方をきちん守ることもあれば、だますことも
ある」
「やつと取引を?」
「オレは、合法なものしか扱わない。やつの好みのものとは違う。美形
の若者や少女が、製作者や監督に気に入られようとするのはいいが、や
つの扱う連中には、1つの才能しかない」
「やつがどこにいるか、手掛かりは?」
「とんづらしたままだ。そうでなければ、今夜、ここへ来る」と、ハー
ト。「とにかく、サムがもっともやつに接近した人間だったことは知っ
ている?」
「だったとは?」
「オレは、ランダールはすでに砂漠で細切れにされている気がする。や
つには多くの敵がいた。失礼、そろそろ行かなくては」と、ハート。カ
ールした髪の若者がひとりでいるのを見て言った。
「最後の質問。ナンバープレートにスノートとあるメルセデスに乗って
いるやつは?」
「ビッグサム」と、ハート。レッドを残して立ち去った。
数分で、ビデオショーは終わった。お客たちの騒ぎようから判断する
と、成功だった。
ホイトは、疲れた顔をして隣の室から戻ってきた。拍手喝采を無視し
てバーへ行くと、スコッチのストレートをもらって、アンダースのとこ
ろへ行った。いくつか言葉をかわして、まっすぐレッドのところへ来た。
バーガスとトニーは、室の遠いサイドからこちらを見ていた。
「ありがとう」と、ホイト。
「なにが?」と、レッド。
「バーガスを遠ざけてくれた」
レッドは、肩をすくめて、感謝を伝えようとするホイトを無視した。
「聞いてくれ」と、ホイト。「ランダールはオレもだました。オレから
千ドル借りたままどこかへ行ってしまった。その少女を知っている。彼
女は今もランダールと親密なはずだ。やつがどこにいるか知っているか
もしれない。彼女は気まぐれだが、オレには正直に話してくれると思う。
だれにも知られたくはない。そうでなければ、すぐにバーガスに知られ
てしまう。バーガスは、ランダールよりもっとオレが憎んでいる人間だ」
「いいね。いつ連絡したらいい?」
「明日の午後。スコーピオスタジオで」
ふたりは別れた。レッドは、アンダースのところへ行った。
「そろそろ帰ろう」と、レッド。
「パーティはまだ始まったばかりだ。それに、この美人は、古典的象徴
主義について、教えてほしいそうだ」と、アンダース。美人のブルネッ
トの肩に腕をまわした。「オレは残る。この子に教えなければ」
レッドは、だれにもあいさつすることなく、冷たい夜風の外に出た。
静かだった。音楽もしゃべり声も歓声もなかった。あまりに静かだった。
車に向かっていると、後ろ髪がヘビ使いのコブラのように逆立った。
トニーの棍棒が弧を描いて迫ってきたとき、レッドは寸前で身をかわ
した。一撃はレッドの頭をはずしたが、右耳に当たった。ベルが鳴り出
した。
レッドはスウィングしてめちゃくちゃ放ったきつい一発が、トニーの
ストマックにヒットした。トニーはつぎの一発をかわして、レッドの腹
に一発をお見舞いした。レッドは体を折った頭に、トニーの棍棒を食ら
った。
レッドは腹をおさえて地面に倒れた。トニーはそれをサーカーボール
のように扱って、いくつかゴールを決めた。
「私立探偵は、ここでは歓迎されない」と、トニー。「バーガスさんは、
そこらじゅうを嗅ぎまわるやつは好きじゃない。軽くと言われたからこ
のくらいにしておくが、つぎ会ったときは」
レッドは、トニーが去ってゆく足音を聞いた。地面に横たわったまま、
胎児の姿勢でいた。体を丸めて、ひとかたまりになっていた。正面ドア
が開き、楽しそうな騒音が聞こえ、トニーがパーティへ戻って行った。
レッドは、そこにどの位いたのか思い出せなかった。正面ドアがまた
開き、騒音が近づいて来たとき、なんとか起き上がり、車に戻った。
古いブルースを聞きながら、マンフレッドの家に帰った。
24
レッドは、胎児の姿勢で丸まっていた。まわりは、弾丸の跡のある裸
体に取り囲まれていた。やつらは死んでいる。しかしゾンビのようにグ
ロテスクに動き出した。死体の山を乗り越えて、フィフィにたどり着こ
うとした。そのとき、メイド服を着た女が立ち上がった。銃口がレッド
をねらっていた。メイドはハンマーを振り下ろした。そして、クリック
音。
クリック音は、夢ではなかった。なんとか目覚めようとした。枕の下
に手を入れて、38口径をすべり出してドアを狙った。
廊下の照明でシルエットになった人影は、あきらかに女だった。黙っ
ていると、彼女はレッドのズボンのポケットの中を捜し始めた。
「なにか捜しもの?」と、レッド。ロザリーは跳び上がった。ズボンを
たたんでいるふりをして、レッドのところに来た。胸のあいた水色のロ
ーブを着ていた。
「驚かさないで!」と、ロザリー。不満そうだった。
「ぬいだズボンに女が捜しものをするのは、初めてじゃない」
ロザリーは近づいて、レッドの銃に気づき、はっとする声を上げた。
レッドは銃を枕の下に隠した。
「あなたが来るのを待っていた」と、ロザリー。「寒い。いいかしら?」
「今夜はだめだ。疲れて、傷がひりひりするし、そんな気分じゃない」
「なにがあったの?1日じゅうどこへ行っていたの?」
レッドは本当のことを言いそうになったが、ポケットを捜していた彼
女のイメージが、レッドの舌をフリーズさせた。
「1日のことを話して!」
「うう」
ロザリーはレッドをゆすった。「わたしを信用して!」
「うう」
◇
つぎに気づいたのは、朝早い日射しだった。ドアにやさしいノックの
音。ナイトスタンドの時計は、AM8時。
「どうぞ」と、レッド。力ない声で。
グウェンが入ってきた。短めのナイトガウンを着て、歩くと細い足の
筋肉が見えた。グウェンはベッドに自分では色気たっぷりに飛び込んだ
が、かわいいが見苦しい結果になった。
「最近、あなたを見てないわ、レッド」
「あんたのお父さんのために働いてないときは、眠ろうとして、ここに
いた」
グウェンは空気をかいで、ロザリーの香水の匂いを見つけた。
「ロザリーがここに?」と、グウェン。嫉妬の気持ちで。
「ロザリーはメイドだから、仕事でここへ来たんだろう。雇い人を調べ
ているのか?」
「そのことで来たのよ。家庭教師は、理由を教えてくれないけど、いろ
いろ調べようとすると、家庭教師から忠告される。もっと注意すべきっ
て、あなたにも知らそうと思って」
「家庭教師は、ほかになにを?」
「それだけ。彼女に質問してみた。わたしも私立探偵になったつもりで、
彼女にいろいろ質問したけど、彼女はなにか知ってるわけではなかった」
やせたティーンエイジャーの私立探偵としての考えは、レッドの顔に
笑顔をもたらした。グウェンは笑いを返し、ナイトガウンのへりを旗め
かせた。
「レッド、わたしってセクシー?」
「まだだよ、かわい子ちゃん。しかし2年もすれば、きっと驚くよ」
「なにを習えばいい?」
「待つことを習えばいい。ホルモンはそのうち成長させてくれる。今を
楽しむのがいい」
グウェンは体を傾けて、レッドにキスしようとしたが、レッドはやさ
しく押し戻し、頬を指の先で軽く突っついた。
「待っている者のところには、すべてがやって来る」と、レッド。「オ
レがガキの頃、ヒゲを剃りたくなかった。ヒゲを伸ばしたかった。しか
しそれは取り越し苦労だった。今は、見てくれ!」
レッドはグウェンの手をとって、無精ヒゲだらけの顔にさわらせた。
「2年もすれば、きっと誘惑に勝てなくなる。しかし、顧客の娘と関係
を持つのはよくない」
愛されたい子犬のように、グウェンは別の戦略に切り替えた。まじめ
な顔をして座り直した。「私立探偵になりたい。調査テクニックについ
ての本を何冊か買ったわ。指紋が一致するには、いくつのポイントが一
致すればいいか知ってる?」
レッドはグウェンの頬を軽く叩いた。「知らないが、すぐれた探偵は、
眠りが必要なことは知っている。話したいが、今は疲れている」
「ここにいてもいい?ベッドで眠りたい」
「今はまずい。どう見られるか分からない」
「分かった、行くわ。でも約束して!どうしたらそうタフになれるのか
教えて!あなたのような私立探偵になるにはどうしたらいいか」
「いいとも。少し眠らせてくれ!」
グウェンがドアから出てゆくころには、レッドは眠りに落ちていた。
◇
またノックの音がして、時計を見ると、AM10時だった。
「どうぞ」
トッドだった。「ミスターダイアモンド、お話があります」
「あんたも、他のみんなも、グランドセントラル駅にようこそ!」
トッドはとまどった顔をした。「重要な話です」
レッドは伸びをした。打たれて傷ついた体は、まだ眠りが必要だった。
「いつものことだが、オレは熱い風呂と2杯のコーヒーが欲しい。1時
間くらいであんたとおしゃべりができる」
「しかし、だれにも見られてはなりません」
「どこで会いたい?」
トッドは窓のカーテンをあけて、マンフレッド邸の端にあるヤシの木
立を指差した。「あそこで。かならず来てください」
レッドがマンフレッドの書斎に入ったのは、10時半を数分過ぎたこ
ろだった。
「疲れているようだな」と、マンフレッド。退役軍人は、自分自身もか
なり疲れていた。顔の肌は、張りがなく、頭蓋骨から垂れ下がっている
ように見えた。「昨夜、なにか進展は?」
「娘さんの知り合いのランダールから、いくつか手掛かりを得た。絵画
はどこにある?と前にきかれたが、その答えは、この家の中」
「なぜそう思う?」
「明らかに内部の犯行だからだ。別の日にオレはこの家のセキュリティ
システムを調べたが、完璧だった」
「プロでも入れないのか?」
「ああ。しかし、プロなら、内部にスパイを送り込んで、邸宅のレイア
ウトやものがちゃんとあるかを調べさせる」
「そうか」
「ランダールは、システムを調べられるくらい長くここで働いていた?」
「防犯カメラの位置は分かっただろうが、その詳細までは分かってない」
「犯行は見事だった。普通に考えたら、あんたが第一容疑者だ。保険金
詐欺として。ウォールストリートジャーナルで最近の記事を2つ読んだ
が、それによると、あんたの会社の財政はそれほど良くないそうだ。札
束があれば、ヨナのように日本の大企業の鯨に飲み込まれないようにで
きそうだ」
マンフレッドは、憤慨して怒っているように見せようとした。しかし、
レッドには恐怖の影が見えた。退役将軍の薄い唇の端が、神経質に震え
ていた。
レッドは、マンフレッドのデスクにある絵画リストを手に取った。
「これが問題の絵画?」
マンフレッドはリストをつかもうとしたが、レッドはポケットにしま
った。
「1つ言っておくと、オレは出てゆく。しかし、ここにいる誰にも、出
てゆくところを見られたくない」
「どこへ行く?」と、マンフレッド。声が弱々しかった。
「電話する」
「今後、きみがどこにいるかを正確に知りたい」マンフレッドの声は、
老人のように震えていた。
「大きな進展があったら、知らせる」
「まったく、すぐカッとなる男だな」と、マンフレッド。やさしい声で。
「お尻がうずくという意味なら、その通りだ。オレはオレのやり方でや
る。それぞれのピースを本来の場所に落とす。警官に嫌われるし、泥棒
にも嫌われる。時として、顧客にも嫌われる。しかし、かならず結果は
残す」
◇
レッドは、玄関ホールで家庭教師に会った。グウェンにした忠告につ
いて聞いてみたが、なにか知ってるわけではなかった。女の直感以上で
はなかった。レッドは、これからも物事に注意しておくよう言った。彼
女はそうすると答えた。
室に戻って、バッグを詰めた。誰にも邪魔されなかった。車まで行っ
て荷物を出すと、バッグに入れた。
邸宅の庭を歩きまわった。庭は見事だった。小さな公園をいくつも見
てるようだった。アゼリア、カメリア、バラが鮮やかな色彩を爆発させ
ていた。ブラシノキやジャカランダの木立を抜けて、遠くにふたりの庭
師の姿が見えた。
トッドと会う約束をした場所に近づくにつれ、土壌は砂っぽくなり、
何百万もの人々を養うために水を盗む行為が見逃されなかったら、そう
なったであろうロサンジェルス砂漠に生える植物の景色になった。
すべてが、ぎざぎざでトゲがあり鋭くなった。大きなサボテン、アロ
エやリュウゼツラン、ローヤルヤシやワシントンヤシが聳え立っていた。
トッドは、屋敷の誰からも見えない太いユッカの木の後ろで待っていた。
「来てくれてありがとう」と、トッド。
「なにか有益なことを知らせてもらえるのか?」
「今ややっこしいことになっている。犯罪に巻き込まれて、犯罪者にさ
れそうだ」
「警察へ行け!初めてなら、丁重に扱われる」
「あなたは分かってない。これは盗難にあった絵画に関係する」
「なにがあった?」と、レッド。タバコに火をつけた。
「それが━━━」
「言ってみろ!知らない話ではないらしい」
「オレは1970年に中西部からここへ来た」
「あんたのライフストーリーをしゃべる必要はない」
「静かに!父は牧師だった。オレは町でもっとも有名な若者で、野球チ
ームのキャプテンだったが、悪いウワサがたって、家を出た」
「それで、ここへ来たわけだ。盗まれた絵画となんの関係が?」
「オレは、ブルバードでいかがわしい仕事をしていた」トッドは下を向
いて、靴のつま先で地面を蹴った。
「しかし、オレはそれもやめた。人材派遣会社に登録して、まともな仕
事を始めた。いかがわしい仕事はやめた。聞いてます?」
「ああ。続けてくれ」
「ある日、ランダールが現われた。やつはオレの経歴をすべて知ってい
て、今度の仕事に手助けしないと、すべてバラしてやると言った。それ
が絵画を盗む仕事だった。
あんたは分からないだろうが、やつも分かってない。オレはまた堕落
する。またいかがわしい仕事に戻るなんてできない。それなら死んだ方
がましだ」
「どういう計画だったんだ?」
「防犯システムに細工する計画だった。数日して、日本人の男が加わっ
た。オレたちは、リトル東京のすし屋で会った。オレの役割の説明を受
けた」
「その男の人相は?」
「35才くらい。背は5フィート8インチくらい。顔立ちは良く、短め
の黒髪。全身に刺青があった。龍とサムライとおかしな模様。やつには
小指の先が片方なかった」
「なに?」
「小指の先。左か右か忘れた。聞いたところでは、その理由は━━━」
「オーケー。ランダールとはその後会ったか?」
トッドは頭を振った。「会って話したのは1度だけで、そのときに脅
された。マンフレッド氏にも、なにか脅すようなことをしたようだ」
「どんなふうに?」
「よくは知らない」
「会話の中に、ロコリコという名前が出て来なかったか?」
その時、銃声がした。なにか手立てを打つには遅すぎた。トッドの頭
は、2階の窓から地面に落としたスイカのように爆発した。レッドはす
ぐに地面に伏せて、38口径を抜いた。トッドの顔のかけらをぬぐった。
庭師たちは、周りを見回したが、なにが起こったのか分からなかった。
彼らの姿しか見えなかった。レッドはトッドの手首に触れて脈を見た。
分かってはいたが、それは無駄な作業だった。
◇
家庭教師とグウェンは図書室で勉強していた。ロザリーはキッチンで
銀食器を磨いていた。マンフレッドは、主人用のバスルームにいた。見
たところ、屋敷にいた誰も銃声を聞いてなかった。木立のそばの死体以
外は、いつもの静かな日常だった。
レッドは、マンフレッドを書斎に連れていった。スナイパースコープ
付きAR−15は、無くなっていた。トッドの最後の言葉を伝えると、
マンフレッドはイスに深く沈み込んだ。
「すぐに警察に電話すべきだ」と、レッド。「しゃべってないことがあ
れば、すぐに全部話してくれ」
マンフレッドは両手で顔をおおって、身を振るわせた。
「オレがバカだった。こういうことはないはずだった。誰も傷つけない
はずだった」
「振り返って反省してるヒマはない。すべて話してくれ」
「会社はトラブルを抱えていた。技術は次々に進歩する。それに追いつ
くことは不可能だった」
「あんたはオレにダウ平均株価を調べてくれと言うつもり?」
「待ってくれ!考えをまとめさせてくれ!」
「時間がない」
「1ヶ月ほど前、オレは会社をやっていけないことが分かった。田中産
業という日本の企業が会社を乗っ取る計画を知った。オレはその会社の
社長に会って、取引を持ちかけた。手を引いてくれれば、絵画を提供す
ると。社長は興味を示した」
マンフレッドは顔の皮膚を引っ張った。長身の体をほとんど2つに折
った。
「絵画に保険を掛ける時間はあると思っていた。2ヶ月待ってから盗難
を手配するはずだった。しかし、絵画は消えていた。合意はダメになっ
た。絵画を失い、会社も失うかもしれない」
「あんたは前に、絵画がある場所は知らないと言った」
「盗難のあと、田中に会った。彼は絵画を盗んでないと言っていた。ラ
ンダールが双方をだまそうとしたのではないかと思う。誰が絵画を持っ
ているのか分からない。ランダールがそううまく立ち回れるとも思えな
いが」
「ロコが仕組んだのかもしれない。それだけのコネはある」
「そいつはだれ?」
「いや、こっちの話。警察にはいっさいしゃべらないことだ。知らぬ存
ぜずで通す」と、レッド。デスクの上の電話を指差した。
退役将軍は、ゆっくりとダイアルを回した。
25
殺人は、サンマリノ警察では大きすぎて扱えない犯罪であったため、
郡保安官事務所の殺人課が、このあたりでは珍しい殺人事件を扱うこと
になった。
殺人課長の警部補リックブラウニングが到着するころには、鑑識課員
や検視官代理は、そのぞっとするような仕事をほば終えたところであっ
た。ブラウニングが現われたことは、公式に、これが通常の事件ではな
いことをあらわしていた。
ブラウニングは、電話があったとき、休暇中でゴルフをしていた。彼
はグレイの髪、グレイの目、頬はバラのような赤だった。ゴルフ用の帽
子をかぶって、黄のスラックスでしかめっ面をしていた。電話があった
とき、彼は勝っていた。
レッドは、鑑識課員が血のあとにチョークで線を引いていた場所の近
くで、ブラウニングと話していた。『犯罪現場立入禁止』と書かれた黄
の旗がサンタアナの弱い風に揺れていた。空気は暑かったが、風があっ
た。殺人課警部補にとって涼しくはなく、レッドの答えにも満足できな
かった。
「では、もう一度聞かせてくれ。おまえたちはここで、人生についてし
ゃべていた?」
「そう」と、レッド。
「でたらめだ」
「ミスターマンフレッドがあんたに言ったように、信じられないという
なら捕まえればいい。人身保護令状を使うまでもなく、弁護士がすぐ出
してくれる」
「その銃の携帯許可証は?」と、ブラウニング。レッドの腰の38口径
を指差した。
「ないと言ったはずだ。しかしここはマンフレッドの土地で、彼から携
帯許可をもらっている」
「証拠として押収できる」
「検死官があんたに言ったはずだ。彼は遠くからライフルで撃たれたと」
「おまえは手間を焼かせるな。それならおまえにも手間を焼かせてやる」
「警部補、オレはややっこしい話にしたくない。オレにも仕事がある」
「しかし、仕事がなにか教えたくないのだろう?」
「調査の仕事だと言ったはずだ」
「見たところ、無免許だな。で、なにを調査している?」
「話すには、顧客の許可がいる」
「マンフレッド?」
「そうとは言ってない。顧客が許可しない限り、なにもしゃべれない」
「殺人事件だぞ」
「オレだって困っている。殺された男と話していて脳みそをかけられた
ことは、オレの名誉にも影響する。しかし誓ったことだ」
ブラウニングは悪態をついた。
「町を離れるな」と、ブラウニング。レッドとあたりを数回歩き回って
から命令した。
「その予定はない。ここから調べ始める」
◇
マンフレッドは、顔を両手にうずめたまま考え事をしていた。壁の銃
は、警察の弾道検査に通すため、6丁以上が持ち去られて、空になって
いた。マンフレッドのしゃべることは、脈絡に欠けた。レッドはスコッ
チをついでやり、出て行った。
ロザリーは願い出て、半日休暇をもらった。家庭教師はグウェンの相
手をしていた。そして、レッドは仕事をしていた。
図書室へ行くと、田中産業に関する資料を読みあさった。外国企業だ
ったので概要だけだった。社長は田中健似野。日本の大企業の1つで、
半導体事業に投資していた。
田中は詳細不明で、決してインタビューを受けず、政界に太いパイプ
があった。年齢は62才、アメリカ人の妻がいて、子どもはいなかった。
レッドは、ゴシップやフューチャー記事も調べた。そこにはヒントは
あったが、明確な記述はなかった。行間から、結婚が不幸だったこと、
田中には暴力団とのつながりがあったことが読み取れた。
ゴシップ雑誌には、暴力団では男たちはイレズミをして、ヘマをした
ら小指の先を切ることが書かれていた。
ロコの名前はどこにも出てなかった。しかしちゃんと調べれば、やつ
のあぶらぎった指紋はそこらじゅうで見つかるだろう。モブスターは合
法的に、まともな人間を雇い、いい会社に投資するが、裏ではお気に入
りの戦略を使って、強奪や殺人を行っている。
◇
レッドは、シャーマンオークスのベンチュラブルバードにあるモーテ
ルで、直接電話が引かれている室を借りた。そして一握りの小銭を持っ
て公衆電話に行って、電話した。
田中の秘書は、ボスは1ヶ月は会えないと言った。スケジュールは、
やつが作っている半導体のようにすべて埋まっていた。マンフレッドの
名前を出しても、氷のように冷たい声の秘書にはなんの効果もなかった。
レッドは自分の名前も告げなかった。
ホイトはもっと協力的だった。
声が変だったので、レッドはなにかあったのか訊いた。
「唇がはれたまま話している」と、ホイト。「トニーが、オレたちがな
にを話していたのか知りたがったが、オレは言わなかった。やつとバー
ガスは怒って、トニーにかなり殴られたが、しかしヘマをやらかした」
と、ホイト。声を出さずに笑った。「殴った跡を残してはだめだったの
に、オレは抵抗した。それで、オレの傷が直るまで、映画の撮影が延期
されることになった」
「大丈夫か?」
「アンダースよりはましさ。寝室にいたところを乱入されて、殴られた。
アンダースはなにも知らなかったが、やつらには信じてもらえなかった」
「ひどかったな」
「そう。アンダースはきっとしばらくはおとなしくしてるだろう。それ
より聞いてくれ。オレはあんたのために住所を聞いてきた。ベニスの近
くのウェイブクレスト通り」ホイトは住所を読み上げた。「そこが、オ
レたちの友人がいた場所だ。少なくとも3日前までは」
「すばらしい!またなにか分かったら、ここへ電話してくれ」と、レッ
ド。モーテルの電話番号を告げた。
「気をつけて、レッド!バーガスは、殴られるのは好きじゃない」
「レッドダイアモンドが関わった今、それにも慣れてもらわないと」
26
レッドは、ホイトが教えてくれた住所の1ブロック手前で車を降りた。
スケートボードやローラースケートのヘッドフォンをした子どもたちの
騒音は、レッドが子ども時代に過ごしたヤシの木通りの過去を思い出さ
せた。建設中のビルの騒音が、さらに音を増幅させた。
平屋建てのバンガローの黄のドアをノックした。長いブロンドの髪を、
頭の片方におさげにした若い女がドアを開けた。だぶだぶのドレスが、
将来性のありそうな体を包んでいた。
「なんの用?」と、女。ニュージャージーのガーデンステートパークウ
ェイ受付嬢のような声だった。
「ジェームズはいるか?」
「もう借りていた室を引き払った。2日前のこと」と、女。ドアを閉め
ようとした。
「やつに話がある。どこへ行ったか知ってる?」
「あんた、警官?」コップを、口に出すのも嫌そうに発音した。
「いや。やつの友人」
「あいつは、こそこそしていた。友人がいるように見えなかった。あん
た、双子座?」女は、突然、訊いた。
「いや、知らない」
女は、驚いてレッドを見た。「誕生日は?」
「9月16日。なぜ?」
「それは、乙女座。あんたは乙女」
「ハニー、それはちょっと違うんじゃないか?」
「いいんだ。わたしは山羊座。ジェームズは、双子座。二重人格。あん
たには、いいオーラを感じる」
レッドは、自分のオーラが流れ出してないか、下を見た。出てはなか
った。
「星占いをしてあげられる。たったの20ドルで。あんたの過去、現在、
未来を話して」と、女。
「今日はやめておこう。ジェームズが借りていた室を見れるかな?」
「難しい。室はまだそうじしてない。見せるには、バンガローのオーナ
ーの許可がいる」
レッドは20ドル紙幣を出して、高く掲げた。
「星占いの前払いでは?」
女は紙幣をつかむと、中へ行って、鍵を持って戻ってきた。バンガロ
ーの1つに案内した。
中は、古くなった食べ物やカビの臭いがした。床には、半分詰まった
ダンボール箱があった。そこから毛皮のようなものが跳びだして、たぶ
んネズミが、冷蔵庫のうしろに消えた。
「急いで出て行ったようだな」と、レッド。
「そう。200ドルの支払いを残したまま」
「見て回っていいかな?」
「どうぞ」と、女。ドアフレームにもたれた。「そうじは借主がする。
わたしはそんな仕事はしない」
レッドは、3つある室を見て回った。ロックスターのポスターが2枚、
はがれかかった壁紙にピンで留められていた。床のマットレスの上には
汚れたシーツがあった。寝室の窓には、ダンボール紙と新聞紙が貼られ
ていた。安宿でさえ、もっと豪華だった。
女は、神経質に指先でこつこつ叩いていた。
「名前は?」と、レッド。
「エレーヌ」と、女。
「エレーヌ、オレは、しばらくこのクッションに座っている」と、レッ
ド。座ると、クッションが不謹慎な音を出した。
「オーラを感じられるかな?」
「たぶん。ヨガかなにか、やってた?」
「まぁ、少しは」
「ここは悪臭がするから、自分の室に戻ってる」
レッドは、エレーヌが室に戻ってドアをパタンと閉める音がするまで
待ってから、ランダールの箱を調べ始めた。箱の中味は、仕事や生活に
要するものや皿やプライベートのさまざまなものだった。一見普段と違
うものは、45口径の弾装と大きなハッシュパイプだけだった。
最後の箱は、紙類と本が詰まっていた。参考書には、家庭菜園や総合
化学剤があった。第三帝国滅亡のあと30年後に復活するナチスの恐怖
小説が2冊。その1冊にチラシとして挟んであった名刺を見つけるまで、
レッドは、ほとんど諦めかけていた。それは、マンフレッドの名刺で、
表に会社の住所と電話番号、裏に自宅の住所と電話番号があった。
レッドは、本類をもう一度見直した。麻酔の歴史という本には、田中
健似野の名刺があった。裏に電話番号とサンタモニカの住所があった。
レッドは、2枚の名刺をポケットに入れ、本を元に戻して出ていった。
海から吹いてくるフレッシュな風が、今までいた室がいかに臭かった
かを教えてくれた。塩辛い海風を、がつがつと吸い込んだ。
エレーヌにはさよならを言わずに出てきた。彼女には星座もあるし、
20ドルもらったから自分のビジネスを続けられる。
ぶつかりそうになったスケートボーダーに、悪態をついた。彼女の耳
はウォークマンの大音量で、レッドの声は聞こえなかった。かわいらし
い少女で、舗装道路をまたぐ足は黒だった。長いブロンドの髪は、フィ
フィと同じだった。レッドは追い越して、彼女の顔を見た。フィフィで
はなかった。冷たい視線でレッドを見ると、元気よくすべっていった。
レッドは、塩気のある運河のひとつをゆっくり歩いた。水の中に小石
を投げ入れて、数分を過ごした。たくさんのパズルのピースは出揃った
が、全体像が見えて来なかった。
首筋の後ろ髪が、うずうずした。誰かの視線を感じたが、人影は見え
なかった。
車に戻り始めた時、追けられていることを確信した。しかし、ロコの
手下の姿はなかった。同じペースで歩いているのは、建物や景色をニコ
ンで撮っている日本人のツアー客だけだった。
ボロボロのバンガローの近くに来た時、通りにはニコニコしたツアー
客しかいなかった。そのツアー客が路地の入り口で近づいてきた。
「すいません、サンホセに行くには?」
「なに?」
「もう気づいてしまったなら」と、男。のどにとどろくような声を出し
て、ニコリともしないオートマチックを出した。「これがなにか分かる
?」
「たぶん、ベレッタ」
「その通り!少し後ろに下がって!」
男は4フィート先にいた。ちょうど手が届かない距離だ。男の動きは
スムーズでプロのものだった。レッドは路地の方へ下がった。
「ありがとう」と、男、銃をベルトへ戻した。
レッドは突きを入れたが、逆に、腹に一撃を食らった。フレッシュな
海の空気がレッドの肺からシュッと吐き出された。
男は、時間をかけた。そこには、サディスティックな喜びはなかった。
息が荒くなることもなかった。ただ単に強く、強烈なブローで、想像で
きないくらいに、やっつけられた。脳からすべり出た赤い苦悶のベール
に包まれて、レッドは戦うことをあきらめた。
「他人のことに口を出すな」と、男。レッドのテンプルをタコのできた
方の手で殴る前に言った。
ショーが終わったことを告げるかのように、黒のカーテンが降ろされ
た。その直前、レッドは男の右手に小指の先がないのを見た。
尻ポケットがスリムな手でさぐられている気がして、目が覚めた。レ
ッドはうつぶせに横たわっていた。
悪ぶった若者がふたり、見下ろしていた。ふたりはレッドが目を覚ま
したことに気づかなかった。
「浮浪者にしては、いい身なりだ。靴だけで5ドルになる」と、やせた
方の若者。レッドの財布に手を伸ばした。
「小銭以外のカネがあればな」と、もうひとり。出っ歯の若者で、ステ
ーキナイフを手にしていた。
痛さから涙目になりながら、レッドは腰の銃をつかんだ。なんとか座
る位置まで体を起こして、若者の頭に銃を向けた。
「手をかしてくれ、ボーイスカウト!それとも、頭を吹き飛ばされたい
か?」
「分かった、分かった」と、やせた方。出っ歯の方は、路地へ逃げた。
はいていたスニーカーで、1マイル3分を切るかのように、ゴミ箱を蹴
り上げて走っていった。
レッドは足元がふらついた。どのくらい倒れていたのか知るために、
腕時計を見ると、時計は無くなっていた。
腕を若者の肩に巻きつけて、銃でポケットをつついた。なるべく荒々
しくつついた。
「時計を返せ!」
「分かった、分かった」と、やせた方。時計を出して、レッドに手渡し
た。「オレたちは別に」
「言い訳はいい。ニューヨークにいる代償だ。世界一タフな街。黙って、
歩け!」
不釣合いなふたりだった。背の高い方は、フォレストローンから今着
いたばかりのように見え、明らかにいやいや善きサマリア人に体をもた
げていた。
しかしベニスは風変わりなものたちばかりで、ふたりはほとんど目立
たなかった。
車まで来ると、レッドは腕をほどいて、若者をポケットの中の銃で押
した。
「逃げていい」
若者は、うなづく間もなく、レッドがドアをあける前に、半ブロック
は逃げていた。
車でモーテルに戻るには、力の限りを尽くさなければならなかった。
おまえは、殺されて当然だったと、レッドは考えた。小男にパルプのよ
うにぺちゃんこにされ、ジェシージェイムズ兄弟のようなガキに身ぐる
みはがされて、道に放置されそうになった。被害者の名は、レッドダイ
アモンド。
レッドは目を細め、歯を食いしばり、運転を続けた。
日本人は頭が良かった。やつは、まるで、だましゲームで子どもを扱
うように、レッドを手玉に取った。日本人を使うのは、ロコらしくなか
った。それで油断したのだ。あの小男は、すごい腕力があった。ヘビー
級の相手と1対1で戦ったことはあったが、これほどの痛みは感じたこ
とがなかった。
まだ、トニーにやられた痛みが残っている。これは、もちろん、ロコ
のスタイルだ。倒れてもまだ蹴り続けるのは、ロコのやり方だ。ネズミ
を殺す前におもちゃ遊びするのだ。
しかし、そのネズミは38口径を手にして、ロコに弾丸を撃ちこむチ
ャンスをねらっているのだ。
27
少し眠り、熱い風呂を浴び、バーボンで割った2杯のコーヒーを飲ん
でから、レッドは服を着て、田中の名刺の裏にあった住所に向かった。
田中の事務所に強引に乗り込むこともできた。ロコの手下たちが、銀
行の金庫室に立てこもったことがあった。2フィートの厚さの鉄とコン
クリートの壁に囲まれた室に、トンプソン銃を持った6人のガンマンた
ちが待ち構えていた。キャンサスシティ警察がなにもできずに外で待っ
ているあいだに、レッドは強引に乗り込んでいったのだ。
自宅にいるところを捕らえれば、やつには不利だ。本拠地での戦いに
持ち込もう!意外性をつくのだ。直行せよ!
サンジエゴへ向かうため、ベンチュラからサンタモニカフリーウェイ
に入った。高速を出たのは、ラジオがグレンミラーの「アンヴィルコー
ラス」を終え、フレディマーチンオーケストラの「4月のパリ」を演奏
し始めた頃だった。
曲と一緒にハミングした。左は太平洋、右はヤシの木が並び、そして
前方には、困難が待ち構えていた。
田中の自宅の正面入り口は、きれいに刈り込まれた樹木と多彩な色の
石で覆われていた。裏庭は海だった。その間に、2棟の白の船舶風家屋
があった。小さな丸窓、2階は丸いデッキ、霧笛のような突き出しはエ
ントツ。海上を走り回るフェリーのようだった。
レッドが呼び鈴を押すと、「錨を上げて」の最初の数小節が内に響い
た。次のコーラスが始まる前に、ドアが乱暴にあいた。レッドは銃に手
を置いた。
しかし、ドアをあけたのは女だった。手は脇に下げた。女は中年で、
ブロンドの髪は白髪が混じり、生え際は茶色になり始めていた。少しは
手入れすれば、女はきれいだったろう。微笑んだりすれば、きれいだっ
たろう。大量の飲酒をずっと前にやめていれば、きれいだったろう。
「なんの用?」と、女。酒の臭いのする憎悪の雲が、レッドの方へ漂っ
てきた。
「健似野は在宅で?」
「いいえ。ネズミのような部下のところ」
「オレはレッドダイアモンド。私立探偵」
「そうなの」と、女。ドアを閉めようとした。
レッドは、足で止めた。
「足をどかさないと、警察を呼ぶよ!」と、女。
「ご主人のことで」
「それじゃ、わたしには関係ない」と、女。ドアに力を込めた。
「ご主人がクライアントの妻と浮気をしている」
女の顔の不機嫌さがなくなって、ドアを押すのをやめた。「ずっと、
あの野郎をやっつけたかった。証拠があるの?」
「仲間のひとりが、やっとシッポをつかまえた。入っても?」
女は荒波のヨットのように後ろにのけぞり、レッドは、海の見えるリ
ビングルームに続く、玄関ホールに通された。女はハッチカバーででき
たテーブルから酒のグラスを取って、青と緑のソファに座った。
「あいつが嫌い。海が嫌い。このディズニーランドのような家が嫌い。
魚が嫌い。あいつのヨットが嫌い。メイドがひとりもいないのが嫌い。
なにが知りたいの?」
「裏の情報。ご主人の」
「なぜ?」
「なぜなら、オレはご主人がクライアントの妻と浮気をしていると見て
いる」
「証拠は?」
「少し」
「どんな?」
「そう、写真があるが持ってきてない」
「写真?」
レッドはうなづいた。最初、女は微笑んだ。グラスを飲み干して、酒
をついだ。レッドの分はなかった。
「写真がいる」と、女。
「離婚するのに、写真はいらない。簡単に離婚できる」
「法律くらい知っている。わたしは、あいつに証拠を突きつけたいのよ。
新聞記事のコピーをみんな送って!日本のも。あいつを破滅させてやる」
彼女の憎しみは、酒臭い息より強かった。「写真が必要よ!」そう言っ
て、女はスコッチをがぶ飲みした。
「道徳的にどうかな」と、レッド。声に少し躊躇があった。
「十分気を配ってる」
「クライアントと相談しないと」
「そうして」
「もう少し情報をくれたら、クライアントを説得しやすい」
「どんな?」
「ジェームズランダールという名前の男と、なにか取引は?」
「なんの取引?」
「ランダールはポン引き」
「主人はそういうことにはカネを使わなかった。秘書にまかせていた。
ランダールは、聞いたことがある。昨夜も電話で話していた」
「どんな話だった?」
「女のことではなかった。絵画とかカネとか。ランダールは、絵画を売
りつけようとしていたようだ。健似野は、夢中になっていて、いつもの
かんじでなかった。こころが虚ろで、名前を呼んでも、半笑いだった」
「5フィート6インチくらいの背で、鍛えられたからだ、右手の小指の
先がない日本人は?」
「それは、片那。主人のドライバー兼ボディガード、右腕。ぞっとする
やつよ」
女は立ち上がった。上体を揺らし、嵐の中の苗木のように震えた。
「主人は言っていた。もしもわたしが逆らったら、片那をけしかけると。
そうするに違いない。もうこれ以上話したくない。帰って!」女は、ス
コッチの強い一杯をあおった。
「飲むのをやめて、話してくれれば」
「指図はやめて!」女は叫んだ。「出て行って!出て行って!ひとりに
させて!」女は座った。自分だけの辛い世界に戻って行った。レッドが
出て行こうとしても、気にもとめなかった。
28
レッドがマンフレッド家に戻るとすぐに、家庭教師にしがみつかれた。
「戻ってくれて、ありがとう」と、家庭教師。「マンフレッド氏は外出
中で、グウェンは広間でヒステリーになって、わたしにはどうすること
もできない。どうにかしてあげて!」
広間に近づくと、長い間使われてなかったかのように、かびの臭いが
した。広間は、アーサー王が王冠を載せ、100人の客を祝宴に招くよ
うな室だった。テーブルは丸くはなく、細長く上になにも置かれてなか
った。
一方の端に座って、すすり泣いているのは、グウェンだった。マンフ
レッド家歴代10世代の肖像画が壁から不服そうに見下ろしていた。グ
ウェンは先祖たちの陰気な表情を気にもしなかった。レッドが入ってき
たことさえ、気づかなかった。
「どうした、かわい子ちゃん!」
グウェンは顔を上げて跳び上がると、レッドへかけ寄った。腕を伸ば
して抱きついた。力がもっと強ければ、窒息させるところだった。
やさしく言葉をかけてあげて、頭をなでると、どうなっているのかが
分かった。
アリソンが15分くらい前に電話してきた。彼女がランダールと隠れ
ているところへロザリーがやってきた。ランダールは、盗んだ絵画を売
りさばいてから、2人の女と逃げるつもりだった。しかしアリソンは、
3角関係がイヤだったので、マンフレッド氏に迎えに来てと電話したの
だ。
グウェンは、これ以上盗み聞きできなかった。
「私立探偵になれるように盗み聞きしたの」と、グウェン。鼻をすすっ
た。「ダディが出かけようとしたとき、止めようとしたけど、押し返さ
れた。どこへ行ったのか分からない」
「彼が電話を取ったのはどこ?」
「書斎よ」
「よし、そこへ行こう」と、レッド。グウェンに腕をまわして、元気よ
く歩き出した。
「怖いわ、レッド」
「かわい子ちゃん、どうしたらタフになれるか知りたいか?」
グウェンはうなづいて、ハンカチで目をぬぐった。
「まず、最初に、怖がることだ」
「ほんとう?」
「スーパーマンの漫画を読んだ?」
「今は読まないけど、前は読んでいた。なぜ?」
「スーパーマンは、弾丸を跳ね返したとき、タフだった?」
グウェンは質問をよく考えた。「そう思う」
「いや、そうじゃない。弾丸はただ跳ね返っただけ。彼がタフだったの
は、クリプトナイトに直面したとき。彼を痛めつける恐ろしいなにかに
立ち向かっていったとき、タフだったのだ。同じように、オレはあんた
とケンカしたら、タフなんじゃないか?」
グウェンは笑った。「いいえ。ケンカしないだろうし」
「そうだな。オレは大きいし、乱暴だからタフではないかも。しかし、
もしも、あんたがオレにケンカしたら、あんたはタフなんじゃないか?
分かるか?」
「あんたは乱暴でない」レッドに抱きついた。「いっしょにいて!」
「それができないんだ。オレには仕事がある。オレがいなくても、あん
たはタフになれる。ぐっすり眠っているときは、どのみち、みんなひと
りなんだ」
書斎のドアは、半開きだった。レッドがマンフレッドの机の上の書類
を調べていると、グウェンは見ていた。電話の横にメモ帳があったが、
一番上は白紙だった。
レッドはメモ帳を光にかざした。マンフレッドは、物を書くとき強く
書いた。跡がくっきり残っていた。「ランダール、銃、ロザリー。トパ
ンガ、ハッピートレイル」しかし、住所は読み取れなかった。
いっしょに行きたいという要求を無視して、レッドはグウェンの頬を
お別れに突っついた。急いで室を出るとき、オートマチックのひとつが
壁のコレクションから無くなっていることに気づいた。
車まで走り飛び乗った。トーマスブラザース地図で、ハッピートレイ
ルとトパンガキャニオンブルバードの場所を確認した。
フットヒルフリーウェイには時速60マイルで入り、ベンチュラフリ
ーウェイには時速75マイルで入った。スピードメーターが時速80マ
イルを越えると、車は異議を申し立て始めた。それを無視して、レッド
はアクセルペダルを踏み続けた。
車はキーという音を立てて、トパンガキャニオンブルバードの出口を
出た。最初の1・5マイルは、きれいな住宅地を抜ける3車線の直線道
路だった。ロサンジェルス市を出て、郡のエリアに入ると、道はヘビの
ように曲がりくねって、危険な野獣と化した。街灯はほとんどなく、車
もまばらだった。木ばかりで、わき道は隠れて見えず、乾いた峡谷だっ
た。ベガスのコーラスラインよりもカーブが多かった。
道は、登り坂になった。ガードレールはなく、落ちる危険が増した。
それでも、スピードを出し続けた。のろい制限スピードは、無視した。
石を踏んでガリガリ音を立て、落石注意の看板も見なかった。
オレはレッドダイアモンドだ。フィフィを助けに向かっている。
29
サンタモニカロードの急カーブを曲がったときに、大きな銃声がした。
マンフレッドのオートマチックが近くにある気がした。
しかしメモ帳には、ランダールには銃があるとあった。ベニスのラン
ダールの箱には、45口径の弾装が入っていた。
ランダールは危険で、ウィルロジャースの友人の数以上の敵がいた。
マンフレッドは覚悟を決めた老人で、怒りから周りが見えず、たぶん、
限界を越えていた。ロザリーは裏切り者で、ウソばかりつく。そして、
フィフィがその中に囚われていた。
車をハッピートレイル近くの路肩に停めると、レッドは車から跳び出
した。一番近くの木造平屋の家に走って行って、ドアを叩いた。38口
径は手に持っていた。
返事はなかった。ドアを蹴ってあけた。誰もいなかった。つぎの家に
走ってゆくと、また、同じことを繰り返した。そこも誰もいなかった。
3番目の家には、電気がついていた。ドアを叩くと、ずんぐりしたヒ
ゲをはやした若者が、マリファナを吸いながら出てきた。
「なにか?」と、若者。
「銃声を聞いたか?」
「ああ、しかしこのあたりでは、みんなうさ晴らしに銃をうつ」
「どこから聞こえてきたんだ?」
「さぁ、分からない」若者は顔に白痴のような笑いを浮かべた。「テレ
ビに戻らないと!ドラグネットの再放送があるんだ」
「待ってくれ!」と、レッド。ポケットをさぐった。「この女を見なか
ったか?」マンフレッドの娘の写真を見せた。
「言ったように、この峡谷では自分のことしか気に掛けない。他人のこ
とに鼻を突っ込むのは悪いカルマとされている」
レッドが若者のへそに銃を突きつけると、彼は初めて銃に気づいた。
「こいつで、へそをもうひとつ作ると言われても、教えないか?この女
はどこに住んでいる?ジャックウェブが犯人を捕まえるところを見れな
くなるそ!」
「3軒となりのトレーラー」
レッドは、若者をドア口に立たせたまま、道路を走った。トレーラー
からはオレンジの光が漏れていた。小さな焚き火が凶暴になったような
光で、レッドには、居心地がいい光には感じられなかった。
窓から炎が見えた。レッドはトップスピードでドアを蹴破った。動く
ものに銃を構えながら、床に伏せた。
3つの死体がころがっていた。男がふたり、女がひとり。腕や足は互
いにからまったまま。それは1つの大きな野獣で、床の炎と同じ真っ赤
な血を流していた。
この場を地獄のように見せてる炎のことも忘れて、レッドは凍りつい
た。ふたりの男、ひとりの女。床の上の死体。
フラッシュバックが始まった。ホテル、クローゼット、暗闇、銃声、
死体、絶望、サイモン、ミリー、売春婦。
女の悲鳴が、そこからレッドを連れ戻した。彼女はイスに縛られてい
た。フィフィ。炎が彼女をジャンヌダルクに変身させようとしていた。
フィフィ。
アドレナリンの力で、レッドは炎に飛び込んで、女をイスごと持ち上
げて、引っ張り出した。ズボンの裾を焦がし、彼女を縛っていたロープ
をほどいた。女は立ち上がり、気を失った。
トレーラーのプロパンガスが爆発して、炎は屋根を這い出した。レッ
ドは女を抱き上げて、車に運んだ。目はかすみ、ゾンビのようなぎこち
ない動きで、手足はホルモンから来る震えで小刻みに揺れていた。
ど田舎から早く出ろ。レッドは運転しながら考えた。隣のシートに女
がいた。田舎にいても客は拾えない。都会に戻ろう!
彼女は前のシートでなにをしている?客は前には乗れない。注意書き
を読めない?注意書きがない。ミリーなのか?いや、ブロンドだ。ミリ
ー。本。レッドダイアモンド。やつはだれだ?やつはやつ。ロコ。ロン
グアイランド。メロニー。フィフィ。
フィフィ!
彼女は目を覚まし、ゆっくり体を動かした。ブロンドの長い髪は、汚
れた白のブラウスにかかっていた。彼女は胸あてをつけてなかった。車
が道をはずれるたびに胸が上下にゆれた。目の片方は、くまになって腫
れ、もう片方は、ぼんやりしたブルーだった。足は裸足で、足指の8本
に赤のマネキュアをしていた。彼女は煙のにおいがして、肌にぴったり
の焦げたジーンズをはいていた。
「ここはどこなの?」彼女の声は、長い間、聞くのを待ち望んでいたも
のだった。「わたしはだれ?あなたはなに?」
「オレは、レッドダイアモンド。私立探偵。あんたは、フィフィラロッ
シュ。オレの昔からの、長い間会えなかった友人。オレたちはロサンジ
ェルスに向かっている。あんたはもう安全さ、ドールフェイス」
「フィフィラ━━━なんですって?」
「ラロッシュ」
「ちょっと違う気がする、よく分からないけど」彼女は、人差し指の長
いツメをかんだ。それは足指と同じ赤のマネキュアだった。
「いいんだ。あんたはショック状態にある。あそこでなにがあったか、
思い出せる?」
彼女がツメをかじっている間、車はさらに数マイル進んだ。
「だれかといっしょだった。男」
「ジェームズランダール。やつはギリシャ人」
「そういう気がする。かわいいけど、切れもの」
「続けて」と、レッド。嫉妬心を感じた。「記憶はそれほど正しくはな
いが」
「それから、あの女が来た。ローズだったと思う。尻軽女」
「尻軽女と切れものがなにを?」
「ふたりはなにかを盗んだ。女は分け前を欲しがった。男は、まだ、カ
ネをもらってないと言った。女は怒った。男はいっしょに来てもいいと
言って、今度はわたしが怒った。3人ともいがみ合った」
娘は心の動揺を静めようとした。レッドはラジオのスイッチを入れた。
車は南へ向かい、グレンミラーは「さぁ、ついに」を演奏し始めた。
「わたしは誰かに電話して、助けに来てと言った」
「あんたの父、エドワードマンフレッド」
「さっき、わたしの名はラロッシュって言わなかった?」
「つづきを」
「それで、彼が来た。彼は、これを見て怒った」と、娘。腫れた目を指
差した。「それから、ジェームズとローズ、つまりロザリーが彼に跳び
かかった。彼らはもめていて、カネが必要だと言った。それは、彼に跳
びかかる前。それからケンカになって、ジェームズは銃を持っていて、
老人も銃を持っていて、それから、それから━━━」
娘は泣き出した。
「絵画について、なにか言ってなかったか?」
「そう、そう。老人が、あなたによるとマンフレッドが、言った。『お
まえらは、娘と絵画を盗んだ』と」
「それで、ランダールは?」
「彼は、マンフレッドが100万ドルで買い戻せると言った。さもなけ
れば、もっと高値で別の人に売ると」
レッドは娘の言ったことを考えていた。娘は記憶を整理しようとした。
「わたしの名前は、フィフィだっていうの?どうも、そうは、思えない」
レッドは、うなづいた。無言で車を走らせた。じゃり道の音に対抗す
るのは、ラジオのビッグバンドの演奏だけだった。
「空港近くのホテルに泊まろう。それですぐに、この町ともおさらばだ。
今はそれしか計画できない。知りたいのは、この事件に、いかにロコが
関わっているかだ。あんたは、このことでなにか知ってるはずだ」
「ロコという人は、まったく知らない」と、娘。おどおどしながら。
「いいんだ、ベイビー。今は。いろんなことがあって、ショックを受け
ている。別に咎めやしない。今夜は休んで、明日、物事は解決だ」
30
モーテルのフロント係は、きれいに髪をセットし、高慢な笑みを浮か
べ、モーテルチェーンのロゴのついた青のブレザーを着て、レッドを注
意深く観察してから、宿泊カードを渡した。
レッドは宿泊カードに記入しながら、若いフロント係がフィフィをじ
ろじろ見ていることに気づいた。青白く、黒のくまのある目で、すそを
引きずって汚し、火事の燃え残りのような臭いがしても、フィフィはそ
れでもいい女だった。
レッドは、彼女を室まで案内して、ベッドに座らせた。まっすぐ前を
見て黙ったまま、涙がすすけた頬を伝って流れ落ちた。それから、しゃ
べりはじめた。
「わたしの名前は、フィフィじゃない。アリソンマンフレッドよ。父は、
エドワードマンフレッド。父は死んだ。父とジェームズは、互いに殺し
合った。あとあのひどい女、ロザリーは、うちのメイドだった。わたし
も危うく殺されるところだった。そして、みんな死んでしまった。ひど
かった。みんな死んだ。殺し合った。それから火が、銃撃のあとで、そ
れから━━━」
レッドは、すすり泣き出した彼女をやさしく抱いた。
「いいんだ」と、レッド。「あんたはショック状態にある。ゆっくり休
んだらいい。みんなうまくゆく」
慰めの言葉をかけてから、シャワーを浴びるよう説得した。
ベッドルームのドアを閉め、水を出す音がしてから、彼女が泣いてい
るのが聞こえた。
バーガスとトニー、田中と片那たちは、まだ、自由の身だ。それに、
ロコやその部下たちも。黒幕を捕まえられたら、小さなハエたちは逃が
してしまってもいい。
もしも悪魔のようなずるがしこい敵を取り逃がしてしまったら、もっ
と多くの涙が流されることになる。
レッドは、ただ逃げてしまうという考えで遊んでみた。フィフィとい
っしょに、警察の仕事が少なく、みんなが自然死まで生きられる場所を
見つけるのだ。
なぜ、レッドダイアモンドは、世界の警察機構でも失敗するような場
所でひとり抵抗しなきゃならないんだ?オレはひとりなのに。疲れ切っ
たひとりの人間なのに。
フィフィは、すぐにバスルームから出てきた。肌の色つやを取り戻し、
石鹸の香水のかおりがした。彼女をベッドに寝かしてから、レッドは熱
いフロを浴びた。
なんて女だと、タオルに包まれたフィフィの体を思い浮かべながら、
レッドは考えた。すぐに、フィフィは、レッドだけのものになる。レッ
ドダイアモンドは決断する時なのかもしれない。多くの撃ち合いのあと
なので、ささいな家庭的な幸せは大歓迎だ。
とんでもない結婚式になるだろう。いろんな人物を招待しよう。今世
紀最大のハードボイルド祭典だ。マーロー、スペイド、ニックとノラチ
ャールズ、レースウイリアムズ、レスターレイス、リューアーチャー、
シェルスコット。コンチネンタルオプ探偵局の者たち。フィリピンから
ジョーガル。イギリスからサイモンテンプラーとブルドッグドラモンド。
ニューヨークからマイクハマーとマットスカッダー。ボストンからスペ
ンサー。ワシントンDCからチェスタードラム。神に見捨てられたシン
シナティーからハリーストーナー。マックスラーチンが式を仕切ってく
れる。ケイシーかケネディが、写真を撮ってくれる。
長い間語り継がれる式になる。みんな入り口でチェックして、銃を預
かる。すぐ頭に血がのぼるやつもいるが、みんないいやつだ。酒もあり、
女もいて、楽しい時間になるに違いない。
レッドダイアモンドと恥ずかしそうな花嫁が、みんなの注目を集める
ことだろう。
花嫁を、女好きの連中から遠ざけるのは大変だろうが、レッドは他の
連中と同じくらいタフなのだ。
うとうとしながら、タキシードを着た自分を想像した。フィフィは彼
女の魅力を引き立たせるガウンをかぶり、品位があった。2本のやさし
い腕が肩をもみ始めた。
お礼にキスをした。タオルでふいてもらっているとき、洗面台の上に
置かれたソーダの空き缶に気づいた。
「あれをどこで?」と、レッド。
「外出したとき、ロビーの自動販売機よ」彼女は、くすくす笑った。
「あのフロント係はすごくキュート。黒あざはあなたが付けたと思って
いた。あなたからわたしを守ってくれると言っていた。しかし、あなた
はわたしのヒーローだって言ってやった」彼女はレッドにキスした。
レッドは怒り出した。「オレの許可なしに今後外出するんじゃない!
外は危険なんだ、ロコを始末するまでは」彼女を強く抱いた。「分かる
かい、フィフィ?」
「わたしの名前は、フィフィじゃない。アリソンマンフレッドよ。ズボ
ンのポケットに免許証を見つけた」
「ニセの免許証さ。ゲームをやるのはよせ!あんたの名前は、フィフィ
ラロッシュ」
「違う」彼女はバスルームのタイルを足で踏んで音を立てた。「アリソ
ンマンフレッドよ。わたしを誰かと間違えないで!自分が誰か分かって
るわ」
「ベガスのナイトクラブで歌ったこともない?シカゴのカクテルウェイ
トレスとして働いたこともない?ボストンの金持ちの男と結婚したこと
もない?ニューヨークのマンゲチェズジョセフの店で働いたこともない
?」
「どこでそんな情報を?わたしは、そんなところで働いたことはない」
レッドはやさしく彼女にキスをした。「現実を直視するんだ、天使ち
ゃん。タフな世界だが、逃げちゃだめだ」
「狂ってる!」
「あんたに狂ってるのさ。オレはすべてを知っている。他のやつらのこ
とは構わない。フリスコビリヤード場の裏で、ロコの手下にひどいこと
されたときのことも知っている。いいんだ。忘れるなよ、オレがあんた
をネバダの売春宿から救い出したことを。ロコを始末したら、オレたち
は結婚するんだ」
彼女は目を見開いて、レッドを見た。「まだ、会ったばかりよ!」
レッドは彼女を抱いて、くちびるを重ねた。バスタオルは床に落ちた。
彼女を抱き上げると、ベッドに運んだ。
彼女の服は、秋の枯葉のように舞い落ちて、ふたりのほかには世界は
誰もいなくなった。
夢に、ロングアイランドの家が出てきた。レッドダイアモンドは仕事
場。フィフィはキッチン。息子はショーン、娘はマロニー。幸せで家庭
的なシーンだった。しかしそのとき、ミリーという女が、ロコという男
といっしょに玄関に来た。銃声がして、床に死体の山がふたつ。6人の
死体。ひとつの山に3人づつ。カーペットに洗っても落ちない血のあと。
レッドは、夢から覚め始め、「ミリー」と呼んだ。
「わたしの名前は、フィフィじゃなかった?」
レッドは、となりにいる女を見た。悪夢は消え去った。「ただの結婚
前のイライラさ」と、レッド。腕を女の肩にまわした。そしてまた眠り
に戻った。彼女が安心するに十分な時間だった。
ふたりは、つぎの日の遅くまで眠っていた。
モーテルの室のドアが開く音で目覚めた。レッドは枕の下の銃をつか
んで、眠りのもやを目を細めて追い払いながら、入ってくる人影に照準
を合わせた。
「なにしてるの?」と、フィフィ。ドア口で叫んだ。「わたしを殺す気
?」
「ひとりで外出するなと言っただろう」と、レッド。大声で。銃をナイ
トテーブルに置いて、起き上がった。
「わたしはもう大きいのよ」と、フィフィ。背後でドアを閉めた。「ラ
ンチが終わった時間。なにか食べ物を買いに行った。それにも許可がい
るの?」
「そう、外はジャングルだ」
レッドは立ち上がり、服を着始めた。
「今後、決して、そのようなことはするな、フィフィ」と、レッド。車
道で遊ぶ子どもを注意するように。
「あなたは、わたしをフィフィと呼ぶし、昨夜は2回も『ミリー』と言
っていた。どういう女性なの?」
レッドは、自分の頭を引っかいた。「ミリーだって?たぶん、フィフ
ィのことだ。あんたの名前は、フィフィ」
「違う!」
「そう!」
「違う。アリソンマンフレッドよ」
飛行機が頭上で轟音をたて、サンアンドレアス断層が裂け始めたかの
ように、モーテルを揺らした。「いいかい、ベイビー、オレたちはこの
クレイジーな町から飛び立ってゆくビッグバードの1つになる。結婚式
のあとすぐに。あんたはミセスレッドダイアモンド」
レッドはベッドに座り、彼女のぼんやりした様子に気づかずに、保安
官事務所の殺人課に電話をかけた。レッドは、ブラウニングに助けに来
て欲しかったが、保安官はレッドに出頭するよう言ったため、逆探知さ
れる前に電話を切った。
「そんなことのために出頭できない」と、レッド。苦々しく。「世間と
対立するのは、オレとあんた、分かるかい、ドール?」
「着る服がない!」
「オレが行っていくつか買ってこよう。しかしあんたはここ。もしも約
束しないなら、あんたを鎖でベッドに縛り付けなければならない」
彼女は約束し、体のサイズのリストを渡した。
レッドは、ブロックスの店で女性店員に買いたいものを説明するのに
苦労した。フィフィが欲しいものリストに書いた、ジーンズやスニーカ
ーやブラウスは買いたくはなかった。彼女は、レッドダイアモンドの妻
のように見えなくてはならない。
レッドはやっと、女性店員との共通の基盤を見つけた。注文した1着
のドレスは、ヴェロニカレイクが『拳銃貸します』で、もう1着は、ロ
ーレンバコールが『大いなる眠り』で、もう1着は、メアリーアスター
が『マルタの鷹』で着ていたものだった。靴の専門店で、ハイヒールパ
ンプスの1足も買い、これでだいたい600ドルになった。
レッドは上機嫌で、モーテルへの帰り道、アーティショウのジャズメ
ドレーを口ずさんだ。
モーテルの室に戻ると、ドアをあけて、「帰ったよ!」と叫んだ。顔
は、手に持った洋服の箱で隠れて見えなかった。
レッドの嬉しそうな声が、誰もいない室に響いた。箱を置いて、狂っ
たように室を捜し回った。誰もいなかった。
受話器を持ち上げて、フロントに掛けた。
「フロントです」と、気むずかしそうな老人の男性の声。
「109のダイアモンドだが、妻を見なかったか?」
「見てないが、見たら連絡する。ちょうど、今5時。なぜ、時間を知ら
せるのかって?それは、あんたの妻がうちのフロント係と出て行ったま
ま、帰ってこないからさ。金庫の現金も持ち逃げされた。どうしようも
ない。やつをつかまえたい。きっと━━━」
怒鳴りまくるモーテルのオーナーの電話を切った。
レッドは、また、ブラウニングに電話した。ブラウニングは、レッド
が来ない限り、手助けはできないと言った。決して逮捕しないと約束し
た。政治家の選挙演説のように、やさしそうな口調だった。
レッドは、フィフィが出て行ったことが信じられなかった。彼女がし
たことじゃないだろう。ロコだ!ロコの仕業に違いない。フィフィはフ
ロント係と出て行ったが、だまされたのだ。ロコが手を回したのだ。そ
う、ロコの臭いがする。フィフィをロコの支配地域へと誘拐したのだ。
レッドは、フィフィを守るために置いたナイトテーブルの上から、3
8口径をつかんで、シリンダーをチェックした。その音は、ルーレット
で回転する玉の音のようだった。玉は毎回ダブル0に来るのだ。
ロコはどこにでも現われる。レッドは今までは単純に自分の守りに徹
していた。しかし、もうそろそろだ。これ以上は、がまんしないでいい、
ミスターナイスガイ!こちらから戦いを仕掛ける、その時が来たのだ。
31
アンダースに電話すると、ガチャンと切られた。
それで、アンダースの家まで車で行った。
「ウェストウッドへは2度と行かないと約束してくれ!」と、アンダー
ス。レッドは約束した。わざとなにもしゃべらないでいると、アンダー
スは不平を並べた。
「あんたがビニーとトラブルを起こして、オレがひどく殴られた。それ
で、もう2度と招待しないと言われて、家から追い出された。あんたと
はもうこれ以上、なにもしたくはない。出て行ってくれ!」
「また、もとに戻したいと思ってるだろ?」
アンダースはうなづいた。
「それなら、ビニーバーガスの別の電話番号を教えてくれ!さもないと、
あんたを1軒ごとに連れまわして、アパートを見つけなけりゃならなく
なる」
アンダースは、レッドが追い詰められていると感じた。レッドの目に
潜む狂気のきらめきが、突然甦って、暴力的に室じゅうに満ちた。アン
ダースには、もし銃を奪ったとしても、今、目に前にいる凶暴な野獣を
止めることなどできないと分かっていた。レッドに電話番号を教えた。
「さぁ、あんたはバーガスに電話して、レッドはここだと教えることも
できる」と、レッド。「どのやり方でゆくかは、重要ではない」震える
アンダースを残して、出て行った。
レッドは公衆電話から、バーガスの家に電話した。
「ビニーを出してくれ!」と、レッド。電話に出たトニーに。
「おまえはだれだ?」と、トニー。
「レッドダイアモンド。ビニーの欲しいものを持っている」
バーガスはすぐに電話に出た。「ランダールのことは聞いた。おまえ
がやったのか?」
「あんたの欲しいものを持っている」
「いくらだ?」
「コールドウォーターキャニオンに来い。今夜9時。あんたひとりで。
取引をしよう」
「こうしたらどうか、なにか━━━」
レッドは電話を切って、田中のオフィスに電話した。秘書にレッドだ
と伝えると、田中が出た。
「妻と話したそうだな」と、田中。「そのやり方は好きじゃない」
「オレもあんたとあんたのヤクザの友人を好きじゃない。しかし、オレ
とビジネスする気はあるんだろ?」
「どんな?」
「ランダールがどうなったか聞いたか?」
「ああ。おまえがやったのか?」
「あんたの欲しいものを持っている」
「どんな?」
「コールドウォーターキャニオンに来い。今夜9時。ブツを見せる」
「いくらだ?」
レッドはまた電話を切って、ブラウニングに電話した。
「今夜10時に、コールドウォーターキャニオンで会いたい。話がある。
トリックはなし。見張っている。別人なら分かる。グッバイ、チャーリ
ー」
「ダイアモンド、どうして━━━」
レッドはまた電話を切って、会話を中断した。太陽が沈むまで、2時
間あった。わなを仕掛けた。ロコはきっと来るだろう。それを感じた。
最後の戦いだ。ブラウニングは、散らかったゴミの後始末をすることに
なる。唯一残念だったのは、グッバイを言えなかったことだった。
我が愛するフィフィに。
70マイルを車で走った。ワッツのボロ家から始まって、海沿いのマ
リブーの豪邸を過ぎ、夕陽のパシフィックパリセーズ、ウェストロサン
ジェルスを抜け、最後はハリウッド大通りへ。
売春婦がふたり立っていたが、通りに多くは出てなかった。車高を低
くした車が走り回り、ピンクの車体をジャンプさせながら、歩道のすま
し顔の女性をからかっていた。
旅行者は、ガイドブック片手に間の抜けた笑みを浮かべ、グローマン
ズセメント会社のプリントを折り曲げて持ち、ポストカードや安いみや
げ品を買っていた。
レッドは、旅行者たちが夢に見るようなマンションやホテルの正面玄
関を過ぎ、サンセット大通りに戻ってきた。観光名所をゆっくり見て回
る時間はない気がした。
その時間は近づいていた。レッドは、コールドウォーターへ向かった。
霧が出始め、道の両側の堂々としたヤシの木の鋭い輪郭をぼやけさせた。
霧は、丘を登るにつれ、薄いスープから濃いシチューになった。最初、
何百万ドルもする豪邸の玄関は、通り過ぎた道の後ろに見えていた。霧
が濃くなると、歩道近くの太い幹のヤシの木の輪郭だけが見えた。
すぐに、それらさえ見えなくなった。白の大波の中を進むことになっ
て、時速10マイルに落とさなければならなかった。
サンタモニカ山のたてがみに向かって、のろのろ進んだ。そこには、
巨大な傷跡を舗装したようなマルホランドドライブが通っていた。この
道はデートスポットになっていて、ロサンジェルスの街の明かりを見下
ろしたり、スポーツカーで即席の恋を楽しむことができた。
それは、レッドにフィフィを思い出させた。彼は歯を食いしばって耐
えた。ロコに会うのだから、恋人たちの道においても、レッドには愛も
なにもなかった。
最も近いカップルたちから2千フィートの路肩に車を停めて、イグニ
ッションキーを抜いて窓をいっぱいに開けた。
霧の向こうから音が聞こえた。ブルドッグドラモンドの事件を扱って
るときに、ロンドンで習ったやり方だった。レッドは思い出していた。
敵対するグループから有利になるやり方だった。
ラジオを聞きたいが、音を立てるリスクは犯せなかった。シートを倒
して、タバコに火をつけた。自然が、いかに物事のバランスを保ってい
るかが不思議だ、とレッドは考えた。真実を聞き分けられる盲目の男の
ように、霧の中ではなにも見えないが、聞くことはできる。レッドダイ
アモンドは、哲学者になった。
タバコを備え付けの灰皿に押しつぶすと、青のニコチンの煙の最後の
雲を吐いた。胡椒の木の臭いのする空気を吸い込むと、腕時計を見た。
8時数分過ぎだった。6台の車が通り過ぎて、ヒルサイドの住人たち
が家路を急いだ。
レッドは車から出て、公園までの数百フィートを歩いた。一番高い場
所まで、腰の高さの石垣があった。それを楽々と登った。
アメリカスギのまっすぐな木立に向かって歩いていると、足元の落ち
葉が音を立てた。レッドは、正面も背後も頑丈な2本の木の間に立った。
霧の中の道を走る車は、滝のような音を立てた。空気は、オーガニッ
クな香水の臭いに満ちていた。湿気のある風が、心地よかった。
ロコと手下たちは、すぐにやって来る、とレッドは考えた。早めにや
ってきて、わなを仕掛け、レッドダイアモンドを落とそうとするだろう。
しかし、レッドはパンチをお見舞いする。今すべきことは、辛抱強く
待つことだった。
レッドは、長く待つ必要はなかった。
32
道でタイヤが軋む音が聞こえた。土の路肩に乗り上げる音。4台の車
のドアがバタンバタンと音を立てた。
「この辺に散らばって、オレが合図するまで待て!」と、バーガスらし
き声。
「了解、ボス」と、トニー。「さっさか片付けようぜ。この霧はオレの
神経にさわる」
「ブルーノとバディはついて来い!所定の位置に!」と、バーガス。3
つのフードが右へ動いて行った。
3つのフードが20ヤード動いたところで、バーガスが叫んだ。「伏
せろ!だれか来る」
別の数台の車。田中の、のどから出るしゅうっという音。「ハイ、親
分」と、片那。もうひとりがなにか言った。
レッドは、こぶし大の石を拾い上げ、トニーがいると思える場所へ投
げた。
「そこにいるのは誰だ?」と、田中。「ダイアモンドか?」
「田中か?」と、バーガス。
「誰だ?」と、田中。
レッドは口を手でおおって、声が別の方向から聞こえるようにした。
「やつは、あんたたちが欲しがってる絵画を持ってるらしい」
「ダイアモンドか?」と、同時にバーガスと田中。
「フィフィはどこだ?」と、レッド。
「誰?」と、バーガス。
「絵画を持ってるのか?」と、田中。
「ロコとだけ取引する。フィフィと会ってから」
「なんの話だ?」と、バーガス。
「どこにいる?」と、田中はバーガスに叫んだ。
バーガスはそれを無視した。「ダイアモンド、絵画が欲しい。カネを
用意してる」
「そうだろうな」と、レッド。不気味に。
「誰が払うって?」と、田中。バーガスと35フィート離れていたが、
濃い霧のため、相手の姿が見えなかった。「オレはもっと払う」
「フィフィが必要だ。ロコもだ。あんたたちふたりは、絵画を分ければ
いい。ちょうど半分づつにだ。うまく分配できる」
しばしの静寂。レッドには、トニーと片那や他の部下たちが、下草を
這う音が聞こえた。彼らは、自分たちのボスからかなり離れていた。
「そろそろ動き出すぜ!」と、レッド。声の方向を少し変えた。双方の
殺し屋たちが近づく音が聞こえた。
「近づきすぎるな!」と、バーガス。レッドの方に悪態をつく前に叫ん
だ。
「これは、おれとおまえのふたりだけの問題だ、ダイアモンド」と、田
中。彼は、明らかに、バーガスに近づき過ぎていた。
「ふたりとも聞いてくれ!オレは6人のならずものを雇って、木の影か
らあんたたちを狙わせるなんてことは、していない!」
レッドは、みんなが凍りついて、はっと息を飲む音が聞こえた気がし
た。
「みんな落ち着いてくれ!」と、レッド。「あんたたちふたりとも、お
互いの欲しいものを持っている。オレは、フィフィと会って、ロコの居
場所を教えてもらうだけでいい」
力強い腕を持った連中がこそこそし出して、動きがもっとのろくなっ
た。
「なんのことだ?」と、バーガス。
「あんたたちふたりとも、やつに雇われているんだろ?オレをバカ扱い
しないでくれ!」と、レッド。
「どうかしてる!」と、田中。
「絵画が欲しい」と、バーガス。「取引しよう。娘とは関係ない」
長い静寂。田中の足元で砂利の音とシュッという音。バーガスの、の
のしる声。
「トニー、オレは撃たれた!」と、バーガス。
トニーの銃が爆音を上げた。片那のサイレンサーが、シュッという音
で応えた。ブルーノとバディは、急に動き出した。ひとりがマシンガン
でひと息で2ダースの弾丸を木々の間に撃ち込んだ。
片那のサイレンサーは、マシンガンのあとでは、ささやきのような音
だった。しかし、トニーのあえぎ声がした。日本の用心棒がトニーの先
手を打った。
レッドは、弾丸の猛り狂った嵐が一瞬静まったときに木々の間から出
た。静寂の間に、レッドは、トニーの死にかけたあえぎ声を聞いた。
田中がなにか日本語で叫んだ。片那が答えた。レッドにはなにを言っ
たのか分からなかったが、38口径を、片那が来ると思われる方向に構
えた。
片那が下草の脇をカニのように横歩きしてくるのが見えた。3ピース
のスーツを着た大人が、とレッドは考えた。子どものように汚れながら
這ってる姿はいただけない。それから、2発撃った。
片那は死ぬ前に、レッドの横のアメリカスギに4発の弾丸を撃ち込ん
だ。
ブルーノあるいはバディは、マシンガンを撃ちまくった。レッドは低
くかがんで、5ヤード離れた太い木に移った。
マシンガンのおしゃべりが止んでから、レッドは立ち上がって、ブル
ーノとバディが茂みをかき分けてやってくる音を聞いた。
レッドは位置を変えた。そのとき、黒の人影が空中を飛んできた。
「アチャーッ!」と、別の日本人の手下。
跳び蹴りと気合の声に、レッドは驚いた。手を蹴られて、拳銃を落と
した。カンフーの達人は、気を失わせるほどレッドを叩きのめした。
レッドを救ったのは、空中を飛んできた無数のマシンガンの弾丸だっ
た。最後の蹴りを入れようとしたカンフーの達人は、そのまま腰を無数
の弾丸で縫いこまれた。
一瞬ニヤリとし、ため息をつき、絶命して倒れた。
まだ、マシンガンは鳴りっぱなしだった。レッドは、大慌てで落とし
た38口径を、まるで近視の図書館員が落としたコンタクトレンズを捜
すように、森の床を這い回った。
ブルーノとバディは、マシンガンの連射を短くしながら近づいてきた。
やつらは、ふたりともマシンガンを持っているようだな、とレッドは気
づいた。連射パターンの微妙な違いを聞き分けた。
レッドは、落ち葉が溜まっていたところにあった38口径を拾い上げ
た。周りの木々に弾丸がつぎつぎにめり込んでゆくあいだ、あえて立ち
上がらずに丘を転がった。最後は、水の枯れた沢に転がっていった。
息を整えてから、汚れたジャケットを脱いだ。銃撃がテンポアップし
たとき、レッドは近くの茂みに這っていって、ジャケットで覆った。
「散らばれ!」と、手下のひとり。「やつを追い詰めるのだ!」
ふたりは、別方向から近づいてきた。
レッドは、石を拾って、ジャケットをかけた茂みに投げた。なにかが
うまくゆきそうになると、それにこだわってしまう、とレッドは歯を見
せて笑いながら考えた。
人影が前進してきて、不運な茂みに向かってマシンガンを撃ちまくっ
た。発射口の火花が、レッドにはいい的になった。2発撃った。マシン
ガンは静かになった。
「バディ!バディ!」と、生き残った手下。
「ブルーノ、聞いてくれ!ダイアモンドだ、話し合おう!」
ブルーノは、マシンガンの連射で答えた。
レッドは、自然のくぼ地の土に守られていて安全だった。しかしあら
ゆる点で追い詰められていた。銃にはあと1発しか残ってなかった。耳
がガンガンするにもかかわらず、かすかなサイレンが近づいてくるのが
聞こえた。
「取引しよう!あと3人の日本人がこのあたりに潜んでいる」と、レッ
ドは嘘をついた。「あんたとオレでチームを組もう!」
静寂。サイレンの音は、弱くなったあと、だんだん大きくなった。
「オーケー」と、ブルーノ。「出て来い!」
「あんたの信用は?せめて、武器を捨ててくれ!」
「おまえの信用は?」と、ブルーノ。
「オレは、レッドダイアモンド、私立探偵。武器を持たない相手は撃た
ない」
マシンガンが空中を飛んできて、レッドから10フィートのところに
落ちた。レッドは、くぼ地を注意深く登った。おそらく、ブルーノは2
0フィート先だった。レッドの左手には38口径、右手には石を持って
いた。
「おまえはどうなんだ?」と、ブルーノ。「銃を捨てろ!」
「オーケー」と、レッド。右手の石を、茂みに投げ捨てた。すぐにレッ
ドは、新しい石を拾った。これは、サンフランシスコのバーでいっしょ
にビールを飲みながら、コンチネンタルオプから教わったトリックだっ
た。レッドは、この10分間に、ネアンデルタール人が最初のマンモス
狩りで投げたより多くの石を投げた。
レッドとブルーノは、2匹の動物が相手が攻撃してくるか分からない
まま近づくように、ゆっくり近づいた。レッドは銃を腰に押し付けてい
た。左手は右手の上に押し付けていたので、傷を負っているように見え
た。
「銃を持ってるな?」と、ブルーノ。太ったからだが霧からぼうっと浮
かび上がった。
「いや、分からないのか?傷を負ってる」
「そりゃひどい!」と、ブルーノ。突然、脇のホルスターから32口径
を抜いた。ふたりは4フィートのところにいた。
ブルーノが引き金を引く前に、レッドは最後の弾丸を相手の大動脈に
撃ち込んだ。
死体にヒザをついて、32口径をつかみ取った。38口径の台座をズ
ボンでふくと、死体の近くの地面に落とした。道路に向かって数歩ある
いてから、木に寄りかかって、耳をすました。
サイレンが、あと2分くらいのところまで、近づいていた。
「バーガス!田中!あんたたちの手下は死んだ!直接話しをしよう!ゲ
ームは終わりだ!娘が欲しい。ロコもだ!」
返事はなかった。サイレンだけが近づいていた。
茂みをそっと歩くとき、足が見えるようになった。
「バーガス!田中!答えてくれ!娘が欲しい。ロコもだ!あんたは逃げ
られる!」
「なんの話か分からない!」と、バーガス。声は、傷を負ってるのか弱
かった。
レッドは近づいた。
「オレたちは生き残りのようだな」と、バーガス。「日本人は死んだ。
取引できそうだな。オレは絵画が欲しい」
「娘はどこだ?」
「先に絵画だ!」
レッドは、バーガスから20フィートも離れてないと読んだ。「バー
ガス、あんたは助けがいる。娘はどこだ?」
「オーケー、彼女は━━━」バーガスの声は、小さすぎて聞き取れなか
った。
逃げるための時間があまりない、とレッドは考えた。霧から出なきゃ
ならないし、国を横断しなきゃならない。誰が誰を殺したとか刑事に説
明しているあいだに、ロコは、ボゴタかマルセイユか、6つの隠れ家の
どれかに行ってしまうだろう。
「なんて言った?」と、レッド。急いで近づいた。
「娘は━━━」
バーガスの声は、サイレンの音にかき消された。
「どこ?」と、レッド。バーガスの姿の外枠が見えた。「急いで!彼女
はどこ?」
「ここだ!」と、バーガス。銃を上げて発砲した。
レッドは腰のあたりを蹴られたように感じた。32口径を2発撃つと、
バーガスは土の路肩に倒れた。そこは見た目よりずっと居心地良さそう
だ、とレッドは考えた。そして眠りに落ちた。
33
フラチロンビルのオフィスは暗く、夕暮れの光は、骨董のベネチア製
ブラインドを通して傾きかけていた。デスクの上のスコッチのビンは、
土曜の夜の教会のように空だった。
女の名前はミリー。問題を抱えていた。夫が失踪した。夫は金持ちで
はなかったが、彼女には夫がすべてで、カネがなかった。彼女は、支払
いは体か本でと申し出た。
彼女は、美しいブルネットで、なにか固有の、変というのではないが、
防腐剤の匂いがした。レッドダイアモンドは、不幸な妻に乱暴するよう
な男ではなかったので、本を選んだ。本は、彼女から手渡されると、粉
々になった。
そのとき美しいブロンドがドアから入ってきて、ふたりの女性は胸に
ぶつかってきて、爪で引っかこうとした。ふたりの爪はどんどん長くな
って、差し込む光は、明るくなっていった。
「そろそろ気がつく」と、男。
レッドは、目をひらいた。病院だった。窓のブラインドの黒を除いて、
すべてが白だった。あと、胸の包帯の一様でないしみの赤を除いて。
「なにがあったんだ?」と、レッド。初老の担当医は、濃い眉毛でレッ
ドに前かがみになっていた。
「もうダメかと思った」と、担当医。「弾が大動脈をかすめていた。助
かったのは、とてもラッキーだった」
「オレがラッキーだったら、やつの弾は当たらなかった」と、レッド。
頭を枕から上げた。「やつの方は?」
「ミスターバーガスのことなら、だめだった。警察が到着したとき、4
人の死体があった。警察が話したいそうだ」
「だろうな」と、レッド。頭は重く、枕に頭を落とした。
「今は、休んで」と、担当医。「話はできないと言っておく」
「あんたがドクター」
つぎの3日間、意識のはざまをさまよった。繰り返し見た夢は、黄の
キャブに追い回される夢で、そのボンネットは、ロボットの口のように
閉じたり開いたりした。
皮膚は、栄養注射、輸血や抗生物質の大量投与で穴だらけになった。
しかし、目が覚めるたびに、胸の包帯はだんだん小さくなっていった。
それがペーパーバックスの大きさになったとき、ドクターは刑事の入
室を許した。
レッドはベッドに座り、ブラウニングが入ってきた。他の殺人課の刑
事や法廷速記者が補佐としていっしょだった。
「ドクターによると、あんたは回復に向かっているそうだ。コングラチ
ュレーション!」と、ブラウニング。
「サンキュー!病気見舞いに?」
速記者は、家庭的な中年の女性で、熱心にガムをかみながらタイプラ
イターのフタをあけた。
「準備オーケー?」と、ブラウニング。速記者に。
彼女はガムをパチンとさせて、うなづいた。
「オーケー、ミスターダイアモンド、あんたの権利についてだが」と、
ブラウニング。カードを使わずに、ミランダ警告を読み上げた。レッド
が権利を放棄したあと、ブラウニングは訊いた。「なにがあった?」
「マンフレッドの会社はビジネスがうまく行ってなかった。図書館に行
けば、図書館員のおばさんがこれから話す経済用語の意味を教えてくれ
るだろうが、田中の会社があからさまにマンフレッドの会社を乗っ取ろ
うとしていた。この乗っ取りの条件は、とんでもなく不利だった」
レッドがベッドのボタンを押すと、2つに折れて背の部分が持ち上が
った。そこに寄りかかった。
「タバコはあるか?」と、レッド。
「あんたの分はない。ドクターの命令」と、ブラウニング。「続けて!」
「交渉を続けてる間にマンフレッドは、オレの推理によると、所有する
絵画で田中を買収しようと考えた。マンフレッドが戦前から日本に駐在
していた間に購入した貴重な絵画だった。早すぎる?」と、レッド。速
記者に。
彼女はガムをパチンとさせて、首を振った。
「彼女は英語が分かる?」と、レッド。ブラウニングにささやいた。
速記者は、無表情のまま、その言葉をタイプした。
「寄り道しないで、続けて!」と、ブラウニング。
「マンフレッドは、絵画に盗難保険をかけて、田中に盗ませようとした。
田中にいくらか払って、絵画を買い戻そうとした。
一方、邸宅に戻ると、マンフレッドは、3人の召使を新たに雇った。
田中が人材派遣会社に関わっていたのかどうか、あんたに調べてもらい
たい。3人は、トッド、ロザリーにランダールだ。ロザリーは、それま
で召使をしたことがあったのか?」
「あんたはどう思う?」
「オレが思うに、ロザリーはトッドを撃つことができた唯一の人間だ。
彼女は軍事用のライフルで見事な射撃を行った」
「彼女は、16までに売春容疑で何回か捕まっている」と、ブラウニン
グ。「最後に捕まったあと、裁判官がブタ箱か兵役を選べと言った。彼
女は兵役を選んだが、不名誉除隊になった」
レッドは笑った。「ランダールは絵画が取引されることを知り、その
仲介をしようとした。ロザリーも仲間に加わった。トッドもいやいやな
がら。トッドが撃たれたとき、オレに話していたのは、このことだった」
「あんたはあのとき、オレに話すべきだった」と、ブラウニング。
「そうかも」と、レッド。肩をすくめた。「田中の手下の片那とトッド
は、絵画を盗み出し、ランダールに渡した。ランダールは、田中を裏切
って、ビニーバーガスに売ろうとした。また、フィフィを仲間にした」
「フィフィ?」
「マンフレッドの娘のアリソン。すごい美人。オレたちはもうすぐ結婚
する。オレもそろそろそういう年ごろだ」
「そう?」と、ブラウニング。疑わしそうに。「続けて!」
「ランダールはバーガスに借金があった。絵画の取引で、この借金を清
算しようとした。しかしバーガスを信用できず、トパンガキャニオンに
身を潜めた。フィフィといっしょだった。あとで、ロザリーが来た。も
めごとがあって、マンフレッドがそこへ来た。結局、3人が死んだ」
レッドは、ベッドの背もたれの位置を変えた。
「コールドウォーターキャニオンであの夜、なにが?」と、ブラウニン
グ。
「答える前に、いろいろ考えたい」と、レッド。「ほかに質問は?」
「絵画はどこ?」
「たぶん、ロコが持っている」
「だれ?」
「裏の人物。やつは、オレをコケにした。バーガスは、やつの手下だ。
田中もだ。あんたの情報ファイルに載ってるはずだ」
「どこまでが事実で、どこまでが推測?それに、あんたが殺したのは何
人?」
めまいを感じて、レッドはベッドにもたれた。
「ロコのラストネームは?」と、ブラウニング。
「リコ。ロコリコだ。1900年生まれ。やつは、だいたい50のはず
だ」
「待ってくれ。1900年生まれなら、今はもう84にはなっている」
「いや、だいたい50だ。猛牛のような体をして、熊のような黒髪、や
つは、やつは━━━」
レッドは、真っ青になった。しゃべろうとしても唇が動かなかった。
「ここまでにしよう」と、ブラウニング。速記者に、手振りで終わりを
告げた。「法廷指定の精神科医が、明日会いにここへ来る。そのときに
また」
レッドは、手を振ろうとしたが、その力もなかった。安らかな眠りの
闇に戻った。
◇
「ミスタージャッフィ!サイモンジャッフィ!」
中年の男が奇妙な名前を口にしながら、レッドのベッドに寄りかかっ
ていた。笑った顔が、大きくぼうっと浮き出た。長い黒髪がレッドの鼻
に触れているのが見えた。とっておきの商売人の笑顔だった。担当医は、
うしろで顔をしかめて立っていた。
「まだ、元気じゃない」と、担当医。「許可できないことは、分かって
るはずだ」
中年の男は、笑顔のままだった。「しかし国の許可がある。重要だ。
聞こえる?ミスタージャッフィ!」
「患者を間違えてる、バディちゃん。オレの名は、レッドダイアモンド」
「あんたの指紋は、そうじゃないと言っている。自己紹介させてもらう
と、私は精神科医で、チャールズマンデルバウム。みんなにはチャーリ
ーと呼ばれている」
「スカンクだろ?」
担当医はニヤリとした。
「スカンクでなく、精神科医!」と、マンデルバウム。「どこからその
ような?」
「オレは私立探偵。直感で動いている」
「あんたの指紋は、そうじゃないと言っている」
レッドは、体を起こした。「そう?」
「断固反対する」と、担当医。「あまりに急すぎる。その前にすること
が━━━」
「ドクター、あんたは身体を直す。私は精神を扱う」と、マンデルバウ
ム。ヌメヌメとした笑いを浮かべた。
担当医は、室を出て行った。マンデルバウムは、レッドに向き直った。
「さて、ミスタージャッフィ、あんたの指紋に一致するものが警察にあ
った。あんたはサイモンジャッフィ。キャブドライバーで、2週間前に、
ニューヨークで行方不明になった。名前になじみはある?」
精神科医の声は、温かいワセリンを塗ったように心を静めた。賢くも
アゴにヒットした。顔に特徴がなく、年齢を推測できなかった。黒髪が
フサフサで、暗い探るような目をしていた。
「ミリーという妻がいる」と、マンデルバウム。「息子はショーン、娘
はメロニー。家はロングアイランド。助けになった?」
「ファイルを間違えたんだろ?」と、レッド。少しためらったあとで。
「オレはレッドダイアモンド。私立探偵。過去5年間は、オレ自身のも
のだ。ロコリコというとんでもない悪党を追っている」
「警察がその名前を調べた。あんたの言っていた場所近くの唯一の犯罪
者は、5年前に死んでいる」
レッドは、くすくす笑った。「ロコのようなやつは、うまく行方をく
らます。今頃はどこかで、フィフィを人質にとって、大笑いしてる」
「フィフィ?」
「オレの彼女さ。この5年間、ずっと捜している。ずっと地獄だった」
「うーん」と、マンデルバウム。手帳に急いでメモを取った。「何枚か
カードを見てもらっても?」
「ご自由に」
マンデルバウムは、ポケットからロールシャッハカードを出し、1枚
を見せた。
「なにに見える?」
レッドはカードをよく見た。
「心に浮かんだ最初のものを言って!」と、マンデルバウム。
「オレの腰が痛む」
「違う、カードのこと。なにに見える?」
「インクのしみ」
「イマジネーションを使って、さぁ、すぐに、なにに見える?」
「ふたりの男が拳銃を奪い合っている。オレとロコがエンパイヤステー
トビルの屋上でやったように。やつは拳銃を抜いて━━━」
「拳銃と言ったね、それはペニスのことかね?」
「あんたはオレが病気かなにかだと思ってるのか?拳銃と言ったら銃の
こと、ピストル。ドック、だいじょうぶか?」
「それじゃ、これは?」と、マンデルバウム。別のカードを見せた。
「これはやさしい。オレとフィフィだ。いっしょにケンタッキーの酒の
密造小屋のクローゼットに隠れていた。やがて小屋が焼け落ちて━━━」
「それじゃ、これは?」
「血の水たまり。フリスコの波止場でロコの手下に捕まっていた時のよ
うに。オレはでかい図体に弾を撃ち込んで、やつは倒れ、血の水たまり
が、まるで━━━」
「もう十分だ、マンデルバウム!」と、メガネをかけた若い男。ドア口
に立って怒ったように。担当医は、若い男のうしろに立って顔をしかめ
て言った。「私の患者と話がしたいのなら、裁判所の許可を取ってきて
くれ!」
「ロバーツ、患者の同意は得ている」と、マンデルバウム。「その上、
国の許可もある」
「関係ない!出て行ってくれ!依頼人と話がある。あとで報告する」と、
若い男。
マンデルバウムは、カードをそろえてから室を出て行った。前を過ぎ
るときに担当医をにらみつけた。担当医は笑い、レッドとロバーツを残
して、ドアを閉めた。
弁護士は、35くらいで、やせて、きちんとした身なりをしていた。
確信のある足取りでレッドに近づくと手を広げた。親愛の気持ちを示す
だけの強さで握手した。
「私はアルビンロバーツ。担当弁護士」ベッドの上に黒皮製のブリーフ
ケースを置いた。
「国選弁護人?」と、レッド。
「いいえ。弁護料は安くはないが、すでに、支払い済みなので、ご心配
なく」
「だれが、オレの妖精のようなゴッドファザー?」
「むしろ、ゴッドマザー。グウェンマンフレッドが、どうやって父親の
遺産管財人を口説いたのか知らないが、支払いはすでに十分なほど済ん
でいる。あんたの弁護料も。よって、あんたの弁護ができる。検察はケ
ガが重いのに乗じて、マンデルバウムのようなガチョウを送ってきた。
彼はカネさえもらえれば、カマリロの患者でさえ州知事だと言うような
人間だ」
「とにかく、オレはクレージーではないわけだ」
「もちろん!しかしこちらも、マンデルバウムに匹敵するドクターを見
つけた。いろいろなオプションは残してある。こちらのドクターは、小
切手さえ渡せば、あんたを多重人格者と診断する」
レッドは顔をしかめた。「そういうのは好きじゃない」
「心配なく。躁うつ病とすることもできるし、誇大妄想とも。あんたの
好きなように」
「バグハウスは好きじゃない」
「聞いて、マイフレンド。相手はあんたに不利な証拠をつかんでいる。
ブラウニングは、これで6件の事件を終わらせようとしている。ニュー
ヨーク州はいくつかの事件で、あんたの身柄を要求している。信号無視
の話ではない。ビッグMのこと。殺人事件。お分かり?ミスタージャッ
フィ?」
「オレは、ジャッフィじゃない、ダイアモンド。レッドダイアモンド」
「そう、その調子。多重人格。私は法廷に戻らなきゃならない。その調
子を続けて。誰とも話さないこと」
ロバーツはブリーフケースを持ち上げると、ドアに向かった。
「ヘイ!あんたは、フィフィがどうなったか知っているのか?」
「こちらの証人のこと?」と、ロバーツ。向き直った。
「そう、オレの女」
「調べてみる。あした、罪状認否のときに知らせる」
◇
レッドはゆっくりなら歩けたが、ロバーツは車椅子で予審法廷に来る
ことを主張した。保安官補佐がレッドを車椅子に乗せて、予審法廷に押
していった。
自分がどれだけ弱っているか、法廷に来るまで気づいてなかった。騒
音、テレビカメラ、尋問がレッドを車椅子にだらりともたれさせた。ロ
バーツはウインクしてレッドを元気づけた。
ブラウニングは、レッドを事実上、ロサンジェルスに来てから会った
すべての人間を殺した犯人であるという宣誓陳述書を読み上げた。レッ
ドのことを、サイモンジャッフィもしくはレッドダイアモンドと呼んだ。
検察官は、やさしい仕草のかわいらしい若い女性で、舌はレザーのよ
うに鋭く、ずたずたに切り裂くときは、ミスタージャッフィと呼んだ。
レッドは大声で文句を言ったので、裁判官は、静かにしないのなら法
廷侮辱で拘束すると言った。
検察官は、レッドのことを、チャールズマンソンとリチャードスペッ
クにフン族のアッティラ王を加えて失笑を買うような男に仕立て上げた
ので、彼女に投げキスを送った。
ロバーツは、レッドのことを、あまりに輝かしい人物に仕立て上げた
ので、いったい誰のことをしゃべってるのか、法廷じゅうを見渡した。
ロバーツの主張はこうだった。「私の不幸な依頼人」は、もしもやっ
たことすべて正当とするほど、すばらしい人物でなかったとしても、正
気を失っていた。その上、警察の捜査は、すべて違法だった。
ロバーツの印象的な陳述のあと、裁判官は咳払いをして、レッドを保
釈なしで拘留するよう命じた。
ロバーツは、市民権の侵害や警察資料の発見、不利な証拠の隠蔽、検
察の越権行為、偏見に満ちた報道を理由に、訴訟却下を申請すると言っ
た。
裁判官はまた咳払いをして、レッドに次の日の身柄引渡し審問に出廷
するよう命じた。
レッドは車椅子で法廷を出た。ロバーツとふたりだけになったとき、
フィフィのことを訊いた。
「ブラウニングによると、彼女はホテルのフロント係と逃げた」と、ロ
バーツ。「ふたりは東に向かった。たぶん、ニューヨークだ。彼女は、
目撃者として身柄を要求されているので、私立探偵を雇って、行方を追
った」
「誰?」
「ゴールデン調査。優秀なとこだ」
「オレに相談して欲しかったな。友人のフィルマーローなら、打ってつ
けだった」
「あのフィルリップマーロー?」と、ロバーツ。眉毛がロケットのよう
に舞い上がった。
「ほかにいる?」と、レッド。
ロバーツは、車椅子に引かれてゆくレッドをじっと見つめた。
34
身柄引渡し審問で、ロバーツは雄弁な陳述を始めたが、レッドがさえ
ぎった。
「裁判官、話しても?」と、レッド。車椅子から立ち上がった。
傍聴人たちはおしゃべりをやめ、ニュース記者たちはメモを始めた。
ロバーツは口をあけたまま、ポカンとしていた。
「どうぞ」と、裁判官。背の高いイスにもたれて、鼻を退屈そうにさわ
った。
「しなきゃならなかったことを、しただけ」と、レッド。声は性格に似
合わず、ソフトだった。「ここでは、もうこれ以上は歓迎されない。ニ
ューヨークに戻りたい」
ロバーツはレッドの腕をとって、座らせようとした。
「裁判官、私の不幸な依頼人は、今ちょっと━━━」
「ミスターロバーツは、すばらしい弁護人だが、賛成できない」と、レ
ッド。「身柄引渡しは拒否せずに、ニューヨークに戻るつもりだ」
ニュース記者たちは、法廷から走って出て行った。ロバーツは、がっ
かりしてイスに座り込んだ。裁判官は、別の殺人事件の起訴のため、レ
ッドをニューヨークに戻すと命じた。検察官は、歯を見せて笑った。
◇
事務処理に2日を要した。南カリフォルニア医療センターでの囚人病
棟から、バウンセットストリート拘置所の付属病院に移された。レッド
は、2日間、食事を拒否して壁を見て過ごした。
ロコにやられた、とレッドは考えた。すべてがうまくゆかず、生涯で
初めて、懐疑的になり、冷笑的になり、厭世的になった。深く落ち込ん
でも、人々の親切さを信じる心や文明の力といったものへの確信があっ
た。レッドは拘置所で座ってるだけなのに、ロコは自由にやりたい放題
だった。いい人間がいつも勝つとは限らないという事実が、バーガスの
一撃より強く、レッドを打った。
そして、フィフィは奇妙な状況で姿を消した。フロント係と逃げたな
んてことが、本当にありうるだろうか?それは、彼女に望んでいるもの
とは違った。すべてが、計画通りに行ってなかった。たぶん、ニューヨ
ークでいくつか答えが見つかるだろう。
敗北の沼地に沈んだ。ねばねばして、ラブレアタールピットと同じく
らい深かった。ほかの囚人としゃべったり、からかったりすることも禁
じられ、ロバーツと話すことさえも禁じられた。
昼食も夕食も食べず、夜は壁を引っかいて書かれた文字を、なにが書
かれているかも分からず、ただ見ていた。
朝食も昼食も夕食も、ふたたび食べなかった。ロバーツは来たが、レ
ッドはなにもしゃべらなかった。
「あすの朝、あんたはニューヨークに戻る。刑事が迎えに来る。グッド
ラック!」と、ロバーツ。背後でドアが閉まった。レッドはふたたび、
ひとりになった。
◇
拘置所の中に朝の光が射し込んできても、レッドは動かなかった。
廊下から降りてくるふたりの足音が聞こえた。太った刑事の足音に聞
き覚えがあった。唇から火のついてない葉巻をぶら下げた、なじみのあ
る顔だった。
「ハロー、覚えてるかい?」と、ピートアングリッチ刑事。
レッドは、うつろな充血した目で刑事を見た。
レッドが手首をそろえて前に出すと、アングリッチは下ろさせた。
「それはいつでもできる」と、アングリッチ。親しげな親愛の情を込め
て、ニューヨークなまりで言った。「箱に折りたたんで郵送することも
できる。頭を殴って運ぶことも。手錠をはめて歩かせることも。あるい
は、ふつうの人間として飛行機で行くことも」
アングリッチの言い方は、準備されたものには聞こえなかった。自然
で信頼できた。レッドは安全を感じた。
「オレはトラブルはごめんだ」と、レッド。ソフトな感じで。
「言葉通りに受け取ろう」と、アングリッチ。
刑事補佐は、歩いてゆくふたりを疑わしそうに見た。アングリッチは
なまいきそうに、よたよた歩き、レッドは敗北したように、少し身をか
がめて歩いた。
刑事補佐の運転で、サイレンの付いてない車で空港まで行った。
「ひどい町」と、アングリッチ。ロサンジェルス空港に近づいた。
「ああ」と、レッド。
「天気はいい。6年前にディズニーランドに前の妻と行った。真冬だっ
たがTシャツで歩き回った。ショートパンツのかわいいブロンドでいっ
ぱいだった。妻は肘うちで、目移りさせないようにしていた」
「ああ」
「しかしすべてが離れ過ぎている。トイレに行くのにも車で20分かか
る!」アングリッチは笑顔で、冗談の反応を待った。
「ああ」
◇
空港に着くと、747に乗った。アングリッチはレッドの安全ベルト
を留めて、ランプの間、横で疲れたように座っていた。
35000フィートまで来ると、シートベルト着用と禁煙のランプは
消えた。アングリッチはレッドの安全ベルトはそのままにして、タバコ
を勧めた。レッドは1本取り、ふたりでタバコに火をつけた。刑事は、
リラックスして振舞おうとした。
「ブラウニングは、ハリウッド殺人事件やあんたが話したことをいろい
ろ教えてくれた。ロコリコやフィフィのことも」
レッドはうなづき、タバコをふかした。
「あんたに最初に会ったとき、レッドダイアモンドという名前は、不確
かだが知っている気がした。その名前を、ニューヨークの年配の刑事ふ
たりに聞いてみた。ふたりとも、レッドダイアモンドを知っていた」
小さな笑いが、レッドの唇にしわを作った。「オレもたぶん、かつて
は一目置かれた存在だった」
「ふたりは、レッドダイアモンドをパルプ雑誌で読んだそうだ。10セ
ント雑誌。タフな私立探偵。ある年配の刑事は、1ヶ月くらいしたら引
退するそうだが、そんな探偵小説をすべて読み返したいと言っていた。
レースウィリアムスやコンチネンタルオプ、フィリップマーローを、ま
るで好きな娘の話をする若者のように話していた」
レッドは窓の外を見た。飛行機は雲に囲まれていた。それは、コール
ドウォーターキャニオンの夜を思い出させた。
「それで彼に、レッドダイアモンドについてきいてみた」と、アングリ
ッチ。「彼は、ダイアモンドやロコやフィフィについて話してくれた。
ブラックマスクという雑誌には25の短編があって、それ以外に6冊の
長編があるそうだ。それがダイアモンドのすべて」
レッドは、相手が望んでいる謙遜した笑いを返した。そして座席の肘
あてにある灰皿にタバコを押しつぶした。「ああ、作家たちはオレのこ
とを、かなりりっぱに書いてくれた」
「あんたは何才?」
「43」
アングリッチはレッドの反応を見ていた。タバコを消して、火のつい
てない葉巻を口にくわえた。
「とにかく、短編は30年代や40年代に発表された。2つは50年代
初め」と、アングリッチ。長いジョークのオチのように。
「それが?」
「それが意味するのは、短編が発表されたとき、あんたは父親の目から
見たら、かすかな存在だったってこと。あるいは、オムツを卒業したこ
ろ」
レッドの頭の中で、ジェットエンジンでない轟音がした。アングリッ
チは、別のタバコに火をつけ、レッドを見ないようにした。
「それはありえない。オレは知っている。事件をよく覚えている。国境
を越えて、悪者たちが走っていた。オレは探偵事務所で働いていたし、
町にも行った。そこにやつらがいて━━━」レッドは、しゃべりだした。
「あんたは、ほかの小説から細かいところを読んだのだと思う。コーク
スクリューという町へ行ったように」
「そう、あれはコークスクリューだった」と、レッド。自信をもって。
「なぜ知ってる?」
「ダシールハメットの小説。コンチネンタルオプをたくさん読んだ。か
なりおもしろかった。最近のゴミに比べたら、かなりいい」
「ロコの手下のひとりのトリマーウォルツのことは?フィフィが通りで
客商売のふりをさせられた。オレは潜入捜査をしていた。タフタウンで
それは起きた。ヌーンストリートだ。そのことをよく覚えている」
「レイモンドチャンドラーの『ヌーンストリートで拾った女』」
レッドは震え始めた。6つの冒険をしゃべったが、アングリッチは、
それぞれのタイトルと作者をあげた。
「し、しかし、それはオレのことだ!」と、レッドは叫んだ。「すべて
オレがやった!やつらは盗んだんだ!ハメットやチャンドラー、ダリー、
ネベル、ガードナー、デントは、みんな泥棒!オレの人生!オレのスト
ーリーだ!」
まわりの乗客たちは、じろじろながめ始めた。レッドはぶつぶつ言い
っていたが、やがて静かになった。唇は、音もなく動いていた。アング
リッチは、手をレッドのヒザに置いていた。レッドの心は爆発していた。
アングリッチには、それがよく分かっていた。
ブラニーストーンにとまったアイルランドの妖精のようなスチュワー
デスがやって来て、大丈夫かたずねた。
アングリッチはウィンクして、レッドは有名な俳優で次の舞台のリハ
ーサルをしていると説明した。スチュワーデスは、静かにやってくださ
いと言って、食事の注文を受けた。
食事が来て、アングリッチは手の付いてない囚人の分までたいらげた。
レッドは、ただ外の雲を眺めていた。ロッキーの山々やアメリカの平原
を飛行機は過ぎていった。
「分かるだろうが、オレはパルプ雑誌の探偵小説を本当に楽しんだ」と、
アングリッチ。食事のトレイが片付けられるときに、レッドを貝殻から
引っ張り出そうとした。
レッドはただうなづいた。
アングリッチはスチュワーデスに、戦争の古傷で立ち上がれないので、
スポーツ雑誌を1冊持ってきてくれるよう頼んだ。スチュワーデスが戻
ると少しからかい、雑誌を受け取ると、最初から最後まで読んだ。
レッドは、ぶつぶつ言いながら、窓の外を見ていた。アングリッチは
体を傾けて、レッドのひとり言を盗み聞きしようとしたが、なにを言っ
ているのか分からなかった。
ニュージャージーを過ぎるころ、アングリッチは赤毛のスチュワーデ
スから電話番号を聞き出そうとしたが、うまくゆかなかった。彼はレッ
ドに注意を払わず、レッドも彼に注意を払わなかった。
「彼女は実にかわいい!」と、アングリッチ。シートベルト着用と禁煙
のランプがついた。スチュワーデスは通路を異常がないか調べながら歩
いた。
レッドはなにも言わなかった。
少しドスンとして、エンジンがブウンというとケネディ空港の滑走路
に着陸した。
通路は降りようとする乗客でごった返した。レッドとアングリッチは
乗客たちがすくのを待っていた。レッドは刑事に向き直りささやいた。
「もしもオレがレッドダイアモンドでないなら、オレはだれなんだ?」
アングリッチはノートを開いた。「あんたの指紋からすると、サイモ
ンジャッフィ、年齢43、ロングアイランドに住むキャブドライバー。
ミリーという女性と19年前に結婚した。子ども2人。逮捕歴なし、ス
ピード違反2回。ミリーとはしゃべったが、いい女性のように見えた」
「誰に似ている?」
「写真がある」と、アングリッチ。写真には、普通の造りの家の前に、
ひとりの男、女、少年少女が写っていた。「彼女が言うには、写真は5
年ほど前のものだそうだ」
レッドは写真をよく見た。写真の男は、彼かもしれなかった。アゴは
ちょっと弱そうで、目はもっとソフトで、疲れたふうだが、彼かもしれ
なかった。女は悪くはなかった。子どもたちも元気そうだった。
レッドの手は震え始めた。平静を保つために、イスの肘あてを握った。
「降りる時間」と、スチュワーデス。ふたりに仕事上の笑顔を送った。
「あと、少し」と、アングリッチ。まじめな顔をした。「歩けるか?サ
イモン」
「オレは━━━サイモンジャッフィ━━━じゃない」と、レッド。「オ
レは━━━レッドダイアモンド、私立探偵」ひと言、ひと言を振り絞っ
た。
スチュワーデスは、なにが進行中かよく分からぬまま、神経質そうに
見ていた。
「オレは━━━準備よし、すぐに行ける」レッドはぶつぶつ言い始めた。
アングリッチは腕をとって、レッドを立たせた。「行こう!」声は強
かった。命令だった。レッドは従った。
「もう、しゃべるな!」と、アングリッチ。
「もう、しゃべらない。オレは━━━レッドダイアモンド」と、レッド。
声にできる限りの強い確信を込めた。
ふたりは外へ出て、荷物受取所を過ぎた。アングリッチは荷物がなか
った。レッドの荷物は、州検事局が手配してくれた。
ふたりが歩道でキャブを拾おうと待っているとき、夕方の冷たい風が
吹いた。アングリッチは腕時計を調整した。タイムゾーンが変わって、
旅行時間を入れると、すでに午後4時半だった。
地方検事は、できるだけ早くレッドを連れてくることを求めていた。
落ち着いてる時間はなかった。6時のニュースで流される見出しは決ま
っていた。
キャブはつかまり、ふたりは乗り込んだ。
35
アングリッチは運転手にマンハッタンの地方検事のオフィスを告げる
と、キャブは走り出した。
「気分はよくなった?」と、アングリッチ。
「ああ」かつては殺人課の刑事に、なにも告げないこともあった。しか
しそうした時間は終わった。ゲームは終わった。
「これから地方検事と会う」と、アングリッチ。「検事は話が分かる。
そのあとベルビュー病院であんたを診せなければならない」
レッドはうなづいた。ベルビュー病院が意味することは分かっていた。
精神疾患の検査。アングリッチの言葉の奥になにかがあったが、レッド
は疲れすぎていて、抵抗する気になれなかった。
「さっきの写真はまだある?」と、レッド。
「ああ」と、アングリッチ。写真を出して、レッドに手渡した。
レッドは、写真の中の人々の生活を想像してみた。体型はスマートだ
った。少女は、おしおきが必要にみえた。女は知ってると思えない女の
だれかに似ていた。かつては知っていただれか。現実との境界線が定か
でない、デジャブの深い海で溺れている気がした。
「ヴァンウィック高速は使うな!」と、レッド。突然、運転手に。「混
雑していてメーターが上がる。一般道を使え!オレたちは旅行者じゃな
い!」
反射的に出た言葉だった。運転手はミラーでレッドを見ると、高速を
降りた。
「ヘイ!あんたを知ってる!」と、運転手。「キャブをしていた!オレ
を覚えてる?フリットクラフト。チャーリーフリットクラフト。42番
通りから44番通りまで乗せてくれた」
運転手の顔は、前の席に貼られたライセンス写真を見るまで、記憶に
なかった。
フリットクラフトを思い出した。記憶の映像に埋もれた顔の海で、溺
れそうになった。料金?羽振りのいいチップ?レッドダイアモンド?い
や、フリットクラフト。チャーリーには顔がない。顔のない男。敗北者。
オレのように。
レッドは分解し、サスペンションがいかれた64年型シボレーのよう
にふるえた。言葉を発すると爆発し、互いに乗り越えようとして、先を
争い、落ちて、くずれた。
「ゴミ、ヘルプ、パルプ、なくなった、パルプ、ヘルプ、ミリー、売ら
れた、ひとり、キャブ、売春婦、わな、わなにかかった━━━」
アングリッチはレッドにしゃべらせていた。運転手は驚いてミラーで
見た。
「売春婦、つかまった、ぽん引き、銃声、血、血、死体、血、パルプ、
クローゼット、ヒーロー、暗い、ヘルプ、ヘルプ━━━」
「気を楽に」と、アングリッチ。しゃべり出したレッドを心配して、安
心させるように、腕をつかんだ。
「病院へ行ったほうが」と、フリットクラフト。「吐かれたら困る」
「黙って運転しろ!」と、アングリッチ。
レッドの片言は小さくなって、知的になっていった。子どもが初めて
言葉を発して、組み立てようと努力しているように。うまくゆかない赤
ん坊が、人間の声と言葉を学んでゆくように。
「医者に診せた方がいい」と、フリットクラフト。
アングリッチは、警察バッジを見せ、説明した。「これは警察の仕事
で、地方検事のオフィスへ行くところだ。心配しないで走れ!」
フリットクラフトはアクセルを踏むと、ニヤリとした。
「だんな、ガレージの仲間に話したい。刑事コジャックみたいだ。本当
に刑事?」
アングリッチは黙っていた。レッドは黙らず、独自の言葉をしゃべっ
ていた。アングリッチと同じ言語だが、順番が違った。
フラットブッシュ通りに入ると、クラクションを鳴らし、すごいスピ
ードで走った。
「オレたちを殺さないでくれ!」と、アングリッチ。「レオナード通り
の地方検事オフィスまで行くだけでいい。道は分かる?」
「ええ、墓苑の近く。うしろで座っていてくれれば、ちゃんと着ける」
フリットクラフトは、早口でしゃべり、クラクションを鳴らし、赤信号
を無視した。
「もう十分だ!」と、アングリッチ。バスがぶつかりそうになって歩道
にジャンプした。
運転手は明らかにがっかりして、スピードを落とした。しかし、ブル
ックリンを抜けて、マンハッタンブリッジに近づくと、またスピードを
上げた。
「客を乗せろ、順調、嫌いなやつを乗せるな、委員会をかき回せ、歩道
のフィフィ、背後のロコ、料金を払え、私立探偵が見ている」レッドの
たどたどしい言葉は、スピードといっしょに増えた。
「マンハッタン」と、フリットクラフト。橋の中央を過ぎて誇らしそう
に。「この混雑で30分で着いた。やった!刑事コロンボやアダム12
よりいい」
チャイナタウンからシビックセンターへ抜けると、道は混んでいた。
いつもは楽しく通りを渡っていた多くの歩行者は、フリットクラフト
のキャブが迫ってくると、身をかわしてよけなければならなかった。
威厳のある婦人は怒って、みんながするように指を立てるしぐさをし
た。アングリッチは人々がなにを叫んでいるのかよく聞こえなかったが、
あまり賞賛されるようなことでないのは分かった。
フリットクラフトはブレーキを踏んだ。
◇
「ここは?」と、アングリッチの囚人。声は変わって、独断的で自信に
満ちたところがなくなった。「後ろの席で、オレはなにを?誰がオレの
キャブに防弾パーティッションを入れたのだ?」
アングリッチは驚いて、フリットクラフトに20ドル紙幣を渡した。
「チップはいらない、ダンナ」と、フリットクラフト。「こんな楽しい
ことはめったにない」
「とっとけ!」と、アングリッチ。サイモンジャッフィとして生まれ変
わった男を片手で支えて、車から降ろした。
サイモンは震えながら立っていた。オフィスで働く人々は、ビルから
出てくるとサイモンの脇をさっと通り過ぎて行った。
ふたりの男がフリットクラフトのキャブを奪い合っていた。アタッシ
ュケースを楯にして、背の高い方が先に乗り込んだ。キャブが走り出す
と、背の低い方は歩道で悪態をついた。
「安心しな、ダンナ。オレのキャブがすぐ近くにある」と、サイモン。
「今はだめだ!」と、アングリッチ。「あんたは上の階で用事がある」
アングリッチは、サイモンの腕をとるといっしょに花崗岩ベースの石
灰石のビルの中に入った。デスクにいる当直の刑事にバッジを見せると、
通り過ぎた。
「なにか覚えてるか?」と、アングリッチ。3台並んだエレベータの脇
で待っているとき、サイモンに気楽にきいた。
「雨だったと思う」と、サイモン。「ミリーがオレの大切なものを捨て
た。ぜんぶ」苦しそうな表情を浮かべた。「オレは都会へ行った。分か
らないが、別の空気が吸いたかった。雨だった。ガソリンを使い切った。
この数年間で初めて、ガソリンを使い切った。そしたら、売春婦が」
サイモンは恥ずかしそうに中断した。「オレはそうしたことをする、
その手のやからじゃない。ただ、そのときは成り行きで」
「ああ、分かる」と、アングリッチ。慰めるように。「いいやつでも、
たまにあるさ」
「女は、オレが捜している女を知っていた」と、サイモン。「さもなけ
れば、ついて行かなかった」
エレベータがひらき、おかしな車から出てくる道化役者のように、多
くの人間を吐き出した。ふたりは乗り込んで、8階のボタンを押した。
サイモンは後ろに下がった。4人乗ってきて、それぞれのボタンを押し
た。エレベータは上昇した。
サイモンは、周りの人たちのことを忘れて、落書きのある壁を見つめ
ていた。
「女は売春婦だった」と、サイモン。大声で。「女とホテルへ行った」
アングリッチは、殺人課の刑事しか見せないような、きまり悪そうな
顔をした。ほかの乗客たちは、床を見ているふりをした。
「女はオレを触り始めた」と、サイモン。「いい感じがした。今までそ
んなことはしたことなかった。売春婦ともなかった。オレはずっと、大
切なものを捨てたミリーに夢中だったんだ。売春婦はうまくコントロー
ルして支配権を持った」
6階のドアがあいて、閉まった。ボタンを押した粋な男は、降りるチ
ャンスをパスした。
「そのとき、ドアをノックする音がした」と、サイモン。「オレはクロ
ーゼットに隠れた。女は隠れるのを手伝ってくれた。もの音。びくびく
するようなもの音。暗闇。クローゼットから出たとき、静かだった。あ
とでなにが起るか分からなかった。誰もいなかった。女はオレをもてあ
そんだ」
7階のドアがあいて、閉まった。最初にボタンを押した、ふとった清
潔そうな女性は、降りないと決めて、別のボタンを押した。
「オレはちょっとおかしかったのかも」と、サイモン。耳を傾けている
5人の聴衆がいることに気づかなかった。「いろいろ歩き回っって、具
合が悪くなった。なにをすればいいのか分からなかった。行くところが
なかった。それで、クローゼットに戻った。なん日にも思えた」
サイモンは、記憶をよみがえらせようとして、空気を吐いたり吸った
りした。
「また、もの音がした。別の売春婦と男。ぽん引きがまた。叫び声。銃
声。オレは出た。みんなそこで。死んでいた」
サイモンは、目を見開いて、早口でしゃべった。「なにが起きたのか
分からなかった。血と死体があった。服が無くなった。物事がかすんで
いた。そして」
8階のドアがあいた。アングリッチはサイモンの腕をとった。「オレ
たちの階だ」やさしく言った。
ほかの乗客は、刑事と囚人が降りるのを見ていた。アングリッチはサ
イモンと長い廊下を歩いた。
「ほかにも死体があった。黒人。白人。女に男。たくさんの死体」サイ
モンは泣き出した。アングリッチはサイモンに汚れたハンカチを渡し、
サイモンはそれで目をぬぐった。
「ここに座って」と、アングリッチ。サイモンを、地方検事オフィスの
外側のソファでゆっくり休ませようとした。「すぐ戻る」
アングリッチは、室の反対側にいる制服警官に合図を送り、サイモン
を指差して、口の動きで「見ていて!」と伝えた。制服警官はうなづい
た。
アングリッチは、地方検事オフィスの中へ急いで入った。中から興奮
した彼の声と、公衆の前で話すのに慣れた男のよく通る声が聞こえた。
彼らの声は、サイモンから数歩離れたデスクで秘書がタイプする音にか
き消された。
サイモンは頭を向けて、若い女性に気づいた。涙を恥じて、アングリ
ッチのハンカチをポケットに押し込んだ。泣いてたことをなかったこと
にした。彼女は、地方検事オフィスで多くの悲しい人々を見てきたよう
に、彼に理解のある笑いを送った。
長いブロンドの髪が、体にぴったりの赤のドレスの肩の上にかかって
いた。体は、バラバラにならない程度のぎりぎりの布で覆われていたが、
内容を理解せずにタイプできる秘書のようには見えた。彼女の化粧は、
唇に豊かさを、あたたかな目に深さを付け加えていた。
彼女は、彼がみつめてるのに驚いて、また笑った。
「フィフィ?」と、彼。
「名前はフィオナ」と、秘書。ボスが男というのと同じように、芝居が
かった女の声だった。「しかしみんなが呼ぶのは、フィフィ」
アングリッチは、急いで、地方検事オフィスの中から出てきた。ダー
クグレイのスーツを着た古代ローマ貴族のような地方検事といっしょだ
った。
アングリッチがなにかがおかしいと気づいたのは、彼の囚人がイスか
ら自信たっぷりに立ち上がり、地方検事に手を差し出したときだった。
「ダイアモンド」と、レッド。「レッドダイアモンド。弁護士と話がし
たい」
エピローグ
キャブドライバーの疑い晴れる
キャブドライバーで私立探偵レッドダイアモンドとして国民的名声を
得ている、サイモンジャッフィは、州法廷で3週間にわたる裁判の末、
昨日、5件の殺人容疑で無罪を言い渡された。
ジャッフィ(43才、自分を1940年代のタフガイ私立探偵だと信
じている)は、7人の男性と5人の女性からなる陪審員の4時間にわた
る慎重な議論の末、無罪とされた。
同時に、カリフォルニア州検察は、彼が関わったとされるウェストコ
ーストの6件の殺人容疑について訴追しないと発表した。
「正義の観点から、起訴を却下する」と、ロサンジェルス地方検事フラ
ンクキャンディタ。「調査によると、レッドダイアモンドとしても知ら
れる、ジャッフィ氏には全くとがめられる点がなかった」
ジャッフィは、5件の殺人容疑で法廷に送られた。最初の事件では、
8ヶ月前、タイムズスクエアのリドホテルで、ぽん引き、売春婦、客が
銃殺死体で発見された。
警察は、その後1週間たたないうちに発生した西96番通りの2件の
殺人にもジャッフィが関わったとした。ふたりはいずれも、黒人犯罪組
織につながりがあり、ひとりのアパートで殺されているのが発見された。
ジャッフィの東西海岸からなる弁護団には、ハーバード出の憲法専門
家、ニューヨークの精神障害者専門弁護士やロサンジェルスの刑事専門
弁護士が含まれていた。
多額の弁護料を払う者の正体は不明で、事件をいっそうミステリアス
なものにしている。
ニューヨークの裁判は、地方検事ティモシーロバロに不利に進んだ。
弁護団は、公判前に提出した多くの申請によって、検察側のキーとなる
証拠や自白の提出を不可能にさせた。
自己防衛と一時的錯乱の弁護側陳述で、さらに検察は不利になった。
「私は3年間キャブドライバーをしたが、誰でも気が変になる」と、陪
審員エドワードウェイト、48才。
もうひとりの陪審員ベンジャミンドーバーはこう言った。「彼が殺し
た者は、殺されて当然だったと、みんな言っている。そして、殺される
べきでなかった者も、彼が殺したわけではない。彼は、悪い時間に悪い
場所にいただけだった」
ジャッフィのいたライカーズ島の収監施設には、何百通もの手紙が来
たという。施設や弁護士によると、内容はジャッフィを雇いたいとか結
婚したいという要望やファンレターだった。
妻のミリーは、ジャッフィの失踪後すぐに離婚手続きを済ませたが、
判決についてコメントはなかった。
裁判所は、連日、被告を応援する傍聴人でいっぱいだった。傍聴人は、
キャブドライバー、以前の近隣の友人、それにパルプ雑誌の愛読者たち
だった。
ジャッフィが、自由な人間として裁判所から出てくると、聴衆は喜ん
だ。裁判官のマーシーノートンは、法廷のモニターに微笑んだだけだっ
た。
ジャッフィは、多くの支持者たちに背中を押されたり抱擁されながら
言った。
「外は、ほんとにすばらしい。そのうちどこかで、酒のボトルを持って
ゆっくりしたい。そして、フィフィを見つけるつもりだ」
そして、付け加えた。
「ロコに通告する!レッドダイヤモンドが帰ってきたぜ!」
(終わり)