ジバゴ
原作:ボリスパステルナーク
ロバートボルト、デビットリーン
プロローグ
夕方、大勢の女工員たちが、ダムの建設現場の門から出てきた。
それを、守衛室の窓から見下ろしている将軍。
「どういった娘たちだ?」と、将軍。
「いい子ですよ」と、守衛室の青年。「ちょっとシャイですが。金を稼
ぐために、よく働く」

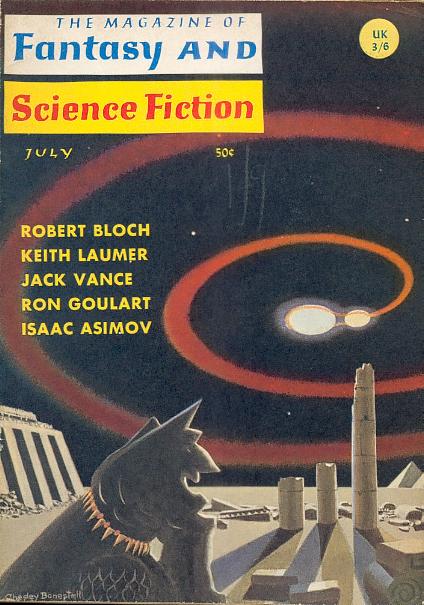
「読み書きは?」
「できると思います。施設に入っていた子が、大半ですね。こんな仕事、
重労働だ。人間は、土堀りをするためにいるんじゃない」
「そうだな」
「非効率的ですよ。掘削機を、あと2台入れれば、作業を1年短縮でき
る」
「若いものは、せっかちだな」
「あなたは、どうでした?」
「昔は、みな、そうだった。あせるな、我々は、ここまで、いそいで進
みすぎた」
「分かってます、将軍」
「その代償の大きさを知っているか?当時は食べ物もなく、雑草で飢え
をしのいだものだ」
労働者の女性たちの列が、だんだんと、守衛室に近づいてきた。
「なぜ、その少女を気にかけられるんです?」と、青年。
「弟の子かもしれん」と、将軍。
「ユーリアンドレアビッチ!」
「ああ。腹違いの兄弟だがね。もし、そうなら、ラーラの娘ということ
になる」
将軍は、自分のかばんから、弟のユーリの詩集を出して、載っている
ラーラの写真と、少女の写真を見比べていた。
「あの、ラーラの」
「そう、あのラーラだ。この詩集は、ラーラに捧げる詩集の、改定版だ
よ」将軍は、詩集を青年に見せた。
「知ってます。弟さんの詩は、とても人気がある」
「今でこそ、そうだが、当時はな」
「昔は、読むのを許されませんでした」
「そうだ」
ノックの音。少女がドア口に立っていた。
「入って」と、青年。ドアをあけて、少女を招き入れた。「わたしが呼
んだんだ。心配しなくていい」そう言うと、青年は、入れ違いに外へ出
て行った。
少女は、おそるおそる室へ入ったが、将軍の眼光におびえていた。
「私は、イエブグラフアンドレアビッチジバゴ将軍だ。人をさがしてい
る。分かるかね?さがしているのは、私の姪にあたる娘だ。座りたまえ」
将軍は、イスをひいて、少女を座らせた。少女は、持っていたバララ
イカのケースをひざの上に置いた。
「きみの名前は?」と、将軍。少女のはすむかいの席に着いた。
「トーニャコマローバです、将軍」と、少女。
「モンゴル地方にいたそうだね?」
「はい、そうです」
「そこで、なにをしていた?」
「親とはぐれてしまって」
「なぜ、はぐれたんだね?」
「忘れました」
「父親の名は、コマロフスキーか?」
「たぶん、そうだと思います」
「たぶん?」
「よくある名前なので」
「父を覚えてないのか?」
「覚えてないです」
「では、母親のことは?」
「はい、覚えてます」
「なんて、名前だ?」
「マミー」
「どんな人だ?見た目は、どんなだった?」
「大きかった」
「大きい?」
「そう見えました。わたしが、まだ、小さかったから」
将軍は、机の上に置いてある、先ほどの詩集を少女に見せた。
「読めるかね?」
「はい。ラーラ。Y・A・ジバゴ詩集?」少女は、ジバゴ将軍の顔を見
た。
「私じゃない。私の弟だ。さがしているのは、この男の娘だ」将軍は、
詩集をめくって、作者の写真を少女に見せた。
「━━━」
ページをめくると、ラーラの写真が載っていた。
「これが、母親だ」と、将軍。「ラーラ。お母さんは、ラーラと呼ばれ
ていなかったか?」
「分かりません。違うと思います」少女は、ラーラの写真を見ながら言
った。
「きれいな人━━━わたし、将軍の姪では、ありません」
「姪がほしいわけではない。子どもなら、親のことを知りたいだろうと
思ってね」将軍は、詩集を閉じて言った。
「父親が、詩人だと聞かなかったか?」
「うちの父は、詩人じゃありませんでした」
「では、職業は?」
「詩人じゃありません」
将軍は、あきらめて、立ち上がり、窓の外を見た。
「お父さんを、好きじゃなかったか?」
「忘れました」
「母親のことは、好きだったか?」
「はい、もちろん」
「ストレルニコフという名に、聞き覚えはあるか?」
少女は、首をふった。
「ベリキノは?場所だ。人の名前じゃない」
やはり、少女は、首をふった。
「グロミーコは?」
「グロミーコ?」
「そう」
よく考えて、やはり、少女は、首をふった。
「彼が、母親を亡くした時も、ちょうど、きみが母親と、はぐれた時と、
同じ年齢だ。場所も同じ、モンゴル」
少女は、将軍の言葉に、当時を思い出そうとした。
◇
モンゴルの平原。葬式の列。遠くに雪におおわれた山々。
棺おけをかつぐ人々の後ろに、まだ、幼い喪主の少年。
墓地に着いて、母親の亡がらに対面しても、涙ひとつ見せない少年。
「生けるときの虚栄は」と、神父。「すべて破壊され、魂は、肉体より
消え去り、残されたからだは、墓苑のなか。しずかに、土に帰る。哀れ
み深き救い主よ。主のしもべの魂を、やすらかに、眠らせたまえ」
棺おけは、閉じられて、墓に埋められた。
「ユーリ」と、呼ぶ声にうながされて、少年は、手に持っていた花束を
墓に捧げた。叔父夫婦と従妹とともに、少年は、墓地をあとにした。
◇
少年は、叔父夫婦とともに、家に戻り、ベッドについていた。
「いっしょに食事をどうぞ、グロミーコ婦人」と、少年に付き添ってき
た神父。
「ありがとう、神父さま」と、グロミーコ婦人。神父が、室をあとにす
ると、少年に話しかけた。
「横になりなさい、ユーリ。お母さんとわたしは、とっても仲良しだっ
たの。これから、わたしが、お母さん代わりよ」
「ありがとう」と、ユーリ。
ドアがあく音がした。バラライカを持った叔父が立っていた。
「母さんのだ」と、ユーリ。
「おまえのものだよ」と、叔父。
「お母さんが、ユーリに残したの」と、叔母。
「遺書で?」と、ユーリ。
「おまえ、遺書って知っているのか?」と、叔父。バラライカをベッド
まで持ってきて、言った。
「お金」と、ユーリ。
「ユーリには、これだけよ」と、叔母。「あとは、お父さんが」
ボロンと、ユーリがバラライカをはじいた。
「弾けるの?」と、叔母。ユーリは、首をふった。
「この辺の者なら、みんな弾けるんじゃないのか?」と、叔父。
「叔父さん、この辺の人じゃないの?」
「うちは、モスクワなの。ここから遠いけど、きっと、好きになるわ」
と、叔母。「そうよね?」
「まぁな。時間がたてば、慣れるものだよ」と、叔父。
「母さんは、弾けたんだ」
「ええ。お母さんは、バラライカの名人だったわ。この小さな楽器ひと
つで、ギター2本分くらいの音色を出した。才能があったのよ」
「おまえも、受け継いでいるかもしれんな。習ってみるか?」
「ボク、弾けないよ!」と、ユーリ。
叔父夫婦は、顔を見合わせた。
「トーニャ、ユーリにおやすみを言って」と、叔母。「今日から、兄弟
よ」
トーニャは、ユーリの枕元に行って、おやすみの頬すりをかわした。
「おやすみ、ユーリ」と、叔母。
「ゆっくり、お休み」と、叔父。バラライカを、棚の上に片付けて、ろ
うそく立てを持って、室を出て行った。
「おやすみ」と、ユーリ。ベッドで、窓を風で小枝がたたく音が気にな
って、なかなか眠れなかった。母親が弾くバラライカのメロディが聞こ
えた。窓からのぞくと、外は雪が舞い、風が音を立てて吹きあれていた。
1
「グロミーコ一家は」と、ジバゴ将軍。少女に、両親の物語を語って
いた。「ユーリの才能をはかりかねたが、彼は、医学を学ぶかたわら、
詩人としても、名をあげた。彼にとって、詩は、天職とも言えたが、生
活の糧は必要だった」
医学生のユーリは、医学校の教室で、顕微鏡でウィルスを覗いていた。
「美しいだろ」と、ユーリに医学を教える、ボリスカート教授。
「ええ」と、ユーリ。教授に顕微鏡を見せた。
「おお、美しいのはウィルスの特権だな」と、教授。顕微鏡をのぞいて
から、言った。
「来年の予定は、ジバゴ?」
「一般医療の方に進もうかと」と、ユーリ。
「研究職は、どうだ?おもしろいし、大切な分野だぞ」と、教授。
「でも、一般医療に」
「現場で、命と取り組みたいかね。この美しいウィルスが、どんな悪さ
をするか、見られるぞ」教授は、ウィルスのプレパラートを顕微鏡から
はずして、机の上に無造作に置いた。
◇
外は晴れていたが、路面は雪が積もっていた。路面電車が発車したと
ころへ、ユーリが走ってきた。ユーリは、しかたなく、路面電車を追い
かけて、あいているドアから、飛び乗った。電車には、ラーラが乗って
いて、ユーリは、知らずにラーラの後ろの席につくと、窓の外を走る子
どもをふたりで目で追った。降りようとして席を立ったラーラと、別の
女性に通路を譲ろうとして立ち上がったユーリの背中が、オーバーコー
ト越しに触れると、路面電車の架線が激しく火花を上げた。
ラーラは、路面電車を降りると、家路を急いだ。通行人が多い場所に
来ると、ビラを配っている青年がいた。その青年のもとに、ふたりの男
が近づいた。
「名前は?」と、男のひとり。
「アンティポフ」と、ビラを配っていた青年。
「住所は?」
「ペトロフカ15番地」
「これは、預かる」と、青年から、ビラを没収しようとした。
「警察署長の許可を得ている」と、青年。ビラから手を離さなかった。
「え?警察で、そう言え」と、男。ビラを強引に奪った。
「いつ?」
「なんなら、今からゆくか?」
「いいとも」と、青年。
「パーシャ」と、ラーラが青年に気がついてやってきた。「兄がなにか
?」
「うちに連れて帰るんだな」と、男。「めんどうにならんうちに」
ラーラは、青年の腕をとって、男たちから離れていった。しかし、青
年は、オーバーコートのポケットから、また、別のビラを取り出して、
人々に配り始めた。
「パーシャ、やめて!」と、ラーラ。
「やらなきゃいけない」と、パーシャ。
「なんのためにやらなきゃいけないの?」
「民衆のため、革命のためさ」
「みんな、革命なんて、望んでいないわ」
「のぞんでいるさ。自分で気づいていないだけさ」
「分けてくれ、同志」と、知りありの男性が、パーシャに声をかけた。
パーシャは、ビラを半分、手渡した。
「パーシャ、あなた、ボリシェビキなの?」と、ラーラ。
「いや、ぼくは、ボリシェビキとは、そりが合わない。やつらは、なに
も分かっちゃいない」
「パーシャ、あなたって、手厳しいのね」
パーシャは、人々の列から離れると、ラーラに訊いた。
「なぜ、ぼくのことを、兄だと言った?」
「ほかになんと言うの?」と、ラーラ。
「ほかにもあるだろ。婚約者とか」
「パーシャったら、バカ言わないで」
向かいの家の前に馬車が止まって、御者が脇に立って、馬車の上で犬
がほえていた。
「コマロフスキーさんが、また、母の店に来ているわ」と、ラーラ。
「また、うわさになるわね」
「体制が悪いんだよ」と、パーシャ。「革命をすれば、人々も変わる」
ラーラは、ビラを1枚もらって、家の建物に入ろうとした。
「きみも来て」と、パーシャ。ビラにあるデモのことだった。
「それは、ムリ。試験勉強しなきゃ。わたし、奨学金がほしいのよ」と
言って、ラーラは、建物へ入って行った。
◇
ユーリは、家に戻ると、すぐに、2階へ上がった。
「ただいま、叔母さん」ユーリは、叔母にあいさつした。
「手紙が来ているわ」と、叔母。「パリから」
「へぇ」と、ユーリ。「きれいな字だ」
「来月、戻ってくるんですって」
「トーニャが!待ち遠しいな!」ユーリは、手紙をもって自分の室へ行
った。
◇
ラーラの母の洋装店。ラーラの母が、お客の女性のドレスの着付けを
手伝っていた。
「顔が広い方なんですよ」と、ラーラの母。
「それに、とても、かっぷくがいいし」と、お客の女性。
そこへ、ラーラが帰ってきた。
「ただいま」と、ラーラ。「マダム」と、お客の女性に一礼した。女性
は、「ラーラ」と答えた。
「勉強は、そこでね。コマロフスキーさんがいらしているから」
「はい、ママ」
ラーラが、お針子さんが仕事をしている仕立て室を抜けて、奥の室へ
ノックして入ると、コマロフスキーが、長いすでくつろいで、新聞を読
んでいた。
「お帰りラーラ」と、コマロフスキー。
「いらっしゃい」と、ラーラ。
◇
洋装店のドレスルーム。
「お偉方の相談もしているのよね」と、お客の女性。
「そうですってね」と、ラーラの母。
「政府にも、コネがあるんでしょう?」
「さぁ、それはどうかしら?」
「相談料、お高いんでしょう?」
「コマロフスキーさんは、亡き夫の友人なので、ご好意で助言してくだ
さるの」
「あら、そうなの?」
ラーラの母は、お客の手袋を渡すと、店のドアをあけて、見送った。
店の鍵を掛け、店じまいして、奥へ戻った。
◇
洋装店の仕立て室で、ひとり試験勉強しているラーラ。外は雪が降っ
ていた。奥のドアがあく音がして、声が聞こえてきた。
「じゃ、また、来る。火曜日に」と、コマロフスキー。歩いてきて、ラ
ーラが勉強している机のところで立ち止まった。どんな本なのかめくっ
ていて、ビラを見つけて、問いただした。
「どこでもらった?」
「友だちがくれたんです」と、ラーラ。
「平和的デモなんて、行くんじゃないぞ」と、コマロフスキー。
「はい」と、ラーラ。
「平和的なんて、大きな間違いだ。友だちにも、よく忠告しておけ。バ
カはするなと」
「分かりました」と、ラーラ。鍵束をもって、ドア口まで、コマロフス
キーを見送りに行った。
「いくつになった?」洋装店のドアまで来ると、訊いた。
「17です」と、ラーラ。
コマロフスキーは、洋装店の茶のベールを1枚とって、ラーラにかぶ
せた。口元も茶のベールでおおうと、ラーラの美しさがきわ立った。コ
マロフスキーは、ボーッとしているラーラから、鍵束を奪うと、自分で
ドアをあけて、帰っていった。
◇
ラーラの母の洋装店の奥の室。長いすに座って、体温計をくわえてい
るラーラの母。コマロフスキーとラーラが心配そうに見ている。
「39度」と、ラーラ。コマロフスキーから渡された体温計の目盛りを
読んだ。
「そんな!楽しみにしてたのに」と、母。
「あ〜あ」と、コマロフスキー。懐中時計を出して、時間を気にしてい
た。
「しかたないわね。あきらめるわ」と、母。「ラーラだけでも連れてっ
てくださる?だって、この子、初めての夜会だし、ハックション、ゴホ
ッ、ゴホッ」
「今日は、やめた方がいいだろう」と、コマロフスキー。
「残って看病するわ」と、ラーラ。
「ママは、ひとりでも大丈夫よ。行ってちょうだい。こんな機会は、め
ったにないんだもの。上流社会の集まりに、ごいっしょできるなんて」
「分かった。コートを取っておいで」と、コマロフスキー。ラーラに言
った。「時間がないから、クロパトキン通りは、避けよう」
◇
クロパトキン通りでは、広い通りいっぱいに人々が隊列をなし、横断
幕を掲げて、平和的デモ行進を行っていた。なん人もの警官がデモ隊を
監視していた。
ユーリは、テラスに出て、叔母といっしょに、デモ行進を、もの珍し
そうに見学していた。
「同胞愛と自由。すばらしい言葉だわね」と、叔母。「正義、平等と日
々の糧。いい言葉だと、思わない?」
「思いますね」と、ユーリ。
「同胞愛と自由」
「同胞愛でもなんでもいいが、凍えてしまうじゃないか」と、叔父。テ
ラスに出てきて、叔母の手を取った。「さぁさぁ、中へ入ろう。早く」
◇
夜会に着いた、コマロフスキーとラーラ。
「お待ちしておりました」と、夜会の給仕の男性。コマロフスキーが連
れてきたラーラを見ていた。
「姪だ」と、コマロフスキー。
「どうぞ、お嬢様」と、給仕の男性。
「行こう」と、コマロフスキー。給仕に誘導されて、テーブルについた。
夜会は、夕食を楽しむ人々で大賑わいで、中央にダンスを楽しむスペー
スもあった。渡されたメニューは、分厚くて、ラーラにはなんのことだ
か分からなかった。
「フォアドボーガスコーニュは?」と、コマロフスキー。
「おすすめでございます」と、給仕。
「マスタードは、ひかえてくれ」
「かしこまりました」
「ジャンボファルシアンクルート」と、ラーラ。
「ウィ、マドモアゼル。ワインは、いかがなさいますか?」
「軽いのをもらおう」と、コマロフスキー。
「ウィ、ムッシュ」給仕は、メニューを下げて、戻っていった。
「とっても高いお店なんでしょう、コマロフスキーさん」と、ラーラ。
「高いね。ビクターと呼んでくれないか」
「フフフ、呼べない」
コマロフスキーは、立ち上がって、ラーラをダンスフロアに誘った。
ワルツを1曲踊って、テーブル席にもどった。
「ドレスは、母が作ったの」と、ラーラ。
「きれいだ」と、コマロフスキー。
「器用な人でしょ?」
「お母さん?ああ、いい人だし」
その時、演奏がやんだ静けさに、外で合唱する人々の声が聞こえてき
た。その歌声に、みんな食事をやめて、とまどいの表情を見せた。
「革命までには、歌もうまくなるだろう」と、コマロフスキー。みんな、
拍手喝采した。そして、ふたたび、軽快な演奏が始まった。ラーラとコ
マロフスキーは、ワインやワルツを楽しみ、雪道を、御者の操る馬車で
帰っていった。
その直後、待機していた騎兵隊が出動し、平和的デモ隊の進路をふさ
ぐ形で、対峙した。先頭でデモ隊を指揮していたパーシャは、逃げまど
うデモ隊をどうしようもできなかった。誰かが落とした拳銃を、パーシ
ャは、逃げる途中で拾った。テラスに出てきていたユーリは、刀剣をふ
りかざす騎兵隊を見ていた。叔父も、コートを寝巻きの上にはおって、
テラスに出てきた。
「なんだね、なんだね?」と、叔父。「これは」
ユーリは、なにも言わずに下へ降りて、雪道に横たわる、負傷者を助
けに出てきた。雪道は、鮮血が飛び散っていた。
◇
コマロフスキーの家の前。
「おやすみ、ラーラ」と、コマロフスキー。馬車から降りた。
「おやすみなさい」と、ラーラ。そして、言い直した。「おやすみ、ビ
クター」
ラーラは、馬車に乗ったまま、家に向かった。
◇
雪道のデモ隊の死亡者が、リヤカーに積まれていた。
「家に戻りたまえ」と、警官。「ケガ人は、こちらで、めんどうをみる」
ユーリは、足を怪我した女性に包帯を巻いていた。
「帰りなさい」と、馬に乗った警官。「ケガ人の手当ては、われわれが
おこなう。家に入ってなさい」
「家に戻ってください」と、別の馬に乗った警官が、ユーリの元へ来た。
ユーリは、立ち上がってなにか言おうとしたが、叔父に止められた。
「ユーリ、戻れ!」と、叔父。「もめるんじゃない」
「連れて行ってください。でないと、逮捕します」と、警官。
「ユーリ、頼む。あしたは、トーニャが帰ってくるんだ」
足を怪我した女性は、警官ふたりに運ばれて行った。
家のドアまで戻ったユーリが、振り返ると、デモ隊の死者やケガ人は、
すべて運ばれて行った。
◇
母の洋装店に戻ったラーラ。鏡を見ながら、白いレースをかぶった自
分の顔を見ていた。
◇
翌朝、駅のホームに列車が入ってきた。
窓から身を乗り出して、手を振る女性。「ユーリ!」
「トーニャ!」と、ホームにいたユーリも、手を振って、列車を追った。
「ユーリ」と、列車から降りたトーニャ。
「おかえり」と、ユーリ。抱擁で出迎えた。
「パパ」と、トーニャは、父をみつけて駆け寄ると抱き合った。
「さぁ、行こう。むこうで、待ってるぞ、母さんが」と、父。
「ママ」と、トーニャは、ベンチにいる母をみつけて駆け寄ると抱き合
った。
「ママ、からだは、どう?」
「ママ?とっても元気よ!」と、母。「まわって、見せて!」トーニャ
は、まわって、ピンクの帽子にピンクのオーバーコート姿を見せた。
「さすが、パリ仕込みね!」
ユーリが、トーニャの荷物を運ぶ二人の駅員といっしょに歩いてきた。
「ほ〜、すごいな」と、父。
「ユーリもりっぱになったでしょ?」と、母。
「さぁ、行こうか」と、父。母を手助けして立たせようとした。
「ふたりは、先に行って!」と、母。ユーリは、トーニャといっしょに、
歩き出した。
「そうだ、これ、あなたに」と、トーニャ。「ロシアの若手詩人の記事
よ」新聞を、ユーリに見せた。
「ほんと?ありがとう。ぼくのこと、載ってる?」
「トップで、大絶賛よ」
「ハッハ!フランス人は、見る目があるね!」と、ユーリ。
「あんなに顔を寄せ合って」と、母。ふたりのうしろから、父に支えら
れて歩いていた。
「あれは、新聞を読んでいるんだ」と、父。
「お似合いじゃないこと?」
「やめなさい!結婚は、天のご意志で決まるものだ」
◇
誰もいない母の洋装店。ラーラは、ドアへ向かって歩いていた。
ドアの前に誰かいることに気づいて、驚いて、立ち止まった。
「だれ?ビクター?」
「パーシャだ。話したいことがある」
「だめよ、パーシャ」
「大事な話だ」
「わかったわ」ラーラは、ドアの鍵をあけた。
「ああ、パーシャ!どうしたの、その傷?」
パーシャは、顔の左頬を深く刀剣で切り裂かれていた。
「やられたんだ。騎兵隊に」
「ああ、かわいそうに!入って、パーシャ」
ラーラは、パーシャを抱きかかえるようにして、店へ入れた。
「お母さんは?」
「むこうよ」
パーシャは、店の長いすにすわると、メガネをとった。
「パーシャ、ひどい傷だわ」
「消毒液あるか?」
「ええ」
「くれ!」
パーシャは、棚にあった消毒液を、鏡の前で、傷口に直接、流しこむ
と、激痛に倒れこんでしまった。
「パーシャ、だいじょうぶ?」タオルで傷口にあてて、抱き起こした。
「パーシャ、病院にいかないとだめよ」
「だめだ。身を隠さなきゃ。頼みを聞いてくれ」
「いいわ、なに?」
「これを、隠して」
パーシャは、デモの混乱の中で拾った拳銃を手渡そうとした。
「こんなもの捨てて!」と、ラーラ。
「だめだ」と、パーシャ。「平和的デモは、もう、終わりだ。やつらは、
女や子どもまで、踏みつけにした。みんな、飢えてパンを求めているの
に、太ったブタどもは、たらふく食い、酒を飲み、歌い踊っている。預
かってくれ!」
ラーラは、自分のことを言われているように感じて、銃を受け取った。
「ありがとう、同志」
「やめて、わたしは、同志じゃないわ」
そのとき、「ラーラ」と、奥で母が呼ぶ声がした。ラーラは、いそい
で、銃をソファーの下に隠した。
「なぁに?」
「だれか、来ているの?」と、母が心配して出てきた。
「パーシャよ」
「そう。夕べは、ずいぶん、遅かったのね」
「楽しさに、時間を忘れて」
「そう。教会に行くの?」母は、ラーラが聖書を持っているのに気づい
て、聞いた。
「ええ」と、ラーラ。母は、奥の室に戻ろうとして、不審そうにラーラ
を振り返って見た。
◇
ラーラは、教会で、神父に告解をしていた。
「不貞をはたらいた女に、主は、なんと言われた?」と、神父。
「主は、2度と罪を犯すな、と」
「犯したのか?」
「分かりません」
「誰にも分からん。肉欲とは、強いものだ。結婚を誓ったものだけに、
許される」
それだけ聞くと、ラーラは雪道を家に戻っていった。雪ソリがシャン
シャンと音をたてて、追い越していった。
◇
高級ホテルの庭園を抜けて、階段を駆け上って、一室に入ろうとする
コマロフスキー。
「ああ、ムッシュ」と、呼び止めたのは、給仕の老人。「今日は、6号
室をお使いください。こちらには、さるお方が」
コマロフスキーが、別室のドアをあけると、そこには、真っ赤なドレ
スに身を包んだ、ラーラがいすに座って待っていた。コマロフスキーが
入ると、立ち上がった。
「遅れて、すまん」と、コマロフスキー。
「1時間も待たされたわ」と、ラーラ。
「注文はしたのか?」
「まだ」
「なぁんだ、すればいいのに」
コマロフスキーは、ソファーにすわり、ラーラにまわってドレスを見
せるよう、手で合図した。
「あなたが、選んだのよ」と、ラーラ。
コマロフスキーは、隣にすわるよう、ソファーを軽くたたいた。
ラーラが座ると、話しかけた。
「もう、りっぱなおとなだな」
「ええ」
「母さんになんて、言ってきた?」
「いじわるね」
「ああ、吸ってもいい?」コマロフスキーは、葉巻を吸おうと立ち上が
った。
「どうぞ」
ろうそくの火で、葉巻に火をつけた。
「好きだろう、このにおい、葉巻のけむり。ほら、カンパイ!」
ラーラは、コマロフスキーが差し出したワイングラスを受け取って、
乾杯に応じた。
「カンパイ!」
「ぐっと飲んで」と、コマロフスキー。ラーラのグラスを傾けて、無理
やり飲まそうとした。「ぐっと、ぐっと、ほら、ぐっと、そうそうそう」
ラーラは、グラス半分のワインを飲んだ。
「行き先を知っているのか、お母さんは?」
「聞かれなかったの」
「気づいているんだ」
「それは、ないわ」
「知ってるのに、気づかぬふりをしているだけだ。おまえも、母親似」
「やめて、ビクター!」
「なにを」
「苦しめないで」
「苦しむ?はっはっは、おまえも偽善者だな」
ラーラは、おこって、手袋をした手で、コマロフスキーの頬をぶって、
立ち上がった。
「わたし、帰ります」
「好きにしろ!どうせ、また、戻ってくる」
ラーラは、ドアの脇で、掛かっていたオーバーコートを着た。コマロ
フスキーが近づいてきて、言った。
「帰るんじゃない。いてくれ!」
ラーラは、あきらめた顔をして、オーバーコートを脱がされるにまか
せた。
◇
数日後の夜。ラーラの母の洋装店の外は、雪が降っていた。ガラス越
しに、ラーラの母が、ベッドで苦しむ様子が見え、コマロフスキーが、
なにやら大急ぎでメモ書きを、御者に渡そうとしていた。
「起きろ!いいか、この手紙を大急ぎで届けろ、ボリスカート教授だ!
急げ!行け!」
御者は、すぐに馬車を出した。「ボリスカート教授だ!」
◇
ユーリの家の2階のサロンでは、人々がピアノの演奏を聴いていた。
その中に、ボリスカート教授とその妻の姿があった。
「ボリス、彼は、天才よ」と、教授の妻。
「ラフマニノフかと思ったよ。一服してくる」と、教授は席を立った。
教授があいているドアを抜けて、廊下に出ると、階段のところで、く
つろいでピアノを聞いている、ユーリとトーニャを見かけて、声を掛け
た。
「一般医療の方は、どうかね?」
「いえ、試験が心配で」と、ユーリ。
「うん、心配はいるまい。一般医療の妻では、どうだね?」と、教授は、
トーニャに。
「なりたいんですけど、どこからも、申し込みがなくて」と、トーニャ。
「そうか。草原の男は、情熱的かと。だが、一般医療の先生は、奥手ら
しい。病理学者は、どうかね?」
「詩も書きます?」
「書かんな」
「じゃぁ、問題外ですわ」
玄関の呼び鈴が鳴り、「失礼」と、トーニャは、玄関へ降りていった。
「いいお嬢さんじゃないか、ジバゴ」と、教授。
「ぼくも、そう思います」と、ユーリ。「先生に、だ!」
トーニャは、受け取った手紙をかざしていた。
ボリスカート教授は、渡された手紙をすぐにひらいて読むと、言った。
「詩人くん、一般医療を見に、いっしょに行くかね?」
◇
ラーラの母の洋装店。コマロフスキーがドアをあけると、ユーリとい
っしょに、教授が入ってきた。
「ああ、ボリス教授。すまん、たいへんなんだ」と、コマロフスキー。
「ああ、分かっておる」と、教授。「助手だ」と、ユーリを紹介した。
「よろしく」と、コマロフスキー。
「で、患者は?」と、教授。
「こっちだ」コマロフスキーは、ふたりを、奥に案内した。
「いつからだ」と、教授。患者の容態を見ていた。
「今夜、8時ごろ」
「なにを飲んだ?」教授は、懐中時計を見ながら、訊いた。
コマロフスキーは、棚に置いてあった空のビンを見せた。
「なぜ、かかりつけの医者を呼ばん?」
「まずいんだ」
「そうだろうとも!」
教授とユーリは、コートを脱いで、患者の医療を始めた。
「ユーリ、患者の向きを変えろ!そうだ!水!」
教授は、水さしの中に、液体の薬剤を入れた。「頭を!さぁ、しっか
り!さぁ、ユーリ、急げ!早くしろ!」
「すいません」と、ユーリ。
「そうだよ、そう、そう。そう、そう。大丈夫だよ。そう、そう」
一時間後。教授は、体温計を見た。
「助かるのか?」と、コマロフスキー。
「水を」と、教授。コマロフスキーは、水さしを持って、水をくみに出
て行った。
「助かるんでしょう?」と、ユーリ。
「ああ〜しかし、おかしなものだ。あれだけの地位があって、政府にも、
改革派にも、顔がきく男が、こんなスキャンダルで、危険にさらされる」
ベッドに上半身裸で、うつぶせに横たわって、荒い息をしていたのは、
ラーラの母だった。
「こんな現実は、詩人には、見られん。医者ならではだ。これが、人間
の本性だよ」
「それでも、この人は、美しく見えます」と、ユーリ。
「きみも、なかなか手ごわいな」
コマロフスキーが、水を持って戻ってきた。
「ラーラ、ラーラ」と、ラーラの母。
「娘だ」と、コマロフスキー。「こんなことになったのも、娘がからん
でいるんだ」
「母親と娘とはな」と、教授。水さしから、洗面器に水を移した。「娘
は知っているのか?」
「知っている」
「うちにいるか?」
「ああ」
「じゃぁ、助かると、伝えてやれ」コマロフスキーは喜んで向かおうと
した。
「待て、ビクター」教授は、ユーリに合図した。
「伝えてきます」と、ユーリが室を出ていった。
「病院には、なんて言う?」
「言わなきゃだめか?」
「入院させるには、なにか理由がなけりゃな」
「なんとか、うまく頼む」
◇
洋装店の、暗い仕立て室を歩くユーリ。長い貨車の列車の音が響いて
いた。ラーラの曲が聞こえ、机の上には、ラーラが勉強していたノート
や万年筆があった。暗がりで籐のイスで眠っているラーラの手だけ見え
たのは、向かいの奥の室の窓だった。そこへ、ろうそくをかざして入っ
てきたのは、コマロフスキーだった。ラーラは、母が助かる知らせを聞
いて、コマロフスキーに抱きついた。ふたりは、暗い仕立て室にいるユ
ーリには気づかなかった。ドアをあけて、室を出ようとするコマロフス
キーは、ユーリに気づいて、こちらを見た。ユーリは、黙ったまま、ラ
ーラがまた籐のイスに座りこんで泣いている様子を見ていた。
◇
「あの助手の名前は?」と、コマロフスキー。戻ってくると、教授に訊
いた。
「ジバゴだ」
「アンドレアビッチ?」
「ああ、そうだが、知っているのか?」
「彼の父親を、ちょっとな」
「そうか」教授は、オーバーコートを着て、玄関に向かった。
◇
馬車で戻ってゆく教授とユーリ。
「今夜のうちに、入院できるよう、取り計らうよ」
「彼の名前は?」
「コマロフスキーだ。きみを知っていたぞ」
「父の遺言を執行した人です」
「おお」
「叔父が却下しましたが。コマロフスキーが言うには、父の微々たる遺
産は、彼の所有になるのだと」
「商売のうまいやつだ。だが、あくどいやつじゃない。つきあいはいい
し、世渡りもうまい。今夜は、肝を冷やしただろう」
◇
昼間の場末の食堂。ラーラとコマロフスキーがテーブルについていた。
給仕が運んできたグラスワインの飲み口を、コマロフスキーはふいてい
た。
「こんなお店でごめんなさい、ビクター」と、ラーラ。
「思い出すよ、若いころをね」コマロフスキーは、ワインをひと口飲ん
だ。
「また、病院に行ったの」
「また?」
「母が、あなたにあやまって、と。疑ったこと」
「ほんとのことを言ってもいいんだぞ」
その時、食堂の戸があいて、パーシャが入ってきた。
「あいつか?」と、コマロフスキー。
「ええ」と、ラーラ。
「われわれのことは?」
「知らないわ!」
ラーラは、立ち上がってパーシャの腕をとって、紹介した。
「パーシャ、こちらは、コマロフスキーさんよ」
コマロフスキーは、立ち上がって、パーシャと握手した。
「かけて!」と、コマロフスキー。3人は席についた。
「食事は?」
「けっこうです」と、パーシャ。
「余計なお世話だと思わずに、聞いてほしいのだが」
「思いません」
「私は、ラーラの母親の相談役を勤めている。ラーラの将来を気にかけ
ている」
「言っておかねばならないことがあります」と、パーシャ。「ぼくは、
革命にかかわっています。なにより、このラーラよりも、革命を優先し
ます」パーシャは、ラーラの手を握った。
「私はだな、きみらの思想に関心はない。心情的には、理解できないわ
けでもない。その筋の知り合いも、数多くいるしね。飯の種はあるのか
?」
「教師の口があります」
「どこで?」
「グラドフです。ウラルの」
「あそこか。なにもないとこだ」
「でも、とても、きれいなところだわ」と、ラーラ。
「静かに暮らすにはいいがな」
「それでいいの」
「立ち入ったことをきくが、給料は十分なのか?」
「食べてはいけます」
「私の印象を、正直に言わせてもらえば、きみたちは、まだ、若すぎる
!」
「お言葉ですが、人間は、年さえとれば、よくなるとでも言うんですか
?」
「忍耐強くなる」
「汚れた自分自身に耐えるからでしょ。年をとってから結婚すると、い
いことがありますか?」
「いろいろ経験を積める」
「ぼくは、26です。母は、ぼくが8つの時に死に、父は獄死しました。
自分で自分を養い、苦労して大学を出ました。あなたが想像もできない
生活を体験してきて」
「それもある意味、人生経験ではあるがな」
「色恋の経験のことをおっしゃっているなら、ふたりともありません。
ラーラは、まだ、17才ですし。あなたは、笑うかもしれませんが、ぼ
くたちは真剣です。来年、結婚するつもりです」それだけ言うと、パー
シャは立ち上がった。
「づけづけ言いましたが、お気を悪くなさらずに」
「いや、感心したよ」
パーシャは、ラーラの額にあいさつして、一礼して出て行った。
「若き戦士か」と、コマロフスキー。
「いい人よ」と、ラーラ。
「いい若者だ。見ればわかる」
「あなたは、心の広い方だわ」
「ラーラ、話がある」
◇
洋装店に戻ってきたラーラとコマロフスキー。
「コマロフスキーさん」と、ラーラ。
「頼むから、そのコマロフスキーさんなんて、他人行儀な呼び方は、や
めてくれ!おまえと私の仲で、それは、ないだろう!ラーラ、お前が不
幸になる前に、救ってあげたいんだ。男には、2種類しかない。ひとつ
は、あの青年のように、理想が高く、純粋な男。世間は、そういうやつ
を、ほめそやすが、腹の底では、さげすんでいる。あの手の男は、他人
を幸せにはできん。とくに、女はな。分かるか?」
「いいえ」
「分かるはずだ。もう1種類は、純粋ではないが、現実を生きている人
間だ。おまえの年なら、若い男に引かれるのは、無理がないと、思うが、
あの男と結婚すれば、不幸は目に見えている。女にも2種類いるからだ」
それを聞いて、ラーラは聞くまいと両手で耳をふさいだ。コマロフス
キーは、ラーラの両手をつかんで、聞こえるようにして、言った。
「女にも2種類いる。そして、おまえは、清純な女じゃない」
ラーラは、おこって、手袋の手でコマロフスキーの頬をはたいたが、
今度は、コマロフスキーにも反撃されて、自分の頬をはたかれた。
「おまえは、尻軽女だ」
「そんなことないわ!」
「ためすか?」
ラーラは、危険を感じて、逃げようとしたが、コマロフスキーにつか
まって、ベッドにほうり投げられた。必死に抵抗するが、ラーラの腕か
らは、抵抗する力が抜けていった。
しばらくして、ドアへ歩くコマロフスキー。
「無理やりだったとは、言わせないぞ。お互い、楽しんだはずだ」そう
いい残すと、ドアをあけて出て行った。
ドアのすりガラス越しに、ラーラは、コマロフスキーが去る様子を見
ていた。悔しい思いに、荒い息をしていたが、急に、目を見開いた。前
に、拳銃をソファに隠したことを思い出したのだ。
◇
コマロフスキーの玄関の前。雪道を歩いてきたラーラが、呼び鈴を鳴
らした。拳銃は、毛皮のコートの腕のあたりに隠した。ドアがあいて、
執事が現われた。
「だんな様は、お留守でございます」と、執事。
「いないの?」と、ラーラ。
「スベンティスキー家のクリスマスパーティに、おいでです」
ラーラは、雪道を走り出した。
「行かれるんですか?」と、執事。「わたしがお教えしたことは、内密
に!」
「言わないわ。ありがとう」と、振り返ったラーラ。
「メリークリスマス、ミスラーラ!」と、執事。
◇
スベンティスキー家のクリスマスパーティ。トーニャといっしょにユ
ーリが、知り合いにあいさつしていた。
「メリークリスマス!」
ふたりで歩いてゆくと、コマロフスキーが柱のところに立っていた。
「メリークリスマス、ユーリ」と、コマロフスキー。トーニャにも、一
礼した。
コマロフスキーは、すぐに、別のブリッジのテーブルに向かった。
◇
雪道をいそぐラーラ。腕は、毛皮のコートに隠していた。疲れて、シ
ョーウィンドウの前の手すりにもたれていると、偶然、通りかかったパ
ーシャに呼び止められた。
「ラーラ!」と、パーシャ。「どうしたんだ?」
ラーラは、なにも答えずに、早足で歩き出した。パーシャに腕をとっ
て止められた。
「今夜、会う約束だったろ?どこへ、行くんだ?」
「手紙を見てないの?室に置いたのに」と、ラーラ。
「今から帰るところだ」
ラーラは、また、歩き出した。
「どこに行くんだ?教えてくれ。手紙になにを書いた?」パーシャは、
ラーラを強引に振り返らせて訊いた
「なにを書いたんだ?まさか、ぼくと、別れると」
「手紙に書いたわ」
「なにをだ!」
「全部よ!離して!」ラーラは、パーシャの手をふりほどいて、歩き出
した。雪ソリをよけて、通りの角を曲がって行った。
パーシャは、それを見送っていたが、あとを、追うことにした。角ま
で来たが、ラーラの姿は消えていた。ボーイたちは、建物のドアを閉め
て、クリスマスの夜会を始めるために、中へ入っていった。パーシャは、
立ち止まって、建物の2階で、人々が騒ぐ様子を見ていた。2階の電気
が突然消され、人々が歓声をあげた。
ラーラは、毛皮のコートのまま、夜会に紛れ込んで、柱の影に隠れて
いた。また、電気がつくと、歩きだした。トーニャは、ラーラを見て不
審に思った。しかし、ユーリにダンスに誘われると、笑顔で応じた。
「ユーリ、今、とても、きれいな人がいたのよ」と、トーニャ。ユーリ
とワルツを踊っていた。
「ぼくが、踊っている相手だろ?」と、ユーリ。
ブリッジのテーブルで、あがりの手を見せるコマロフスキー。
「今日は、ついてるな、ビクター」と、隣の紳士。
「勝ちまくるそ」と、コマロフスキー。
「みなさま、どうか、お聞きになって」と、パーティの主催者の女性。
「お静かに。今日は、とても嬉しいお知らせがありますの。ふふふ」主
催者の女性は、ユーリとトーニャの手をとった。
「そんな、奥様」と、トーニャ。
「かまいませんよ」と、ユーリ。
「じゃぁ、発表しますわ。ドクターユーリジバゴが、なんと、お医者様
の試験に3位で合格しましたの」一同、拍手で喝采した。
「待って!まだ、あるんですのよ」と、主催者の女性。「ドクターユー
リジバゴは、このたび、ご婚約━━━」
そのとき、銃声が響いた。ブリッジのテーブルの前で、ラーラは、銃
の引き金を引いていた。
全員が、振り返ってラーラの近くにやってきた。コマロフスキーは、
ブリッジのテーブルから立ち上がった。左手から出血しているのに気づ
いて、また、すわりこんだ。悲鳴が聞こえ、ラーラは、ボーイの男性ら
に両脇を取り押さえられた。
「おい、ビクター、大丈夫か?」と、ボリスカート教授。コマロフスキ
ーを抱きかかえるようにした。
「連れ出せ」と、コマロフスキー。
「なに?」と、教授。
「女をはやく、外に出せ!」
「あ、分かった、警察を呼ぶ」
「いや、呼ぶな!」と、コマロフスキーは、叫んで、立ち上がった。ラ
ーラは、まだ、近くで取り押さえられたまま、こちらを見ていた。
「警察には、言わんでいい!」
ドア口でボーイたちと言い争う声が聞こえた。
「離せ!」と、パーシャ。パーシャが、静止を振り切って、毅然とした
態度で、歩いてくると、人々は、道をあけた。
パーシャは、まっすぐに、ラーラのところまでくると、ラーラの顔を
まっすぐに見た。
「離してやれ!」と、ボリスカート教授。
倒れそうになるラーラを支えたのは、パーシャだった。パーシャは、
コマロフスキーを見たが、なにも言わずに、ラーラを連れて、人々のあ
いだを戻っていった。その姿を、ユーリとトーニャも見ていた。
「みなさん、すいません、通してください」と、ボーイの男性。コマロ
フスキーは、ユーリに腕を支えられて、別室に向かった。ふたりの姿が
見えなくなると、婦人たちは、それぞれにつどって、大声でうわさ話を
始めた。
◇
洗面所で、コマロフスキーは、ユーリに、撃たれた左手に包帯を巻い
てもらっていた。
「きみとは、よくよく、縁があるらしいな」と、コマロフスキー。
「ええ」と、ユーリ。
「お父さんとは、親友だったよ」
「仕事のパートナーと聞いています」
「死に際にも、立ち会ったんだよ。きみの兄さんも知っている」
「イエブグラフを?」
「正確には、人を介して、知っているだけだが。ボリシェビキが嫌いで
ね。ありがとう」コマロフスキーは、包帯を巻いてもらって、立ち上が
った。
「腕はよさそうだな。だが、私は、ボリシェビキを尊敬している。なぜ
か、聞きたいか?」
「ええ」
「やつらは、勝つ」ふたりは、その冗談に、すこし笑った。
「会ってみたいな、兄に」と、ユーリ。「手紙をもらったことがある。
受賞をほめてくれた」
「おやじさんも喜ぶぞ。きみのお父さんは、ひとが言うほど、悪いやつ
じゃなかった」
「よく、知りません」
「信じないかもしれんが、きみのお母さんを深く愛していた」
「じゃ」コマロフスキーは、洗面所のドアをあけた。「きみの医者とし
ての分別を信じていいだろうね?」
「ああ」ユーリも立ち上がって、洗面台で手を洗った。
「あなたと、彼女の関係を、口外しないかと、心配なんですね?」
「まぁ、そういうことだ」
「医者としての分別なら、ありますよ。ご心配なく」
「不満もありそうだな」
「あなたとの手を切って、この先、彼女はどうなるのか」
「気になるのか?きみに、ゆずろうか?」
「タバコはいけません。出血が多いのに」ユーリは、コマロフスキーの
葉巻を取って、トイレに投げ捨てた。
「彼女をきみに、おゆずりするよ。結婚祝いだ」そう言うと、コマロフ
スキーは出て行った。
◇
パーシャのアパートの一室。窓越しに、ろうそくの明かりで、パーシ
ャがラーラの手紙を読んでいるのが見えた。頭をかかえるパーシャ。そ
れを、見ているラーラの顔が見えた。パーシャがなにか訊き、それに答
えるラーラ。怒ったパーシャが手を上げようとするが、途中で、思いと
どまった。ひとりで横をむいて、くやしがるパーシャ。ラーラが、ゆれ
るろうそくの火を目で追うと、窓の外を通りかかった馬車に乗っていた
ユーリも、窓際にゆれる、そのろうそくの火を目で追った。
「ユーリ」と、トーニャ。同じ馬車の隣に座っていた。
「うん?」と、ユーリ。ろうそくの火から、視線を戻した。
「彼女と、前に、なにかあったの?」
「どうして、そういうふうに思うの?」
「会ったの?」
「ああ」
「どこで?」
「患者のプライバシーにかかわるんでね。医者の立場としては」
「それなら、別に、言わなくてもいいの」
2
大通りを行進する歩兵軍隊。沿道には、多くの市民が歓声を上げてい
た。その群集のなかに、若き日の黒い普段着姿の、イエブグラフジバゴ
将軍がいた。
「ブルジョアに言わせれば」と、ジバゴ将軍。少女に、両親の物語を語
っていた。「それは、連合国とドイツの戦争だが、ボリシェビキに言わ
せれば、上流階級同士の戦争となる。どちらが勝とうと、世の中が変わ
りやしない」
うながされて、何人もの若者が、志願兵の列に加わった。黒い普段着
姿のジバゴ将軍もその列に加わった。
「私は、党の指令により、偽名を使って軍隊に志願した。ヨーロッパじ
ゅうが勝利を求めて叫び、同じ神に、それぞれの勝利を祈っていた。党
から命じられた私の任務は、戦いを、敗北に導くこと。敗北こそが革命
の引き金となる。革命こそが、われわれの勝利になるのだ。党は、徴用
された農民に目をつけた。新しい長靴がすりきれるころには、彼らもわ
れわれの声に耳を傾けるだろう。のちに、私は、戦闘中、前線から3個
大隊を離脱させることに成功するが、このときは、まだ、じっと、様子
を見ていた。まだ、志願兵が多すぎる。その多くは、熱におかされ、志
願した連中だが、なかには、愛国心に燃え、危機感を感じて、志願した
ものもいる」
ウラルのグラドフで暮らすパーシャとラーラの姿もあった。子どもを
抱えたパーシャは、ラーラに子どもを預け、志願兵の受付のテントに入
っていった。ラーラは、子どもを抱えながら、不安そうな顔をした。
「将来を憂うものや、不幸なものが志願する。仕事に不満を持つもの、
妻に不満を持つもの、自分に疑問を持つもの。幸せな者は、志願などし
ない。年齢や職業で、徴兵が先送りになれば、神に感謝する。腕や目や
足を失っても、家に戻れた者はまだいい」
負傷兵の病院で、ユーリは、看護婦とともに診療に忙殺されていた。
病床はいっぱいで、負傷兵にあふれていた。
「彼らは、まだ、幸運だ」
雪原にいくつも横たわる、凍りついた、戦死者たち。
「同志レーニンでさえ、1500キロにわたる前線のすさまじさと、凍
てつく戦場での苦しみは、予想しきれなかった」
「戦争に突入して、2度目の冬には、長靴は、すりきれた。だが、戦線
は動かず、兵士たちの軍服は、ボロボロになった。配給も途絶えがちで、
兵士の半分は、武器も持たず、戦闘に臨んだ。信頼のできぬ上官もいれ
ば━━━」
「イケーッ!腰抜けども!」と、上官。剣をふりかざした。しかし、だ
れも、塹壕から出ようとしなかった。
「信頼に足る上官もいた━━━」
「同志たちよ!進め!」と、軍服姿のパーシャ。塹壕からつぎつぎに兵
士たちが出てきて、敵の機銃掃射にむかって走り出し、パーシャに続い
た。
「進め、進め、オレたちの力を見せてやれー」と、パーシャ。銃剣を持
って突撃した。
「行けー!」
そのとき、パーシャの横で迫撃砲が炸裂して、パーシャは、倒れた。
雪の上にパーシャのかけていたメガネが、落ちた。次々に倒れる兵士た
ち。上官を失って敗走する兵士たち。
「そして、ついに、彼らは、夢に見たことを実行に移した。
故郷に帰り始めたのだ」
塹壕から出て、敗走してゆく兵士たち。
「それが、革命の始まりだった」
雪原を埋め尽くす、敗走してゆく兵士たち。
ユーリは、軍医の軍服を着て、医療品を積んだ馬車に乗って、前線に
向かう兵士たちとともに、隊列を組んで進んでいた。敗走してくる兵士
たちの一群が、向こうから、ばらばらに歩いてきた。
「脱走兵だ」と、先頭の馬に乗っていた将軍。
「補充兵が来た」と、敗走する救護用馬車の兵士。となりに、看護婦姿
のラーラが乗っていた。
「捧げー、筒!」と、補充兵の隊列の副官。
脱走兵たちは、草原へ逃げ始めた。
「戻って来い!バラバラになるんじゃない!」と、救護用馬車の兵士。
「おそれることはない!みんなで固まっていれば、だいじょうぶだ!」
その声に、逃げ始めた兵士たちは、戻ってきた。道に群れをなして、
行進する隊列に道をあけた。
先頭で、堂々と行進する、馬に乗った将軍と副官たち。
「むだ死にするぞ!戻れ!行かない方がいい!」と、脱走兵たち。
「彼らにかまうな!」と、隊列の上官。「前見て進め!」
隊列が、脱走兵たちの群れの中央まで来ると、群れの中に取り込まれ
てしまった。
上官は、近くにあった樽の上に飛び乗って、上に向けて、銃を3発撃
った。その音に、騒ぐ声は静まった。
「よく、聞け!」と、上官。「この15キロ先には、ドイツ軍がいる!」
「ウソをつけ!」と、脱走兵。
「ウソじゃない!」と、上官。「敵は、迫っている!食い止めきれない!
おまえたちのせいだ!」
脱走兵たちは、大声で野次を飛ばした。
「敵は、おまえたちの妻を奪い!家を奪い!」
「バカ言え!」と、脱走兵。
「国を奪う!」と、上官。
「あんたの国だろ!軍人さん!」と、救護用馬車にいた、兵士。
「そう、私の国だ!そして━━━」と、上官が一歩踏み出すと、樽のフ
タが壊れて、上官は汚物の樽の中に、半分、落ちた。
脱走兵たちは、それを見て歓声を挙げた。そのとき、脱走兵のひとり
の銃から、銃声が響いた。上官は汚物の中に沈んだ。
「全員、列に、戻れ!」と、別の馬に乗った上官。「全員に告ぐ!列に
戻れ!」
隊列は、乱れたままで、上空に向けて、銃を撃つものもいた。
馬に乗っていた上官、副官までも、馬から引きずり降ろされた。
「戻れ!なにをしておる!」と、将軍。剣を振り降ろしたが、奪われ、
なん人もの群衆によって、銃の背で殴り殺された。脱走兵と補充兵は、
いっしょになって、歩きだした。
ラーラは、馬車を降りて、逆の方向へ歩いていた。ユーリは、脱走兵
たちが去ったあとに残された、負傷した上官の手当てをしようとした。
「きみは、看護婦か?」と、ユーリ。
「はい」と、ラーラ。
「ケガはないか?」
「ええ」
「手伝ってくれ!」
ふたりは、負傷兵の手当てを始めた。
◇
草原に太陽が沈みかけていた。医療用馬車の荷台の戸があいて、ユー
リが飛び降りた。
「まだ、経験は浅いんです」と、ラーラ。ユーリに馬車から降ろしても
らった。「志願したてで」
「そうか、わかった」と、ユーリ。「なぜ、志願したんだ?」
「戦場に出た、夫をさがしに」
「そっと、運べ!」ユーリは、患者の担架の一方をもって、荷台から降
ろそうとした。「手術を見たことは?」
「あります」
「じゃぁ、頼む」
馬車の戸の上に患者を横にして、カンテラの光で、ユーリは、患者の
頭部に、手術のメスを入れていた。ラーラが、脱脂綿でこまめに血をふ
きとっていた。
「敵は、隣り村まで来たぞ」と、声がした。「ドイツ軍だ!」
「先生」と、カンテラを持った兵士。
「静かにして!」と、ユーリ。手術を見ていた兵士たちは、みんな行っ
てしまった。敵が来ても、動じることなく、手術しているユーリを、ラ
ーラは、感心して見た。やっと、縫合がすむと、ラーラが糸を切って、
手術は終わった。
「ご主人は、見つかった?」
「まだです」
「先生!」と、カンテラを持った兵士。銃声が、すぐ近くまで迫ってき
ていた。
「分かった、出発しよう!」と、ユーリ。
◇
昼間の草原。医療兵の一団が、ゆっくり移動していた。馬車にゆられ
る、ユーリとラーラ。ラーラは、すいとうから水を飲んだ。
「なつかしそうな目で、わたしを見るのね?」と、ラーラ。
「前に会っている」と、ユーリ。「4年前のクリスマスイブに」
「あの晩にいたの?そう、どうりでね。コマロフスキーは、知ってる?」
「ああ、知ってる。きみを連れていった青年が」
「主人よ」
「勇敢な人だ。まわりは、見てるしかなかった。きみも、勇敢だったと
思うよ。あんなやつは、撃っていいほどだ」
「もう、2度と会いたくないわ」
◇
街道沿いの道路脇で、大勢の兵士が休んでいた。1台のオンボロトラ
ックが、警笛を鳴らしながら、ビラを多量にまきながら、通りすぎた。
ユーリも1枚取った。字の読めない老兵が近づいてきた。
「なんだって?」
「皇帝が投獄されて、レーニンが帰ってきた!市民の戦争が始まったん
だ!」
「いいぞ!」と、頭に包帯をまいた兵士。
「市民の戦争?すごいわ」と、ラーラ。ユーリのビラを、いっしょに読
み始めた。
「すごくはない。当然の結果だ」と、兵士。「ついに、レーニンがモス
クワに戻ったか!」
「そのレーニンというのが」と、老兵。「新しい皇帝になるのか?」
「いいかい、ジィさん、もう、皇帝も支配階級もない!労働者だけの国
ができるんだ!すげぇだろ!」
兵士たちが歓声を上げていた。
「あんた、医者か?」と、ひとりの兵士が、ユーリに訊いた。
「ああ」
「いっしょに来てくれ」ユーリは、ラーラとともに、その兵士について
いった。
◇
ユーリとラーラは、医療用馬車で、1軒の邸宅に入って行った。中庭
には、袋に入れられた遺体が横たえられていた。そこは、野戦病院で、
病室は患者であふれていた。
「とても、ひとりじゃ手に負えない!」と、ユーリ。
「臨時政府からの命令だ」と、兵士。命令書を、ユーリに手わたした。
「従ってもらう!」
ユーリとラーラは、患者の多さに困惑しながらも、兵士に従って、病
室の奥へ向かった。
◇
ユーリの叔父の家の書斎。
「こちらは、仕事に追われる毎日です」と、トーニャ。ユーリから来た
手紙を、父に読んで聞かせていた。「なかなか手紙が書けませんが、許
してください」
「いつの日付だ?」と、父。
「7月20日」
「8週間前か」
「ようやく、戦争も終結して、患者も減り、時間もできました。詩を書
く時間も持てると思います。書き方を忘れていなければね」
トーニャは、笑って、父に言った。「はは、覚えているわよ」
「ラーラも、まだ、こちらにいます」と、トーニャ。手紙の続きを読ん
で聞かせた。
「彼女は、すばらしい人です。医学には説明できない力で、患者を癒す
ことができる。間違った手当てをしても、不思議と、それが患者に効く
━━━叔父さんは元気?葉巻は、まだ、手に入りますか?」
「なかなかね」と、父。
「サーシャは、しゃべるようになった?叔母さんは、元気?」
トーニャは、父を見て行った。
「手紙に書いたのに━━━そして、愛するトーニャ。きみは元気?」
「アンナが死んだことを、まだ、知らんのか」と、父。「知ったところ
で、変わらんが━━━」
そのとき、遠くで、砲撃の音が聞こえた。
「また、始まった!」と、父。立ち上がって、書斎の窓のカーテンを閉
めた。「どちらでもいいから、さっさと決めてくれ!あの小競り合いを
している、暴徒どもの、いったいどっちが、この国を治めていくんだ!」
◇
野戦病院の中庭。ユーリは、片付けの馬車の兵士から、書類を受け取
って戻った。
「どうした、セルゲイ?」と、ユーリ。玄関の脇に座った老人に。「故
郷に、帰らないのか?」
「帰ったって、戦争だよ。もう、たくさんだ。赤衛軍に白衛軍。年寄り
には、つらい」
ユーリは、励ますように、セルゲイの肩をたたいた。
「先生は、やさしいね!」と、セルゲイ。「あの、看護婦さんも、やさ
しい人だ!」
ユーリが、野戦病院の中へ戻ると、そこは、簡易ベッドがすべて解体
されて、シーツや毛布類は、たたまれて、積み上げられていた。
「片付いた?」と、ラーラ。奥で、シーツにアイロンをかけていた。
「なんとかね」と、ユーリ。机に腰をかけて、ラーラのアイロンがけを
見ていた。
「きみも、もうじき、娘さんに会えるね」
「汽車に乗れればね」と、ラーラ。「今は、だれより、カーチャに会い
たいわ」
「そうだろうな」と、ユーリ。
「ここを出るのは、さびしいけど━━━さびしいわ、ほんとうに」
「長いあいだ、いたからな」
「ええ。昔は、きれいなお屋敷だったんでしょうね。そう、思わない?」
「これからどうする?」
「グラドフで?」
「ああ」
「だいじょうぶよ」
「そうだと、いいけど」
「クリーニングの店をやる?」
「あなたは、どうするの?」
「たぶん、病院勤務に戻るよ」
「あの病院にいたのね。学校に行く途中、いつも、前を通ったわ」
「モスクワに戻る気はない?」と、ユーリ。
「グラドフから?」と、ラーラ。
「だれか、むこうに、頼れる人がいればいいが、いたらいたで、ぼくは、
嫉妬する━━━」
「やめて、ジバゴ!」と、ラーラ。「お願い、それ以上、言わないで!」
こげ臭いので、下を見ると、アイロンの手を止めたせいで、シーツが
こげていた。
「もう、あなたのせいよ!」と、ラーラ。こげたシーツを手に、ユーリ
に言った。
「ユーリ。わたしたち、半年間、いっしょにいたけど、奥様に言えない
ようなことは、なにもなかった。わたしのことで、ウソをついてほしく
ないの。わかってくれる?あなたは、分かるわよ!」ラーラは、アイロ
ンがけを続けた。
◇
野戦病院。荷物がすべて運び出され、人々は、出口に向かった。
「もう、出発だぞ」と、兵士。「いそげよ!」
「故郷に帰るのか?」と、ユーリ。
「いや、おれの行き先は、ペトログラードだ。赤衛軍に入る」
「奥さんは、どうするの?」と、ラーラ。
「女は待つもんだ。がまんするさ。よし、それじゃぁな、先生」兵士は、
ユーリと握手した。「忠告をしとくよ」
「時代にさからうな、だろ?」と、ユーリ。
「そのとおり!順応することだ」
ほかの兵士たちも、ユーリと握手をして、トラックに向かった。
「元気でな、イワノフ」と、ユーリ。
「先生も」と、イワノフ。
「さよなら、アンドレ」
「さよなら、シメオン」
「先生のことは、忘れません。一生」シメオンは、ユーリに抱きついた。
「さよなら、ジバゴ先生」と、ラーラ。
「さよなら、ありがとう」と、ユーリ。ラーラは、握手して、トラック
にむかった。
「元気でな」と、ユーリ。別の兵士と握手をした。
ユーリは、病院に残って、玄関から、ラーラがトラックに乗る姿を見
送った。ラーラの後ろ姿が遠ざかると、ラーラの曲が聞こえた。あの洋
装店の仕立て室で、汽車の過ぎ去る音にまぎれて、聞こえた曲だった。
「みんな、元気でな」と、セルゲイは、トラックに手を振った。セルゲ
イも、病院に残った。ユーリは、ラーラの曲に追い立てられるように、
がらんとした屋敷に戻っていった。
◇
ラーラの乗った、トラックの荷台。
「あの先生は、紳士だ」と、老人。銃を手入れしている兵士に話しかけ
た。
「ああ、見るからにな」と、兵士。
「いい、お人だ」
「おきれい過ぎるんだよ」
兵士のこの言葉に、ラーラが兵士をにらみつけた。兵士は、ラーラの
怒った視線に気づいた。ラーラは、なにも言わなかった。
◇
モスクワのユーリの叔父の家。トーニャがテラスに出てきた。
「ユーリ」と、トーニャ。ユーリの姿を見つけて、手を振った。ユーリ
も気づいて手を振って、走りだした。開いた玄関先で、走って降りてき
たトーニャと抱き合った。
ユーリが、家の中を見ると、階段から廊下まで、人々でいっぱいであ
った。
「ユーリ」と、トーニャ。玄関に出てきた、赤い腕章をした男性を紹介
した。「こちら、同志、イエルキン。この地区の委員で、ここに住んで
るの」
「ああ、初めまして」と、ユーリ。手を差し出したが、イエルキンは握
手をしなかった。
「ようこそ」と、ユーリは、会釈をした。
「同志、カプルジーナ」と、トーニャは、別の女性も紹介した。
「ようこそ」と、ユーリ。
「あなただけの家では、ありません」と、カプルジーナ。
「同志、カプルジーナは」と、トーニャ。「住宅委員会の委員長でいら
っしゃるの」
「あ、そうですか」と、ユーリ。
「除隊証明書は?」と、イエルキン。
「ああ、はい」と、ユーリ。「サインは、自分でしましたが」紙を差し
出した。
「聖十字架、これは?」
「聖十字架病院ですよ」
「第2改革病院と、いうの」と、トーニャ。ユーリに。
「ああ、改革の余地は、あるね」と、ユーリ。しかし、誰も笑わなかっ
た。
ユーリは、トランクを持って、トーニャと2階に上がろうとした。
「すぐに、病院のチームに入ってもらいたい」と、イエルキン。
「チフスがはやっていると聞いたが」と、ユーリ。チフスの言葉に、周
りの人々は、後ずさりした。
「それは、単なる、ウワサだよ、同志」と、イエルキン。「チフスなど、
流行してはいない」
「そう、それは、よかった。病院へは、明日」
「働き始めれば、配給手帳を出す」
「ずっと、働いてたよ」と、ユーリ。トーニャと階段を上がって行った。
「なにが、気に入らないんだ?」
「あなたよ」と、トーニャ。
「この家には、13世帯が住めますよ」と、カプルジーナ。「こんな広
さがあれば」
「ああ、おっしゃる通りだ。いいはからいですよ、同志。より、公平だ」
ユーリとトーニャは、書斎に入って、ドアを閉めた。
「より、公平だろ?」と、ユーリ。「なにを笑っているんだよ」
「我が家は、どう?」と、トーニャ。ユーリは、トーニャと抱きあった。
カーテンの脇から、それを、子どもが見ていた。
「サーシャか?」
「ほかに、いる?」と、トーニャ。「サーシャ、お父さまよ」
「サーシャ!」と、ユーリ。かがんで、サーシャにあいさつしようとし
たが、サーシャは、ユーリの頬をたたいた。
「サーシャ、いけない子ね」と、トーニャ。サーシャを抱き上げた。
「いいよ!きつく、しかるな!」と、ユーリ。
そこへ、ドアを開けて、買い物に行っていた、叔父が帰ってきた。
「入って、いいかな?」
◇
ユーリの叔父の家の書斎。3人で、夕食後のコーヒーの準備をしてい
た。
「よく見てろ」と、叔父。ランプから、棒状にした紙に火をつけた。
「モスクワにある、最後の葉巻の、最後の半分だ!火をつけるぞ」そう
言って、葉巻をくゆらせた。「どうだ、料理は?」
「おいしかったです」と、ユーリ。
「ほめてやれ」と、ユーリに合図した。
「とても、おいしかったよ、トーニャ」
「たいしたものじゃ」と、トーニャ。
「3か月とっておいた、サラミだ」と、叔父。
「ほんとなの?」と、ユーリ。
「時計と交換したの」
「やり手でね。コーヒーも、その手で手に入れた」
「やめて、パパ。言わなくたって。むこうで、詩は書いたの?」
「たくさんね」
「いいのが、書けた?」
「ああ、そう思うよ」
「見てもいい?」
「もちろんさ」
「看護婦さんは?どうされたの?」トーニャは、カップにコーヒーを注
いだ。「いつも、手紙に書いていたでしょ?」
「ああ、そうだったね」
「ううん、コマロフスキーを撃った娘だろう、たしか?」と、叔父。
「ええ、知ってるわ」
「子どもの待つ家へ、帰ったよ」
「じゃあ、会えないの?」
「ああ」
「残念━━━」そう言って、トーニャはユーリに抱きついた。
「さらば、わが楽しみよ」と、叔父。最後の葉巻に、お別れを言った。
「果たして、この冬を、無事に越せるかどうか━━━」
◇
昼間の雪の中、ユーリは、イエルキンに付き添われて、歩いていた。
「仕事中に、呼び出す権利があるのか?」と、ユーリ。
「ソビエトの代表として」と、イエルキン。
「それは、権力であって、権利じゃない」
「なんて態度だ。記録しておくぞ!」
「なぜ、地区担当の医者を呼ばない?」
「内密に処理したいのだ」
「なんの病気だ?チフスか?」
1軒の建物に入り、患者を診察した。
「病院に運ぶ、車を用意してくれ!」と、ユーリ。「チフスじゃない」
それを聞いて、イエルキンは、ホッとした表情を浮かべた。
「モスクワにはない、もうひとつの病気」と、ユーリ。「飢えだよ」
「思い通りの結果で、満足か?」と、イエルキン。
「あんたが、現状を認めてくれればね」
「なぜだ?」
「認めないんだろ?」と、ユーリ。先に、走って、階段を上がって行っ
た。
「きみの態度は、記録するぞ」と、イエルキン。「要注意人物だ!」
ユーリが叔父の書斎に帰ると、トーニャが驚きの声を上げた。
「ユーリ!」
「ただいま!」と、ユーリは、サーシャの頭をさわってから、言った。
「ストーブは?トーニャ、火が消えているぞ!サーシャが弱って、やせ
細っているじゃないか!」
トーニャは、なにも言わずに室の奥に行って、ドア代わりの布を閉め
た。
「いつも」と、叔父。「おまえが出かけたあと消して、おまえが帰って
くる前につけている」
ユーリが、ドア代わりの布を開けると、トーニャは泣いていた。
「燃料が足りないの━━━」と、トーニャ。
「しっ!」と、ユーリ。なにも言わずに、トーニャにわびた。
◇
夜更け。ユーリは、燃料にするため、金網の板をはがしていた。それ
を、ひとりの警官、若き日のジバゴ将軍が見ていた。
「私は思った」と、ジバゴ将軍。少女に、両親の物語を語っていた。「薪
泥棒ごときを逮捕しては、私の品格が落ちる。だが、党の命令の前には、
品格など、問題ではない。党は、正しいのだ。薪泥棒もひとりなら、あ
われをさそうが、500万人の人が同じことをすれば、町は破壊される。
彼と会うのは、初めてだったが、ひと目で弟と分かった。私は、党の命
令を無視した。兄弟の絆ゆえか?そうは、思わない。弟といっても、腹
違いだし、兄弟同士が裏切ることもある。私は警官として、裏切りあう
兄弟を、数多く見てきた。彼を、尊敬していたからというわけでもない。
一目はおくが、私より優れた人間だとは、思わない。それに、私は、自
分より優れた人間も、処刑してきた。
ユーリは、コートの下になん枚もの板を隠して、家のドアを開けた。
家の中は、大騒ぎだった。2階から、花瓶や銀食器を持ち出してくる人
々に、1階の人々が歓声を上げていた。
「先生も、わたしたちみたいに、つつましく暮らしなよ」と、女性。階
段をあがるユーリに。
「返せ!こら、それを返せ!」と、叔父が、書斎から出て叫んだ。
「あん?だんながわめいているよ」と、女性。
人々が、書斎に集まってきた。花瓶が割れる音がした。
「秩序を乱すな!」と、イエルキン。「もっと、整然とことを進めたま
え!」
「なにをしている?」と、ユーリ。叔父といっしょに尋ねた。
「居住区の配分見直しだ」
「4人家族なら、50平方メートルでじゅうぶん!」と、カプルジーナ。
「どうかな!だれの家だと思っている?」と、叔父。
「パパ、静かにして!」と、トーニャ。
「じゃぁ」と、ユーリ。「50平方メートルでいい。だが、ものを持っ
てゆくな!」
「押収します」と、カプルジーナ。
「泥棒じゃないか!」と、ユーリ。
「ユーリ!」と、トーニャ。ユーリは、母の形見のバラライカを取り返
そうとした。そのとき、ユーリのコートに隠してあった板が床に落ちた。
「これは、どこで手に入れた?」と、イエルキン。
「囲いから、はがしてきた」と、ユーリ。
ユーリの後をつけてきた警官は、このさわぎを書斎のドア口で見てい
た。パチンと、彼が指を鳴らすと、家族4人を残して、人々は、みな、
書斎から出ていった。警官は、書斎のドアを閉めた。
「私が名乗ると」と、ジバゴ将軍。少女に、両親の物語を語っていた。
「老人は、敵意を示し、女は警戒した。弟は、とても喜んでいた。立場
を分かっているのは、彼女だけのようだった」
「思っていたとおりの人だ!」と、ユーリ。「兄さんの、政治姿勢は、
りっぱだよ!」
「自分の姿勢はどうなのか?と尋ねると、彼は革命について、語り出し
た」
「兄さんは」と、ユーリ。「世の中の不平等という腫瘍を切り取ってい
る。りっぱだよ!」
「そう思うなら、党員になれ!と、誘ってみた」
「いや、不平等という腫瘍の切除は、大きな手術だよ。だが、それと同
時に、日々の生活も大切だろ?そうじゃないか?」
「当時、その考えは、間違っていた。彼の党に対する考えを聞き、危険
だと思った。わが党に賛同してはいるが、その根拠は、彼の詩のように、
あいまいなものだ。そんな賛同は、一夜にして消える。そう、忠告する
と」
「明日の行動に、今日、賛成しろと言われてもムリさ」
「彼は、首にロープを巻かれていながら、それに、気づいていないのだ。
私は、彼の詩に対する世間の評判を聞かせた」
「評判が悪い?誰にだ?どこが、気に入らないんだ?」
「私は、理由を話した」
「ぼくの詩は、個人のことに、かまけすぎる。ブルジョア的だと?」
「私は、ウソをついた。だが、彼は信じた。私の意見に、これほど、左
右されるとは。トーニャは、この事態の意味を、理解していた。この町
にいては、危機は、目に見えている。生き延びるためには、町を出て、
田舎に移った方が安全だと、私は、すすめた」
「それなら」と、トーニャ。「ベリキノに、うちの別荘だったところが
あるわ。知り合いもいるし」
「彼は、承知した。私は、移転許可の手続き、いっさいを引き受け、荷
物は、なにを持ち、なにを残すか、指示した。私は、彼の詩集を一冊く
れないかと頼み、そして、別れた。別れ際、また、いつか会おうと言っ
たかどうか。おそらく、言わなかっただろう」
警官は、階段を降りて、家を出て行った。
◇
夜のモスクワ駅。ホームには、多くの人々が寝そべって、いつ来ると
も知れない、汽車を待っていた。焚き火をして、その周りで歌っている
者たちもいた。ユーリは、家族といっしょに、壁沿いにすわり、男性の
弾く、バラライカの音色を聞いていた。その時、警笛を鳴らして、汽車
がホームに入ってきた。人々は、みな、立ち上がって、走り出した。汽
車は、20両編成だったが、客車は、中央の1両だけで、ほかはすべて
貨車だった。貨車の中は、粗末な簡易ベッドで囲われ、真ん中に暖房用
ストーブがあった。木組のベッドの上には、わらがしかれていた。ユー
リは、サーシャを抱いて、貨車に乗り込んだ。
「50人だそ!定員は、50人だ!」と、貨車の管理人の男性。
「トーニャ!」と、ユーリ。ベッドを4人分確保して、叫んだ。
「あなた!」と、トーニャ。父と貨車に乗り込もうとしていた。
「こっちだ!」と、ユーリ。トーニャと父は、荷物を持って、ユーリの
ところまできた。
「定員は、50人だ!指示に従え!」と、貨車の管理人。「50人まで
だそ!50人で終わりだ!」そして、貨車の扉は閉じられた。無理に乗
り込もうとした男性は、貨車の管理人に銃で振り落とされた。
「快適な宿舎だ!」と、叔父。冗談半分に。
「快適な宿舎ねぇ、気取った言い方だな」と、隣りに前から乗っていた
男。「オレも、インテリだぜ!」
「黙ってろ!」と、貨車の管理人。「このインテリ野郎!」
「黙ってろ!ケツなめ野郎!」と、隣りの男。ユーリが見ていることに、
気づいた。
「強制労働さ!」と、自分の腕の赤い腕章を、指さした。
貨車の扉が開いて、書類を持った、警官が入り口に立った。
「同志諸君、列車は、明朝、出発だ。衛生管理の規則を、述べる。排泄
物は、毎朝、捨てること。敷きワラは、10日ごとに、交換。代えが無
い場合は、使用済みのワラを、裏返して、再度、使用。消毒液は、この
中だ」警官は、大きな缶を蹴った。「なお、志願労働員も同乗している」
「うそつけ!」と、さきほどの強制労働の男。警官は、にらみつけたが、
貨車の管理人が、この男、あたまがおかしい、というしぐさをするのを
見て、さきを続けた。
「労働作業には、同志諸君も協力すること。別の車両には、誉高き、ソ
ビエト海軍の兵士たちも、乗っている。頼りになるぞ!」なん人かが、
拍手した。
「あんな、アホども!」と、強制労働の男。警官は、それを無視して、
さきを続けた。
「当列車は、11日目に、ウラル地方を通過する予定だ。ウラル方面で
は、最近、白衛軍、その他の反動的組織の活動が、活発化しているが、
諸君は、心配には、及ばない。この地方の反乱分子は、赤衛軍により、
一掃された。指揮官は、同志、ストレルニコフだ!」
その名前を聞いても、誰も反応しなかった。
「英雄だよ」と、強制労働の男。「拍手!」と、ひとりで手をたたいた。
「よって」と、警官。「安全は、確保された!革命万歳」警官は、こぶ
しを上げてから、貨車を降りた。
「無秩序万歳!」と、強制労働の男。「おべっか野郎!役人め!」
貨車の扉は、ふたたび、閉じられた。貨車の管理人は、なにも言わず
に、強制労働の男に、手錠をかけた。
「それ、必要なの?」と、トーニャ。
「6人を護送するのが、任務だ」と、貨車の管理人。「逃げられちゃ、
困る」
「オレは、自由だぞ」と、強制労働の男。「おべっか野郎!だれにも、
束縛は、されない」
貨車の管理人は、なにも言わずに、離れていった。
「この中で、自由なのは、オレひとりだ!」と、強制労働の男。鎖をガ
チャガチャいわせた。「あとの連中は、みんな、家畜だ!」
トーニャは、強制労働の男を、哀れそうに、見ていた。
◇
汽車は、赤旗をはためかせて、雪に覆われた、森の中を走った。貨車
の人々は、簡易ベッドにつけたものも、ストーブの周りに雑魚寝してい
るものも、みな、目を閉じて、眠っていた。ひとり、隣りの強制労働の
男だけ、目をギラギラさせていた。ユーリは、目がさめると、貨車の小
窓をあけてみた。汽車は、広い川の鉄橋を渡っていた。広大な川の雪原
が、広がっていた。雲におおわれた空に、大きな月が顔を出していた。
ユーリは、ずっと見ていたかったが、隣りの男性の足で、小窓を閉めら
れてしまった。
汽車は、どこまでも続く、雪原を走った。
強制労働の男と管理人は、シャベルで、汚れたワラをかきあつめ、貨
車の外に捨てるために、扉をあけた。出入口は、氷で閉ざされていたが、
シャベルで氷を割ると、雪原が、広がった。汚れたワラを捨ててしまう
と、今度は、ユーリが、消毒液を床にまいた。
汽車は、雪原に降り積もった、多量の雪を蹴散らせて走った。
貨車の中では、踊りの上手な女性が、民族舞踊を披露して、全員で、
手拍子をとった。トーニャも喜んで、叔父に感謝した。
そのとき、汽車が急速に速度を落とした。踊っていた女性も床にふせ
た。管理人が、貨車の扉をあけさせた。徐行する汽車は、家をすべて焼
かれた村の脇を通っていた。
また、速度を上げ始めた汽車に、追いすがろうとする女性がいた。
「助けて!」と、女性。手には、毛布にくるまれた、赤ん坊を持ってい
た。ユーリは、手をのばして、赤ん坊を受け取ってあずけ、叫んだ。
「来るんだ!」
女性は、手をのばして、貨車の男たちにひっぱり上げられた。
「赤ちゃんは、死んでるわ」と、トーニャ。ユーリは、うなづいた。
汽車は、沈みゆく夕日の雪原を、走った。
「わたしの子じゃないよ」と、女性。ストーブの前で、出されたスープ
やパンを食べていた。「今、天国で安らかに眠っている」
「村を焼いたのは、白衛軍か?」と、管理人。
「白衛軍?」と、女性。「いや、ストレルニコフさ」
「おまえたち、なにか、悪さ、したんだろ?」と、管理人。
「なんにも、してないよ。白衛軍に馬を売ったっていう、罪だってさ。
売ったのは、よその村の連中なのに、ぜんぜん、信じてくれなくて」
「おまえは、ウソをついているだろう?」と、強制労働の男。
「神様が承認さ!」と、女性。
「神はいない」と、強制労働の男。「ストレルニコフは、偉大だ。オレ
たちの味方だ。貧しい暮らしを知ってる」
「ほんとう?」と、サーシャ。ユーリに。
「さぁね」と、ユーリ。「そういう、うわさだが」
「ほんとうさ」と、強制労働の男。「だれも、彼がどこから来て、どこ
にいるのか知らない」
「追ってきてるよ」と、女性。
「ほんとか?こんどは、だれが、標的かな?え?」
汽車が、また、急に速度をゆるめた。
「どうした。また、止まった」と、叔父。「今度は、なんだ?」
汽車は、引込み線に入って、停車した。
「心配ないわ。すこし、眠ったら?」と、トーニャ。
「死んだ子を、埋めてやろう」と、叔父。
汽車が停まっているあいだ、死んだ子のために小さな墓を作って埋め
た。人々は、みんな、外に出て、休憩した。
「ごらん!ウラルだ!」と、ユーリ。トーニャに。前方に、雪に覆われ
たウラル山脈がそびえていた。
「見てごらん、サーシャ」と、トーニャ。「あそこへ行くのよ。山を抜
けて、森へ行くの。ここより、暖かいわよ」
「森に、オオカミはいない?」と、サーシャ。
そのとき警笛が聞こえ、2両編成の汽車が、猛スピードで追い越して
いった。人々は、歓声を上げた。
「あれが、ストレルニコフだよ」と、女性。
猛スピードの汽車には、軍服姿のパーシャが乗っていた。左頬には、
刀剣のあとが、生々しく残っていた。

3 (幕間の10分休憩。ラーラの曲。)
汽車は、トンネルを抜け、ウラル山脈に入った。ユーリは、簡易ベッ
ドの小窓を
開けて、サーシャに外を見せた。そのとき、運悪く、汽車は
トンネルに入ったために、すすが小窓から侵入した。
汽車は、森の中で、ふたたび、停車していた。
「パパ、あの音はなに?」と、サーシャ。
「うん?ただの、滝の音だよ」と、ユーリ。
「ちがう、別の音!」
ユーリが耳をすますと、遠くで銃声がした。
「銃声だよ」と、ユーリ。
「戦っているの?」と、サーシャ。
「そうらしい。でも、遠くだよ━━━さぁ、おやすみ」
サーシャは、また、ベッドに入った。
ユーリは、汽車が止まったままなので、外へ降りて、森に入った。森
の中は、霧がたちこめて、木漏れ日が射していた。そのとき、また、ラ
ーラの曲が聞こえた。ユーリは、楽しくなって走りだすと、線路で出た。
そこには、2両編成の汽車が止まって、兵士たちが降りて休んでいた。
ユーリは、逃げようとした。
「捕らえろ!」と、上官。ユーリは、兵士のひとりに、取り押さえられ
た。
「所持品を調べろ!」
兵士のひとりが、ユーリのポケットから、袋を取り出して上官に渡し
た。
「これだけか?」
「そうです」と、兵士。
袋の中には、フォークとスプーン以外に、くだものナイフが入ってい
た。
「連行しろ!」と、上官。
ユーリは、列車の中へ連行された。
「だれの指令を受けてきた?」と、パーシャ。机に座って、ユーリの身
分証を調べた。
「指令など、受けてません」と、ユーリ。立ったまま、説明した。「モ
スクワからユリアティンに行く途中で、家族も汽車にいます」
「それは、確認した」と、パーシャ。
「では━━━」
「きみが、フォークとスプーンで、ナイフをカモフラージュしていたよ
うに、家族を連れていたのも、まわりの目をあざむくためでは?」
「違います」
「ユリアティンは、白衛軍が占領している。だから、行くのか?」
「いいえ。そこから、ベリキノへ行くんです」
「ユリアティンは、戦闘中で通れないぞ」
「わたしは、白衛軍のスパイでは、ありません」
「スパイとは、思わんよ」そして、兵士たちに言った。「もう、いい。
ご苦労だった」
兵士たちは、出て行った。
「座りたまえ、ドクター!」ユーリは、席についた。
上官は、拳銃を机に置こうとしたが、パーシャは、「もっていけ」と、
言って、それを、上官に持っていかせた。
「失礼したね。私をねらうものが、多いので━━━きみは、詩人だろ?」
「ええ」
「昔は、好きで、よく、読んだ」
「どうも」
「今は、感心しないな。主題が、個人的すぎる。分かるかね?感情や愛
など、今は、とるにたりぬことがらだ。きみは、分かっていないようだ
な。ロシアにおいて、個人の生活は死んだ。歴史が、殺したのだ。わた
しが憎いという顔だな」
「憎くても、それで、殺そうとは、思わない」
「兄がいるな」
「イエブグラフ?」
「そう、警察官をしている」
「それは、知らなかった」と、ユーリ。
「秘密警察だからな。彼に、送りこまれたのか?」と、パーシャ。
「イエブグラフが?いや、兄は、ボリシェビキだ」と、ユーリ。パーシ
ャは、うなづいた。「わたしは、政治のことは、さっぱりで」
「いや、かなり、詳しいはずだ。わたしの顔を知っていたようすだった。
なぜだ?だれかに、写真を見せられたのか?」
「いえ」
「ひと目見て、わたしとわかったはずだ」
「以前、会ったことがあるんです」
「いつだ?」
「6年前」
「続けろ!」
「クリスマスイブに」
「見たのか?それとも、うわさに聞いたのか?」
「あなたの奥さんに撃たれた男を、手当てした」
「なぜ、彼女が妻だと思う?」
「ウクライナで、前線の病院で、いっしょに働いた。彼女に聞いてもら
えれば、誤解も解ける」
「妻とは、戦争以来、会っていない。今は、ユリアティンにいる」
そのとき、遠方で砲撃の音がした。
「ユリアティンに?」
パーシャは、うなづいた。
「個人の生活は、ない。男としての、生活もだ」
「ミンクの村を焼き討ちにしたのは、不満のはけ口か?」
「白衛軍に馬を売ったからだ」
「ちがう!馬を売ったのは、違う村だ」
「われわれを裏切れば、報復を受ける。その示しをつけることが、肝心
なのだ」
「たとえ、違う村でもか?」
パーシャは、立ち上がって、兵士を呼んだ。「同志!」兵士が入って
きた。パーシャは、見ていた身分証を、机の上で、ユーリの方へはらっ
た。
「家族で、ベリキノへ行って、なにをする?」
「生きるだけだ」と、ユーリは、身分証をつかんで立ち上がった。
「連れてゆけ!スパイでは、ない!」と、パーシャ。
ユーリは、ストレルニコフの客車から、降りた。
「運が良かったな」と、兵士。ユーリを、別の線路まで誘導した。パー
シャは、窓から、その姿を見ていて、苦々しい表情をした。
ユーリが、汽車に戻ると、待っていた汽車は、警笛を鳴らした。
「来たぞ!」と、誰かが叫んだ。
トーニャは、父といっしょに貨車の入り口で、ユーリの姿を見て、ホ
ッとした表情をした。ユーリは、走って、貨車の入り口に飛び乗った。
汽車は、走り出した。
「進路が違う。どこへ、行くんです?」と、ユーリ。
「ベリキノの駅だよ」と、叔父。
「よかった」と、ユーリ。
◇
ベリキノに降りると、家族は、去ってゆく汽車を見送った。
「だれか、いるかね?」と、叔父。サーシャの手をひいて、駅舎に入っ
ていった。
トーニャは、雪のない森や、ホームの花壇の花を見ていた。
「すてきなところ!すてきだわ!」ユーリと抱き合った。
「だれか!いるか?」と、叔父。
そのとき、駅員が、走って出てきた。叔父の姿を見ると、立ち止まっ
た。
「アレキサンダーのだんなさま!」と、初老の駅員。
「ああ、わしだよ。ペーチャ」
ペーチャは、帽子をぬいで、頭を下げた。
「顔を上げて!」と、叔父。「そういう時代じゃない。うん?屋敷には、
どうやって行く?」
「昔のとおり、お送りします!」
駅員は、御者になって、家族を、1頭馬車で送った。母馬のうしろに、
子馬が追いて来た。高台に来ると、馬車を止めた。広い川のむこうに煙
が立ち上っていた。
「見てごらん」と、ユーリ。サーシャに。
「あれは、なんだ?山火事か?」と、叔父。
「火事じゃありません」と、ペーチャ。「ユリアティンですよ━━━最
初は、赤衛軍。次は、白衛軍。で、また、赤衛軍。ストレルニコフって
やつは、血も涙もないやつですよ!」ペーチャは、「それ!」と、また、
馬車を出発させた。
「もうすぐよ、サーシャ」と、トーニャ。
「あと、8キロを行けば」と、ペーチャ。
「こんなに遠かったか?」と、叔父。「忘れたな。屋敷は、無事か?」
「しっかり、鍵が掛かっていて、だれも、入り込めませんや」
草原の向こうに、防風林の脇に、宮殿のような屋敷が見えてきた。
「ベリキノだわ」と、トーニャ。
屋敷に着くと、周りはツタで覆われ、入り口が2枚の板で封鎖されて、
張り紙がしてあった。
「しっかり、鍵が掛かっているでしょう?」と、ペーチャ。
叔父は、真っ先に、入り口の張り紙を、めがねを出して読んだ。
「またか!どこでも、これだ。ユリアティン革命公正委員会だと?人民
の名をふりかざして、人の家を奪いおって!よかろう!この、わしだっ
て、人民のひとりだ!」
叔父は、おこって、シャベルを手に取って、入り口を破壊しようとし
た。
「おこらんでください。反革命行為になります」ペーチャは、叔父を止
めに入った。
「やめてください!」と、ユーリも加わった。「つかまったら、ペーチ
ャまで、反革命罪で罰せられてしまう!反乱分子は、射殺ですよ」
叔父は、あきらめて、庭まで行って、遠くにシャベルを投げ捨てた。
「やったのは、森にいる革命軍だ」と、ペーチャ。「パルチザンです」
「なに?」と、ユーリ。
「あちこちで、好き勝手をする連中ですよ」
「わたしたちは、屋根させあれば、いいの」と、トーニャ。
「それと、畑と」と、ユーリ。「どこかに、ないか?」
「あの小屋なら、だいじょうぶ」と、ペーチャ。ペーチャが指す方向に、
小さな門番小屋があった。
叔父が門番小屋をあけて、みんなが入ると、そこは、ほこりだらけで
あった。
「いいね。じゅうぶん、しのげる」と、ユーリ。荷物を置いた。
「ストーブも使えます」と、ペーチャ。「わたしがまきをさがして来ま
すよ!」
「ついでに、種イモも」と、ユーリ。
「はい。畑は、ずいぶん、荒らされちまってますが」ペーチャは、裏戸
を開けて、畑を見せた。
「だいじょうぶだ」と、ユーリ。
◇
ユーリは、サーシャといっしょに、畑で野菜を収穫して、小屋に運ん
だ。
「ごくろうさん」と、叔父。「ロシア人は、ひと皮むけば、みな、農民
だな。根っからの」
「違うわ」と、トーニャ。収穫したじゃがいもの、ドロをとっていた。
「畑仕事はしても、ユーリは医者よ」
「はは、ぼくは、気にしてないよ!この暮らしもすばらしい」と、ユー
リ。
「まったくだ」と、叔父。「あとで思いだして、なつかしむかどうかは、
別だがな。赤ん坊がここで生まれるのも、なにかの、縁だな。母さんも、
ここで、生まれたんだ」
「知りませんでした」と、ユーリ。「うれしいですね」
「ほうら!」叔父は、ぺーチャを見て、言った。「ようやく、帰ってき
た━━━足取りが、重いな」
ドアをノックして、ぺーチャが入ってきた。
「なにか、ユリアティンのニュースは?」と、叔父。
「ラードも砂糖もありません」と、ぺーチャ。「油は、来週、入るとか。
小麦粉と、塩と、コーヒーと、釘」そこで、ぺーチャは、黙った。
「悪い知らせか?」と、叔父。
「ええ」
「ああ、また、例によって、粛清か?」
「ストレルニコフは、失脚しました」
「お、それは、いい知らせじゃないか」
「ええ、なんでも、彼は、満州にいるらしい」ぺーチャは、持っていた
新聞を叔父に渡した。「悪い知らせは、これです」
ぺーチャは、駅の仕事に戻っていった。
叔父がメガネをかけて、新聞を読んだ。
「皇帝は、銃殺された。一族全員だ。なんて、ひどいことをするんだ!
いったい、なんの、ために!」
「あと戻りしないために」と、ユーリ。
◇
冬が来て、ベリキノの屋敷も深く、雪に覆われた。門番小屋では、一
家がくつろいでいた。ユーリは、詩に思いを巡らせていた。トーニャの
アイロンの音がドスンドスンと響いていた。
「ねぇ、ユリアティンへ行ってきたら?」と、トーニャ。
「そうだ。たまには、町に出ろ!気分もかわるぞ」と、叔父。
「ユリアティンになにか、あります?」と、ユーリ。
「都会とは違うが、りっぱな図書館があるぞ。まだ、あればだが」
「行ってらっしゃいよ」と、トーニャ。
「いや、やめておくよ」と、ユーリ。「どうせ、道も通れまい」
◇
やがて、陽射しがさして、窓の雪をとかした。春が来て、黄すいせん
が咲きほこった。白樺の白い木肌に、黄がよく似合った。
ラーラは、ユリアティンの図書館で働いていた。ユーリが入り口で、
入館証に記入しているときに、ラーラは気づいていた。ユーリは、歩い
てきて、階段のところで立ち止まった。
「ジバゴ」と、ラーラ。
「ああ」と、ユーリ。「元気だった?」
「どうして、ここにいるの?」
「ベリキノに住んでいる」
「ベリキノに?」
図書館の仕事を終え、ラーラは外へ出た。ユーリがいっしょだった。
「なぜ、ベリキノに?」と、ラーラ。
「モスクワには、いられなくなってね」と、ユーリ。
「まさか、会うなんて!夫をさがしに来たの。でも、戦死したって━━
━」
「ストレルニコフ。会ったよ」
「会ったの?」
「ああ」
積もる話がつきなかった。雪のなくなった、ユリアティンの町を歩き
ながら、話し続けた。ラーラは、1軒の家の戸をあけて、中に入って、
鍵を壁にかけた。ユーリは、室の様子がもの珍しかった。
「ここに住んで、どのくらい?」と、ユーリ。
「1年よ」
「ひとりで?」
「カーチャと」
「カーチャは、いま、どこに?」
「学校よ」
ふたりは、静かに抱き合った。
しばらくして、ベッドの中で、ラーラは訊いた。
「奥さんも、いっしょ?」
「ああ、家族みんな」
「サーシャも?」
「いっしょだ」
「どうするの?」
「分からない━━━」
◇
朝、黄すいせんの畑に囲まれた、ベリキノの門番小屋。
ユーリは、目覚め、ベッドから起きだした。枕元には、モスクワから
大事にもってきたバラライカが置いてあった。トーニャは、となりでま
だ、眠っていた。窓の外を見ていると、トーニャの声がした。
「ユーリ。まだ、早いのに」
「6時半だ」
「どうかしたの?」
「べつに。眠れなくて」
「悩みごと?」
「いや」
トーニャは、起き出して、肩掛けをはおった。
「お茶でもいれる?」
「頼むよ」と、ユーリ。窓に、視線を移した。
◇
ユーリは、馬にまたがって、ユリアティンの町にやってきた。家のレ
ンガのひとつをはずすと、置いてある鍵を手に、階段をのぼった。室に
入ると、鍵を壁にかけた。室の様子を見ていると、誰かが階段を急いで
上ってきた。入ってきたのは、9才くらいの女の子で、学校から帰った
カーチャだった。
「いらっしゃい!さっき、大声で呼んだのに!」と、カーチャ。
「ほんとう?聞こえなかった」と、ユーリ。
「ほんとだよ!」
あとから、ラーラも買い物かごを手に帰ってきた。
「やぁ、ラーラ」
「ええ」ラーラは、台所へ行った。
「どう、学校の先生は?」と、ユーリ。
「やんなっちゃう。午前中、ずっと、特別授業なの」と、カーチャ。
「特別授業?」
「市民教育よ」と、ラーラ。台所で、料理をあたためていた。
「見て!」と、カーチャ。ノートをかばんから出して、描いた絵を、ユ
ーリに見せた。
「へぇ、じょうずだね、カーチャ」
「これはね、皇帝なの」
「ああ」
「皇帝は、人民の敵!」と、カーチャ。ユーリは、少しとまどった。
「でも、皇帝は、自分がそうだって、知らなかったんだ」
「気づかなきゃ、だめでしょ?」
「そのとおりだ」
「市民教育も知らないなんて!サーシャは、学校へ行ってないの?」
「お昼よ!」と、ラーラ。「さぁ、おいで!」ラーラは、カーチャを抱
き上げた。
◇
ユーリは、ベリキノの門番小屋の窓から、畑にいるトーニャの姿を見
ていた。トーニャは、ふたり目を身ごもっていて、おなかが大きかった。
小屋を出て、ユーリは、トーニャを出迎えた。
「かいでみて!」と、トーニャ。香草を差し出した。「どう?あ、元気
のいい子だわ!さわって!」トーニャは、ユーリの手をとって、おなか
においた。「待って!ほら!」
トーニャは、香草を持って、小屋に入っていった。ユーリは、トーニ
ャの姿を目で追っていたが、急に思いついたように、小屋の入り口に立
った。
「ちょっと、ユリアティンへ行ってくるよ」
「今から?」
「薬を買わないと。モルヒネと消毒液も」
「モルヒネは、いらないわ」
「念のためさ」
「陣痛も、まだだし」
「でも、もうじきだ。うっかりしてた」
ユーリは、上着を着た。
「暗くなる前に、帰ってね!」
「わかってる!」
ユーリは、馬にまたがって、ギャロップで出かけた。トーニャは、そ
の姿を、目で追っていた。
◇
ユリアティンのラーラの家。
「あなたが、一番いいと思うようにして!」と、ラーラ。
「もう、ここには、戻ってはこない!」と、ユーリ。
「分かるわ!」
「2度と、会わない━━━分かって、くれるかな?」
ラーラは、なんども、うなづいた。
「ぼくの言葉を、信じる?」
ラーラは、うつむいて、頭をふった。ユーリは、そのまま、ラーラの
家を後にした。
4
ユーリは、馬をゆっくり歩かせながら、ベリキノに戻る途中だった。
考え事をしているうちに、馬が立ちどまった。そこは、トーニャが引く
糸と、ラーラが引く糸が、釣り合った場所だった。ユーリの乗った馬は、
進むことも、戻ることもできなかった。すると、多くのひづめの音がし
て、横の林から、10頭ほどの馬に乗ったパルチザンが現れ、ユーリを
馬ごと、横へさらっていった。ユーリのかぶっていたベレー帽が、道の
中央に落ちて、残された。
しばらく走って、パルチザンの野営地に着いた。
「医者の手が必要なもんでね」と、パルチザンの首領。
「悪いが、ベリキノに妻子がいるんだ」と、ユーリ。
「町には、愛人もいるぞ」と、パルチザンの副領。
「へへへ」と、首領。「いっしょに来い。われわれは、パルチザンだ!
脱走すれば、殺す!」
首領の合図で、100頭ほどの、馬に乗った仲間が続いた。ユーリを
ともなったものたちも、続いた。
川のほとりで、パルチザンはキャンプを張った。
「どこへ、連れてゆく?」と、ユーリ。首領に。
「前線だ」と、副領。
「前線とは、どこなんだ?」
「へへへ、いい質問だね」と、首領。
「革命の敵がいるところ、すべてだ」と、副領。「白衛兵のいるところ。
反革命論者のいるところ。それが、前線だ。それから、ブルジョアのい
るところ。信用ならん教師のいるところ。個人の生活にこだわる、ふと
どきな詩人のいるところ。これも、前線だ」
「はははは」と、首領。
「いつまで、拘束する気だ?」と、ユーリ。
「必要があるかぎり」と、副領。
◇
朝。雪原におおわれた、湖の岸の木立の中。パルチザンは、戦闘体制
をとっていた。
「いけー!」と、首領。剣をふりかざして、突撃の合図をした。兵士た
ちは、馬に走らせて、突撃した。対岸に近づくと、機銃掃射が浴びせら
れた。ものともせずに、突撃してゆく兵士たち。
ユーリと副官は、荷物を積んだ数頭の馬とともに、林で待機していた。
◇
草地での別の戦闘。今度は、林の中で、草地を突撃してくる白衛軍に、
機銃掃射を浴びせた。首領が双眼鏡でのぞいているあいだに、敵は全滅
した。
「ふん。簡単だったな!さ、戦果を見にゆこうか」と、首領。
草地を進んでゆくと、死んでいるのは、みな、白い服を着た少年ばか
りであった。まだ、うごくものがいたので、ユーリは、手当てしようと
した。
「聖マイケル士官学校だと?」と、首領。「こんなところに、のこのこ
と!」
ユーリが診ていた少年は、すぐに、死亡した。
「たいしたことじゃない」と、副領。
「きみは、人を愛したことがあるのか?」と、ユーリ。
「かつては、妻と4人の子がいた」副領は、そういい残して、先に進ん
だ。
◇
夜中の野営地。
「もう、じゅうぶん、役に立ったろ」と、首領。ユーリを解放するかど
うかを、議論していた。
「医者は、必要だ」と、副領。
「妻と子から、引き離してきたんだぞ」
「それは、重要じゃない」
「じゃ、なにが、重要なんだ?教えてくれ!わからなくなったんだ」
「とにかく、医者は、ここに残す」
「指揮官は、オレだ!」と、首領。
「わたしも強大な指揮権を、党から与えられている!」と、副領。
「おまえを、始末することもできるんだぞ!」
「わたしがいなくて、やってゆけるのか?よく、考えるんだな!軍事闘
争が終われば、政治闘争が激しくなる。そういう状況下では、人の能力
は、政治力の有無で評価される。戦闘の手柄など、意味をなさない。そ
れに、白衛軍は近くにいる。医者は、残す。会議は、終わりだ!」
◇
真冬の雪原の行軍。馬には荷物を乗せて、ほとんどが歩いて、雪原を
進んでいた。
吹雪の向こうから、10人ほどの、女や子どもたちが歩いてきた。
「どうした?」と、副領。ぼうっとした表情の女に。「どこへゆく?な
にかから、逃げているのか?」
「兵隊が」と、女。目がうつろだった。
「赤衛軍か?白衛軍か?」
「兵隊が━━━」と、女。うしろを指さした。副領は、それ以上、なに
も聞かずに、また、馬に乗った。
ユーリが振り返って、吹雪の空を見ると、そこだけ、もやが晴れて、
太陽が見えた。そのとき、ラーラの曲が聞こえた。兵士たちは、行軍を
続け、女や子どもたちとすれ違った。
ユーリは、立ち止まったまま、どちらにもついてゆかなかった。馬を
横に向かせて、ラーラの曲の方へ、ゆっくりと、離れていった。
◇
吹雪の中を、馬なしで歩くユーリ。電信柱の列で、かろうじて、街道
だと分かった。
前方に、幼な子の手を引いて歩く、女性と男性の姿が、見えた。ユー
リには、それが、トーニャとサーシャと叔父の姿に見えた。
「トーニャ!トーニャ!」と、ユーリ。前方の3人に向かって、走りだ
した。「サーシャ!トーニャ!━━━トーニャ!待って!トーニャ!ト
ーニャ!」
3人は、小さな小屋に入って、走ってきたユーリを、ナイフを見せて
追い払った。
ユーリは、人違いだったことを知ると、また、歩き出した。
ユーリは、歩きつかれて、もうろうとしていた。汽車の警笛の音で、
あわてて、脇に倒れた。
そこは、駅の線路であった。
「ここは、ユリアティンか?」と、ユーリ。
「ああ、ユリアティンだ」と、ホームにいた兵士。
「ベリキノは、どうなった?」
「別荘の人か?」
「ああ」
「出て行ったよ、みんな。ベリキノには、だれもいない」
それを聞いて、ユーリは、悲しそうな顔をした。
ユーリは、歩いて、ラーラの家の階段までくると、ねずみが何匹も走
りまわっていた。だれも、いない様子に、ユーリは、肩を落とした。レ
ンガをはずして、鍵の置いてあるところを見ると、鍵といっしょに手紙
があった。凍える手で、手紙を開いて、読みはじめた。
「よかった!」と、ラーラの手紙。「生きていてくれたのね!町で、あ
なたを見たという人がいました。あなたは、ベリキノへ行くでしょうか
ら、わたしも、カーチャと向かいます。念のため、食べものを用意して
おきました。ネズミがいるので、なべにフタをしてね!ああ、ほんとう
に、無事でよかった!」
ユーリは、うれしさから、手紙をくちゃくちゃにして、抱きしめた。
室に入ると、机の上には、スープ皿が並べてあった。鍵を壁に掛けて、
となりの室へ行くと、ベッドも整えてあった。姿見をみると、顔じゅう
が雪でおおわれたやつれ果てた自分の姿に、あぜんとした。遠くに、逃
げてゆく3人の姿が見えた。
「トーニャ!トーニャ!」と、ユーリ。
「ユーリ!」と、ラーラ。ユーリは、寝巻きを着て、ベッドに寝かされ
ていた。
「トーニャ!トーニャ!」と、ユーリ。
「だいじょうぶよ」ラーラが、のぞきこんでいた。「だいじょうぶよ、
ユーリ。ご家族は、無事よ。モスクワにいるわ」
「モスクワに?」
「ええ」
「トーニャは?」
「だいじょうぶよ。みんな、無事よ」
「ああ、よかった━━━」そのとき、外で銃声がした。「銃殺隊が━━
━」
「しーっ!」と、ラーラ。窓に行って。カーテンを閉めた。雪の積もっ
た街角に、こちらを見ている人影があった。男が、マッチをすって葉巻
に火をつけていた。
◇
ユーリは、服を着て、凍傷になった右足を動かす訓練をしていた。
「だいぶ、いいよ」と、ユーリ。ラーラを抱き寄せた。「なんだ?」
「手紙を預かっているの」と、ラーラ。「3か月前から━━━届くのに
3か月かかっている。モスクワからよ」ラーラは、ミシンの下から、手
紙を出してきて、ユーリに見せた。「たぶん、奥様だわ。ここの住所を
見て!あなたが、消えたとき、ここへ、さがしにいらしたの。だれかに
聞いたらしくて」
「会ったのか?」
ラーラは、うなづいた。「ステキな人ね」
ユーリは、手紙を開いて、読み始めた。
「愛する、あなた」と、トーニャの手紙。「この手紙を、ラーラさん宛
てに送ります。もし、生きていれば、きっと、あなたは、ラーラさんを
訪ねるでしょうから。赤ちゃんが生まれました。女の子です。名前は、
アンナ。父からも、よろしく、と言っています。サーシャは、すくすく
育って、とても大きくなりました。あなたの話が出るたび、恋しがって、
泣いています。実は、わたしたちは、ロシアから追放されます。あなた
の同行が、許されるかどうかは、わかりません。行き先は、パリの組織
が知っています。組織の名は、言えません。確かなことは、なにも分か
らず、もう、時間もありません。もうすぐ、迎えがきます。どうか、お
元気で。ラーラさんに、お会いして、よい方だと分かりました」
手紙をよみ終えると、ユーリは、顔を手でおおった。
窓際にいたラーラが、ユーリのもとへ来て、言った。
「ご家族が、モスクワへたつとき、預かったものがある」
ラーラが棚の下のカーテンを開けると、ユーリの衣類とバラライカが
あった。
◇
夜。ラーラの家。吹雪の中を歩いて、階段を上がってくるものがいた。
ラーラは、窓からその姿を見て、おびえた顔をした。
「ユーリ!」と、ラーラ。
ラーラがドアを開けると、入ってきたのは、コマロフスキーだった。
「入って、いいかな」と、コマロフスキー。戸口に立って、オーバーコ
ードは、雪だらけだった。「ユーリ!ずいぶん、変わったな。しばらく、
見ないうちに、老けたな。ラーラは、ちっとも、変わらん!」
コマロフスキーは、姿見で、顔についた雪をはらった。
「モスクワから来た。これから、ウラジオストックに行く」
コマロフスキーは、コートをぬいで、長いすに座った。
「逃げるのを、助けてやろう」
「あんたの手は、借りん!」と、ユーリ。
「ラーラは、いいのか?」
「手は借りないわ」と、ラーラ。
「ユーリ。おまえは、2年間、パルチザンと行動をともにし、除隊の許
可なしに、脱走した。パリにいる、おまえの家族は、亡命者の組織と関
わっている。これだけでも、問題人物だ。それに、おまえの生き方、思
想、言動、作品のすべては、きわめて、反革命的だ。私の助けなしには、
命は、危ないぞ。それでも、助けはいらんと、言うのか?」
「いらん」と、ユーリ。
「待って、ユーリ」と、ラーラ。
コマロフスキーは、起き上がって、テーブルの上に、持ってきた酒の
ビンを置いた。
「ラーラ、グラスを3つだ!」
「よせ!」と、ユーリ。
「ユーリ、真剣に受け止めるべきよ」と、ラーラ。
「私を、みくびらんでほしい」と、コマロフスキー。「きみが思ってい
るほど、堕落してはいないし、力もある」
「どうして、ユーリのことが分かったの?」と、ラーラ。グラスを、台
所から3つ持ってきて、テーブルに置いた。「どうやって、助ける気?」
「助けてやれる。それで、じゅうぶんだろう!」コマロフスキーは、グ
ラスに酒をついで、ラーラに持たせた。
「いいえ」
「カンパイ、ラーラ!」コマロフスキーは、じぶんのグラスをいっきに
飲んだ。
ラーラは、口をつけずに、グラスを置いて、ユーリのもとに戻った。
「沿海州は、未開拓の地域だ。人民委員会の外部部門は、そこに、自治
政府を置こうとしていて、今なら、そこを使えば、国外に出るルートは
得られる。極東の政府なら、顔がきく。司法大臣に任命されたんでね」
「ボリシェビキが、あんたを?」と、ユーリ。
「信用はしてない。使えるとふんだのさ」コマロフスキーは、ラーラの
ぶんのグラスもいっきに飲んだ。
「計画は、こうさ。きみらは、私といっしょに、太平洋岸まで行く。そ
のあとは、好きにしろ。パリに行くのもよし。行かぬのもよし」
「出ていってくれ!」と、ユーリ。
「まったく、どこまで、身勝手で、傲慢な男だ!ラーラの身も危険なん
だぞ!」
「ぼくといるからか?」
「まさか!おまえのようなこものと関わったくらいで!ストレルニコフ
とのからみだよ!」
「そんな人、会ったこともないわ」と、ラーラ。
「おまえの夫だ。当局は、知っている」
「夫は、パーシャアンティポフよ」
「気持ちは分かるが、そう言っても、通用しないぞ」と、コマロフスキ
ー。「おまえは、見張られている。なぜだか、分かるか?亭主っていう
のは、女房に未練たらたらなもんだよ」
「帰って!」と、ラーラ。
「いつまでも、きれいごとを言ってられる、立場か!」コマロフスキー
は、立ち上がった。「娘のことも、考えろ!」コマロフスキーは、ふと
ころから砂糖の袋を取り出した。
「さぁ、どうだ!娘にくれてやれ!」
「いらないわ!」
「ひとの好意をむだにするのか?いったい、なにさまのつもりだ!」
「出て行ってくれ!」ユーリは、コマロフスキーを強引に玄関まで引き
ずっていって、彼のコートを手渡した。
「出てけ!」
「いいか、オレは、おまえたちのために!」
コマロフスキーは、ユーリに、階段から押しやられた。コマロフスキ
ーは、階段から落ちそうになりながら、柱につかまった。
「勝手にしろ!どうなっても、知らんぞ!」
ユーリは、玄関のドアを閉めた。
「勝手に殺されるがいい!」コマロフスキーは、階段でコートを着て、
降りようとして、つまづいて雪の上に倒れた。「精錬潔白なつもりか!
おまえは、そんなわけない!おまえは、知ってるぞ!聞こえているか!
おれたちは、みんな汚れているんだ!おきれいな人間じゃない!聞こえ
ているか!聞いてんのか!」
◇
夜。ラーラの家の寝室のベッドの中。
「ラーラ」と、ユーリ。
「うん?」と、ラーラ。
「あいつは、クズだ━━━」
「ええ、クズだわ!過去を、消してしまいたい!」
「関係ないよ」
「あるわ」
「ぼくは、平気だ」
ラーラは、ユーリの方に向き直って、感謝の気持ちをしめした。
「どうする?汽車で逃げる?」と、ラーラ。
「どうせ、すぐに、つかまってしまう」
「ここで、じっと、待つのはいや」
「ああ」ユーリは、思いついたように、言った。「ラーラ。あそこへ行
こうか!」
「ベリキノね!」
「いずれは、見つかるだろうが━━━」
「いっしょに行く。残された時が短いのなら━━━」
「せめて、大事に生きよう━━━最後の時まで」
「ええ」
◇
雪の晴れた日。1頭馬車で、ユーリとラーラは、ベリキノの屋敷の見
える草原まできた。ふたりのあいだに、カーチャも乗って、はしゃいで
いた。
ベリキノの屋敷は、つららでおおわれて、氷の宮殿のようだった。室
内まで、雪が吹き込んでいて、ドアも、なかなか開かなかった。
「うれしいな!真っ白だ!」カーチャは、雪の積もった庭で、ひとり走
りまわっていた。「イチ、ニ、サン!イチ、ニ、サン!うれしいな!真
っ白だ!イチ、ニ、サン!」
ユーリとラーラが、一番奥の書斎まで来ると、そこは、雪のかわりに、
埃が、うず高く積もっていた。ユーリは、窓際の広い机の引き出しを開
けた。引き出しには、インクつぼやペン、それに、真っ白な原稿が入っ
ていた。
「叔母が、ぼくにくれた机だ!」と、ユーリ。
夜。カーチャは、子ども用のベッドで、ラーラは、ユーリのとなりで
眠っていた。
ユーリは、ひとり起きだして、コートを着て、書斎机に座ると、原稿
を出した。ろうそくの光で、ペンを走らせた。題名は、ラーラと書いた。
ラーラの曲が聞こえた。
1行目を書こうとして、おおかみの遠吠えが聞こえたので、ペンを置
いた。テラスに出てみると、外はすでに明るく、おおかみの声がすぐ近
くで聞こえた。防風林のところに、5・6匹のおおかみがいた。ユーリ
は、両手を広げて追い払った。
書斎の机に戻ると、ユーリは、詩を書き始めた。
ラーラは、起き出してきて、机の上に置かれた、書かれたばかりの詩
を読み出した。ユーリが戻ってきて、詩を取り戻そうとしても、ラーラ
は手で制して、読み続けた。
「これ、わたしじゃないわ!」と、ラーラ。読み終えると、言った。
「いや、きみのことだよ」と、ユーリ。
「いいえ。あなたよ」ユーリが指をさすタイトルを声に出して、読んだ。
「ラーラ」
◇
夜。ユーリは、書斎机に向かって、いくつもの詩を書いていた。何枚
も破いては、また、書き出した。
「ユーリ!」と、ラーラ。寝巻きの上にオーバーコートを着て、起きだ
してきた。「おおかみがほえているわ!」
「ああ、知っている」と、ユーリ。「襲ってはこない。むこうも、おび
えていたよ!」
「そうね。わかったわ。ごめんなさい」
ラーラは、寝室に戻ろうとした。また、おおかみの遠吠えが聞こえる
と、立ち止まった。ユーリは、立ち上がって、ラーラの元へ行った。
「今の時代は、生きるには、つらすぎるわ」と、ラーラ。
「そんな!」
「わたし、たえられない」
「なにを、言うんだ!」
ユーリは、おびえるラーラを、枕元まで、連れていった。
◇
昼食の後。カーチャは、木製の子馬で遊んでいた。ラーラとユーリは、
テーブルから、それを見ていた。
「もっと早く、あなたと出会いたかったわ」と、ラーラ。
「もっと早く?そうだな」
「結婚して、子どもも生まれて。もし、子どもが持てるなら、男がいい?
女がいい?」
「そんなこと考えても、よけい、苦しくなるだけだ」
「わたしは、いつも考えてる━━━今日は、詩を書くの?」
「いや、今日は━━━」
そのとき、ソリの音が聞こえ、玄関に止まった。
「いるか?」男の声がして、戸を強く叩く音がした。男が戸をあけて、
こちらに歩いてきた。
「カーチャ、こちらにいらっしゃい」と、ラーラ。カーチャを書斎に連
れ戻した。
「いました」と、兵士。ふたりの兵士が、書斎のドアを開けて、後ろの
男に報告した。
入ってきたのは、コマロフスキーだった。
「ビクター!」と、ラーラ。「てっきり、連中かと!」
「そうだ」と、コマロフスキー。「はずしてくれ、同志!」
ふたりの兵士は、室の外へ出て、玄関へ戻った。
「ユリアティンから出る汽車の座席を、私と同行の分、確保した。これ
なら、安全に移動できる」
「あんたといっしょに行くつもりは、ない」と、ユーリ。
「わたしは、あなたといっしょよ」と、ラーラは、ユーリに言った。つ
ぎに、コマロフスキーに向かって言った。「はなしは終わりね」
「ユーリとふたりだけで、はなしがしたい」
ユーリは、うなづいて、コマロフスキーと、玄関の方まで出て行った。
「ストレルニコフが死んだ」
「なんだって?」
「くやみの言葉なんぞ、いらんぞ!やつは、殺戮者だ!だれも、悲しん
じゃいない━━━だが、ラーラへの影響は、おおきいぞ」
「分かるものか」
「ストレルニコフの妻を、なぜ、当局は、さっさと逮捕しないで、ユリ
アティンで泳がせていたと思う?だんなを待っていたんだ!」
「妻の元へ戻ってくると、思っていたんだな?おかど、違いだ」
「そうでもないさ。ストレルニコフが見つかったのは、この近くだ。顔
を隠さず、町じゅうを歩いていて、つかまったそうだ。取調べ中も、ス
トレルニコフの名をかたくなに否定し、自分のほんとうの名は、アンテ
ィポフと言い張ったらしい。処刑の当日、警備員の銃を奪い、自分で頭
をぶち抜いた」
「なんて、ことだ」と、ユーリ。「ラーラには、言わないでくれ!」
「彼女のことなら、言われるまでもない。だが、危険なんだ。ラーラの
役目は、終わった。今日、私と来た兵士は、あしたには、銃撃隊の一員
として、ここに乗り込んでくる。きみが、私を嫌う気持ちは、よく分か
る。その理由もな。だが、きみが、いっしょでなければ、ラーラも動か
ん。だから、いっしょに来てくれ。相手が、オレのような卑劣な悪党で
も、目をつぶって、保護を受けてくれ!それとも、自分の意地を通した
いがために、女や子どもまで、犠牲にするつもりか?」
ユーリは、何も言わずに、目を見開いていた。
◇
ベリキノの屋敷の前。2頭馬車と、ふたりの兵士たちが待機していた。
「荷物を積み込むぞ、同志たち」と、コマロフスキー。荷物を、馬車に
運んだ。
ユーリがかばんを持って、ラーラを連れてきた。ラーラは、立ち止ま
った。
「乗れ!」と、コマロフスキー。
「乗って!」と、ユーリ。ラーラを馬車に乗せた。
「人数は?」と、兵士。
「4人だ」と、コマロフスキー。
「全員は、乗りきれない」
「何とか乗せろ!」
「じゃ、ぼくは、自分のソリで行く!」と、ユーリ。
「汽車は、待っちゃくれないぞ!政府の要人が乗る」
「行っててくれ!追いつくよ!」と、ユーリ。バラライカを、ラーラに
手渡した。
ラーラを乗せた馬車は、出発した。
「待ってるわ!」と、ラーラ。手をふった。
「いそげ!」と、コマロフスキー。
兵士ふたりの馬と、ラーラを乗せた馬車は、去っていった。
ユーリも、手をふっていた。ラーラを乗せた馬車が、見えなくなると、
ユーリは、大急ぎで、屋敷の3階まで上がり、窓ガラスを割って、遠く
を行く馬車を見送った。馬車は、ラーラの曲とともに、地平線に消えた。
◇
ユリアティンの夜のホーム。3両編成の客車。発車の合図の笛が鳴っ
た。窓を開けて、コマロフスキーが外を見ていた。個室の座席では、眠
っているカーチャの横で、ラーラが不安そうな顔をしていた。コマロフ
スキーが戻ってきて、個室のドアを閉めた。
「もう、時間だな。おまえの男は、来ない」
「バカね。彼が、あなたの手を借りると思った?」
汽車が走りだした。
「バカな男だ!モンゴルから中国へ行けば、そこから━━━」
「彼は、ロシアを離れない!」
「だが、おまえは、私といっしょに来たんだろ?」
「ええ」
「はは、それも、母親としての義務か?」
「そうよ、ビクター。お腹に彼の子がいるの」
ラーラを乗せた汽車は、黒煙をあげて、雪原を疾走していった。
エピローグ
夜の守衛室。
「わたしが生まれたのは、どこか、ずっと、東の方です」と、女工員の
少女。「モンゴルかどこか。覚えてない」
「きみは、モンゴルで、その年に生まれたんだよ」と、ジバゴ将軍。
「そんな子は、ほかにもたくさんいます」
「トーニャやコマローバの名前をもらった子は、そうそうはいない」
「トーニャもコマローバも、よくある名です」
「金髪で、青い目で、8才の時、極東で行方不明になった、トーニャも、
そういるか?隠さず、話してくれ!どうして、親とはぐれたんだ?」
「覚えてません」
「なにか、覚えているはずだ!話しなさい!」
少女は、立ち上がって、窓のところへ行った。外はすっかり明るくな
っていた。
「お母さんの話しをしよう」と、ジバゴ将軍。
「母とは、限りません」
「まぁ、いい。その後、私は、モスクワで、弟とばったり会った。配給
も少なく、からだも弱ってはいたが、彼は、気にしていないようだった。
私より、しあわせそうに見えた。私は、新しい服を買ってやり、病院で
の仕事を見つけてやった。そして、初出勤する彼を、見送った。彼が、
ラーラと別れてから、8年後のことだ」
「それっきり、会えなかったの?」
◇
モスクワの路面電車乗り場。
「いろいろ、お世話になった」と、ユーリ。兄にあいさつして、路面電
車に乗りこんで、手を振った。
「弟は、心臓を病んでいた」と、ジバゴ将軍。「自分で知っていたに違
いない。だが、彼は、すべてを、胸のうちに秘めた」
ユーリが乗った路面電車が、通りを進んで行った。ユーリは、窓から、
通りを歩く、ラーラの姿を見つけた。いそいで、降りようとしたユーリ
は、混んでいて降りられなかった。すぐ近くを歩くラーラに、窓を叩い
て知らせようとした。やっとのことで、降りて、ラーラに追いつこうと
した。しかし、追いつけずに、心臓をおさえて、倒れてしまった。ラー
ラは、まったく気づかずに、通りを曲がって行ってしまった。
◇
墓地。ユーリの墓地を列をなして歩く人々。
「弟の詩を愛した人々の多さに、私は驚いた。作品は、持つことは禁止
され、入手困難だったのに。人々は、詩を愛し、詩人を愛した。ロシア
人ほど、詩を愛する国民はいない」
シバゴ将軍は、弔問の列の絶えない、弟の墓地の前に立っていた。
「失礼ですが━━━」と、ラーラ。シバゴ将軍に声をかけた。「イエブ
グラフさん?わたしは、ラーラです」
「ラーラの名は、弟の書いた詩のなかに出てきたので、知っていた」
「弟さんの、知人です」と、ラーラ。「助けてください!」
「彼女は、娘をさがすため、モスクワに来たのだ」と、シバゴ将軍。
「私も捜索に力を貸した」
孤児院の子どもたちを一通りみてから、頭を振るラーラ。院長が手を
たたくと、子どもたちは、走って室へ戻っていった。
「しかし、望みは薄かった━━━私は、彼女を愛しはじめていた」
ラーラは、通りを渡り、手を振って去っていった。シバゴ将軍も、手
を振った。
「ある日、彼女は、出てゆき、それっきりだ。強制労働収容所かどこか
で、死んだのだろうか?名前だけの、番号だけの名簿も、どこかへ、ま
ぎれて、消えた。そんなことは、当時、よくあることだった」
◇
守衛室。女工員の少女は、ユーリの詩集にある、ラーラの写真を見て
いた。
「トーニャ、なぜ、親とはぐれたんだ?」と、シバゴ将軍。
「町を走っていたら━━━」と、少女。急に思い出したように。「お父
さんと」
「父さんじゃない、コマロフスキーだ!」
「知りません。町は、火の海で、あちこちで爆弾が爆発してて、父さん
が、手を離したの!わたしの手を離したの!それで、はぐれて━━━」
「実の父なら、離すか?」
「ええ、きっと、あんな状況だったら」
「コマロフスキーだ!」
シバゴ将軍は、また、詩集のユーリの写真を見せた。
「この男が、きみの、ほんとうの父親だ。なぜ、信じようとしない?信
じたくないのか?」
「だって、違っていたら」
「きみは、よく似ているよ」
「子どものころ、両親がほしいと思いました。両親がいたら、どんなに
よかったか。ひとりは、死ぬほど、つらかった。でも、今は、もう分か
りません。今さら、娘と分かって、なにになるんです?」
「できるなら、きみの力になりたい。考えてくれるか?」
「はい」
守衛室のドアを、青年がノックした。少女がドアを開けた。
「だいじょうぶよ、デビッド」
「ここの者か?」と、シバゴ将軍。
「はい、機械の操作をしています」と、青年。
「なんの機械だ?」
「あれです」と、少女。水を放水中のダムを指さした。将軍がうなづく
のを見て、ふたりは、階段を降りた。
「考えてくれるな?」と、シバゴ将軍。
少女は、うなづいて、青年といっしょに歩き出した。そのとき、持っ
ていた、バラライカがボロンと鳴った。
「トーニャ!」と、シバゴ将軍。「バラライカを弾けるのか?」
「弾けるどころか」と、青年。「名手ですよ」
「名手か━━━誰に習った?」
「だれにも習ってません」と、青年。
「では、血筋だな━━━」
ふたりは、なにも答えず、ダムの方向へ歩いていった。
(終わり)
![]()
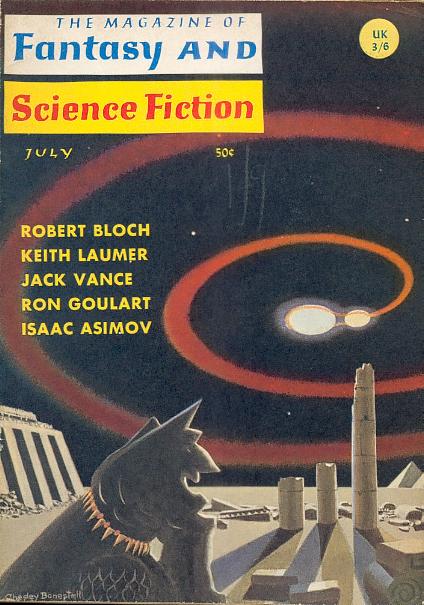
![]()
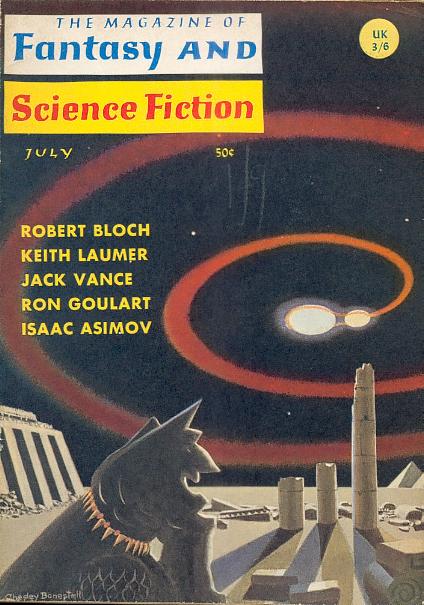
![]()