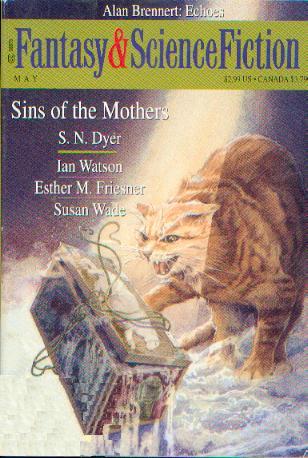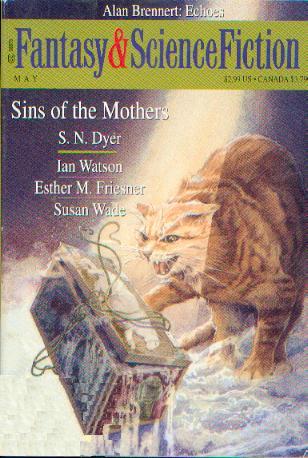ドール
原作:スティーブンキング
クリスカーター
プロローグ
スーパーマーケットの前の駐車場。
助手席に5才くらいの少女が、人形を抱いて、座っていた。母親は、
助手席のドアをあけた。
「さぁ、ポリー、降りてちょうだい。ほんの2つ3つ、お買いものする
だけだから」
ポリーは、母親をにらみつけた。
「お願いだから、ママの言うとおりにして!さぁ!」
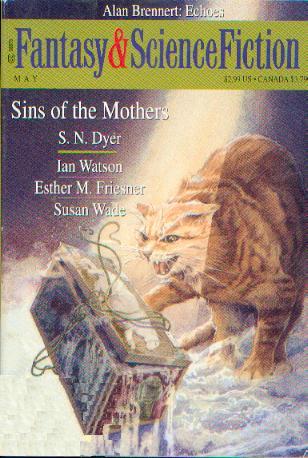
母親は、ポリーのシートベルトをはずして、手を引いて、スーパーマ
ーケットに入っていった。入れ違いに袋をかかえて出てきたメガネの女
性は、ポリーににらまれて、振り返って親子を見ていた。
母親は、カートにポリーを乗せて、押していった。精肉コーナーの男
性と目が合った。
「ママ、わたし、このお店、きらい!」と、ポリー。
「すぐ、すむから、がまんして!」と、母親。
「早く、帰りたい!」
そのとき、ポリーの抱いていた人形が、いきなり目をあけた。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
母親は、いやな予感を感じた。冷凍食品のガラス戸に、精肉コーナー
の男性の姿が、映っていた。男性は、目にナイフが刺さっていた。
「助けてくれ!」と、男性。「ああ!」
母親は、いそいで、カートを走らせて、出口に向かった。
「今すぐ、帰るから!お願い、ママを困らせないで!」
母親は、ポリーを抱いて、なにも買わずに、出口に向かおうとした。
周りにいたお客たちは、みな、目をかきむしって、目から血を流して
いた。悲鳴が、あちこちから、聞こえてきた。母親は、そのまま、出口
から外へ出た。
精肉コーナーの男性は、店先に出てきて、やはり、目をかきむしり始
めた。いそいで、奥に戻り、電話した。
「デイブだ、スーパーセイバーの。大至急来てくれ!」
目の前のガラスに、人形の姿が見えた。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
精肉コーナーの男性は、ナイフをつかんで、自分の目に刺そうとした。
必死に抵抗する姿を、ガラスに映った人形が見ていた。
「ギャーッ!」
1
メイン州の海辺の町。
ガソリンスタンドに1台の車が止まった。青いジャガーのオープンカ
ー。ジーパンに白いTシャツの女性が、自分でガソリンを入れていると、
トランクに入れてあった携帯電話が鳴った。
「ダナスカリーです」と、女性。
「スカリー、ぼくだ」と、モルダー。
「モルダー、休暇中は、お互い、休むって、約束したでしょう?」
「あ、そ、それは、そうなんだけど、ちょうど、Xファイルの典型とも
いえる、事件の情報を、入手したもんでね。ぜひ、きみに、報告してお
きたいと思ってさ」
「モルダー、わたし、休暇中よ。お天気はいいし、ニューイングランド
地方の新鮮な空気を満喫しようとしているんだから、ジャマしないで!」
「まさか、コンバーチブルじゃ?」
「なぜ?」
「あれは、ジコると、クビがふっとぶ確率がデカイ!」
「モルダー、もう切るわよ!ケータイ、オフにしておくわ。あとは、月
曜日に、オフィスで!」
「それから、運転中の通話も命取りだ。統計によると━━━もしもし?」
◇
スカリーは、スーパーマーケットの駐車場に入った。
別の車が、急にバックしてきて、スカリーは、車を止めた。その車の
女性は、子ども連れで、車を急発進させて出て行った。スーパーマーケ
ットの入り口を見ると、老人の男性が、目から血を流しながら出てきた。
スカリーは、黒いジャケットを着て、車から降りた。
「すいません、どうなさったの?」と、スカリー。
「い、医者を呼んで、もらえんかな?」と、老人。
スカリーは、スーパーマーケットの中へ入ると、女性店員もお客も、
目から血を流していた。
「あなたは?」と、スーパーマーケットの売り場主任の男性。
「ああ、わたしは、ダナスカリー。FBI捜査官よ━━━なにが、あっ
たの?」
「わ、わかりません。でも、精肉担当のデイブが━━━死んだみたいだ」
スカリーが、精肉コーナーの事務室に入ると、デイブが目にナイフを
突き刺して死んでいた。
◇
モルダーは、FBIの地下のオフィスで、Xファイルのビデオをチェ
ックしていた。電話が鳴った。
「フォックスモルダーです」
「モルダー、わたしよ」と、電話のスカリー。
「休暇中だろ?」
「ええ、そうよ。今、メイン州にいるの」
「ふーん、新鮮な空気を満喫したいから、邪魔するなって言わなかった
?」
「そうよ、たしかに、そう━━━」ビデオの音が聞こえてきた。「なに
を、見てるの、モルダー?」
「世界の殺人バチ大集合さ!それより、なんで、また、電話したの?」
「じつは、今、スーパーにいて、ある事件を、地元の警察に通報したと
ころなの」
「事件って?」
「それが、どう、説明したらいいのかしら━━━わたしも、直接見たわ
けじゃないから、はっきり言えないけど━━━」スカリーは、警察署で、
警部と警部補といっしょに防犯ビデオの映像を見ていた。「でも、状況
からして、店にいたみんなが、急に、暴力的になったみたい」
「誰にだ?」と、モルダー。見ていた、殺人バチのビデオを消した。
「自分たちによ」
「自分たちに?」
「ええ。自分の顔を殴ったり、目をかきむしったり。ひとりは、死んだ
わ」
「どうして?」
「見た限りでは、自殺ね」
「ああ、聞いた限りじゃ、魔術とか、なんらかの妖術に、関係があるか
んじだな」
「それは、どうかしら。わたしには、魔術や妖術が関係があるとは、思
えないわ。現場を調べたけど、それらしきものは、見かけなかったもの」
「それらしきものって、たとえば?」
「たとえば、呪術とか黒魔術とか、あるいは、シャーマニズムや、占い
の道具、それに、悪魔崇拝、その他の儀式の痕跡、チャームにタロット
カード、使い魔に血石、魔除けのお守り、そのほかあらゆるオカルトや
中国のまじないに関連するシンボル、それに、原始宗教や━━━」
「スカリー!」
「なぁに?」
「ケッコンしてくれ!」
「もうすこし、ましなことを言ってくれると、思っていたわ」
「それだけ調べたんなら、あとは、とんがり帽子をかぶって、ほうきに
乗った、ばぁさんをさがすしかないんじゃないか?」
「参考になったわ」
スカリーは、電話を切った。ビデオに、駐車場で見た、子ども連れの
女性が映った。
「この女性は、だれ?」と、スカリー。警部補に訊いた
「メリッサターナー」と、警部補。
「見る限り、彼女だけ、無傷みたいね」
「だったら、なに?」警部補は、警部と目を見合わせた。
「話を聞くべきじゃない?」
◇
警察署を出ようとするスカリーを、警部が呼び止めた。
「ダナスカリーさん!とうぶん、町に?」
「ええ、ちょうど、休暇中なの。なぜ?」
「いやぁ、さっき、裏で、おたくが、メリッサターナーについて、言っ
た、ひとことが、妙に、引っかかってね」
「というと?」
「じつは、あのメリッサは、魔女じゃないかっていう、うわさがある」
「その手のうわさを聞くのは、初めてじゃないけど━━━」
「あ、まぁね」
スカリーは、警部の胸にある名札を見て、言った。
「正直に言うわ、ジャックボンザント警部。わたし、魔術とかって、信
じないほうなのよ」
「ああ、私もそうさ。だから、うわさも、ねたみだろうと思っていた。
彼女は、美人で、独身だ」
「今は、そう思わない?」
「というか━━━おたくの協力には、感謝しているし、私も非科学的な
ことは、言いたくないがね、今度の件には、どうしても、単なる偶然と
は、思えないことがあるんだな」
「偶然とは、思えないこと?」
「メリッサの男友達だよ」
「メリッサの男友達?」
「ああ、そう。死んだデイブが、そうなんだ━━━」
それを、聞いて、スカリーは、不思議そうな顔をした。
◇
メリッサの家。電話が鳴って、メリッサが出た。ポリーが好きな、軽
快なレコードがかかっていた。
「もしもし」
「いやぁ、バディだ」警察署から、電話している警部補。
「ああ、ハーイ」
「だいじょうぶかい?」
「ええ、どうして?」
ポリーが、人形を抱えて、座っていた。
「誰なの、ママ?」
「スーパーにいたろ?メリッサ、分かっているんだ」と、バディ。電話
を聞かれないように、警察署の裏の室へ移った。
「なんのことだか、さっぱりだわ、バディ」と、メリッサ。
「切ってよ、ママ」と、ポリー。
「メリッサ、音楽を小さくしてくれ!」と、バディ。
メリッサは、電話を持って、子ども室から出て、裏庭で話した。
「今日の事件で、きみがかかわっているといううわさだ」
「わたしは、なんにも、かかわってないわ」
「分かっている。よく、分かっているよ。きみを、責めているんじゃな
い」
「それじゃ、なんの用なの?」
「力になりたいんだ。でも、口外はしないでくれ。お互いの立場がマズ
くなる」
「ママ!」と、ポリー。子ども室から、呼んでいた。
「それから、知らせなきゃいけないことがある」
「なに?」
「悪い知らせだ」
「なんなの、バディ」と、メリッサ。
「デイブが死んだ」
「なんてこと!」
「これから、そっちへ行くよ。いいだろ?」
「だめよ!」
「きみを、ひとりには、しておけないよ!」
ポリーの抱えている人形が、目をあけた。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
「お願いだから、来ないで!」と、メリッサ。
「なぜなんだ?わけを言ってくれ!」
「悪いけど、今は、言えないわ!」
「来るなと言われても、行くよ。友達として、ほっておけないからね!」
庭に干されたシーツに、人形の影が映った。
2
午後2時過ぎに、ボンザント警部とスカリーが、メリッサの家を訪れ
た。
警部がドアをノックしても、応答がなかった。
「裏口があいているわ」と、スカリー。窓をのぞいていた。
ふたりは、裏庭にまわった。
「メリッサ!」と、警部が呼んだが、返事はなかった。警部は、庭に干
されたシーツを見て言った。「まだ、干したてだな」
スカリーは、2階の子ども室に入った。
「警部!」と、スカリー。警部がやってきた。
「これを見て!」スカリーは、子ども室の窓に打たれた、いくつもの釘
を見せた。
「なんのために、こんなことを?」と、警部。
「なにかに、おびえていたみたい」
「いすれにせよ、よぼど、あわててたんだな。戸締りもしないで、出て
ゆくなんて。どういうことだ?」
「どんな人?」
「メリッサか?生まれも育ちも、この町で、漁師のリッチーターナーと
結婚したが、昨年、漁の最中にリッチーを亡くしたんだ」スカリーは、
棚に飾られた、家族写真を見た。「子どもの名は、ポリーというんだが、
すこし、変わった子でね。表情がない」
「つまり、自閉症?」
「うわさではね。昨年、保育園で、園長が、ポリーの顔を平手でたたい
て、話題になった」
「たたいた?どうして?」
「園長の話では、ポリーのかんしゃくがひどくて、やむをえなかったそ
うだ。それが、次の瞬間には、なぐり返され、気絶した」
「ポリーにやられた?」
「園長は、そう言っている。私は、信じる気になれんがね。ま、そんな
ことで、結局、保育園は、認可を取り消され、ポリーに関して、あるこ
とないこと、うわさがたち、メリッサは、魔女呼ばわりだ。それ以来、
あの子は、保育園にも通ってない」
「今回、メリッサと浮気していた、精肉屋が死んだ件で━━━」
「デイブか、ああ、私の言い方が、まずかった。あれは、そんなんじゃ
ないんだ。もっとも、デイブのほうは、すきあらばと思っていたようだ
がね」
「それじゃ、片思いだったの」
「まぁ、そうだな」
「じゃ、窓を釘付けにしたのも、彼を、締め出すため?」
「そこまでじゃなかった━━━ひょっとして、これは、締め出すための
手立てじゃなく、閉じ込めるための策かも?」
「なにを?」
「さぁ、なにかな?」
スカリーは、警部の返答に、ふたたび、不思議そうな顔をした。
◇
アイスクリーム屋の店先。
「どうだい、うまそうだろ?」と、バディ。ポリーの前に、チェリー付
きのアイスクリームを置いた。ポリーは、チェリーを先に食べてから、
なにも言わずにアイスクリームを食べ始めた。
バディは、メリッサの向かいの席についた。メリッサは、泣きそうな
顔をしていた。
「はやく、町を出ろ」と、バディ。
「出て、どこへ行くのよ?」と、メリッサ。「今だって、やっと、暮ら
しているのに!」
「金なら、だいじょうぶだよ。オレの蓄えを使えばいい」
「そんなの、だめよ」
「今まで、黙っていたが、ずっと、前から、きみのことが好きだった。
一度は、あきらめたが、これも、なにかの、巡り合わせだ。こんなこと
になって、心から気の毒に思う。でも、だからこそ、力になりたいんだ」
「余計なこと、しないで!」
「それは、オレみたいな男の世話には、なれないってことか?」
「そんなんじゃないけど━━━」
ポリーは、チェリーがなくなったアイスクリームを持って、席を立っ
た。
「今日、スーパーで起きたことも━━━」と、メリッサ。「デイブが死
んだことも、どうしようもなかったのよ」
「なにを、言っている?」
「わたしには、見えるの」
ポリーは、店先のカウンターに、自分のアイスクリームを置いて、言
った。
「チェリーがもっと食べたい!」
「なぁに?」と、女店員。
「チェリーがもっと食べたい!」
「デイブが死ぬのを見たの。実際に、死ぬ前に━━━」と、メリッサ。
「クーラーの中で、額に包丁が刺さって、血だらけだったわ。これが、
初めてじゃないのよ。夫の死も━━━わたし、見たの。かぎづめが頭に
刺さった姿を、窓ガラスに━━━」バディは、怪訝そうな顔をした。
「ママに話して、お金をもらってらっしゃい!」と、女店員。ポリーに
向かって、言った。「ただじゃ、あげられないわ!」
ポリーの隣のイスに座っていた人形が、目をあけた。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
「注文だ!」と、店主。
女店員は、抽出機の前に立って、ソフトクリームを作り始めた。長い
髪が、風もないのに、なびいていた。
「チェリーがもっと食べたい!」と、ポリー。今度は、母親に向かって。
「帰るわよ、ポリー!」と、メリッサ。席を立って、バッグと人形を持
った。
「これを、持っていけ、メリッサ」と、バディ。「狩りで使っている、
スクーディック湖の近くの小屋の鍵だ。この町にいたら、きみたちの身
が危ない!」バディは、無理やり、鍵をメリッサに持たせた。
「ママ!ママ!ママ!」と、ポリー。
「キャァアー」と、女店員。長い髪が、ソフトクリームのかくはん機の
中にからまった。
バディは、カウンターを乗り越えて、機械の電源を切ろうとしたが、
機械は反応しなかった。メリッサとポリーは、いそいで、店の外に出て
行った。
◇
ボンザント警部は、海辺にある、1軒の家のドアをノックした。
「だれ?ジャック?」窓から顔を出したのは、朝、スーパーマーケット
の出入口で、メリッサ親子を不振そうに見ていたメガネの女性。
「私だよ、ジェーン。いいかな?」
ジェーンは、ドアをあけた。スカリーは、ドアの前に立っていた。
「この人、だれ?」と、ジェーン。
「フローリックさん、FBIのダナスカリーです。休暇で、たまたま、
この町に立ち寄ったもので」
「それで?」
「それで、そのぉ、警部を手伝うことに」
「女と会った?」
「女?」
「ちょっと!メリッサに決まっているでしょ!誰がなんと言おうと、あ
の女は、魔女よ。魔女裁判があった、セーレムのホーソーン家の子孫な
の。あの女の呪われた血が、今、娘に受け継がれようとしているわ。早
く手を打たないと、たいへんなことになるのよ」ジェーンは、警部に向
き直って、言った。「あんたは、知らん顔!」
「ジェーン、もしよければ、中で話したいんだけどね」
「あんたと話してもムダってことは、いやってほど分かったわ。知って
ることは、すべて話したのに、あんたは、ムシしたじゃない!わたしの
祖先は、魔女のあつかいかたを知ってたわ。もし生きてたら、今ごろ、
悪魔ばらいして、あの女を、徹底的にこらしめてやれたのに!」
ジェーンは、言い終わると、すぐに、ドアを閉めた。
「ニューイングランド地方の、もてなしがどういうものか、実際に、身
をもって体験できてよかったわ」と、スカリー。ふたりは、パトカーま
で戻った。
「これで、世間が、あの親子をどう思っているか、分かっただろう?」
と、警部。
「メリッサターナーの家系のことだけど」と、スカリー。
「それが?」
「うわさでしょ?だだの」
「さぁ、よく知らんが、なぜだ?」
「どうせだから、この際、本人を呼んで、確かめたらどうかしら?」
「どんな名目で?」
「参考人としてよ」
「なんのだ?」
「今回の事件を、論理的に解決する鍵を、握っているかもしれないでし
ょ?」
ジェーンは、パトカーのところで話しているふたりの姿を、カーテン
越しに見た。
「まぁな」
「あ、もっと手伝いたいんだけど、わたし、休暇中だから━━━」
パトカーの助手席に乗り込んだスカリーは、こちらを見ているジェー
ンと、目が合った。
◇
スクーディック湖の森林管理局詰所。午後11時すぎ。
1台の車が来たので、警備員の男性が出た。
「ハーイ」と、メリッサ。運転席の窓をあけた。
「ハイ、こんな時間に、どちらへ?」
「知人の山小屋に招待されたの。好きに使っていいって」
「食料や水の準備は?」
「それは、だいじょうぶ」
「油断は禁物ですよ。冬の山は、危険ですから。停電も、しょっちゅう
だ。おふたりだけですか?」
「ええ、今は」
「ママ、おうちにかえりたい!」と、助手席のポリー。人形を抱いてい
た。
「これから、キャンプに行くのよ」
「おうちにかえって、レコードが聞きたい!」
人形の目がひらいた。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
メリッサは、その声を聞いて、急に不安そうな顔をした。
「ナンバーだけ、控えさせてください」と、警備員。
メリッサは、後ろのガラス窓に、女性の姿が映ったのを見て、ギョッ
となった。
「助けて!」と、ガラス窓の女性。メガネをしていて、ジェーンにそっ
くりだった。
メリッサは、車を急発進させて、Uターンして、戻っていった。危う
くひかれそうになった、警備員は、車を、呆然と見送った。
◇
海辺のジェーンの家。
深夜に、レコードの音がするので、ジェーンは、ガウンをはおって起
きてきた。
「だれ?」
ジェーンは、ローカの電気をつけ、居間に入った。
「だれ?だれか、いるの?」
居間の電気は、切れて、つかなかった。居間は、レコードが何枚も散
乱していて、音楽がつきっ放しなので、歩いていって、レコードをとめ
ようとした。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
ジェーンは、割れたレコードを手にした。レコードが同じところを繰
り返していた。
「そんな手に、のるもんか!」
ジェーンは、逆らいながらも、割れたレコードを自分に向けて、何度
も振り下ろした。人形の後ろ姿が、それを見ていた。
3
朝、スカリーは、モーテルの1室で、泡ブロにつかっていた。
電話が鳴ったので、浴室のドアを足でけって、閉めた。
やっと、フロから出て、ピアノコンチェルトを聞いていた。電話の伝
言ランプがついていたが、聞く気になれなかった。窓のカーテンをあけ
ると、ちょうど、今、着いたばかりの、ボンザント警部と目があった。
海辺のジェーンの家。
スカリーとボンザント警部は、家へ入った。
「どうも、自分の手でやったらしい」と、警部。「あごの下の頚動脈を
かき切ってる」
「なにで?」と、スカリー。
「バディ、あれを見せてやれ!」
バディは、ビニールに入れてある割れたレコードを見せた。
警部は、自分のケータイが鳴ったので、電話で話した。
「ボンザントだ。そうだ。だれ?ああ、よし、今、かわる━━━あんた
に、電話だ」電話を、スカリーにわたした。
「もしもし?」
「おはよー、元気かい?」
「モルダー?」
「ああ、きみが心配で、かけてみた。ぼくのヘルプがいるんじゃないか
?」
「ヘルプって、なんのために?」
「モーテルに残した伝言、聞いていないの?」
「ああ、今朝は、早い時間から、出ていたから━━━モルダー?なに、
その音?どこなの?」
「え?窓の外で、工事やっているんだ、ちょっと、待ってくれ!きみた
ち、静かにしてくれ!電話中だぞ!」モルダーは、自室で、バスケット
ボールのドリブルをやめて、ボールを放り投げた。
「どうも!いや、例の事件のこと考えていたんだけど、もしかしたら、
原因は、魔術とかじゃなくて、科学的なことかもしれないよ」
「科学的って、どういうこと?」と、スカリー。
「つまり、病気さ。ヒョレアって呼ばれている」
「舞踏病ね」
「ああ、聖ビトゥスの踊りだ。舞踏病の中でも、流行性で、集団で発症
し、激しいけいれんを起こして、踊りだすんだよ」
「でも、18世紀を最後に、歴史から消えた病気よ」
モルダーは、冷蔵庫をあけて、牛乳を飲もうとしたが、賞味期限が1
か月前だったので、そのまま、飲まずに、牛乳パックに戻した。
「きみ、最近の、ダンス教室の実態を、知らないな」
「モルダー」
「うん?」
「助かったわ」スカリーは、電話を切って、警部に返した。
「相棒かい?」と。警部。
「ええ」
「立ち入ったことを、きいて悪いが、なにか、参考になるようなことで
も?」
「いいえ」
「そうか」
軽快な音楽が鳴った。バディが、レコードをかけてしまったのだ。バ
ディは、聞き覚えのある音楽の気がしたが、すぐに、レコードをとめた。
「ボンザント警部、あ、ジャック?そう、呼んでいいかしら?ずっと、
考えていたんだけれど、もしかしたら、発想の転換が必要なのかもしれ
ない」
「つまり、どういうことかな?」
「だから、そのぉ、規定の概念にとらわれることなく、あらゆる可能性
を検討するの」
「ああ、それは、かまわんが、あんた、休暇中だろ?」
◇
メリッサの家の子ども室。
ポリーが人形を抱いたまま、昼寝をしていた。ポリーのお気に入りの
軽快なレコード音楽がかかっていた。
メリッサは、子ども室に入って、眠っているポリーに近づくと、レコ
ードが引っかかって、音楽が止んだ。メリッサが人形をつかまえようと
近づくと、人形が目をあけた。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
レコードが、また、軽快な音楽を始めた。メリッサは、人形をあきら
めて、下のキッチンへ戻って、泣き始めた。その時、キッチンの窓に人
影が映った。
「メリッサ━━━助けて、お願い━━━」と、窓の人影。血だらけで、
バディにそっくりだった。
「いやぁ!」と、メリッサ。
◇
ヨットハーバーの隣のレストラン。女店員が、大きなロブスターの料
理を運んできた。
「まぁ、すごい!」と、スカリー。ジャックと、テーブルについていた。
「まるで、ジュールベルヌの世界ね!ほんとに、食べるの?」
「もう、来ちまったからな」と、ジャック。さっそく、ロブスターを引
きちぎって、スプーンでみをかきだし始めた。「それで、あんた、どん
な可能性を考えているんだい?」
「メリッサのことが、どうも、気になるのよ。彼女の夫のリッチーだけ
ど、漁に出て、亡くなったって言ってたわね?」
「ああ、そうだ」
「その時のことで、なにか、納得のゆかない不審な点はなかった?」
「そういえば、あの事故に関して、結局、分からずじまいだったことが
ある」
「どんなこと?」
「でかいかぎづめは、どうやって、あごから、頭を貫通したかだ」
「そのことで、メリッサに質問したの?」
「メリッサに?いやぁ、彼女には、関係のないことだ」ジャックは、ヨ
ットハーバーの方を見た。「ちょうど、あそこにとまっているのが、事
故のあった船だよ」
その小さな船では、船長の老人が、バケツを持って操舵室から出てき
た。
「あの人、スーパーで見たわ」両目の周りに引っかき傷のある老人は、
バケツの水を海にあけていた。
◇
メリッサの家の子ども室。ポリーが、人形をかかえたまま、お気に入
りのレコードをかけた。
「ママ、ポップコーンがほしい!」と、ポリー。
「いいわ」と、メリッサ。子ども室をのぞいてから、下へ降りようとし
て、警部補が立っていたので、ビックリした。
「なにを、している?」と、バディ。
「バディ!」
「なぜ、町に戻ってきた?」
「ここにいたら、だめよ!」
「森林管理局から聞いたよ。詰所にいた警備員を、ひき殺そうとしたそ
うだね。彼女を殺したのも、きみなんだろ?」
「なんのはなしをしているの?」
「ジェーンフローリックさ!」
「わたしは、やってない!」
「はなしは、署でゆっくり聞こう。いっしょに来てもらうぞ」バディは、
子ども室のドアまで来て、ポリーを見た。「娘もだ」
ポリーは、横向きに座っていた。人形を、バディの方へ向かせると、
人形の目がひらいた。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
◇
夕暮れのヨットハーバー。船長の老人の両目には、引っかき傷が残っ
ていた。スカリーは、ジャックといっしょに、船長と話していた。
「わけが、知りたいって?」と、船長。「リッチーが、なぜ死んだかに
は、いろんな説がある。オレには、分からん」
「でも、同じ船に乗っていたんでしょ?」と、スカリー。「あなたは、
どう、思うの?」
「知っていることは、警部に、もう、話した」
「もう一度、聞きたいわ」
「世間は、女房のせいと」
「あなたは、どう、思うの?」
「やっこさんは、ほれてた。女房に、家を建ててやるって、はりきって
たよ。娘が生まれたときは、朝から晩まで、ニヤニヤしどうしだった。
そして、去年、その子の誕生日に、やっこさんは、うしろ髪をひかれる
思いで漁にでた」
◇
夜の海で、木でできたかごのしかけを、リッチーは、ロープで船に引
き上げた。船長の老人も、操舵室から出てきた。
「見ろ!娘に海からの、おくりものだ!」木のかごをあけると、中から
人形を出した。
「こりゃ、かわいい!」
◇
「その3日後」と、船長。スカリーに話していた。「あいつは、死んだ」
「なぜか、知っているんでしょ?」と、スカリー。
「夜の海は、魔物だよ。ないものが見えたり、船にあたる波が、人の声
に聞こえたりもする」
◇
夜の海で、リッチーは、ふたたび、木のかごを引き上げた。なかの獲
物はカラで、かごをたたいた。そのとき、操舵室の方から、人形の声が
聞こえた。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
「なんの音だ?」と、リッチー。かぎづめを持って、操舵室のドアをあ
けた。
「どうした?」と、船長。イスにすわって、居眠りをしていた。
リッチーは、なにも言わずに、そのまま出て行った。外で、人形の声
がした。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
船長が、いやな予感がして、外へ出てみると、かぎづめが、リッチー
の頭を貫通して、船の梁に突き刺さっていた。リッチーは、海の方向を
向いて、立ったままだった。「なんてこと━━━」
◇
「あのときは」と、船長。スカリーに話していた。「わが目を疑ったよ」
「でも、あのスーパーで」と、スカリー。「あなたは、はっきりと見た。
リッチーの娘と、例の人形を」
「それで、すべての、なぞが解けた━━━」
◇
スカリーは、ジャックといっしょに、パトカーに向かって歩いていた。
スカリーのケータイが鳴った。
「スカリーです」
「いやぁ、ケータイには出ないと思っていた」と、モルダー。
「なぜ、かけたの?」ふたりは、パトカーに乗り込んだ。
「いやぁ、きみが手伝ってる事件だけど、もしかしたら、ウィルス性の
感染症かもしれないと思ってさ」
「モルダー、聞きたいんだけど、オカルト関連の文献に、人間の行動を
支配する力を持つ、なにかについての記述があるかしら?」
「ああ、なにかって?」
「ああ、そうね、たとえば、人形とか?」
「チャッキーみたいな?」
「ええ、そんなかんじよ」
「ああ、あの手のおしゃべり人形に関する、言い伝えは、とくに、ニュ
ーイングランド地方では、数多く、存在しているよ。そして、たいてい
の場合、人形に宿った霊は、持ち主にも乗り移る、と信じられているん
だ。時代によっては、単に、呪物を賛美しただけで、魔女の烙印を押さ
れた人も、おおぜいいたらしい。そういうひとたちには、未来を見るこ
とができる能力がそなわっていて━━━でも、なぜだい?」
「ちょっと、興味があってね」
「まさか、おしゃべり人形を見つけたっていうんじゃ━━━」
「まさか!そんなんじゃないわよ!」
「もし、人形なら、背中の部分を見ることを、すすめるよ。そこに、ヒ
モのついたプラスチック製の輪があれば、まず、間違いなく━━━もし
もし?」
電話を切ったスカリーは、ためいきをついた。
「メリッサに話を聞きましょう!」
エピローグ
夜、メリッサの家の子ども室。ポリーが、キッチンに向かって、大声
を出した。
「ポップコーンは、まだ?」
「すぐよ、ポリー!」メリッサは、キッチンで、なべをゆらせて、ポッ
プコーンを作っていた。キッチンの床では、バディが、野球のバットを
手にしたまま、血だらけで、横たわっていた。
「ポップコーンは、まだ?」
「もう、すぐよ!」
◇
深夜、メリッサの家の子ども室。ポリーが人形を抱いたまま、眠って
いた。
メリッサは、戸棚から、かなづちと釘を1箱だしてきて、キッチンの
ドアに打ちつけ始めた。
「ママ!」と、ポリー。人形を抱いて、階段の上に立っていた。「わた
し、眠れない!」
「ベッドに戻りなさい。眠る時間は、とっくに、過ぎているわ!」と、
メリッサ。
「うるさいの、やめて!」
「いいから、ベッドに戻って!」
そのとき、人形の目がひらいた。メリッサは、ギョッとした。
「あ・そ・ぼ!」と、人形。
メリッサは、階段の窓を見ると、かなづちのとがった方の先を、頭に
刺した自分の姿があった。
「助けて!」と、窓のメリッサ。
「なにも心配しなくていいのよ!」メリッサは、階段を上がっていった。
「さ、ベッドに戻って!」
◇
深夜、メリッサの家の前に、パトカーが来て、スカリーとジャックが
降りた。
「バディの車だ」と、ジャック。別の白い車が、斜めに停めてあった。
ふたりは、家に向かった。
メリッサは、ポリーを寝かしつけると、かなづちと釘を戸棚にしまっ
て、南京錠をかけた。キッチンに戻って、石油ストーブを倒して、灯油
をまくと、マッチをすろうとした。
「メリッサ!」と、ジャック。玄関のドアをノックした。スカリーは、
窓からカーテンごしにのぞいた。
「なにか、見えるか?」
「いいえ」と、スカリー。裏に回った。
「メリッサ!」と、ジャック。ノックを続けた。
メリッサは、キッチンでなんどもマッチをするが、火がつかなかった。
「メリッサ!」玄関でノックする音が聞こえた。
やっと、1本のマッチに火がついた。
「ママ!」と、ポリー。キッチンまで、来ていた。
ポリーが抱いている人形が、目をあけた。すぐに、マッチの火が消え
た。
「火遊びは、ダメ!」と、人形。
「ベッドに戻りなさい!」と、メリッサ。また、マッチをすった。しか
し、火はすぐに消えた。「さ、はやく!」
「メリッサ!」と、ジャック。ノックを続けた。
スカリーは、裏のキッチンのドアまで来た。ドアは、中から釘で打ち
つけられ、あかなかった。窓から、のぞくと、バディが倒れた横で、メ
リッサがマッチをすっていた。
「メリッサ!メリッサ!」と、スカリー。窓をたたいた。メリッサは、
マッチをなんどもすっていた。「ジャック!」
メリッサは、マッチに火がつかないので、引き出しをあけた。
「ナイフも、ダメ!」と、人形。引き出しは、どれも、すぐに自然に閉
まった。
「ママ!」と、ポリー。
「ドアを釘付けにして、いっしょに死ぬつもりだわ!」と、スカリー。
裏にまわってきた、ジャックに。ジャックは、ドアに体当たりであけよ
うとした。
「フーッ!フーッ!」と、ジャック。
「メリッサ!」と、スカリー。
「ママ、ママ、たすけて!はやく!」と、ポリー。キッチンのドアが、
破られそうなのを見て、おびえた。ジャックの体当たりで、家全体がゆ
れて、奥の戸棚の南京錠がはずれ、ハンマーが現われた。
「ハンマーで、あそぼ!」と、人形。
「メリッサ!」と、スカリー。スカリーも、体当たりに加わった。ポリ
ーは、おびえた顔をした。
ふたりがかりで、やっと、キッチンのドアがあいた。ふたりは、階段
を上がった。
「近寄らないで!」と、メリッサ。あいた戸棚から、ハンマーを持ち出
して、ふたりにむけた。
「置きなさい、メリッサ!」と、スカリー。ふたりは、ハンマーをふり
かざすメリッサに、近づけなかった。ポリーもやって来た。
「あんたなんか、もう、きらい!」と、人形。
「うわぁー」と、メリッサ。ハンマーをそのまま、自分の頭に打ちつけ
た。
「人形を、よこしなさい!」と、スカリー。ポリーに言ったが、ポリー
は、首をふった。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
メリッサは、ハンマーを、自分の頭に打ちつけた。
「人形を、よこしなさい!」と、スカリー。ポリーは、首をふった。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
メリッサは、ハンマーを、自分の頭に打ちつけた。
「人形を、よこしなさい!」と、スカリー。ポリーは、しぶしぶ、人形
をスカリーに手渡した。スカリーは、人形をつかむと、キッチンへ走っ
た。
「ゲームの時間よ!」と、人形。
メリッサは、ハンマーを、自分の頭に打ちつけた。
「ゲームの時間よ!」と、人形。「ギャーッ!」と、メリッサ。
「ゲームの時間よ!」と、人形。「ゲームの時間よ!ゲームの時間よ!
ゲームの時間よ!」
スカリーは、人形を、電子レンジのなかへ入れて、3分にセットした。
ジャックは、走ってきて、人形が、電子レンジのなかで炎につつまれる
のを見た。
メリッサは、やっと、ハンマーを落として、ひざをついて、泣いてい
た。ポリーが、なぐさめるように、そばまで来たが、なにも言わなかっ
た。
スカリーは、人形が燃えるのを、見て、ためいきをついた。
◇
朝、FBIの地下のオフィス。
モルダーは、電動鉛筆削りで、鉛筆をけずった。机に並べると、20
本、そろった。
ドアがあいて、スカリーが入ってきた。
「ああ、いやぁ、スカリー。元気?」モルダーは、ひじをついて、鉛筆
を隠した。
スカリーは、うなづいた。
「おかげさまで」と、スカリー。不思議そうな顔をした。
「なに?」
「あの、ポスター、どうしたの?」UFOのポスターが、壁に貼られて
いた。
「M通りの、ちょっとマニアックな店で買ったんだが、5年くらい前に
━━━」
「ふぅん」
「なぜ?」
「いやね、ある人に、贈りたいと思って」スカリーは、ポスターの前ま
で歩いていった。
「ある人?」モルダーは、引き出しをあけて、見つからないように、鉛
筆をすべて引き出しに落とした。「だれ?」
「だれって、知り合いよ━━━ジャック━━━M通り?」
「ああ、なにか、例の事件と関係があるの?」
「事件?ああ、ええ、そうなの」
「解決した?」
「わたし?ああ、とんでもないわ。こっちは、休暇中で、ただ、リラッ
クスして、過ごしただけ。それより、あなたは?週末、なにか、片付け
た?」
「ああ、もちろんだよ。ぼくのやることに、いちいち口出しする人間が
いないから、もう、仕事がはかどって、なんのって、もう━━━」
天井から、鉛筆が落ちてきた。モルダーが見上げると、また、1本落
ちてきた。
スカリーは、ゆっくり、上を見上げた。天井には、100本近い鉛筆
が、突き刺さっていた。
「これには、わけがあるはずだよね」と、モルダー。
「どうかしら」と、スカリー。「なぞのままにしておいた方が、いいこ
ともあるわ」
また、1本落ちてきて、モルダーの頭を直撃した。
◇
夜の海。
漁師は、木でできたかごのしかけを、ロープで船に引き上げた。
木のかごをあけると、1匹のロブスターと、人形が出てきた。人形は、
煤で真っ黒だった。突然、目をあけて、言った。
「ゲームの時間よ!」
(第五_十一話 終わり)